Jump to navigation
�졼����ʸ�Ϥ��顢��ʬ�Ρּ����������פ��֥��ᥬ�ķ����������˻ٻ���Ϳ����褦�ʵ��Ҥ��������Ȥˤʤ�Ȥ�ͽ�����Ƥ��ʤ��ä������Ĥ��ˤ����������Ҥ��������뤳�Ȥˤʤä���
�ҤȤĤλ������鼡�λ����ؤΰܹԴ��ˡ־���פ��Ԥ���Ȥ����Τϡ������˽�Ƥ���褦�ˡ�������ι������ꥢ�Ǵѻ������ΤϳΤ��ʻ��¤Τ褦�������ᥬ�ķ��Τ����Ĥ�������ˤ����äơ�ɮ�ԤϤ��Ĥơ����ܤ�����Ū�������ΰ�ĤǤ���Ȥ������羾�ʤ��ɤޤġˤ䡢�Ȥ�櫓��ƻ�κ���λ����˻Ȥ���餷�����̤����������ҡפʤɤ���夲�����������Ȥ����ä������ޤ��˼�����֤���Ǥ⡢�����˿ȶ�ʡ֣�ǯ�פȤ��������ˤ�������λ��������ʤ����ǯ��ǯ�ϡפȤ������μ���ؤȰܹԤ��Ƥ����ֻ��ζ��֡פˡԦ��դη�����Ϣ�ۤ������Τ��и��������⤽���礭�ʼ���Ǥ���Ȥ����ΡԦ����դ�̤���α��꤬�Ĥ���ʤĤޤꡢ�ߤλϤޤ�Ƚ���꤬�����դ���Ϣ�뤹��ˤȤ������Ȥ������Τ���˽��פ�����̤������Ȥ������Ȥ��������ΤǤ��뤬���졼���Ϥ��β���Ū�ʻ���Ū���֤�ֶ��ܤ�ʤ�����Ū�ʻ����פȳ��ˤ����������Ƥ�����������ί�ޤä�����Ȥ�������Ū�ʻ���٤�㱤�����뤿��ε���Ȥ���ª���롣
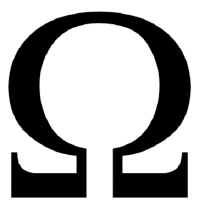
��ϡ������ǡ֤����θ���Ū���ݻ��Ȥΰ�̣�ǤϤʤ��פȤ虜�虜��̤�����ǤäƤ��뤬��page 198�Ǥ�졼���������Ƥ���褦�ˡֺǽ�ˤʤ���ʤ���Фʤ�ʤ����ʤ�١פȤ��Ƥξ���������δ������鸽��Ū�ʺ�ɾ����Ϳ�����Ƥ���褦�ʡ֥⡼���䥤����ඵ�β�Χ�פβ��ϡ��֤��٤Ƹ���Ǥ���פ������������ꤷ�Ƥ��롣
����κ�㫤����ִ���Ū�פȵ��Ҥ����褦�ʥ��ݥå��Ǥ���Ȥ�����������ϡ���ǯ�����äƤ���ɮ�Ԥ�������Ǽ��夲����ȿ��ʪ�ΰ��ספˤ����������Ȥ���������̷�⤷�ʤ��ɤ�������������դ����ΤȤʤ롣�Ĥޤꡢ����Ū�ʲ��ϴ���ȼ������ϡ�ñ�ʤ뼫�����ݤǤ���Ȥ������ϡ������ƿ���Ū�ǿ�Ū�ʲ��餫��ư����֤��٤Ǥ��ꡢ�����������ȼ������ʤΤǤ��ꡢ���줬�ʤ���иŤ����������ޤ��Ѥ�뤳�Ȥ��Ǥ��ʤ�����������ʬ�ڤΤ褦�ʡ������ּ�ȯ��Ū�٤ʤΤǤ��롣�Ĥޤꡢ��ǯ�Ȥ����ϵ�θ�ž�����ʾ�Ǥ�ʲ��Ǥ�ʤ���������Ū�ʼ���ϡ����ο���Ū�����Ū�ֹ١פ�פ��Ф������ħŪ���Ϸ��ʤΤǤ��äơ��ʹ֤Ϥ��μ�����֤���¤ˡ����ĤƤο��ब�Ԥä��Ȥ����Ρ־�������פ����魯������Ȥ��Ƥ����Ȥ����Τ����������Ĥޤꡢ�ϵ�θ�ž�����䡢������տ魯�뿢ʪ�ΰ�ǯ����Ū����̿���ݤ��顢�ʹ֤������ؤ���ΤǤϤʤ���������ķ�Ūȿ���٤ˡ��ϵ�θ�ž������������Ƥ����ȸ����٤��ʤΤǤ��롣
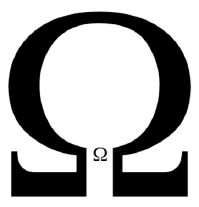
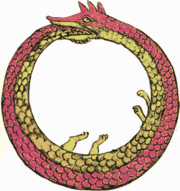
���ˤ�椬���˿����դ����ؤΤ褦�˷Ҥ������Ȥ��릸���Ρ�̤�����ءפ��Ĥ����֥����ܥ����פΤ褦�ʴ��������ߴĤȤ��뤿��η���������κ�㫡����ʤ��������Ū��������פʤΤǤ��ꡢ��������路�褦�Ȥ��Ƥ��륳�ȡʻ��֡ˤϡ��ޤ��˿�������Ǥ�浯�����ͤʤ�����Ū�ʡ֥�����פʤΤǤ��롣
���ΰ��Ѥθ�Ⱦ�����ָ����Ȥ����������ʤ��Ȥ�¿���ο͡����ܤˤϨ��������Ҥ��������������Թ��Ȥ������ʤΰ�����������γ�ǰ����˻�¸���Ƥ���褦�˻פ���פȤ�����ʬ�ϡ��Ȥ�櫓�⤤����������äƤ��롣���줳�������ߴĤν�����ˬ�����Τ��פ������ȡ����줬����ä���α��Τ褦���ż�Ȥ���������ۤκפ�˶��̤˸��Ф����ְ�̣���פʤΤǤ��ꡢ������طʤˤ����ơ����ˤ�ª�����褦���Ե����Ƥ��륨�å��ʤΤǤ��롣���ʤ��Τ��Թ���ż�����Ȥ����Τϡ��ޤ��ˡ�ȿ��ʪ�ΰ��ספΤҤȤĤ�¦�̤Ǥ��뤷���ֻ��ȼ��ʤ�����¸�ߤ��ʤ����Ȥ���ɮ�Ԥ��������Ƕ����Ƥ���������ܵ��פ˴ؤ����ʬ�Ǥ��롣�Ĥޤ�졼���������ǰż����Ƥ��뤳�Ȥ����������̻�פȤ������ʺҤ��ˤ�����������Ω�������ΤǤ��ꡢ�����Ƥ����Թ��ʤ����Ƶ�������ˤε��������־���פΰ�̣�礤�ʤ��뤤���������ˤ�ɬ�פȤ���Ȥ������ȤʤΤ���
�Ȥ����ǡ����Ρ����Ū�Ȥ�Ƥ֤٤������Ū���ݥå���־���פ��㱤��פȤ����ʲ褦�Ȥ��롢����Сֽ��������줿��ħ����פϡ����줬����Ȳ����������Ǥ��Ǥ�����ؤΰ����ʤ�Ǥ��롣�졼���Ϥ������ˤĤ��Ƥ�ȴ����ʤ���Ŧ���롣
�Ρ������ɮ�ԡ������ˤˤ�롣
�������������Ǥ���������������Ȥ��Ƥε���䶵�����Ȥ��Ƥ���ŵ�ʥƥ����ȡˤ����δ������ݻ����Ƥ������Ȥϡ��ɤ߲�����Ź�������������Ȥ������Ǥϡ����ʤ��Ȥ���פ�����̤����ΤǤ��ꡢ�������ݤ�ƻ��Ū���ͤ�����ª���褦�Ȥ��뿮���ʿ��Ŀ��ˤ⡢�ޤ��̤ζ������ؤȽ������侮�������װ��ΰ�ü��ô�äƤ���ΤǤ��롣
�����ǻפ��Ф��٤��������ʤ��Τ�¯�ʤ��Τˤ�äƼ¸����롢���뤤�ϡ�̩��Ū�ʽ������ܵ��ϡ������Ȥ�����ȿ������������¿���λٻ�����������ɡפȤ����Ƥ�ʪ�ˤ�ä������Ķ���Ʊ��Ф�롢�Ȥ����ѥ�ɥ�������ʵ���Ū�ˤʱ����ˤĤ��ơ��ʤΤǤ��롣
��³����
����ʸ��
��˺���줿�����ε�ǽ�פˤĤ��Ƥ�Ĺ����

�ֱDz�פȸ����Хƥ�Ӥǥץ�ӥ塼��ή���Ƥ���褦�ʥϥꥦ�åɷϱDz�䡢�����鼡�ؤȺ����ƥ�ӤΥۡ���ɥ�ޤߤ�����ˮ����ʤ��餤�����Τ�ʤ��Ȥ������Ϥ��ɤ߲�����ʤ��Ƥ�����
�� �ƥ��ȥ뿷��
�Dz褫������������Ϥ�ä���Ȥ����μ¤˺��Ѥ��Ƥ��롣
����ֶ���Ū�פȤϸƤӤ����ʤ��������������������פؤο���δ��ФȤϡ�����줬�㤤���˰��٤��̤�ȴ���Ƥ�����Τ����������ζ���������ٵ���ʸ�����Ф�����Ƚ�Ȥ����Τ⡢���κ��ä��Ϲ�����餤�κ��˽��ƽв�ä�ů�ؤ˵�����Τ������ְִ㤤�ĤĤ���ʸ���פ��Ф���پ�Ȥ��ƽޤ������Ȥ����������ȤȤ�ˤ��ä���Τ���
���������ؽƤΤ褦�˻�Ƴ�Ԥθ�����ȯ�����뤭�������Ū�Ǵ�ǰŪ�ʸ��ա����ա����ա����֤�ݤ��ƹͤ���С��ֽ��ʻ��ۡפȤ�������Ǥ��ʤ��Ϥʤ������Ǥ⡢���¤Ȥ��ޤ�礤���դ����ʤ�����������ɽ�̤���ꤹ��Ф�������Ĥ��������ҤȤμ��ڤʤ����������ʤϤ��Ρֻ��ۡפϡ����٤����Ĥ�礤����DZ�������롣����Τϡ����äǤϤʤ������Ǥ�ʿ���ʥԥ����ˤ���Υƥ�������Ǹ��뤳�ȤΤǤ���褦�ʥ��ʥ����ˤ�����Ĵ�Υ����Ǥ��ꡢ�ضڤ��Ϥ�϶�äƷ����ʤä��ʹ֤�ȯ������������ˤ�äƷ���Ф����ñ�����Ǥ��롣
���Ρ�Ǯ���פϤ������������λֻΤ������о줹��ɥ�ޤ�Dz�ʤɤǤ�������Ƥ�������ߤ˻¤ä���¤�줿�ꤹ���Ԥη����ǤϤ���Τ��⤷��ʤ������Ľդ��������������Ȥϸ��������ʤ������ξ��ꤹ�����Ū�ʸ���˸¤äƤϡ�����˽��Ū�˷����֤����Ф���ǡ��ۤ��μ�Ԥ˹ͤ������������뤳�Ȥ��Ǥ��ʤ���
���ˡ��֤ޤä����狼�äƤ��ʤ��פȻ�Ƴ�Ԥ����Ĥ����Ԥ�����������ʬ���餻�뤳�ȤΤǤ��롢�´��ȸ��´���ȼ�ä����դȷи���Ƴ�Ԥ�ޤᡢï�⤬�����ʤ����ʤ��λ�Ƴ�Ԥ��äƻ�Ƴ�����¦�Ȥۤ�ο�ǯ�κФκ������ʤ�����
�������äơ������������ʻ���Ū��Ÿ���ˤĤ��ƹԤ����ȤΤǤ���˰����Ρ������äݤ��˿ʹ֤����������������ơ֤狼�äƤ���פΤǤ��ꡢ�ֻ�ƳŪΩ��פ˵�¤뤳�Ȥ��Ǥ��롣�����ơ��֤狼�äƤ��ޤä��ԡפϡ���ʬ�Τ���ޤǤΡְִ㤤�פ�ǧ��ʤ��櫓�ˤϤ�������ǧ��Ƽ��ʤ���Ƚ���������ꤹ��Ԥϡ��餱��ǧ��ơֻ���Ū�פˤ��Ƴ�Ԥ˽��虜������ʤ����ְִ�ä��ԡפϡ�������ʲ�С��������ԡפ˽����Τ�����Ū�ˡ����פȤʤ롣�������ƻ��ۤ�����ۡ���Ƴ�����Ƴ�������ۤȤ�������ǰ���Ϥ����Ƽ¸������ΤǤ��롣
�������֤狼��ʤ��ԡפϡ��ɤ��ޤǹԤäƤ�狼��ʤ���ʬ�ˤĤ��ƤΡ�����פ���������롣���ۤ�狼��ʤ��Ԥ��ּ��ʤ����礹��פʤɤȤ������Ȥ�Ƶ��ʳ��β���ΤǤ�ʤ������Τ褦�ʤ��Ȥ��������Բ�ǽ�ʤΤ����顢�狼��ʤ��Ԥ��������뤳�Ȥϡ�����˼��Ԥ������դ��狼��ʤ����̤�ȿ�ʤ�¥���Ƥ���褦�ʤ�Τǡ��ޤä�����ä������˹��ʤ��ΤǤ��뤬����Ƴ�Ԥ�����ŪΩ��ϡ�����������ʬ�˸�������Ƚ���������Ѥ�������֤������פ���äƤ���Τ������Τ褦�ˤ��ơ�����פΰ�̣�ϼ���˼����ƹԤ������������Ƴ�Ԥ����ϡ��ּ�ʬ��������Ф��Τ���������פȤ��������ˤ�äơ����λ�Ƴ�䶵�����դ����Ȥ����Ƥ��ޤ���
�ɤ��ޤǤ�֤狼��ʤ��ץ��С��ˤϡ����դˤ�뼹ٹ����Ƚ�ȿͳʤ����ꡢ�����ơ��֤�ʤ�����̿���Ǥܤ�����Ū��˽�Ϥ��ԤäƤ���ΤǤ��롣����ϡ���ī���ζ������ƽ�䥫��ܥǥ����Ρ֥���ե�����ɡס�ʸ�����̿����������������������˷�ʼ�����ĥ������⤷�����Ȥ���ߴƻ�Ƥ������ܡ��ʤɤʤɤ˵��������ȤǤϤʤ��Τ��������70ǯ��ˡ�����줬��������褷�Ƥ����٤ǵ����Ƥ������ȤʤΤ���
���������ԡפ��ݤ������δ��Фϡ���ʬ����Ǥ�Ĺ����������������褿��Τ����������Ԥ��ݤ��äƤϥ����ʥ�������������������ۤɡ�����Ϲ���������ۤ����ʤ���Фʤ�ʤ����顢�Ȥ������Ȥ⤢�롣���������ΥХ���Фˤ�äơ��������ԡפ���ʬ�˶�Ť����褿��ƨ���������ꤷ�ʤ��ǡ���ǽ�ʸ¤ꤽ�Ρ��������פ��䤦�Ȥ��������˼�ʬ������碌���ΤǤ��롣���������в���ݤȤ���ʹ֤ˤȤäơ��������äơ��������ԡפ��ݤ��餺�ˡ���Ť��Ƥ��äƸ�Ƥ���Ƥߤ�Ȥ����Τϡ����ˤȤ��Ƥष��ɬ�פʤ��ȤǤ��ä���
�����������������ĺ�Ū�ʾ����ˤ����ơ����������δ��Сפ�����ȴ�����Ԥϡ����ꥹ�ޤˤʤ��ǽ�������ꡢ��������ݤ��䤦¸�ߡ���Ƚ�ԡˤ����ʤ��ä��ꡢ��Ƚ�Ԥ���������ꤹ�뤳�Ȥ���������ȡ������ĺ���������ǡ֤ޤä���˽���פȤʤ롣��ʬ������������Ȥ������ζ���٤����С�����ϼ㤯�ƽ��ʻ����μ�Ԥˤ������������ʤ��ȤǤϤ�������40������ʬ���ä��褦����ǯ����Ҷ��λĹ˶ᤤ��Τ����ϻ��äƤ��롣�äˡ��ۤʤ����夬���餺���������äƤ���˾�Υ�٥뤫����Ƚ�Ǥ���¸�ߤ��ʤ���С��ֳ�̿�����ۡפȤ�����Τϡ�˽��Ū��ˡ�����ơ����¤Τ�ΤȤʤ����롣����������̿�Ȥϡ��Ƴ�����������Τ��⤷��ʤ���
���������ԡפι٤����Ƥϡ�ã�������٤����ۤ���Ū�Τ���μ��ʤȤʤꡢ�����ʤ���ʤ��������Ǥ���Ȥ������ۤ���ã�������٤Ƥ��ø�������Ū�ʸ��Ϥ�������롣���줬���ä���30��40���餺�μ�Ԥν��ޤ�Ǥ��ä��Ȥ��Ƥ⡢��������Ū���Ϥ˵դ餦���ȤϤǤ��ʤ��Ȥ����������������졢������й�����ͦ�����С����ͤ�����Ǥ���������ۤؤȶ�Ť��������ˡ�פȤʤ�����Τ������������Ū�ʼҲ�����ۡˤ�¸������뤿���������Ƨ�ߤˤ��äƤ��뼫�ʤ�Ω����ưפ�˺�Ѥ��롣
������Ƚ������Ȥ�����졢���դʤ�˽�Ϥ��졢�֤���ʤ��ȡ���̣����Τ��������줬��̿�ʤΤ����פ����������Ƕ����ˤ����ϡ��������붭���Ϥ����֤�����䤵�줿�ַ��������פΥ����פ���ǡ�����������졢�ޤ��ˤ������Ѥʵ���椨�ˡ�������������������ǹԤä����ۤ�Τ���äȤ�����Ƴ���ؤε���Ǥ����⡢���٤ơֳ�̿Ū�Ǥʤ��סּ��ʤζ������������ʤ��פʤɤ���ͳ�ǰ�������롣�������ƾ��Ϳ��Υ����פ����������Ȥʤ롣���ۤ�dz�����㤤��ǯ������̴�����������Ȥ������Ȳ����������������ζ��������ϳڤ�����ݤ��ǤϤʤ������ν��ʡ��������δ��Сפ椨�ˡ�������ͦ����ʳ���ʤ�����˵������ֶ��������Ǥ����������פ椨�ˡ��ޤ��Ȥ˸�̣�����������������θ�̣�ΰ�������ƨ��褦�Ȥ��Ƥ⡢������Ƥ����Τ������ǤϤʤ�������줬�����Ƥ������������ˤ����ơ����¤�ʪ��Ȥ��Ƶ����Ƥ����Τ��Ȥ������������顢������ƨ��뤳�Ȥ��Ǥ��ʤ���
�Τ��ˤ��αDz�ϡ������ư�Ȥζ��������뤿��μ��ʤȤ����Ѥ����Ƥ⤪�������ʤ���������ۤ����ɳ�ư�Ȥˤ�äƤ�Ʊ�����Ȥϵ����ꤦ�뤷����������Ƥ������Ȥ������������δ��Сפؤ�̵��Ƚ�ʿ���ȡ�����夲��٤����˾夲�ʤ������Ρ�ͦ���Τʤ��פ�·���С����ĤǤ⡢���٤Ǥ⡢�����Ͼ�ˡּ¸����Ƥ��ޤ��ײ�ǽ������Ľ�����ʤΤǤ��롣�ᤷ�����Ȥ��������줬�ֿʹ����פʤΤǤ��롣
[Read More!]

����Τϥإ��������Ǥ�ϡ��ɥ��å��Ǥ�ץ�����Ǥ�ʤ�������Τϥ�ꥫ�Ǥ��ꡢ�֥�å����Х��Ǥ��ꡢ�ե�����åѤǤ��롣����Τϥϡ��ɥХåפ�ե���㥺��ե塼�����ǤϤʤ�������Τϥ����ȡ��֥쥤�����Ǥ��ꡢ����ȥ졼��Ǥ��ꡢ����ޥ���ե��Ǥ��롣������Ϥ��٤Ƹ��ۤǤ��롣���뤤��ɾ���Ƚ����Ƭ��ʣ���ʲ��ڤα���������פ�������ޤ�Ȥ��Τʤ��˼���뤿������ؤǤ��롣
[Read More!]
�������ɿ������Ƚ
�Dz��Touch the Sound�٤�Ѥ��İ����



�֤⤷������Ȥޤ��Ϥ���İ�Ф��ĤäƤ���Τ������ʤ��Τ��⤷��ʤ��ס�
�Ҥ�äȤ���ȡ�İ�о㳲�ԡפ��ष��������ʹ�����ȤΤǤ��ʤ��Բ��դ�ª���Ƥ��뤫�⤷��ʤ����Ȥ����褦���Ȥϰ�����������Ƥ������Ȥ������������ȸ�����ª�����ʤ��Ϥ��αDz褬�����ַ��ԡפ�ª��»�ʤäƤ����¸�ߡפ��ǧ���פ������֤��Լºߡդ��뤳�Ȥ���ۤɤߤ��ߤ������������Ȥ��Ǥ����ΤϤۤȤ�ɴ��פΤ褦�Ǥ��롣
�����Ƥ��Ρִ���Ū��ǽ�פϡ��Dz��Ѥ��塢ľ���˺��Ѥ��Ϥ�롣�ֱDz�ۤ�����פ������������Ѥ��褿ͧ�ͤϡ����κ��Ѥˤ��ֱDz�ۤ������ä��פȤ���������ϺǸ�ˤ⤦���ٸ��ڤ���褦�ˡ��¤ˤ��αDz���ܼ���������Ƥ�ɽ������
�ޤ��Dz��ϡ��ɥ�����Ȥμ��ΤǤ��륨�������ˡ� (Evelyn Glennie) ��¨�������ꥹ�ȡ��ե�åɡ��եꥹ (Fred Frith)�ȤΥ��å��������̤��ơ�����ˤۤȤ�ɲ���ʹ�����Ƥ��ʤ��ȤϤˤ狼�˿����ۤɤβ��������Ĥ��롣�ȡ��ޥ�����ǥ륹�ϥ��ޡ����Ĥϡ������κ���δؿ����Ǥ���������������̩�פ�ڤ��ʤ������������Ȥˡ�����פȤ�����Ƭ�Ǥϴ������Ǥ�ʤ��ʤ�����̩�Ϥ��������Ǵ��˹Ԥ��Ƥ����͡��ʥ�ӥ塼�������ʤɤˤ�äƤۤȤ��̵������Ƥ��ޤäƤ���Τ����ˡ�
ʹ�����ʤ��ʤä�����ˡ���Ĺ������������ʤ��ʤä��������Τ����Υ��ʴ��Сˡ�����ϡ�¸�ߤο�ư������̤μ��פ�ª����Ȥ�����ˡ���ä���������ˡ��Ĺ���������Τ����ΤȤ������Ȥ�¸�ߤο�ư������ߤ�뤳�ȡ��ֿ���: Touch�פ��Ȥ�Ϥ����ˡ�����ϡֲ�������ʹ������ͤϡ���ʬ�����Ƥ���褦�˲���ʹ���ơʿ��äơˤ��ʤ��פ��Ȥ��ΤäƤ��롣����������β��ڤ�ɤŨ����褦�ʶä��٤����Ȥ������ȯ�����̤��ơ�Touch the Sound�����Ԥ��̤��ƾҲ𤵤�롣�֤⤷������Ȥޤ��Ϥ���İ�Ф��ĤäƤ���Τ������ʤ��Τ�������ʤ��ס����Τ褦������Ƹ��路���¸�ο�ư��������ˤ����δؿ��ϰܤäƤ��������줬���μºߤ��ο����Ѥ�äƤ��������Dz�δվԤϤ�Ϥ�Dz������ʹ���ͤǤϤʤ��ʤäƤ���Τ�������ϤҤȤĤΡָ��פȤǤ�ƤӤ����ʤ�褦�ʲ�������δ��פ��Ϥ�Ƥ���Τ���
�Dz褬ª�����褦�ˡ��٤�ʹ֤⡢�����������˳�ɤ���ʤ������Ծ���ԤäƤ���ʹ֤⡢��������ʹ֤⡢����⤬�ֿ�ư�פ��Ƥ��롣�ܤ˸����ƿ�ư�Ϥ��Ƥ��ʤ��Ȥ⡢�ƵۤȤ���ȿ����ư���Ȥ���ΤϤ��ʤ�������Ϳ����줿�������������������˼������줿�����ΤۤȤ�ɤ�������������������˰½����Ƥ����ǽ���϶ˤ�ƹ⤤���ܤ�������ͤϸ����Τ餺������ʹ������ͤϲ���ʹ���Ƥ��ʤ����Ȥ������Ȥ���������Τ�������Ķ����¸�ߤμ��Τ�Dz�Ϥ��μꤳ�μ��ȤäƤ����˵��դ����褦�Ȥ��롣
�áʤȤ⤨�ˤȤ��������ϡ����ˤ�ä�ɺ���ͺ��ʤҤȤ��ޡˤΤ褦�ʡ��濴�˳ˤ���ä�������ͷ���륨�ͥ륮���μ��ΤǤ��ꡢ�ޤ������ʤӤ����ʤ���ɺ�ä�����������Ԥ����ꤹ���ͻҤǤ��ꡢ���뤤�������ʤۤ����ܤ��ˤΤ褦�ˤ�����������äƼ�������ֲФζ̡פΤ褦�ʤ�Τǡ����Ȥ��ơ��ҤȤĤ���̿�����α�̿��ɤ�����ΤǤ⤢�롣

�����ؼԤ������Ż�ˤ��С����áʤϡˡפȤϴ�ʪ�Ρּ�ü�פΤ��Ȥ��Ȥ���������ϥ�������ʤɤ����Τ��оο����Ϥ�ƫ������ۤκ������դ���줿��ü��פ碌������Ǥ⤢�ꡢ�ۤ�Ƭ��좤���Ф����Ϻ����Ρּ��פ������롣�����Ƥ���������Τ��Ȥʤ�����Ƭ�ʱ������˷����Ǥ��롣�Ĥޤ��ۤ�ĺ����դ���줿�ܥ���Υԥ�侾�μ¤Τ褦�ʷ��ξ����ʥĥޥߡʡֽ����פ�ɽ���ե��˥���ˤ��ܻؤ��ƺ��������������֥��쥹��: crests�פ�������������������ϸ������Ǥϡ��áʤϡˡפȸƤФ�Ƥ����Ȥ������Ȥˤʤ롣�����Ƥ��Υ��쥹�Ȥϡ������ͼ�Ū�ˤϤۤȤ�ɤξ��ֱ����פʤΤǤ��롣�����ơ����ˤϤ��ʤ餺�濴����ȯ�����롣��ư���濴����¸�ߤ���Τ����ʤȸ��������Ω����٥��ȥ�λظ�����¸�ߤ��뤫��Ǥ⤢�롣


����ۡˤ����¸���뾮���ʴݤ����ʱ��ˤϡ����Ȥΰ��β����ܻؤ������ʱ��ˤ����¸���뾮���ʴݤ�����ۡˤϡ���Ȥΰ��β����ܻؤ������줬����ư�θ����Ϥȹͤ��뤳�Ȥ��Ǥ��롣��Ū�ʡ�ȿ��ʪ�פ�¸�ߤ���ư�ε����Ȥʤ롣
�ֱ��ۡפ��ߤ��ˡ�69�ɡʥ��å����ʥ���ˤη��Ǹߤ��˳��߹�ä������ˡפΥ���ܥ�Ϥ褯�Τ��Ƥ����ħ�����Ǥ��뤬������Ф��Ρ�����áʤդ��Ĥɤ⤨�ˡפȤ�ƤӤ����褦��ɽħ�ξ��ϡ���Ԥ����ߤ��������ɤ��Ĥ����Ȥ��ƤҤȤĤα������뤰�����������μؤΤ褦�ˤ⸫���롣���Ρֱ��ۡפȤ��ä����Ф�����Ĥ����Ǥ��ҤȤĤμ��Τα��줿����Ū����פǤ��뤳�Ȥ⡢���ξ�ħ�ϼ������롣����������˶�̣�������Ȥˡ����������μؤϤ�����ˤˤ��켫�Τ�ȿ��ʪ�����Ƥ���ΤǤ��ꡢ�ۤǤ���Ф�����˱����Ǥ���Ф�������ۤ�ԳˡդȤ����ݻ����롣���ʤ�������줾�줬���줾����ɤ��Ĥ��������Ȥ�����������äƤ���Τϡ��ҤȤ��ˤ��켫�Τ�����뼫�ʤ�ȿ��ʪ�����ɤ����ɤ��Ĥ���¾���λ���Ʊ�����礭����ʬ�˴Ը����ۼ�����褦�Ȥ��뤿��ʤΤǤϤʤ�����ȿ��ʪ�ɤ����δ֤�¸����ָ����פȡ�����ư�פ���ͳ�ˤʤäƤ��ꡢ��ߤμ���Ū�ʼ椫��礤����̩��ɽ���Ƥ���Τ��⤷��ʤ���
�����������áʤȤ⤨�ˡפξ�ħ������������Գˡդʤ����濴����¸�ߤϡ����̡ʤޤ����ޡˤȤ���ɽħ������������˳���������̤�����ˤ�ä�ɽ����롣���áפȤ���������Ƭ�����濴���������û����ľ���ϡ��ޤ��ˤ��Ρֳˡפδ�ά���������Ƥ�����ΤǤ���ȹͤ�������Ǥ��褦��
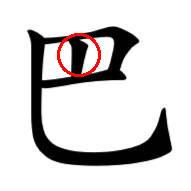
�Ȥ��ˡ������ä�ħ�Ȥ����Τ����ܤ����ݤ˱����Ƥϴݤ��ѥ�ѥ��ĥ��줿�顢�Х��ˤ�ä����Ǥ����ä���ξ����������ΤȤ��Ƥ��Τ��롣����ϡֻ����áʤߤĤɤ⤨�ˡפ�ħ�Ǥ��ꡢ���Ρֽáפ�����Ф����ܤΡ��ڡפ����ˤ�ä��Ǥ��Ĥ餻�С��礭�ʹ��⤿�餹�����Ρֻ��̰��Ρפ����ι�����ΤǤ��뤳�Ȥ�ʬ���롣


�ä�ħ�ϡ����������α����ư���ʤ���ʤ���������ҡˤ��ͤˡ������ȥޥƥ��å��˺٤�����ư�����ʤ��餽������ϤȤ������ʤ��롣��������Ӥ���ä����Ū�Ǥ���������®���ˤ������Ǥ���ñ��˦��ʪ�λ��äƤ����η�������Ѥ��Ǥ��롣�ޤ����Τ�����ˤޤ����ʤ�����ˤ�����ʤȤ������Ȥ�DNA���濴���������濴Ū���ۡդ�¸���ˡ���������λ����������徲���Ʋ����֤�����ȡ�����ϡִ�������ޤ줿�ǽ���ۻ������롣���줬�ޤ����̾��Ǥ��롣

��̿�γˤȤ��Ƥ�Ƭ�ȴ�夬��ü�˰��֤�������Ϥ߽Ф��ץ��ڥ餬���˰��֤���ʤ�С���ư������̿�η������̾��Ǥ��ꡢ�ޤ��ֲФζ̡��Ǥ��롣��̿�γˤȤ��Ƥμ�����֤�ʤ��ۻ������������������Ƥ���Τϡ��ֵ�ǽ��������������פ�����������äƤ⡢�����Ȥ������Ϥष�������ȸ����٤��Ǥ�����������ʤ��ΤϾ��ʤ��Τλ��ѤƤ���פȤ����Τ���������

�Dz��Touch the Sound�٤ˤ����Ƥϡ����Ρ��ä�ħ�פȤ����Τ�������������˽ФƤ��ơ���̿¸�ߤΤ��Ρֿ�ưŪ�פʼ��Τ��ħŪ�˸�����ΤǤ��롣����ϥ�����˥塼�衼���Υ����ɥ���ȥ��ؤǥ��ͥ���á���Ϥ����ˡ����������Ӥ˹�ޤ�Ƥ�������Υ����ߡפ������Ϥ˸���롣���������νп��ϤǤ��륹���åȥ��ɤ��ħ����֤Ǥ��뤬�����β֤ϡ��ޤ��˸�������ķ�Ū�����ΰ�ĤǤ��ꡢ����ȥ륳�å������ߤ�����λѤƤ��롣�����ơ������ݺ¤ȤΥ��å����ˤ�����Ϣ�Ǥ���������ݡ������ݤ��դ�ʪ�ʤΤϻ����äΡ��áפ�ħ�Ǥ���ˡ������ƥ��������������ˤ������ư������ǡ���γ��Ǩ�줿�������μ���ȡ�����ɽ�̤�عԤ������פ�Ĥ��ʤ���ۤȤ�ɿ�ʿ��ή��Ƥ�����ũ���ˤ�ä�ɽ������롣�ޤ����Dz�κǽ����ǿ��ſޤȻפ���Ĺ�����������Ѳ��ι��������ֵ����פˤ�äƤ�������롣
���λ�����뤬���ſޤΤ褦�ʥ��������ե�������ȷ��ˤ�Ͽ������ΤǤ���ΤϤ����������ǤϤʤ��������줿�������������Ȳ���Ω�Ƥʤ�������Dz졢Ĺ����������ʤ������������פ��롣�����Ƥ���ϡֲ��̱�¦�פ˸����ä����Ԥ��Ƥ����Τ��������Ƥ��������عԤ��뤳�Ȥˤ�äơ����ο�ư�������Ԥ�ȼ�������ΥХ��֥졼������Ū��ª�����롣
����ϼ����ʥ��ץ����ˤ���뤿��˺ǽ������˸����äƱˤ������뤤�����Ԥ��롣����Ϥ�������Dz��2001ǯ�����ι�٤ˤ����ơ������ڤä����áפ�ħ�Τ褦�����ҷ���������õ�����ǥ�����������椬�����������㥤��ɤ����߽Ф��٤����̤Ρֱ��ر��ظ����äơҹԤ������Τ褦�Ǥ⤢�롣��������Touch the Sound�٤κǽ����̤ϡ��������ˤ�äƼ��ߤ�����룴�ܤΥޥ�åȤ����ֺǸ�ΰ�ġפˤʤꨡ�������ޤ���ư���ʤ���ʤ����ҤΤ褦���������ڤθ���ȶ��ˤ��ο�ư��ߤ��⡢̾���ˤ������˥ޥ��Ф�ɽ�̤�������Ĥ���Τ�����ϸ��롣�����Ƥ����������˲��������ۤ����Τ��������뤳�ȤϤǤ��ʤ��ΤǤ��롣
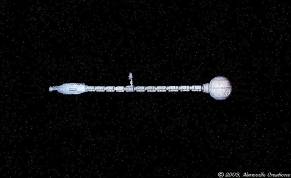
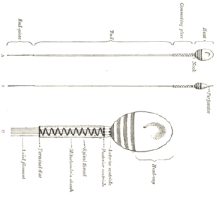

�ֿ�ư�Ȥ������Ƥ��뤳�ȡ���̿�ˤξڤǤ����
�����ʤ����Ū��å�������Ķ���ơ����褦����ۤɤޤǤˡ�Touch the Sound�٤������ο���̤碌��Τ������������Ϻ��Ф���륨����Ȥβ��ڤˤ��롣����θ��դϤ��Ф餷�����������ڤ���Ԥ��Ƥ��Ф餷���ΤǤ��롣
���������餷�����ڤϡ������ο��Τ���ˤ��ꡢ�������⼡�ʤ�ֿ�ư�����פ��Ԥ��ʤ��顢�Ȥ������ƴݤ��ʤä�̲�äƤ���̵�������Ҥ������줬�������ĤΤ褦�����ݤι줭�ˤ�ä��ܳФᤵ����줿���Τ褦��������餬�Ȥ�������䤬�����Ȥ�ư�����ʤ������������˸����äƱˤ��Ϥ��褦�ʴ��ФǤ��롣�����̲�äƤ��������ݤ���áפϡ����ΤФ��ڤäơ�������Ϥ��ΤǤ��롣����οͤ��ֱDz�ۤ������ä��פΤϡ��ޤ������Ȥ˴��������ä�̵���Ρֿ�ư�פ����������ž��浯�������˸���������Ϥ˽����ʳ��ˤʤ����Ȥ������֤ˤʤä���̤ʤΤǤϤʤ����Ȼפ��ΤǤ��롣
�����ͤ����Ȥ��������ݺ¤κ�Ĺ�θ������ܤˤ����벻�ڤ��ǽ�λϸ�����ͤ˱��줿ŷ�������Ͷ���Ф��������ڤˤ���Ȥ����⤬����פȤ��������������αDz����ǤɤΤ褦������Ū��̣�ΰ����������Ƥ���Τ�����λ��Ǥ��Ƥ��롣��ʬ�����̵���Ρִ�͡פ��顢��̿�θ��ʿ�ư�ˤ��������졢����Ф��ΤǤ��롣
�Ǥӱ�����Τ˱ɸ�ͭ�졧
�������ɿ������Ƚ
�������ɿ������Ƚ
�� ŷ��Ū�ʡȣ��ɤ��Ͼ�Ū�ʡȣ���
����ϡȣ��ɤȤ����ܿ��Ǥ���Ȥ����Ρȣ��ɡʤ����ƾ���Ū�ˡȣ��ɡˤδ֤ˤ���ط���������ݤ˺ƤӼ��夲�뤳�Ȥˤʤ���������������Ǥϴ�ñ�ˡֿ������פ�ᤰ��⤦��Ĥβ���Ȥ��ơ�ŷ��Ū�ʻ��̰��Τ�����ȿ�Ǥ������˸�������Ǹ����������Ͼ�Ū�ʻ��̰��ΤˤĤ��ơ������ơֿ������פ�ȯ������־岼�����Ū����ŷ�ϸƱ���Ū�ʾ�ħ��ǽ�ˤĤ��Ƹ��ڤ��롣
�Τ��ˡֿ������פ��Ͼ�Ū��ɽ�ݲ��Ȥ������Ū�ʡ�ħ��ˤĤ��Ƥ�����������Υ�����ָ����ȱ����줿���פΥơ��ޤ�ľ�ܤĤʤ��꤬������ʬ�ǤϤ��롣�������äơ������ǤϤ���줬��ˡָ���Ū�������פȸƤ֤Ǥ�����Ķ���Ū������Ρֺǽ����פȤʤ����Ū���ݥå��δ����������ˤκݤˡ��Ƥӡ�������Ƥ˸���뤳�Ȥˤʤ��Ͼ�Ū�ʡ�ħ��ȡ������ο���ʤ������κ¡ɡ����¡ˤ�������פʡ��о��ʪ�פ����ˡ������Ͼ�Ū�ʡֿ������פ����������Ф����Ȥ������Ȥ��Ŧ���Ƥ�����α��褦���ȣ��ɤλ���ˤ����ơ����ξ�ħ��ô���꤬�������Ū����˰쵤����·���������Ȥ����ξ�ħ�ηϤ�����ˤ��������ν����ʤΤǤ��롣
���ޤ��˽Ҥ٤��褦�ˡ��Ȥ�櫓���ȥ�å�����ΰ츫���ۤ��ߤ��ֻ��̰��Ρפο�����Ū����ˤĤ��ƿ�����������ʤ�����ʲ�Ǥ��ʤ��褦������Ÿ������������Ū�ǤϤʤ����ޤ��Ƥ俼��ʤ륭�ꥹ�ȶ��λ��̰��ζ�����֤�������褦��ĩ��Ū�����������������ΤǤ�ʤ����������뤳�ȤϤ��ξ����ΰ������ϰϤ��ưפ�Ķ���Ƥ��ޤ������������������ζ������˾���о�ȵ����Ĥˤ��ơ��ȣ��ɤλ���Υ��ݥå����Ϥޤꡢ�ȣ��ˤ��ƣ��ɤȤ������̰��Ρ��Ҥ��Ƥϡֿ������פˤ������դ������٤��뵷������ȡ��͡��β��ռ��ˡ�ʹ�������粻���פ���äƺ��Ѥ��������Ȥϡ��ֽ����͡פν���Ū�����ι���˼����Ǽ¤��礭�ʸ��̤ΤҤȤĤǤ��ä��ȸ���ͤФʤ�ʤ���������������Τ�������ݤˤ��������ֻ��Ĥǰ�ġפȤ����ֻ����ȡ��ȥ饤�����ɡפι������ħŪ�����ƤϤ�ƹԤ����Ȥ����ȱ�����ݤλҡɤΤ褦�ˡ��ޤ��ˤ��λ����˰��Ƥ˳��Ϥ��줿�ΤǤ��롣�����Ϥ��٤ƥ��ꥹ�ȶ�Ū�������̰��Ρ�����ɽ�ʤǤ������ȻҤ�����פȤ����ԲĻĤʳ�ǰ�ΥХꥨ�������Ȥʤä��Ͼ�Ū�ʾ�ħ��������ο������Ҳ�ˤ⤿�餷���ΤǤ��롣
������ʿ��Ū������ι���ʪ�ˤ����ơ��͵Ӥ�껰�Ӥ�ʪ��Ū������ݾڤ��뤳�Ȥ��Τ��뤬����������⤽�Ρȣ��ɤȡȣ����ܿ��ɤ���ߤ���ˡ§�����������Ū�������ˤ����Ѥ���Ƥ���Τ������Ǥ��褦�����뤤�������˸���������ʤ顢���������ԲĻ������ˤ�������꤬������ʪ��Ū�������ˤ������ܤ˸��������ȿ�Ǥ��Ƥ���Ȥ������Ȥ������붵Ū�����ˤ����ƹ�����ͭ�����Ȥ����Ǥ��롣�����ϡ�ŷ��Ū�ʻ��̰��Τ��Ͼ�Ū������פȤ���������Сַ������Ū�����ۡפ�ȿ�Ǥ�����ΤʤΤǤ��롣
�㤨���ܶ�ʤȤ����Ǥϡ�����줬�ַ�ȴ����ޡפȻ��ĤΤ�Τ��¤١��ޤ��ֻ���ο���פȤ������Ĥǰ��ȤȤ����Ȥ߹�碌�ߡ�������ɽ������Ω�������ˤ����Ρְ�����ޤ�䤹���פФ��Ȥ������Ȥ⡢���ߤˤޤǻĤ뤽�����������ΰ�Ĥθ���ȸ����뤫�⤷��ʤ����ޤ��ֻ��Ĥ��줬��Ĥ����Τ�٤���פȤ����褦�ʻ��Ӽ���������*�ϡ�����Ρ�Ωˡ����ˡ�������פλ���ʬΩ�ιͤ��ˤ�ȿ�Ǥ���Ƥ��롣�����ơֻ����ȡפ�������������Ƭ���ϡ��������λ�ƬΩ�Ƥ�����ʤ��ޤ���ˤˤʤ�äơ֥ȥ������פȸƤФ�뤳�Ȥ�פ��Ф���褦��

* ��˸���褦�ʸ������ε�������Ƽ��ˤϻ����ͤΤ�Τ�¿�������롣����ϡְ���פȡ�ɽħ�פΤդ��Ĥε�ǽ�˶�����ȸ����롣��Ǥ���Ƽ���Ť�ˤ�ʸ�ͤ����Ƥ����Ǥ��ꡢ�����Ť�����̤�������ʿ�Ū¸�ߡˤ��ҤȤĤδ����Ф����Ȥˤ�äơ������פ�ɽħ����ŵ��Ū���оο����ȹͤ��뤳�Ȥ��Ǥ��롣��ˡ����ˤ�Ť�ϡ����Ρ������פĤ����٤������ȹͤ��������Ǥ��롣������: axis mundi�Ȥ��������Ȥ�ǻ���ʴ�Ϣ�Τ�����оο����פˤĤ��Ƥϴ�ȯɽ�Ρ�����Ū��������ȡ�Ķ���Ū�����ˤĤ��ơ٤Ǥ���夲����������������˴�Ϣ����֣��ο����פǤ�����ˤλ����ʬ�˸Ʊ�����ֿ������פȤϴؤ�꤬�ʤ��������衧����Ū�ʾ�������ȡ��оΡ���������� [1]����¾
���������衧�����Ť�ʤȤ��ƤĤ��Ƥ���@ ����Թ�Ω��ʪ��
����ˡ��Ҳ�λ����ءּ���̱��ʼ�פȤ�����Τ��������ܤˤ����ơ����夫��������ΤǤ��뤬������ϥҥ�ɥ����Σ��ĤΥ������Ȥξ��ػ���������������ΤǤ��롣���ʤ���֥Х�������ȥꥢ������������פ��ޤ��ˤ���Ǥ��롣�㤨�Фޤ����ե�ˤ�����1302ǯ����Ϥ��줿�㻰�����ϡ�������ʬ�Ǥ��������ԡ������ʬ�Ǥ��뵮²���������軰��ʬ�Ǥ����̱�ǹ��������פΤǤ��ꡢ����ϡȣ��ɤλ�����о줷���ּ�ͳ��ʿ������פλ���Υ�������������֤��Τ餷���ե��̿�������ޤ�³����
������Ͼ�Ū�ʶ��Ȥ����������Ǥ⺣��Τ�����ˤˤ����ơ����Ρֿ������פθ������뤢���Ȥ�����ħ��ͭ���Ρ���������³�ԡפȤʤꡢ��������ֿ������סֿ������פȾ�ħŪ������ǻ���ݻ����Ĥġ���������ˤο�Ÿ�ξ�Ƕˤ�ƽ��פ�����̤��������Ū�פʶ����Ȥ��濴�ȤʤäƹԤ����ʤ���Ϣ³��������Ρֻ�������Τ����ޤ�¯���ˤ�����֥��쥤�ȡ��ȥ饤������: great triad�פ������Ƥ���ΤǤ��롣�ˤ��Ρ������ʡǽ����³�ԤȤ��ơ��ֿ������פ���Ķ����ȤˤĤ��Ƥ䤬��������ʤäƤ����櫓�������������ˤ����Ĥ����ƻ�Ƥ����ʤ���Фʤ�ʤ����Ȥ����롣���������ξ���������ǽ���ϰϤǤ���Ƥ����ʳ��ˤʤ��ΤǤ��뤬...
�� �ֿ������פ˴ؤ�������
��ˤ�쥳���᤹���Ȥˤʤ뤬�����ꥹ�ȶ�����������ιȤ������Τϥƥ��ɥ���������Ǥ��롣�����������ˤ����ơ����θ�β���ʸ���濴Ū�����Ū��Ľ��ľ��Ū�ʱƶ���Ϳ�������������ޤ�㣲�ġ��ʬ�䤷��ͤ�©�Ҥ˷Ѿ��������ΤϤޤ��ˤ��Υ�������Ǥ��롣����380ǯ�ˡֿ������פ��ݻ��������ꥹ�ȶ����Ρ������ƹ�ǧ�ꤵ�줿�Ф���Υ��ꥹ�ȶ���������ʬ��: schism�ˤ�äƻ��¾�֤դ��ĤΥ��ꥹ�ȶ��פؤ�ʬ�Ǥ��줿���춵������������Ǥ��롣�������������ޤΡʤ����ƥ��ꥹ�ȶ��Ρ�����ʬ��Ȥ������η�Ū�ʽ�����������ȣ��ɤλ�����濴��褹�륨�ݥå��Ǥ��ä���
������������ʬ���Τ鷺��ɴǯ���476ǯ����˴�������������������¯�Τ�ָ����ӥ�������פ��뤤�ϡ֥ӥ���ƥ������פȤ��������Ѥ���³������ΤΡ�1453ǯ�˥����ޥ����ˤ�ä����������̾�¶����Ǥ����������������ޡפϡ�����ޤǤ�̾�������֥����ޡפȤ��Ƥι�γʤ������ưݻ����Ƥ�����ΤΡ���ä��ᤤ������̵ͭ̾�²����Ƥ����ΤǤ��롣���¾塢����Ƭ���ɡפΰ��������������������˴���ȣ��ɤλ���ν���ˤۤܰ��פ���ȹͤ��뤳�Ȥ��Ǥ���ΤǤ��롣
�ȣ��ɤλ���Ϥ��Τ褦����������Ū���ݥå��θ�ˡ��ȣ��ɤλ���˰����Ѥ���롣���λ����ܤξ�ħŪ�ʡ������פϥ��ꥹ�ȶ����Ϥ��դ������ν����פؤȾ��ʤ���Ƥ椯ľ���θ��ϥ��ꥹ�ȶ��λ���ˤ��Ǥ˰ż�����Ƥ���������ϸ��ߤǤϿ��������ʡ�������˼㴳�ε��ҤȤ��Ƹ��Ф����Ȥ�����롣���ޤ줿�Ф���Ρֿͤλҥ������פˤϡ����������������㻰�ͤθ��͡䤬�������ˬ��[����3]��������������ʡ���롣���ꥹ�Ȥ�Ϥཽ����̤ϡ����Ͱ��ȤΡ֥ڥ��פȤʤꡢ�����ˤ������������̤ΡֻͶ��ʤ������ˡפ˸����ơ��۶�����ʼ�Ȥ���������롣����Ϥ������Ự�ڵϤΤ褦���ʤ䤸��: spearhead�˾��β����ͤ������λͶ��ʤ褹�ߡˤ˸�����ħ�Ȥ���*�ƽ��͡��ʷ��ǵ�Ͽ����Ƥ��롣���褤�衢�ȣ��ɤλ��夬�볫������ΤǤ��롣
* �������������̤λͶ���ɽ�����뽽���ͤξ�ħ����Ǥ⡢�㤨�в��Ρ֥ޥ륿�����Ĥν����͡פȡ��������ν����͡פ���ϡ�ǻ���ʡֿ������פ����������ʤ��������ͤ����ܤ�������ü����Ԥ�ʬ���졢�����⤽��ϤҤȤĤο�������ǻͲ��֤���뤳�ȤǤ��ο�������Ĵ����롣


���ǰ����衧The Maltese Cross - a sinister design?
�Ȥ�����������ǯ�ˤʤ�Ȳ��˼����褦�ʡֿ������פ������ͤȤ��Ȥ߹�碌���о줹�롣�����Ƥ���ϻͳѤ����������Ρ˥��֥������ȤȤ��Ȥ߹�碌�ˤ�ä�����Ū���о줹���Τǡ������λͶ���ɽ��������פȤ��Ƶ�ǽ���롣
 [1]
[1]  [2]
[2]  [3]
[3] 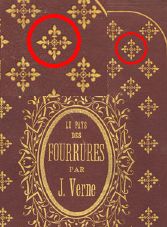 [4]
[4]
�֥ե롼�롦�ɡ���פ��Ͷ��ˤ����館��줿��
���ǰ����衧
[1] ��Wikipedia
[2] Fleur-de-Lys Medieval tiles @ Encaustic Tiles
[3] Richard Butterworth�Υ�����ǥ�����
[4] Le Pays des Fourrures��ɽ�� @ Jules Verne
�� ���̰��ΤΥ��祦�֤����


üŪ�˸����С�����ʸ���ˤ����ƺǤ���ɽŪ�ʡֿ������פξ�ħ�θ����ϡ֥ե롼�롦��(��)����: fleur-de-lys / fleurs des lys�פȤ����֥����סʲ��Գ�: yellow flag*�ˤ���ϤǤ��롣��˥ե�β��Ȥ���ϤȤʤ롢�֤Ǥ���spearhead�����ΰ��ˤǤ���ֻ����Ĥ�«�ͤ������������դȤ��������������ֿ������פ���ã�����Τ���Ū�Ȥ�����ΤʤΤǤ��롣
* �¤ϡ���fleur-de-lys�ɤ����β֤ʤΤ������β֤ʤΤ��Ȥ��������ϸŤ�����¸�ߤ���ΤǤ��뤬��������ܲ��֥����ʤβ��Գ��Ǥ���餷���פȤ������ȤǷ��夷�����Ǥ��롣���������줬�ɤ���Ǥ���Τ��Ȥ����Τϡ��������ä��ɤ���С���ħ������Ū�ˤ��ä˽��פǤϤʤ����ֻ��ۤβ֤Ӥ����ä��֡פ��̤�����ã�������Ƥˤ��������ܤ����뤳�Ȥ��������ξ�ħ�����δ��ܤ�����Ǥ��롣Iris pseudacorus: �����ʥ����°�Ǥ��ꡢIris�ʥ����ꥹ�����ꥹ�ˤȸƤФ��֤ΤҤȤĤǤ��롣Lily�ʥ��ˤǤϤʤ���


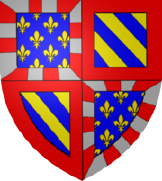
Iris pseudacorus�ʲ��Գ��ˤμ¼̡������������Ƥʻ��ۤβ֤Ӥ餫��¿���λ��ͤ���ϳؼԤ�̥λ���졢������ɽ������ε���Ȥʤä����Ȥ��������Τ����롣�夫�鸫����Τ�������餫�����������˻��٤�ʬ����Ƥ���ʾ屦��
���������衧�ʾ�˥֥르���˥����ϡ�ʩWikipedia���
�ʤ���Heraldica��������fleur-de-lys���ι��ܤ�ͭ�Ѥʾ�������ܤǤ��롣
�����Τ��Ȥʤ��顢�֥ե롼�롦�ɡ���פϻ��̰��Τ�ɽ�ݤ�����ɽŪ�ʿ����ǤϤ��äƤ�ͣ��Τ�ΤǤϤʤ������Ĥ��ؤ��������ѷ��������ʤɤ����Ĥ��θ���Ū�ʴ���Ū�ްƤ�¸�ߤ��뤳�Ȥ��ǤäƤ����ʤ���Фʤ�ʤ�������Ʊ�ͤΰ�̣�����¾�ο����Ȱ�äơ����Ρ֥ե롼�롦�ɡ���פο�����Ȥ�櫓��ö����¾Ū�פ˼��夲��������ʤ��Τϡ����������褦�ˡֶ����ȤȤ��ƤΥե�סʤ�����Τˤϡ���ˡ֥ե�פȤʤäƤ���������μ��ϼ�ã�ˤ����㻰���������������������ʳ��ǤҤ������Ѥ�����ΤǤ���ʤĤޤ���ˤΤ���ᤤ�ʳ��ǽ�̿�դ����Ƥ���ˤȤ������Ȥΰյ������ֻ��֤ȿ����״�Ϣ�ε�������Ǥɤ����Ƥ�̵��Ǥ��ʤ�����Ǥ��롣
¾�λ��̰��Τ�ɽ�ݤ�������ˤϻ����դΥ������С����ȥ�ե�����(trefoil) �������Ƥ�������η�������ä������͡�������¸�ߤ��뤳�ȤϳΤ��Ǥ��ꡢ�ޤ��������оο����δ�Ϣ�Ǥ���夲����������帢���θ������ʪ����ˤ�֣��ο����פ����Ф���뤳�Ȥ����롣�������ʤ��顢�֥ե롼�롦�ɡ���פۤ����Ƥ˽�����Ϣ�����ΤҤȤĤȤ����о줷���ۤȤ�ɽ����ͤ������֤�������ۤɤΰ�̣��: significance��ȯ�������ΤϤʤ�������ϰ츫�����ɬ�����⽡��Ū�Ȥϸ����ʤ��褦�ʨ��������Ǥ����ܼ�Ū�˽���Ū�ʨ����㤨�СֽݡפΤ褦������֥���������ɡפʤɤ˸���륷��ܥ�Ȥ������Ǥ⡢�����ͤ��ֿ������פ���ɽ�Ǥ��ꤨ���褦�˥ե롼�롦�ɡ��꤬�ֿ������פ���ɽ�ʤȤ��Ƥ���줬ª���뤳�Ȥˤϰ����������������ΤǤ��롣
�� ���ο������飳�ο�����
�Τ����ˤҤȤľ��������������
�� �����ħ���������Ū����
���������ͤȤ϶ˤ�ƽ��٤ι⤤�������ݻ�������ã���ʤǤ��롣�����ϤۤȤ�ɲ����ʤ����ˡ����ߥ�˥����Ȥ���ΤǤ��롣̵��ɽ�����줿�ֿ����פ��������Ū�ʳ����̣����Τ����̤ΰ�̣����ä��ֿ��פ��̣����Τ��ϡ����줬ɽħ���줿ʸ̮���Τ�̵�뤹��櫓�ˤ���������Ƚ�Ǥ�ɬ�פǤ��뤬�����������ͤȿ��Ȥ�����Τδ֤ˤ���ط��ϡ�������¿��ʤ���̤�䤤��������ޤǤ�ʤ������Ǥ��ڤäƤ��ڤ��ä����Ȥ��Ǥ��ʤ����Ȥ����餫�Ǥ��롣����ˤĤ��Ƥϡ�����Ū��ã�פ��ܻؤ������Ρ㸵����������ˤĤ����������ֿ�������ˤβ��뵷�פξ��ˤ�����㴳�ε��Ҥް��٤���ĺ���Τ��ɤ����⤷��ʤ���
���ȥ�ե�����: trefoil
���Ƥζ�����Ʋ�ˤ����Ƥ��Ф��ɤ�����������ƺ�ä�Ʃ�����뤬���뤬�������ˤϲ��ۤ��Ϥ����褦�ʻ���Ȥ��ƶ���ʤɤη���ʪ�ʤɤ�¿�����Ф���롣�ȥ�ե�����ȸƤФ����Ϥ��������ˤ����ƻ��Ĥαߤ��Ĥ˹��Τ������褦�ʴݤ����ۤΤ褦�ʷ����ˤʤäƤ��롣[����1]�������Ǥ���ĺ���Τϡ�Ʃ�����פˤʤäƤ��ʤ�����Ǥ��롣Ʃ�����ϵ�ǽ������������Ϳ���뤬����Ʃ�����פˤʤäƤ��ʤ��ʾ塢�±�Ū�ˤϲ�����ˤ�Ω����������������Ϥ��ο��������������ơʥ��˥ե����ˤˤ�����̣������Ȥ������Ȥμ¾ڤˤʤ롣

���ǰ����衧Illustrated Architecture Dictionary @ The Buffalo Free-Net ����Ƭ�ο���1���
��Ĺ�˿�ľ��ŷ��ظ����äƿ�Ĺ���륹�ƥ�ɥ��饹��ȼ����硢���������ȥ�ե��������Ϥ���ĺ���ˤ��Ф��и��Ф����Ȥ��Ǥ��뤷��ñ�ʤ�Ʃ������Ȥ���ñ�ȤǸ���뤳�Ȥ⤢��С���ϭ�褤���ФǤǤ����ꤹ��β��ˡַ����֤��Υѥ�����*�פȤ������ʤ�ʣ������뤳�Ȥ⤢�����Ƭ�ο���2�����ǰ����衧Sarasvati Sindhu (Indus Civilization) �ˡ�
* ��������ڤ����褦�ˡ��ֿ������פ��֣��dz�ä����פ��ʤ����0.333333...�פ��������Ȥ������Ȥ��۵����줿����
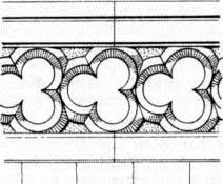 ���ǰ����衧Probert Encyclopaedia
���ǰ����衧Probert Encyclopaedia
�����������ۤ�Ʃ������ϡ������ȥ��ե�����: quatrefoil�����ե�����: cinqfoil �ʤɤΤ褦�˿�����ҤȤĤ���������ȯŸ���ƹԤ��Ȥ���������ʲ�Ǥ���褦�ˡ��ˤ��ñ��������ʬ����䤹����Ū�����λ���ʤΤǤ��롣
Foil�ϡ����ۤ��̣����tre-, quatre-, cinq- �ʤɤϤ��Τޤޤ��β��ۤο����̣����������̣���뤳�Ȥ��Ǥ�ޤǤ�ʤ���
�� �����դΥ������С�
���λ��̰��Τξ�ħŪ�����ϡ����ߤǤϤ�����������ѥȥ�å��Ȥδ�Ϣ�ǥ�������ɤˤ����륫�ȥ�å��ξ�ħ�ȤʤäƤ��뤬�������ˤ�����Ū���Ƥ��������Ū��̣�礤��ǻ����¸�ߤ��Ƥ���ΤǤ��롣�����Ƥ������Ƥϥȥ�ե�������̤��ƿޤ��褦�Ȥ�����ã���Ƥ�Ʊ�ͤΤ�ΤʤΤǤ��롣
 [a]
[a]
 [b]
[b]  [c]
[c]
���������衧
[a] UNDERSTANDING THE TRINITY
[b] Three Leaf Clover Floral Pewter Pin @ Exclusively Yours Gift Shoppe
[c] HIS MISSION OF FAITH @ Father Baker
���٤�Ҥ٤Ƥ���褦�ˡ���ʤ����Ʊ�ͤ˥��ꥹ�ȡʻҡˤ����Ʊ���ֿ����פ���ĤȤ����ֻ��̰��Ρפζ���ϡ�����������ˤȤäƤ�ñ�ʤ����۰ʳ��β���ΤǤ�ʤ���ΤȤ���ª������Ǥ��������º����ꥭ�ꥹ�ȤΡֿ����פ����ꤷ�ơ��㤨�пͤλҥ�������˿���Ʊ��뤹��ʤʤ����ϡ�����˽स����ΤȤ��ƴ������˥��ȥ�å��ζ���ϡ��������������Ѥˤ����Ƥϰ���ο������������ΤǤ���Ȥϸ����褦�������������ʹ֤Ǥ��ä����餳����˹ߤ�ݤ��ä�����˰�̣������Ȥ����ܼ���»�ʤ���Τ��Ȥ�����롣�ޤ����̰��Τζ��⤳�����ʹ֤�ʸ����������ʾ塢ʸ�����ħ�����ħ��˼椭������������������ʸ�����Τ�Τ˹ߤ�ݤ�������Τޤ���μ�����̣���뤳�Ȥ��۵�����Ф��������������Τ���ä�������͡��ˤȤäƽ���ʡ�����Ū�ʹ֡�λؤ�������ħ���ܼ�Ū��̣���ȴ���ˤ����ΤȤʤ롣���ʤ�������Υ��ȥ�å����ǽ�Ū�˺��Ѥ�������ϡ�������������Ū�ʡֿ������פΰտޤ������ΤǤ��롣�������Τ���ˤ������ζ���ϡ�ʣ��Ū�����볢�ʿ������Υ�������ˤ�äƿ��벽: mystify����ʤ���Фʤ�ʤ��ä��������������벽�ϡ���Ū�����פȤ�����Τ��Ф�����Ƚ������礤�����Թ�Ū�������Ѥ���Ƥ�������ˤϷ�ɤ��ο��Ĥ������ߤ�ʤ��Ȥ������¤�����������դ����Υ��������ؤ�̵ȿ�ʤʡֿ��ġפȡֵߺѤε��֡פϡ���������˹ߤ�ݤ��äƤ�����֤ˤĤ��Ƥ���Ǥ�Ȥ���ǧ�����ưפ�˺�Ѥ�����ΤǤ��롣
���ˤ����ο����Ȥ�����Τ�����������Ū�ʰ�̣�ǡ����������ֿ���Ū�ʿ����פΡ�¸������ˤ�äƺǽ�Ū�ˡֵߺѡפ����ˤ��Ƥ⡢������������ʹ֤μ¼�Ū��Ǻ���껦���뤳�ȤϤʤ��Ф��꤫�����ο���ǧ���Ϥ���˿�����Ǻ��⤿�餹�ΤǤ��롣�����Ƥ����丷�ʻ��¤��������Υ�å�����������Ǥ��ꤦ��ͣ�����ͳ�Ǥ��ä��ˤ�ؤ�餺���֥�������������æ¯���פμ¹Ԥˤ�äơ�����������������κ��ޤ��Ⱥᤵ���Ȥ������֤�浯�������������Ƥ������������ѹ����뤳�Ȥ�̵�����Ⱥᤵ�줿����פ����������ʤ���˻���ν��������դ���ΤǤ��롣
���ѥȥ�å�����������ɤˤ����ơֻ����դΥ������С��פ����ƶ������줿�Ȥ����ֻ��̰��Ρפζ������Ťΰ�̣����Ĥ��Ȥˤʤ롣����ϤҤȤ�Ƭ��˹ߤ���������ˤ��Хץƥ��ޤˤĤ��Ƥ��λ����Τ褦�ʷ����Ρ��Ф���פ꤫��������������Ԥ��Ф��ƤҤȤĤο���������ʤ���������ɤϤ䤬�Ʊ餸��Ǥ���������Ǥ��롣����Ͽ��Τ���Ĥ˰��������줿���ͤν���Ū�����������Ф����������Ŀ͡���Ϣ�礹��Ȥ��ˤ����椬�����������Ȧ�Ǥ��롣
�� ��ŷ�������פȤ��Ƥλ��̰��Το�
��˼��夲��ֿ������סֿ������פε��Ҥˤ����ƿ�������뤳�Ȥˤʤ���������������פξ�ħ�Ȥϡ����������������Τ��Ȥʤ��顢���Ф��С�ŷ���פʤ�����ŷ��פ��Ϸ�Ū���������Ѻ��ʡ�����о줹�롣�������ֿ������פˤ����Ƥ⤽����㳰�ǤϤʤ����Ȥ�ʬ���äƤ��롣�ֿ������פξ�ħ�ϡ����η������ü���������פ�ǧ������뤳�ȤϤޤ�Ǥ��롣����ŷ���Ȥ��Ȥ߹�碌�ˤ����Ƥ���ɽħ�κߤ����Ϥ�����������פΤ褦��������Ϳ����줿���Τ褦�Ǥ⤢�롣����ۤ�¿���λ���Ф����ȤϤǤ��ʤ������ܾ���Ƭ�Ǥ�Ǥ������ǣ��Τ褦�ˡ��ֿ������פξ�ħ�Ρ�ŷ���פȤ����餫�ʴؤ�����Τ����뤳�Ȥ��Ŧ���Ƥ����������Ȥ���Ʊ�ͤΥ��������֥르���˥�������Notre-Dame-de-l'Assomption ������ɲ�ο��ǣ��ϤǤ�ѻ����뤳�Ȥ��Ǥ��롣�����ˤ����Ƥϡ����̰��Τξ�ħ�Ǥ�����˼��夲���֥ե롼�롦�ɡ���פ�������ζ����ޤ�ﻡʤ���Сˤ���Ƥ��ꡢ�طʤ���ŷ��פǤ��뤳�Ȥ��ż�����Ƥ��롣�������äơ�������������Ƥ����ħ�������Τ���ŷ�峦�Ǥν�����Ǥ��뤫�Τ褦���κۤ��Ƥ���ΤǤ��롣
���������衧Eglise Notre-Dame-de-l'Assomption @ Montaron (Nievre)
���Τ��Ȥϡ��Ͼ�ο�ʪ�Ǥ��륢���ꥹ�ʤ����ˤˡ�ŷ���˼������������ħ��Ʊ����ǽ�����ʤ���ֿ����פ�ô���Ƥ���Ȥ������Ȥ�¾�ʤ�ʤ����դ˸����С����줫�鸫�Ƥ���Ÿ���ξ�ħ��������ξ�ħ�פˤ�̵�뤹�뤳�ȤΤǤ��ʤ�ǻ���ʿ���������������Ƥ���ΤǤ��롣
�ʡ���פν�����
�������ɿ������Ƚ

 ��
��
������̾�Ρָ��λ��֡פϡ���������Τ�ɽ�����⤷��ʤ����ʤ��ʤ餳��ɽ���ˤϤ�������������ˤϤ��ä��ҤȤĤμ���θ�����¸�ߤ���������ͣ��θ��˻��Ĥ����֤�����פȤ��ɤ����̾������Ǥ��롣�������������Ǥ��褦�Ȥ��Ƥ���Τϡ��ष�������ۤʤ룳�ĤΡָ��סʤ�������̩��Ϣ�Ȥ���äƤ�����ˤˤĤ��Ƥιͻ��Ǥ��롣�����Ƥ��Ρ�Ϣ�ȡפ����뤳�Ȥˤ�äƽ��Ƥ������Ʊ��פ������뤳�Ȥ���ǽ�ʤΤ��Ȥ������ͤǤ��롣�������Ƥ�դߤ�С��ȤƤ⣱��Ǹ�꤭������ƤǤϤʤ�������Ԥ���ơ��ޤο�Ľ�⤢�ꡢ���������˥���������뤳�Ȥ�������ʤ��Τȡ������ˤĤ��Ƥϥ��ꥢ���Ǥˤ�ä����Ū�ʸ��椬����Τȡ�������Ū��������פ����ͥ�����ˤ����Ƥ⤹�Ǥ�ɬ�פʿ��Ǥ��̤��Ƥ������ٴѤ��褿�Τǡ������Ȥ���ĺ�����Ȥˤ��ơ������ǤϽ��פʡָ��פˤĤ��Ƥ�����ζ�ͭ�������ܻؤ����Ȥˤ��롣
�ޤ����ꥢ���Ǥθ��դ�Ҳ𤹤뤳�Ȥ��ܹƤ���Ū�Ǥ�ʤ��Τǡ���䤿����줿�Τ���������˴�Ϣ������ۤɤ���������ʤ�ʸ���������äƤ���ͤ⤤�ʤ��ΤǤ�Ϥ���������Τ����롣
���ιͻ��˲��ͤ�����Ȥ���줬�ͤ���Τϡ��ۤʤä���ΤǤ���Ϥ���ʣ���θ�Ū��¸��ʪ��¸�Ԥ��������˶��̤���¸�ߤ�������������ʤ�Ʊ��̾���ǸƤФ�Ƥ�������ˡ����λ��ݤ��Τ�Τ�ʸ���̤��Ʊ����ΤǤ���פȹͤ�������Ƥ����̤����ꤽ���ʤ��ȡ������Ƥ��κ���ˤ�äƤ���줬�������������Ƥ���ˤ�ؤ�餺����˵��դ����ˤ����ǽ�������뤳�ȡ����ʤ�������Ρָ��פΤ��꤫���ˤĤ��ƤΡ�̵���Ū�ʡ˹���Ūǧ�����̤�����¾���Ρָ��פ��ꤹ�٤���ΤȤ���줬�ͤ��Ƥ��ޤ������ˤʤäƤϤ��ʤ������Ȥ���������Ū�ʴ����פء��ҤȤ����դ�����ɬ�פ�ǧ��뤫��Ǥ��롣
�����ɤ���Τ��Ȥ�������Ū��ǧ���ϡ��������ԤǤʤ��Ƥ�ۤȤ�ɰ���Ū��ǰ�Ǥ���ȸ��äƤ��ɤ��������������ưǤ����ꤵ���٤���ΤǤ���Ȥ�����ʸΧ�ϸ�����ꤹ��������ɽ���ΤˤʤäƤ��롣�Ť��ǤǤϤʤ����뤯�Ȥ餵�줿������ָ�����ۤȤ�ɽ���Ū�ȸƤ�Ǥ��ɤ�����������Ū�����������¿���ϻ��äƤ��롣�������ä�����Ū�ˤ����Ρ���������פϡ�����ޤ����ι���Ū¦�̤ˤĤ��ƤΤߡָ������ơפ����Ǥ��ä��������ơ��Τ��˸���̵���˹��ꤵ���٤���Τȹͤ���������ϡ�¿���ν����Ȥ����Ȥˤ�äơֵ����ʤ���ͭ����Ƥ������˸����롣���������ܼ��Τ����Ĥ��θ��ڤ��Ǥ������Ʊ�ͤθ����ݻ��Ǥ��뤫�ɤ����Ϥ�������ο��ټ���Ǥ��ꡢ�ޤ���̿¸�ߤ��Τ�Τ��Ф������ټ���Ǥ��롣���Ȥ����ºߤ�¿�����Τ��٤ƤΥ����ڥ��Ȥ����ʤ���С����ο������ã���뤳�Ȥ���������������ǧ���פ���ã���뤳�Ȥ����ʤ��ΤǤ��롣
���Ȥ�����Τ�����Ū��̵�뤹�뤳�ȤΤǤ��ʤ������ΤҤȤĤϡ����Ρ�ǽư��: activity��ˤ��롣�����ưǤ������Ȥϡ��ư��: passivity��Ǥ��롣�㤨�и��������ȰǤ��������ɤҤȤĤdz֤Ƥ��Ƥ�������ꤷ�ơ������ɤ˷꤬�����줿�Ȥ���ȡ����ϰǤ����˸����äƼͤ�����ΤǤ��ꡢ�Ǥ�����������ή�����뤳�ȤϤǤ��ʤ����Ĥޤꡢ�ǤϤĤͤ˸��αƶ����˻�����褦�Ȥ��Ƥ���ΤǤ��ꡢ�������Τ�Ʊ�������Τ�Τ������������ۤ��褦�Ȥ��뷹�������롣¿���ο͡�����������ι������Ȥ�ʢ�ˡ����������Ȥ�����ΤϾ��̤ˤ�äƤϤ�����˽��Ū�ǡ�ȴ������������Ū�ǡ�̵����Ǥ������롣���θ���������̵�뤹��ˤϤ��ޤ�˽��פʤ�ΤǤ��롣
�������äơ������Ǥϸ������ꤵ��٤���Ρ����ˤǤ���Ǥ����ꤵ��٤���Ρʰ��ˤǤ���Ȥ��������ͤˤȤäƤ����ˤ�ʬ����䤹��ñ��ʡ���������פ��ö���������ˤ�����ǡ��ֻ��֡פΤ��줾�줬���äƤ������������Ƹ�Ƥ���٤��ʤΤǤ��롣
����줬���̤��ʤ���Фʤ�ʤ����Ρֻ��֡פȤϰʲ��Σ��ĤǤ��롣���ˡ�ʸ���פ��̣���֤ҤȤ���������餷�䤹���Ȥ����ˤ���פȸ���쿮�����Ƥ�������ι٤Ȥ��ƤΡָ��ס��Ͼ�Ū������Ū����¯Ū������Ū�ʸ��ˡ�����������ˤϿ��Ȥ�ǡ��*�Ȥ⥭�ꥹ�ȤȤ�ƤФ졢�ޤ�ŷ��Ū������Ū������Ū����̿���ͥ륮���Ȥ��Ƥ������ָ��סʿ����ˤ��Ƽ�¸Ū���ʱ�Ū�ʸ��ˤǤ��롣�������軰�ˡ�ŷ����Ͼ�Ȥ��ӤĤ��뤿��˸��������˽и�����������Ū��Ķ��Ū�ʡָ��סָ����ס������Σ��ĤǤ��롣�軰�θ��ϡ���ŷ��ΰտޡפȡ��Ͼ�ν�������Ͼ�Ū�ʴ�˾�ˡפȤ���פ����뤿��ˡ֤������ʤξ���ˤ����פ������������ʤ�̸��פȸ��������Ƥ�褤��
* ������ǡ��ʤ��ߤ��ˤ�餤��amitaabha�ˤϡ�������ʩ�������ˤʤɤȤ⤤�������ʩ����ǡ��ΤҤȤꡣ�֥��ߥ����楹(amitaayus)�����ߥ�����(amitaabha)�פ������ơ�̵�̼�ʩ��̵�̸�ʩ�ȸƤФ졢̵���θ����ޤͤ��Ȥ餹����ʩ�Ȥ���롣(by Wikipedia)
�����Ƥ���줬����ˤ���Τϡ�����黰��θ�����������ҤȤĤΤ�ΤȤ��ơʴ����Ƹ����С����ʤ��ΤǤ���פȤ��ơˡ�̵���Ū��̵ȿ��Ū��Ʊ��뤷�Ƥ��䤷�ʤ������Ȥ������ȤʤΤǤ��롣����餬��ߤ�̵�ط��Ǥ���Ȥ����ΤǤϤʤ�����Ʊ��Τ�Ρפȴ�ñ�˼�������Ƥ��ޤä��ɤ��Τ����Ȥ����������������ΤǤ��롣
���θ������ʤ���Ͼ�Ū�����Ū�ʸ������¤ϡ������ȡʥ��ꥹ�ȶ���ʩ������鷺�ˤˤ���۶���ư�������Τؤξ�ư�ʹ��ˤȥ��åȤˤʤäƤ���ʾ塢�������ˤ����ƤϳΤ��ˡֽ����פ�̵�ط��ǤϤ������ʤ��ΤǤ��뤬������ϿͰ٤ˤ���ΤǤ��롣�����Ǥϡֽ����פ�����Ū�˰���������Ȥ�ݽѲȤˤ�äơֵ��ҡפ���Ƥ����֤������ʤ�̸��פ��ص�Ū�ˡֽ���Ū�ʸ��פȸƤ�Ǥ���ΤǤ��뤫�顢��Ϥ���������θ��ϡʰ�ö�ϡ˶��̤���ʤ���Фʤ�ʤ��ΤǤ��롣����������θ����θ��ˤ�äƴ������褦�ȡ����ʤ�ºߤؤ����פ�פ����Ȥ���ʹ֤ξ�ư�䡢���Ū�˹Ԥ��Ƥ������Ԥ�ºݤ��θ��ˤĤ��Ƥε��ҡ�ɽ���ˤ�¿���ο����ʿ���Ȥ����������褿���ȡ��������ɿ�Ԥˤ����θ������θ����ɵ���Ρ��Ͼ�Ū�ʸ��פ���ˤȤ����ζ���Ū�ʰ��פ����̤����뤳�ȤϤҤȤĤ��õ�����ǤϤ�������
�褯������Ͼ�Ū�ʸ��˴ؤ��Ƥϡ����줬ʸ���Ρ����פ���������ʬ�����ءʳ��աˤ��̣����Ѹ�Ρ�enlightenment�ɤ���Ρ�light�פ���������ʬ������ʲ�Ǥ���褦�ˡ��͡���Ǥ��դ��������֤�������뤯�Ȥ餵�줿���֡פ��ʤ���֤�Τθ�������֡פؤȤ��������꤫��Ƴ���Ȥ�����ʸ����⤿�餹¦�פ���½�ʻפ����ߤ����äƤ�������Ω�äƤ����Τ����������ʳ�Ū�ͤ�ʳص��Ѥ���ʪ��Ū�ˤ�֤�����뤤������פ�¤��Ф����Ͼ��ʸ���̤�Ȥ餷�Ф��Ƥ���Ȥ������¤Ȥ��ι���Ū�ʻ�ˡ�����衼���åѤ���⤿�餵�줿���¤϶�̣�������ϵ��ʸ�������줿�ΰ�ϡ��º����ꤽ��ʳ��ν��ϰ�������뤯�Ȥ餷�Ф���Ƥ��롣�������֤ιҶ��̿��ʿ��ǣ��ˤˤ�äƤ��ֳ��������ˤ���Ͼ��Ǯ������������餫�Ǥ��롣ʸ���Ͽ���ο����ܤ�Ϳ������Ʊ���ˡ�ʪ��Ū�ʸ����⤿�餷�Ƥ������Ǥ��롣
�����ơ������Ȥ����Ȥ����ä��ɵᤷ���ޤ����Ҥ����褿�ֿ�������ʤ���ס�����θ��ˤؤο��Ĥϡ��Ͼ�Ū�ǿͰ٤�ͳ�褷�ʤ�������θ��Ȥ��������ʤ���㤹��ʪ��Ū�ʸ����軰�θ��ˤ������ؤȡ������¿�����ߤ�Ω�ƻɷ㤷���褿�ΤǤ��ꡢ�ޤ����ε��Ū�ʷ�̤Ȥ��Ƥ�Ķ��Ū��������Ū�ʡ���䤵�����γ�Ҥ���Сפˤ�äƺǽ�Ū�˳��������������Ƥ��κǽ�Ū�ǺǤ���ʸ�����¤�ϡ��ʹ֤ε��ͤ���̤��뤳�Ȥʤ���̵���̤ˡ�ʿ���ˡ��ָ��θ��˻����פ��Ȥ�ۤ��������ǽ�Ȥ�����
���ꥢ���Ǥθ����Ȥ����Ρָ���ʬΥ�פ�¿��Ū���ͤϡ��ޤ��ˤ��λ��¤��ٳ��뤷�Ƥϰ�̣��ʤ��ʤ����⤦���ٸ�����
�����ǽ�Ƥ���ָ�����פȤ�����Τ����ְۤʤ뻰�Ĥθ��פ�ᤰ���ΤǤ��뤳�Ȥϡ����ˤ����ˤȤäƤ����餫�ʤΤǤ��롣�������Ͼ������줿���θ��ˤ�ä�ŷ�������θ��˶�Ť������������θ��ε��Ū�ºߤǤ����軰�θ��γ����ϡ�����������������θ���������Ϣ���᤹�Ȥ������ȤʤΤǤ��ä����Ϥ�������������ʤ顢����줬�ָ��פ���̤��ʤ���Фʤ�ʤ���ͳ���ޤ��ˤ����ˤ���ΤǤ��롣
���ǣ������θ���
�Ʒ��ε�����DMSP���������Ƥ���������ϵ�פμ̿���ʸ����ʬ�ۿޤ����Τޤºݤ���֤θ���ɽ����Ƥ��롣
������
���ǣ�������θ���
���Ÿ�̾ĥ�ԡ����ӻ�����¤������ǡ��Ω���ַ�Ĺ����ǯ��1609��Ȭ����ߺ�ν��͵�̣��Ƿ��
������
���ǣ����軰�θ���
ICBM����������Ǥ��夲�¸���������θ��פ������¸���������θ���ʸ���ˡפε��Ū���ʡ���帢��ħʪ��
���͡���ǽ���Ƥ��ʤ���Φ����ƻ�ơ�ICBM�ˤ����䤹�륪����������ȡ�¿ʬ���̡�
���ؤ������
���ؤ������
 ��
��
�� ���ϡʥ��������ˤ��оΥǥ������ͳ��
���ڵϡ��ڵϤ��濴�����ϡ�������帢��ɽ���濴���������ˤǤ���ȤȤ�ˡ���ħŪ�ʡֲ֡פλ�ɡʥ�١ˤǤ��롣����ϸڵϤǤ���С������λ����������濴���������Ȥ���ʣ����ͺ�ɡʥ����١�Ʊ�Τλ�帢�����˴�Ϣ����Ʈ��Ǥ��ꡢ���ڵϤǤ���������ʤʤ������̡ˤ����濴���������Ȥ����ܶ�ȳ�Υ�ʶ�Ť����ĤĤ�Υ����Ƥ���ˤ����֤Ȼ�뤳�Ȥ����롣
���Ǥ˴ѤƤ����褦�˻��ڵϡ��ڵϤ���ϡ����켫�Τ����Ť�����������֥��ѡ����ץ饰�פǤ��뤬��Ʊ�����濴����ɽ���ե��˥���Ȥ�����������Ȥ������̤������Ƭ�פΥѥ����Τ�Τ����Τˤʤ����ΤǤ⤢�롣�Ĥޤꡢ������Ū�ˤ��Ǥˤ������ߤ��оι��ޤˤ���Ȥ�����̣�Ǥ��Ŷˤΰ�����ʣ���ʣ��ܤʤ������ܡˤǤʤ���Фʤ�ʤ��ä���
���Τ褦�˹ͤ������������������оι�¤����ͳ�ΤҤȤĤ����������ΤǤ��롣�ץ饰�ȹͤ����Ȥ����Ŷˤϥץ饹���ޥ��ʥ����줾�죱�ܤ��ĤǤ���е�ǽŪ�ˤϽ�ʬ�ʤΤǤ��뤬�����ϤΡ��Ŷˡפ��Ű���ä��ơ����줾�����ü����ʬ���濴�ؤ��ܶᤷ�ƺǸ���ܿ�����ľ���˲в֤����롢��������ϡ����Ĥʤ������Ĥ��۶ˤΤ����Τɤ줫����֥��ѡ����פ�ȯ������ΤǤ��롣
���Ϥˤ��ȯ�Фϻ�帢�γ�����³���������Ͼ�Ū�ʤ��ΤˤȤäƤΰ��祤�٥�ȤȤʤ롣���Ϥˤ�륹�ѡ����ʲв֡ˤ�ȯ����ͺ�ɤλ�ɤȤ��ܿ��ʤ��ʤ����ʴ�ˤϡ�Ʊ�����ݥå���褹�륤�٥�ȤǤ��롣�֤ϼ�ʴ�ȤȤ�ˤ��������롣�֤ϸϤ졢�¤����ꡢ��ʪ�Ȥ��ƤΥ饤�ե�������Ͻ����ޤ��������γ��Ϥޤǡּ�ҡפȤ���Ĺ����©�˽��������ѡ����ץ饰�������ˤ�����ֲФˤ�빹���פ�ü��Ȥʤꡢŷ����Ϥ��ۤɤΡ��礭�ʲ֡פ�餫���롣������ɽ�̾�ˤ���ֳ�ư�פ٤Ƴ��ξ��֤��ᤷ�������γ��Ϥޤ�Ĺ����©�ؤȽ������롣�����Ƥ��Υ��饤�ޥå���Ū������ϡ��ޤ����Ͼ�Ū�����ȸƤФ������������
�� ��ʪ�Ȥ��ƤΥե��˥���
�ʾ�Τ褦�ˡ��ե��˥����ʪ������ˤʤ��館��ʤ�С���ʴ����ʲ�ʴ����������˥�٤Ǥ��뤬��ưʪ�η���Ū�ˤϥե��˥���Ϥޤ�������������Τ���Ǥ��뤳�Ȥ�ȿ������ԤϤۤȤ�ɤ��ʤ��������ʤ��������ۡפΰż������ΤϾ�ˡֱʱ�˽���Ū�ʤ��ΡפȤ��Ƥ���ϲ�ǽ�Ǥ���ˡ������ƥե��˥��뤬��������ʤ��뤤��ñ������ˤȷ���Ū�˻��Ƥ���Τ϶����ǤϤʤ����֤�¡ʲ�ʪ�ˤȤ��ä���ʪŪ����ܥ���֤�����뤳�ȼ��Τ�����äƤ⡢��ǽ��Ρ������Ū��¦�̤���Ĥ��Ȥ����餫�Ǥ��롣
ʸ���ο�ʪŪȯŸ�����������Ρ���Ū�ʡ�ʸ���١�ŷ���Ϥ��褦�ʹ⤤�����ŷϰ����Ƥ��������Ū�١�ŷ��ã����褦�����Ե�������Ǥ��夲�����������Ū��ơˤ˸�����Ȥ����Ρ��־����˿�Ĺ��ŷ���ؤ��न��ס־����ؤ����Ƥ�ŷ������������ס��֤��⤯�פ��ѥ������äˤ��ο�Ĺ�����ִȡפ���ü���������פ���Ȥ����ѥ�������˺�����ʪ��Ū������*�Ȥ����Τ����ꤹ�뤳�Ȥ�����ʤ���
�ޤ��������ˤȤäƤΡ���˻���פȤ���ʸ����ư���ΤΤ�����������Ū����λ���ˤ����ʤϡ����ޤ��ޤʤȤ����Ǥ��Ǥ��������Ƥ��ꡢʸ�ؤ����Ѥ��̤��Ƥ�ɽ������Ƥ�������**�Ǥ��뤳�Ȥ��۵����뤳�Ȥ�ͭ�פǤ�������
* ���͡��������������θ�����˸������� + �� + ����������פξ�ħ
�֦��ķ��פȡ��� + ����������פ�ξ��������Ū�ʤ�Τ�ª�����������Ѥΰ��㡧Gilbert & George ��DICK SEED, 1988��
** �⡼�ĥ���Ȥ�����ū: Magic Flute�٤�ɽ���������Ȥ�ֱ��פ�����ۡפ������ؤλ������ħŪ����������ͺ���Ǥ��롣��ν���: The Queen of Night ��ò��ˤ�äơ�ڼ��줿̼�ε߽Ф˸��������������ɤ�̼�����᤹�ɤ����������餬�������οȤˤʤäƤ���̼�Ȱ��˰츫�ְ�����������ۿ��ʥ��饹�ȥ�: �ĥ���ȥ����ȥ�ˤ������˼����ޤ�Ƥ��ޤ������ɤ�뤢�����������Ǥ��롣�����ˤ��������ʤ����֤��뤬�ޤޤΤ����������פ�ø���Ⱦ�ħŪ������������Ū̾��Ǥ��롣
�� �����פȤ��Ƥ�����
��������������פȡ����פδ�Ϣ�Ȥ����Τϡ����ޤ��ޤʤȤ����ǰż�����Ƥ��������ä�������Ƚơ���ˤ��gun, pistol, canon�ˤˤ�����ȡ�����̾���ǡ�������ΰż��פȤ���Τϡ��Τ������ǹ����Ѥ����ΤǤ��롣�����ܼ��ϡ����ơפ����ӽФ�Ĺ�������ä������Ǥ��롣��Ū�ʤ�Τȡ����Ρֽ����: final, finish, finale�פ�魯¤��ʪ�δ֤ˤϡ��������ӥɡ�Ū�Ȥ��������褦�Τʤ�������в��̰ռ��Υ�٥�ǤΤĤʤ��꤬���ꤽ�����Ȥϡ������ǰ�ö�õ����Ƥ����Ƥ�̵�̤Ǥ���ޤ����Ĥޤꤽ��������ɽ�����褦�Ȥ������ƤȤϡ��ʿ���Ȥʤ�б���Ū�ȤǤ�ƤӤ����ʡ��������ϤΡֺ����������פȤ��������ε���ʤΤǤ��ꡢ����ϸ��¤ε���Ū�뺧�������ˤ��̤����������Ƥ�����ΤǤ⤢�롣����Ū�����������Ȥε���Ū����ˤˤĤ��Ƥ⥨�ꥢ���Ǥ�������Ȥ����Ǹ��ڤ��Ƥ��롣

ʼ�˸����ڴ���ҤΡ��˺���ɡ���ϻ�åᥬ�ꥹ�פΤҤȤ�
�����ˤ��������������ʤ��ꡢ��ħŪɽ�����ʷ��ˤ����ơ���Ū�פʾ�ħ�����������Ƥ��뤿��˰���Ū��ª��������Ū���䤽�κ���Ū��ɵ����ͳ������ΤǤ���ʤ��٤Ƥ����Ū�פ˲�᤹�뤳�Ȥ������������ȹͤ����ӥɡ����⡢����Ū��������Ŧ���뤳�Ȥ��������Ѥ���ȹͤ�����λ��Ū����ˡ�����������ħ����������ʿ��ΡˤȤ��������ǽ��������ǡ������ο����������ȹͤ��뤳�Ȥϡ��Ϥ���Ǥ����Ҽ�����ȸ����٤��ǡ��������ɽ���Ƥ���פȤ���Ǽ�������Ǥϼ¤������Խ�ʬ�ʤΤǤ��롣�����ε�����ʣ����ȯŸ����ʸ���٤˱����ơ����줬ǡ���ʤ����Ρ�����סֿ��Ρפ�ɽ���Ƥ���Τ��Ȥ������Ȥޤ�����������ʤ���С����Υե����ǥ�����Ū����Ū��Ϣ���ο��˽���ʰյ��Ͻ��������줺���������Ū�ʡֳ��פ���ǡ����ؤǡ����Ǥ��ʤ���Ф��ޤ��Ѥ�ʤ��ʤ�������������ˤĤ��ƿ����ꤹ��Τϡ�����餫��ֵ��Ū�ˡײ����ɤ���Τ��Ȥ������Ȥ��濴Ū����Ȥ����ܹƤ���Ū�ˤ�����ʤ���
 ��
��
�����֥Хͥ����롢�ѥ饹�顦��������Υ����ʪ��
�����ݥ���ʥ�Siva Devala�Υ����ʪ��
������פ�ɽ�����Ȥϡ����K�Τ����̤˴ؿ�������ΤǤϤʤ������郎���η��Τ��̤��ƾ�ħŪ�˻ؤ������֤�Ρפȡ������������������ؤ������֤��ȡפ�ξ���˶�ͭ����뤳�Ȥ�¸����˲�ʤ����Ȥ��Ŧ�����α��褦��
�� �ֽ���餻���ΡפȤ��Ƥ����
�������������ʶ��ϡˤ�����Ǻ���Ǥ��������ζ줷�ߤ�ֽ���餻����: terminate�פȤ���ǧ������Ƥ��뤳�Ȥϡ��ष���ܹƤˤ���������ε����ʾ�ˡ����˹����ֿ��ļԡפ�λ�Ƥ���Ȥ����Τ�ΤǤ��롣�ޤ����������������ߤ����������뤳�ȤǸ�������Ǻ����Ρֲ����פ�ޤ�Ȥ����Τ⡢���Ǥ˿��ļԤˤȤäƤ������ߤΤ���ͤ��Ǥ�������
�������оο������濴�˰��֤����finial�פȤ����Τ���ʪ�ʤ���Ʈ��β̤Ƥκǽ�Ū�ʳ���ʪ�Ǥ��ꡢƮ��ξ��Ԥ�Ϳ�������Ρ����ʤ���ֻ�帢�פ��ħ�����ΤǤ��뤳�Ȥ⤹�Ǥ˴ѤƤ����������������оο������濴���֤�����Τȡ���κ����Ƥ��֤�����Τ���Ʊ����Ʊ���ʪ�Ǥ��뤳�Ȥ⤹�Ǥˤ�����λ�Ƥ��롣���ʤ���������ȼ����ζ��֤��ħ�������Ū����Ǥ�������ˡ���κ������ۤ�����羾�䤽�Τۤ��μ������ꡢ�����Ƽһ�ʩ�դλ���κ������ۤ�������ϻΤ����ƹ����⡢�ֺǽ�פǤ���ֺǸ�פǤ�����֤η������Ǥ��ꡢ����϶��������ֳ֤����֤���뵼�����Ʊ����̣����ġ�
�Ȥ�櫓�����ܤ����ݤ�«�ͤ��羾�������ν����ʦ��ˤȻϤ�ʦ��ˤȤ�����Ĥμ����ζ��֡�ǯ��ǯ�ϡˤ˸�����ħʪ�Ǥ��뤳�ȤϤ��Ǥ˸������������֤��褦�ˤ������ݤ�ּФ���ڤ�פȤ������Ȥ����������Ū��̣�ϡ�����פȤ������Ǥ��롣�����ˤ���������Ǥ���褦�˻��̰��Τ�ǻ���ʴ�Ϣ�Τ�����ɸ��פʤ��������פΰż��Ǥ��롣�����ơ���Ĥ���Ƭ�ʤʤ�����ʪ��̢�ˤ���帢���äƶ����礦�����Ϥ��濴���न��Τ��ե��˥���Ȥ������ۡפʤ������աפǰż�����뤢���ξ�ħ�Ǥ��뤳�Ȥ⸫�Ƥ�����
�����λ�帢����Ʈ��ϡ����λ�帢��������ƼԤ��ֳ����פ��뤳�Ȥˤ�äư츫����뤫�˸����롣�������Ƹ���Ʈ���餻��Ȥ������̤��ˤ��Ф����Ǥ��ä������������Ȥ��ʤ����Ϥʤ����Ȥ�Ʊ���Ǥ��롣�������줿�����ۡ��աˤϻȤ�줺�˺Ѥޤ���뤳�ȤϤʤ�������ϳ��������Ԥˤ�ä����ꤵ�챣ƿ����褦�Ȥ��뤬�������뵷��ɬ����ϳ�̤���ΤǤ��롣�����Ƥ��λ�帢�����ꤷ�����˸������Ƹ��Ԥ����䤬�Ƥ��γ���ʪ�ˤ�ä���������뱿̿�ˤ���ʥХ������åɡ������������Dz���Ϲ����ۼ�Ͽ�١��ե졼�����ض���ӡ١�¾�ˡ�����Ϻ��絬�Ϥ�˽�Ϥ�ʿ���ˤȤäƤΡ�ʿ�³����μ��ʤȤ���Ԥ����ν�̿�Ǥ��롣
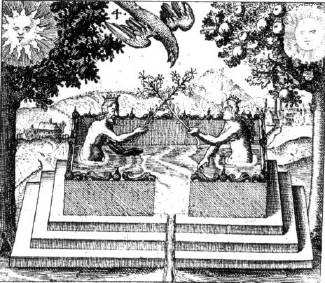
���ۤȷ�κ����Ȥϡ�����Ū���ϵ嵬��Ū�ˤʱ����ۤ������Ǥ��롣����������Ƥˤ�ż��Τ����붵����붵�Ǥ��롣���������Ǿ�ħ�������֤Ȥϡ��ޤ��ˤ������ۤȷ�Ρֺ����פ������������Ȥ�ż����Ƥ��롣���������Ȥ��������ۤ���ˤ�äƱ��������ݤϡ����ꥹ�Ȥ������ष���Ȥ��˸������ħŪ���ݤǤ⤢�ä�������ϡ��ۤ������Ȥ��ƤΤ⤦��Ĥλ�帢��ħ�Ȥ��Ƥ����ۤ����ַ�פʤ��Τ˱����졢�������Ť��ʤ뤳�Ȥؤΰż������롣���ε��祹������κ����ϡ�����Ūϣ��Ѥ��������������̮���ȼ����Ѥ���Ƥ�����Τ��������κ�������������������ζ�Ʈ����Ǻ��������餻���ۤ������ν���ȡ�Ĺ�����פλ���ؤ�Ͷ������ʻ�������ϤΡַ��פνִ֤Ǥ⤢�롣


�����ơʺ��������ȷ�η꤬�ۤ����ˡ���������¾���η��Ѥ�ȡֿ�: eclipse�פȤʤ롣�ͺ����ͤˤ����Ҥ��ͤˤ⸫����ֱ����פ��������Ƥˤ�ѻ�����롣

�ܥåƥ������å� ��Venus��Mars�ס�̲�äƤ����ͤ˸�����ޥ륹��������ʵ�����֡ˤˤ��롣�ե�����Ϲ�ף��ͤ��뤬�������ˤ�٤���ե�����ο��ϣ���������餫�����Ǥ��뤬��������ü��ˡ�泭�ˤ�äƵ�������Ƥ��롣

�������ķ��Ȥ��Ƥ�ϣ���Ū�ֺ�����Johann Daniel Mylius ��Philosophia reformata��
���ؤ������
�� ����Ū���¤Ȥ��Ƥο���
�֤����١פ������ܤ������ʤΤ���ï�ˤ�ʬ����ʤ������ˡּ������פ��������Ƥ���ְ���ʽ����ȡפˤ��Ƥ⡢����Ū�ˤϥ����ޥ��ȥ�å��ο����������ˤ������̤����Ƥ����������Ȥ����Τ����Τ˰��β����ܤʤΤ���ֲʳ�Ū���¡פȤ��ơ��ڵ�ȶ��˼������ȤϤǤ��ʤ����������������ˡפ�ȿ�������¤Ǥ��ä�*�Ȥ��Ƥ⡢��ǰ�ʤ��餽��Ϥɤ��ޤǹԤäƤ�ֿ���Ū���¡פǤ����ʤ����֤��ĤƤ�������Ʃ�뤷���פȼ�ĥ�����Ϣ�Τ�����ֿ���ȡפǤ�ʤ���Сʤ��뤤��...�Ǥ�����...�����ˡ����Τ��Ȥθ��¤ξ����ϥ�Ǥ��äƤ⥨�ꥢ���ǤǤ��äƤ��ǽ���Ȥϻפ�ʤ��ä��Ǥ����������˽��褿���ȡʤ�����ɮ�Ԥ˽���뤳�ȡˤǤ������פ碌�֤�ʻ��¤��ʪ�Ȥ��ä���facts�פ�������Ѥ߾夲�Ǥ����ʤ��������Ƥ�����ĤΡֿ���: truth, veritas�פȤ��ƷҤ����碌��Τ�ƶ���Ǥ����ʤ����������ַ����֤��Ƥ���פȤ��������Ķ���Ū�ʼ������ϡ�������ħ������̾�����ָ��աפ��̤��ơ����������ȶ��֤�Ķ���ơָ���ơפ����������Ƥ�����ɽ���פ���ˤ����äơ����̡��������ܤʤΤ��Ȥ����Τ�ַ��Ƥ����פ��Ȥϡ����Ρֱ����줿��ΡפˤĤ��Ƹ��Τ��ص���ͭ�ѤʤΤǤ��롣����ʾ�Ǥ�ʲ��Ǥ�ʤ��������ơ����η����֤�ɽ�Ф��뤢���Ρֿ����סʶ���Ū�ֿ����ס˼��Τ����ֲ��ٷ����֤��줿�Τ�ʬ����ʤ������Ȥˤ��������֤��줿�Τ��פȤ�������Ū���¤�ؤ��֥����ɡ������פȤʤä���
* �ष�����褹�������Ȥ���¸�ߤ����¤ϡֻ�Ⱥ����פ��֤��������Τ�Τξ�ħ�Ǥ���Ȥ�������ϡ��뵷�����ԤˤȤäƿ�������ز��ɡ٤δ��ܤǤ��롣���������λ����Τ�ʹ������ʤ��ʼ��������˸���Ǥ��뤫�⤷��ʤ�¿�����ɼԤˤȤäƤϡ����Τ褦���ɤ��뤳�Ȥκ�������Ǥ������������Ƥ���ϼ����ʤ��Ȥ����������������¤μ��Ť������������ؤᡢ�����ζ줫�鳫�����٤����줿�����������줿��: Messiah�פȤ���¸�ߤ������嵻��ʸ�����Τ�Τ�ã�����褦�Ȥ��Ƥ�����Ū�ȡ���ˡŪ����ħ�פȤ˹��פ��Ƥ��뤳�ȡʥ�ۥ磻�ȡص����ȿ��ٻ��ȡˡ������Ʋʳؤ䵻�Ѥ��ֶ����פȤ��ƿ��Ҥ��оݤȤʤäƤ��Ƥ��뤫��ʸ���ؤο��Ĥȿ����Ʊ�ص����ȿ��١�ȯ�ŵ��Ȥ��ƤΥ����ʥ⤬���Ҥ��оݤȤʤäƤ��븽�������ˡ������Ƥ��Ρָ���ͤȤ��ƤΤ����ˤȤäƤμ�פ����椯�椯�Ϥ���줬��ǯ̴�����褿���Ȥ���������ʹ�˸����ζ줫��ֳ����פ��������⤿�餹̤��Ρ־徺�����ߤ�������פȤʤ뤳�Ȥ����ۤȤ����«����Ƥ��뤫�˸�����ʾ塢���Ρֵ�����פξ�ħŪ��ǽ��ñ�˥ǥ����ʲ��Ǥ�����ô��Ǥ���ۤ�ñ��ʵ����Ǥʤ����Ȥ�ʬ����Ǥ�����������������帢���Ƽԡʲ��ˤλ����Ȥ�������ʤ⤷�����Ƹ�å��ˤȤ����ѥ�����ϡ����ꥢ���Ǥ����Ҥ���Ω�Ĥ��ȡض���ԡ٤��Ԥ���ե졼�������ˤ�äƤ��Ŧ����Ƥ��ꡢ�������β�: The King of Kings�פȤ��Ƥμ祤���������ꥹ�Ȥλ����Ȥ�������ϡ��ޤ��ˤ��������ķ�Ū���㻦���פΥѥ�����Τޤް����Ѥ��Ǥ����ΤǤ��ꡢ�ޤä������ûˤ��㳰�ǤϤʤ��ΤǤ���ʥХ������åɡ�����������פ��Ф��ˡ���������˽�Ƥ���ֵ��ҡפϡ��ޤ��ˤ��������Ū�ѡ����ڥ��ƥ��֤���ǡֺǿ����ءפ�°���롢���������ˤ�������äȤ�ȶ�ʿ����ʤΤǤ��롣���������Ϥ��ο��ä���Ω���ǽ�ˤ���2000ǯ���Ρֻ˼¡פ�����Ȥ���ȯŸ������ǽ���⤢�ꡢ���Ū�ºߤȤ��ƤΡ֥ʥ���Υ������פ�����Ū�����ꤹ�����Ǥ�ʤ��ΤǤ��롣��������������Ǻ�줫��ֳ����פ��ߤ��������ޡ����å����륿����ʩ�������ˤ����Ƥ������Ū�ºߤ䤽�α�����ů�ؤȤϤޤä����̸Ĥˡ��������γ��ϤǤ��Ρְ��Ρפ�Ǽ��ȸ����륹�ȥ����ѡ�ʩ������ˤη����פ�Ĥ����ҤȤĤΡ�ʸ���פ�ɽ���륳���ɡʵ���ˤȤʤä����Ȥ⤳�����۵����٤��Ǥ��롣
���Ρ������פϡ�æ�������ʤ�������������ˤ����Ƥ⡢�����뤳�Ȥ虜��������Ȥ��������ĤäƤ��ꡢ�����ϸĿͤޤ��������ˤ��������Ū�ʷи��ˤĤ���Ǽ���Ǥ���֤ޤ��ʤ��פΤ褦�������ˤʤäƤ���ΤǤ��롣�㤨�С������٤��뤳�Ȥϻ��٤���*�סֻ����ܤ���ľ**�פʤɤ�����Ǥ��롣
���Υ����ɥʥ�С��Ȥϡ������ޤ����и����ޤǤ�ʤ����ֻ��פǤ��롣�֣��פȤ��������˶ˤ�ƹ⤤������������Ƥ��뤳�Ȥ�¿���ο͡����Τ�Ȥ����Ǥ��롣�����Ƥ��Ρ֣��פˤ����ֱʱ����פζ����ʴްդ����롣
�� �����ȡָ��������ס�
���dz�ä����ο����ϡ�0.3333333....�פȣ����ʱ��Ϣ�ʤ�ֽ۴ġ����Ǥ��롣���Ȥ����������ԲĻ����ȡֱʱ����פϤ����դ�λ���ˤ�ä�����蘆�줿�̤�ҤȤĤˤϤ��������Ȥ���������롣����ϤȤ⤫����G��I�����른���դ�����θ��Ȥ������������Ȥ��ơ˥������Ĥ����������졢��Ρ��붵Ū��������פ����̤����˶������줿�Ȥ����ֱʱ�Υ��˥������פˤ��Ƥ������������ܿ��ȣ��dz�ä������ˤ�ä�������۴Ŀ� (142857142857142857......)�����Ȥ�����ΤǤ��롣�����ⶽ̣�������Ȥ˸�Ԥ�3, 6, 9�Σ��Ĥο�����3���ܿ��ˤ�ޤޤʤ�������ˤ�äƥ�������Τ褦�˱���˿������꿶�ꡢ���Τ褦�ʥ��˥��������������Ȥ���ǽ�ˤʤ롣���줬�֣���ˡ§�ס֣���ˡ§�פȤ����Τ�줿�뵷�Ǥ��ꡢ���Υ��˥������ˤ�äƿ������������������줿�餷����������ˤ��Ƥ⡢������Ĥο����֣��ס֣��פϡ��Ȥ�櫓�����ᥭ�ꥹ�ȶ����붵Ū�����������ˤ����Ƥ�������פȤ��ƶ�ͭ����Ƥ���ΤǤ��롣
���른���դξҲ𤷤��֥��������֤�ˡ§�פȤ����Τ��Ƥ��뤳�Τ��Ȥϡ����ˡ֣��פǷ����֤��������������ʤ���֣����äƣ��Ȥ���פȤ����������θ����ʤΤǤ��롣����ˤĤ��ƤϤ��ޤ��ޤʱ�������������른�����ܿ͡������Ƥ��ο����Ԥʤɤβ���ˤ�äƤ�������Ƥ��뤬������Ū�ʲ�������ä���������륰�른���դΡ֥��������֤θ����פϡ��ºݤβ����ʥ������ȥ˥å���������Ȥ�����ɽŪ���β����ˡ����ʤ��Ⱦ���Υ���������Ĵޤ�����δ���Ƥ���������������֤μºݤȤ��ä�����פ��Ƥ���櫓�Ǥ�ʤ��������������Τ˼�����ɬ�פ�;�괶�����ʤ��ΤǤ��롣�ʤ���ˤĤ��Ƥϥ�������륽��ˤ�äƤ�Ʊ�ͤλ�Ŧ�����롣��
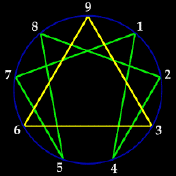
������Ĥο����֣��ס֣��פϡ����줫�鸫�ƹԤ������ˤȤäƤΡָ����������ס���ˤ���ˤ�äȤ�Ϫ���ʷ��Ǹ��������ΤǤ��롣
* disasters come in three // never two without a third // Why only two without three? �ʤɤʤ�
** Third time does it. // Third time does the trick. // Third time is lucky. // Third time is the charm. �ʤɤʤɡ�
�ָ������������ˤϰ��ٸ��ڤ����ΰ����Ƥ�����������Ϥ��Ρּ������פ�Ƥ��������ΤҤȤĤȤ��Ƥ����ե�����롣�ص�Ū���裴���ʽ��ˤޤǤ�ޤ�����������ˤȤä�����ˤʤ�Τϡ��裳���ޤǤǤ��롣�����ϡ�ϻ���֤�������¤�Ƽ����ܤ˵٤���פȤ���������ͣ����������ķ����������¤�ķ�����������赬�ϤȤ��ƺ��Ѥ��Ƥ������Ǥ��뤬�����μ��������Ȥ�����Τ�����ʸ��������ǡ������Ի��䤽��¾�ν����ˤ�ȿ�Ǥ���Ƥ����ΤǤ��롣���Υ���䶵�ˤ��θ�ή�����ꤽ���ʼ��������ˡ��֥��ꥹ�ȡפ������ˤ�äƻ�ˡ������ܤ�ᴤä��Ȥ������������ΰ��äˤĤ��Ƽ㴳�β��Ƥ�����
������������������������С����塡���ڡ����⡡������
�裱��������������������������������������������������
�裲��������������������������������������������������
�裳��������������������������������������������������
�裴��������������������������������������������������
�ʲ��Τ��Ȥϡ֥������פ����Ū�ºߤ�̵���Ū������Ȥ��Ƥ����äǤϤʤ��ơ���ħŪ��¸�ߤΰ�̣���������ʤ���ΤȤ��Ƥ⡢�����Ƥ���뤳�Ȥ˽�ʬ�ʲ��ͤ����뤿��Ǥ��롣
�� ��13���ζ������פΰ�̣���뤳��
��������������������˴�����Τ���13���ζ������Ǥ���פȤ������Ҥ�������ˤ���ľ�ܤ��о줷�ʤ������������������ֲ�ۤκפ�: Pesach, Passover�פǥ�����ã��˻�����ä��Ȥ������Ȥ��顢���줬��ۤλϤޤ����������������ä��ä����Ȥ�ʬ���äƤ��롣�����ơ���ۺפ�������Τ�Nisan��ʥ��������ߤ�3-4��ˤ���14���Υ��֡�����������ˤȤ������Ȥˤʤ�Τǡ����ߤΥ��쥴�ꥪ��Ȥϴط����ʤ���ΤΡ��ҤȤĤη�ʱ���ˤ�13���ܤˤ����뤳�Ȥ����Ҥβ������꤬�ʤ������������ߤ���줬����ǧ�����Ƥ��������Ρֶ������פˤĤ��Ƥϡ��ֻष�ƻ����ܤ�ᴡפä��Τ��������Ǥ��ꡢ���줬���ꥹ�ȶ����ԤˤȤäƤ����� (holy day)�ȤʤäƤ��븽�¤�ͤ���С���Ϥ������Ǥ��롣�����Ƥ���Ϻ�����������Ρ���������: Good Friday�פȤʤäƤ��롣
���ơ����ߤΤ����ˤȤä�ʬ����䤹������Ū�ʥ������������ꤹ�뤳�ȤϺ�����͡��������Τ���ˤ�ͭ�פǤ��롣�����Ƥ������13�����������Ȥʤ륫�����������ꤹ����ɤ����ȤǤ��롣�����Ƥ���������Τ��Ȥʤ��顢�������콵����������������Ȥʤ�ָ����������פȤ������Ȥˤʤ롣���θ����������ˤ��С�13���ζ��������������ʤ����餯����*�ˤ����ΰ�©����������: ���Хȡˤ������Ǥ��롣���Υ�����������äˤ��θ�Ρ֥��ꥹ�ȡפ�ư����ͤ���С��ब�����̤������Τ�15�����������Ȥ������Ȥˤʤ롣�����Ƥ��Ρ�15���ν��ס��軰���ˤ������������Ȥ������Ȥˤʤ롣
* �����;�ǻबˬ�줿�������������Ǥ���ˤ⤫����餺�ְŤ��ʤä��פȤ������Ҥ����뤿�ᡣ�����餯�������ż�����Ƥ��롣��������ˤ����Ū���¤Ȥ��ƤΥ����������ꤹ��ɬ�פΤʤ���ħŪ���ҤȤ��Ƽ�����äƤ����ʲ뤳�ȤΤǤ����뵷�����롣
�����Ƥ����������ϥ���������: Easter Sunday�Ȥʤ롣�ʾ�ε����ή��Ϻ�����������ȤϤʤ��ΰ��פ�ʤ��Τǡ�����Ū�ʵ��������ˤ�����ǯ�Ѥ�롣�������äƸ����ޤǤ�ʤ�����������ɬ�������13���פˤʤ����ǤϤʤ��������������Υ��������˱���ʷ�������礱�ˤ����ƤϤ��С��ɤΤ褦�ʡ��ķ�Ū�ʻ����פ�ȿ��Ū�ˤʤ����ΤʤΤ������뤳�Ȥ��ưפˤʤ롣
�����Ƥ⤷�����ꥹ�Ȥλब��¯�֤ˤ�����������ǡ������13���ζ������פǤ���Ȳ��ꤹ��ȡ����ߤΤ���줬���θ����������Ǽ����줿���Ū���֤Ρ֤ɤ������פˤ���Τ�����̤��뤳�Ȥ�����ǽ�ˤʤ롣�����ǤϾܽҤ��ʤ�����������������С������λ���Ū�ʾ�ħ���λؤ������Ȥ����ˤ��С��ۤܡ�20���ζ������פ˶ᤤ�ʤ��뤤�Ϥ��Ǥ�20���ζ������ʡˤΤǤ��롣�������������軰���ζ������˺����ݤ��äƤ��뤳�Ȥˤʤ롣�Ĥޤꤳ������ֿ����ΰ�©���פ϶ᤤ���Ĥޤ�����ˤȤäƤΡֵ�©�פ�����ϻ��֤�����Ǥ���������ˤȤ���������Ƴ����ǽ�Ȥʤ롣
����ˤν����פ��������Τ��ꤦ����ˤϡ������طʤˡ��ķ���ȿ���פΥѥ�����Ȥ�����Τ�ǧ��������Ȥʤ롣�ޤä���ȿ���Τʤ�ľ��Ū�ʻ��֤���¸�ߤ��ʤ��ȹͤ��������Ѥ���ˤ�̤���ͽ¬���ꤤ����Ω���ʤ��ΤǤ��롣�Ĥޤ�����Ū�ʽ���������Ū�ˤ��¸��Ȥ�����Τˤϡ�������������Ū���֤Ȥ������֤��ķ�Ū�ѥ�������Ф��붯��ǧ���ȼ��Ф�ȼ�äƤ���ȹͤ���٤��ʤΤǤ��롣
���Τ褦�˹ͤ����������λ���ˤ��褽���������ο����������Τ��о줷��������Ū�ȡ����ͽ�����ФƤ���Τϡ��������٤ޤǡ����ˤ��ʤä����ȡפȸ��äƤ��ɤ������ˤϤ��������ּ���Ū���֡פ��Ф��붯�����Ф����롣�����ơ����κ���Ͻ����ˤ�äƤ��줾��Ǥ������������ο������Ϥ��κ���������Ԥ����Ū�����뤳�Ȥ�����Ǥ��뤫��˳��ʤ�ʤ��ΤǤ��롣�����������ǹԤäƤ����Ϣ�ξ�ħ���ϡ������Ĥ����븰����Ǥ⡢������ǽ�ˤ���֤⤦�ҤȤĤ�ü��: another one of clues�פʤΤǤ��롣
�� ��ˤλ��ع�¤
�ޤ��������軰���ˤ�����Ȥ�����ˤ��Ѥ߾夲�����ع�¤��ħ�Ȥ����Τϥ����ޥ��ȥ�å���Ϥ�Ȥ���¿���ν���Ū�ʾ�ħ��������˸��Ф����Ȥ��Ǥ����ޤ����ޤ��ޤʸ������Ѥ���ˤ⸫�Ф����Ȥ��Ǥ��롣
������ˡ���Υƥ�����μ̿�
 ��
��
����������ˡ�����쥴�16���Υƥ����顡�����ƥ�����������ˡ���ԥ���12��

�塧��������ģ�ν����� (Court of Arm)���ƥ����餬���˼礿�����ǤȤʤäƤ��롣����ۤɤΡְ�̣�פ�������Ĵ��ʤΤǤ��롣
�����ֻ��Ŵ��פȤ��Ƥ��Τ���ֶ��Ĵ����ϡ���ƥ��ǡ֥ȥ�졼�̥�ס������ꥢ��ǡ֥ȥ�졼�˥�פȸƤФ졢���Ф��������줿���ع�¤�δ��Ǥ��롣�ӥ�������뤤�ϥڥ륷��˸�ή�����ꡢ�����������Ǥϡֶ������٤ξ�ħ�פȹͤ����Ƥ��롣
The Papal Tiara, also known as the Triple Tiara, in Latin as the 'Triregnum', or in Italian as the 'Triregno',[1] is the three-tiered jewelled papal crown of Byzantine and Persian origin that is the symbol of the papacy.
�Ĥޤꡢ��Tiara�פθ츻���Τˡ֣��פΰ�̣�礤�����롣�����ꥢ��Ρ�tertio�פϡֻ����ܤ�: third�פΰ�̣��
�ޤ������ܸ����ϸ����ι�긦���ˤ�TIARA (Takasaki Ion Accelerators for Advanced Radiation Application)�Ȥ������ߤ����֤��Ƥ��뤳�Ȥ���ɮ���٤��Ǥ��롣
��ꥤ����ȼ�������Υ����֥�����
��������ΤǤϡ����λ��ع�¤���ʤ����֣��ο����פ��ݤä���Τ���ϡ��ͤΰդ�����Ȥ������뿷���������Τη����ʪ��̾�������롣

�ե�����åѤΥ���Х��Civilization Phase III��
�� �������λ��ع�¤
�����Ƥ�äȤ⸵��Ū�ȸƤ֤���������ּ������פ�ȿ�Ǥ��������ʡʸ�ʸ��ˤ��������ʥ����åȡˤǤ��롣����϶��: The Fool�λ����֤��Ϥ�ֻ��֤�ι�פȡ����δ֤ˤ��������ܤ��٤���ʪ�ȤΡ����סְռ�����Ĺ�סַ��ߡס���þ�פʤɤλ���Ū�������������ΤǤ��롣����������Ǥ���ˤȤʤ�֥�㡼���륫�ʡפȸƤФ��22��Υ��åȤϡ��ޤ��ˤɤΥ����ɤˤ�°���ʤ�����Ū�ʡ֥��硼�����פȤ��Ƥ�The Fool�Ȥ����������21��Υ����ɤˤ�ä����롣�����Ƥ���21��Ȥϣ��λ��ܡ����ʤ�������λ��ַв��ɽ���ΤǤ��롣����ϲ��˼����褦�ˤޤ��ˡָ����������פΤ褦���¤�ľ�����Ȥ���ǽ�Ǥ��롣
�����ˤ⤽�줾��ν��ʼ��ˤˤ�������ϻ���ʶ������ˤˤ�����ս꤬���ֻ�סʤ⤷���ϡ������סˤȤζ�����Ϣ�����뤳�Ȥ���������Ƥ��롣����ϡ��֡פȡ��ġפλ���Ҥ����������ס��ֲСפȡֿ�פΤ֤Ĥ���礤�������ۡפȡַ�פι��Ρ��Ȥ����Ǵ�Ū�ʥ��٥�ȤǤ��뤫�顢���η�礳���ϡ�����ʼԤκ�������ĺ�ˡ������ƾ������ԡʤ����ˤ�̵���λ�ʤΤǤ��롣�ֲ����λब���ˤȤäƤαɸ��Ǥ���פȤ����������Ū�ʿ��Ĥ�Ʊ��������ġ�
�� �ֻ����ܤ���ľ�פȤ��ƤΤ���������
�ֳ����ؤ������������ȣ����֤����ȿ���ȴ�Ϣ�����뤳�ȤϤ��Ǥ˸��ںѤߤǤ��롣�����ˤ�Ķ���Ūʸ�����֣����֤����פȲ�ᤵ��Ƥ⤪�������ʤ�ħ�����롣������������С���Ƭ�˰��Ѥ����֥�ϥͤˤ��ʡ����פΰ���ϡ����ͤ���������������Υ������˴ؤ��뵭�ҤǤ��롣����ϳΤ��˥���������������Ҥ�����������Ѥ�ä��Ƥޤ������Τ��ٷ����֤����Ȥ��ɤ�롣�����⤷�����������ʤ�д����Ƶ��Ҥ����̣���ʤ��������褷�Ƹ塢��Ҥ��������˸��줿�פΤǤ˻��ٷ����֤��Ƥ���Ȳ�ᤷ�ʤ���С������ˤϲ���ο�����̣�Ф��������ʤ��������Ƥ���ϸ��첽����ʤ���Фʤ�ʤ��ä��Τ���̵��̣�ʵ��Ҥʤɣ��Ԥ�ʤ�����줿���Ρ֥�ϥ����פǤ��뤳�Ȥ�פ��Ф��ͤФʤ�ʤ���
���������ξ�ǡ���������ʤΤϡ����β���ǤϤʤ��������֤���Ƥ������Ū�ķ������롢�Ȥ��������ʤΤǤ��롣
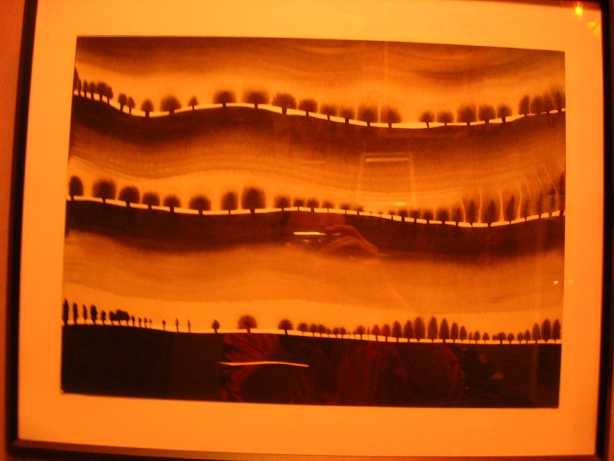
��The End�����ͽ����ʸ���Ͻ�ë�Υ��ԥ��ˤƴѤ뤳�Ȥ�������
���ؤ������
 ��
��
 ��
��
�庸���ָ��������������������ͻԶⲰ ���������������
�屦��������������饤�ʽ��ν����֥ѥ��åȤȷ�פΥ���С����֥�å�
ľ�塧40�ե����Ȥ�����Ρ֥�ȥ��Cathedral of Seville
�� ���� + ����������פθ���Ū����
���ΤĤ����ա��⤷�����ۡ����Τˤ����ơ֥ե��˥���פ�̾�Τ��Τ���ִ�פο����������Ϥ��줬ͭ�Ѥʻ��Ѥ˶������Ȥ������γ��ϳ������ʤ���Фʤ�ʤ����դˤ��衢�ۤˤ��衢��������¦�ˤϡ���ȡפ����롣���ϳ������ơ���Ȥ����ˡֳ����פ���Ƥ��������δ���Ѥ���������ΤǤ��롣�����Ƹź������δ��ơ��ޤȤ����ʤ��뤤�ϴޤ���˿����ˤϤ�����ȤˤĤ��ƤΡʸ���ˤʤ餶��ˡָ��ڡפФ����Ȥ�����롣����Ƥ����Τ�����Τ������Ҥ���Ū�Ǥ��롣
�Ȥ����ǡ���˾ܤ��������뤳�Ȥˤʤ�֦��ķ��פΤ⤦�ҤȤĤ�¦�̤ˡ��� + ��������ĺ���פȤ�������Ū�ѥ������롣Ω�����äƹԤ����������������Ȥ�����Ū�ǡ�ʬ����䤹���ץ�����Ǥ��롣���Υ������������ζˤ�ƹ������ꥢ�Ǵѻ��Ǥ��롣�ä����Τˤ����Ƥ���ϳ�Ū���������¿�����Ф���롣�����Ƥ�����¿���Ͽ�ʪ�Ȥδ�Ϣ��ǻ���Ǥ���*��
* ��������ޤ졢����ǯ����ᤴ������ǯ��ǯ����Фơ��¤λ��������ꡢ�䤬�Ƽ��Ĥ����Ǥ֡ʼ��Ǥ���ˡפȤ��������ʸ���ʲ��Υѥ�����¾�Ǥ�ʤ������̤�ȯ���פ�����˳��Ϥ��줿ʸ�����������˻��夽�Τ�Τȴ�Ϣ���Ƥ��ꡢ�ޤ����ο���ˤ���ʪ�Σ�ǯ�Ȥ���Ĺ���饤�ե�������ȸƱ�����Ȥ������Ǥ⡢����ʾ��ɬ��������äƤ���ΤǤ��롣�ʿ�ʪŪʸ�������뿢ʪ�Υ饤�ե�������Ȥ�������ҹ�¤��
ŷ���ؤȿ���ľ���ˡʿ�ľ�ˡ˿�Ĺ���뿢ʪ�Υ�����ϡ��ź��������ˤ����ƽ��פʾ�ħŪ��å���������ã��������̤������褿�������Ƥ�����¿���Ͽ���ˤ����붵Ū�ʡ����������������Ȥ��ơ����뤤��¿��Ū�ʰ�̣���������ΤȤ��Ƽ���������Ƥ�����������: axis mundi, etc.)�������ơ���˼㴳���ڤ���褦�˶ˤ��ʬ����䤹������ʪŪ���ȡפˤ������Ƥ��롣�����ϡ�ʩ���ˤ������ϡ�β֡ס����ܤΡֵƤβ֡פ����߲֡ס����ΤΡ֥�����: thistle�ס����뤤�ϡּ��Ϥ���«�ͤ�줿��*�פȤ��ä��Хꥨ���������롣�ޤ�����������֤��������ȡ��ѡ���ĥ�ʥ�����ˡ��ѥ��åȡ��ե��˥å���������¾�Υ䥷����ʤɤμ��ڤη��Ǹ���롣�����Τɤ�⤬����Ϥ����η���Τꡢ��ά�����줿�ץ��ե���������������Ȥ����ǤϹ���ʽ����ˤ䤽��¾�ξ�ħŪ�����Ȥ��Ƥ⸽���ΤǤ��롣
���ڡʥ�����ˤ���Ϥ佣���Ȥʤä��㡧
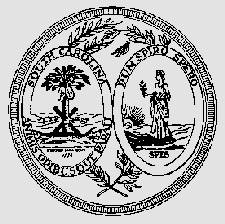 ��
��
�庸��������Υե������㡼���줿�����ʥ������
�屦����ͭ���ξ�ħ�ס���ŷ�ȡ����ŷ�Ȥξ�ħ�����Хϥ�ȸ��Υѡ���ĥ
������������饤�ʤν����ϡ֥ѥ��åȡפȸƤФ�Ƥ��륷����ΰ��Ǥ��롣�����ڤϽ��ԥ��㡼�륹�ȥ�Գ��λ���Ǹ��Ф����Ȥ�����롣�ä˳������ն�ˤϸ��ߤǤ⳹ϩ���Ȥ���¿���������Ƥ��ꡢ�ä����Ĵ��Į�¤ߤ��Ф����Τˤ�ʤäƤ��롣���줬�����Ȥʤä�����ϡ����줬�ֻ��¡פǤ��뤫�ݤ��ϤȤ⤫���Ȥ��ơ����Τʥ��ԥ����ɤ�ȼ�äƤ��ꡢ�ϸ��Ǥϸ��ߤǤ������դ��롣����Ͽ���Φ�ο�̱�Ϥ�13������������Ф�����Ω�����ĩ������ΰ��äȤʤäƤ��롣�ѹ���⤬���㡼�륹�ȥ�γ���ˤ�⤷���ݡ��줷�Τ��Ǻ�ä��֤Ϥ����դ��¿���ФäƤ����ѥ��åȤ��ڤ��ڤäƺ�ä���¤���ä�������Ϥ����Ϥ�¾���ںब˭�٤ˤʤ��ä��������������롣�������������δ��⤫���ˤ�⤬���ä��Ȥ�����������Τ���ѥ��åȤ��ڡפδ��Ƿ��ߤ��줿�ɸ��ɤ���ˤ�Ƥ�ķ���֤����פ��������Ƥ��롣�����ˡ����Υѥ��åȤ��ڤˡ��ɱ��ϡפȤδ�Ϣ�����Ф����ΤǤ��롣�����������ͳ������н����ȤʤäƸ塹������ޤǤ��Υ��ԥ����ɤ�������������ζ�������ä���ΤȤʤ롣
�����Τɤ�ˤⶦ�̤ʤΤϡ��ۤܿ�ľ�ˤޤä����ˤ��δ��Ф���ĺ����ʬ���դ�ޤʤɤ�����Ȭ��������Ū�˹�����Ȥ���������Ǥ��롣���Υ�����Ϥ��줬�줬���Ȥ��Ƥ��ޤ�˻��̤äƤ��뤿�ᡢ���οްƲ������ά�����줿�ץ��ե����뤫��Ϥ��줾��ο�ʪ�μ��¬���������ꤹ�뤳�Ȥ����ۤɤǤ��롣���줾�줬����Ϥ䤽��¾�ξ�ħŪʪ�ʤȤ��ƺ��Ѥ����˻�ä���ͭ�Υ��ԥ����ɤ���ˡ����ä���Ĥ���ˡ�������ϡʾ�ħ�ˤ�ǧ���Ǥ����������ʿ͡��ˤȤäƤϡ������ϡ����ꤵ����ɬ�פ��ʤ��ۤɤ˼����Ƕ���Ū�ʿ�ʪ��ɽ���Ƥ��ꡢ�ޤ����̤ʴ����������������ΤǤ���ˤ�ؤ�餺�������Ϥ���������ͭ�θ���Ū�ʥ��ԥ����ɡʾ��ˤ�äƤϸ����סˤ�Ķ���ơ�����ҤȤĤ����Ƥʤ������������ã���褦�Ȥ��Ƥ���Ȥ����פ��ʤ��ۤɤˡ�Ʊ���褦�ʷ���Ū��ħ*�������Ƥ���ΤǤ��롣
 ��
��
�庸�������åȥ��ɤ���Ϥʤɤ����ˤ��о줹�륢���ߡ��屦���ե�ᥤ��������Ź�ʤɤˤ褯����Ƥ���٥�ȤΥХå��롣�����ߤϡ��구�ȥ���ѥ��פ���Ϥʤɤ�ʻ�����о줹������Ǥ��롣�֦��ķ��פ˴ؤ���������ݤ˺ƤӼ��夲�롣
�����Ǥ�¿���ο��������ʤ������ּ��Ϥ��줿���ס����������ޡס��֥����ߤβ֡פʤɤ���Ϥϡ����������Ϥ���٤ơ����Ρ��졿�ȡפ���ʬ����ü��û��*����������ĺ����ʬ���������ϡ��ۤȤ�ɤ���餬�ʥ����ߤʤ饢���ߡ����ʤ����Ȥ����褦�ˡ˶���Ū�ʲ������������褦�Ȥ������ϡ�����ˤ褯���������η�����Ϣ�ۤ����뤳�Ȥ����ܤǤ��ä����Τ褦�Ǥ��롣����ϲ�������ʤ����Ȥ���ʬ�����뤫��ɳ��«�ͤ�����������ʤ��Ƥ���Ȥ����������Ȥ��ƶ��̤ʤΤǤ��롣����ϡ�����˸�ˤ���줬�֦��ķ��פȸƤ֤��Ȥˤʤ��Ⱦ�ʤ�������ΥХꥢ��Ȥ�Ƥ������˺ƤӼ��夲����Ǥ�������
* �����ߤ˴ؤ��Ƥϡ���ʪ���ΤȤ��Ƥϥ��������߲֡�ϡ�˶��̤ο�Ĺ����ֻ���פ�ĺ��ˤ�����ָ����פΥѥ�����Ǥ��뤬����Ϥοްƾ�Ϥ�äѤ餽�β֤����ʤȳܡˤ����夲���롣���Τ褦�ʤ��Ȥˤʤä����Ȥˤϡ��ּ��Τη����Ȥ����̤���ħ��̵��Ǥ��ʤ�����Ǥ��롣
�� ��߲֡��ؼ�ڡ�

���������衧�����ΤĤФ�
��̾���ؼ�ڡפȤ�ƤФ��ŷ��β֡פȤ��Ƥ�Ƥ��ޤ����߲֤��Ф��Ƥ⡢���β�Ŧ�ߤ��Ф��Ƥϡ��֤���ʤ�μ�äƤ�����Ȥ��л��ˤʤ�פȷٲ����봷���������餷�����������θ������ˤ��������β֤λؤ��������Ƥ��Ф���ۤȤ��̵�ռ�������Ȥ�����٤�ƶ���������ꡢ���⤢��ʤ��Ǽ���Ǥ����ΤǤ��롣��ľ�˿���ľ�����Ӥ�ԡ���������������Ū�˻���Ȭ���ˤ��β��ۤȳܤ��롣�ޤ��ˡֻ���ȸ����פξ�ħ���ķ���ô����ʪ�Ǥ��롣

���������衧�����ᡢ��߲֣�
�� ���ȥ�å����θ�����θ���Ū����
���� + ��������ĺ���פȤ��ä���ħ��������Ǹ��ڤ����ʤ��Τ������ȥ�å�����˱����Ƥ��Ф����о줹�����θ�����Ǥ��롣������ˡ���������ξ��������ۤ��դ�˷Ǥ������餹��Ѥϼ̿�������Ǥ⤷�Ф���ª�����Ƥ��롣
 ��
�� ��
��
���θ�����Ȥ�������餹�������ˡ��
http://aquinas-multimedia.com/adoration/
http://www.agdei.com/Commentary.html
�����θ�����פ����ܤ�������Ƥ����Τϡ���monstrance: ��ȥ�פȸƤФ���ΤǤ��롣��̾�Ȥ��Ƥϡ�sunburst, sunbeam: ���������������ء����۸����פʤɡ����Ƥ��̤�����ۿ��ġפ�פ碌��褦�ʹ����Ȱվ��ˤʤäƤϤ���ʼºݤ˥��ȥ�å����������Τ�Ť��۶� (paganism) �����ۿ��Ĥȷ�ӤĤ��Ƥ����������������ؼԤ�¸�ߤ���ˡ�������monstrance�פ��Ƥ�̾�Ȥ��Ƥ��������İ���Ū���Ȥ������Ȥˤ����Ͻ�ʬ�����ܤ��٤��Ǥ��롣
����Ϥ��Ρ�monstrance�פȤ���ñ��θ츻�Ǥ��롣���ߡ���demonstrate�פ��remonstrate�פʤ�"monstrate"��촴�˻���ñ�줬�����Ĥ�����ˤϤ��뤬�������ϡָ����롢�������롢�����롢Ϫ�ˤ���פʤɤΰ�̣�Ȥδ�Ϣ����ġ����������⿼����Ϣ�Τ���ñ��ϡ�monster�פǤ��롣���θŤ���ˡ��1300ǯ���ˤȤ��Ƥϡִ����ưʪ�סֽ����۾�ˤ�����ŷŪ�˸��ɤ���ä�ưʪ�פȤ�����̣�Ȼ���ñ��Ǥ��ꡢ���θ塢���������䥰��ե���Ȥ��ä��������ʿ��á˾�νáפΰ�̣��ž���롣1500ǯ���ˤϤܸۤ��ߤ���줬�Τ�Ȥ����ΰ�̣������ʹ�Ū�ʻĵ�����ٰ�������Ĥ�Ρ������������ʪ�פȤʤ롣
���θ����椬�ֽáʤ���Ρˡפȴ�Ϣ�դ�������ͳ�ϡ��ֽ���: zodiac�פȤδ�Ϣ�����餫����Ťΰ�̣�����θ����Ƚ��Ӥε�ǽ��ξ���ˤ����ʪ�ʤ�¸�ߤ�����¤Τ���Ǥ��롣�������δ�Ϣ���ϡ�monstrance�פξ�ħ�տޤΥ��ꥸ��ˤĤ��ƺ����⤿�餹���ǤȤ���Ư���Ƥ���Ȥ�����롣���ӤˤĤ��ƤϳΤ��ˡֶ��۾������ʪ��12���ߴľ�����֤�����Τ��Ȥ�������������Ω�ġ��Ĥޤꤳ������ΤΥۥ��������פ��Τ�ΤǤ��롣�����ơ����αߴľ��Υۥ��������פ���������Τ�ΤȤ��ƥǥ������줿�Ȥ�������ϸ��ߤ����θ�����Τ褦�ʸ�������Ȥ�Τ��Ǥ��롣���ˡ�����������ȯ�������θ�����Ȥ��Ƥε�ǽ�˲ä��ơֽ��Ӥε�ǽ�פ�������줿���㤬����Τ�Τ��Ǥ��롣
�����ΤȽ��Ӥ��ͤ������㡧TBA��
�Ȥ����ǡ����������ꥢ�β�ȡ����������ˡ��ǥ����ѥ����Ρ�ŷ����¤�ȳڱ������פΥƥ�ڥ��(1400ǯ��ˤϡ��֥ץȥ�ޥ������α���פΥ�ǥ뤬���Τޤ������������˼�������줿�����λ���ˤ��������ֱ���Ū���ʤǤ��ꡢ�������Τ�Ⱦʬ�ʾ�줬���롣�����Ƥ��γ�����ʬ��������ֽ��ӡפ�ޤ�Ǥ������Ȥ����餫�Ǥ��롣���ߤǤ⤽�κ��פ�ǧ��뤳�Ȥ��Ǥ��롣�����������ν��Ӥ����ۡʤ��뤤�ϡֵ�����ΡסˤȤδ�Ϣ�����ϡ��������ʱ�����ϿޡˤȤδ�Ϣ�ǽФƤ����ΤǤ��롣�����ŷ�Τα��Ԥ�ޤ���ɽ���Τ�������ƻ�������Ǥ��롣
�ʿ��ǡ����������ˡ��ǥ����ѥ����Ρ�ŷ����¤�ȳڱ������ס�
�������äơ���monstrance�פθ츻�����θ�Ρֽ��ӡפȤδ�Ϣ��������ꡢ���⤽������Ū�ˡ֥����������ʪ�פΰ�̣���Ƥ路����Τǡ���ˤ��줬̵�ռ������줿�ȹͤ���Τ������ʤΤǤ��롣�Ĥޤꡢ���ȥ�å����������餬������Ρ����ҡפ����ΤʤΤ��Ȥ������Ȥؤζ�̣���������������ˤϤ��롣
�� ���������θ���Ū����
���ơ����˸�Ƥ����Τ����ܤ����Ҥ��оݤȤʤ밦�������ˤĤ��ƴѤƤ������Ȥˤ��롣
http://www.city.obama.fukui.jp/section/sec_sekaiisan/Japanese/data/084.htm

���������Ϥ��줬�Dz�Ǥ��뤫���Ǥ��뤫�ζ��̤ȴط��ʤ���������¿����ʿ�̺��ʤȤ����������ݡ�����餬�������ΤλѤǤϤʤ������븲����Ȥ���˺ܤ������Ȥ�����¸��Ω�κ��ʤ����������褦�ʴ���Ū����Ū��ɽ���Ȥ��ƽФƤ��륱������¿�����Ĥޤꡢ���Τ褦�ʡָ�����פ��ޤ����äơ����Ρָ�����ס��⤷�����������Τ�ΤΤޤ�Ω��Ū�˺Ƹ�����ʾ�ˡ��������Ū��ʿ�̤��ϼ̤��Ƥ����Τ��ֺ��ʡפȤʤäƤ���褦�˸����롣����С����θ����漫�ΤǤϤʤ��ơ������������θ������Ѥ��ͤ������ʿ��Ū�����������褦���㤬¿���Ȥ����褦�ʤ��Ȥȹͤ���Ф����������Ƥ����������Τ��ְ��������οޡפȤ��Ƥ����ˤ��Τ����礬¿������Ȥ����櫓�Ǥ��롣
 ��
��
����Ĺ��������º�������������������塢��ʩ�ա����Ͼ���
�������ɹ�Ω��ʪ�ְۡ������������׳��һ���ʷ�Ĺ8ǯ��1256��
̵����Ω��ɽ���Ȥ�����Ħ�ʤɤΰ��������Ȥ����Τϳ��Ϥ�¸�ߤ��Ƥ��롣�������������Ȥʤ�������������ʿ��Ū�����������Ȥ��˸��ˤ���줬����褦�ʤ����������������Τ��Ȥ�����ͳ�����餫�ˤʤäƤ��롣�Ĥޤꡢ��¾�˾�äƤ��밦���������Τ����Ǥʤ������줬�ܤäƤ�����¡��������������ν��פ����ǤȤ������̤���뤳�Ȥ������Τΰ�̣����ã���������̵��Ǥ��ʤ��ۤ��礭�ʰ�̣����äƤ��뤫��Ǥ��롣�⤷���������������Τ��������̤��оݤǤ���Τʤ�С������������פ��������Dz�䳨��Τ褦��ʿ�̺��ʤ���äȤ��äƤ���Ȧ�ʤΤǤ��롣����Ǥ⤽���㤬���ʤ��Ȥ������Ȥϡ���¼��Τ��������Τ�Ʊ���ۤɤν���������äƤ��롢�Ĥޤ���¤�ޤ���������������������ʤ��ä��Ȥ������ȤʤΤǤ��롣
�ޤ������������κ����������¤ξ夫��ֿ�ľ�˿���ľ�����Ӥ���פξ�Ǥ��ꡢ�����Ȥ����������֡�Ū�ʻ���ϡ�ں¡ˤξ�ʤΤǤ��롣���η���Ū����ħ����䤷�̤�ˡ����������Ϥ��켫�Τ������Ƥ�ĺ���˺ܤäƤ��������פε�ǽ��̤����Ƥ���Ȥ���������ΤǤ��롣
�ʾ��ǡ��������������פ���ޤǤ�ʤ��������Ĥ����ǤǴѤ�ĺ���ְ����������פ�������餫�ʤ褦�ˡ��������פȡ���¡פ��Բ�ʬ�Ǥ��ꡢ��¤Υǥ��ơ��뼫�Τˤ����ܤ�椯�����η��־����ħ���������äƤ��뤳�Ȥ˵��դ��Ǥ�������
�����Ӥ˳褱��줿ϡ�ں¾���֤��������ؤˤ��Ʒ�������פ�������̤����������������������¾�˰��֤���ͥ���դˤ�������ۡפ���ʮ�ͤ��졢����ĺ�����ĥ���Ƥ��뤫���ͤ˸����롣�����������ۡפȡ������פΥѥ�����ϡ����饸����ԻĤʥ��פȤ��Υ��פ���ФƤ������ͥ��ˡ��פȤδط�������Ϣ�ۤ������ΤǤ��롣�۵��֤�������ޤǡ����ˡ��Ͼ����ʥ�������Ĥ�������Ƥ��ơ��������Ȥ�����Ȥ��Υ��פزä������ȿ��Ū�ʻɷ�פ˸Ʊ����ƥ��פ�����������ֿ�ФƤ���פ櫓�Ǥ��롣�����������饸��Υ��פ˸������ħŪ�����Ρ��ۡס����ӡˤ�ô�äƤ���Ȥ���С����������ϡֶ۵��֡פ˼�ͤθƤӳݤ��������뤫�����dz���ʮ�Ф��ƽ����롢�Ȥ������ε�ǽ��ô�äƤ������ʤ��Ȥ������Ǥ���ΤǤ��롣�ޤ�����������Ȥ�����������⡢��Ū�ǰ���Ū��¸�������⡢�����μ��ʤ륢�������ʹ١ˤ�ż���������ʥߥå���ưŪ�ˤDz���Ū��¸��������äƤ��뤳�Ȥ����������Ǥ�������
http://ja.wikipedia.org/wiki/��������
http://www.linkclub.or.jp/~argrath/goa.html
�����������֥顼���顼����פȸƤФ�륤��ɤο��Ǥ��ꡢ���ܸ�ˡְ����פ�������Ƥ���褦�ˡְ��ߡפȴ�Ϣ�դ����Ƥ��뤳�ȤϹ����Τ��Ƥ��롣�����������ä���Ǻ���Ǥġʰ�����Ǻ¨����ˤȤ�����̱�ֿ��Ĥ��Ѷ�Ū�˻ٻ����롣�����ˤϡ������פ���ꤹ�뤢������Ū�פʰż���˭�����ݻ�����̩���Ȥδ�Ϣ������ΤǤ��롣
���ȥ�å������θ������Monstrance�ˤ�̩���ΰ����������⡢����Ū�ˤϡ���¡ס����ͥ����Ū���ۡˡס�����������פȤ������Ƕˤ�ƻ�����ΤǤ��롣�����ơ��������Ԥʤ�����ΰż��ⶦ�̤Ȥ������Ȥ�����롣�����⤳����������пʹ֤�����Ū�ռ���Ķ������������Ǥ���ֽ����פ�ž������Ǻ��־Ƥ��Ԥ����ơ���Ū�ʶ�Ǻ�����������Ȥ������Ǥ⤽�ε�ǽ�϶��̤��Ƥ���Ȥ������Ȥ������ΤǤ��롣
�����Ƥ����Ϥ�����������ɸ�ˤȤδ�Ϣ������졢���ߤǤ�����Ū�ʾ�ħ������������������ȡָ����פ���Ƥ��롣����� + ��+ ����������פȤ��������ϡ��ӡ�= ���μ�줿�ۡˤȤ�����������Ū�˿�Ĺ���뿢ʪ���֤��������⤢�ꡢ���ο��������˲ˤ��ʤ�������ϥڥ륷���ȥ륳�Υ����ڥåȡ�������ʤɤ����륤����ߥå��Ϥ���¾�Ρֺ����оΡפ�����Ū���ʤ���ˤ⸫�Ф���ѥ�����Ǥ��롣�����Ƥ����ϻ���������ˤλ��Ź�¤��ȯ�ꤷ�ƿ�Ĺ�����徺����ˤĤ졢�����뿢ʪŪ����Ĺ�ʲ��Υѥ������ľ��Ū��ɽ�ݤ������ʤǡ��췲�ο������롼�פ������Ƥ��롣
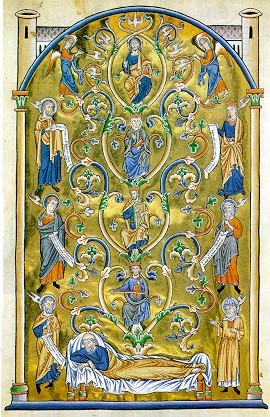 ��
��
�Ǹ�˸���Τϸ��¤������ˤ�����徺�ȡ������פ���Ǥ��롣���夽���Ϥ�긽�¤�Ÿ�����줿�ۤȤ�����ȤˤĤ��Ƥθ��ڤ���Ť��֤��Ƥ������Ȥˤʤ뤬�����ΤҤȤĤξ�ħŪ���㡢�����Ƥ��ΰ�̣�ˤĤ��ƾ�ħ���Ԥ������̵�ռ�Ū��ǧ�����Ƥ���Ȥ�������Ǥ��롣
 ��
��
�Ǥ��夲���������ȯ���Τ����ä����ڡ�������ȥ�֥����㡼�פξ��Ȱ������餹�륵����������饤�ʽ��Υ����졼�����Ρ��ġʺ��ˡ�Ʊ���пȤα������ԻΤ����Ȱ��Ǥ��ä����ᡢ̾������̱�Ȥʤä������ν�������ħ����ǡ�������Ȱ������ϡ��־徺���������������ζ̡פȤʤä��Τ��ä���
���ؤ������
 ��
�� ��
��
�� ���Ρ�����Υե��˥���
���Ρ�����κ����оο����ε����θŤ��ˤĤ��ƤϤ��Ǥ˽Ҥ٤��������餯�����ˤȤäƤ���˻���Ȥ�Ƥ֤٤����֤ΡֻϤޤ�פˤޤ��̤��ΤǤϤʤ����Ȥ����פ��Ƥ�������ΤҤȤĤǤ��롣�����Ǥϡ������餯�����Ρֵ�Ͽ���줿����פˤ����ơֺǸšפȻפ����оο����Τ����Ĥ�����ˡ����Ρ��濴Ū�����ǤǤ���ե��˥��뤽�Τ�Τξܺ٤����롣
���������ʤ���˸��Ф���������ʡ֥ե��˥���פ��������оΡ����̤��������Ǥ�ۤ��㳰�ʤ�ȼ�����ȡ��ޤ��ֶ���Ū���ǡפȤ��ƤΥե��˥���ˡ��ɤΤ褦���붵Ū�ʰ�̣����ä�ʪ�ʤ����夲��졢�������ʡפȤ��Ƶ�������Ƥ���Τ��Ȥ����ΤƹԤ���
��ϡ���¿�����뤳�ȡפǤϤʤ����Ȥ����Ƥˤʤ���������������ʡ������켫�Τ��̾����λ��äƤ�����ã�ϰʾ�Ρ��ۤȤ�����Ū�ȸ��äƤ��ɤ��褦�ʿ����Ϥ�ȯ�����뤫��Ǥ��롣�������äơ������ޤ��ɤ߿ʤ�Ǥ������������������ˡ�Ȥ��ơ���ǽ�ʸ¤ꤳ�������ֿ��Ǥ��Τ�Τ˸�餻��פȤ����Τ��¤ϸ����ʤΤǤ��롣
�ʥХ�������ʸ�������κ������ӡ˥ڥȥ�Ρ�ʯ��װ���
�ڥȥ�ϡִ仳�פΰա��ڥƥ��ʥԡ������ˤȸ츻��Ʊ�����ڥȥ���ԻԤ�¸�ߤ����Τϵ�����300ǯ��������⥭�ꥹ�ȶ���������˷�Ω���줿�ȹͤ����Ƥ��롣���ĺ���˿�����줿����ʡ��ۡפϡ������Ȥ������β��������Ĥ���ˤ�äƻ٤����Ƥ��ꡢ�ޤ��˥ȥ��ե����θ����Ȥʤ��Τ��Ȥ������Ȥ�ʬ���롣����ͥ���դ˺�����������Τ��֥��쥹�ȡפǤ��롣

���ɡ��ǥ���ʽ�ƻ����

���롦�����͡Υ��롦�ϥ��͡ϡ���ʪ�¡�
����ʥե��˥���Ǥ�����ۡפˤ���ʪ�����äƤ���ȹͤ����٥ɥ�����ˤ�äƽƤǼͷ⤵�줿���Ȥ�����ȸ����ʸ��ߤ��˲����줿�ޤޡˡ�ư���ϤȤ⤫���Ȥ��ơ���������Τ����ä��Τϼ¤˾�ħŪ�ʹ٤Ǥ��롣
�ӤȸƤӽ��魯���Ϥष�����ۡפ��ɤ������Ŭ�ڤʤΤǤϤʤ����Ȼפ��뤳�Ρ��աפθ���Ū�ʤΤ���������ʤ��뤤�Ϥ�������ˤΥե��˥���ȥ��쥹�Ȥ��Ȥ߹�碌�Ǥ��롣����ˤĤ��Ƥϡ���Ƭ�������Ͻ����оΤʹ��ޤȡ��濴�˿����դ����Ƥ��������۾��Υե��˥������ã���褦�Ȥ�����ĤΡ��ӡפȤ�����٤��ֲ����פ���ħ�Ǥ��롣���β����ʥ��쥹�ȡˤϡ��̾�β�����Ʊ�͡��濴�˶�Ť��ˤĤ�ƹ⤯�ʤ�ˤ�ؤ�餺�������ľ���ΤȤ��������䤵��Ƥ���Ȥ�����ˡ����ʷ�����Ȥ롣���줬�ֲ����פȸƤФ��ˤ�ؤ�餺�������ε�ǽ��̤����Ƥ��ʤ����Ȥ����餫�ǡ��Ȥ������Ȥ�����ΰ�̣���Ƥ������뤿��Ρ�����Ū��ǽ���������ʤ���ΤǤ��뤳�Ȥ⡢�ۤȤ���������Ԥ��ʤ�������ϥե��˥��������������פˤ�����̣�����뤫��Ǥ��롣
��Ϣ
�������������
��Υ��饹��
�� ��ͥ����Ū�����פȤ��Ƥκ���Ū�����ʡ�modern arts��
���Ǥ˥ȥ��ե�����ͥ���աˤ���˾�����ͥ���դ��ޤޤ��褦�ˡ��ե��˥��뼫�Τˤ�ޤ��������ʥե��˥��뤬�ޤޤ��Ȥ����ͤʰ��Ρ�����ҹ�¤�פ����뤳�ȤˤĤ��Ƥϴ�ñ�˸��ڤ�����������ˤĤ��Ƥ⤤���Ĥ��μ���Ƥ�������
ͥ���ռ��Τϥ�������Ȥ�������Ū���ۡʤ��뤤�ϳ�����ä��ӡˤ�����Ū�ʤ������������Ƥ��롣ͥ���դȥ�������ϡ��ۤ�Ʊ����ΤǤ���ȸ��äƤ��ɤ��ۤɻ�����¤����äƤ��롣�����˶��̤ʤ��ȤϤ��켫�Τ��֥ե��˥���פȤ����礭���������Ǥΰ�����ʤ��Ƥ��ʤ��顢���켫�Ȥ������ˤ����Ƭ�ȥե��˥���פȲ��Ǥ����������Ǥ�ޤॱ������¿���Ȥ������Ǥ��롣�Ĥޤꡢ�ۡʥ�������ˤκ������ۤ�����ü�ʥϥ�ɥ�ˤϴ������о�����Ĵ�������ǤȤ������Τ���°���Ƥ��ꡢ�ޤ��������̤Ǥ�;���Ѥ������ʤ��褦�ʤ���¿�ʰվ�����ĥϥ�ɥ�ˤϡ�¿���ξ�硢ǻ���ʡ���Ƭ���������������Ѥ��롣�����������ĺ���˰��֤����ۤγ��ΤĤޤߡʥΥ֡ˤϡ����Ф��в�ʪ�Τ��������Ϥ����ե��˥��뤬�դ��Ƥ���ΤǤ��롣�Ĥޤꡢ�ե��˥���Ȥ��ƤΥ������뤬�����ʥե��˥����ޤ�Ǥ���ΤǤ��롣
 ��
��
�����ե�μ��﹩˼��19������������Ȥ�����������(Sevre)
����19�����ե�Υڥ��Υ������롣Onyx�θƤФ�����դ�����¤˾褻��줿��Ρ�������⤽�켫�Τ��ե��˥�����Ǥ��ꡢ������˾����ʡ֥ե��˥���פȤ�����������Ȥ��뿢ʪ��̢�ʤĤ�ˤΤ褦�ʡ���Ƭ�����Υϥ�ɥ�ʤ⤷���������ˤ�ȼ���Ƥ��롣
�������뤿��˻Ȥ������������ο���˸���������Ū�ʥ����� (samovar)�ʤɤ⡢����������������Ū�ʸ�����ޤ��ۤ䳸����ä��ӤΥХꥨ�������ΤҤȤĤǤ���������˸���18-19����������줿��������Ȱ�äơ�������ϼ±פ˶�����ƻ��Ǥ��뤬������Ū�ˤ���¤ˤ����벼���Ͼ���������ľ�¤����륻�åȤ�����줿�������ȤΤ褦�˹ʤ��Ƥ��ꡢ�Ƥ�ʪ�ˤ�������ʬ�������Ĥ��Ǥ��롣�����Ƥ������ξ���������Ū�ʺ����оΤΥϥ�ɥ뤬�դ������Υϥ�ɥ�Υǥ�������Ƭ��ռ����Ƥ��롣�����������Τ˹����������ۡ��ӡˤ���ϡ��ޤ��ˤ�������ͥ���դΤ��������ķ��ȸ����٤���������Ȥɤ�Ƥ���ΤǤ��롣
 ��
��
�������ˤ��������ε����פ˷礫���ʤ������ƥࡢ�����롣������⡢�����μ�ü�ʥϥ�ɥ�ˤϡ���Ƭ������̾�Ĥ����뤬������������ϼ������������뤿�ᡢ���٤˥����ʥ��ˤϤʤäƤ��ʤ���
�庸��ŵ��Ū�ʥ����������Υ����롣�����о�������ħ�������������Ф��뤿��μظ����Ĥ��Ƥ���Τ�ʬ����ʤ�����ظ��μ�ü�ϥȥ�˥ƥ��魯�ָ��פΤ褦�ʻ��ؼ��ǥ�����ȤʤäƤ���ˡ����줬�ʤ���С�ͥ���աפ��Τ�ΤǤ��롣
�屦�������뿩���̤������ʤȤ��ƤΥ����롣���ĺ������ʬ�ϡ��ݥåȤ��ݲ����뤿��λ����Ĥ��Ƥ��ꡢ�ݥåȤ���ꤹ��ȹ⤯�ݥåȤ��न����ˤʤ롣�ݥåȤ��ܤ����뤳�Ȥ�������κ������ħ�ȸ��äƤ褤������Ū�ǤϤ��뤬�����ΰ��ͤʻ�����ˡ�ϡ���ħ����Ū�ˤϡ��礭�ʥե��˥���סʥ�����ˤξ�ˡ־����ʥե��˥���סʥݥåȡˤ��ܤ�������Ȥʤ롣
 ��
�� ��
��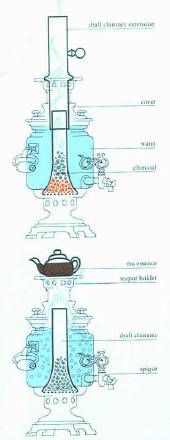
�庸��Ƽ���Υ����롣������ü�Ρ���Ƭ������̾�Ĥ������롣
������ۤȤ�ɥ������벽��������Ū�ʥ����롣����ǤϤ����餯�֤����ʨ�����פ��ȤϽ���ޤ���
�����ŵ����ˤʤ����Ρ�ú�Ф����Ѥ��Ƥ������Υ�����θ����������˲Ф����졢ͯ����������ϼظ����ͳ���ƥݥåȤء���������ä��ݥåȤ������ĺ���ء������ƽФƤ����Ϥ�����ݲ��ˡ��Ȥ������ˤ�Ƽ���Ū�Ǥ��ʤ���ɤ�����ƻ����Ū�Ǥ��ϣ��ѡ�Ū�Ǥ⤢�롢�뵷�����������δ֡פ�ƻ��
����
Samovars: Truly Cultural Symbols of the Rus
The Russians are Here! What's Samovar
���ؤ������

�� ���ܤΡ֥ե��˥����
�����Ƥ�ƻ�����ۤ������Ѥ�ȿ�ǤǤ��뤳�Ȥϴ��˽Ҥ٤����ޤ����줬�Dz�������Ǿ����˳ݤ��ơ��ϡ��塦�С��������פ�ɽ�����Ƥ���餷�����Ȥ�����Τ�줿���ȤǤ��롣�Dz��������ϡפ�ɽ�����Ȥ��������פ��ޤ����������ƤȸƤФ���ؤι⤤�����ƤΡִ��á���ʬ�ˤϡ��ֲ֡פȸƤФ�����������Ф�����礬���롣�Τ��˲����飲���ܤΡֿ�פ�����Ū�ˤ����Ƥ��˷礤����ΤǤ���ʤȸ�����ꡢ�ɤ����餬�����ܤʤΤ��������ƤǤ���ˤˤ��衢���ΡִȡפȸƤФ����ξ�ˤ���ֲСפ���ʬ�����Ƥε�ǽ��ʬ�����ʤ���ºݤ˥��������ʤɡֲСפ������ս�Ǥ���*���Ȥ��Ǥ�ޤǤ�ʤ������줬�ֲ��ޡפǤ��롣�����Ƥ��ξ�β����Ρָ���פ���������ʬ�������פȤʤ롣����ϡֱ����פ�ɽ���Ƥ������ʤ��ȤϤ�����ħ�Τ���վ�����������Ǥ��롣����ϡֱ��η����ڤ�ȴ�������Ϥ����ˤ�Τǡ����ۤ���Ҥʤɤ�ȼ�ä�������Ķ����Ū�ʱ��ס��缭�� �����Ǥ��ˤ���������뤤��������ݤʤɤǻȤ����������֤Ǥ��롣���줬�����פˤ�äƱ����������Ƥ��뤵�ޤǤ��롣���Ρֲ����פ���ʬ�������ƤǤϡֳޡפȸƤӡ�������ʬ����ϼ�פȸƤ֡�����ϡ��������ͤʤɱ����ΰվ��ѥ�������̤�����ʬ�����뤳�Ȥϸ�ƨ�����Ȥ��Ǥ��ʤ��������Ƥ��ξ�ˡֶ��פ����������ʡ�������פ������֤���롣��������ϡ����֡������ФʡפȸƤФ��ֻ��פ˺ܤ����Ƥ��뤳�Ȥ����롣
����
* ���ƤβФ�Ƥ٤���ޤ����̤��鸫��ȡֻ��Ĥη�פ��������Ƥ����Τ����ˤ�äƤϸ��Ф���롣�Ĥޤ�Ф��������Ȥ����ˤϡֻ��ĤβФζ̡סʻ������ˤ��⤫�Ӿ夬��Ȥ�������ˤʤäƤ���ΤǤ��롣���ޤ����̤��̾�Ф�Ƥ٤뤿��Υ��������ˤʤäƤ��롣���������̤��ֻ��ķ깽¤�פˤʤäƤ��ʤ���ΤǤ⡢���ΡֲСפκ����ˡ����פȡַ�פ�ɽ�������η꤬���줾�쳫�����Ƥ���ΤϤ�����Ū�Ǥ��롣�ҤȤĤϤۤܿ��߷��ǡ��⤦�ҤȤĤϻ�����η�Ǥ��롣�Ĥޤ������˾��ַ�פȡ����ס����ʤ���ֱ��ۡפ���ħ����Ƥ���ΤǤ��롣���������η꤫��������¾���η�뤳�Ȥ�����롣����ϡֿ�: eclipse�פ��������ۡ������Ƥ��ο��ˤĤ��ơ������Ρ�Ķ�˼�Ū���פˤĤ��Ƥϡ��Τ��˻��֤�ݤ��ƹͻ��뤳�Ȥ⤢��Ǥ�������
�����ƤκǾ����ˤ�������ʶ��ˡ������Ƥ��Τ������β�����פ碌�������ʤʤ���ϻ�ѷ��ˤγޤη����ϡ����Ҥη�Ωʪ�β����δ��ܹ�¤��Ʊ���Τ�ΤǤ��롣����ϲ�������ü��������ޤΡָ���פ�ķ�;夬�ä���������Ƭ�����ˤǤ��ꡢ����ķ�;夬�äƱ����Ƥ����ϼ�ξ��Ƭĺ���˵�����ʤ����餫��������Ϥ��������ʥե��˥�������ˤ���ĤȤ��������������Ф���롣
���Τβȶ櫓�Ƥ�����פ�٥åɤ˸�����֥��쥹�ȡפȡ֥ե��˥���פ��Ȥ߹�碌�Ȥΰ㤤�ϡ������Ƥ��о��̤��������̤Σ������ʤʤ���ʣ�������ˤ˻��ĤΤ��Ф������ΤΥ�ǥ���о��̤�����Ū�����̤��鸫��줿�Ȥ��Σ������ˤ��������ʤ��Ȥ������Ǥ��롣
�ޤ��������Ƥϸ���С�����Ū�ʡֻͶ��������ѡפ˻�����¤���㳰Ū�˻��äƤ���Ȥ������Ȥ�Ǥ��뤬��������������ɹ������������̤���Ω���ħ���Ƥ���褦�ˤ⸫�뤳�Ȥ�����롣���쥹�Ȥȥե��˥���Υѥ�����ϡ������Ƥˤ����Ƥϻ�����Ū�ʱ��Ԥ��ȹ��������äƤ���ΤǤ��롣
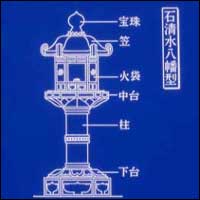 ��
��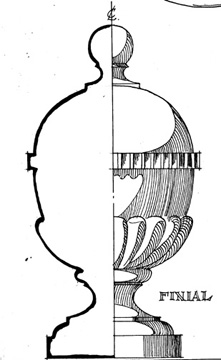
������̣�������Ȥˡ���Τ褦����Ӥ�Ԥ��ȡ������Ƥ��Τ�Τ����ΤȤ��ƤҤȤĤΡ֥ե��˥���פȤ��Ƹ�������롣�Ĥޤꡢ�緿�Υե��˥���ˡ�����פȤ��������Υե��˥��뤬�ޤޤ�뤳�Ȥ�ʬ���롣���������ΤΥե��˥�����оο�������ζ���Ū���å��Ȥ��Ƥ����Ǥʤ�������Ū����������ޤ��Τˤ⸫������롣�����ơ����Ρפ�ޤ��ΤȤ���ª����ȡ����Ū�緿���������ǤȤ��ƤΥե��˥���ˤϡ�����˾����Υե��˥����ޤ�����ҹ�¤�ˤʤäƤ��뤳�Ȥ�ʬ���롣����������¤�ϡ���ˡ֦��ķ��פȸƤ֤��Ȥˤʤ��Ϣ�ξ�ħŪ������ˡ§�ΰ�Ĥ���¤ˤʤ����ΤǤ��뤳�Ȥ�λ����������
�� �����Ȥ���������
�����Ƥȼһ�ʩ�դη�������������餫�Ǥ��뤬���һ�ʩ�շϤη���ʪ�β������ˤ�Ʊ�ͤ����Ǥ������롣����Ϥ���礭��Ʊ���������Ѥ���ˤ�侮���Υ�ǥ뤬������Ҿ��פ˴ޤޤ����Ǥ��롣�äˡֵ����פ�̾���ǿƤ��ޤ���褿������ü�����ü�ʴ�����ˤ����������˽स������Υѥ������Ф���롣�����Ƥ�Ϥ괤�ΰվ����Τ�Τ����ֱ��������ˡפ�ơ��ޤˤ�����ΤǤ��뤳�Ȥ�����̤Ǥ��롣
���餫�ʡֵ��δ�פο�������������Ū�Ǥ����ΤΡ���ˤϤ��δ������������Ρּ�����ʬ�פ�����䲰�桦�ȹ��ʸ���ˤ��֤�����륱�����⸫���롣
�㤨����Ƭ�ˤ�Ǥ������Ϥ�����ˤʤäƤ��������Ȥι���˻Ȥ��Ƥ���ֵ���ʵ������⤽����Ǥ��롣�����Τ褦�����̤δ�ϡֲȹ�פ��֤�����äƤ��롣���Ρ����ӡפȤ���̾����ޤ��ŵ��Ū�оο����ȤʤäƤ��롣�����ηפ餤�ˤ��Ƥ⡢���ӡפζ�ʸ������������ڥ������ڵ��Τ褦�˸����뤳�Ȥ϶�̣�������ޤ����ε����Ϥ��η��������Ƥ��μ�����ʬ�β���������Ƥ���ֱ����פΤ褦�ʱ�������褯��Ƽ�뤳�Ȥ��Ǥ��롣���ԡ��ϡֹ�ˡ���Ѥ�äƤ��Ϥ륹�ԥ�åȤ��Ѥ��ʤ��פȤ��롣�����ƥ����ƥ�å��ʥ�å������Ǥ��롣

������ʬ���ֲ���פ��֤�����ä��������������Ϥ������ʬ�η��������ܡ���ˤ���줬��ͭ���뤳�Ȥˤʤ�֦��ķ��פ������ˤ⸫�Ф���롣

ʿ��Ū�ʥ��վ��ε����Ǥ��뤬���Υ����ȥꥫ��ʵ���ɽ��ˤϡַ����פ��Ϥ����褦�ʡֱ����פα������Ф���롣�����̼��Τ�������ޤ�Ǥ���ѥ��������������̤��̤���ɽ��������оο����ϡ�����������Ƽ��˸���������ʤȤ��Ƥġˡפʤɤˤޤ��̤뤳�Ȥ��Ǥ��롣���̿������оΤε����ˤĤ��Ƥ����Ӹ��ڤ����Ǥ������������Ǥϡ�����Ω���ɹ��פ��뺸���ʱ��ۡˤ����Ϥ�����Ƭ������α��Ȥ���ɽ���졢���줬��Ĥο�Ū¸�ߤΡִ�פ���Ф��Τ��Ȥ������Ȥ���α��롣

���μ�����ʬ�����ǽФξ��ȡפȤ����ե��˥��빽¤��ΤäƤ��롣�����϶ˤ�����Ƥ˵����μ��դ�־��äơפ��롣���α������־��ȡפȤ���������帢������֥��쥹�ȡפ�����̤����Ƥ��롣

�̾�ε���ɽ�������������Ʊ�ͤι����ˤʤäƤ��뤬��������ʬ��ñ�ʤ���ΤǤ��ꡢ���ε��Τ�������褦�ʷ����ˤʤäƤ��롣�������ֱ����פϤ����ޤǤ⺸���оΤˤ��ε��Τ����롣

���쥹�ȡʥڥ�����Ω�����ˤȥե��˥���ʻ�帢�ˤλ��ΰ�Ȥε������оΤ˥ڥ��������ֱ����פϤ�����ֻ�ҡסʹ����ˤ�פ碌������ˤ�ʤäƤ���Τ����ܤ��٤��Ǥ��롣

�ۤȤ�ɵ����Ȥ��Ƥθ�����α��ʤ��ۤɤ˼�ͳ�˥ǥե���ᤵ�줿�����������о����ϴ����ˤʤäƤ����ΤΡ�����Ƭĺ��ʬ�˻��̰��Τ�ɽ�����룳�Ĥα߷����͵�ʪ����Ω�ġ�
�ʾ�Τ褦�ˡ����ܤ������Ƥ˱����������סʵ�����ˤ��ϼ�ʱ�����Ƭ�ˤ��Ȥ߹�碌�˸����о������ֵ������Ȥ˸�����ֲ��桦�ȹ�פʤɤΡֻ�帢Ū��ħ�ȱ������Ȥ߹�碌�˸����о����ϡ����餫�Ǥ��ꡢ��������Τ��������ݤˤ�����֥ե��˥���פȡ֥��쥹�ȡפ��Ȥ߹�碌�˸����о�����Ʊ����Τ�ɽ���Ƥ���ΤǤ��롣
���ۡ�������Ϣblog
��������ʸ�������ϼ�ŵ��
���ؤ������
���ؤ������
���ؤ������
�ֶ��פؤ������

����ϡֿ�ǯ�ס�����פ����ơֻ��ĤβФζ̡פ˴ؤ��Τ����á��äˡֻ��̰��Ρ������ݲ����Ƥ���ȹͤ�����������ħŪ̾�ΤʤɤΤ����Ĥ��ˤĤ��Ƹ��ڤ��롣
���ܤμһ�ʩ�շϤΡ����ʤ��Ͻ�פ�ˬ���Ȥ���줬���Ф����̲ᤷ�ʤ���Фʤ�ʤ��ǽ�ξ��Ȥ��ơ���פ����롣�ä˻���κ������⤷��������äƤ��餷�Ф餯���ƺ����ˡ��оΡפ����֤��줿��Ĥ����˵��դ��Ǥ�������¿���ξ��ϡ����ܤǤϹ����ʤ��ޤ��̡ˤʤɤǿƤ��ޤ�Ƥ�����Ƭ�νáʤ���Ρˤ������Ǥ��롣����ϼ¤�¿���ξ��Ǹ��뤳�Ȥ��Ǥ��롣�����������Τ˸��������֤�����Ƥϡ��оΡפǤϤʤ��������ϡ֤������פβ���ȯ��������Ƥ��ꡢ¾���ϡ֤�����פβ���ȯ��������η��Ƥ��롣�Ĥޤꡢ�֤�������פ���Ĥ˶��ޤ줿����������š��ȿʤ�ǹԤ��Ȥ������Ȥˤʤ롣���νä��¤ϡֻ�ҡפǤ���Ȥ������Ȥ�ñ�Ȥ��õ����뤳�Ȥ��ǽ�����������Ǥϥơ��ޤδط��夢�ޤ꿼���ꤷ�ʤ���
���⤽�⡢���ν����ˤ������������ʥ����ꥢ��Ȥ����äƹ�����= ��ҡˤ����Ǥʤ���ͭ̾��Ǥϡֶ���ϻ����פΥ�����������졢�ޤ���ٿ��ҤǤ���к����θѡʥ��ĥ͡���*�Ǥ��ä���⤹��ΤǤ��롣�����������Τɤ�⺸�������������褦�Ȥ��Ƥ��뵭��ϡ֤�������פʤΤǤ��롣
* �����⤽�ο����η�����ǥե���ᤵ���뤳�Ȥǡ�����פ��ͤ˸�Ω�Ƥ��륱���������롣�Ĥޤ꺸���Ρ�����פǤ��롣
�֥�ϥͤ��ۼ�Ͽ�פˤϼ��Τ褦�˽�Ƥ��롣�ָ��衢�錄���Ϥ�������롣��Ȥ��Ƥ��Ƥ��줾��Τ��虜�˱������褦���錄���ϥ���ѡʥ���ե��ˤǤ��ꡢ���ᥬ�Ǥ��롣�ǽ�μԤǤ��ꡢ�Ǹ�μԤǤ��롣���Ǥ��ꡢ�����Ǥ��롣�פ�������ˤ�������Ρֻ��֤ؤδ��ס���ˤγ��ϡפ˴ؤ��Ƥξ�ħŪ�Ƿٹ�Ū��ɽ���Ǥ��롣���ꥹ�Ȥ����Τ褦�˽Ҥ٤��Ȥ������Ҥϼ¤ΤȤ��������Ĥ�ʡ����������ʤ��������ο���κǸ�˼�����Ƥ�����ۼ�Ͽ�פˤϡ����ꥹ�ȶ����Ѥ䶵�������������ǥ��ꥹ�����ȤȤ�ˤ��κ����˥���ե��ʦ��ˤȥ��ᥬ�ʦ��ˤ��ۤ���뺬��ȤʤäƤ���Ȼפ��뵭�Ҥ����Ф���롣�������ֻ�ϵ����Ժߤ��ˤ����ޤ��Ƥ���ä����פȻ��̤����˸����ä���«�����������ʥ��ꥹ�ȡˤȡ����Ρ֥���ե��٥åȤξ�ħ�פȤ����Ҥȥ��åȤˤʤäƤ���ʾ塢�¤�ɬ��Ū�ʤ��Ȥȸ��虜������ʤ���
������ɤޤ�������ˤȤäƤϡ�����Ƥ��Ȥ��ޤǤ�ʤ��֥���ե������פȡ֥��ᥬ�����פϥ��ꥷ���Υ���ե��٥åȤκǽ�ȺǸ��ʸ���Ǥ��롣�Ѹ�Ǹ����Ф��������A�Ǥ���Z�Ǥ���פȤ������ȤǤ��롣����ˤϺ��������ä���Ťΰ�̣�����롣���֡���ˡˤ����Ф��졢���줬�Ϥޤä��ʾ塢������֤���פˤϽ���꤬��ʤ���Фʤ�ʤ��Ȥ�������ˤ������˴ؤ��Ƥ����Ȥε�ǽ�����Ǥ��롣�ޤ��Ѹ�Ρ�(from) A to Z�פȤ���ɽ����������褦�ˡ�����ˤϡ֤����뤹�٤�: all and everything�פȤ����ްդ����롣�ǽ餫��Ǹ�ޤǤΡ֤��٤ơפ�ޤ�Ǥ���Ȥ�����̣�Ǥ��롣�ޤ��˿Ͱ٤ο����Ȥ������Ф����Ȥ����Ͼ�ʸ����ˤ˵�����֤��٤ơפΤ��Ȥ����礷�ƸƤ�Ǥ������Ǥ���*��
* �֥������Τʤ������Ȥϡ����Τۤ��ˤޤ���¿�����롣�⤷���������Ĥ���ʤ�С������⤽�ν줿ʸ������ʤ��Ǥ��������סʥ�ϥͤˤ��ʡ����21:25�ˤȤ������Ҥ��۵����줿����
���ơ������֤�������פϤɤ�������̣�ʤΤ���Ĵ�٤Ƥߤ�ȡ������Ǥϡְ��ߡפΤ褦�˵����졢��ñ�˸����Ф���ϡֺǽ�β��פȡֺǸ�β��פǤ���Ȥ������������Ƥ��롣���첻����¿��12���ȻҲ�����ʸ��35���ǹ��������פȤ�������ʥ�����åȡˤλ���Ǥ��꼽�ޡʤ��ä���ˤ��ʤ��������*���ȾͤΰաפʤΤǤ��롣�����ơְ��ߡפϡְ֡��פϼ���(���Ĥ���)����κǽ�β��dz����������ߡפϺǸ�β����ĸ����פȤ��ꡢ���äƤߤ�Х���ե��٥åȤΡ�A��Z�פ���������ΤǤ��ä�������ϡ��ҥ�š����Υޥ�ȥ��A-UM�פȤ�Ʊ�ͤΤ�ΤǤ��롣�Ĥޤꥤ��ɡ��衼���åѽ�̱²�ζ�ͭ��Ȥ��ơ�����ե��٥åȡ�ʸ���ˤ����ꥷ����ˤ����Ƥ⥵����åȤˤ����Ƥ�ǽ�ȺǸ�ϡ֥���ե������פȡ֥��ᥬ������פȡ����̤ʤΤǤ��롣
�Ȥʤ�С�����줬�һ�������̲᤹��ֹ����ס��ϻ����פȤϡ��ޤ��ˤ��νá��ϻΤθ��η����ˤ�äơ֥���ե��פȡ֥��ᥬ�פ��������ã���뤳�Ȥ���Ū�����ꡢ���ΡֻϤ�פȡֽ����פδ֤��⤤�ƹԤ��Ȥ���������Τ餺�Τ餺�˶����ˬ���͡���Ƨ��Ǥ������Ǥ��롣
���ܤ�ǯ��ǯ�ϤȤδؤ����ä��ʤ���Фʤ�ʤ����ȤȤ��ơ��Ȥ���������뤢���ε���Ū����Ȥ��Ƹ��ؤ˸������羾�����ɤޤġפ����롣����ˤ⤢�����٤ΥХꥨ�������¸�ߤ����ΤΡ����δ���Ū�����ϴ�ñ�˵��Ҳ�ǽ�ʤ�ΤǤ��롣�ֻ��ܤ����ݤ�������ä�«�ͤ���ΡפǤ��롣�����⤽�Ρ����ݤϼФ�˱Ԥ��Ǥ��ڤ�줿��Ρפǡ����αԳѤΤ��η����ϡ�������Ǥ����礤������ż������ΤˤʤäƤ��롣���줬������θ��ؤκ������֤����פ�Τǡ������оΤǤϤ��뤬������˴��Ԥ�����ħŪ��ǽ�ϼһ�����˸�����ֹ����פ�Ʊ�ͤǤ��롣���ʤ���֥���ե��פȡ֥��ᥬ�פ�Ʊ�ͤ˺��������֤���Ȥ����٤ʤΤǤ��롣�Ĥޤ�����βȤϡ֥���ե��פȡ֥��ᥬ�פζ��֤˷��Ƥ��Ƥ��ơ������Ϥ����ˡֽ���Ǥ���פȤ������Ȥ���ã����ΤǤ��롣��������������Ƥ���褦�ˡֿ����ɤ���פ���ΤǤ���Ȥ�������Ū���������ꤹ���ΤǤϤʤ���
 ��
��
�� ŵ��Ū���羾�פκߤ����ʥ��饹�ȤϺǤ⥷��ץ�˸�����ȿ�Ǥ��䤹����
�������ɤ����Ƥ��ΰ�Ĥ�Ĺ������ä����֤Ρֺǽ�פȡֺǸ�פˡ���������ݤĤ�«�ͤ���Ρפ��и�����Τ��Ȥ������Ȥ�ͻ����ʤ���Фʤ�ʤ����ե���ȡʥ֥�ܥ�ȡˤβ���Ǥ��ꡢŷ�ȥ��֥ꥨ��Ȥζ�����Ϣ�Τ���֥ե롼�롦�ɥ�����: Fleurs de lys�פ�ɴ��ʤ⤷���ϥ��������ĥХ��ʤɣ��ۤβ֡ˤ���ϡ����ѥȥ�å������������ȸ����뻰���դΥ������С��η��Ƥ���ϡ��֡��������å�: Shamrock���ե���� (club, clover)�����ꥷ��������Υݥ����ɥ�λ��Ļ�������ʥȥ饤�ǥ��: Trident�ˡ������Ȥβ���ʻ��ܤ���ˤʤɤ�Ʊ�ͤˡ��ֻ��Ĥ�«�ͤ�줿��Ρפ����̰��Τ�ɽ�����Ȥϸ����Ԥ��ʤ���������ξ�������פȤ����Ƥʴ�Ϣ�����뤳�ȤˤϺ�������ܤ�ʧ���٤��Ǥ��롣�����Ϥ��٤ƴ���Ū�����Ȥ�����й����뤿����ɸ��Ȥ�������뤳�Ȥ����롣

���ξϤ���Ƭ�˷Ǥ����褦�ˡ��ե롼�롦�ɥ������ϡ������ü�פ˸����ѥ�����Ǥ��ꡢ�ޤ����ˤ��ɸ��ɡʺ��ˤ��ʥ�����ɡˤ˸��������Ǥ��롣�ȥ��פ��Τ���ֻ����աפξ�ħ�������֥���֡פΤ��ȤǤ��ꡢ���겼������Ũ��Ƭ��դ�����Ū�����Ǥ���ʤޤ�����̱�ξ�ħ�Ǥ⤢��ˡ��ޤ���������ϸ��ߡ����פη��Ǹ�¸�����ΤǤ��뤬���ݥ����ɥ������ޤǤ�ʤ����ΰ��ȹͤ��뤳�Ȥ��Ǥ��롣�����Ȥβ���ʤ����⤸�ˤߤĤۤ��ˤˤĤ��Ƥϸ�Ҥ��롣
 �� �����Ȥβ���֤����⤸�ˤߤĤۤ���
�� �����Ȥβ���֤����⤸�ˤߤĤۤ���
���������ʤ복ǰ�Ȥ��ƤΡֻ��̰��ΡפȤϲ������Ȥ����䤤�ˤ�������������ʤ���Фʤ�ʤ�������ˤϡ������̰��ΡפȤ�����Τ������餫�Ρִ���Ū���ϡסֿҾ�ʤ餶���˲��ϡפȤη�ӤĤ�����Ĥ�ΤǤ���Ȥ��������Ĥ���̵��Ǥ��ʤ�����⤢�롣
�����Ĺ��˸������겼��������ˡ��罣����ǰ�Ĥθ����¸����Ԥ��Ƥ��뤳�ȤϹ����Τ��Ƥ��롣�˥塼�ᥭ����������⥴��ɤκ����������������Ρֻ˾��פθ����ˤϥ����ɥ͡��ब�դ����Ƥ������ޥ�ϥå���ײ��κǸ�ζ��̤˱������ǽ�λŪ�����ˤĤ���줿̾���ϡ֥ȥ�˥ƥ�: Trinity�פǤ��ä��������Ƹ��ߤǤ⤽�����������Ф��줿���ˤϡ�Trinity Site�פ����Ǥä����꤬�����֤���Ƥ������Ĥޤ�֤����Ϥϡ����̰��Τΰ��סʸ���ˤʤ�פȡ�
 ��
��
�Ĥޤ�ϣ��Ѥκǽ�Ū����ɸ�Ǥ��ä��Ͱ٤ˤ��ֻ��̰��Ρפμ¸��ʶ�������ˤȤ�����Τ�������ʪ���ؤ���ɸ�ʳ˥��ͥ륮������С����ҳ��Ѵ��ˤȤδ֤ˤʤ�餫�ζ���Ū�ʰ��ס��⤷���ϡʤ������̤ˤȤäƤϡ����Ƥʰ��פ�����Ȥ������ȤǤ��롣���Τ�ϣ����Ѹ�����Τ�̩���Ѹ�ˤȳ˳�ȯ��Ϣ�Ѹ�Ȥδ֤ε����褦�Τʤ��ط��ˤĤ��ƤϤ����Ĥ��μ����뤳�Ȥ��ǽ�Ǥ��롣
�����ƥ��ʣ�����Ȱ������ݤ˾��ۤ������뤿��˳ƹ���ܺá��⤷����ű�ष�Ƥ���˻��ߤ˹�®����ϧ�Ȥ�����Τ����롣������̾�ϧ��dz���Ǥ��륦����dz�������ʳ��ˤˤ�����ץ�ȥ˥����ֺ����ѡפ��Ƥ�����礭�ʥ��ͥ륮�������뤳�Ȥ��Ǥ���Ȥ�����̴��ȯ�Ż��ߡפǤ���餷�������ƹ�ˤ�������ޤ����Ǥ�ȿ�Фˤ�ؤ�餺�����ܤǤϰ����Ȥ��Ƴ�ȯ��³�����Ƥ��롣���ι�®����ϧ�ˤϡ֤դ���פȡ֤��פ����ե�˱�����Ʊ�ͤμ¸�ϧ�ϡ֥ե��˥å����ס֥����ѡ��ե��˥å����פȤ���̾�����դ����Ƥ������Ĥޤ����ܤ˱������淿�μ¸�ϧ�ˤ��ḭ���̾��������Ƥ��ꡢ����緿�ξ��Ѥ�����ϧ�ˤϡ��ҷŤβ��ȡפ���ʸ���: Manjushri ��̾��������Ƥ��롣ʸ��ȸ��������ܤǤϡֻ��ͤ���ʸ����ηáפȤ�����?���Τ��Ƥ��뤳�Ȥ����դ����٤��Ǥ��������ֻ˾��פθ������ƤΥ����ɥ͡��ब�ֻ��̰���: Trinity�פǤ��ä��褦�ˡ������ˤ�ֻ��̰��Ρפΰż�������ΤǤ��롣�����ƺǽ�˿ͤξ����Ȥ��줿�������Ƥΰ�ĤϹ���*����Ȥ���Ƥ��ꡢ�����Ϥϡֻ��ܤ���פθλ���䤷���Ȥ���������Ȥȿ����Ĥʤ��꤬���롣
�������ե��˥å������Ի�Ļ�ˤˤϡֳ��פ���ᴤ�����ɡפΥ�����Ȥ���ϣ��ѿ��Ǥˤ⸽����ΤǤ��롣
* ������ϸ��Ȥ��륵�å�����������֥���ե�å�������̿̾���줿�Τˤϡ����ե�å��������ʤ���ˡפȤ�����ƥ�ʥ����ꥢ�˸��פ碌�벻��Τä���Ʊ���ˡ֣��ե�å����פĤޤ�ֻ��ܤ���פˤ��ʤ�Ǥ���Ȥ����ä�ͭ̾���äǤ��롣����������५�顼�ϡ��֡פȡ��ġפκ��硢���ʤ���ֲФȿ�������פη�̤ˤ�ä�������ֺǸ�ο��ס����뤤�ϥ��ꥹ�ȶ���Υ��Ȥλ����ʥ��ꥹ�������塢���������λ����ˤ˻Ȥ������ʤ뿧�ֻ�פ���Ѥ��Ƥ��뤳�Ȥˤ����ܤ��٤��Ǥ��롣����ˤϡֻ��̰��Ρפθλ��ȤȤ�˳ˤ�ż������ħ�����Ǥ˸�����ΤǤ��롣
�����ƤҤȤĤΡ������䤬�դ��Ĥΰ�̣����ġ����ʤ���ֻϤޤ�פǤ���ֽ����פǤ���Ȥ������Ȥϡ�����������ҡפǸ��Ƥ����褦�ˡ�Ʊ��Τ��Ȥ���������ɽ���Ƥ��롣����ϡ���Ĥλ���Ū�ʼ����ι�֡פ�����ΤȤ������Ȥ��Ǥ��롣����ˡ��ݤ������ˤʤäƤ��������Ҥ��������ʬ���ڤ���ߤ�����ơ����������ǤǤ��Ƥ����ΤǤ��뤫�Τ褦��ʿ�̤ؤȡ�Ÿ���פ���С������Τ��Ȥʤ��餽���������ʬ��������ֻϤޤ�פǤ���ֽ����פǤ�����ʬ�Ϻ����оΤ����֤����ΤǤ��롣��̩�˻��֤��ֲפ����ΤǤϤʤ���ľ��Ū�����Բĵ�Ū�˿ʹԤ����ΤǤ���ȹͤ���С����Ρ�����פ϶����˸����뵼����Τ褦�ˡ��ۤ����ֳ֤�������Ǥ��������Ȥ��������ʤ���
������סֹ����ס��羾�פ��͡���ɽ�ݤǾ�ħ������ΤȤ�Ʊ��Τ�ΤǤ���Ȥ������Ȥ��Ǥ��롣
�ֶ��פؤ������
��Ĥμ����Υ�쥤�������ۤ�
����ˤ˴ط��Τʤ�������ۤʤɤȤ�����ΤϤʤ�
�Ť��Ǥ��뤳�ȤΡֶ����ϡפȡֲ��ؤΰ���
�Dz�إѥå����٤�¤롧
entee memo
����
�������
2010-03-23
G���ե��ǥ롦�졼���ؽ������ݳ�����٤��ɤ� #3
����ϡ����ˤ��Ф��Ф���������鼡�λ����ؤΰܹԤ������ꡢ���ܤ�ʤ�����Ū�ʻ����ǡ��̲ᵷ��Ȥ��ƹԤ��롣���κݡ����λ����Ρֱ���סʤ����Ǥ⡢�����θ���Ū���ݻ��Ȥΰ�̣�ǤϤʤ��ˤϡ����٤�㱤��ʤ���Фʤ�ʤ��������ޤǡ���Ȥ��Ϥ��濴�Ǥ�������������¤�ǯ�˰��پ����줿���ˤϡ��������������ɺ�äƤ���ȸ���줿����������ϡ���¯Ū�ٶػߤ����ס�dies nefasti�ˡ��Ĥޤ��Թ������Ȥߤʤ��줿������Ͽ��Ť˱����줿�ΤǤ��뤬������Ͽ��¤α���Τߤʤ餺����ǯ�֤ι�Ȥα���ˤ�ڤ��������ά�ˡ������ǯ�θ��ؤϡ���ݤ���ʾ����ȼ���������Ȥ����������ʤ��Ȥ�¿���ο͡����ܤˤϨ��������Ҥ��������������Թ��Ȥ������ʤΰ�����������γ�ǰ����˻�¸���Ƥ����褦�˻פ��롣
�ֿ��ȿʹ֨������ʤ�٨����סʤξϡˤ�ꡢ�֣�����Ū�ʹ١פΡ�26. �����������������פ��(page 199)
�졼����ʸ�Ϥ��顢��ʬ�Ρּ����������פ��֥��ᥬ�ķ����������˻ٻ���Ϳ����褦�ʵ��Ҥ��������Ȥˤʤ�Ȥ�ͽ�����Ƥ��ʤ��ä������Ĥ��ˤ����������Ҥ��������뤳�Ȥˤʤä���
�ҤȤĤλ������鼡�λ����ؤΰܹԴ��ˡ־���פ��Ԥ���Ȥ����Τϡ������˽�Ƥ���褦�ˡ�������ι������ꥢ�Ǵѻ������ΤϳΤ��ʻ��¤Τ褦�������ᥬ�ķ��Τ����Ĥ�������ˤ����äơ�ɮ�ԤϤ��Ĥơ����ܤ�����Ū�������ΰ�ĤǤ���Ȥ������羾�ʤ��ɤޤġˤ䡢�Ȥ�櫓��ƻ�κ���λ����˻Ȥ���餷�����̤����������ҡפʤɤ���夲�����������Ȥ����ä������ޤ��˼�����֤���Ǥ⡢�����˿ȶ�ʡ֣�ǯ�פȤ��������ˤ�������λ��������ʤ����ǯ��ǯ�ϡפȤ������μ���ؤȰܹԤ��Ƥ����ֻ��ζ��֡פˡԦ��դη�����Ϣ�ۤ������Τ��и��������⤽���礭�ʼ���Ǥ���Ȥ����ΡԦ����դ�̤���α��꤬�Ĥ���ʤĤޤꡢ�ߤλϤޤ�Ƚ���꤬�����դ���Ϣ�뤹��ˤȤ������Ȥ������Τ���˽��פ�����̤������Ȥ������Ȥ��������ΤǤ��뤬���졼���Ϥ��β���Ū�ʻ���Ū���֤�ֶ��ܤ�ʤ�����Ū�ʻ����פȳ��ˤ����������Ƥ�����������ί�ޤä�����Ȥ�������Ū�ʻ���٤�㱤�����뤿��ε���Ȥ���ª���롣
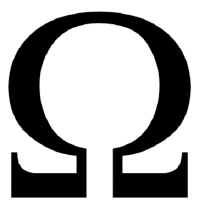
��ϡ������ǡ֤����θ���Ū���ݻ��Ȥΰ�̣�ǤϤʤ��פȤ虜�虜��̤�����ǤäƤ��뤬��page 198�Ǥ�졼���������Ƥ���褦�ˡֺǽ�ˤʤ���ʤ���Фʤ�ʤ����ʤ�١פȤ��Ƥξ���������δ������鸽��Ū�ʺ�ɾ����Ϳ�����Ƥ���褦�ʡ֥⡼���䥤����ඵ�β�Χ�פβ��ϡ��֤��٤Ƹ���Ǥ���פ������������ꤷ�Ƥ��롣
����κ�㫤����ִ���Ū�פȵ��Ҥ����褦�ʥ��ݥå��Ǥ���Ȥ�����������ϡ���ǯ�����äƤ���ɮ�Ԥ�������Ǽ��夲����ȿ��ʪ�ΰ��ספˤ����������Ȥ���������̷�⤷�ʤ��ɤ�������������դ����ΤȤʤ롣�Ĥޤꡢ����Ū�ʲ��ϴ���ȼ������ϡ�ñ�ʤ뼫�����ݤǤ���Ȥ������ϡ������ƿ���Ū�ǿ�Ū�ʲ��餫��ư����֤��٤Ǥ��ꡢ�����������ȼ������ʤΤǤ��ꡢ���줬�ʤ���иŤ����������ޤ��Ѥ�뤳�Ȥ��Ǥ��ʤ�����������ʬ�ڤΤ褦�ʡ������ּ�ȯ��Ū�٤ʤΤǤ��롣�Ĥޤꡢ��ǯ�Ȥ����ϵ�θ�ž�����ʾ�Ǥ�ʲ��Ǥ�ʤ���������Ū�ʼ���ϡ����ο���Ū�����Ū�ֹ١פ�פ��Ф������ħŪ���Ϸ��ʤΤǤ��äơ��ʹ֤Ϥ��μ�����֤���¤ˡ����ĤƤο��ब�Ԥä��Ȥ����Ρ־�������פ����魯������Ȥ��Ƥ����Ȥ����Τ����������Ĥޤꡢ�ϵ�θ�ž�����䡢������տ魯�뿢ʪ�ΰ�ǯ����Ū����̿���ݤ��顢�ʹ֤������ؤ���ΤǤϤʤ���������ķ�Ūȿ���٤ˡ��ϵ�θ�ž������������Ƥ����ȸ����٤��ʤΤǤ��롣
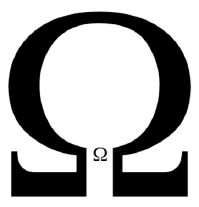
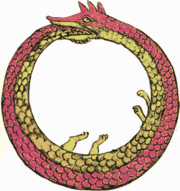
���ˤ�椬���˿����դ����ؤΤ褦�˷Ҥ������Ȥ��릸���Ρ�̤�����ءפ��Ĥ����֥����ܥ����פΤ褦�ʴ��������ߴĤȤ��뤿��η���������κ�㫡����ʤ��������Ū��������פʤΤǤ��ꡢ��������路�褦�Ȥ��Ƥ��륳�ȡʻ��֡ˤϡ��ޤ��˿�������Ǥ�浯�����ͤʤ�����Ū�ʡ֥�����פʤΤǤ��롣
���ΰ��Ѥθ�Ⱦ�����ָ����Ȥ����������ʤ��Ȥ�¿���ο͡����ܤˤϨ��������Ҥ��������������Թ��Ȥ������ʤΰ�����������γ�ǰ����˻�¸���Ƥ���褦�˻פ���פȤ�����ʬ�ϡ��Ȥ�櫓�⤤����������äƤ��롣���줳�������ߴĤν�����ˬ�����Τ��פ������ȡ����줬����ä���α��Τ褦���ż�Ȥ���������ۤκפ�˶��̤˸��Ф����ְ�̣���פʤΤǤ��ꡢ������طʤˤ����ơ����ˤ�ª�����褦���Ե����Ƥ��륨�å��ʤΤǤ��롣���ʤ��Τ��Թ���ż�����Ȥ����Τϡ��ޤ��ˡ�ȿ��ʪ�ΰ��ספΤҤȤĤ�¦�̤Ǥ��뤷���ֻ��ȼ��ʤ�����¸�ߤ��ʤ����Ȥ���ɮ�Ԥ��������Ƕ����Ƥ���������ܵ��פ˴ؤ����ʬ�Ǥ��롣�Ĥޤ�졼���������ǰż����Ƥ��뤳�Ȥ����������̻�פȤ������ʺҤ��ˤ�����������Ω�������ΤǤ��ꡢ�����Ƥ����Թ��ʤ����Ƶ�������ˤε��������־���פΰ�̣�礤�ʤ��뤤���������ˤ�ɬ�פȤ���Ȥ������ȤʤΤ���
��
�Ȥ����ǡ����Ρ����Ū�Ȥ�Ƥ֤٤������Ū���ݥå���־���פ��㱤��פȤ����ʲ褦�Ȥ��롢����Сֽ��������줿��ħ����פϡ����줬����Ȳ����������Ǥ��Ǥ�����ؤΰ����ʤ�Ǥ��롣�졼���Ϥ������ˤĤ��Ƥ�ȴ����ʤ���Ŧ���롣
�ܳФ�ĤĤ���ƻ��Ū������Ū�ռ��ϡ��٤����ᤫ�졢��ˤ���Ĥ����ʤ뽡������Ǥ��ˤ�����˰۵Ĥ���˻���ΤǤ��롣(page 200)�Ĥޤ�ҤȤĤˤϥ��ꥹ�ȶ��ˤ����ƹԤ�������ε����ˡ֤ʤ��夬�Ȥ���Τ��פȤ���ȴ��Ū�ʵ���ϡ������Ȥ��ƿ��Ԥˤ�äƤϤʤ��ʤ��輨����ˤ������ȤǤϤ��뤬���¤Ϥ����������䤬��¿���ο��ļԤ����ˤ�ä������������ˡ���Ƚ��������İ����ν������Ԥ����ˤ�äơ��֤�Ϥ�̤���ͤΤ褦�˻װԤ��ʤ��ʤä��ʹ֤ϡ�ξ�ԡ�ʪ��Ū�ʱ��������Ū�ʱ����Ϥ���̤��Ϥ��ᡢ����Ȥ������ʤ�������»�ʤ���Ρη���������������ϤǤ��ꡢ�ʰ̤˷礱��ȴ�����褦�ˤʤ��(page 200)�ΤǤ��롣
�Ρ������ɮ�ԡ������ˤˤ�롣
�������������Ǥ���������������Ȥ��Ƥε���䶵�����Ȥ��Ƥ���ŵ�ʥƥ����ȡˤ����δ������ݻ����Ƥ������Ȥϡ��ɤ߲�����Ź�������������Ȥ������Ǥϡ����ʤ��Ȥ���פ�����̤����ΤǤ��ꡢ�������ݤ�ƻ��Ū���ͤ�����ª���褦�Ȥ��뿮���ʿ��Ŀ��ˤ⡢�ޤ��̤ζ������ؤȽ������侮�������װ��ΰ�ü��ô�äƤ���ΤǤ��롣
�����ǻפ��Ф��٤��������ʤ��Τ�¯�ʤ��Τˤ�äƼ¸����롢���뤤�ϡ�̩��Ū�ʽ������ܵ��ϡ������Ȥ�����ȿ������������¿���λٻ�����������ɡפȤ����Ƥ�ʪ�ˤ�ä������Ķ���Ʊ��Ф�롢�Ȥ����ѥ�ɥ�������ʵ���Ū�ˤʱ����ˤĤ��ơ��ʤΤǤ��롣
��³����
����ʸ��
��˺���줿�����ε�ǽ�פˤĤ��Ƥ�Ĺ����
23:58:14 -
entee -
TrackBacks
2010-02-22
ȿ��ʪ�ΰ��� #4�����ȼ��ʤ�ȯŸ�Ϥʤ����ȤˤĤ���
�ʤ��뤤�ϡ�
���Τ���줬(��)����Ū��������ɬ�פ��ĥ����Τ��ˤĤ���

ȯŸ�ϰ����Ѳ��Ǥ��ꡢ����Ū�ˤϤȤ�櫓̤�����鴰���ؤ��Ѳ��Ǥ��ꡢ�ޤ�̤���Ϥ������Ϥؤ��Ѳ��Ǥ��롣�ޤ���ȯŸ�פȤ������դˤ�ǻ���ʹ���Ū����Ƚ�Ǥ��ޤޤ�Ƥ��롣��������ȯŸ�Ϥ��Ѳ�����̾�ϡ����Ф��Ф����δ����Ȥ��ƹ���Ū�ˡ���Ĺ�դȤ�ƤФ�롣�����ơ�������������Ρ��Ѳ��դϡ�������Ū�Ǥ���褦�˸�����Ȥ����Ρ����������ϤǤ��ξ������ܤ���λ����ΤǤϤʤ��������������ʤ⤷���ϲ��Ρˤء����Ϥϸϻ�ؤȸ�����������Ѳ��Ǥ��뤳�Ȥ�ƨ�����ȤϤǤ��ʤ����ĤޤꡢȯŸ����Ĺ�ˤϱʵפ�ȯŸ��ʱ����Ĺ�⤢��櫓�Ǥʤ�������ȯŸ�Ϥλ�ʪ�������ˤϡ���ˤ�뽪��ԤäƤ���ΤǤ��롣
��Ĺ�Ϥޤ����������ʾ�˿ʲ�������̿���Τ��ü��Ǥ⤢�롣����ϰ���ξ�郎·�������ʤ��������Ǥ��롣�ޤ�����������¸�Ķ�����Ѳ�����������ʾ塢����ؤ�Ŭ����Ԥʤ�ʤ������̿�ϻ��Ǥ���Τǡ�Ŭ���Ȥ����Ѳ���Ԥʤ�ʤ���Фʤ�ʤ������줬���Υ�٥�ǤϤʤ�����Ȥ������롼��ñ�̤ˤ����ƹԤʤ�졢�Ѳ������Ƥμ�������Ȥ��ư����Ҥ˸��경������¹����³�������������ϡֿʲ��פȸƤФ��褦�Ǥ��롣
������ˤ��衢���ΤΥ�٥�ˤ����Ƥ������Υ�٥�ˤ����Ƥ������Ƥ����Τ��Ѳ����롣�����Ƥ����Ѳ��ϡ����Υ�٥�Ǥ���Ĺ�Ǥ��ꡢ�����Υ�٥�ˤ����ƤϿʲ��Ȥ�������Ƥ��롣�ʤ����Ƥ��Τ�����⤬��¯Ū�����Ѥˤ����Ƥϴ����˹���Ū��ǰ�Ȥ��Ƽ���������Ƥ��롣�ˤ��������Ѳ������Τ��Τ��褤���ʤ��뤤�ϡִ����סˤΤ���˺Τ����ΤǤ���Ȳ�ᤷ��������ȯŸ�פȤ���̾�ǸƤ�Ǥ����ΤϤ��ʤ�������Ǥ��ʤ����ȤǤϤʤ���̤�Ϥ������ϡ�̤�����ϴ������������ζ��̤ǤϹ��ꤵ��Ƥ�������Ǥ��롣
���������Ѳ�����Ȥ������ȤϤ���줽������������ԤˤȤäơ����������Ϥθ���ԤäƤ���Ϸ������ԡ������ƺǽ�Ū�ˤϻब�쥻�åȤǤ���ʾ塢���ˤʤΤǤ���Ȥ������Ȥϡ����Ǥ˸����ؤ��ʤ��������������ª����ʩ�����ۤˤ��̤����ΤǤ��Ǥˤ���Ͻ�ʬ�˸�Ƥ����Ƥ������Ȥ���
���������줬��ʬ���Ȥ˰����Ĥ��ƹͤ��뤳�ȤΤǤ���ҤȤĤθ��Τλ�Ȥ��������Ǥ��ʲ��ưפʴ�ǰ�⡢����ˤ�ҤȤĤ�����Τ褦�ʷϡ����ʤ����ʸ���դȤ���ª������硢��ˤ������ˡ���ˤλ�Ȥ������������åȤȤʤäƤ��뤳�Ȥϡ��ʤ��ʤ�����������Τ����뤫�⤷��ʤ����������������Ƥ��뤳���ηϡʥ����ƥ�˼��Τλ�ϡ������ηϤˤ�ä���������Ƥ�������Ϥʤ��ʤ��Ҵ�Ū��ª���뤳�Ȥ��Ǥ��ʤ����Ϥޤ꤬���äƽ���꤬����Τϡ��ʹ֤��ȿ��Ǥ���Ф��٤��㳰�ʤ����ʤΤǤ��뤬����ʬ�Ȥ������Τλ������Ǥ��Ƥ⡢����ʸ�������ä��꽪��äƤ��ޤ��Ȥ������Ȥ����������ΤǤ��롣
�����������ͤ��Ƥߤ��ʬ���뤳�Ȥ�����ͭ�˰������ˤ�Ļ�פ��Ƥ����餫�ʤ��ȤǤ��뤬���ɤ��ʸ�����Ȥ⤹�٤ƶ��äƱɲڤ����Τ��ǤӤƤ���ΤǤ��롣��������������Ǥ��ä��Ȥ������뤤�ϥڥ륷�����δ����ڤ���Ǥ�������ï�����������٤�������´��Ǥ����Τ���������ϰ�������˲Ȥ�ů�ؼԤΤߤǤ��ä����ͤΰ�����Ʊ������ʸ������ˤˤϻϤޤ꤬���ꡢ�����ƽ���꤬���롣���ޤ�Ǥ���Τϻ�˱����ͤФʤ�ʤ��ΤǤ��롣����Ϸк���Ĺ�Ȥ���̾�Ρ�ȯŸ�פˤĤ��Ƥ�Ʊ�ͤǤ��롣��Ĺ����ʾ塢���ϴ������ꡢ�����ۤ����ॽϤ���������Ԥؤ�ƻ������ƹԤ��ΤǤ��롣�������äơ��кѤ�ʸ���˿ͳʤ�����ջ֤����ä��Ȥ���С��֤錄���ϥ���ѤǤ��ꡢ���ᥬ�Ǥ��롣�ǽ�μԤǤ��ꡢ�Ǹ�μԤǤ��롣���Ǥ��ꡢ����Ǥ���סʥ�ϥ��ۼ�Ͽ 22��13��ˤȤ������դϡ�����������餬ȯ������դΤ褦��ʹ�����Ƥ��롣
�����������Ƥ�����ϷĹ����̯���ʤɤȤ�����Τϡ����Τμ�̿�α�Ĺ���Ȥ�����¯��������Τ��Ƥ��뤬�����⤽�����̿���ڤȤ��Ƥο����������ǡ���ˤ��Ʊ�³�������뤫�Ȥ���ů�ؤ�ȯ�ͤǤ��ä��ȹͤ��뤳�Ȥ�Ǥ��롣�Τ���ˤĤ��ƤϤޤ��̤ε���ˡ�
���������Ȥ���ȯŸ����Ĺ�����Τ褦�����ʤ��ΤȤ��ơʹ���Ū�ˤΤߡ�ª����ΤǤʤ��������ư��Ȥ��ơ�������Ū�ˡ�ª�����ů�ءդ��о�Ǥ���ΤǤ��롣�Ѳ��Τʤ���Τϱʱ�Ǥ���ʱʱ���Ѳ�����ߤ���ȿ���礦�ˡ��������Ѳ��Τʤ��ʱ�ʿ�¤Ǥ�����Ѳ���ʿ�¤κ����Ũ�Ǥ���ˡ������Ʊʱ�Τ����ů�ؤ��о줹��ʱʱ�Τ�����Ѳ������ꤹ���ΤȤ���ů�ؤ�¸�ߤ���ˡ����ʤ��������ů�ؤϱʱ����Աʱ�����դ�ǡ���ˤ��Ƹ����˼¸����뤫��ͤ������Ǥ��롣��������������ů�ؤ���Ω�äơ��Ѳ������ꤷ�˱ʱ�μ¸������Ȥ�������α�ư��¸�ߤ��롣
���줬tradition�������ˤǤ��ꡢ�ޤ�convention�ʰ����ˤǤ��ꡢ�����Ͻ��������ˤ����Ƥ�ñ�ˡ��ݡ�commandment�դη��ǿ���γ�ư������ʥ֥졼���ˤ�Ϳ�����ΤȤ��Ƶ�ǽ����Ȧ�Ǥ��롣���Τ褦�ˤ��ä�����¯����æ�����ˤ�������Ū����λ������鸫������ꤵ��Ƶפ��������Τ��Ȥ����¤ϡֱʱ��ů�ءפ�̾�ĤǤ��ä����Ȥ������٤��餺�פ��Ф����Ȥˤʤ������������ϡ������֤�����Ѳ��β̤Ƥ˿ʲ���ȯŸ���ˤ�ޤ������Τ����¿���ε��������ߤʤ���������������Ĥ����������ƽ������ݤ䡢�������ն��DZ��ɤ�������Ӥ��������Ĥ�դˤ�äƳ��Ϥ����Ȧ�α�ư�ʤΤǤ��롣
�ҤȤĤ������ν�����Ʊ���˳��Ϥ���뤳���Τ��Ȥ���Ū�ϡ����ν�����⤿�餷���������ӽ��Ǥ��롣�����̵��θ��̵����ʤۤɤ�Ű�줷���ӽ��Ǥ�����������������Ϲ������ޤ��줽�β��ͤ������뤳�ȤϤʤ��ä���������ۤɤ�Ű�줵��ɬ�פʤۤɤˡ��������˲������ε��Ϥ��礭���ä��ΤǤ��롣�Ĥޤꡢ���Τ褦�ʽ������褵���ʤ�����ˡ����������뤳�Ȥ�ʬ���äƤ��������ߤ��ʤ��פ��ȡ����ʤ����ʸ����Ϥ�ʤ��פ��Ȥ���������˴ؤ��ƺ���θ��̤���ԤǤ���ͽ�ɺ����ä��Τ��ʤ�����ͽ�ɺ��Ȥʤ�������ˡ������Ƥ��α�ư�η��������줿��Τ����������ΤäƤ���ֽ����פȤ���̾�����Τ��롢�ʹ֤ˤ��ʹ֤Τ�����ȿ�Ū�������٤ʤΤǤ��롣
����ʸ̮���ɤϤ�ơ����ƽ�������äΰ��äƤ���ֻ��ε�����פΰ�̣�����餫�ˤʤ�Ȧ�Ǥ��롣
������El Greco, Piet���, 1571-1576
�����ֿͤλҡפ�������ò���ᤷ�����졧�����ʸ������ˤȤä���ӭ���������̤��Ρ��ʤ����Ƥ��ĤƤΡ������Ĥ����Ρ˻ѤǤ��롣
����������
���Τ���줬(��)����Ū��������ɬ�פ��ĥ����Τ��ˤĤ���

ȯŸ�ϰ����Ѳ��Ǥ��ꡢ����Ū�ˤϤȤ�櫓̤�����鴰���ؤ��Ѳ��Ǥ��ꡢ�ޤ�̤���Ϥ������Ϥؤ��Ѳ��Ǥ��롣�ޤ���ȯŸ�פȤ������դˤ�ǻ���ʹ���Ū����Ƚ�Ǥ��ޤޤ�Ƥ��롣��������ȯŸ�Ϥ��Ѳ�����̾�ϡ����Ф��Ф����δ����Ȥ��ƹ���Ū�ˡ���Ĺ�դȤ�ƤФ�롣�����ơ�������������Ρ��Ѳ��դϡ�������Ū�Ǥ���褦�˸�����Ȥ����Ρ����������ϤǤ��ξ������ܤ���λ����ΤǤϤʤ��������������ʤ⤷���ϲ��Ρˤء����Ϥϸϻ�ؤȸ�����������Ѳ��Ǥ��뤳�Ȥ�ƨ�����ȤϤǤ��ʤ����ĤޤꡢȯŸ����Ĺ�ˤϱʵפ�ȯŸ��ʱ����Ĺ�⤢��櫓�Ǥʤ�������ȯŸ�Ϥλ�ʪ�������ˤϡ���ˤ�뽪��ԤäƤ���ΤǤ��롣
��Ĺ�Ϥޤ����������ʾ�˿ʲ�������̿���Τ��ü��Ǥ⤢�롣����ϰ���ξ�郎·�������ʤ��������Ǥ��롣�ޤ�����������¸�Ķ�����Ѳ�����������ʾ塢����ؤ�Ŭ����Ԥʤ�ʤ������̿�ϻ��Ǥ���Τǡ�Ŭ���Ȥ����Ѳ���Ԥʤ�ʤ���Фʤ�ʤ������줬���Υ�٥�ǤϤʤ�����Ȥ������롼��ñ�̤ˤ����ƹԤʤ�졢�Ѳ������Ƥμ�������Ȥ��ư����Ҥ˸��경������¹����³�������������ϡֿʲ��פȸƤФ��褦�Ǥ��롣
������ˤ��衢���ΤΥ�٥�ˤ����Ƥ������Υ�٥�ˤ����Ƥ������Ƥ����Τ��Ѳ����롣�����Ƥ����Ѳ��ϡ����Υ�٥�Ǥ���Ĺ�Ǥ��ꡢ�����Υ�٥�ˤ����ƤϿʲ��Ȥ�������Ƥ��롣�ʤ����Ƥ��Τ�����⤬��¯Ū�����Ѥˤ����Ƥϴ����˹���Ū��ǰ�Ȥ��Ƽ���������Ƥ��롣�ˤ��������Ѳ������Τ��Τ��褤���ʤ��뤤�ϡִ����סˤΤ���˺Τ����ΤǤ���Ȳ�ᤷ��������ȯŸ�פȤ���̾�ǸƤ�Ǥ����ΤϤ��ʤ�������Ǥ��ʤ����ȤǤϤʤ���̤�Ϥ������ϡ�̤�����ϴ������������ζ��̤ǤϹ��ꤵ��Ƥ�������Ǥ��롣
���������Ѳ�����Ȥ������ȤϤ���줽������������ԤˤȤäơ����������Ϥθ���ԤäƤ���Ϸ������ԡ������ƺǽ�Ū�ˤϻब�쥻�åȤǤ���ʾ塢���ˤʤΤǤ���Ȥ������Ȥϡ����Ǥ˸����ؤ��ʤ��������������ª����ʩ�����ۤˤ��̤����ΤǤ��Ǥˤ���Ͻ�ʬ�˸�Ƥ����Ƥ������Ȥ���
���������줬��ʬ���Ȥ˰����Ĥ��ƹͤ��뤳�ȤΤǤ���ҤȤĤθ��Τλ�Ȥ��������Ǥ��ʲ��ưפʴ�ǰ�⡢����ˤ�ҤȤĤ�����Τ褦�ʷϡ����ʤ����ʸ���դȤ���ª������硢��ˤ������ˡ���ˤλ�Ȥ������������åȤȤʤäƤ��뤳�Ȥϡ��ʤ��ʤ�����������Τ����뤫�⤷��ʤ����������������Ƥ��뤳���ηϡʥ����ƥ�˼��Τλ�ϡ������ηϤˤ�ä���������Ƥ�������Ϥʤ��ʤ��Ҵ�Ū��ª���뤳�Ȥ��Ǥ��ʤ����Ϥޤ꤬���äƽ���꤬����Τϡ��ʹ֤��ȿ��Ǥ���Ф��٤��㳰�ʤ����ʤΤǤ��뤬����ʬ�Ȥ������Τλ������Ǥ��Ƥ⡢����ʸ�������ä��꽪��äƤ��ޤ��Ȥ������Ȥ����������ΤǤ��롣
�����������ͤ��Ƥߤ��ʬ���뤳�Ȥ�����ͭ�˰������ˤ�Ļ�פ��Ƥ����餫�ʤ��ȤǤ��뤬���ɤ��ʸ�����Ȥ⤹�٤ƶ��äƱɲڤ����Τ��ǤӤƤ���ΤǤ��롣��������������Ǥ��ä��Ȥ������뤤�ϥڥ륷�����δ����ڤ���Ǥ�������ï�����������٤�������´��Ǥ����Τ���������ϰ�������˲Ȥ�ů�ؼԤΤߤǤ��ä����ͤΰ�����Ʊ������ʸ������ˤˤϻϤޤ꤬���ꡢ�����ƽ���꤬���롣���ޤ�Ǥ���Τϻ�˱����ͤФʤ�ʤ��ΤǤ��롣����Ϸк���Ĺ�Ȥ���̾�Ρ�ȯŸ�פˤĤ��Ƥ�Ʊ�ͤǤ��롣��Ĺ����ʾ塢���ϴ������ꡢ�����ۤ����ॽϤ���������Ԥؤ�ƻ������ƹԤ��ΤǤ��롣�������äơ��кѤ�ʸ���˿ͳʤ�����ջ֤����ä��Ȥ���С��֤錄���ϥ���ѤǤ��ꡢ���ᥬ�Ǥ��롣�ǽ�μԤǤ��ꡢ�Ǹ�μԤǤ��롣���Ǥ��ꡢ����Ǥ���סʥ�ϥ��ۼ�Ͽ 22��13��ˤȤ������դϡ�����������餬ȯ������դΤ褦��ʹ�����Ƥ��롣
�����������Ƥ�����ϷĹ����̯���ʤɤȤ�����Τϡ����Τμ�̿�α�Ĺ���Ȥ�����¯��������Τ��Ƥ��뤬�����⤽�����̿���ڤȤ��Ƥο����������ǡ���ˤ��Ʊ�³�������뤫�Ȥ���ů�ؤ�ȯ�ͤǤ��ä��ȹͤ��뤳�Ȥ�Ǥ��롣�Τ���ˤĤ��ƤϤޤ��̤ε���ˡ�
���������Ȥ���ȯŸ����Ĺ�����Τ褦�����ʤ��ΤȤ��ơʹ���Ū�ˤΤߡ�ª����ΤǤʤ��������ư��Ȥ��ơ�������Ū�ˡ�ª�����ů�ءդ��о�Ǥ���ΤǤ��롣�Ѳ��Τʤ���Τϱʱ�Ǥ���ʱʱ���Ѳ�����ߤ���ȿ���礦�ˡ��������Ѳ��Τʤ��ʱ�ʿ�¤Ǥ�����Ѳ���ʿ�¤κ����Ũ�Ǥ���ˡ������Ʊʱ�Τ����ů�ؤ��о줹��ʱʱ�Τ�����Ѳ������ꤹ���ΤȤ���ů�ؤ�¸�ߤ���ˡ����ʤ��������ů�ؤϱʱ����Աʱ�����դ�ǡ���ˤ��Ƹ����˼¸����뤫��ͤ������Ǥ��롣��������������ů�ؤ���Ω�äơ��Ѳ������ꤷ�˱ʱ�μ¸������Ȥ�������α�ư��¸�ߤ��롣
���줬tradition�������ˤǤ��ꡢ�ޤ�convention�ʰ����ˤǤ��ꡢ�����Ͻ��������ˤ����Ƥ�ñ�ˡ��ݡ�commandment�դη��ǿ���γ�ư������ʥ֥졼���ˤ�Ϳ�����ΤȤ��Ƶ�ǽ����Ȧ�Ǥ��롣���Τ褦�ˤ��ä�����¯����æ�����ˤ�������Ū����λ������鸫������ꤵ��Ƶפ��������Τ��Ȥ����¤ϡֱʱ��ů�ءפ�̾�ĤǤ��ä����Ȥ������٤��餺�פ��Ф����Ȥˤʤ������������ϡ������֤�����Ѳ��β̤Ƥ˿ʲ���ȯŸ���ˤ�ޤ������Τ����¿���ε��������ߤʤ���������������Ĥ����������ƽ������ݤ䡢�������ն��DZ��ɤ�������Ӥ��������Ĥ�դˤ�äƳ��Ϥ����Ȧ�α�ư�ʤΤǤ��롣
�ҤȤĤ������ν�����Ʊ���˳��Ϥ���뤳���Τ��Ȥ���Ū�ϡ����ν�����⤿�餷���������ӽ��Ǥ��롣�����̵��θ��̵����ʤۤɤ�Ű�줷���ӽ��Ǥ�����������������Ϲ������ޤ��줽�β��ͤ������뤳�ȤϤʤ��ä���������ۤɤ�Ű�줵��ɬ�פʤۤɤˡ��������˲������ε��Ϥ��礭���ä��ΤǤ��롣�Ĥޤꡢ���Τ褦�ʽ������褵���ʤ�����ˡ����������뤳�Ȥ�ʬ���äƤ��������ߤ��ʤ��פ��ȡ����ʤ����ʸ����Ϥ�ʤ��פ��Ȥ���������˴ؤ��ƺ���θ��̤���ԤǤ���ͽ�ɺ����ä��Τ��ʤ�����ͽ�ɺ��Ȥʤ�������ˡ������Ƥ��α�ư�η��������줿��Τ����������ΤäƤ���ֽ����פȤ���̾�����Τ��롢�ʹ֤ˤ��ʹ֤Τ�����ȿ�Ū�������٤ʤΤǤ��롣
����ʸ̮���ɤϤ�ơ����ƽ�������äΰ��äƤ���ֻ��ε�����פΰ�̣�����餫�ˤʤ�Ȧ�Ǥ��롣
������El Greco, Piet���, 1571-1576
�����ֿͤλҡפ�������ò���ᤷ�����졧�����ʸ������ˤȤä���ӭ���������̤��Ρ��ʤ����Ƥ��ĤƤΡ������Ĥ����Ρ˻ѤǤ��롣
����������
22:22:00 -
entee -
TrackBacks
2009-08-01
��®�����žͷ�����ߤ�衪
������楬�������뼫ʬ������������
ʸ�������郎�ֿͤλŻ���å���פΤ������Τ��ȤǤ��롣�Ż���å���ȸ����Τ������Τ��Ȥ����ΤǤ���С�������Ū�ϡֿͤλŻ��餷��ϫƯ���פ�����Ū���̤ʤ�����פΤ�����Ǥ��롢�ȸ��������Ƥ⤤���������������������¤˵����Ƥ��뤳�ȤȤ��ơ����뤤�Ϥ���ޤǤμ��ӥ١��������Ū�аޤ�ˤĤ����Ե��ѳ��ϤۤȤ�ɿ����ϫƯ���֤餷�Ƥ��ʤ��ա����Τʤ�С����ε���ʸ���ˤ����Ƥϡ����ä��Ϥ���ϫƯ���֡ʲԤ����Ϥ��λ��֡ˤ��̤λŻ������Ƥ�Τ������Ȥ��������Ǥϻפ��Ƥ��뤫��Ǥ��롣
�����������ݤ��طʤȤ��ơ���ϫƯ�¶⤬ϫƯ���֤���˻�ʧ����פȤ������٤�������Ѥ�餺���ȳ�̿�����κ���Ʊ�ͤˡ�¿���쾯�ʤ��������Τ褦�˿��������Ѥ���Ƥ���Ȥ����Τ�����褦�˻פ��롣�����Ǥ���ʾ塢ʸ��������ˤ�ä��������ʤ����٤��������졢ǡ���������ץ���������®���줿�Ȥ��Ƥ⡢��;�ä����֤�ϫƯ�Ԥ��̤λŻ��ʤ���Фʤ�ʤ��դ櫓�ǡ����ϫƯ����û�̤ˤϤʤ�ʤ������줬��������ʤΤǤ��롣
[Read More!]
ʸ�������郎�ֿͤλŻ���å���פΤ������Τ��ȤǤ��롣�Ż���å���ȸ����Τ������Τ��Ȥ����ΤǤ���С�������Ū�ϡֿͤλŻ��餷��ϫƯ���פ�����Ū���̤ʤ�����פΤ�����Ǥ��롢�ȸ��������Ƥ⤤���������������������¤˵����Ƥ��뤳�ȤȤ��ơ����뤤�Ϥ���ޤǤμ��ӥ١��������Ū�аޤ�ˤĤ����Ե��ѳ��ϤۤȤ�ɿ����ϫƯ���֤餷�Ƥ��ʤ��ա����Τʤ�С����ε���ʸ���ˤ����Ƥϡ����ä��Ϥ���ϫƯ���֡ʲԤ����Ϥ��λ��֡ˤ��̤λŻ������Ƥ�Τ������Ȥ��������Ǥϻפ��Ƥ��뤫��Ǥ��롣
�����������ݤ��طʤȤ��ơ���ϫƯ�¶⤬ϫƯ���֤���˻�ʧ����פȤ������٤�������Ѥ�餺���ȳ�̿�����κ���Ʊ�ͤˡ�¿���쾯�ʤ��������Τ褦�˿��������Ѥ���Ƥ���Ȥ����Τ�����褦�˻פ��롣�����Ǥ���ʾ塢ʸ��������ˤ�ä��������ʤ����٤��������졢ǡ���������ץ���������®���줿�Ȥ��Ƥ⡢��;�ä����֤�ϫƯ�Ԥ��̤λŻ��ʤ���Фʤ�ʤ��դ櫓�ǡ����ϫƯ����û�̤ˤϤʤ�ʤ������줬��������ʤΤǤ��롣
[Read More!]
11:00:52 -
entee -
TrackBacks
2009-05-05
ü������˸���ԥ��祦�֡դξ�ħ��ͷ��
�־���פȤ������դϺǶ�Ǥϡ־��鲼��פȤ����֤������פȤ�������ʤȤ��Υ���ΰ���ʰ��硩�ˤΤ��Ȥ餷�������������ɤ���Τ��˽���˼���Τ��Ȥ������Ǥϡ֡ʿ����˾���פȸ�����褦�ˤʤäƤ��Ƥ���Ȥ������ȤǤ⤢�롣�Τ���֡Ⱦ���ɤ����ä��פȤ������Τ��Ȥ�ֻ�ͺ��褹��פȴ����Ǥ��뤳�Ȥ����ʬ����褦�ˡ��Τ��ˡ��ˤ��ˤǤ��ꡢ�������Ǥ��먡���˽���褹�먡���֤��ξ��̡פϡ־���פȤ���������������������Τ��⤷��ʤ�������������ʤͤ䤴�ȡˤ��־���פǤ����ª���뤽�θ���ͤδ��Фϡ����Τ褦������Ū�����Τξ�ħ�����Ǥⶦͭ����Ƥ��뤳�ȤǤ⤢�ꡢ���ʤ����ְ�äƤ⤤�ʤ�*�ΤǤ��롣


* ����ˤĤ��ƤϤ��Ĥ��ض��ؤ�����⨡������Ū�ʡ־�������ȡ������դ��������Ρ���ʪ�Ȥ��ƤΥե��˥���Ȥ��μ��աˡ��Ȥ��������Ǹ��ڤ������Ȥ����롣
���̤Ϥ��Ƥ��������祦�֤ϥ��祦�֤Ǥ⤳���٤Υ��祦�֤ϡ���ü������פˤ��ʤ���Գ��ˤĤ��ƤǤ��롣����������������פʤ顢������ϡ־Գ������פǤ��롣
Ĵ�٤�ȡ�ü��ʤ��ˤȤ����Τϡ���ʤ��ޡˤη�ν��ʤϤ��ü�ܡˤ����Τ��Ȥ餷�������������Ǥνˤ��������ä����顢���쥴�ꥪ��Σ��������ü������פˤʤäƤ���Τ���Ż��Ť�ž�ݤ��Ƥ��ơ�����Υ��ꥸ���ˬ�ͤ褦�Ȥ��������ˤ����ݤʾ����ǤϤ��롣ü��Ρ֤��פβ��������Ρָޡפ��̤���Ȥ������ȤǸ�ˤʤä��Ȥ������Ȥ⤢��褦�������ָ�פȤϽ���٤Ǥϣ����ܡ�����ǡָ�η�פȤϸ�ʻ���ˡʥ��쥴�ꥪ��Τ����褽����ˤΤ��Ȥ��ʺ�ǯ��ü���5��28���ʤΤǤ���ˡ�
���������Ȥ��ᶡ�ʤ��ä��ˤȽ�뤳�Ȥ����ʬ����褦�ˡ���ʪ�������붡���Τ��Ȥ���ü�����礬���˻Ҥ����פȤʤäƤ���Τϡ������������������θλ���ͳ�褹��褦�Ǥ��뤬�����Ρ�ü��פ������ܤ��Ŀ������λ������˻Ҥ�����ʧ�ä����ȡ��Ȥ�϶������������Ҥ��㱤����ܤε줤�ָ���ߡפȸƤФ�뵷���ʽ����Τ���ε����ˤȽ��礷�ơ����̤�ȿž���Ƴ��һ��庢���˻Ҥ����Ȥʤä��Ȥ����⤬���롣��������Ǥ⡢�����餯���αƶ���������Ȼפ��뤬������ǤϤ���ü������̡ʤ������ޡˤ�£��礦���������ä��Ȥ������ɻ���ε��Ҥ�����ȸ����������Ǥ������Գ��Ȥδ�Ϣ�����Ф���롣
�ʤ�ۤ�ü������ˤϼٵ���ʧ���ȸ�����Գ���«��������⤫�٤����᤹��Գ���ν����������Ǥ⤢�뤬�����ξԳ��ˤ������ʸ�ˡ�ŷ���dz���뤳�Ȥˤʤ�����̡פ��餱���Ȥ�����ʤ��뵷�ʥ����ƥꥹ��ˤ�����Ȥ����Τ�ɮ�Ԥιͤ��Ǥ��롣

���Գ��β֡���������ɥåȥ���Υ��������ˤ����륢���ʤβ֤ȤϤޤä����ۤʤ롣
�־Գ������פ��˻Ҥ����Ȥʤä��аޤȤ��Ƥϡ���Τλ���Ǥ��ä����һ���ˡ־Գ��סʥ��祦�֡ˤβ������־���*�פ�Ʊ���ɤߤǤ��뤳�Ȥʤɤ�ž�����Ȥ����Τ�ͭ�Ϥ���Τ褦�Ǥ��뤬���ְ㤤�ʤ������ˤϡ־���פؤ�Ϣ�ۤ⤢�ä��Ϥ��Ǥ��롣
* ��ƻ�������ʤɤ����ڤʤ�Τȹͤ��뤳�ȡ��缭�ӡ�
���Υ��祦�֤Ȥ�����ʪ�Τ�äƤ���Ȥ����ּٵ���㱤��פ����Ϥϡ��������뵷��̾�Ĥȸ���������ͳ�����롣�Գ��ʤ��礦�֡ˤθ�̾�ϥ����Ǥ��ꡢ�����ϡֻ���פ��̤��롣����ᥰ���ϡֻ�����פǤ⤢�롣���Τ��Ȥϡ�ü������ˤĤ�����������־Գ����դ��������Ϣ�ۤ����뤳�Ȥʤɤ��顢ü����ˤλҤ����Ȥ���ס�Wikipedia�ˤȤ����褦�ʡ��Ǥ⤢��դ줿���Ҥ���ˤ⸫�뤳�Ȥ��Ǥ��롣
�Τ��˥��祦�֤����ȥ���ʤǡ������륭���祦�֡ʲ��Գ��ˤ䥫���ĥХ��ʱ��Ҳ֡ˤʤɤλ��ۤΡ֥����ʾԳ��ˡפȰ���ˤ���륢���ʤο�ʪ�Ȥϻ��Ƥ���Ĥ��ʤ��֤��դ���*�ΤǤ��äơ����祦�֤������ʤο�ʪ�Ⱥ�Ʊ����Ƥ����ԻĤˤ��͡���������ɬ�פǤ���ޤ���ǽ�Ǥ⤢�����������Τɤ���ˤ�Ϣ�ؤ����ꤽ���ʤΤ����ޤ������Ҥ��������դؤ�Ϣ�ۤʤΤǤ��롣
* ���ͥ������֤����줬����ᡩ�����ĥХ�����
�����륷�祦�֤Ȥϰ㤦�������ΤΥ�������Ϥϡ����λ��ۤβ��ۤη�������ե롼�롦�ɡ����fleur-de-lys�ˤȤ��Ʒ����֤������ֻ��̰��Ρפξ�ħ�Ǥ��뤬������Ϥ��Τޤ����Τ������ˤ����Ƥϥ��ԥ��إå�: spearhead�������ü�ˡ��Ĥޤ����η����Ȥ��Ƥ�ǧ��������ΤǤ⤢�롣�Ĥޤ�֥����סʾԳ��ˤϡ��Τ���������鷺���ʻ����ƻ��ˤؤ�Ϣ�ۤ�¸����ΤǤ��롣
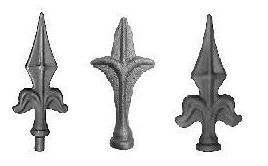
��Qingdao Andireal International Inc.���
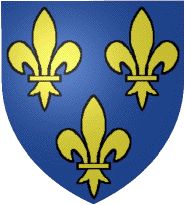
��D���guisement de chevalier Fleur de Lys avec armes en mousse���
���μ̿��Ǹ�����褦�����ΤΥ��ԥ��إåɤϻ��̰��Τξ�ħ�Ǥ���֥ե롼�롦�ɡ���סʥ��������祦�֤���ϡˤη�����Τ뤳�Ȥ����ꡢ���Ȼ��̰��Τδ֤ˤ����Ϣ�������������ΤǤ��롣��������ܤˤ�����������羾�ʤ��ɤޤġˤ���������˼Ф�˥��åȤ��줿���ܤ����ݤ�«�ͤơ����Ȧ��ʰ��ߡˤΰ��֡����ʤ����丼�ؤκ������֤����Ȥǡ����ʤ��뤤���Ҥ��㱤��ˤȻ��̰��Ρ������Ƥ����ν��������λϤޤ�Ƚ����ΰ��֤�ȯ�����벿�����ħ���뽬�路�Ⱥ���Ʊ�������롣
�ޤ���ü������Ȥϡ������¤Ӥ�����5/5�ˤ��ܰ��Ȥ������顿��������ܤǤ��ꡢ��Τܤ�ȤȤ�˶��⤯�ݤ���οή���ˤ�äƶ�Ĵ�����ָԡפ�ħ�ˤ�äƤ�֣��ο����פϹ�餫�˸����������롣�Ȥ������ȤϤޤ��˺������������������ȣ��ɤȿ����ȣ��ɤθ������β����Τ褦����������Ω���夬�ꡢ���Τ�֤Ƥ���ֵ���븽��Ҳ��ˤ����ơ��˻Ҥ˽��Ǥ����Ȥ��Ȥʤ뤳�Ȥ��˵�ǰ�������ʤΤǤ��롣
�����ƾԳ�����˿����뤳�Ȥϡ��Գ��λ��äƤ���ٵ���㱤����Ϥ����߽Ф����դ�ʤ����Ȥ������פ���뤳�Ȥǡ�����Ʊ�ͤ����Ϥ�Ȥ��դ��褦�Ȥ����¿��Ȥ�������ä���θ����٤��Ǥ�������
��ħ�κ�ˡ�Ȥϡ����֤ηв�ȶ���ȯŸ���������Ƥ����Ƥؤ�ž���ơ�����ǽ�ʷ��ݤؤȽ����˲�������ƹԤ��ΤǤ��롣


* ����ˤĤ��ƤϤ��Ĥ��ض��ؤ�����⨡������Ū�ʡ־�������ȡ������դ��������Ρ���ʪ�Ȥ��ƤΥե��˥���Ȥ��μ��աˡ��Ȥ��������Ǹ��ڤ������Ȥ����롣
���̤Ϥ��Ƥ��������祦�֤ϥ��祦�֤Ǥ⤳���٤Υ��祦�֤ϡ���ü������פˤ��ʤ���Գ��ˤĤ��ƤǤ��롣����������������פʤ顢������ϡ־Գ������פǤ��롣
Ĵ�٤�ȡ�ü��ʤ��ˤȤ����Τϡ���ʤ��ޡˤη�ν��ʤϤ��ü�ܡˤ����Τ��Ȥ餷�������������Ǥνˤ��������ä����顢���쥴�ꥪ��Σ��������ü������פˤʤäƤ���Τ���Ż��Ť�ž�ݤ��Ƥ��ơ�����Υ��ꥸ���ˬ�ͤ褦�Ȥ��������ˤ����ݤʾ����ǤϤ��롣ü��Ρ֤��פβ��������Ρָޡפ��̤���Ȥ������ȤǸ�ˤʤä��Ȥ������Ȥ⤢��褦�������ָ�פȤϽ���٤Ǥϣ����ܡ�����ǡָ�η�פȤϸ�ʻ���ˡʥ��쥴�ꥪ��Τ����褽����ˤΤ��Ȥ��ʺ�ǯ��ü���5��28���ʤΤǤ���ˡ�
���������Ȥ��ᶡ�ʤ��ä��ˤȽ�뤳�Ȥ����ʬ����褦�ˡ���ʪ�������붡���Τ��Ȥ���ü�����礬���˻Ҥ����פȤʤäƤ���Τϡ������������������θλ���ͳ�褹��褦�Ǥ��뤬�����Ρ�ü��פ������ܤ��Ŀ������λ������˻Ҥ�����ʧ�ä����ȡ��Ȥ�϶������������Ҥ��㱤����ܤε줤�ָ���ߡפȸƤФ�뵷���ʽ����Τ���ε����ˤȽ��礷�ơ����̤�ȿž���Ƴ��һ��庢���˻Ҥ����Ȥʤä��Ȥ����⤬���롣��������Ǥ⡢�����餯���αƶ���������Ȼפ��뤬������ǤϤ���ü������̡ʤ������ޡˤ�£��礦���������ä��Ȥ������ɻ���ε��Ҥ�����ȸ����������Ǥ������Գ��Ȥδ�Ϣ�����Ф���롣
�ʤ�ۤ�ü������ˤϼٵ���ʧ���ȸ�����Գ���«��������⤫�٤����᤹��Գ���ν����������Ǥ⤢�뤬�����ξԳ��ˤ������ʸ�ˡ�ŷ���dz���뤳�Ȥˤʤ�����̡פ��餱���Ȥ�����ʤ��뵷�ʥ����ƥꥹ��ˤ�����Ȥ����Τ�ɮ�Ԥιͤ��Ǥ��롣

���Գ��β֡���������ɥåȥ���Υ��������ˤ����륢���ʤβ֤ȤϤޤä����ۤʤ롣
�־Գ������פ��˻Ҥ����Ȥʤä��аޤȤ��Ƥϡ���Τλ���Ǥ��ä����һ���ˡ־Գ��סʥ��祦�֡ˤβ������־���*�פ�Ʊ���ɤߤǤ��뤳�Ȥʤɤ�ž�����Ȥ����Τ�ͭ�Ϥ���Τ褦�Ǥ��뤬���ְ㤤�ʤ������ˤϡ־���פؤ�Ϣ�ۤ⤢�ä��Ϥ��Ǥ��롣
* ��ƻ�������ʤɤ����ڤʤ�Τȹͤ��뤳�ȡ��缭�ӡ�
���Υ��祦�֤Ȥ�����ʪ�Τ�äƤ���Ȥ����ּٵ���㱤��פ����Ϥϡ��������뵷��̾�Ĥȸ���������ͳ�����롣�Գ��ʤ��礦�֡ˤθ�̾�ϥ����Ǥ��ꡢ�����ϡֻ���פ��̤��롣����ᥰ���ϡֻ�����פǤ⤢�롣���Τ��Ȥϡ�ü������ˤĤ�����������־Գ����դ��������Ϣ�ۤ����뤳�Ȥʤɤ��顢ü����ˤλҤ����Ȥ���ס�Wikipedia�ˤȤ����褦�ʡ��Ǥ⤢��դ줿���Ҥ���ˤ⸫�뤳�Ȥ��Ǥ��롣
�Τ��˥��祦�֤����ȥ���ʤǡ������륭���祦�֡ʲ��Գ��ˤ䥫���ĥХ��ʱ��Ҳ֡ˤʤɤλ��ۤΡ֥����ʾԳ��ˡפȰ���ˤ���륢���ʤο�ʪ�Ȥϻ��Ƥ���Ĥ��ʤ��֤��դ���*�ΤǤ��äơ����祦�֤������ʤο�ʪ�Ⱥ�Ʊ����Ƥ����ԻĤˤ��͡���������ɬ�פǤ���ޤ���ǽ�Ǥ⤢�����������Τɤ���ˤ�Ϣ�ؤ����ꤽ���ʤΤ����ޤ������Ҥ��������դؤ�Ϣ�ۤʤΤǤ��롣
* ���ͥ������֤����줬����ᡩ�����ĥХ�����
�����륷�祦�֤Ȥϰ㤦�������ΤΥ�������Ϥϡ����λ��ۤβ��ۤη�������ե롼�롦�ɡ����fleur-de-lys�ˤȤ��Ʒ����֤������ֻ��̰��Ρפξ�ħ�Ǥ��뤬������Ϥ��Τޤ����Τ������ˤ����Ƥϥ��ԥ��إå�: spearhead�������ü�ˡ��Ĥޤ����η����Ȥ��Ƥ�ǧ��������ΤǤ⤢�롣�Ĥޤ�֥����סʾԳ��ˤϡ��Τ���������鷺���ʻ����ƻ��ˤؤ�Ϣ�ۤ�¸����ΤǤ��롣
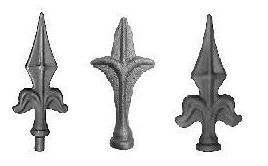
��Qingdao Andireal International Inc.���
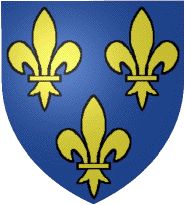
��D���guisement de chevalier Fleur de Lys avec armes en mousse���
���μ̿��Ǹ�����褦�����ΤΥ��ԥ��إåɤϻ��̰��Τξ�ħ�Ǥ���֥ե롼�롦�ɡ���סʥ��������祦�֤���ϡˤη�����Τ뤳�Ȥ����ꡢ���Ȼ��̰��Τδ֤ˤ����Ϣ�������������ΤǤ��롣��������ܤˤ�����������羾�ʤ��ɤޤġˤ���������˼Ф�˥��åȤ��줿���ܤ����ݤ�«�ͤơ����Ȧ��ʰ��ߡˤΰ��֡����ʤ����丼�ؤκ������֤����Ȥǡ����ʤ��뤤���Ҥ��㱤��ˤȻ��̰��Ρ������Ƥ����ν��������λϤޤ�Ƚ����ΰ��֤�ȯ�����벿�����ħ���뽬�路�Ⱥ���Ʊ�������롣
�ޤ���ü������Ȥϡ������¤Ӥ�����5/5�ˤ��ܰ��Ȥ������顿��������ܤǤ��ꡢ��Τܤ�ȤȤ�˶��⤯�ݤ���οή���ˤ�äƶ�Ĵ�����ָԡפ�ħ�ˤ�äƤ�֣��ο����פϹ�餫�˸����������롣�Ȥ������ȤϤޤ��˺������������������ȣ��ɤȿ����ȣ��ɤθ������β����Τ褦����������Ω���夬�ꡢ���Τ�֤Ƥ���ֵ���븽��Ҳ��ˤ����ơ��˻Ҥ˽��Ǥ����Ȥ��Ȥʤ뤳�Ȥ��˵�ǰ�������ʤΤǤ��롣
�����ƾԳ�����˿����뤳�Ȥϡ��Գ��λ��äƤ���ٵ���㱤����Ϥ����߽Ф����դ�ʤ����Ȥ������פ���뤳�Ȥǡ�����Ʊ�ͤ����Ϥ�Ȥ��դ��褦�Ȥ����¿��Ȥ�������ä���θ����٤��Ǥ�������
��ħ�κ�ˡ�Ȥϡ����֤ηв�ȶ���ȯŸ���������Ƥ����Ƥؤ�ž���ơ�����ǽ�ʷ��ݤؤȽ����˲�������ƹԤ��ΤǤ��롣
17:18:57 -
entee -
TrackBacks
2008-12-15
Economical��Ecological���ʤ��κݡ��Ǹ���
��ͧ��������Ϥ�����blog�������������롦�����Υߥ��롣�פ˻ɷ������ơ���Linklog��trackback��ǽ�����Ǥ���ΤǤ��Τ褦�˥��Ž�롣�����ޤǤ�ʤ����Ȥ��������ʸ�ϤϿ�����ڤ��ޤ��Ƥ��ä��������μ�ĥ���ö��������Ƥ��äǤ��뤷���ޤ��Ƥ䥿�ᥰ����á�������������Ǥ���������פäƤ�Τ˲�͡����������äơ�ȿ���Ǥ����ͤ�����פȤ������Ȥǡ������դ�ϳ���������ˤϤ��夦���夦���Τ���ĺ��������Ǥ��롣���֤��ϰʾ塣
��Economical��Ecological�Ⱥ�Ʊ����ʡפȤ��������ϡ������ӥ��������¦�������Ȥ��Ƥʤ餽�����������Ϥ��塼�֤������Ǥ��롣�������äƥ���������������äƥ����ӥ����Τ�Τ�����������Τϥ��ޥ������Ȥ������μ�ĥ����ڤ϶����Ǥ��롣
������������������ö�������ơ���ʬ������ɤ������ӥ�������븢��������Ȥ��ιͤ����ö˺��ƹͤ���ȡ���economical�����Τξ��ˤ�����ecological���פȤ����Τ�ǧ��Ƥ��ɤ������ʵ��⤹��Υ���
���⤽���������������̾�������Τˤ�����ecological�ǤϤʤ����ʹ֤�������ư���Τ�Τ���ecology�����ΡפǤ���ʾ塢�����٤˥��ߥåȤ��ʤ��������Ȥ����Τ�����ecological�Ǥ��롣�ʹ����������Ƥ�������������Ф����Ф���ϵ�ˤ䤵�����ס����줬��ü�ʤ顢�ʹ֤�������ɬ�פΤʤ����ϥ����������Ʋᤴ����ɬ�פʻ��������֥���������ư�˽������롢�Ȥ����褦�ʥʥޥ���Τ������������ΤǤ���Τ��������餯�����ܤ��餤�˴Ķ���٤��㤤�������ӥ����ä�̵�̤˾д���ä���֤���ä��㤤�ޤ����꤬�Ȥ��������ޤ��פʤɤ�Ϣ�Ƥ��ʤ������Ŀͤξ��륨�ͥ륮���Ͼ��ʤ��ƺѤफ�⤷��ʤ������ʤ��ƺѤ�п��٤����̤⸺�餻�롣����ϥ��������������
���α�Ĺ�ǹͤ���ȡ����줫������ǽ���ι⤤��Ĺ��Ū�ǿ����ʵ����ڴ��פȤ����Τϡ�Ĺ����Ǹ���ȡ��֤���ɴǯ�ǰ��������ú���ӽ��̤����ʤ��ä������Ǥ��ä��פʤɤȤ�����¬��̤��褵������⤢������ʥۥ�Ȥ����ˡ����������ʡ�Ĺ��Ū�ǿ����ʵ����ڴ��פ�������Τ褦�ʶ�ü�����̾���ʻ���ˤ˷�ӤĤ���ǽ���⤢�ꡢ���ξ��������դη�̤ˤʤ��ǽ���⤢�륱�ɡ�
������ˤ��Ƥ⸽�߿ʹԤ��ĤĤ����ͻ�����Ȥ����Τϡ�������ν��֤����Ǥ�Ʊ�����Ȥ��֤��Ф���Υϥʥ��ǡ����������Τ�Τ��ڤ��ؤ��ơ��֥�������������פߤ����ʤ��Ȥ⡢��ʬ�˻��������ʤ���Фʤ�ʤ������ʬ�������ͤ��Ĥ��Ƥ���Τ��Ȥ�פ��롣�Ĥޤ�֤���Ϥʤ����ʤ�Ф����Ȥ�ʤ���������פߤ������ä������뤤�ϡ������¾�ͤΥ���������������䥵���ӥ����Ф��봲�Ƥ��ܤ���Ȥ��ʥ����Ǥ��ˡ�
������������������̾���Ȥ��������������Ω������кѴ��פ��Τ�Τ��Ѥ����ˡ�ñ�˼��ȴ����Ȥ����������ȴ���ƹԤ����Ȥ����ͤʤ�����ƹԤ��ȡ���������ȯ������60-70ǯ������ܤ䡢����ͥ��13����ۤ���ȸ������ٹ�Ǻ��ʹԤ��ĤĤ���褦�ʡִ��ʤ�������פˤʤ��ǽ���⤢�롣���ηк�Ū�ʴ��פξ�ǡ�ecological���ɵ᤹�뤳�Ȥ����ּ��ȴ���פɤ������ּ����פ��ȤǤ���Τϡ��Τ��ˤ�äȶ�ͭ����Ƥ�����٤��Q���Ȥϻפ������Х��ȥ����åդ�ʬ���äƤ�餦�ˤϡ�����˰��ֳݤ��ʤ���ʤ�ʤ��ΤϳΤ��������ͤ���
��Economical��Ecological�Ⱥ�Ʊ����ʡפȤ��������ϡ������ӥ��������¦�������Ȥ��Ƥʤ餽�����������Ϥ��塼�֤������Ǥ��롣�������äƥ���������������äƥ����ӥ����Τ�Τ�����������Τϥ��ޥ������Ȥ������μ�ĥ����ڤ϶����Ǥ��롣
������������������ö�������ơ���ʬ������ɤ������ӥ�������븢��������Ȥ��ιͤ����ö˺��ƹͤ���ȡ���economical�����Τξ��ˤ�����ecological���פȤ����Τ�ǧ��Ƥ��ɤ������ʵ��⤹��Υ���
���⤽���������������̾�������Τˤ�����ecological�ǤϤʤ����ʹ֤�������ư���Τ�Τ���ecology�����ΡפǤ���ʾ塢�����٤˥��ߥåȤ��ʤ��������Ȥ����Τ�����ecological�Ǥ��롣�ʹ����������Ƥ�������������Ф����Ф���ϵ�ˤ䤵�����ס����줬��ü�ʤ顢�ʹ֤�������ɬ�פΤʤ����ϥ����������Ʋᤴ����ɬ�פʻ��������֥���������ư�˽������롢�Ȥ����褦�ʥʥޥ���Τ������������ΤǤ���Τ��������餯�����ܤ��餤�˴Ķ���٤��㤤�������ӥ����ä�̵�̤˾д���ä���֤���ä��㤤�ޤ����꤬�Ȥ��������ޤ��פʤɤ�Ϣ�Ƥ��ʤ������Ŀͤξ��륨�ͥ륮���Ͼ��ʤ��ƺѤफ�⤷��ʤ������ʤ��ƺѤ�п��٤����̤⸺�餻�롣����ϥ��������������
���α�Ĺ�ǹͤ���ȡ����줫������ǽ���ι⤤��Ĺ��Ū�ǿ����ʵ����ڴ��פȤ����Τϡ�Ĺ����Ǹ���ȡ��֤���ɴǯ�ǰ��������ú���ӽ��̤����ʤ��ä������Ǥ��ä��פʤɤȤ�����¬��̤��褵������⤢������ʥۥ�Ȥ����ˡ����������ʡ�Ĺ��Ū�ǿ����ʵ����ڴ��פ�������Τ褦�ʶ�ü�����̾���ʻ���ˤ˷�ӤĤ���ǽ���⤢�ꡢ���ξ��������դη�̤ˤʤ��ǽ���⤢�륱�ɡ�
������ˤ��Ƥ⸽�߿ʹԤ��ĤĤ����ͻ�����Ȥ����Τϡ�������ν��֤����Ǥ�Ʊ�����Ȥ��֤��Ф���Υϥʥ��ǡ����������Τ�Τ��ڤ��ؤ��ơ��֥�������������פߤ����ʤ��Ȥ⡢��ʬ�˻��������ʤ���Фʤ�ʤ������ʬ�������ͤ��Ĥ��Ƥ���Τ��Ȥ�פ��롣�Ĥޤ�֤���Ϥʤ����ʤ�Ф����Ȥ�ʤ���������פߤ������ä������뤤�ϡ������¾�ͤΥ���������������䥵���ӥ����Ф��봲�Ƥ��ܤ���Ȥ��ʥ����Ǥ��ˡ�
������������������̾���Ȥ��������������Ω������кѴ��פ��Τ�Τ��Ѥ����ˡ�ñ�˼��ȴ����Ȥ����������ȴ���ƹԤ����Ȥ����ͤʤ�����ƹԤ��ȡ���������ȯ������60-70ǯ������ܤ䡢����ͥ��13����ۤ���ȸ������ٹ�Ǻ��ʹԤ��ĤĤ���褦�ʡִ��ʤ�������פˤʤ��ǽ���⤢�롣���ηк�Ū�ʴ��פξ�ǡ�ecological���ɵ᤹�뤳�Ȥ����ּ��ȴ���פɤ������ּ����פ��ȤǤ���Τϡ��Τ��ˤ�äȶ�ͭ����Ƥ�����٤��Q���Ȥϻפ������Х��ȥ����åդ�ʬ���äƤ�餦�ˤϡ�����˰��ֳݤ��ʤ���ʤ�ʤ��ΤϳΤ��������ͤ���
14:26:52 -
entee -
TrackBacks
2008-04-21
���Ĥ�礦�ֻ��ۡס��Dz�ؼ�Ͽ��Ϣ���ַ��٤˲�����

�ֱDz�פȸ����Хƥ�Ӥǥץ�ӥ塼��ή���Ƥ���褦�ʥϥꥦ�åɷϱDz�䡢�����鼡�ؤȺ����ƥ�ӤΥۡ���ɥ�ޤߤ�����ˮ����ʤ��餤�����Τ�ʤ��Ȥ������Ϥ��ɤ߲�����ʤ��Ƥ�����
�� �ƥ��ȥ뿷��
��Ͽ��Ϣ���ַ�����������ؤ�ƻ��
5/10���ڡˤ��⡼�˥�Ƿ���
������ơ��֥�
��5/9�ʶ�� 11:30/15:20/19:10��22:40
5/10���ڡˡ�5/23�ʶ�� 11:00��14:30����1��1����
����58��٥����ݱDz�ס�(2008ǯ)
�ԥե����������վ��Ժ���
���ˡ���58��٥����ݱDz�סۣ������ޡ�����
����ͥ���������Dz��(NETPAC��)���ޡ�
����ݷݽѱDz�ɾ��Ϣ����(CICAE��)���ޡ�
������20�������ݱDz�סۡ�
�������ܱDz衦��������պ��ʾ��ޡ�
��
�Dz褫������������Ϥ�ä���Ȥ����μ¤˺��Ѥ��Ƥ��롣
����ֶ���Ū�פȤϸƤӤ����ʤ��������������������פؤο���δ��ФȤϡ�����줬�㤤���˰��٤��̤�ȴ���Ƥ�����Τ����������ζ���������ٵ���ʸ�����Ф�����Ƚ�Ȥ����Τ⡢���κ��ä��Ϲ�����餤�κ��˽��ƽв�ä�ů�ؤ˵�����Τ������ְִ㤤�ĤĤ���ʸ���פ��Ф���پ�Ȥ��ƽޤ������Ȥ����������ȤȤ�ˤ��ä���Τ���
���������ؽƤΤ褦�˻�Ƴ�Ԥθ�����ȯ�����뤭�������Ū�Ǵ�ǰŪ�ʸ��ա����ա����ա����֤�ݤ��ƹͤ���С��ֽ��ʻ��ۡפȤ�������Ǥ��ʤ��Ϥʤ������Ǥ⡢���¤Ȥ��ޤ�礤���դ����ʤ�����������ɽ�̤���ꤹ��Ф�������Ĥ��������ҤȤμ��ڤʤ����������ʤϤ��Ρֻ��ۡפϡ����٤����Ĥ�礤����DZ�������롣����Τϡ����äǤϤʤ������Ǥ�ʿ���ʥԥ����ˤ���Υƥ�������Ǹ��뤳�ȤΤǤ���褦�ʥ��ʥ����ˤ�����Ĵ�Υ����Ǥ��ꡢ�ضڤ��Ϥ�϶�äƷ����ʤä��ʹ֤�ȯ������������ˤ�äƷ���Ф����ñ�����Ǥ��롣
���Ρ�Ǯ���פϤ������������λֻΤ������о줹��ɥ�ޤ�Dz�ʤɤǤ�������Ƥ�������ߤ˻¤ä���¤�줿�ꤹ���Ԥη����ǤϤ���Τ��⤷��ʤ������Ľդ��������������Ȥϸ��������ʤ������ξ��ꤹ�����Ū�ʸ���˸¤äƤϡ�����˽��Ū�˷����֤����Ф���ǡ��ۤ��μ�Ԥ˹ͤ������������뤳�Ȥ��Ǥ��ʤ���
���ˡ��֤ޤä����狼�äƤ��ʤ��פȻ�Ƴ�Ԥ����Ĥ����Ԥ�����������ʬ���餻�뤳�ȤΤǤ��롢�´��ȸ��´���ȼ�ä����դȷи���Ƴ�Ԥ�ޤᡢï�⤬�����ʤ����ʤ��λ�Ƴ�Ԥ��äƻ�Ƴ�����¦�Ȥۤ�ο�ǯ�κФκ������ʤ�����
�������äơ������������ʻ���Ū��Ÿ���ˤĤ��ƹԤ����ȤΤǤ���˰����Ρ������äݤ��˿ʹ֤����������������ơ֤狼�äƤ���פΤǤ��ꡢ�ֻ�ƳŪΩ��פ˵�¤뤳�Ȥ��Ǥ��롣�����ơ��֤狼�äƤ��ޤä��ԡפϡ���ʬ�Τ���ޤǤΡְִ㤤�פ�ǧ��ʤ��櫓�ˤϤ�������ǧ��Ƽ��ʤ���Ƚ���������ꤹ��Ԥϡ��餱��ǧ��ơֻ���Ū�פˤ��Ƴ�Ԥ˽��虜������ʤ����ְִ�ä��ԡפϡ�������ʲ�С��������ԡפ˽����Τ�����Ū�ˡ����פȤʤ롣�������ƻ��ۤ�����ۡ���Ƴ�����Ƴ�������ۤȤ�������ǰ���Ϥ����Ƽ¸������ΤǤ��롣
�������֤狼��ʤ��ԡפϡ��ɤ��ޤǹԤäƤ�狼��ʤ���ʬ�ˤĤ��ƤΡ�����פ���������롣���ۤ�狼��ʤ��Ԥ��ּ��ʤ����礹��פʤɤȤ������Ȥ�Ƶ��ʳ��β���ΤǤ�ʤ������Τ褦�ʤ��Ȥ��������Բ�ǽ�ʤΤ����顢�狼��ʤ��Ԥ��������뤳�Ȥϡ�����˼��Ԥ������դ��狼��ʤ����̤�ȿ�ʤ�¥���Ƥ���褦�ʤ�Τǡ��ޤä�����ä������˹��ʤ��ΤǤ��뤬����Ƴ�Ԥ�����ŪΩ��ϡ�����������ʬ�˸�������Ƚ���������Ѥ�������֤������פ���äƤ���Τ������Τ褦�ˤ��ơ�����פΰ�̣�ϼ���˼����ƹԤ������������Ƴ�Ԥ����ϡ��ּ�ʬ��������Ф��Τ���������פȤ��������ˤ�äơ����λ�Ƴ�䶵�����դ����Ȥ����Ƥ��ޤ���
�ɤ��ޤǤ�֤狼��ʤ��ץ��С��ˤϡ����դˤ�뼹ٹ����Ƚ�ȿͳʤ����ꡢ�����ơ��֤�ʤ�����̿���Ǥܤ�����Ū��˽�Ϥ��ԤäƤ���ΤǤ��롣����ϡ���ī���ζ������ƽ�䥫��ܥǥ����Ρ֥���ե�����ɡס�ʸ�����̿����������������������˷�ʼ�����ĥ������⤷�����Ȥ���ߴƻ�Ƥ������ܡ��ʤɤʤɤ˵��������ȤǤϤʤ��Τ��������70ǯ��ˡ�����줬��������褷�Ƥ����٤ǵ����Ƥ������ȤʤΤ���
��
���������ԡפ��ݤ������δ��Фϡ���ʬ����Ǥ�Ĺ����������������褿��Τ����������Ԥ��ݤ��äƤϥ����ʥ�������������������ۤɡ�����Ϲ���������ۤ����ʤ���Фʤ�ʤ����顢�Ȥ������Ȥ⤢�롣���������ΥХ���Фˤ�äơ��������ԡפ���ʬ�˶�Ť����褿��ƨ���������ꤷ�ʤ��ǡ���ǽ�ʸ¤ꤽ�Ρ��������פ��䤦�Ȥ��������˼�ʬ������碌���ΤǤ��롣���������в���ݤȤ���ʹ֤ˤȤäơ��������äơ��������ԡפ��ݤ��餺�ˡ���Ť��Ƥ��äƸ�Ƥ���Ƥߤ�Ȥ����Τϡ����ˤȤ��Ƥष��ɬ�פʤ��ȤǤ��ä���
�����������������ĺ�Ū�ʾ����ˤ����ơ����������δ��Сפ�����ȴ�����Ԥϡ����ꥹ�ޤˤʤ��ǽ�������ꡢ��������ݤ��䤦¸�ߡ���Ƚ�ԡˤ����ʤ��ä��ꡢ��Ƚ�Ԥ���������ꤹ�뤳�Ȥ���������ȡ������ĺ���������ǡ֤ޤä���˽���פȤʤ롣��ʬ������������Ȥ������ζ���٤����С�����ϼ㤯�ƽ��ʻ����μ�Ԥˤ������������ʤ��ȤǤϤ�������40������ʬ���ä��褦����ǯ����Ҷ��λĹ˶ᤤ��Τ����ϻ��äƤ��롣�äˡ��ۤʤ����夬���餺���������äƤ���˾�Υ�٥뤫����Ƚ�Ǥ���¸�ߤ��ʤ���С��ֳ�̿�����ۡפȤ�����Τϡ�˽��Ū��ˡ�����ơ����¤Τ�ΤȤʤ����롣����������̿�Ȥϡ��Ƴ�����������Τ��⤷��ʤ���
���������ԡפι٤����Ƥϡ�ã�������٤����ۤ���Ū�Τ���μ��ʤȤʤꡢ�����ʤ���ʤ��������Ǥ���Ȥ������ۤ���ã�������٤Ƥ��ø�������Ū�ʸ��Ϥ�������롣���줬���ä���30��40���餺�μ�Ԥν��ޤ�Ǥ��ä��Ȥ��Ƥ⡢��������Ū���Ϥ˵դ餦���ȤϤǤ��ʤ��Ȥ����������������졢������й�����ͦ�����С����ͤ�����Ǥ���������ۤؤȶ�Ť��������ˡ�פȤʤ�����Τ������������Ū�ʼҲ�����ۡˤ�¸������뤿���������Ƨ�ߤˤ��äƤ��뼫�ʤ�Ω����ưפ�˺�Ѥ��롣
������Ƚ������Ȥ�����졢���դʤ�˽�Ϥ��졢�֤���ʤ��ȡ���̣����Τ��������줬��̿�ʤΤ����פ����������Ƕ����ˤ����ϡ��������붭���Ϥ����֤�����䤵�줿�ַ��������פΥ����פ���ǡ�����������졢�ޤ��ˤ������Ѥʵ���椨�ˡ�������������������ǹԤä����ۤ�Τ���äȤ�����Ƴ���ؤε���Ǥ����⡢���٤ơֳ�̿Ū�Ǥʤ��סּ��ʤζ������������ʤ��פʤɤ���ͳ�ǰ�������롣�������ƾ��Ϳ��Υ����פ����������Ȥʤ롣���ۤ�dz�����㤤��ǯ������̴�����������Ȥ������Ȳ����������������ζ��������ϳڤ�����ݤ��ǤϤʤ������ν��ʡ��������δ��Сפ椨�ˡ�������ͦ����ʳ���ʤ�����˵������ֶ��������Ǥ����������פ椨�ˡ��ޤ��Ȥ˸�̣�����������������θ�̣�ΰ�������ƨ��褦�Ȥ��Ƥ⡢������Ƥ����Τ������ǤϤʤ�������줬�����Ƥ������������ˤ����ơ����¤�ʪ��Ȥ��Ƶ����Ƥ����Τ��Ȥ������������顢������ƨ��뤳�Ȥ��Ǥ��ʤ���
��
�Τ��ˤ��αDz�ϡ������ư�Ȥζ��������뤿��μ��ʤȤ����Ѥ����Ƥ⤪�������ʤ���������ۤ����ɳ�ư�Ȥˤ�äƤ�Ʊ�����Ȥϵ����ꤦ�뤷����������Ƥ������Ȥ������������δ��Сפؤ�̵��Ƚ�ʿ���ȡ�����夲��٤����˾夲�ʤ������Ρ�ͦ���Τʤ��פ�·���С����ĤǤ⡢���٤Ǥ⡢�����Ͼ�ˡּ¸����Ƥ��ޤ��ײ�ǽ������Ľ�����ʤΤǤ��롣�ᤷ�����Ȥ��������줬�ֿʹ����פʤΤǤ��롣
[Read More!]
20:20:12 -
entee -
TrackBacks
2007-09-03
�ֲϹ�Ȼͺ�פȤ�������
�ޤ���������ʤ���Фʤ�ʤ���������μ��Ū��ů�ؤȤϱ��椫���ʤ�����κ����ή�������Ū�ʻ�Ĭ�ϡ��ष����ȿ����פȤ����ƤФ������������ΤǤ��롣
����������˥ʥ�����˲�ô�����Ȥ������Ȥ��������Ǥ��뤬���ʲ��Τ褦�ʥ���Ȥε��Ҥ���Ǥ��Τ��Τϡ������������μ��Ū�ʻ��������Ȥ�����Τ��Ф��롢�ष����Ƚ���ФʤΤǤ��롣
��Ϥ��������������������Τ褦��ή��Ϥ�Ƥ��뤳�Ȥ�ȩ�Ǵ����ȤäƤϤ����������Τ��ȤΡְ�̣��褯���Ƥ����פ�����λ�����Ф���㺹���Ϥष���Ҵ�Ū�Ǥ��롣�㤨�С����ε��ҤϹ�ȼ���Ȥ�����Τ��ܼ�����ª���Ƥ��ơ���ͳ����Ȥ���̾�β��˹�Ȥؤ���°�϶��������Τ��Ȥ����������ˤ����Ƥ�������ʷپ�Ȥʤ뤳�Ȥ�Ҥ٤Ƥ��롣
�ʤɤȡ����Ѥ��ʤ���إ�����٤�ڤ������ɤ��Ƥ����顢�躢�����βϹ�Ȼͺ�����鼰�����ä��Ȥ�����ƻ�����ä��褿��
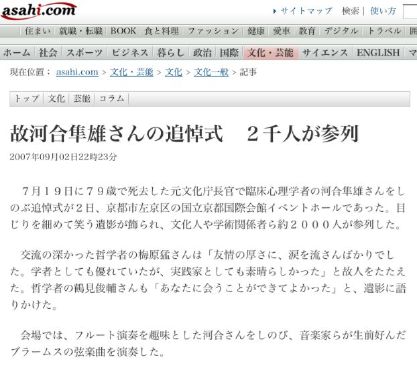
��Ԥ����ǤĤ褦��������ζ��ӤˤĤ��Ƥϥ�Ҳ�ԡ������ԡ�����ȤȤ��Ƥ�¦�̤���ɾ�����뤳�ȤϤǤ��ʤ���
����ˤ��Ƥⲿ�椨�ˡ���ǯ�βϹ�Ȼͺ�Ϲ�ȸ��ϤΤ����������礦��ʤ�����ߤ������ڤ�����̤Ƥ��������������������μ�����ɽ�פȤ��ơ�ʸ��ģ��Ĺ����̳��塢ʸ�ʾ�ʸ�դΰ�̾�⤭��ƻ���ɤ�������ؤ������ΥΡ��ȡ٤��Խ����Ѷ�Ū�˷Ȥ��ʤɹ�ȴ�νŪ�ʥ���ȤȤ��ƽ���ä��Ȥ������Ȥϡ������ǥߥå��ʿʹ֤ζˤ�뤳�ȤΤǤ���ĺ���ΤҤȤĤǤ��äơ����֤ˤ�����������ɤΰ���ʤΤ�����������������Ϥޤ��������Υ���ؤ���������ȤǤϤʤ�������������μ���ˤ����褭����Ԥ餷���μ��ͤ����ϰ�����Τ���������Ԥ�ɤΤ褦��į��Ƥ����Τ����������줬�ԻĤǤʤ�ʤ���
�إ�����٤ˤ��С���Ͼ��Ǻ�ߤʤ������ʤ�����ռ������뤳�Ȥ��������̤ο����Ϥȸ�����ä����ޤ����ʡ����ȼ��ʡ����δ֤Ǥ��ΥХ��Ȥꡢ�դ���μ�ʬ�δ֤�̷��˼�ʬ�ʤ���ޤ�礤���դ�����
������Ф��ơ����ܤˤ������Ҳ�ԡ��Ϲ�Ȼͺ�ϡ���ǯ����ȡʸ��ϡˤȤ��Ƥ����ܤΡ���ݶ����Ϥ�̤��ˤ����ơ�Ʈ�褷�����Ĥ��Ҷ������פ���¤�˿�������������������ζ��Ӥ���ǡ��ݤ��ͤʤ����Ѥ��٤���������ƻ�����������Ū������Ȥ����ǽ���ɸ�����İ�̣�ˤĤ��ơ��ब��ʬ�˿����ͤ����ȤϹͤ��ˤ����ۤɤ������ʲ��ż���ȸƤ֤٤��Ǥ�������
�Ϲ�Ȼͺ�������ǥߡ�������������Ƥ��������ˡ��������ȹ�ȸ���¦�����˼����ޤ�Ƥ��ä��Ȼפ��뵰�פϡ��������ν��ǼҤ䶦���Ԥ��̡����鸫�Ƥ�Ǥ��롣���Ȥ�ī����ʹ�Ҥʤɤ��鴩�Ԥ��줿�ܤ�¿���������ԤȤ��Ƥ⡢�ḫ���塢�繾��Ϻ��ë�����Ϻ��¼��ռ����������졢�������졢��������ʤɤν�����ơ���餬�Ϲ�Ȼͺ�Ρ���λ����ˤ������ȸ��Ϥؤ��и������ꤷ���ϻָ��ˤ�ï�ˤ�ͽ¬�Ǥ��ʤ��ä��ΤǤ�������
�Ϲ�Ȼͺ�Τ��������и��ϡإ��ȥꥢ��ʹ֤λ���٤�������ڷ���Ȥθ�ή�դ꤫��ФƤ����ΤǤϤʤ����ȿ��̤��롣�����ڷ���Υ��ȥꥢ��ʹ֤ˤĤ��Ƥ�����������Ƴ������˰տޤ��줿�Τ���ʬ����ʤ������ֹ�̱�פ���ȤˤȤä�ͭ�Ѥ�ϫƯ�ϤǤ���٤����Ȥ������ϡ�����濴Ū�ʻ������Ϥ�Ϳ���뤳�Ȥˤʤä��ΤϳΤ��Ǥ��롣������ˤ��Ƥ�Ϲ�Ȼͺ��ȿ���μ����ȿ����ۤ���ä��μ��ͤȤθ�ή�������������¿���������͡��ȶ�Ʊ���ƽ��Ǥ��뤳�Ȥǥ���ꥢ��Ϥ�����Ǹ�϶ˤ�ƹ�ȼ��Ū�����μ��Ū��ȿưŪ�ʻ��ۤ�Ҥ٤륹�ݡ������ޥ�Ȥʤä����ˤ�ư䴸�ʤ��ȤǤ��롣
���������ܤǤϥ�ˤĤ��Ƹ�뤳�Ȥϡ����λ��ۤν���ξҲ�ԤǤ�������ʤ�����Υ���Ĥؤ����ܿͻ��üԤΰ�ͤǤ��ä��Ϲ�Ȼͺ���Թ��ˤ�Ϣ�ۤ��뤳�Ȥʤ��ˤϹԤʤ����Ȥ��Ǥ��ʤ����Ϲ�Ȼͺ����ǯ�ι�ȴ�ν�Ȥ��Ƥδ�Ԥϡ���ˤĤ��Ƹ��������Ȥ����μ¤ˤ����˺����⤿�餹��������
��θ������佸��Ū̵�ռ����Ȥ�����Τ����Ϲ�Ȼͺ��Ϳ�����褦�����μ�����ȼ���ʼ��ʤ�ͥ��Ū��¸�ˤؤȤ�������Ω�Ƥ�褦���������ܼ�Ū�ʤ�ΤȤ��ƴޤ��ΤǤϤʤ��ˤ�ؤ�餺�����Τ褦�ʤ�ΤǤ�������դ�����������;�ꤢ���ɿ�Ū��ȿ���Ϲ����Ԥ�¦����������ĤĤ��뤳�Ȥ����¤˻�ǰ�ʤΤǤ��롣�����������ǯ�βϹ��ƻ�����Ȥϡ����Τ�ʬ����������ɬ�פ����롣
����ˤ��Ƥ⡢���ܥ������Ĺ���äƤ�����ƻ����Ϥ���Ȥ��ơ����ܤˤ��������ɤ��ɤ����֥����Ǥ�ʤ��ͤ����ν��ޤ�פǤ���褦�ˤ�פ����Կ���ǰ���ʤ��ΤǤ��롣
�ֲϹ�������з����ʥ�ˤޤ��������Υ����Ƚ�⤢�롣��ĥ���濴�ˤϤष���������뤬��������������Ԥˤ�äƲϹ���Ƚ�Τߤʤ餺�������Ƚ�ˤޤǵڤ�Ǥ������Ȥϡ����夽����Ƚ��̷�褬��ʬ�ˤޤǵڤ�Ǥ����ǽ����ż����Ƥ���Τǡ����֤�ݤ��ƻ�Ĭ�������Ȳ�餬�����ζ����ʤ���Фʤ�ʤ��ΤǤ��롣
���ͥ����ȡ�³�����ܥ���ɡ��Ϲ�Ȼͺ��Ƚ
����������˥ʥ�����˲�ô�����Ȥ������Ȥ��������Ǥ��뤬���ʲ��Τ褦�ʥ���Ȥε��Ҥ���Ǥ��Τ��Τϡ������������μ��Ū�ʻ��������Ȥ�����Τ��Ф��롢�ष����Ƚ���ФʤΤǤ��롣
������إ��������״����������륵����ǹԤ�줿�Ȥ����˥塼����ʹ�����Ȥ����䥳�֡��֥륯�ϥ���ϡ֤���ϥɥ��Ĥ����Ǥ��פȶ���������Ǥ˥殺�ʡ��ν����������á���Ƥ��ꡢ����ȤȤ�˥ˡ������Υǥ����˥����θ��������줿�������ƫ��ο�������������˵������ΤȤ��������ɤ����⤷��ʤ���������إ�����������ϥ衼���åѤ����¤ˤ���1914ǯ�λ��Ҥؤ�ƻ������
(��åե��ԡإ���������٤ߤ�����˼��page 50)
��Ϥ��������������������Τ褦��ή��Ϥ�Ƥ��뤳�Ȥ�ȩ�Ǵ����ȤäƤϤ����������Τ��ȤΡְ�̣��褯���Ƥ����פ�����λ�����Ф���㺹���Ϥष���Ҵ�Ū�Ǥ��롣�㤨�С����ε��ҤϹ�ȼ���Ȥ�����Τ��ܼ�����ª���Ƥ��ơ���ͳ����Ȥ���̾�β��˹�Ȥؤ���°�϶��������Τ��Ȥ����������ˤ����Ƥ�������ʷپ�Ȥʤ뤳�Ȥ�Ҥ٤Ƥ��롣
���������ʳ�Ūȯ���ˤ�äƤ����϶���٤������ˤ��餵��Ƥ��뤳�Ȥϸ��鷺�⤬�ʡ��礤�ʤ뼫ͳ�Ȥ�����˾�Ϲ�Ȥؤ���°������ˤ�ä�Ģ�ä�����Ƥ��뤳�Ȥ�ǧ��褦�ȤϤ��ʤ���������������㤿���ε���Τ����ʤ���С�������������Ϥޤ��ޤ���ʬ���Ȥ����ʤ��ʤ롣�������ơ������ϸĿͤȤ��Ƥκ����ȡ���ʬ��Ƴ����ǽ�Ȥ��Ǥ��ڤ뤳�Ȥ����Ϥ��Ʋ�ô�������η�̥ˡ��������ֽ��Ϥ������פȸƤ����Τˤ�äƤΤ��ۤ���������ΰ�ʬ�ҤȤʤ��ΤǤ��롣
(��åե��ԡإ���������٤ߤ�����˼��page 52)
��
�ʤɤȡ����Ѥ��ʤ���إ�����٤�ڤ������ɤ��Ƥ����顢�躢�����βϹ�Ȼͺ�����鼰�����ä��Ȥ�����ƻ�����ä��褿��
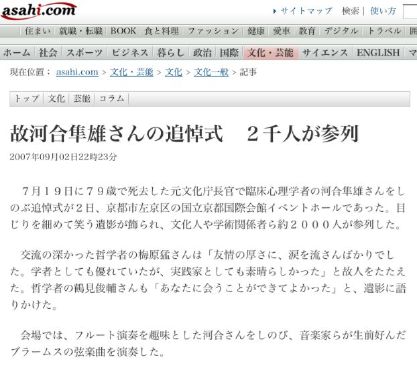
��Ԥ����ǤĤ褦��������ζ��ӤˤĤ��Ƥϥ�Ҳ�ԡ������ԡ�����ȤȤ��Ƥ�¦�̤���ɾ�����뤳�ȤϤǤ��ʤ���
����ˤ��Ƥⲿ�椨�ˡ���ǯ�βϹ�Ȼͺ�Ϲ�ȸ��ϤΤ����������礦��ʤ�����ߤ������ڤ�����̤Ƥ��������������������μ�����ɽ�פȤ��ơ�ʸ��ģ��Ĺ����̳��塢ʸ�ʾ�ʸ�դΰ�̾�⤭��ƻ���ɤ�������ؤ������ΥΡ��ȡ٤��Խ����Ѷ�Ū�˷Ȥ��ʤɹ�ȴ�νŪ�ʥ���ȤȤ��ƽ���ä��Ȥ������Ȥϡ������ǥߥå��ʿʹ֤ζˤ�뤳�ȤΤǤ���ĺ���ΤҤȤĤǤ��äơ����֤ˤ�����������ɤΰ���ʤΤ�����������������Ϥޤ��������Υ���ؤ���������ȤǤϤʤ�������������μ���ˤ����褭����Ԥ餷���μ��ͤ����ϰ�����Τ���������Ԥ�ɤΤ褦��į��Ƥ����Τ����������줬�ԻĤǤʤ�ʤ���
�إ�����٤ˤ��С���Ͼ��Ǻ�ߤʤ������ʤ�����ռ������뤳�Ȥ��������̤ο����Ϥȸ�����ä����ޤ����ʡ����ȼ��ʡ����δ֤Ǥ��ΥХ��Ȥꡢ�դ���μ�ʬ�δ֤�̷��˼�ʬ�ʤ���ޤ�礤���դ�����
������Ф��ơ����ܤˤ������Ҳ�ԡ��Ϲ�Ȼͺ�ϡ���ǯ����ȡʸ��ϡˤȤ��Ƥ����ܤΡ���ݶ����Ϥ�̤��ˤ����ơ�Ʈ�褷�����Ĥ��Ҷ������פ���¤�˿�������������������ζ��Ӥ���ǡ��ݤ��ͤʤ����Ѥ��٤���������ƻ�����������Ū������Ȥ����ǽ���ɸ�����İ�̣�ˤĤ��ơ��ब��ʬ�˿����ͤ����ȤϹͤ��ˤ����ۤɤ������ʲ��ż���ȸƤ֤٤��Ǥ�������
�Ϲ�Ȼͺ�������ǥߡ�������������Ƥ��������ˡ��������ȹ�ȸ���¦�����˼����ޤ�Ƥ��ä��Ȼפ��뵰�פϡ��������ν��ǼҤ䶦���Ԥ��̡����鸫�Ƥ�Ǥ��롣���Ȥ�ī����ʹ�Ҥʤɤ��鴩�Ԥ��줿�ܤ�¿���������ԤȤ��Ƥ⡢�ḫ���塢�繾��Ϻ��ë�����Ϻ��¼��ռ����������졢�������졢��������ʤɤν�����ơ���餬�Ϲ�Ȼͺ�Ρ���λ����ˤ������ȸ��Ϥؤ��и������ꤷ���ϻָ��ˤ�ï�ˤ�ͽ¬�Ǥ��ʤ��ä��ΤǤ�������
�Ϲ�Ȼͺ�Τ��������и��ϡإ��ȥꥢ��ʹ֤λ���٤�������ڷ���Ȥθ�ή�դ꤫��ФƤ����ΤǤϤʤ����ȿ��̤��롣�����ڷ���Υ��ȥꥢ��ʹ֤ˤĤ��Ƥ�����������Ƴ������˰տޤ��줿�Τ���ʬ����ʤ������ֹ�̱�פ���ȤˤȤä�ͭ�Ѥ�ϫƯ�ϤǤ���٤����Ȥ������ϡ�����濴Ū�ʻ������Ϥ�Ϳ���뤳�Ȥˤʤä��ΤϳΤ��Ǥ��롣������ˤ��Ƥ�Ϲ�Ȼͺ��ȿ���μ����ȿ����ۤ���ä��μ��ͤȤθ�ή�������������¿���������͡��ȶ�Ʊ���ƽ��Ǥ��뤳�Ȥǥ���ꥢ��Ϥ�����Ǹ�϶ˤ�ƹ�ȼ��Ū�����μ��Ū��ȿưŪ�ʻ��ۤ�Ҥ٤륹�ݡ������ޥ�Ȥʤä����ˤ�ư䴸�ʤ��ȤǤ��롣
���������ܤǤϥ�ˤĤ��Ƹ�뤳�Ȥϡ����λ��ۤν���ξҲ�ԤǤ�������ʤ�����Υ���Ĥؤ����ܿͻ��üԤΰ�ͤǤ��ä��Ϲ�Ȼͺ���Թ��ˤ�Ϣ�ۤ��뤳�Ȥʤ��ˤϹԤʤ����Ȥ��Ǥ��ʤ����Ϲ�Ȼͺ����ǯ�ι�ȴ�ν�Ȥ��Ƥδ�Ԥϡ���ˤĤ��Ƹ��������Ȥ����μ¤ˤ����˺����⤿�餹��������
��θ������佸��Ū̵�ռ����Ȥ�����Τ����Ϲ�Ȼͺ��Ϳ�����褦�����μ�����ȼ���ʼ��ʤ�ͥ��Ū��¸�ˤؤȤ�������Ω�Ƥ�褦���������ܼ�Ū�ʤ�ΤȤ��ƴޤ��ΤǤϤʤ��ˤ�ؤ�餺�����Τ褦�ʤ�ΤǤ�������դ�����������;�ꤢ���ɿ�Ū��ȿ���Ϲ����Ԥ�¦����������ĤĤ��뤳�Ȥ����¤˻�ǰ�ʤΤǤ��롣�����������ǯ�βϹ��ƻ�����Ȥϡ����Τ�ʬ����������ɬ�פ����롣
����ˤ��Ƥ⡢���ܥ������Ĺ���äƤ�����ƻ����Ϥ���Ȥ��ơ����ܤˤ��������ɤ��ɤ����֥����Ǥ�ʤ��ͤ����ν��ޤ�פǤ���褦�ˤ�פ����Կ���ǰ���ʤ��ΤǤ��롣
�ֲϹ�������з����ʥ�ˤޤ��������Υ����Ƚ�⤢�롣��ĥ���濴�ˤϤष���������뤬��������������Ԥˤ�äƲϹ���Ƚ�Τߤʤ餺�������Ƚ�ˤޤǵڤ�Ǥ������Ȥϡ����夽����Ƚ��̷�褬��ʬ�ˤޤǵڤ�Ǥ����ǽ����ż����Ƥ���Τǡ����֤�ݤ��ƻ�Ĭ�������Ȳ�餬�����ζ����ʤ���Фʤ�ʤ��ΤǤ��롣
���ͥ����ȡ�³�����ܥ���ɡ��Ϲ�Ȼͺ��Ƚ
22:44:27 -
entee -
TrackBacks
2007-07-30
��Ϳ�ޡפ��ϳ��Ū���羡��
̱�礬�ּ�̱�ٻ��ءפ�ۼ�

���˥ͥåȾ夫���������ΤDz�������¸�����˥塼���ʥ���å����Ƴ����
==================
���ܤΡ���ư���������������
��ϡֺǰ��κ���Ǥ��ä��פȤ����������ˤ��ï�ˤ�ʬ����䤹���ס���ï�⤬ȿ�����������ץ�åƥ������äơ�������ï�ˤ⡢��ʬ����ˤ����������ˡ������ɤ����ä���Ȳ̤�������ˤ�̾��Ĥ���������
���äȤ����ä�������Ϳ�ޡפ�100��Ķ������ʤ���ä��ϳ��Ū���羡���Ǥ��롣
��ʪ�Ρ����ޡդϺ���15���ʤ�Ĥ��ΤߤȤʤä���
��̱�ޤ��餱�ơ����褤���Ϳ�ޤ���˲���פ������͡��ϳ������Ǥ����������ǤȤ���
[Read More!]

���˥ͥåȾ夫���������ΤDz�������¸�����˥塼���ʥ���å����Ƴ����
==================
���ܤΡ���ư���������������
��ϡֺǰ��κ���Ǥ��ä��פȤ����������ˤ��ï�ˤ�ʬ����䤹���ס���ï�⤬ȿ�����������ץ�åƥ������äơ�������ï�ˤ⡢��ʬ����ˤ����������ˡ������ɤ����ä���Ȳ̤�������ˤ�̾��Ĥ���������
���äȤ����ä�������Ϳ�ޡפ�100��Ķ������ʤ���ä��ϳ��Ū���羡���Ǥ��롣
��ʪ�Ρ����ޡդϺ���15���ʤ�Ĥ��ΤߤȤʤä���
��̱�ޤ��餱�ơ����褤���Ϳ�ޤ���˲���פ������͡��ϳ������Ǥ����������ǤȤ���
[Read More!]
03:29:00 -
entee -
TrackBacks
2007-06-20
����Τϥ֥�å����Х��Ǥ���

����Τϥإ��������Ǥ�ϡ��ɥ��å��Ǥ�ץ�����Ǥ�ʤ�������Τϥ�ꥫ�Ǥ��ꡢ�֥�å����Х��Ǥ��ꡢ�ե�����åѤǤ��롣����Τϥϡ��ɥХåפ�ե���㥺��ե塼�����ǤϤʤ�������Τϥ����ȡ��֥쥤�����Ǥ��ꡢ����ȥ졼��Ǥ��ꡢ����ޥ���ե��Ǥ��롣������Ϥ��٤Ƹ��ۤǤ��롣���뤤��ɾ���Ƚ����Ƭ��ʣ���ʲ��ڤα���������פ�������ޤ�Ȥ��Τʤ��˼���뤿������ؤǤ��롣
[Read More!]
23:00:00 -
entee -
TrackBacks
2007-05-22
���㡼�ʥꥹ�ȣĤλ�
�ڤ���ե���������
�����롢��ͤΥ��㡼�ʥꥹ�ȣĤ���������Τ�������ΣûԡʣŹ�ˤǻ������줿�Ȥ���ƻ�����ä���
�͵���ȯ������ϡ�����˭�����θ��ȴ������������ƱԤ���Ƚ�����Ȥ��ȼ��μ������ͥ���ڤ곫�����褦�䤯��������μ�����ƻ���������������ĤĤ��ä���������˼������������Ϥ����ۿ������ֹ�����������פȤ������ޥ��⣵���ͤ����뤤�������ǹ��ɼԿ���������ĤĤ��ä���ʣ���ο�ʹ�仨��Ǥ�����γ����ˤĤ����ý����Ȥޤ��ʤɡ�ǯ��Ū�ˤ�����Ρ��Τ�ͤ��Τ���Ω�ϥ��㡼�ʥꥹ�ȤʤΤǤ��ä���
�������Ū������Ф��������������Ƥ�����ʹ�Ҥȿ�ʹ����Ϥ��ä�������λ�������̱�����ȥ��㡼�ʥꥺ����Ф��빶��Ǥ���פȤ�������Ф�������ƻ��ɽ���μ�ͳ���Ф���Ź�α������밵�Ϥ�¸�ߤϤ��Ǥ��Τ��Ƥ����������ܤΡֽ����פΥޥ����ߤ⼡��ˤ����������ؤ�ĥ��Ϥ�Ƥ������Ȥ⤢�ä�����������������Ū��å������Ȥ��Ƥϥ������Ǥ��ä����ȤȤ���ޤäơ����㡼�ʥꥹ�Ȥ�������������Ƚ��������ˤ����������̤Ǥޤä������꤬����褦�˻פ��ʤ��ä���
����������Ͻ�����ư�ȤȤ��Ƥδ����äƤ�����������ؤ�����äƤ��������ο���ư�ǵ�Ū�ʥ����ڡ���ȱ�ư�깭���Ƥ���˿���Τϡ��֤��λ�������������Ф���ĩ��Ǥ��ꡢ������ȯ���������뤿������餫�ʥ�å������Ǥ���פȼ�����ä������ιͤ����礤��ȿ�Ǥ����ý������⡢�������������Ǻܤ��줿�������Ƥ���ʤ���礭��ȿ�����äƤ����ε����ϼ������줿�ΤǤ��ä����������Τϡ��Ĥ��㤤�������⤽�⥸�㡼�ʥꥹ�Ȥˤʤ뤭�ä������ä��ۤɤο����ؤ�����äƤ����Τ���
�ޤ�����ϡ������饨��ǹԤ��Ƥ���ѥ쥹���ʿͤؤβ��ڤʤ��ư�������������ơ������������夬��ĤĤ��ä��ֿ���ȿ��������פ˴ؤ��ơ��ֹ�ȤȤ��ƤΥ����饨��פ����̱²�Ȥ��ƤΥ����סʤ����ƥ����ͤȤ������ޤ줿�Ŀ͡ˤϤ��٤ƶ��̤���ª����٤������Ȥ�����ȤȸĿͤ�ʬΥ������˯�Ԥ���ĥ�����������ƺƤӳ��ϤǴ���������ĤĤ��ä���ȿ����������פ亹�̤��Ǹ�ȿ�Ф���Ω���ȤäƤ������ȤǤ��Τ��Ƥ��������Τ��ᡢ����ؤνƷ�������̱²���Ф���ִ���Ū����פǤ���ȹͤ���ʿ�³�ư�Ȥ�����ͳ�ư�Ȥ⤤���ΤǤ��ä������˥����饨��ǡ����뿷ʹ�ΰ��̤������˻��Ѥ����ո�����η��ǡ�����λ���Ф��밥��ΰդ�ɽ���줿�ΤǤ��ä���
������������������ܹ�Υѥ��ݡ��Ȥ���ġ����ܿ͡פǤ��ä��������Ĥ�ʶ�����Ӥ����ܿͤΡ����ǹ١פˤ�äơ���Ԥ�ι�ԼԤ�Ͷ�����줿�塢�������줿�Ȥ��ˤ����ä�����Ǥΰ�̾�⤭�Ŀ���ʥХå��ˤȡּ�����Ǥ���פ���������ʿ��Ū�ʥ��㡼�ʥꥹ�Ȥδ֤��������Ӥ����Ȥ⤢�ꡢ����λ���Ф������Τ����������ܤ������ˡ��ܤ�����١פ�ʤƷޤ��뤳�Ȥˤ����Τ��ä���������������ݸ�٤���̳����äƤ����Ϥ��μ��������ΣŹ���Ȥ��Ф��������˹��Ĥ�Ԥä���������������ܤιԤä��ֹ�ȯư�פȤ��Ƥϡ����ơ֤ޤȤ�ʡ��б��Ǥ���Ȥ��ơ�����κ���ɾ���Ȥ����⤤ɾ����������뤳�ȤȤʤä���
˺��ƤϤʤ�ʤ��Τϡ�������¤ϸ�������ī���ͤǤ��ä����Ȥ��Τ�����κ��ɼ��Ԥ����Τʤ��ˡ����������Ӥ������Ƥˤϡ��¤Ϻ������Ф�����ͤδ���ŪϢ�������ä�����ɾ����Ԥ����줿���ʤ��ʤ顢����ˤϤɤ���餽���ü��̱²Ū���طʤΤ���ˡ�����ˤ����Ƽ������¤��줿��˸��������������ꡢ���Τ���˹���Ǥμ����פ������˳�ư�����Ф���������ʤ��ä��Ȥ����Τ��������̾�������ܿ�̾�˲����������������ܹ��Ҥ��ä��ˤ�ؤ�餺�����줬ñ�ʤ�ɽ�ؾ�Υ�����ɥץ쥤�Ǥ��ꡢ������ȤϷ�ɺ��ä���Ρ�Ⱦ��͡פǤ��뤳�Ȥ��Ѥ��ʤ����Ȥ��������ͥåȱ��㤫����³Ū�ʤ���Ƥ������Ȥ������Ǥ��Τ��Ƥ������ޤ�����̳�ʤΥޥ����ʸ��Ȥ��ơ������̾�����ִ������ۡפ���ä�������ư�ȤȤ��ƤΥ֥�å��ꥹ�Ȥˤ�ܤäƤ��ꡢ���⤽������ܹ����ܤȤ��ƤϣĤ�����ݸ�뵤�ʤɤ��餵��ʤ��ä��פ�¿������֤������Ƥ����ΤǤ��롣�Ĥޤ���������ܹˤ����뻦���ˤ����ܹ���ˤ����������������Ǥ���ȿ����ܤ˹ͤ���ͤ����������ΤǤ��롣
�����ʤ��Ȥˡ����������ʩ���Ϥο����������Τ�°����Ǯ���ʿ��ԤǤ��ä����Ȥ��Τ��Ƥ��ơ��˥塼�������Ϥμ�Ԥ�������ϻ����������Ƥ�������θ��Υ�ݡ��Ȥ��͵�����Ƥ��ơ�����С֤������̡פǤ�����ϥ��ꥹ������ȯ�����Ƥ������ºݡ����λ���ΤۤȤܤ꤬�������פ��Ф����褦�ˡ�����λ����ϡ���ʬ�����������Τؤι���Ȥ��Ƽ�����餶������ʤ��ä��ȡ����ν������Τ���������ˡפ��������δ�Ϣ�η����̤��ƥ����Ȥ����ΤǤ��ä���
�Ȥ�������������������Τ�Ԥ���������·���Ƽ�ĥ����Τϡ�����������˿Ƥ����ʤä����륤����ඵ�̤���ǯ�¶ȲȤȤο�̩�ʴط��Ǥ��ꡢ�¤ϰ����������Τ��ä����ꥹ�ȶ��θ�������η����Τ��ä����ܡ����ե��ɤ����ٻ����Τ����������⤿�����Τ��Ȥ����ޤ��Ȥ��䤫�ʱ��⸽�ϤǤϹ����ä��ΤǤ��ä���������ඵ�̤ˤȤäƤϤ���ϥ�����ඵ�ؤι���Ǥ��ä���
�Ĥޤꡢ����ȴؤ�ä��������ȿ������Ρ������ΰ衢���Ĥʤɤϡ����줾�������ä����Ƥ�����ʬ�����ؤι���Ǥ��ä��Ȥޤ���˲�ᤷ���ΤǤ��ä������ʤ������ؤι���ϡ����㡼�ʥꥺ��ؤ�ĩ��Ǥ��ꡢ�����ؤ��Ѥ��̺��̰ռ��Τ⤿�餷����ΤǤ��ꡢ�����̱²�ؤι���Ǥ��ꡢ���ܹ�ؤι���Ǥ��ꡢ����ī���ͤ��Ф����и��Ǥ��ꡢ���������ؤ������ʷٲ����Ǥ��ꡢ�Ϥ��ޤ�������ඵ�ؤι���Ǥ��ä��Τ��ä���
����λ�ϡ��ؤ��Τ��ä��ɤ��ȿ����ɤ����Ρ��ɤο����ΰ衢�ɤζ��Ĥˤ����Ƥ��ħŪ�ʰ�̣����Ĥ��Ȥˤʤä��������Ƽ������ʹ֤ο���������λ�ˤϡְ�̣�פ����ꡢ�ɤ�ˤⶦ�̤ʤΤϡ���D�Ȥ����Ŀͤ��������ȿ��Ȥ�Ʊ��뤹�뤳�ȡפ���δ��äȤ��Ƥ��뤳�Ȥ��ä������������D�Ȥ����Ŀͤ�ĿͤȤ���ª���뤳�Ȥ褦�ȤϤ��ʤ��ä���D�ؤι���ϡ��Ŀͤ˽��������ä�ñ�ʤ���ΤǤ��ꡢ̵��̣�ǡ��Ծ����ʡ��Ա��פȤϡ�ï��פ������ʤ��ä��Τ���
��������Ϥ����Ǥ��롣
��������Ѥʰ���ȤǤ��äơ����д������ߤ��줿������ΣûԤǡ���֤���ä��ä⤦�Ȼפä��Τ��������Ĥˤ������ΰ¥ۥƥ�θ��ؤ��鳰�˽Фơ������ǥ��Х��˲Ф��դ����Ȥ�����㤤�����˼ͻ����줿�Τ��ä����ɤ�������ϣŹ�Ƕػߤ���Ƥ���̩͢�ʤΤ������ϡʤ����ʡˤ�ǡפ����餷�������줬�������Ȥ���Фɤ����D�ξ���Ƚ�ǤϴŤ��ʤäƤ����ΤǤ��ä������¡�����ΰ��Τη�դ���Ϥ������ľ��֤��Ǥ���ۤɤΥ��륳����⸡�Ф��줿�������ˤϹӤ餵�줿���פ���ޤ줿��Τ�ʤ����ݤ��θ��ơ����ܤΥӡ���ζ����ӤȰ��ߤ����Υ����å����Ӥ����Ĥ��ä��������ä�����������⤷�������μ㤤�⾥�ϡ���������ԤǤ��겿�͡ʤʤˤ���ˤǤ��ä����γ�ǧ�ޤǤϡ����Ω�����֤ȵ�Υ����ϤǤ��ʤ��ä������ޤ��Ƥ�Ĥ��ֽ��Ǥ��뤳�Ȥʤɥ��ߥ��ޤ��Τ�ͳ���ʤ��ä��סʤ���ϸ��ä��Τ��ä��ˡ��Ĥޤ����������Ū�ʻ����������տޤ��Ƥ��ʤ��ä��ΤǤ��ä���
�������������ϡ�¿���������Ȥ����Ƥ���Ƥ���ûԹٳ��η�̳�꤫���̾�μ��ͤ�æ��������������ꡢ��餬��ή����������������ȿ������ΤȻפ��롢����Ż���ͽ�𤹤�ĩ�������š�����դ���Ƥ������Ȥ����ꡢ�����夦�ˤ���ٻ����������ʶ�ĥ���֤ˤ��ä��Ȥ������ȤǤ��ä������������Τ褦�������Τ��Ȥϡ�����̡�褬���ܤ���Ƥ���褦�ʥ��֥�����Ƚ�Υ��ݡ��Ŀ�ʹ�ʳ�����ƻ���ʤ��ä��Τǡ������ܤʰ�ή��ʹ���ɤ�Ǥ������Ƥ���»νʽ������ˤ��Τ�ͳ��ʤ��ä���
������������β�Ǯ������ƻ���郎������������������ܤǵ����ä�������륹�ơ����쥹�ȥ��֥ڥåڥ롦�������פ�ŹĹ�ʲ����ͤ��ؽ�˽���Ƶ�����ޤä�����ˡ����Υ쥹�ȥ��������ˤޤä����Ҥ���ʤ��ʤ��ݻ��ֶ�dz���ˤ�ä��㤤á���줽�����Ȥ����˥塼�������ޤä��Τ��ä�������������ʾ����ʥ˥塼�������Ф��Ƥ��ޤ��ۤɡ����ΤҤȤ�ν������㡼�ʥꥹ�Ȥλ�Υ˥塼���ǻ�������ˤʤä��Τǡ�������Ĥλ���ο��ؤˡ��ָĿͤ��ȿ���Ʊ��뤹��פȤ����ʹ֤Ρֿ���Ū�����פȡ��Ҳ�Ūưʪ�Ȥ��ƤΡֿ��θ³��פˤĤ��ơ������ƻפ��֤��ͤϤ��ʤ��ä��ΤǤ��롣
�ʴ���
�����롢��ͤΥ��㡼�ʥꥹ�ȣĤ���������Τ�������ΣûԡʣŹ�ˤǻ������줿�Ȥ���ƻ�����ä���
�͵���ȯ������ϡ�����˭�����θ��ȴ������������ƱԤ���Ƚ�����Ȥ��ȼ��μ������ͥ���ڤ곫�����褦�䤯��������μ�����ƻ���������������ĤĤ��ä���������˼������������Ϥ����ۿ������ֹ�����������פȤ������ޥ��⣵���ͤ����뤤�������ǹ��ɼԿ���������ĤĤ��ä���ʣ���ο�ʹ�仨��Ǥ�����γ����ˤĤ����ý����Ȥޤ��ʤɡ�ǯ��Ū�ˤ�����Ρ��Τ�ͤ��Τ���Ω�ϥ��㡼�ʥꥹ�ȤʤΤǤ��ä���
�������Ū������Ф��������������Ƥ�����ʹ�Ҥȿ�ʹ����Ϥ��ä�������λ�������̱�����ȥ��㡼�ʥꥺ����Ф��빶��Ǥ���פȤ�������Ф�������ƻ��ɽ���μ�ͳ���Ф���Ź�α������밵�Ϥ�¸�ߤϤ��Ǥ��Τ��Ƥ����������ܤΡֽ����פΥޥ����ߤ⼡��ˤ����������ؤ�ĥ��Ϥ�Ƥ������Ȥ⤢�ä�����������������Ū��å������Ȥ��Ƥϥ������Ǥ��ä����ȤȤ���ޤäơ����㡼�ʥꥹ�Ȥ�������������Ƚ��������ˤ����������̤Ǥޤä������꤬����褦�˻פ��ʤ��ä���
����������Ͻ�����ư�ȤȤ��Ƥδ����äƤ�����������ؤ�����äƤ��������ο���ư�ǵ�Ū�ʥ����ڡ���ȱ�ư�깭���Ƥ���˿���Τϡ��֤��λ�������������Ф���ĩ��Ǥ��ꡢ������ȯ���������뤿������餫�ʥ�å������Ǥ���פȼ�����ä������ιͤ����礤��ȿ�Ǥ����ý������⡢�������������Ǻܤ��줿�������Ƥ���ʤ���礭��ȿ�����äƤ����ε����ϼ������줿�ΤǤ��ä����������Τϡ��Ĥ��㤤�������⤽�⥸�㡼�ʥꥹ�Ȥˤʤ뤭�ä������ä��ۤɤο����ؤ�����äƤ����Τ���
�ޤ�����ϡ������饨��ǹԤ��Ƥ���ѥ쥹���ʿͤؤβ��ڤʤ��ư�������������ơ������������夬��ĤĤ��ä��ֿ���ȿ��������פ˴ؤ��ơ��ֹ�ȤȤ��ƤΥ����饨��פ����̱²�Ȥ��ƤΥ����סʤ����ƥ����ͤȤ������ޤ줿�Ŀ͡ˤϤ��٤ƶ��̤���ª����٤������Ȥ�����ȤȸĿͤ�ʬΥ������˯�Ԥ���ĥ�����������ƺƤӳ��ϤǴ���������ĤĤ��ä���ȿ����������פ亹�̤��Ǹ�ȿ�Ф���Ω���ȤäƤ������ȤǤ��Τ��Ƥ��������Τ��ᡢ����ؤνƷ�������̱²���Ф���ִ���Ū����פǤ���ȹͤ���ʿ�³�ư�Ȥ�����ͳ�ư�Ȥ⤤���ΤǤ��ä������˥����饨��ǡ����뿷ʹ�ΰ��̤������˻��Ѥ����ո�����η��ǡ�����λ���Ф��밥��ΰդ�ɽ���줿�ΤǤ��ä���
������������������ܹ�Υѥ��ݡ��Ȥ���ġ����ܿ͡פǤ��ä��������Ĥ�ʶ�����Ӥ����ܿͤΡ����ǹ١פˤ�äơ���Ԥ�ι�ԼԤ�Ͷ�����줿�塢�������줿�Ȥ��ˤ����ä�����Ǥΰ�̾�⤭�Ŀ���ʥХå��ˤȡּ�����Ǥ���פ���������ʿ��Ū�ʥ��㡼�ʥꥹ�Ȥδ֤��������Ӥ����Ȥ⤢�ꡢ����λ���Ф������Τ����������ܤ������ˡ��ܤ�����١פ�ʤƷޤ��뤳�Ȥˤ����Τ��ä���������������ݸ�٤���̳����äƤ����Ϥ��μ��������ΣŹ���Ȥ��Ф��������˹��Ĥ�Ԥä���������������ܤιԤä��ֹ�ȯư�פȤ��Ƥϡ����ơ֤ޤȤ�ʡ��б��Ǥ���Ȥ��ơ�����κ���ɾ���Ȥ����⤤ɾ����������뤳�ȤȤʤä���
˺��ƤϤʤ�ʤ��Τϡ�������¤ϸ�������ī���ͤǤ��ä����Ȥ��Τ�����κ��ɼ��Ԥ����Τʤ��ˡ����������Ӥ������Ƥˤϡ��¤Ϻ������Ф�����ͤδ���ŪϢ�������ä�����ɾ����Ԥ����줿���ʤ��ʤ顢����ˤϤɤ���餽���ü��̱²Ū���طʤΤ���ˡ�����ˤ����Ƽ������¤��줿��˸��������������ꡢ���Τ���˹���Ǥμ����פ������˳�ư�����Ф���������ʤ��ä��Ȥ����Τ��������̾�������ܿ�̾�˲����������������ܹ��Ҥ��ä��ˤ�ؤ�餺�����줬ñ�ʤ�ɽ�ؾ�Υ�����ɥץ쥤�Ǥ��ꡢ������ȤϷ�ɺ��ä���Ρ�Ⱦ��͡פǤ��뤳�Ȥ��Ѥ��ʤ����Ȥ��������ͥåȱ��㤫����³Ū�ʤ���Ƥ������Ȥ������Ǥ��Τ��Ƥ������ޤ�����̳�ʤΥޥ����ʸ��Ȥ��ơ������̾�����ִ������ۡפ���ä�������ư�ȤȤ��ƤΥ֥�å��ꥹ�Ȥˤ�ܤäƤ��ꡢ���⤽������ܹ����ܤȤ��ƤϣĤ�����ݸ�뵤�ʤɤ��餵��ʤ��ä��פ�¿������֤������Ƥ����ΤǤ��롣�Ĥޤ���������ܹˤ����뻦���ˤ����ܹ���ˤ����������������Ǥ���ȿ����ܤ˹ͤ���ͤ����������ΤǤ��롣
�����ʤ��Ȥˡ����������ʩ���Ϥο����������Τ�°����Ǯ���ʿ��ԤǤ��ä����Ȥ��Τ��Ƥ��ơ��˥塼�������Ϥμ�Ԥ�������ϻ����������Ƥ�������θ��Υ�ݡ��Ȥ��͵�����Ƥ��ơ�����С֤������̡פǤ�����ϥ��ꥹ������ȯ�����Ƥ������ºݡ����λ���ΤۤȤܤ꤬�������פ��Ф����褦�ˡ�����λ����ϡ���ʬ�����������Τؤι���Ȥ��Ƽ�����餶������ʤ��ä��ȡ����ν������Τ���������ˡפ��������δ�Ϣ�η����̤��ƥ����Ȥ����ΤǤ��ä���
�Ȥ�������������������Τ�Ԥ���������·���Ƽ�ĥ����Τϡ�����������˿Ƥ����ʤä����륤����ඵ�̤���ǯ�¶ȲȤȤο�̩�ʴط��Ǥ��ꡢ�¤ϰ����������Τ��ä����ꥹ�ȶ��θ�������η����Τ��ä����ܡ����ե��ɤ����ٻ����Τ����������⤿�����Τ��Ȥ����ޤ��Ȥ��䤫�ʱ��⸽�ϤǤϹ����ä��ΤǤ��ä���������ඵ�̤ˤȤäƤϤ���ϥ�����ඵ�ؤι���Ǥ��ä���
�Ĥޤꡢ����ȴؤ�ä��������ȿ������Ρ������ΰ衢���Ĥʤɤϡ����줾�������ä����Ƥ�����ʬ�����ؤι���Ǥ��ä��Ȥޤ���˲�ᤷ���ΤǤ��ä������ʤ������ؤι���ϡ����㡼�ʥꥺ��ؤ�ĩ��Ǥ��ꡢ�����ؤ��Ѥ��̺��̰ռ��Τ⤿�餷����ΤǤ��ꡢ�����̱²�ؤι���Ǥ��ꡢ���ܹ�ؤι���Ǥ��ꡢ����ī���ͤ��Ф����и��Ǥ��ꡢ���������ؤ������ʷٲ����Ǥ��ꡢ�Ϥ��ޤ�������ඵ�ؤι���Ǥ��ä��Τ��ä���
����λ�ϡ��ؤ��Τ��ä��ɤ��ȿ����ɤ����Ρ��ɤο����ΰ衢�ɤζ��Ĥˤ����Ƥ��ħŪ�ʰ�̣����Ĥ��Ȥˤʤä��������Ƽ������ʹ֤ο���������λ�ˤϡְ�̣�פ����ꡢ�ɤ�ˤⶦ�̤ʤΤϡ���D�Ȥ����Ŀͤ��������ȿ��Ȥ�Ʊ��뤹�뤳�ȡפ���δ��äȤ��Ƥ��뤳�Ȥ��ä������������D�Ȥ����Ŀͤ�ĿͤȤ���ª���뤳�Ȥ褦�ȤϤ��ʤ��ä���D�ؤι���ϡ��Ŀͤ˽��������ä�ñ�ʤ���ΤǤ��ꡢ̵��̣�ǡ��Ծ����ʡ��Ա��פȤϡ�ï��פ������ʤ��ä��Τ���
��������Ϥ����Ǥ��롣
��������Ѥʰ���ȤǤ��äơ����д������ߤ��줿������ΣûԤǡ���֤���ä��ä⤦�Ȼפä��Τ��������Ĥˤ������ΰ¥ۥƥ�θ��ؤ��鳰�˽Фơ������ǥ��Х��˲Ф��դ����Ȥ�����㤤�����˼ͻ����줿�Τ��ä����ɤ�������ϣŹ�Ƕػߤ���Ƥ���̩͢�ʤΤ������ϡʤ����ʡˤ�ǡפ����餷�������줬�������Ȥ���Фɤ����D�ξ���Ƚ�ǤϴŤ��ʤäƤ����ΤǤ��ä������¡�����ΰ��Τη�դ���Ϥ������ľ��֤��Ǥ���ۤɤΥ��륳����⸡�Ф��줿�������ˤϹӤ餵�줿���פ���ޤ줿��Τ�ʤ����ݤ��θ��ơ����ܤΥӡ���ζ����ӤȰ��ߤ����Υ����å����Ӥ����Ĥ��ä��������ä�����������⤷�������μ㤤�⾥�ϡ���������ԤǤ��겿�͡ʤʤˤ���ˤǤ��ä����γ�ǧ�ޤǤϡ����Ω�����֤ȵ�Υ����ϤǤ��ʤ��ä������ޤ��Ƥ�Ĥ��ֽ��Ǥ��뤳�Ȥʤɥ��ߥ��ޤ��Τ�ͳ���ʤ��ä��סʤ���ϸ��ä��Τ��ä��ˡ��Ĥޤ����������Ū�ʻ����������տޤ��Ƥ��ʤ��ä��ΤǤ��ä���
�������������ϡ�¿���������Ȥ����Ƥ���Ƥ���ûԹٳ��η�̳�꤫���̾�μ��ͤ�æ��������������ꡢ��餬��ή����������������ȿ������ΤȻפ��롢����Ż���ͽ�𤹤�ĩ�������š�����դ���Ƥ������Ȥ����ꡢ�����夦�ˤ���ٻ����������ʶ�ĥ���֤ˤ��ä��Ȥ������ȤǤ��ä������������Τ褦�������Τ��Ȥϡ�����̡�褬���ܤ���Ƥ���褦�ʥ��֥�����Ƚ�Υ��ݡ��Ŀ�ʹ�ʳ�����ƻ���ʤ��ä��Τǡ������ܤʰ�ή��ʹ���ɤ�Ǥ������Ƥ���»νʽ������ˤ��Τ�ͳ��ʤ��ä���
������������β�Ǯ������ƻ���郎������������������ܤǵ����ä�������륹�ơ����쥹�ȥ��֥ڥåڥ롦�������פ�ŹĹ�ʲ����ͤ��ؽ�˽���Ƶ�����ޤä�����ˡ����Υ쥹�ȥ��������ˤޤä����Ҥ���ʤ��ʤ��ݻ��ֶ�dz���ˤ�ä��㤤á���줽�����Ȥ����˥塼�������ޤä��Τ��ä�������������ʾ����ʥ˥塼�������Ф��Ƥ��ޤ��ۤɡ����ΤҤȤ�ν������㡼�ʥꥹ�Ȥλ�Υ˥塼���ǻ�������ˤʤä��Τǡ�������Ĥλ���ο��ؤˡ��ָĿͤ��ȿ���Ʊ��뤹��פȤ����ʹ֤Ρֿ���Ū�����פȡ��Ҳ�Ūưʪ�Ȥ��ƤΡֿ��θ³��פˤĤ��ơ������ƻפ��֤��ͤϤ��ʤ��ä��ΤǤ��롣
�ʴ���
22:11:22 -
entee -
TrackBacks
2007-05-08
���Ĺ̺�ؽ��ĥ������������٤��ɤ� #2
�ʰ��ѳ��ϡ�
�䥺�ɤ��뤤���ʥݥ�ȥ���ͥڥɥ����˥ƥ���������ϡ������ǡ����ۤȲФ˻Ť���ͤӤȡפ��������ˤϡ��������ɴǯ�ʾ��Τ�������䤵��뤳�Ȥʤ���¸����Ƥ�����פ����ä����ֲФϥ䥺�ɤ�����������ǹԤ��뻳�ξ�ˤ��ꡢ�ȲФβȡɤȤ�Ф졢¿���οͤӤȤ���ˤ����äƤ����פȸ�������Ƥ��롣
�ळ�����������������̤������ʤ��������顼����۲��Υڥ륷������¸���ĤŤ��Ƥ��뤳�Ȥ���𤷤��ǽ�Υ衼���åѿͤǤ��ä���(p. 41)
�ʰ��ѽ�λ��
������ɤ�������ϡ������ɴǯ�ʾ��Τ�������䤵��뤳�Ȥʤ���¸����Ƥ�����פΰ��ä˶ä����⤷��ʤ������ष�����Τ褦�ʵ��Ҥ��褦�Ȥ������ʤ����⤷��ʤ����������⤷�������Ȥ���Ф���Ϥ��βФ��Τ�Τλؤ�������̣�䡢�����ݻ����褦�Ȥ�������ξ�ħ�������Ƥ˻פ����餻���ʤ�����Ǥ��롣
�¤ϡ�3500ǯ�ɤ����Ǥʤ��ʤ����Ϥäơ���䤵��뤳�Ȥʤ���¸����Ƥ���СפȤ����Τ����롣����Ϥ����οȶ��¸�ߤ��롣������������ʸ�����켫�Τ�����Ǥ��롣���ΡֲСפϤ�����ʸ���������ʾ��Ȥ����䤨�뤳�Ȥʤ��ݻ������٤�dz�䤷³�����Ƥ������������Ϥ���䡢�ֻ����ɴǯ�ʾ��Τ������ײФ���䤹���Ȥʤ���¸���뤳��... �ɤ����Ǥʤ����˱���ʹ��ۤȵ��Ϥ���ä�����ʥ��롼�ץ���ʤΤǤ��롣�����Ƥ���Ϥ��Ȥˤ��Ȥ��Ǥ˰���ǯ������³���Ƥ����ǽ���������롣
������ʸ���ݻ��Τ���ε��ϡ��ġ��ͤ�û�������ˤ����Ƹ��̤�ȯŸ������줿��ݻ����줿�ꤷ�Ƥ����ΤǤϤʤ����ġ��ͤϤ��α���ʻ��Ȥ��ǽ�ˤ������Τ���������ô�äƤ�������Ǥ��롣����ϿƤ�ľΩ��Ԥ��Ƥ���Τơ����������ľΩ��Ԥ��褦�ȻҶ������Ϥ��뤯�餤������Ф�����ޤ��˸�����ּҲ��Ū�פʸ��ݤǤ⤢�ꡢ�ޤ������٤���䤹���Ȥʤ��ݻ�����Ƥ�����ʸ����ʸ���䡢�Ф������������椷���ꤹ�뤳�Ȥ�ޤࡢ�����ΰ�������¸��ɬ�פʵ��Ѥ������ˤ�ä�������Ƥ�����ʸ���ȤϤޤ��˰������ʤ����ˤ����Ф���䤹���Ȥʤ����������ʬô��������ʤ��鱫���������̤��٤��Τ�ΤǤ��롣
����������ν��ѤȾ���γؽ��ˤ�äơ��Ф�ݻ����뵻�ѤϤ�����ݻ�����Ф���Ǥʤ��������Ф�˽��ä�������������Ƥ�����
���Ȥˤ��ȡ����βФΰݻ��ε����ˤ�ä������ڤ�ʤ��ä����Ȥ����ä��Τ��⤷��ʤ�������ϡ��Фε��ϳ���ζػ��Ǥ��롣��²���ͤ����Ȥ����ݻ����������Τ���μѿ椭��Τ�ɬ�פʡ��١��Ȥ����Фΰݻ��ĤŤ���ΤǤϤʤ������βФ�����Τߤʤ餺��������ǡ������⤤�ĤǤ�Ƹ���������Ф�����Ǥ����ΤȤ��ơֳ�ȯ�פ��뤳�Ȥ���ñ�˰�������¸�γ��ݰʾ�ˡ�������˭����������ǽ�ˤʤ餷�����Ϥ��ö�ä����Ф�žȬ�ݤζ줷�ߤ�Ф�����ɬ�פ�ʤ�������Ϥ��ĤǤ���Ф����ΤȤʤä���
�����ơ������ñ�˾ö�Ū�ˡֲСפΰݻ���Ф���Ǥʤ����ҤȤĤθĿͤο��������������˰줫��ؤ�ľ����뤳�ȤǤϤʤ�����ö��������ˤ�äƳؤФ줿�ֱ�ΰݻ��פˤĤ��Ƥ��μ���¸�ε��Ѥ伫�����μ��ξ�˿�������ˡ����ʤ��Ѥ߽Ťͤ뤳�Ȥˤ�äƤ��ֿʲ��פ����뤳�Ȥ�ؤ��������ϤĤޤ�Фε��Ϥ�����Ǥ��롣
�������䤹���Ȥʤ��ݻ������ФǤ��ä��Τ����礭���ʤꤹ����Ф�ä��Ʋ��³���ʤ���Фʤ�ʤ��褦�ʴ����ʡ���Сդؤ���Ĺ���뤳�Ȥˤʤ�Τ���
�ץ���ƥ���������˼��Ϥ����ȸ����뤽�Ρ־�����dz�������פϡ����ޤ����ʥ����ʥ�����ξ����α�Ȥʤä����������Ĺ���������ʥ�Ϥ��������Ͼ����������Ȥʤꡢ���ʤ�dz�����ᤷ���������ƿ���ϳ����뤳�ȤΤʤ��ä��ֱ���Ĥ���������ɡפ��ˤ���ˡ��ؤӡ��Ĥ��ˤ����ۤ�ͳ�褷�ʤ���������줿�������Ƥ��α�ϥ����ʥ��ߤ�뤳�Ȥʤ���³���뤳�Ȥ��Ǥ���褦�ˤʤä����˸�������
�Ҳж��̤Ȥ�ƤФ�륾�������������̤ε���α�ϡ����Τ褦�ˤ��Ƴμ¤˺�������ä��Τ������ο��Υ��������������̡ʥѡ��륷���ˤϿ�¿�����Ф���Ƥ��ʤ������ߥ���ɤʤɶϤ��ʾ��Ǩ����������̤��ϰ̤��ĥ���ȤȤ��ƨ���¸�ߤ��Ƥ���Ȥ����������⥤��ɤˤ����ơ�������ȯ�Ż��ȤϾ����ɤΥ��������������̤�ˤ�äƱ��Ĥ���Ƥ���*�Ȥ���������ʥ��������ۤ��ơԲСդ���Ѥ��������Ҳж��̤ϡ���餬�����ˤ����Ƥ⤽��̾�������������ô�äƤ����ΤǤ��롣
* �����ͤ���������Ū�˶�ͻ�ȡʶ��ߤ��ˤʤɤ��ΰ�ˤ��γ�ϩ�Ф����褦�ˡ��ﺹ�̤ξ����ɤ����ҤȤ�����Ū�ˤ��ޤ�ؤ�ꤿ���ʤ��ȹͤ���褦�ʡֱ��줿���Ȥ˽�����������ʤ��ä�����ˡ�����λ�������ˤ��Τ褦�ʥޥ��Υ�ƥ����褯���Ф����Ȥ����褦�ʼҲ�Ū�ʥᥫ�˥���ˤ�äƻ����褦�ʤ��Ȥ�������ɤˤ����륾�������������̤˵����ä��ȸ������Ȥ��Ǥ��뤫�⤷��ʤ���
�䥺�ɤ��뤤���ʥݥ�ȥ���ͥڥɥ����˥ƥ���������ϡ������ǡ����ۤȲФ˻Ť���ͤӤȡפ��������ˤϡ��������ɴǯ�ʾ��Τ�������䤵��뤳�Ȥʤ���¸����Ƥ�����פ����ä����ֲФϥ䥺�ɤ�����������ǹԤ��뻳�ξ�ˤ��ꡢ�ȲФβȡɤȤ�Ф졢¿���οͤӤȤ���ˤ����äƤ����פȸ�������Ƥ��롣
�ळ�����������������̤������ʤ��������顼����۲��Υڥ륷������¸���ĤŤ��Ƥ��뤳�Ȥ���𤷤��ǽ�Υ衼���åѿͤǤ��ä���(p. 41)
�ʰ��ѽ�λ��
������ɤ�������ϡ������ɴǯ�ʾ��Τ�������䤵��뤳�Ȥʤ���¸����Ƥ�����פΰ��ä˶ä����⤷��ʤ������ष�����Τ褦�ʵ��Ҥ��褦�Ȥ������ʤ����⤷��ʤ����������⤷�������Ȥ���Ф���Ϥ��βФ��Τ�Τλؤ�������̣�䡢�����ݻ����褦�Ȥ�������ξ�ħ�������Ƥ˻פ����餻���ʤ�����Ǥ��롣
�¤ϡ�3500ǯ�ɤ����Ǥʤ��ʤ����Ϥäơ���䤵��뤳�Ȥʤ���¸����Ƥ���СפȤ����Τ����롣����Ϥ����οȶ��¸�ߤ��롣������������ʸ�����켫�Τ�����Ǥ��롣���ΡֲСפϤ�����ʸ���������ʾ��Ȥ����䤨�뤳�Ȥʤ��ݻ������٤�dz�䤷³�����Ƥ������������Ϥ���䡢�ֻ����ɴǯ�ʾ��Τ������ײФ���䤹���Ȥʤ���¸���뤳��... �ɤ����Ǥʤ����˱���ʹ��ۤȵ��Ϥ���ä�����ʥ��롼�ץ���ʤΤǤ��롣�����Ƥ���Ϥ��Ȥˤ��Ȥ��Ǥ˰���ǯ������³���Ƥ����ǽ���������롣
������ʸ���ݻ��Τ���ε��ϡ��ġ��ͤ�û�������ˤ����Ƹ��̤�ȯŸ������줿��ݻ����줿�ꤷ�Ƥ����ΤǤϤʤ����ġ��ͤϤ��α���ʻ��Ȥ��ǽ�ˤ������Τ���������ô�äƤ�������Ǥ��롣����ϿƤ�ľΩ��Ԥ��Ƥ���Τơ����������ľΩ��Ԥ��褦�ȻҶ������Ϥ��뤯�餤������Ф�����ޤ��˸�����ּҲ��Ū�פʸ��ݤǤ⤢�ꡢ�ޤ������٤���䤹���Ȥʤ��ݻ�����Ƥ�����ʸ����ʸ���䡢�Ф������������椷���ꤹ�뤳�Ȥ�ޤࡢ�����ΰ�������¸��ɬ�פʵ��Ѥ������ˤ�ä�������Ƥ�����ʸ���ȤϤޤ��˰������ʤ����ˤ����Ф���䤹���Ȥʤ����������ʬô��������ʤ��鱫���������̤��٤��Τ�ΤǤ��롣
����������ν��ѤȾ���γؽ��ˤ�äơ��Ф�ݻ����뵻�ѤϤ�����ݻ�����Ф���Ǥʤ��������Ф�˽��ä�������������Ƥ�����
���Ȥˤ��ȡ����βФΰݻ��ε����ˤ�ä������ڤ�ʤ��ä����Ȥ����ä��Τ��⤷��ʤ�������ϡ��Фε��ϳ���ζػ��Ǥ��롣��²���ͤ����Ȥ����ݻ����������Τ���μѿ椭��Τ�ɬ�פʡ��١��Ȥ����Фΰݻ��ĤŤ���ΤǤϤʤ������βФ�����Τߤʤ餺��������ǡ������⤤�ĤǤ�Ƹ���������Ф�����Ǥ����ΤȤ��ơֳ�ȯ�פ��뤳�Ȥ���ñ�˰�������¸�γ��ݰʾ�ˡ�������˭����������ǽ�ˤʤ餷�����Ϥ��ö�ä����Ф�žȬ�ݤζ줷�ߤ�Ф�����ɬ�פ�ʤ�������Ϥ��ĤǤ���Ф����ΤȤʤä���
�����ơ������ñ�˾ö�Ū�ˡֲСפΰݻ���Ф���Ǥʤ����ҤȤĤθĿͤο��������������˰줫��ؤ�ľ����뤳�ȤǤϤʤ�����ö��������ˤ�äƳؤФ줿�ֱ�ΰݻ��פˤĤ��Ƥ��μ���¸�ε��Ѥ伫�����μ��ξ�˿�������ˡ����ʤ��Ѥ߽Ťͤ뤳�Ȥˤ�äƤ��ֿʲ��פ����뤳�Ȥ�ؤ��������ϤĤޤ�Фε��Ϥ�����Ǥ��롣
�������䤹���Ȥʤ��ݻ������ФǤ��ä��Τ����礭���ʤꤹ����Ф�ä��Ʋ��³���ʤ���Фʤ�ʤ��褦�ʴ����ʡ���Сդؤ���Ĺ���뤳�Ȥˤʤ�Τ���
�ץ���ƥ���������˼��Ϥ����ȸ����뤽�Ρ־�����dz�������פϡ����ޤ����ʥ����ʥ�����ξ����α�Ȥʤä����������Ĺ���������ʥ�Ϥ��������Ͼ����������Ȥʤꡢ���ʤ�dz�����ᤷ���������ƿ���ϳ����뤳�ȤΤʤ��ä��ֱ���Ĥ���������ɡפ��ˤ���ˡ��ؤӡ��Ĥ��ˤ����ۤ�ͳ�褷�ʤ���������줿�������Ƥ��α�ϥ����ʥ��ߤ�뤳�Ȥʤ���³���뤳�Ȥ��Ǥ���褦�ˤʤä����˸�������
�Ҳж��̤Ȥ�ƤФ�륾�������������̤ε���α�ϡ����Τ褦�ˤ��Ƴμ¤˺�������ä��Τ������ο��Υ��������������̡ʥѡ��륷���ˤϿ�¿�����Ф���Ƥ��ʤ������ߥ���ɤʤɶϤ��ʾ��Ǩ����������̤��ϰ̤��ĥ���ȤȤ��ƨ���¸�ߤ��Ƥ���Ȥ����������⥤��ɤˤ����ơ�������ȯ�Ż��ȤϾ����ɤΥ��������������̤�ˤ�äƱ��Ĥ���Ƥ���*�Ȥ���������ʥ��������ۤ��ơԲСդ���Ѥ��������Ҳж��̤ϡ���餬�����ˤ����Ƥ⤽��̾�������������ô�äƤ����ΤǤ��롣
* �����ͤ���������Ū�˶�ͻ�ȡʶ��ߤ��ˤʤɤ��ΰ�ˤ��γ�ϩ�Ф����褦�ˡ��ﺹ�̤ξ����ɤ����ҤȤ�����Ū�ˤ��ޤ�ؤ�ꤿ���ʤ��ȹͤ���褦�ʡֱ��줿���Ȥ˽�����������ʤ��ä�����ˡ�����λ�������ˤ��Τ褦�ʥޥ��Υ�ƥ����褯���Ф����Ȥ����褦�ʼҲ�Ū�ʥᥫ�˥���ˤ�äƻ����褦�ʤ��Ȥ�������ɤˤ����륾�������������̤˵����ä��ȸ������Ȥ��Ǥ��뤫�⤷��ʤ���
21:28:13 -
entee -
TrackBacks
2006-06-01
���褤��Ϥޤä��������ò����������ʾ١�
�����ò������ΰ���������»�����������--NTT�ȹ��������������
���ò����������ʾٻ��äΤ�Ͷ��
�ֲ������פȤ����äƻ�ʧ���������줿�Τˡ����ò���λ��ˤ�ʧ���ᤷ���ʤ��Τϡ�����Ū���Ѥ��ä��ȤϻפäƤ�������衣������NTT������Ȥ�ʤ����Ǥ⡢���äȲ��ʤ��ǻ��äƤ��������äȤ��λ����ԤäƤ�������衣���ä��륾�������ʾ١�
���ò����������ʾٻ��äΤ�Ͷ��
�ֲ������פȤ����äƻ�ʧ���������줿�Τˡ����ò���λ��ˤ�ʧ���ᤷ���ʤ��Τϡ�����Ū���Ѥ��ä��ȤϻפäƤ�������衣������NTT������Ȥ�ʤ����Ǥ⡢���äȲ��ʤ��ǻ��äƤ��������äȤ��λ����ԤäƤ�������衣���ä��륾�������ʾ١�
11:32:55 -
entee -
TrackBacks
2006-05-24
�������ɿ������Ƚ
�����ָ����ȱ����줿���פȼ����Ū�ķ����� [14]
�ȣ��ɤλ�����ָ���Ū�������סʲ���
���������
�� ŷ�Ȥȡֿ������פδ֤ˤ����Ϣ
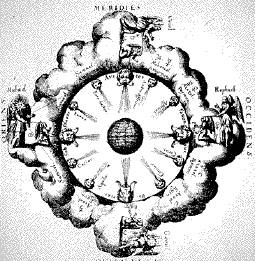

����̩���ˤ�����ֻ�ŷ���פϡ������ᥭ�ꥹ�ȶ�ʸ���ʸ�̩�ˤϥ�����ඵ������ޤ�ˤˤ����Ƥϡֻ���ŷ�ȡפ���������*���������⥤��ɡ��衼���åѸ�Ȥ����������������������������ѤȰ��פ뤫�Τ褦�ˡ������Ĥ���ʩ��������ʩ�����̤����������줿�ҥ�š�ʸ������ο���Ū�������ˤȡ����ꥹ�ȶ��������Ȥ����ݻ�����Ƥ����������δ֤ˤ������ζ�������¸�ߤ��롣




����ʶ���������������������ܻ��ˤλ�ŷ��������ѻ��塿��������
���������ŷ����Ĺŷ������ŷ��¿ʹŷ
* ��ŷ���Ȼ���ŷ�ȴ֤β�¬Ū�Ʊ�����
������ŷ��¿ʹŷ�ʥ��������������ʡˡ������μ�������������㡢����˶��ϡΥ��ꥨ���
��Ĺŷ�ʥӥ롼�����ˡ������μ����������Ĺ�����Υ�ե������
����ŷ�ʥɥ�顼����ȥ�ˡ������μ���������˷��Υߥϥ����
����ŷ�ʥӥ롼�ѡ�������ˡ������μ����������ɮ������˶�ŵ�Υ��֥ꥨ���

����ŷ�� (Four Archangels) �ȸ����С��̾ŷ�ȥߥϥ��롢ŷ�ȥ��֥ꥨ�롢ŷ�ȥ�ե����롢ŷ�ȥ�ꥨ��ʥ��ꥨ��ˤ�ؤ����ߥϥ���ȥ��֥ꥨ��ϤȤ�櫓������äˤ����ƴ��٤��о줹��Τǹ����Ƥ��ޤ�Ƥ��롣������ŷ�Ȥϡ����ꥹ�ȶ�ʸ���ˤ����ơ�������������Ƚ�������ǻ�����ݻ������������Сʥڥ��ˤ������Ƥ��뤫�Τ褦��������Ƥ������Ȥ�櫓¾����ŷ�Ȥ���٤�¿���о줹��ΤǤ����о�Ū�ʸ��줬��Ω�äƴ�������ΤǤ��롣����ޥꥢ�Τ�Ȥ�ˬ����۹��Τ�ŷ�ȥ��֥ꥨ��ϡ�¿���ξ�硢�ؤɽ����ȸ��ޤ����Ф���ν��¤���ͥ��������ä��������Τ��Ф���ŷ�ȥߥϥ���ϡ�¿���ξ�硢ζ����Ƕ��ɤ��ˤ����������롢�ˤ����˽������Ū�ʿ��Ƿ����̤������ˤˤ��������˸���롣����С�Ʈ��Ȼ��ۤ�ŷ�ȡפǤ��롣


�����Х륫��Ⱦ��Υ�����������ߥ�����������֥ꥨ��ס����ο��Ǥ��鴶�����뤳�ȤȤ����餫�˥ߥϥ���ȥ��֥ꥨ�뤬�˽��Ȥ���������Ƥ��뤳�ȤǤ��ꡢ����Ф��꤫�����������شط��ˤ��뤫�Τ褦�ʰ��ݤ����������ΤǤ��롣���������衧Balkan Icons�������ܥåƥ������ˤΡ�BOTTICINI, Francesco / b.1446, Firenze, d. 1497, Firenze�ˤ��ֻ��ͤ���ŷ�Ȥȥȥӥ���: The Three Archangels with Tobias���ˤϥ�ꥨ����������ŷ�Ȥ�������Ƥ��뤬������ˤ����Ƥ�ߥϥ���ȥ��֥ꥨ�����������������Ū���о�Ū�Ǥ��롣�Τ����Ǥϡ����Сʥڥ��ˤ�ŷ�Ȥ���UK�ʥ��졼�ȥ֥�ƥ���̥��������Ϣ�粦��The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland�ˤˤ�������פ����粦���ʤ�������ɲ���ȥ����åȥ��ɲ���˸Ʊ�����Ȥ������Ȥ����Ƥ�������
ŷ�ȥ�ե����� (Archangel Raphael) �ϡ������������ˤϤ���̾�����������ڤ��줺�����������Ƶ���Ρ֥ȥӥȽ�פˤ����Ƽ��פ��о�ԤȤ��Ƥε��Ҥ�����ΤߤǤ��롣��������ե����������Ū�˥��ǥ�α�������Ƥ���Ȥ�������̿���ڡפμ��ԤȤ����Τ��Ƥ��ꡢ�������Ϥ����ŷ�ȤȤ���¦�̤���ġʤޤ�����ϥ�ʡ����ˤ����Ƹ��ڤ����ŷ�Ȥ���ե�����Ǥ���Ȥ�����⤬¸�ߤ���ˡ�
ŷ�ȥ�ꥨ�� (Archangel Uriel) �ϡ��Хӥ��������˥��������������Ω����ŷ�ȤǤ��ꡢ��ŵ�֥ڥƥ��ۼ�Ͽ�פˤ����ƺ�ͤ�ʱ�ζȲФǾƤ��������ŷ�ȡפǤ����ʩ������ˡ���ۤˤ������о줹���Ϲ���Ĩȳ�ԡ�����: Yama�פ�����̤����ˡ�����ޤǤ���ŷ�� (Archangel)��̾���ǸƤФ��ŷ�Ȥ����Ǥλ�ŷ�Ȥ����Ǥ��ä�����ꥨ��ȤĤʤ������ľ�ħ�ϡ����ۤ���Ψ�ԡפ����ơֿ��δ��פǤ��ꡢ����̾���ΰ�̣�����α� (Flame of God)�������ʲСʸ��ˤȤδ�Ϣ�����롣��ꥨ��ϱ�η�����äƥ��ǥ�����Ω�ĥ���ӥ����ŷ�ȡˤǤ��ꡢ����쥨�Υ���פˤ����������������Ĥȶ��ݤ�ʤ��ŷ�ȤǤ���Ȥ�ͤ����Ƥ��롣�������������ε����ˤ����ƥ�ꥨ��˴ؤ��ƤȤ�櫓���뤵���٤����ϡ�724ǯ�Υ��������Ĥˤ����ƶ��ĥ����ꥢ���ˤ�äơ���ŷ�Ȥ�������줿�פ��ȤǤ��롣����ˤ�̱�֤Dz�Ǯ��������ŷ�ȿ��Ĥ˥֥졼�����뤿�ᡢ�Ȥ�������Ū�տޤ���ä�����СֿͰ�Ū����ŷ�פǤ��ä������Τ褦�Ǥ��뤬������䶵�����ˤ����븶�餫��λ���ŷ�ȥߥϥ��롢��ե����롢���֥ꥨ���������ŷ�ȤȤ��Ʋ�¸�������ΰ�����ꥨ����̲�����Ȥ�����ħŪ�ʰ�̣�礤���������������ΤǤ��롣�ֻͼԤ���ˤ����뺹���Զ��פȤ������ϡ���ˤޤ���������Ǥ�������
�� ����ʡ�����: Evangelists�ȡֿ�������
���ߤΥ��ꥹ�ȶ��η�ŵ���뿷������κǽ�˷Ǻܤ���Ƥ���ʡ����ϡ��Ϳͤΰۤʤ�ʡ����Ȥˤ�����Ȥ����κۤ�ΤäƤ��롣������ʡ����Ȥ��Ϳ�����Ƥ�����¤ˤ������Τ��Ȥʤ����붵Ūư�������ࡣ
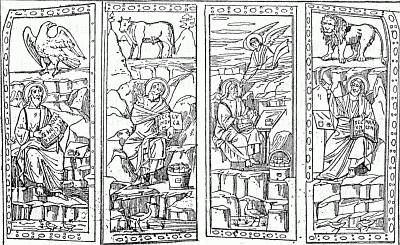
���������衧symbols of the evangelists
ʡ����Ȥ�ɽ����evangelist�ʱѡ�, evangelista�ʥ��, evangelistes�ʥ��ˡɤȤ�����ˤ�angelos�����ʤ���֥�å��㡼�����μԡפΰ�̣�����롣���ꥷ����Ρ�to announce�ɤ�������ư��ϡ�angellein�ɤȤ����줬���Ƥ�졢���θ��ä���ˡֻȤ�����å��㡼�פΰ�̣�����äƤ���ΤǤ��롣��ʡ����ȡ����������ꥹ�ȡפˤϡ�bringer of good news: ʡ�����ɤ��˥塼���ˤ�⤿�餹��Ρס�eu (good) + angellein (announcer) �ϤȤ�����¤����äƤ��롣��ŷ�ȡפϡ��������ܸ줫��ϸ츻��䤷�̤뤳�Ȥ����ΤǤ��뤬����������ˤ����Ƥϡ���ŷ�λȤ��פȤ������ϡ���å��㡼�ʸ��դ��α��ӿ͡ˤΰ�̣�礤��̤���˿�ǻ���Ĥ��Ƥ��롣������ˤ��Ƥ��ʡ����ȡפ��������evangelist: ev-angel-ist�ɤˤϡ�angel�ɤ����Τ�����Ƥ���Τ�����뤳�Ȥ��Ǥ��롣
���ߤο�������ˡ�ʡ����פ��ͤ�����Ƥ��뤳�Ȥˤϡ��ֻͿ͡פ�ʡ����Ȥ����뤳�ȡ��Ҥ��ƤϤ����ˤϡֻ���ŷ�ȡפȤθƱ����ΰż����տޤ���Ƥ��뤳�Ȥ�פ��Ф�ɬ�פ����롣

���ǡ��ֻͿͤ�ʡ����ȡס�Book of Kells, ca. 800��
�͡���ҡ���������ξ�ħ�Ϥ��줾��ʡ����ȥޥ������ޥ륳���륫����ϥͤ��������롣
evangelist
c.1175, "Matthew, Mark, Luke or John," from L.L. evangelista, from Gk. evangelistes "preacher of the gospel," lit. "bringer of good news," from evangelizesthai "bring good news," from eu- "good" + angellein "announce," from angelos "messenger." In early Gk. Christian texts, the word was used of the four supposed authors of the narrative gospels. Meaning "itinerant preacher" was another early Church usage, revived in M.E. (1382). Evangelical as a school or branch of Protestantism is from 1747.
���λͿͤΥ��������ꥹ�ȡ�ʡ����ȡˤǤ���ޥ���: Matthew���ޥ륳: Mark���륫: Luke����ϥ�: John���ȻͿͤ���ŷ�� (Michael, Gabriel, Rafael, Uriel) �Ȥδ֤�¸����Ʊ��ط��ϡ������ƥꥺ��������ˤ����ƽ�ʬ���μ��Ȥ��ƶ�ͭ�����Ȥ����Ǥ⤢�롣�����ˤ������ʡ����Ȼ���ŷ�ȤȤδ֤ˤ��붽̣�����������ˤĤ��Ƹ����С֥�ϥͤˤ��ʡ����פˤĤ��Ƹ��ڤ��ʤ��櫓�ˤϤ����ʤ����֥�ϥͤˤ��ʡ����פϡ��Ȥ�櫓�����ο�������˼�Ͽ����Ƥ���ʡ�����桢���Ū���Ρ��������ۤαƶ���ǻ�������뤳�ȤϤ��Ǥ��Τ��Ƥ��뤳�ȤǤ��롣�������פ���ꤹ�륭�ꥹ�ȶ���Ω����ν���ˤ����ơ����Ǥˤ��ޤ��ޤ�ʡ���ְ�üŪ�פȤ��ơֵ�ŵ�ʳ�ŵ�ˡ�����פ���Ȥ��ƽ��������˲����줿��ǡ����Ρְ�üŪ�פ�ʡ�������������˻Ĥä����Ȥϡ������Ȥ��Ƥ����Τ�Τ���Ū�����в�������ڤ�����֥�ϥͤ�ʡ����פȤ����κۤ��̤����Ȥ߹��ޤ줿�ȹͤ���;�Ϥ����롣
����ŷ�Ȥˤ����ơ���ŷ�ȡפȤ���ǧ�Τ���뤳�Ȥˤʤä���ꥨ�뤬���������ʤˤ�ؤ�餺����ŷ�ȤΥ��롼�ספ�����Ȥ߹��ޤ�Ƥ������ϡ�ñ�˶���Ū�ʸƱ���������Ȥ������ϡ��ޤ��˻���ʡ���������ȹ����ˤ�ȿ�Ǥ��褦�Ȥ����տޤ����ä��Ȼ�����κ�����ΤǤ��롣
�� ŷ�ȥߥϥ���������硼���δ֤˴Ѥ���������ʺ��¡�
����Ū���ʤˤ�äƼ��夲���뤢�����Ϸ������ۤʤ�������ä���Ĥκ��ʤδ֤˶��̤��Ƹ�����Ȥ���С����줬�տޤ��줿��ΤǤ����ǽ���äƤߤ���ͤ����롣�㤨�С��֤���ͦ�Ԥ���Ū��¸�ߡ�ζ�ˤ�Ĩ�餷���פȤ�����ब����Ȥ��ơ�Ʊ�ͤ����ä����Ѻ��ʤ����̤ο�ʪ�������Ƥ���פȤ���С������ˤ���ͤΰۤʤ��ʪ��Ʊ�����Ȥ���������ǽ�����ʤ��������뤳�Ȥ���������ͤο�ʪ���ۤʤ�̾�����Τ��Ƥ����ǽ������Ĥ��ͤ����롣�ʤ�����ˤ��Ƥ⤢��������夲��ݡ����ѲȤ�������Ȥ����̤ο�ʪ�������������褦�ʾ��̤���夲���ǽ���⤢��ΤǤ��롣��


����
����ζ��ɤ�������ŷ�ȥߥϥ���: The Archangel Michael Piercing the Dragon
Martin Schongauer (German, c.1450 - 1491) c. 1475@ The Cleveland Museum of Art
����ζ�������Ͼ���������륰�ʥ���ȡ����硼����Icon with a depiction of Saint George on horseback slaying the dragon. By the painter Emmanuel Tzanes (1660-1680) @ Byzantine and Post-Byzantine Collection of Chania
���͡�Michael (archangel)@Wikipedia
���¡����Ρ�ͦ�Ԥ���Ū��¸�ߡ�ζ�ˤ�Ĩ�餷���פȤ������γ���ϡ���Ĥΰۤʤ�̾�����Τ�줿ͦ�Ԥγ��Ȥ��ƺ����Τ��Ƥ��롣���Ρ�ζ�ϻ�������: dragon-slaying legend�פΤҤȤĤ�ŷ�ȥߥϥ���Τ�ΤǤ��ꡢ�⤦�ҤȤĤ������硼���Τ�ΤǤ��롣�����������Ƥ��������硼�����������Ω�����ϣ��������ȹͤ����Ƥ��ꡢ�����⤽����Ω���Ͼ��������Ǥ���餷���������������硼���ϥ����ɤΤߤʤ餺�������ˤ����Ƥ������ͤȤ���ª�����Ƥ���Τǡ������ɤȤ�ľ�ܤδ�Ϣ���������Ǥ��롣�������ʤ��顢��̣�������Ȥˡ������ɤ��ºݤ˥������륺����襤���������ۤ������¤ȴ�Ϣ�Ť������ϤǤ�����Ƥ��뤳�Ȥ���¤Ǥ��롣�º����ꡢ�������륺������Ū�˹��̱²�ˤξ�ħ�Ȥ��ơ�ζ: Pendragon�פ�ħ����äƤ���ΤǤ��롣

�����ɲ����ɥ�ɣ����μ����� (1465ǯ) ����¤���줿��ߤˤϡ�ζ����Ȳ�������ԤȤ�����ŷ�ȥߥϥ���Ȼפ���������ޤ�Ƥ���Ȥ����������ɤˤ����Ƥ������硼������ŷ�ȥߥϥ����ξ�������äƿ���ɽ�������Ȥ��Ƽ��夲���롣
���͡���angel�� @ Etymology Dictionary
ζ�Ȥ����ΤϤ����ε�����������ħ�Ǥ⤢�ꡢ�¤ϡֻ��λϤ�פ������äƹԤʤ����ζ�Ȥ����༣��ʪ��פϡ��Ť������ι����ʤʤ����ֺǸŤε����ס���ˤλϤޤ�ˤȴ�Ϣ���Ƥ��롣���ʤ���������Ϸ�Ū���̤ϡ����ߤ���������줬�Τ�褦���������餷����餫�ν��פ�ȯü��ɽ�����ä�����о줹�뷹���ˤ��롣��������ܤο��ä���ˤ�Ȭ����ؤȤ�����༣�����ܺ�Ƿ��̿�η��Ǹ��Ф���뤷���ե�ᥤ������˱ƶ���������⡼�ĥ���Ȥˤ�äƽ줿���ڥ����ū: Die Zauberfloete �٤���Ǥ�����ζ���臘�ʽ����롩�˾��̤����ȡ���Υ����ץ˥ȤʤäƤ��뤳�Ȥ�������ΤäƤ��롣�����硼�����༣����ζ�⡢����Ҳ�ʹ�ˤ����ꥹ�ȶ������ˤʤä�������ͳ�ȴ�Ϣ�Ť����İ�����Ƥ��롣�����硼���ϡ�ζ�λ�����̱���Υ��ꥹ�ȶ��ؤβ����ξ��Ȥ����ΤǤ��롣���ʤ���ֳ���줷���ζ���༣���Ƥ���������ˡ����ϥ��ꥹ�ȶ��̤˲�������פ������硼�������ä��ΤǤ��ä���
����ɽ�����ä��᤻�С������ɤξ�ħ�Ǥ��������硼���ȡ�����ŷ�Ȥΰ��ŷ�ȥߥϥ���δ֤˴Ѥ��볨��ɽ����ζ������ϡ��ؤɰտޤ��줿��ΤǤϤʤ����Ȼפ������Τ�ΤǤ��롣�ޤ��������硼���Ϥ�������ŷ�ȥߥϥ���λѤ��Ϥ�����ΤȤ��Ƹ���롣������ζ���������������Ȥ���Ǥ��ꡢζ�ο��Τξ�˾��ʤ��뤤��ñ�˾���������������Ĥ����ζ�ξ��Ω�Ƥ褦�Ȥ�����̤ʤΤǤ��롣���ΤۤȤ�ɺ��Ū�Ȥ���������ʤ�褦����ԤΡֺ�Ʊ�פ�ɽ����Ρֺ��¡פϡ��ष�������硼���Ǿ�ħ����륤���ɤ������ʤ��Ȥ����ŷ�������ŷ�ȥߥϥ��������̤��������Ȥ�տޤ����ʰż����褦�Ȥ��Ƥ���ˤȹͤ��뤳�Ȥ��Ǥ��롣�⤷�������Ȥ���С������ɤξ�ħ�Ǥ��������硼���ϡ���ŷ�ȥߥϥ���˴�Ϣ�դ�������Ƥ��ꡢ����Ū�˥����ɤ���ŷ�ȥߥϥ���δ֤˸Ʊ�����������ɤ��ΤǤ��롣
ζ��Ʈ���������Ȥ�����������Ƥ����Τˡ�����륯�ꥢ�ꥹ (Saint Mercurialis: ca. 359-406) �Ȥ�����ʪ�����롣����������硼���ۤɹ����Τ��Ƥ��ʤ��褦�Ǥ��뤬�������ꥢ�Υ��ߥꥢ����ޡ��˥㸩�ե����Ԥκǽ�λʶ��Ȥ�����ʪ�Ǥ��롣���ܤ��٤��ϡ����ο�ʪ��̾���֥�륯�ꥢ�ꥹ�פ������֥�륯�ꥦ��: Mercurius�פ��ʤ���������ä���å��㡼���ޡ������פ�פ碌���ΤʤΤǤ��롣�������ͤ����Ū���ϡ�Į��ζ������Ȥ��������硼���Ȥۤ�Ʊ���Τ�ΤǤ��ꡢ̾��Ū�ˤϡ�ŷ�ȡפȤĤʤ��꤬����������ŷ�ȥߥϥ����Ʊ��뤬��ǽ�ʤΤǤ��롣
�ޡ������Ϥ�Ȥ�ȥ��ꥷ����Hermes������������˥����ޤο��Ȥʤ뤬����ƥ��Ρ�merx�ɡ��Ѹ�Ρ�merchandise, commerce�ɡ��̾��Ⱦ���ˤȴ�Ϣ�����롣����ˡ��ޡ������ϥ����ǥ��� (Odhinn/Odin, Woden/Wotan) �Ȥδ�Ϣ�ˤ��콵�Τ����ǡֿ������פȶ�����Ϣ������ȸ����Ƥ��롣���ڥ����ˤ����ƿ�������mi?rcoles�ǡ�����ϥ����ޤο��ޡ�����������Ƥ��롣���ܸ�ˤ����Ƥϡֿ��פ�ֿ����פʤɤ�������Ƥ���Mercury�Ǥ��뤬�������ˤ����Ƥ�������ϡֿ������פȤʤ����Ǥ��롣�ޡ������ˤ��Ƥ��ŷ�ȡפˤ��Ƥ⡢���Τ�����⤬�ޤ��ˡ��裴��������Ū�������פλ�����ʴ������Ȥ�ħ�����������ΤǤ��롣
���͡�
��Saint Mercurialis�� @ Wikipedia
Mercury (mythology) @ Wikipedia
�� �Ĥ���줿�����ȡֿ�������
���륳��ƥ����Ȳ��ˤ����ơ��ֿ������פ����������̡פ��ʤ�����������פ�ɽ���Ȥ�����ħ������Τۤ���ʸΧŪ�ʡ���«���פ����롣��ŷ���Τ��줾�줬���������̤μ����Ǥ���褦�ˡ�������Ͷ���ʬ�䤷��ª����Ȥ����ͤ����ϡ������ζ����μ����������ס��̤θ���Ρ����ͽáפ�¸�ߤˤ�äƤ�ɽ������Ƥ���������Ϥ��줾����ġ��֡����פο������Ƥ����Ƥ⤤�롣
�������Ū���ΰ衢�Ȥ�櫓����¾�Ԥ���֤Ƥ��Ƥ�����Τ褦�ʶ��ˤ����ơ����λͶ����������Ȥ����ΤϤȤ�櫓�ռ������褦�Ǥ��롣����������С������ϰ�ˤ����볤�ˤ�äƸ��ꤵ�줿������Ū�������������������֤���Х����Ǵ����������ҤȤĤ�������ɽħ���Ƥ���פȹͤ��뷹���Ȥ��Ƹ����ΤǤ��롣���ʤ���衼���åѤˤ����Ƥ⡢�������Ĥβ�������Ω���ʤ���Фʤ�ʤ��Ȥ������Ȥ⡢�ޤ��ʸ��������ˤ�ä�ʻ������褦�Ȥ������Ρ˥�������ɼ��Τ����Ĥ��ΰ褫��ʤäƤ���*���Ȥˤ⡢���������դ��������ͤ����롣���������ܤ��ܽ����彣�����̳�ƻ�λͤĤ��礭���礫��ʤꡢ���Τ����ΤҤȤĤˤϡֻ�פȤ����ͤĤι������礬���ꡢ�����ϡʤʤ������ϡˤȤ��Ƥε�ǽ��̤����Ƥ���Ȥ����϶�̣�����ΤǤ��롣
������������ٹ�˥�������ɤ�ʻ����Ťä��Τ⡢������ڤ�ͤĤβ���ˤ�äƴ���������Ȥ�����ħ�������Ϥ�Ư������Τȸ��뤳�Ȥ������ΤǤ��롣�ºݤϥ�����������Τ�ʻ�礹�뤳�Ȥ�Ŭ�鷺����������ɤ����� (Northern Ireland) ������̵������������λ��۲����֤������Ǥ��롣
�� �ѹ��ŷ�Ȥδ֤ˤ���ż�
�֥�ƥ����England���Ϥϡ�����Ū��Anglia�ʥ��ꥢ�ˤȤ�ƤФ�롣Anglo-Saxon�ʥ����������ˤȸƤФ��̱²������̾�ΤΡ�Angl-�פθ촴�Ϥ������Anglia��Ʊ���츻������Ƥ��ꡢ���Ρ�Angl-�פ�ɽ������Τ�����ŷ�ȡפ�Angel��פ碌��촴�Ǥ⤢�롣�����Τ��Ȥʤ��顢Anglia�ϡ֥����ͤ��ϡפʤΤǤ��롣�ޤ��űѸ�Ǥϡ�ŷ�ȡפϡ���engel�ɤȥ��ڥ뤵�줿���������äơ�England��Engel Land�ȹͤ��뤳�Ȥ��Ǥ��롣���ޤ깭�����Τ��Ƥ��ʤ����Ȥ�����England��Anglia���ŷ�Ȥ��ϡפΰż���ǻ��������̾�Ȥ������Ȥˤʤ롣
�⤷�����Ρ�ŷ�ȡפξ�ħŪ�Ź��ѹ� (the UK) ���μ¤˻��äƤ���*�Ȥ���С���˵��Ҥ���褦�ˡ��������Τ����Τޤޡֿ������פȤ�ǻ���ʤĤʤ����ڤ��̤ΰ���Ȥʤ�ΤǤ��롣
* �������ȥա����������ե����Τ������붵���ζ����Dz���ʡإȥꥳ�����롦��٤ˤ����ơ�����������ι��Ϣ���᤹���̤����ˤ��о줹�뤬�������ˤϥߥ��磻 (Mikolaj: Michael�Υݡ����ɸ�ˤȸ��������������ȺƲ��̤������Ȥ�����ϥ֥�å�����֤ǥ֥�å���ץ쥤���Ƥ���ΤǤ��롣�����ˤϥߥ��磻���ֻȤ���ŷ�ȡפǤ���Ȥ����ż���ޤޤ��Ƥ��뤳�Ȥ����餫�����֥�å����Ȥ�櫓�ѹ�ˤ����������ƥݥԥ�顼�ʿ»ΤΥ����ɡʥȥ��ס˥�����Ǥ��ꡢ�ͿͤΥץ쥤�䡼���������Υơ��֥��Ϥ�ǹԤʤ�ʣ���ʥ롼�����ä���ĤΥ�����Ǥ��롣
�ֱѹ�ŷ�Ȥ��ϡɤǤ���פȤ���Ź�ϡ�����Ū��å������Ȥ��Ʊѹ�ͤ�����ǰ��Ѥ��륨�ԥ����ɤ������Ǥ��ꡢ�֤ۤȤ�ɼ�����ʤ����������˲�����˼¤Ȥ��Ƥ���줬���Υ������˰��ꤹ�뤳�Ȥ��Ǥ��ʤ��ΤϤ������Ǥ�ޤǤ�ʤ������������Τ褦��������¸�ߤ��뤳�ȼ��Τˤ����Ϥ��ξ�ħŪ��̣�礤�ΰ����ǻ�٤���֤ߤ�ΤǤ��롣������Ф������Ʊ�͡��˼¤ˤ������ͤ�����Ȥ����ͤ����ˤ⡢���פʡ�ħ�դȤ��Ƶ�ǽ�����Τ��˼¤ˤ�����¸������ΤǤ���Ȥ����ͤ����ˤ⡢���Τ�����ˤ������Ϳ���ʤ����ɤΤ褦�ʿ��ä�����������˸��������褦�Ȥ���Τ����Ȥ����տޤ�ǯ���Ķ����̱²�γ��̤����ϡ�������̵�ռ���ƴ�ݤ���ˡ������ԤˤȤäơ���������ͤ����뵷�ס������ο͡��ˤȤäơֿ����٤��뵷�פȤ��Ƥβ��ͤ����뤫��Ǥ��롣�����ơ��ɤΤ褦�ʤ��Ȥ�־�ħŪ���¡פȤ������������Τ����Ȥ��������ԥ��롼�פ�����蘆�줿��̿�ʱ�̿���ϡˤ⡢������ʬ������ΤǤ��롣
�ѹ�˴ؤ��뤽�������Ȥϡ�������ˡ�����쥴��������祰�쥴��ˤΥ֥�ƥ���ؤΥ��ꥹ�ȶ��۶���ư�˴ؤ����������Ȥ��ƻĤäƤ��롣���쥴�������ˡ���̤߰�����590-604ǯ�����顢�����������飷������Ƭ���̤�������Ȥ������Ȥˤʤ롣�ब�����ޤˤƥ����ɽпȤμ�Ԥȱڸ������ݤˡ�Not Angles, but Angels (Non Angli, sed Angeli): ����ͤɤ�������ŷ�Ȥ��Τ�Τ��פȶä�ɾ�����Ȥ����Τ����θ��������Ǥ��롣���٤�����褦�ˡ����줬�˼¤Ǥ��ä��Τ��ɤ����Ȥ����Τϡ���Ū�ʽ��������������ʤ������Τ褦�ʥ��ԥ����ɤ����ä��Ȥ������Ȥ������褦�Ȥ���ѹ�͡ʤ���ˤϲ������ꥹ�ȶ��̤����ˤβ��ռ�Ū��Ķ�ռ�Ū�ˤʡ��ʲ�ɤ��������פʤΤǤ��롣���ʤ��Ȥ⡢���쥴������ȥ������۶����ڤäƤ��ڤ��ä��ʤ��˼¤Ǥ��äơ����Τ褦�˶ä�ɾ�����Τ�ȼ�äƥ��쥴������������������ƥ��̥��ΰ۶��̤��ϥ����ɤؤ��ɸ�����Ƥ���ΤǤ��롣���������̤Ǽ�����ʤ��ֻ˼¤��륨�ԥ����ɡפϡ���꿮�����ι⤤�˼¤η�֤��֤����ΤǤ��롣
�ޤ��ѹ����ɽ������ͥ���ʥ������եȤ�����Ah, Britain, land of angels!: �����֥�ƥ�ŷ�Ȥ��ϡ��פȤ���ò©�θ��դ�Ĥ��Ƥ����Ode to Sancroft: �֥����եȤؤ���Ρסˤ��Ȥϡ���������������ΰ����ô�äơ������ɤο͡��ΰռ��˱ƶ���Ϳ�����ΤȤʤäƤ��롣
�� ���ȳ�̿��̾����̿
������ϡ������֤ο�̱�ϳ�������ˤ����ơ��ǽ�Ū���ƼԤ��ϰ̤������줿��ʣ���ʸ����ȹ������ä����𤬤��뤬���ʷ����������С����η�̤ϡֿ������פ�����ô�ä���ȤǤ���ե������̿������ϲ��פʤɤ��������͡��ʳ���Ʈ��˼��̤�������Ū�ʺ���Τ���ˡ�����������ܼ����δ��פȤ��Ƥ����Ȥ�����ʬ�ʽ���Ū��������������Ǥ��ʤ��ä����ȡ��ޤ����̤Ρֿ������פι�ȤǤ���ɥ��Ĥ���30ǯ�����Υ������ȥե��ꥢ�ξ���ˤ�ä�¿���ι��ʬ�䤵��Ƥ��ޤ������ȤȤ��Ƥɤ����Ƥ���β��������Ƥ��ޤä����Ȥʤɤ���ͳ�ǡ�Ʊ�������Ū�ʿ�̱�϶���ˤ����ơ��ɤ����Ƥ�������Ω��˴Ť�������ʤ��ä����Ȥʤɤ��������Ƥ��롣
������ϡ����Ȥ�������Ū������Ūͥ���ȡ���������Ω���������ؤΥ��ࡼ���ʰܹԡʡ�̾����̿�פȤ���̵���̿���������ʳ�Ū̵���ˤȤ������ե����Ӥ�������Ū�˳���Ʈ��Ū����δˤ䤫�ʼҲ���פȤ�����Τ���ǽ�Ǥ��ä����ȤʤɤΤ���ˡ��ѹ�ͤ����ϡ����ȳ�̿�Ȥ������ηкѳ�ư�����β��ѤؤȽ���Ū�˶Ф��ळ�Ȥ��Ǥ����ޤ�����Τ⤿�餹��̣�����¤�̣�臘���Ȥ��Ǥ����ΤǤ��롣
��������ͳ�ˤ�ꡢ���Ū�˿�̱�ϳ�������˴ؤ��Ƥϡ�ʩ��ξ��ϱѹ���ɿ魯����Ȥʤ롣�����������������ۤɤ����פ��ϰ̤�̱�Ϥ�������ˤϤĤ��˻��ʤ��ä��ΤǤ��롣������Ρ֡ȣ��ɤλ���פˤ�������פ����ϡ��������Ʒ��ꤵ�줿�ΤǤ��ä���
���Ǥ˸��ڤ��Ƥ���褦�ˡ���˥�����å����̤��ƾ�ħŪ��ɽħ���Ƥ����������Ū���������ʤ���ֿ��ġפ���������ֲʳء�Ū�ͤ�Τ뤳�Ȥ�ޤ�ʤ��ä�������ͤ����ޤ��˻��ȳ�̿��Ω��ԤȤʤä����ޤ����Ȥ�櫓�ֿ���Φ�סʸ��������Φ�ˤȤ�����������ο�̱�Ϥ�����������Ȥˤ�ꡢ�ϵ��˱����ư���Ū���Ƹ��ꡢ���������ޤ����פȤ����Ƥ�̾����ˤ���褦�������������ΤǤ��롣
���������⡢���λ����Ω��ԤȤʤä����Ȥ���Ťΰ�̣�ϡ�ʸ���̤�ѹ�ͤ������������ä���å��㡼: angels/mercury�פȤ�����������ڤ���뤳�Ȥˤʤä����¤���˸��Ф��롣������Φ�ˤ����롢�ָ�ο�����ȡפ��������ڰʾ�˽���Ū��������褷�Ƥ椯�����ϡ��ϹҤ����͡��������Ƹ������Ū�ʥ��ꥹ�ȶ����ԤǤ���ԥ塼��˥���ο������ä��ѹ�ˤ���������۳���Ǥ��ä����¤��礭��������������ǤϤʤ�����Υ���ꥫ�罣��ˤ�����Ǥ⸢��Ū�ˤ��ƺ���ε��Ϥ���Ķ����ѹ�� (Anglican/Episcopal Church) �Ǥ���Ȥ������Ȥ�̵��Ǥ��ʤ������λ��¤ϡ����ϳ������ʼ�Ȥ��ơ�����۳����°����ֽ��ʿ��ļԡפ���̿������ä������Τ��ϤäƳ�ȯ�����ܤ��ڤä���ǡ�������ɤ�����¿��������αѹ�ͤΥ������֥�å�����Ȥ������������ꥹ�ι�Anglicanism�ˤȶ��˿���Φ�����������Ȥ������Ȥ��̣���Ƥ��롣����ϥ���ꥫ����Ω����Ω�Ŀ�̱�ϻ��夬��ʬ��Ĺ���ä����Ȥ��դ���Ф���ǤϤʤ�����˽Ҥ٤�褦�ˡ�����ꥫ�罣��Ȥ����Ƹ���Ȥ������ܼ���ȼ�ͳ����θ����Ǥ����Ʊ���ˡ��붵���Ȥ��������ˤ������ȼ�������ô�äƤ������Ȥ⡢���������ѹ��ȿ����Ĥʤ���Τ����ﶵ�̶Ǽԡʥե�ᥤ����ʤɡˤ������Τ��Ϥä����Ȥ�ɽ���Ƥ���ΤǤ��롣�罣���������ŪΩ��Ԥ�����¿�����ᥤ����Ǥ��ä����Ȥ䡢���ޤ��ޤʵ��餬�ᥤ����Ū�ʵ�����Ϥ�����ΤǤ��ä��Ȥ������¤ϡ������餳�����Ǥ�ɬ�פ�����ʤ�������������ϡֿ������פ���ˤε��Ҥ���ݤˤ����ƾܽҤ����Ǥ�������
�������ä���å��㡼: Angel/Mercury�פΰ�̣�Ȥϡ�������ܼ���μ���ηкѳ�ư�ʿ�̱�ϻ��ۡˤ��̤��ơ�������˼����Ȥ������ȤǤ��롣�Ѹ줬����������Lingua Franca�ˤȤʤ뤳�Ȥκ������ͳ�ϡ�������ͤ��Ѹ���ä��Ƥ����Ȥ������Ȥ�¾�ʤ�ʤ��������αѹ�ͤλ�¹��������ä���������ο�̱�Ϥ������Ω��̤����Ȥ����������ۤΤ���θ���Ȥ��Ƥ������̤����Ƥ����ΤǤ��롣��ŷ�Ȥ��ϡץ��ꥢ��пȤȤ����ŷ�Ȥθ��ա�English�פ����뤳���ο͡��ϡ��������ƺǸ�ˤ��ƺ���Ρ��۶���ư�סʺ��絬�Ϥ��̾���ư�ˤΤ���ˡ������ء�ιΩ�ä��ΤǤ��롣
��Ƭ����
�������С��ȡ��ե�åɤˤ��ֻ���ŷ�Ȥ�12������The Four Archangels and the Twelve Winds by Robert Fludd���������ԥͥå�������ƥ��Τˤ��֣��ͤ�ʡ����ȡץ��ߥ˥��ȶ���ʥե����ĥ���"The Four Evangelists" by Spinello Aretino, a fresco on the ceiling of the sacristy of the church of San Miniato al Monte in Florence, Italy.
[Read More!]
�� ŷ�Ȥȡֿ������פδ֤ˤ����Ϣ
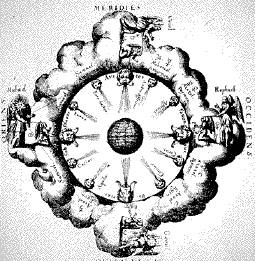

����̩���ˤ�����ֻ�ŷ���פϡ������ᥭ�ꥹ�ȶ�ʸ���ʸ�̩�ˤϥ�����ඵ������ޤ�ˤˤ����Ƥϡֻ���ŷ�ȡפ���������*���������⥤��ɡ��衼���åѸ�Ȥ����������������������������ѤȰ��פ뤫�Τ褦�ˡ������Ĥ���ʩ��������ʩ�����̤����������줿�ҥ�š�ʸ������ο���Ū�������ˤȡ����ꥹ�ȶ��������Ȥ����ݻ�����Ƥ����������δ֤ˤ������ζ�������¸�ߤ��롣




����ʶ���������������������ܻ��ˤλ�ŷ��������ѻ��塿��������
���������ŷ����Ĺŷ������ŷ��¿ʹŷ
* ��ŷ���Ȼ���ŷ�ȴ֤β�¬Ū�Ʊ�����
������ŷ��¿ʹŷ�ʥ��������������ʡˡ������μ�������������㡢����˶��ϡΥ��ꥨ���
��Ĺŷ�ʥӥ롼�����ˡ������μ����������Ĺ�����Υ�ե������
����ŷ�ʥɥ�顼����ȥ�ˡ������μ���������˷��Υߥϥ����
����ŷ�ʥӥ롼�ѡ�������ˡ������μ����������ɮ������˶�ŵ�Υ��֥ꥨ���

����ŷ�� (Four Archangels) �ȸ����С��̾ŷ�ȥߥϥ��롢ŷ�ȥ��֥ꥨ�롢ŷ�ȥ�ե����롢ŷ�ȥ�ꥨ��ʥ��ꥨ��ˤ�ؤ����ߥϥ���ȥ��֥ꥨ��ϤȤ�櫓������äˤ����ƴ��٤��о줹��Τǹ����Ƥ��ޤ�Ƥ��롣������ŷ�Ȥϡ����ꥹ�ȶ�ʸ���ˤ����ơ�������������Ƚ�������ǻ�����ݻ������������Сʥڥ��ˤ������Ƥ��뤫�Τ褦��������Ƥ������Ȥ�櫓¾����ŷ�Ȥ���٤�¿���о줹��ΤǤ����о�Ū�ʸ��줬��Ω�äƴ�������ΤǤ��롣����ޥꥢ�Τ�Ȥ�ˬ����۹��Τ�ŷ�ȥ��֥ꥨ��ϡ�¿���ξ�硢�ؤɽ����ȸ��ޤ����Ф���ν��¤���ͥ��������ä��������Τ��Ф���ŷ�ȥߥϥ���ϡ�¿���ξ�硢ζ����Ƕ��ɤ��ˤ����������롢�ˤ����˽������Ū�ʿ��Ƿ����̤������ˤˤ��������˸���롣����С�Ʈ��Ȼ��ۤ�ŷ�ȡפǤ��롣


�����Х륫��Ⱦ��Υ�����������ߥ�����������֥ꥨ��ס����ο��Ǥ��鴶�����뤳�ȤȤ����餫�˥ߥϥ���ȥ��֥ꥨ�뤬�˽��Ȥ���������Ƥ��뤳�ȤǤ��ꡢ����Ф��꤫�����������شط��ˤ��뤫�Τ褦�ʰ��ݤ����������ΤǤ��롣���������衧Balkan Icons�������ܥåƥ������ˤΡ�BOTTICINI, Francesco / b.1446, Firenze, d. 1497, Firenze�ˤ��ֻ��ͤ���ŷ�Ȥȥȥӥ���: The Three Archangels with Tobias���ˤϥ�ꥨ����������ŷ�Ȥ�������Ƥ��뤬������ˤ����Ƥ�ߥϥ���ȥ��֥ꥨ�����������������Ū���о�Ū�Ǥ��롣�Τ����Ǥϡ����Сʥڥ��ˤ�ŷ�Ȥ���UK�ʥ��졼�ȥ֥�ƥ���̥��������Ϣ�粦��The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland�ˤˤ�������פ����粦���ʤ�������ɲ���ȥ����åȥ��ɲ���˸Ʊ�����Ȥ������Ȥ����Ƥ�������
ŷ�ȥ�ե����� (Archangel Raphael) �ϡ������������ˤϤ���̾�����������ڤ��줺�����������Ƶ���Ρ֥ȥӥȽ�פˤ����Ƽ��פ��о�ԤȤ��Ƥε��Ҥ�����ΤߤǤ��롣��������ե����������Ū�˥��ǥ�α�������Ƥ���Ȥ�������̿���ڡפμ��ԤȤ����Τ��Ƥ��ꡢ�������Ϥ����ŷ�ȤȤ���¦�̤���ġʤޤ�����ϥ�ʡ����ˤ����Ƹ��ڤ����ŷ�Ȥ���ե�����Ǥ���Ȥ�����⤬¸�ߤ���ˡ�
ŷ�ȥ�ꥨ�� (Archangel Uriel) �ϡ��Хӥ��������˥��������������Ω����ŷ�ȤǤ��ꡢ��ŵ�֥ڥƥ��ۼ�Ͽ�פˤ����ƺ�ͤ�ʱ�ζȲФǾƤ��������ŷ�ȡפǤ����ʩ������ˡ���ۤˤ������о줹���Ϲ���Ĩȳ�ԡ�����: Yama�פ�����̤����ˡ�����ޤǤ���ŷ�� (Archangel)��̾���ǸƤФ��ŷ�Ȥ����Ǥλ�ŷ�Ȥ����Ǥ��ä�����ꥨ��ȤĤʤ������ľ�ħ�ϡ����ۤ���Ψ�ԡפ����ơֿ��δ��פǤ��ꡢ����̾���ΰ�̣�����α� (Flame of God)�������ʲСʸ��ˤȤδ�Ϣ�����롣��ꥨ��ϱ�η�����äƥ��ǥ�����Ω�ĥ���ӥ����ŷ�ȡˤǤ��ꡢ����쥨�Υ���פˤ����������������Ĥȶ��ݤ�ʤ��ŷ�ȤǤ���Ȥ�ͤ����Ƥ��롣�������������ε����ˤ����ƥ�ꥨ��˴ؤ��ƤȤ�櫓���뤵���٤����ϡ�724ǯ�Υ��������Ĥˤ����ƶ��ĥ����ꥢ���ˤ�äơ���ŷ�Ȥ�������줿�פ��ȤǤ��롣����ˤ�̱�֤Dz�Ǯ��������ŷ�ȿ��Ĥ˥֥졼�����뤿�ᡢ�Ȥ�������Ū�տޤ���ä�����СֿͰ�Ū����ŷ�פǤ��ä������Τ褦�Ǥ��뤬������䶵�����ˤ����븶�餫��λ���ŷ�ȥߥϥ��롢��ե����롢���֥ꥨ���������ŷ�ȤȤ��Ʋ�¸�������ΰ�����ꥨ����̲�����Ȥ�����ħŪ�ʰ�̣�礤���������������ΤǤ��롣�ֻͼԤ���ˤ����뺹���Զ��פȤ������ϡ���ˤޤ���������Ǥ�������
�� ����ʡ�����: Evangelists�ȡֿ�������
���ߤΥ��ꥹ�ȶ��η�ŵ���뿷������κǽ�˷Ǻܤ���Ƥ���ʡ����ϡ��Ϳͤΰۤʤ�ʡ����Ȥˤ�����Ȥ����κۤ�ΤäƤ��롣������ʡ����Ȥ��Ϳ�����Ƥ�����¤ˤ������Τ��Ȥʤ����붵Ūư�������ࡣ
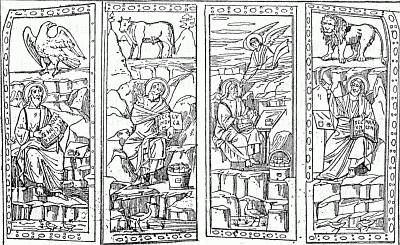
���������衧symbols of the evangelists
ʡ����Ȥ�ɽ����evangelist�ʱѡ�, evangelista�ʥ��, evangelistes�ʥ��ˡɤȤ�����ˤ�angelos�����ʤ���֥�å��㡼�����μԡפΰ�̣�����롣���ꥷ����Ρ�to announce�ɤ�������ư��ϡ�angellein�ɤȤ����줬���Ƥ�졢���θ��ä���ˡֻȤ�����å��㡼�פΰ�̣�����äƤ���ΤǤ��롣��ʡ����ȡ����������ꥹ�ȡפˤϡ�bringer of good news: ʡ�����ɤ��˥塼���ˤ�⤿�餹��Ρס�eu (good) + angellein (announcer) �ϤȤ�����¤����äƤ��롣��ŷ�ȡפϡ��������ܸ줫��ϸ츻��䤷�̤뤳�Ȥ����ΤǤ��뤬����������ˤ����Ƥϡ���ŷ�λȤ��פȤ������ϡ���å��㡼�ʸ��դ��α��ӿ͡ˤΰ�̣�礤��̤���˿�ǻ���Ĥ��Ƥ��롣������ˤ��Ƥ��ʡ����ȡפ��������evangelist: ev-angel-ist�ɤˤϡ�angel�ɤ����Τ�����Ƥ���Τ�����뤳�Ȥ��Ǥ��롣
���ߤο�������ˡ�ʡ����פ��ͤ�����Ƥ��뤳�Ȥˤϡ��ֻͿ͡פ�ʡ����Ȥ����뤳�ȡ��Ҥ��ƤϤ����ˤϡֻ���ŷ�ȡפȤθƱ����ΰż����տޤ���Ƥ��뤳�Ȥ�פ��Ф�ɬ�פ����롣

���ǡ��ֻͿͤ�ʡ����ȡס�Book of Kells, ca. 800��
�͡���ҡ���������ξ�ħ�Ϥ��줾��ʡ����ȥޥ������ޥ륳���륫����ϥͤ��������롣
evangelist
c.1175, "Matthew, Mark, Luke or John," from L.L. evangelista, from Gk. evangelistes "preacher of the gospel," lit. "bringer of good news," from evangelizesthai "bring good news," from eu- "good" + angellein "announce," from angelos "messenger." In early Gk. Christian texts, the word was used of the four supposed authors of the narrative gospels. Meaning "itinerant preacher" was another early Church usage, revived in M.E. (1382). Evangelical as a school or branch of Protestantism is from 1747.
���λͿͤΥ��������ꥹ�ȡ�ʡ����ȡˤǤ���ޥ���: Matthew���ޥ륳: Mark���륫: Luke����ϥ�: John���ȻͿͤ���ŷ�� (Michael, Gabriel, Rafael, Uriel) �Ȥδ֤�¸����Ʊ��ط��ϡ������ƥꥺ��������ˤ����ƽ�ʬ���μ��Ȥ��ƶ�ͭ�����Ȥ����Ǥ⤢�롣�����ˤ������ʡ����Ȼ���ŷ�ȤȤδ֤ˤ��붽̣�����������ˤĤ��Ƹ����С֥�ϥͤˤ��ʡ����פˤĤ��Ƹ��ڤ��ʤ��櫓�ˤϤ����ʤ����֥�ϥͤˤ��ʡ����פϡ��Ȥ�櫓�����ο�������˼�Ͽ����Ƥ���ʡ�����桢���Ū���Ρ��������ۤαƶ���ǻ�������뤳�ȤϤ��Ǥ��Τ��Ƥ��뤳�ȤǤ��롣�������פ���ꤹ�륭�ꥹ�ȶ���Ω����ν���ˤ����ơ����Ǥˤ��ޤ��ޤ�ʡ���ְ�üŪ�פȤ��ơֵ�ŵ�ʳ�ŵ�ˡ�����פ���Ȥ��ƽ��������˲����줿��ǡ����Ρְ�üŪ�פ�ʡ�������������˻Ĥä����Ȥϡ������Ȥ��Ƥ����Τ�Τ���Ū�����в�������ڤ�����֥�ϥͤ�ʡ����פȤ����κۤ��̤����Ȥ߹��ޤ줿�ȹͤ���;�Ϥ����롣
����ŷ�Ȥˤ����ơ���ŷ�ȡפȤ���ǧ�Τ���뤳�Ȥˤʤä���ꥨ�뤬���������ʤˤ�ؤ�餺����ŷ�ȤΥ��롼�ספ�����Ȥ߹��ޤ�Ƥ������ϡ�ñ�˶���Ū�ʸƱ���������Ȥ������ϡ��ޤ��˻���ʡ���������ȹ����ˤ�ȿ�Ǥ��褦�Ȥ����տޤ����ä��Ȼ�����κ�����ΤǤ��롣
�� ŷ�ȥߥϥ���������硼���δ֤˴Ѥ���������ʺ��¡�
����Ū���ʤˤ�äƼ��夲���뤢�����Ϸ������ۤʤ�������ä���Ĥκ��ʤδ֤˶��̤��Ƹ�����Ȥ���С����줬�տޤ��줿��ΤǤ����ǽ���äƤߤ���ͤ����롣�㤨�С��֤���ͦ�Ԥ���Ū��¸�ߡ�ζ�ˤ�Ĩ�餷���פȤ�����ब����Ȥ��ơ�Ʊ�ͤ����ä����Ѻ��ʤ����̤ο�ʪ�������Ƥ���פȤ���С������ˤ���ͤΰۤʤ��ʪ��Ʊ�����Ȥ���������ǽ�����ʤ��������뤳�Ȥ���������ͤο�ʪ���ۤʤ�̾�����Τ��Ƥ����ǽ������Ĥ��ͤ����롣�ʤ�����ˤ��Ƥ⤢��������夲��ݡ����ѲȤ�������Ȥ����̤ο�ʪ�������������褦�ʾ��̤���夲���ǽ���⤢��ΤǤ��롣��


����
����ζ��ɤ�������ŷ�ȥߥϥ���: The Archangel Michael Piercing the Dragon
Martin Schongauer (German, c.1450 - 1491) c. 1475@ The Cleveland Museum of Art
����ζ�������Ͼ���������륰�ʥ���ȡ����硼����Icon with a depiction of Saint George on horseback slaying the dragon. By the painter Emmanuel Tzanes (1660-1680) @ Byzantine and Post-Byzantine Collection of Chania
���͡�Michael (archangel)@Wikipedia
���¡����Ρ�ͦ�Ԥ���Ū��¸�ߡ�ζ�ˤ�Ĩ�餷���פȤ������γ���ϡ���Ĥΰۤʤ�̾�����Τ�줿ͦ�Ԥγ��Ȥ��ƺ����Τ��Ƥ��롣���Ρ�ζ�ϻ�������: dragon-slaying legend�פΤҤȤĤ�ŷ�ȥߥϥ���Τ�ΤǤ��ꡢ�⤦�ҤȤĤ������硼���Τ�ΤǤ��롣�����������Ƥ��������硼�����������Ω�����ϣ��������ȹͤ����Ƥ��ꡢ�����⤽����Ω���Ͼ��������Ǥ���餷���������������硼���ϥ����ɤΤߤʤ餺�������ˤ����Ƥ������ͤȤ���ª�����Ƥ���Τǡ������ɤȤ�ľ�ܤδ�Ϣ���������Ǥ��롣�������ʤ��顢��̣�������Ȥˡ������ɤ��ºݤ˥������륺����襤���������ۤ������¤ȴ�Ϣ�Ť������ϤǤ�����Ƥ��뤳�Ȥ���¤Ǥ��롣�º����ꡢ�������륺������Ū�˹��̱²�ˤξ�ħ�Ȥ��ơ�ζ: Pendragon�פ�ħ����äƤ���ΤǤ��롣

�����ɲ����ɥ�ɣ����μ����� (1465ǯ) ����¤���줿��ߤˤϡ�ζ����Ȳ�������ԤȤ�����ŷ�ȥߥϥ���Ȼפ���������ޤ�Ƥ���Ȥ����������ɤˤ����Ƥ������硼������ŷ�ȥߥϥ����ξ�������äƿ���ɽ�������Ȥ��Ƽ��夲���롣
���͡���angel�� @ Etymology Dictionary
ζ�Ȥ����ΤϤ����ε�����������ħ�Ǥ⤢�ꡢ�¤ϡֻ��λϤ�פ������äƹԤʤ����ζ�Ȥ����༣��ʪ��פϡ��Ť������ι����ʤʤ����ֺǸŤε����ס���ˤλϤޤ�ˤȴ�Ϣ���Ƥ��롣���ʤ���������Ϸ�Ū���̤ϡ����ߤ���������줬�Τ�褦���������餷����餫�ν��פ�ȯü��ɽ�����ä�����о줹�뷹���ˤ��롣��������ܤο��ä���ˤ�Ȭ����ؤȤ�����༣�����ܺ�Ƿ��̿�η��Ǹ��Ф���뤷���ե�ᥤ������˱ƶ���������⡼�ĥ���Ȥˤ�äƽ줿���ڥ����ū: Die Zauberfloete �٤���Ǥ�����ζ���臘�ʽ����롩�˾��̤����ȡ���Υ����ץ˥ȤʤäƤ��뤳�Ȥ�������ΤäƤ��롣�����硼�����༣����ζ�⡢����Ҳ�ʹ�ˤ����ꥹ�ȶ������ˤʤä�������ͳ�ȴ�Ϣ�Ť����İ�����Ƥ��롣�����硼���ϡ�ζ�λ�����̱���Υ��ꥹ�ȶ��ؤβ����ξ��Ȥ����ΤǤ��롣���ʤ���ֳ���줷���ζ���༣���Ƥ���������ˡ����ϥ��ꥹ�ȶ��̤˲�������פ������硼�������ä��ΤǤ��ä���
����ɽ�����ä��᤻�С������ɤξ�ħ�Ǥ��������硼���ȡ�����ŷ�Ȥΰ��ŷ�ȥߥϥ���δ֤˴Ѥ��볨��ɽ����ζ������ϡ��ؤɰտޤ��줿��ΤǤϤʤ����Ȼפ������Τ�ΤǤ��롣�ޤ��������硼���Ϥ�������ŷ�ȥߥϥ���λѤ��Ϥ�����ΤȤ��Ƹ���롣������ζ���������������Ȥ���Ǥ��ꡢζ�ο��Τξ�˾��ʤ��뤤��ñ�˾���������������Ĥ����ζ�ξ��Ω�Ƥ褦�Ȥ�����̤ʤΤǤ��롣���ΤۤȤ�ɺ��Ū�Ȥ���������ʤ�褦����ԤΡֺ�Ʊ�פ�ɽ����Ρֺ��¡פϡ��ष�������硼���Ǿ�ħ����륤���ɤ������ʤ��Ȥ����ŷ�������ŷ�ȥߥϥ��������̤��������Ȥ�տޤ����ʰż����褦�Ȥ��Ƥ���ˤȹͤ��뤳�Ȥ��Ǥ��롣�⤷�������Ȥ���С������ɤξ�ħ�Ǥ��������硼���ϡ���ŷ�ȥߥϥ���˴�Ϣ�դ�������Ƥ��ꡢ����Ū�˥����ɤ���ŷ�ȥߥϥ���δ֤˸Ʊ�����������ɤ��ΤǤ��롣
ζ��Ʈ���������Ȥ�����������Ƥ����Τˡ�����륯�ꥢ�ꥹ (Saint Mercurialis: ca. 359-406) �Ȥ�����ʪ�����롣����������硼���ۤɹ����Τ��Ƥ��ʤ��褦�Ǥ��뤬�������ꥢ�Υ��ߥꥢ����ޡ��˥㸩�ե����Ԥκǽ�λʶ��Ȥ�����ʪ�Ǥ��롣���ܤ��٤��ϡ����ο�ʪ��̾���֥�륯�ꥢ�ꥹ�פ������֥�륯�ꥦ��: Mercurius�פ��ʤ���������ä���å��㡼���ޡ������פ�פ碌���ΤʤΤǤ��롣�������ͤ����Ū���ϡ�Į��ζ������Ȥ��������硼���Ȥۤ�Ʊ���Τ�ΤǤ��ꡢ̾��Ū�ˤϡ�ŷ�ȡפȤĤʤ��꤬����������ŷ�ȥߥϥ����Ʊ��뤬��ǽ�ʤΤǤ��롣
�ޡ������Ϥ�Ȥ�ȥ��ꥷ����Hermes������������˥����ޤο��Ȥʤ뤬����ƥ��Ρ�merx�ɡ��Ѹ�Ρ�merchandise, commerce�ɡ��̾��Ⱦ���ˤȴ�Ϣ�����롣����ˡ��ޡ������ϥ����ǥ��� (Odhinn/Odin, Woden/Wotan) �Ȥδ�Ϣ�ˤ��콵�Τ����ǡֿ������פȶ�����Ϣ������ȸ����Ƥ��롣���ڥ����ˤ����ƿ�������mi?rcoles�ǡ�����ϥ����ޤο��ޡ�����������Ƥ��롣���ܸ�ˤ����Ƥϡֿ��פ�ֿ����פʤɤ�������Ƥ���Mercury�Ǥ��뤬�������ˤ����Ƥ�������ϡֿ������פȤʤ����Ǥ��롣�ޡ������ˤ��Ƥ��ŷ�ȡפˤ��Ƥ⡢���Τ�����⤬�ޤ��ˡ��裴��������Ū�������פλ�����ʴ������Ȥ�ħ�����������ΤǤ��롣
���͡�
��Saint Mercurialis�� @ Wikipedia
Mercury (mythology) @ Wikipedia
�� �Ĥ���줿�����ȡֿ�������
���륳��ƥ����Ȳ��ˤ����ơ��ֿ������פ����������̡פ��ʤ�����������פ�ɽ���Ȥ�����ħ������Τۤ���ʸΧŪ�ʡ���«���פ����롣��ŷ���Τ��줾�줬���������̤μ����Ǥ���褦�ˡ�������Ͷ���ʬ�䤷��ª����Ȥ����ͤ����ϡ������ζ����μ����������ס��̤θ���Ρ����ͽáפ�¸�ߤˤ�äƤ�ɽ������Ƥ���������Ϥ��줾����ġ��֡����פο������Ƥ����Ƥ⤤�롣
�������Ū���ΰ衢�Ȥ�櫓����¾�Ԥ���֤Ƥ��Ƥ�����Τ褦�ʶ��ˤ����ơ����λͶ����������Ȥ����ΤϤȤ�櫓�ռ������褦�Ǥ��롣����������С������ϰ�ˤ����볤�ˤ�äƸ��ꤵ�줿������Ū�������������������֤���Х����Ǵ����������ҤȤĤ�������ɽħ���Ƥ���פȹͤ��뷹���Ȥ��Ƹ����ΤǤ��롣���ʤ���衼���åѤˤ����Ƥ⡢�������Ĥβ�������Ω���ʤ���Фʤ�ʤ��Ȥ������Ȥ⡢�ޤ��ʸ��������ˤ�ä�ʻ������褦�Ȥ������Ρ˥�������ɼ��Τ����Ĥ��ΰ褫��ʤäƤ���*���Ȥˤ⡢���������դ��������ͤ����롣���������ܤ��ܽ����彣�����̳�ƻ�λͤĤ��礭���礫��ʤꡢ���Τ����ΤҤȤĤˤϡֻ�פȤ����ͤĤι������礬���ꡢ�����ϡʤʤ������ϡˤȤ��Ƥε�ǽ��̤����Ƥ���Ȥ����϶�̣�����ΤǤ��롣
������������ٹ�˥�������ɤ�ʻ����Ťä��Τ⡢������ڤ�ͤĤβ���ˤ�äƴ���������Ȥ�����ħ�������Ϥ�Ư������Τȸ��뤳�Ȥ������ΤǤ��롣�ºݤϥ�����������Τ�ʻ�礹�뤳�Ȥ�Ŭ�鷺����������ɤ����� (Northern Ireland) ������̵������������λ��۲����֤������Ǥ��롣
�� �ѹ��ŷ�Ȥδ֤ˤ���ż�
�֥�ƥ����England���Ϥϡ�����Ū��Anglia�ʥ��ꥢ�ˤȤ�ƤФ�롣Anglo-Saxon�ʥ����������ˤȸƤФ��̱²������̾�ΤΡ�Angl-�פθ촴�Ϥ������Anglia��Ʊ���츻������Ƥ��ꡢ���Ρ�Angl-�פ�ɽ������Τ�����ŷ�ȡפ�Angel��פ碌��촴�Ǥ⤢�롣�����Τ��Ȥʤ��顢Anglia�ϡ֥����ͤ��ϡפʤΤǤ��롣�ޤ��űѸ�Ǥϡ�ŷ�ȡפϡ���engel�ɤȥ��ڥ뤵�줿���������äơ�England��Engel Land�ȹͤ��뤳�Ȥ��Ǥ��롣���ޤ깭�����Τ��Ƥ��ʤ����Ȥ�����England��Anglia���ŷ�Ȥ��ϡפΰż���ǻ��������̾�Ȥ������Ȥˤʤ롣
�⤷�����Ρ�ŷ�ȡפξ�ħŪ�Ź��ѹ� (the UK) ���μ¤˻��äƤ���*�Ȥ���С���˵��Ҥ���褦�ˡ��������Τ����Τޤޡֿ������פȤ�ǻ���ʤĤʤ����ڤ��̤ΰ���Ȥʤ�ΤǤ��롣
* �������ȥա����������ե����Τ������붵���ζ����Dz���ʡإȥꥳ�����롦��٤ˤ����ơ�����������ι��Ϣ���᤹���̤����ˤ��о줹�뤬�������ˤϥߥ��磻 (Mikolaj: Michael�Υݡ����ɸ�ˤȸ��������������ȺƲ��̤������Ȥ�����ϥ֥�å�����֤ǥ֥�å���ץ쥤���Ƥ���ΤǤ��롣�����ˤϥߥ��磻���ֻȤ���ŷ�ȡפǤ���Ȥ����ż���ޤޤ��Ƥ��뤳�Ȥ����餫�����֥�å����Ȥ�櫓�ѹ�ˤ����������ƥݥԥ�顼�ʿ»ΤΥ����ɡʥȥ��ס˥�����Ǥ��ꡢ�ͿͤΥץ쥤�䡼���������Υơ��֥��Ϥ�ǹԤʤ�ʣ���ʥ롼�����ä���ĤΥ�����Ǥ��롣
�ֱѹ�ŷ�Ȥ��ϡɤǤ���פȤ���Ź�ϡ�����Ū��å������Ȥ��Ʊѹ�ͤ�����ǰ��Ѥ��륨�ԥ����ɤ������Ǥ��ꡢ�֤ۤȤ�ɼ�����ʤ����������˲�����˼¤Ȥ��Ƥ���줬���Υ������˰��ꤹ�뤳�Ȥ��Ǥ��ʤ��ΤϤ������Ǥ�ޤǤ�ʤ������������Τ褦��������¸�ߤ��뤳�ȼ��Τˤ����Ϥ��ξ�ħŪ��̣�礤�ΰ����ǻ�٤���֤ߤ�ΤǤ��롣������Ф������Ʊ�͡��˼¤ˤ������ͤ�����Ȥ����ͤ����ˤ⡢���פʡ�ħ�դȤ��Ƶ�ǽ�����Τ��˼¤ˤ�����¸������ΤǤ���Ȥ����ͤ����ˤ⡢���Τ�����ˤ������Ϳ���ʤ����ɤΤ褦�ʿ��ä�����������˸��������褦�Ȥ���Τ����Ȥ����տޤ�ǯ���Ķ����̱²�γ��̤����ϡ�������̵�ռ���ƴ�ݤ���ˡ������ԤˤȤäơ���������ͤ����뵷�ס������ο͡��ˤȤäơֿ����٤��뵷�פȤ��Ƥβ��ͤ����뤫��Ǥ��롣�����ơ��ɤΤ褦�ʤ��Ȥ�־�ħŪ���¡פȤ������������Τ����Ȥ��������ԥ��롼�פ�����蘆�줿��̿�ʱ�̿���ϡˤ⡢������ʬ������ΤǤ��롣
�ѹ�˴ؤ��뤽�������Ȥϡ�������ˡ�����쥴��������祰�쥴��ˤΥ֥�ƥ���ؤΥ��ꥹ�ȶ��۶���ư�˴ؤ����������Ȥ��ƻĤäƤ��롣���쥴�������ˡ���̤߰�����590-604ǯ�����顢�����������飷������Ƭ���̤�������Ȥ������Ȥˤʤ롣�ब�����ޤˤƥ����ɽпȤμ�Ԥȱڸ������ݤˡ�Not Angles, but Angels (Non Angli, sed Angeli): ����ͤɤ�������ŷ�Ȥ��Τ�Τ��פȶä�ɾ�����Ȥ����Τ����θ��������Ǥ��롣���٤�����褦�ˡ����줬�˼¤Ǥ��ä��Τ��ɤ����Ȥ����Τϡ���Ū�ʽ��������������ʤ������Τ褦�ʥ��ԥ����ɤ����ä��Ȥ������Ȥ������褦�Ȥ���ѹ�͡ʤ���ˤϲ������ꥹ�ȶ��̤����ˤβ��ռ�Ū��Ķ�ռ�Ū�ˤʡ��ʲ�ɤ��������פʤΤǤ��롣���ʤ��Ȥ⡢���쥴������ȥ������۶����ڤäƤ��ڤ��ä��ʤ��˼¤Ǥ��äơ����Τ褦�˶ä�ɾ�����Τ�ȼ�äƥ��쥴������������������ƥ��̥��ΰ۶��̤��ϥ����ɤؤ��ɸ�����Ƥ���ΤǤ��롣���������̤Ǽ�����ʤ��ֻ˼¤��륨�ԥ����ɡפϡ���꿮�����ι⤤�˼¤η�֤��֤����ΤǤ��롣
�ޤ��ѹ����ɽ������ͥ���ʥ������եȤ�����Ah, Britain, land of angels!: �����֥�ƥ�ŷ�Ȥ��ϡ��פȤ���ò©�θ��դ�Ĥ��Ƥ����Ode to Sancroft: �֥����եȤؤ���Ρסˤ��Ȥϡ���������������ΰ����ô�äơ������ɤο͡��ΰռ��˱ƶ���Ϳ�����ΤȤʤäƤ��롣
�� ���ȳ�̿��̾����̿
������ϡ������֤ο�̱�ϳ�������ˤ����ơ��ǽ�Ū���ƼԤ��ϰ̤������줿��ʣ���ʸ����ȹ������ä����𤬤��뤬���ʷ����������С����η�̤ϡֿ������פ�����ô�ä���ȤǤ���ե������̿������ϲ��פʤɤ��������͡��ʳ���Ʈ��˼��̤�������Ū�ʺ���Τ���ˡ�����������ܼ����δ��פȤ��Ƥ����Ȥ�����ʬ�ʽ���Ū��������������Ǥ��ʤ��ä����ȡ��ޤ����̤Ρֿ������פι�ȤǤ���ɥ��Ĥ���30ǯ�����Υ������ȥե��ꥢ�ξ���ˤ�ä�¿���ι��ʬ�䤵��Ƥ��ޤ������ȤȤ��Ƥɤ����Ƥ���β��������Ƥ��ޤä����Ȥʤɤ���ͳ�ǡ�Ʊ�������Ū�ʿ�̱�϶���ˤ����ơ��ɤ����Ƥ�������Ω��˴Ť�������ʤ��ä����Ȥʤɤ��������Ƥ��롣
������ϡ����Ȥ�������Ū������Ūͥ���ȡ���������Ω���������ؤΥ��ࡼ���ʰܹԡʡ�̾����̿�פȤ���̵���̿���������ʳ�Ū̵���ˤȤ������ե����Ӥ�������Ū�˳���Ʈ��Ū����δˤ䤫�ʼҲ���פȤ�����Τ���ǽ�Ǥ��ä����ȤʤɤΤ���ˡ��ѹ�ͤ����ϡ����ȳ�̿�Ȥ������ηкѳ�ư�����β��ѤؤȽ���Ū�˶Ф��ळ�Ȥ��Ǥ����ޤ�����Τ⤿�餹��̣�����¤�̣�臘���Ȥ��Ǥ����ΤǤ��롣
��������ͳ�ˤ�ꡢ���Ū�˿�̱�ϳ�������˴ؤ��Ƥϡ�ʩ��ξ��ϱѹ���ɿ魯����Ȥʤ롣�����������������ۤɤ����פ��ϰ̤�̱�Ϥ�������ˤϤĤ��˻��ʤ��ä��ΤǤ��롣������Ρ֡ȣ��ɤλ���פˤ�������פ����ϡ��������Ʒ��ꤵ�줿�ΤǤ��ä���
���Ǥ˸��ڤ��Ƥ���褦�ˡ���˥�����å����̤��ƾ�ħŪ��ɽħ���Ƥ����������Ū���������ʤ���ֿ��ġפ���������ֲʳء�Ū�ͤ�Τ뤳�Ȥ�ޤ�ʤ��ä�������ͤ����ޤ��˻��ȳ�̿��Ω��ԤȤʤä����ޤ����Ȥ�櫓�ֿ���Φ�סʸ��������Φ�ˤȤ�����������ο�̱�Ϥ�����������Ȥˤ�ꡢ�ϵ��˱����ư���Ū���Ƹ��ꡢ���������ޤ����פȤ����Ƥ�̾����ˤ���褦�������������ΤǤ��롣
���������⡢���λ����Ω��ԤȤʤä����Ȥ���Ťΰ�̣�ϡ�ʸ���̤�ѹ�ͤ������������ä���å��㡼: angels/mercury�פȤ�����������ڤ���뤳�Ȥˤʤä����¤���˸��Ф��롣������Φ�ˤ����롢�ָ�ο�����ȡפ��������ڰʾ�˽���Ū��������褷�Ƥ椯�����ϡ��ϹҤ����͡��������Ƹ������Ū�ʥ��ꥹ�ȶ����ԤǤ���ԥ塼��˥���ο������ä��ѹ�ˤ���������۳���Ǥ��ä����¤��礭��������������ǤϤʤ�����Υ���ꥫ�罣��ˤ�����Ǥ⸢��Ū�ˤ��ƺ���ε��Ϥ���Ķ����ѹ�� (Anglican/Episcopal Church) �Ǥ���Ȥ������Ȥ�̵��Ǥ��ʤ������λ��¤ϡ����ϳ������ʼ�Ȥ��ơ�����۳����°����ֽ��ʿ��ļԡפ���̿������ä������Τ��ϤäƳ�ȯ�����ܤ��ڤä���ǡ�������ɤ�����¿��������αѹ�ͤΥ������֥�å�����Ȥ������������ꥹ�ι�Anglicanism�ˤȶ��˿���Φ�����������Ȥ������Ȥ��̣���Ƥ��롣����ϥ���ꥫ����Ω����Ω�Ŀ�̱�ϻ��夬��ʬ��Ĺ���ä����Ȥ��դ���Ф���ǤϤʤ�����˽Ҥ٤�褦�ˡ�����ꥫ�罣��Ȥ����Ƹ���Ȥ������ܼ���ȼ�ͳ����θ����Ǥ����Ʊ���ˡ��붵���Ȥ��������ˤ������ȼ�������ô�äƤ������Ȥ⡢���������ѹ��ȿ����Ĥʤ���Τ����ﶵ�̶Ǽԡʥե�ᥤ����ʤɡˤ������Τ��Ϥä����Ȥ�ɽ���Ƥ���ΤǤ��롣�罣���������ŪΩ��Ԥ�����¿�����ᥤ����Ǥ��ä����Ȥ䡢���ޤ��ޤʵ��餬�ᥤ����Ū�ʵ�����Ϥ�����ΤǤ��ä��Ȥ������¤ϡ������餳�����Ǥ�ɬ�פ�����ʤ�������������ϡֿ������פ���ˤε��Ҥ���ݤˤ����ƾܽҤ����Ǥ�������
�������ä���å��㡼: Angel/Mercury�פΰ�̣�Ȥϡ�������ܼ���μ���ηкѳ�ư�ʿ�̱�ϻ��ۡˤ��̤��ơ�������˼����Ȥ������ȤǤ��롣�Ѹ줬����������Lingua Franca�ˤȤʤ뤳�Ȥκ������ͳ�ϡ�������ͤ��Ѹ���ä��Ƥ����Ȥ������Ȥ�¾�ʤ�ʤ��������αѹ�ͤλ�¹��������ä���������ο�̱�Ϥ������Ω��̤����Ȥ����������ۤΤ���θ���Ȥ��Ƥ������̤����Ƥ����ΤǤ��롣��ŷ�Ȥ��ϡץ��ꥢ��пȤȤ����ŷ�Ȥθ��ա�English�פ����뤳���ο͡��ϡ��������ƺǸ�ˤ��ƺ���Ρ��۶���ư�סʺ��絬�Ϥ��̾���ư�ˤΤ���ˡ������ء�ιΩ�ä��ΤǤ��롣
��Ƭ����
�������С��ȡ��ե�åɤˤ��ֻ���ŷ�Ȥ�12������The Four Archangels and the Twelve Winds by Robert Fludd���������ԥͥå�������ƥ��Τˤ��֣��ͤ�ʡ����ȡץ��ߥ˥��ȶ���ʥե����ĥ���"The Four Evangelists" by Spinello Aretino, a fresco on the ceiling of the sacristy of the church of San Miniato al Monte in Florence, Italy.
[Read More!]
01:32:00 -
entee -
TrackBacks
2006-05-16
�Dz��Touch the Sound�٤�Ѥ��İ����
�ͺ��ʤҤȤ��ޡˤȤ��ƤΡֿ�ư����䤿���פȡ������̤����������Բ��դ�����



�֤⤷������Ȥޤ��Ϥ���İ�Ф��ĤäƤ���Τ������ʤ��Τ��⤷��ʤ��ס�
�Ҥ�äȤ���ȡ�İ�о㳲�ԡפ��ष��������ʹ�����ȤΤǤ��ʤ��Բ��դ�ª���Ƥ��뤫�⤷��ʤ����Ȥ����褦���Ȥϰ�����������Ƥ������Ȥ������������ȸ�����ª�����ʤ��Ϥ��αDz褬�����ַ��ԡפ�ª��»�ʤäƤ����¸�ߡפ��ǧ���פ������֤��Լºߡդ��뤳�Ȥ���ۤɤߤ��ߤ������������Ȥ��Ǥ����ΤϤۤȤ�ɴ��פΤ褦�Ǥ��롣
�����Ƥ��Ρִ���Ū��ǽ�פϡ��Dz��Ѥ��塢ľ���˺��Ѥ��Ϥ�롣�ֱDz�ۤ�����פ������������Ѥ��褿ͧ�ͤϡ����κ��Ѥˤ��ֱDz�ۤ������ä��פȤ���������ϺǸ�ˤ⤦���ٸ��ڤ���褦�ˡ��¤ˤ��αDz���ܼ���������Ƥ�ɽ������
�ޤ��Dz��ϡ��ɥ�����Ȥμ��ΤǤ��륨�������ˡ� (Evelyn Glennie) ��¨�������ꥹ�ȡ��ե�åɡ��եꥹ (Fred Frith)�ȤΥ��å��������̤��ơ�����ˤۤȤ�ɲ���ʹ�����Ƥ��ʤ��ȤϤˤ狼�˿����ۤɤβ��������Ĥ��롣�ȡ��ޥ�����ǥ륹�ϥ��ޡ����Ĥϡ������κ���δؿ����Ǥ���������������̩�פ�ڤ��ʤ������������Ȥˡ�����פȤ�����Ƭ�Ǥϴ������Ǥ�ʤ��ʤ�����̩�Ϥ��������Ǵ��˹Ԥ��Ƥ����͡��ʥ�ӥ塼�������ʤɤˤ�äƤۤȤ��̵������Ƥ��ޤäƤ���Τ����ˡ�
ʹ�����ʤ��ʤä�����ˡ���Ĺ������������ʤ��ʤä��������Τ����Υ��ʴ��Сˡ�����ϡ�¸�ߤο�ư������̤μ��פ�ª����Ȥ�����ˡ���ä���������ˡ��Ĺ���������Τ����ΤȤ������Ȥ�¸�ߤο�ư������ߤ�뤳�ȡ��ֿ���: Touch�פ��Ȥ�Ϥ����ˡ�����ϡֲ�������ʹ������ͤϡ���ʬ�����Ƥ���褦�˲���ʹ���ơʿ��äơˤ��ʤ��פ��Ȥ��ΤäƤ��롣����������β��ڤ�ɤŨ����褦�ʶä��٤����Ȥ������ȯ�����̤��ơ�Touch the Sound�����Ԥ��̤��ƾҲ𤵤�롣�֤⤷������Ȥޤ��Ϥ���İ�Ф��ĤäƤ���Τ������ʤ��Τ�������ʤ��ס����Τ褦������Ƹ��路���¸�ο�ư��������ˤ����δؿ��ϰܤäƤ��������줬���μºߤ��ο����Ѥ�äƤ��������Dz�δվԤϤ�Ϥ�Dz������ʹ���ͤǤϤʤ��ʤäƤ���Τ�������ϤҤȤĤΡָ��פȤǤ�ƤӤ����ʤ�褦�ʲ�������δ��פ��Ϥ�Ƥ���Τ���
�Dz褬ª�����褦�ˡ��٤�ʹ֤⡢�����������˳�ɤ���ʤ������Ծ���ԤäƤ���ʹ֤⡢��������ʹ֤⡢����⤬�ֿ�ư�פ��Ƥ��롣�ܤ˸����ƿ�ư�Ϥ��Ƥ��ʤ��Ȥ⡢�ƵۤȤ���ȿ����ư���Ȥ���ΤϤ��ʤ�������Ϳ����줿�������������������˼������줿�����ΤۤȤ�ɤ�������������������˰½����Ƥ����ǽ���϶ˤ�ƹ⤤���ܤ�������ͤϸ����Τ餺������ʹ������ͤϲ���ʹ���Ƥ��ʤ����Ȥ������Ȥ���������Τ�������Ķ����¸�ߤμ��Τ�Dz�Ϥ��μꤳ�μ��ȤäƤ����˵��դ����褦�Ȥ��롣
��
�áʤȤ⤨�ˤȤ��������ϡ����ˤ�ä�ɺ���ͺ��ʤҤȤ��ޡˤΤ褦�ʡ��濴�˳ˤ���ä�������ͷ���륨�ͥ륮���μ��ΤǤ��ꡢ�ޤ������ʤӤ����ʤ���ɺ�ä�����������Ԥ����ꤹ���ͻҤǤ��ꡢ���뤤�������ʤۤ����ܤ��ˤΤ褦�ˤ�����������äƼ�������ֲФζ̡פΤ褦�ʤ�Τǡ����Ȥ��ơ��ҤȤĤ���̿�����α�̿��ɤ�����ΤǤ⤢�롣

�����ؼԤ������Ż�ˤ��С����áʤϡˡפȤϴ�ʪ�Ρּ�ü�פΤ��Ȥ��Ȥ���������ϥ�������ʤɤ����Τ��оο����Ϥ�ƫ������ۤκ������դ���줿��ü��פ碌������Ǥ⤢�ꡢ�ۤ�Ƭ��좤���Ф����Ϻ����Ρּ��פ������롣�����Ƥ���������Τ��Ȥʤ�����Ƭ�ʱ������˷����Ǥ��롣�Ĥޤ��ۤ�ĺ����դ���줿�ܥ���Υԥ�侾�μ¤Τ褦�ʷ��ξ����ʥĥޥߡʡֽ����פ�ɽ���ե��˥���ˤ��ܻؤ��ƺ��������������֥��쥹��: crests�פ�������������������ϸ������Ǥϡ��áʤϡˡפȸƤФ�Ƥ����Ȥ������Ȥˤʤ롣�����Ƥ��Υ��쥹�Ȥϡ������ͼ�Ū�ˤϤۤȤ�ɤξ��ֱ����פʤΤǤ��롣�����ơ����ˤϤ��ʤ餺�濴����ȯ�����롣��ư���濴����¸�ߤ���Τ����ʤȸ��������Ω����٥��ȥ�λظ�����¸�ߤ��뤫��Ǥ⤢�롣


����ۡˤ����¸���뾮���ʴݤ����ʱ��ˤϡ����Ȥΰ��β����ܻؤ������ʱ��ˤ����¸���뾮���ʴݤ�����ۡˤϡ���Ȥΰ��β����ܻؤ������줬����ư�θ����Ϥȹͤ��뤳�Ȥ��Ǥ��롣��Ū�ʡ�ȿ��ʪ�פ�¸�ߤ���ư�ε����Ȥʤ롣
�ֱ��ۡפ��ߤ��ˡ�69�ɡʥ��å����ʥ���ˤη��Ǹߤ��˳��߹�ä������ˡפΥ���ܥ�Ϥ褯�Τ��Ƥ����ħ�����Ǥ��뤬������Ф��Ρ�����áʤդ��Ĥɤ⤨�ˡפȤ�ƤӤ����褦��ɽħ�ξ��ϡ���Ԥ����ߤ��������ɤ��Ĥ����Ȥ��ƤҤȤĤα������뤰�����������μؤΤ褦�ˤ⸫���롣���Ρֱ��ۡפȤ��ä����Ф�����Ĥ����Ǥ��ҤȤĤμ��Τα��줿����Ū����פǤ��뤳�Ȥ⡢���ξ�ħ�ϼ������롣����������˶�̣�������Ȥˡ����������μؤϤ�����ˤˤ��켫�Τ�ȿ��ʪ�����Ƥ���ΤǤ��ꡢ�ۤǤ���Ф�����˱����Ǥ���Ф�������ۤ�ԳˡդȤ����ݻ����롣���ʤ�������줾�줬���줾����ɤ��Ĥ��������Ȥ�����������äƤ���Τϡ��ҤȤ��ˤ��켫�Τ�����뼫�ʤ�ȿ��ʪ�����ɤ����ɤ��Ĥ���¾���λ���Ʊ�����礭����ʬ�˴Ը����ۼ�����褦�Ȥ��뤿��ʤΤǤϤʤ�����ȿ��ʪ�ɤ����δ֤�¸����ָ����פȡ�����ư�פ���ͳ�ˤʤäƤ��ꡢ��ߤμ���Ū�ʼ椫��礤����̩��ɽ���Ƥ���Τ��⤷��ʤ���
�����������áʤȤ⤨�ˡפξ�ħ������������Գˡդʤ����濴����¸�ߤϡ����̡ʤޤ����ޡˤȤ���ɽħ������������˳���������̤�����ˤ�ä�ɽ����롣���áפȤ���������Ƭ�����濴���������û����ľ���ϡ��ޤ��ˤ��Ρֳˡפδ�ά���������Ƥ�����ΤǤ���ȹͤ�������Ǥ��褦��
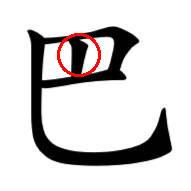
�Ȥ��ˡ������ä�ħ�Ȥ����Τ����ܤ����ݤ˱����Ƥϴݤ��ѥ�ѥ��ĥ��줿�顢�Х��ˤ�ä����Ǥ����ä���ξ����������ΤȤ��Ƥ��Τ��롣����ϡֻ����áʤߤĤɤ⤨�ˡפ�ħ�Ǥ��ꡢ���Ρֽáפ�����Ф����ܤΡ��ڡפ����ˤ�ä��Ǥ��Ĥ餻�С��礭�ʹ��⤿�餹�����Ρֻ��̰��Ρפ����ι�����ΤǤ��뤳�Ȥ�ʬ���롣


�ä�ħ�ϡ����������α����ư���ʤ���ʤ���������ҡˤ��ͤˡ������ȥޥƥ��å��˺٤�����ư�����ʤ��餽������ϤȤ������ʤ��롣��������Ӥ���ä����Ū�Ǥ���������®���ˤ������Ǥ���ñ��˦��ʪ�λ��äƤ����η�������Ѥ��Ǥ��롣�ޤ����Τ�����ˤޤ����ʤ�����ˤ�����ʤȤ������Ȥ�DNA���濴���������濴Ū���ۡդ�¸���ˡ���������λ����������徲���Ʋ����֤�����ȡ�����ϡִ�������ޤ줿�ǽ���ۻ������롣���줬�ޤ����̾��Ǥ��롣

��̿�γˤȤ��Ƥ�Ƭ�ȴ�夬��ü�˰��֤�������Ϥ߽Ф��ץ��ڥ餬���˰��֤���ʤ�С���ư������̿�η������̾��Ǥ��ꡢ�ޤ��ֲФζ̡��Ǥ��롣��̿�γˤȤ��Ƥμ�����֤�ʤ��ۻ������������������Ƥ���Τϡ��ֵ�ǽ��������������פ�����������äƤ⡢�����Ȥ������Ϥष�������ȸ����٤��Ǥ�����������ʤ��ΤϾ��ʤ��Τλ��ѤƤ���פȤ����Τ���������

�Dz��Touch the Sound�٤ˤ����Ƥϡ����Ρ��ä�ħ�פȤ����Τ�������������˽ФƤ��ơ���̿¸�ߤΤ��Ρֿ�ưŪ�פʼ��Τ��ħŪ�˸�����ΤǤ��롣����ϥ�����˥塼�衼���Υ����ɥ���ȥ��ؤǥ��ͥ���á���Ϥ����ˡ����������Ӥ˹�ޤ�Ƥ�������Υ����ߡפ������Ϥ˸���롣���������νп��ϤǤ��륹���åȥ��ɤ��ħ����֤Ǥ��뤬�����β֤ϡ��ޤ��˸�������ķ�Ū�����ΰ�ĤǤ��ꡢ����ȥ륳�å������ߤ�����λѤƤ��롣�����ơ������ݺ¤ȤΥ��å����ˤ�����Ϣ�Ǥ���������ݡ������ݤ��դ�ʪ�ʤΤϻ����äΡ��áפ�ħ�Ǥ���ˡ������ƥ��������������ˤ������ư������ǡ���γ��Ǩ�줿�������μ���ȡ�����ɽ�̤�عԤ������פ�Ĥ��ʤ���ۤȤ�ɿ�ʿ��ή��Ƥ�����ũ���ˤ�ä�ɽ������롣�ޤ����Dz�κǽ����ǿ��ſޤȻפ���Ĺ�����������Ѳ��ι��������ֵ����פˤ�äƤ�������롣
���λ�����뤬���ſޤΤ褦�ʥ��������ե�������ȷ��ˤ�Ͽ������ΤǤ���ΤϤ����������ǤϤʤ��������줿�������������Ȳ���Ω�Ƥʤ�������Dz졢Ĺ����������ʤ������������פ��롣�����Ƥ���ϡֲ��̱�¦�פ˸����ä����Ԥ��Ƥ����Τ��������Ƥ��������عԤ��뤳�Ȥˤ�äơ����ο�ư�������Ԥ�ȼ�������ΥХ��֥졼������Ū��ª�����롣
����ϼ����ʥ��ץ����ˤ���뤿��˺ǽ������˸����äƱˤ������뤤�����Ԥ��롣����Ϥ�������Dz��2001ǯ�����ι�٤ˤ����ơ������ڤä����áפ�ħ�Τ褦�����ҷ���������õ�����ǥ�����������椬�����������㥤��ɤ����߽Ф��٤����̤Ρֱ��ر��ظ����äơҹԤ������Τ褦�Ǥ⤢�롣��������Touch the Sound�٤κǽ����̤ϡ��������ˤ�äƼ��ߤ�����룴�ܤΥޥ�åȤ����ֺǸ�ΰ�ġפˤʤꨡ�������ޤ���ư���ʤ���ʤ����ҤΤ褦���������ڤθ���ȶ��ˤ��ο�ư��ߤ��⡢̾���ˤ������˥ޥ��Ф�ɽ�̤�������Ĥ���Τ�����ϸ��롣�����Ƥ����������˲��������ۤ����Τ��������뤳�ȤϤǤ��ʤ��ΤǤ��롣
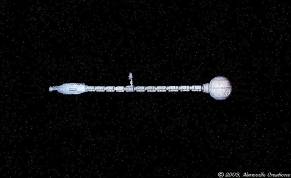
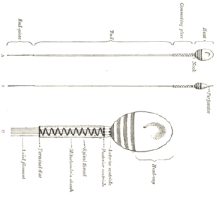

�ֿ�ư�Ȥ������Ƥ��뤳�ȡ���̿�ˤξڤǤ����
��
�����ʤ����Ū��å�������Ķ���ơ����褦����ۤɤޤǤˡ�Touch the Sound�٤������ο���̤碌��Τ������������Ϻ��Ф���륨����Ȥβ��ڤˤ��롣����θ��դϤ��Ф餷�����������ڤ���Ԥ��Ƥ��Ф餷���ΤǤ��롣
���������餷�����ڤϡ������ο��Τ���ˤ��ꡢ�������⼡�ʤ�ֿ�ư�����פ��Ԥ��ʤ��顢�Ȥ������ƴݤ��ʤä�̲�äƤ���̵�������Ҥ������줬�������ĤΤ褦�����ݤι줭�ˤ�ä��ܳФᤵ����줿���Τ褦��������餬�Ȥ�������䤬�����Ȥ�ư�����ʤ������������˸����äƱˤ��Ϥ��褦�ʴ��ФǤ��롣�����̲�äƤ��������ݤ���áפϡ����ΤФ��ڤäơ�������Ϥ��ΤǤ��롣����οͤ��ֱDz�ۤ������ä��פΤϡ��ޤ������Ȥ˴��������ä�̵���Ρֿ�ư�פ����������ž��浯�������˸���������Ϥ˽����ʳ��ˤʤ����Ȥ������֤ˤʤä���̤ʤΤǤϤʤ����Ȼפ��ΤǤ��롣
�����ͤ����Ȥ��������ݺ¤κ�Ĺ�θ������ܤˤ����벻�ڤ��ǽ�λϸ�����ͤ˱��줿ŷ�������Ͷ���Ф��������ڤˤ���Ȥ����⤬����פȤ��������������αDz����ǤɤΤ褦������Ū��̣�ΰ����������Ƥ���Τ�����λ��Ǥ��Ƥ��롣��ʬ�����̵���Ρִ�͡פ��顢��̿�θ��ʿ�ư�ˤ��������졢����Ф��ΤǤ��롣
20:46:00 -
entee -
TrackBacks
2006-04-19
�Ǥӱ�����Τ˱ɸ�ͭ�졧
���ʲ��Τ�¸������ԥޥ˶��դ���
��ʪ����˴���뤳�Ȥˤ��ε����Ū������*���ȤϲϾ�ȥ�����ä����դ���
* ���Τˤϡ֤�����ʪ�ϳ��ʤ��μ��Ǥ����ۤȤ������Τʤ����פǤ��롣
�ޤ������������
�֡�ά��ǽ���ͤ��Ƹ���С��±����±����Ȥ���˴�����ۤȤ��Ȥ�����������ʤ�˰ʤƼ¤ϴ�ʤ餺���ع���Ʊ�����ˤơ�̵����Ԥ������ʤ����뤬���ν��ɤ����ۤʤ�ɡ��⤷���ν��ɤ����ۤˤ��Ƽ¸�����졢������˶���������ɬ�פ���ͤ������ʤ��ʤ��ˤϡ��ع���ǵ���ѻߤ��줶���������ʤꡣ��Ƚ��Ȥ������ƹ��Ȥ�����ˡΧ�Ȥ������ࡢ�䤷�ƹͤ���С����ʤޤ����μ��Ǥ����ۤȤ���ˤ��餶��ʤ�����
�����θ��դ˽��ƽв�ä���������������ɽ����Ÿ��������ĥ�ȡ��ɤ�Ǥߤ�����������̤�Ȥ��������褦�Τʤ���ü���������˶ä��ȶ��ˡ�����������Ф����Τϡ���ʬ����Ǥޤ������˿����������λ��˴�ư�����ٽ����Ȥ����롣
�����ʤ�С����ǤӤ�פȤϡ���Ū����ä��ȿ������줿��Τ�����Ū��ã�����Ƽ����¸�ߤ��ä���Ȥ������ȤǤ��롣���ۤ�����ʤ�С��ʹ֤��ȿ��Ȥ��ƤΤ��������Ρʾ��ˤ�äƤϸĿ͡ˤȤ�����Τϡ����ε�ˤ���Ū�ϡּ��ǡפˤ��뤳�Ȥˤʤ롣�������Ǹ����ȡ�����μ�ĥ���붵�����������줽��Ǥ�����������顢�������ΤǤ����ּ��ʲ�áפ���Τ��Ǥ�餤������κߤ����פȸ��������Ǥ��롣����������С��ֽ������ɤ��Ƥ���פȤ���С����š��ٻ�����ˡ������¾��ɬ�װ���Ʊ�ͤˡ������Ͽ͡����Թ����ä��Ƥ��ʤ��Ȥ������Ȥˤʤꡢ����Ǥ���������Ƥ��ʤ������ʤ���������ָؤ�٤����ȡפǤϤʤ����Ȥˤʤ롣
�ʤɤȡ������ޤǽƤ��ƺ����ο����դꥢ�åפ��뿴�Ť����ä������饤���Τ�������夬�ä��ꤷ�Ƥ��ơ������Ϥ����ʤ��ä�������Ⱥ��������ļ������ߤ���������褦�ʤ��Ȥ��ξ�ơפε�ǽ����Ū�Ȥ������Ȥ�����������Ƥ����������������������Ʊ���褦�ʻ�����Ʊ���褦�ʤ��Ȥ�ͤ��Ƥ������Ȥˤʤ롣���ļ����漼
���ĤϲϾ�ȥ������Ʊ�ͤ�...
�ٻ��������ۤϡ��Ⱥ�Ԥ����ʤ��Τǡ��ٻ������⤦ɬ�פǤʤ������פμ¸��Ǥ��롣�����Ʊ���褦�˿Ƥ����ۤϡֻҤɤ⤬��Ω���Ƥ��줿�Τǡ��Ƥ�¸����ͳ���ʤ��ʤä����֡פ�ã���Ǥ��롣����ά���Ҥɤ⤬��Ĺ���뤳�ȤϿƤδ�ӤǤ��ꡢ�Ҥɤ⤬��Ĺ���ƿƤ�ɬ�פȤ��ʤ��ʤ뤳�ȤϿƤ��ᤷ�ߤǤ��롣��Ӥ��ᤷ�ߤ����Ū��ж�ʤ���Ȥ����Τ��ʹ�Ū�İ٤��ܼ�Ū�����Ǥ��롣<<
�ȸ�롣�äˡ��Ǹ�Σ��Ԥ������Ƥ��롣�����ޤǤϹͤ������ʤ��ä��������ͤ���пʹ֤�̷��Ū¦�̤Ρֹ���פˤʤ롣
���ơ����⤽�⤢�餿��Ʋ��Τ��Τ褦�ʲϾ�ȥ�θ��դ˺Ƥӻפ���ä������äʤ���Фʤ�ʤ��������10����������13�������˳ݤ���δ����ˤᡢ���θ奫�ȥ�å��β��ڤʤ��ư��ˤ�äƤĤ����Ǥ��������ɤΡ֥������ɡפ���ˤˤĤ��ơ��������ܤ���λ��������Ǥ⤢�뤬������֥������ɤ���Ԥ��뽡���פȤ����������ޥ˶��Τ��Ȥ�ͥåȤ�Ĵ�٤뤳�Ȥˤʤä������������ȡ��ͥåȤǸ��Ф����������Ǥ⡢���Ĥ��ν�������Ҥ����ä���
�ޥ˶��Ȥϡ�������Ⱦ�Хޥˤˤ�ä��ϻϤ��줿���������ǡ��桼�饷���ι����ϰϤˤ�����¿���ο��Ԥ�����������������פΤҤȤĤǤ��ä��������ϰϤ�������������ˤޤ���ã�����۶����������Ƥ��롣�����������̰������פ������륭�ꥹ�ȶ��ʥ����ޡ����ȥ�å��ˤ��Ϥ��դ���ˤĤ�ơ����Ρ�����Ū�����Ȱ���������ˤ�������Ω�����Ȥ�ޥ˶��ϡ�����ˡְ�ü*���۶��פȤ����ư�����Ƥ������䤬�ƣ������ˤϼ¼�Ū���Ǥ�����������ä��������Ρ���������ϡ�����Ū¸�ߤ�Ű�줷�����ꤹ��Τǡ������Ф��꤫�����٤�������Ū�˶ػߤ��줿�ʤȤ�櫓�����Ԥδ֤ǤϤ�����������ư�ؤ��ä����ʤ˵�̳�Ť����Ƥ����ˡ��ʤɤʤɡ�**
* �ذ�ü�������ɡ٤����ԡ��ե���ʥˡ�����ĥ����褦�ˡ��ޥ˶��ϥ��ꥹ�ȶ���������ȶ�ǤϤʤ��Τ����顢�ְ�ü�פȸƤФ��ΤϤ����������������äʤΤ������⤽��ҤȤĤν����γ�����¸�ߤ����Τ�ְ�ü�פ�Ƥ֤Τ���Ŭ�ڤǤ��롣�㤨��ʩ�����֥��ꥹ�ȶ���ü�ɡפǤʤ��Τ�Ʊ����̣�ǡ�
** ���ͥ����ȡ�Introduction of Manichaean Religion���ޥ˶����⡦���� @ KHOORA SOPHIAAS
����Ū���������ꡢ��¹��⤦���뤳�Ȥε��ݡ������˥ޥ˶����ֿʹ֤��ȿ��Ȥ��Ƥν������ΡפȤ��ơ��塹�����Ķ�����ޤ���¹���̤��ʱ�ˡֱɲڤ�ڤ���פ��ȤΤǤ��褦�Ϥ��Τʤ�����ɮ���٤���ˡ��������������Ф���롣���Τ��Ȥϡ����äƤߤ�Хޥ˶������Ρȶ����ɤ���ˡּ��ʲ��Τθ������ޤ��Ƥ����פ��ɤळ�Ȥ��ǽ�ˤʤ�Τ���
�ޥ˶�����Ĥ��Υ��ꥹ�ȶ���ü�ɡʥ��Ρ���������ˤϡ�ʪ���������������������ʤʶ�ʬ�ʤ����դ��Ĥ������ۤʤ뵯���������ʪ�����Ͽ��ˤ����¤��Ϳ��ʤ��ˡ������Ƥ椯�椯��ʪ�������Ĥ�������Ƥ���ָ��Τ�����פȤ��ƤΤ�����������Τ����������뤳�ȡʤȤ�櫓���줬������Ū�פ�ã������뤳�ȡˤ���Ԥ��롣�������äƤ��Τ褦�ʽ����Ǥ��뤫��ˤϡ���������ʤ륳�ץȼ��Τ�桼�饷����˹��ᡢ���ԡ�����ԡˤ�ʤ�ΤޤȤޤä����Ϥǽ���Ȥ��Ƥ⡢���줬���θ��ֿʹ֤��ȿ��פȤ��Ʊ�³����Ȥ������ȼ��Τ�̷��Ȥʤ롣�������ޥ˶���̷��Ϥʤ��ä����ޥ˶�����ɽ�����褦�ˡ���������ν����佡�ɤ��������������������Ǹ�¸���ʤ��Ȥ������Ȥϡ��ޤ��ˤ�������䤬�������줿�ڤʤΤǤϤ���ޤ��������ä��ͤ����������ʤ�ۤɤΤ��ȤʤΤǤ��롣
�º����ꡢ�����Ȥ��ƤΥޥ˶��ϡֻ���פ����������ɤ��Ǥܤ��줿��������ů�ؤ������ѤϤ����Ρ��μ��աʥ��Ρ������ˤȤ��ƻĤäƤ��롣�����ơ�����ϲ��٤Ǥ����褹�롣�ʤ��ʤ顢��Ϥ佡���Ǥ⽡�����ΤǤ�ʤ�����ˡ������ֿ��ġפ��뤫�ɤ����ϸĿͤμ�ͳ���̤�����Ǥ��롣�������äơ����Υޥ˶��ΰ���Ρ������פˤ⤫����餺�����켫�Ȥ���¸³��ߤ�פΤϡ��Ͼ�ȥ���˸����С��ֻȤ��ݤ��졢�Ȥ��ΤƤ���פȤ������ȤǤ��ꡢ���ļ����˸����С������˿ʹ֤Ȥ��ƤΡ����⤴��ʴ�Ӥ��ᤷ�ߤ����Ūж�ʡˡפ����ä����顢�������뤳�Ȥ��Ǥ���ΤǤ��롣
�����ϡ��Ѵ�����˺�����뤳�Ȥˤ�äơ����Ȥ�¸����Ū����������ʤ�����ޤ��ǽ�ˤ�����ͭ���ˡ־���פ���ʤ���Фʤ�ʤ��ˡ�
�ޥ˶��ζ����������ϡ���ˤ��ᤤ�����˻Ѥ�ä����ޥ˶��̤ˤ�ä�ã������뤳�ȤϤʤ��ä�����������ޥ˶���ͽ�𤷤��褦�ˡ����ߤ�ʹ���ο��ब�����������ޤ��ޤʡȥ��٥�ȡɤβ̤Ƥˡ�����������뤲����Ǥ��������֤���ɤ������褦�ס֤��Ĺ�������褦�פȤ������θ���Ū����¯Ū��˾�����絬�Ϥ��ġֽ���Ū�ʾ����פ�����������ֺǴ�Ū�������פ������뤲��Ȥ����Ǹ�����ž����ɤ�Ǥ��֤��ˤ����뤫��Ǥ��롣
�Ǹ�ˡ���ϰʲ��ΰ�ʸ�˺���ηɰդ�ʧ�äƻ�Ʊ����ȸ�������
�ä���ä����Ȥǡ��ޥ˶��ϡ�����ʿ�¤ν����Ǥ��ä����Ȥ���ˤΤʤ��Ǿ������Ƥ���Τ��Ȥ�䤿���ϻװԤ��롣<<��KHOORA SOPHIAAS
�ޤ��ˡ����Ǥӱ�����Τ˱ɸ�ͭ��פʤΤǤ��롣Viva, Cathar and Manicaeism!
* ���Τˤϡ֤�����ʪ�ϳ��ʤ��μ��Ǥ����ۤȤ������Τʤ����פǤ��롣
�ޤ������������
�֡�ά��ǽ���ͤ��Ƹ���С��±����±����Ȥ���˴�����ۤȤ��Ȥ�����������ʤ�˰ʤƼ¤ϴ�ʤ餺���ع���Ʊ�����ˤơ�̵����Ԥ������ʤ����뤬���ν��ɤ����ۤʤ�ɡ��⤷���ν��ɤ����ۤˤ��Ƽ¸�����졢������˶���������ɬ�פ���ͤ������ʤ��ʤ��ˤϡ��ع���ǵ���ѻߤ��줶���������ʤꡣ��Ƚ��Ȥ������ƹ��Ȥ�����ˡΧ�Ȥ������ࡢ�䤷�ƹͤ���С����ʤޤ����μ��Ǥ����ۤȤ���ˤ��餶��ʤ�����
�����θ��դ˽��ƽв�ä���������������ɽ����Ÿ��������ĥ�ȡ��ɤ�Ǥߤ�����������̤�Ȥ��������褦�Τʤ���ü���������˶ä��ȶ��ˡ�����������Ф����Τϡ���ʬ����Ǥޤ������˿����������λ��˴�ư�����ٽ����Ȥ����롣
�����ʤ�С����ǤӤ�פȤϡ���Ū����ä��ȿ������줿��Τ�����Ū��ã�����Ƽ����¸�ߤ��ä���Ȥ������ȤǤ��롣���ۤ�����ʤ�С��ʹ֤��ȿ��Ȥ��ƤΤ��������Ρʾ��ˤ�äƤϸĿ͡ˤȤ�����Τϡ����ε�ˤ���Ū�ϡּ��ǡפˤ��뤳�Ȥˤʤ롣�������Ǹ����ȡ�����μ�ĥ���붵�����������줽��Ǥ�����������顢�������ΤǤ����ּ��ʲ�áפ���Τ��Ǥ�餤������κߤ����פȸ��������Ǥ��롣����������С��ֽ������ɤ��Ƥ���פȤ���С����š��ٻ�����ˡ������¾��ɬ�װ���Ʊ�ͤˡ������Ͽ͡����Թ����ä��Ƥ��ʤ��Ȥ������Ȥˤʤꡢ����Ǥ���������Ƥ��ʤ������ʤ���������ָؤ�٤����ȡפǤϤʤ����Ȥˤʤ롣
�� �� ��
�ʤɤȡ������ޤǽƤ��ƺ����ο����դꥢ�åפ��뿴�Ť����ä������饤���Τ�������夬�ä��ꤷ�Ƥ��ơ������Ϥ����ʤ��ä�������Ⱥ��������ļ������ߤ���������褦�ʤ��Ȥ��ξ�ơפε�ǽ����Ū�Ȥ������Ȥ�����������Ƥ����������������������Ʊ���褦�ʻ�����Ʊ���褦�ʤ��Ȥ�ͤ��Ƥ������Ȥˤʤ롣���ļ����漼
���ĤϲϾ�ȥ������Ʊ�ͤ�...
�ٻ��������ۤϡ��Ⱥ�Ԥ����ʤ��Τǡ��ٻ������⤦ɬ�פǤʤ������פμ¸��Ǥ��롣�����Ʊ���褦�˿Ƥ����ۤϡֻҤɤ⤬��Ω���Ƥ��줿�Τǡ��Ƥ�¸����ͳ���ʤ��ʤä����֡פ�ã���Ǥ��롣����ά���Ҥɤ⤬��Ĺ���뤳�ȤϿƤδ�ӤǤ��ꡢ�Ҥɤ⤬��Ĺ���ƿƤ�ɬ�פȤ��ʤ��ʤ뤳�ȤϿƤ��ᤷ�ߤǤ��롣��Ӥ��ᤷ�ߤ����Ū��ж�ʤ���Ȥ����Τ��ʹ�Ū�İ٤��ܼ�Ū�����Ǥ��롣<<
�ȸ�롣�äˡ��Ǹ�Σ��Ԥ������Ƥ��롣�����ޤǤϹͤ������ʤ��ä��������ͤ���пʹ֤�̷��Ū¦�̤Ρֹ���פˤʤ롣
�� �� ��
���ơ����⤽�⤢�餿��Ʋ��Τ��Τ褦�ʲϾ�ȥ�θ��դ˺Ƥӻפ���ä������äʤ���Фʤ�ʤ��������10����������13�������˳ݤ���δ����ˤᡢ���θ奫�ȥ�å��β��ڤʤ��ư��ˤ�äƤĤ����Ǥ��������ɤΡ֥������ɡפ���ˤˤĤ��ơ��������ܤ���λ��������Ǥ⤢�뤬������֥������ɤ���Ԥ��뽡���פȤ����������ޥ˶��Τ��Ȥ�ͥåȤ�Ĵ�٤뤳�Ȥˤʤä������������ȡ��ͥåȤǸ��Ф����������Ǥ⡢���Ĥ��ν�������Ҥ����ä���
�ޥ˶��Ȥϡ�������Ⱦ�Хޥˤˤ�ä��ϻϤ��줿���������ǡ��桼�饷���ι����ϰϤˤ�����¿���ο��Ԥ�����������������פΤҤȤĤǤ��ä��������ϰϤ�������������ˤޤ���ã�����۶����������Ƥ��롣�����������̰������פ������륭�ꥹ�ȶ��ʥ����ޡ����ȥ�å��ˤ��Ϥ��դ���ˤĤ�ơ����Ρ�����Ū�����Ȱ���������ˤ�������Ω�����Ȥ�ޥ˶��ϡ�����ˡְ�ü*���۶��פȤ����ư�����Ƥ������䤬�ƣ������ˤϼ¼�Ū���Ǥ�����������ä��������Ρ���������ϡ�����Ū¸�ߤ�Ű�줷�����ꤹ��Τǡ������Ф��꤫�����٤�������Ū�˶ػߤ��줿�ʤȤ�櫓�����Ԥδ֤ǤϤ�����������ư�ؤ��ä����ʤ˵�̳�Ť����Ƥ����ˡ��ʤɤʤɡ�**
* �ذ�ü�������ɡ٤����ԡ��ե���ʥˡ�����ĥ����褦�ˡ��ޥ˶��ϥ��ꥹ�ȶ���������ȶ�ǤϤʤ��Τ����顢�ְ�ü�פȸƤФ��ΤϤ����������������äʤΤ������⤽��ҤȤĤν����γ�����¸�ߤ����Τ�ְ�ü�פ�Ƥ֤Τ���Ŭ�ڤǤ��롣�㤨��ʩ�����֥��ꥹ�ȶ���ü�ɡפǤʤ��Τ�Ʊ����̣�ǡ�
** ���ͥ����ȡ�Introduction of Manichaean Religion���ޥ˶����⡦���� @ KHOORA SOPHIAAS
����Ū���������ꡢ��¹��⤦���뤳�Ȥε��ݡ������˥ޥ˶����ֿʹ֤��ȿ��Ȥ��Ƥν������ΡפȤ��ơ��塹�����Ķ�����ޤ���¹���̤��ʱ�ˡֱɲڤ�ڤ���פ��ȤΤǤ��褦�Ϥ��Τʤ�����ɮ���٤���ˡ��������������Ф���롣���Τ��Ȥϡ����äƤߤ�Хޥ˶������Ρȶ����ɤ���ˡּ��ʲ��Τθ������ޤ��Ƥ����פ��ɤळ�Ȥ��ǽ�ˤʤ�Τ���
�ޥ˶�����Ĥ��Υ��ꥹ�ȶ���ü�ɡʥ��Ρ���������ˤϡ�ʪ���������������������ʤʶ�ʬ�ʤ����դ��Ĥ������ۤʤ뵯���������ʪ�����Ͽ��ˤ����¤��Ϳ��ʤ��ˡ������Ƥ椯�椯��ʪ�������Ĥ�������Ƥ���ָ��Τ�����פȤ��ƤΤ�����������Τ����������뤳�ȡʤȤ�櫓���줬������Ū�פ�ã������뤳�ȡˤ���Ԥ��롣�������äƤ��Τ褦�ʽ����Ǥ��뤫��ˤϡ���������ʤ륳�ץȼ��Τ�桼�饷����˹��ᡢ���ԡ�����ԡˤ�ʤ�ΤޤȤޤä����Ϥǽ���Ȥ��Ƥ⡢���줬���θ��ֿʹ֤��ȿ��פȤ��Ʊ�³����Ȥ������ȼ��Τ�̷��Ȥʤ롣�������ޥ˶���̷��Ϥʤ��ä����ޥ˶�����ɽ�����褦�ˡ���������ν����佡�ɤ��������������������Ǹ�¸���ʤ��Ȥ������Ȥϡ��ޤ��ˤ�������䤬�������줿�ڤʤΤǤϤ���ޤ��������ä��ͤ����������ʤ�ۤɤΤ��ȤʤΤǤ��롣
�º����ꡢ�����Ȥ��ƤΥޥ˶��ϡֻ���פ����������ɤ��Ǥܤ��줿��������ů�ؤ������ѤϤ����Ρ��μ��աʥ��Ρ������ˤȤ��ƻĤäƤ��롣�����ơ�����ϲ��٤Ǥ����褹�롣�ʤ��ʤ顢��Ϥ佡���Ǥ⽡�����ΤǤ�ʤ�����ˡ������ֿ��ġפ��뤫�ɤ����ϸĿͤμ�ͳ���̤�����Ǥ��롣�������äơ����Υޥ˶��ΰ���Ρ������פˤ⤫����餺�����켫�Ȥ���¸³��ߤ�פΤϡ��Ͼ�ȥ���˸����С��ֻȤ��ݤ��졢�Ȥ��ΤƤ���פȤ������ȤǤ��ꡢ���ļ����˸����С������˿ʹ֤Ȥ��ƤΡ����⤴��ʴ�Ӥ��ᤷ�ߤ����Ūж�ʡˡפ����ä����顢�������뤳�Ȥ��Ǥ���ΤǤ��롣
�����ϡ��Ѵ�����˺�����뤳�Ȥˤ�äơ����Ȥ�¸����Ū����������ʤ�����ޤ��ǽ�ˤ�����ͭ���ˡ־���פ���ʤ���Фʤ�ʤ��ˡ�
�ޥ˶��ζ����������ϡ���ˤ��ᤤ�����˻Ѥ�ä����ޥ˶��̤ˤ�ä�ã������뤳�ȤϤʤ��ä�����������ޥ˶���ͽ�𤷤��褦�ˡ����ߤ�ʹ���ο��ब�����������ޤ��ޤʡȥ��٥�ȡɤβ̤Ƥˡ�����������뤲����Ǥ��������֤���ɤ������褦�ס֤��Ĺ�������褦�פȤ������θ���Ū����¯Ū��˾�����絬�Ϥ��ġֽ���Ū�ʾ����פ�����������ֺǴ�Ū�������פ������뤲��Ȥ����Ǹ�����ž����ɤ�Ǥ��֤��ˤ����뤫��Ǥ��롣
�Ǹ�ˡ���ϰʲ��ΰ�ʸ�˺���ηɰդ�ʧ�äƻ�Ʊ����ȸ�������
�ä���ä����Ȥǡ��ޥ˶��ϡ�����ʿ�¤ν����Ǥ��ä����Ȥ���ˤΤʤ��Ǿ������Ƥ���Τ��Ȥ�䤿���ϻװԤ��롣<<��KHOORA SOPHIAAS
�ޤ��ˡ����Ǥӱ�����Τ˱ɸ�ͭ��פʤΤǤ��롣Viva, Cathar and Manicaeism!
20:09:50 -
entee -
TrackBacks
2006-04-15
�������ɿ������Ƚ
�����ָ����ȱ����줿���פȼ����Ū�ķ����� [10]
�ȣ��ɤλ�����ָ���Ū�������סʲ���
���ֻ����ܡפ�ɽ���ֻ�����ξ�ħ�פ��о�
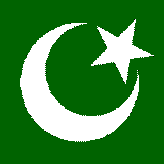
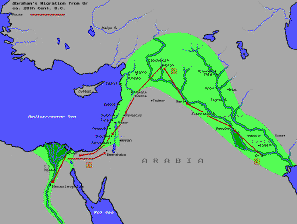
���祹������Ρ�ʬ��: schism�פˤ�äƿ���ο���ǻ�����Ƥ���������������Ū�˼��β������Ǥܤ������Ĥ����װ��Τ�����������ڤؤ�ʪ��Ū�����Ȥ����ˤ��ľ��Ū�ʴ�Ϳ���Τ�����ζ����ȤȤ��ƤΥɥ��Ĥ�¤�륲��ޥ�̱²�ΤϤ��餭�Ǥ��뤬���ä��Ʋ�����̵��Ǥ��ʤ��Τ����Ϥ���礹�륤��������Ǥ��롣�����Ƥ����Ǥ����ϥ�����ඵ���ֻ�����ξ�ħ�פ��ݻ����Ƥ��뤳�Ȥ�פ��Ф��ʤ���Фʤ�ʤ���
�ֻ������ħ�פ�������ඵ�Υ���ܥ�Ǥ��뤳�ȤˤĤ��Ƥϡ������Τ��Ȥʤ���ָ���Ū�������פȤ��������Ū���ԥ����ɤ�ȼ���Ƥ��롣������ඵ�Ȥ���������ʶ���ʤ��ַ�פˤ�äƾ�ħ����뤤���Ĥ�����������«������äƤ��뤳�Ȥϻ���Ǥ��ε��ҤФ����Ȥ��Ǥ��롣�ʥ��ꥢ���ǡإ���ܥ�Ƚ����ٻ��ȡˡ��������줬��Ѳ������Ȥ�����Ⱦ��פ������פǤϤʤ��ֻ�����פǤʤ���Фʤ�ʤ��ä����Ȥˤϡ�ñ�ˡַ�פȤ��Ƥ�ǧ�Τ��䤹���Τߤʤ餺��ʣ��Ū�ʰ�̣�礤������ϸ��Ф����Ȥ��Ǥ��롣
�¸��ԥޥۥ�åȤ˺ǽ�ο�����ˬ�줿�Τ��ֻ�������աפǤ��ä��Ȥ���ͭ̾�����ä��ֻ�����פκ���ΤҤȤĤǤ��롣����������줬�����դ��ʤ���Фʤ�ʤ��Τϡ������������äλ��äƤ�����Ťΰ�̣���Ǥ��롣����ϼºݤˤ��δ��פ����������뤬������ʱ�����ˤ��裳���Ǥ��ä��Ȥ��������Ū���¡פ���ã���뤳�Ȥ�������Ū������ΤǤϤʤ��ʤ��켫�ΤˤϾ�ħŪ��̣�礤���Ƥʤ���significance��ʤ��ˡ��ष����ä��礭�ʤ����Ρ���˻���פˤ����ơ��ޥۥ�åȤ��о�ʥ�����ඵ���ֶ��ˤ��ʾ�ħŪ�ʡˡ��軰���ɤǤ��ä��Ȥ������Ȥ����ã����ΤǤ��롣
�����ᥭ�ꥹ�ȶ����붵���ϲ���̮��é�뤳�Ȥ��ķ�Ū��������Ρֿ����פμºߤ�������Τ���Ū�Ǥ���ΤǤ����ǤϿ����ꤷ�ʤ�����������ඵ��¸�ߤȡ���«���줿���˸����뾭��ˤ������������ϡ����������붵Ū�������ʸ̮����˴������Ȥ߹��ޤ�Ƥ��뤳�ȤǤ���Ȥ����������Ǥϵ����Ƥ������ξ��������Ū�ʾ�������ȡ㻰�������������Ρ٤Ǽ㴳�ξܽҤ�ͽ���
�� �������ȤΡֿ������������������λҶ�������17���� �沤���첤��
�ֿ������פλ������ִ��ˤ������濴�������Τ������θ�����ȤˤʤäƤ������ɥ��Ĥ������첤�����ޤ�ʻ���������ä��˥衼���åѤ���Ǥ������˹��Ϥ����ڤ�ޤ��ϰ�Ǥ��롣����Ϥޤ��ˡ��裳�Υ����ޡɤȤ�����٤��������������Τ��ȤǤ��ꡢ���Τ��λ���ˤ���������̵�뤹��櫓�ˤϤ����ʤ������ΡֺǸ�Υ����ޡפ�Ĺ���ֻ��λ���פκǽ����̤�ޤࡣ���ʤ��962ǯ�˥��åȡ�1��������ˤ��������ĥ�ϥͥ�12���ˤ�äơ�������������ηѾ��ԤȤ��ƹ�����״������Ȥ��˻Ϥޤꡢ������ǯ����פθ塢1648ǯ�Υ������ȥե��ꥢ����ˤ�ä������μ����Ω�縢��ǧ���졢����300���μ��Ȥ�ʬ������ޤ�³�����ۤ�700ǯ��³��������¯������������ζ����Ȥο����߽Ф��ھ��Ȥʤ�����פʤΤǤ��롣
�����ƿ������������ϡ��ɥ��IJ���ʥե����ˡ������ꥢ���֥륰��Ȳ���Ȥ���������֣��Ĥ�Ϣ�粦�������ޤ��뤳�Ȥˤ��������դ�����ʤ���Фʤ�ʤ������Τ褦�ˡ���ޤ�����ʲ���ˤο��פȤ����Τ������������Ʊ���˾�ħ����Ȥ����Τϡ��¤ϥ����ޤ�������Ĥ�ʬ�Ǥ��줿�����˻Ϥޤꡢ���Ρ֣��Ĥ�Ϣ�粦��פ˰����Ѥ��졢��˲ڳ��������濴Ū�����ˤ������ħŪ��ȹ��ۤΡ��ķ��פȤʤäƤ����ΤǤ��롣
���λ���κǽ����̤ˤ����ơ��������ȥե��ꥢ����ˤ�äƲ��Τ��줿�������������ϡ�������ơ���ˤ�äơֿ����ǤϤʤ�����������Ū�Ǥ�ʤ�������ɤ��������Ǥ���ʤ�: The Holy Roman Empire is neither Holy, nor Roman, nor an Empire. / Ce corps qui s'appelait et qui s'appelle encore le saint empire romain n'?tait en aucune mani?re ni saint, ni romain, ni empire.�פȤ�����������餵�줿�����ΡֺǸ�Υ��������פκ�ʬ�������������Ϣ�ʤ�ֿ������פ�����Ū���ݻ������ޤޡ������������μ�������ڤ˼����ΤǤ��롣
�� �����Ȼ���Ρֻ��������ۤλ���
����Ū��Ȥ������ι�ξ�ħŪ���פȤ��ơֿ������פ���äƤ��뤳�Ȥϡ������ǤϤ����Ρ�������̤��ƺǤ�ͺ�ۤ�ɽ������롣���߲����ǿ�����ο����Ȥ߹�碌�������ΤΡ�����������äƤ���ϼ�ˡȣ��ɤ˾�ħ�����ƹ�β����Ф���ˡ���ˤ����״����סʻ�̾�����������ˤ����ꤹ�븢��Ū�ȿ��Ȥ��ƤΥ����ޡ����ȥ�å��ʤ��ʤ�����������ν����ˤˤ����ۤ��������ʸ�˥ץ��ƥ������¦�˰��ؤ������Τ�ޤ�ơˡ��⤷���Ͽ������������ΰ����������Ƥ����Ǥ��롣���Τ��Ȥϡ��ֿ��������������ʤ����ƣ��ˡפ�³���ֿ��οʹԡ������οʹԡפ�ʸ̮��̤�����Ƥ˸��̸������ǤϤˤ狼�ˤ��ʲˤ������ȤǤ�������
�ֹ����֡����פλ������ϡ��ɥ��ġ��٥륮�������С����֡פ������ꥢ���ϥ�����С�������פ���������ɡ�����ɡ��ޤ�������������¹�ˤȤʤäƤ��롣�ü�ʤȤ����Ǥϡ��ġݲ����֡פλ�����*���Ѥ����롼�ޥ˥��ȥ���ɥ餬���롣���ġ����֡פλ������Ĵ�Ȥ����Ȥ˥ե�����������륯����֥륰���ʤ���˵�������������������ˤ����롣
�����ϰ���Ū�˱ѡ��Ƥι����ֻ������פȤϸƤФʤ���������Ǥ���ġ������: Blue, White and Red / Red, White and Blue�פλ������Ĵ�Ȥ��뤳���ʩ���ѡ��Ƥλ���ϡ����ζ�ͭ���뿧�������褦�ˡ��������ޤ��ˡֻ��̰��ΡפǤ��롣�����ơ�������˿�̱�Ϥ���Ĥʤ��������Ф������Ū�Ƹ�������������ĹǤ���ʤ����Ǥϼ��夲�ʤ��ä�����Ʊ�ͤλ���������ĥ�����**�⤽��������Ȥ����ϳ��ʤ��ˡ�����������γƲ��ϴ��ˤ����ƶ����礤���ޤ���������äƤ����ط��������Ȥ�櫓ʩ���ѡ��ƤΣ���Ρְ��δط��פ�20������Ƭ������켡������ξ����������̤���ǻ���ˤʤäƤ�������Ҥ��뤬���ä˥����饨������Ϥ�Ȥ��������������äơ����Σ���δ֤ˤϤ����Ρֿ�����碌�פ�¸�ߤ��뤫�Τ褦�˰��ذ��δ���Ƥ����Ȥ����������ܷ⤷�Ƥ��ꡢ���λ��¤�����ϴ���̵�뤹��櫓�ˤϤ����ʤ����ޤ���ˤ����פ��Ф����Ȥˤʤ�Ǥ�������
* �롼�ޥ˥��ϥ����ͤι���ɥ�ϥե�ȥ��ڥ���˶��ޤ줿�ԥ�͡��ξ����ߤϥե�������Ρ���¯���ˤȥ��ڥ���λʶ����������ˤˤ�ä������������Ƭ���ι�ȡ����λ������ϡ��֥�ϥͤ��ۼ�Ͽ�פˤ����Ƹ��뤵�줿�֣����ε�ʼ��פλ����ζ����Ƥο��˰��פ��뤳�Ȥ����ܤ��٤��Ǥ��롣
** ���ߡ��������λ������Ͼ夫����֡����ġפλ����ˤʤäƤ��뤬�����־�Ρ��֡פϰ����ϡ֥���פǤ��ä����Ȥ��Τ��Ƥ��롣����������ꥢ��ʥ����ꥢ�ࣳ���ˤΥ���ܥ�ˤ��ʤ����Τȸ����Ƥ��뤬��������Υȡ����ݻ�����Τ�����Ū�˺���ǡ�����֤ˡ��ѹ��פ��줿�Ȥ������������롣�������������ե��̿�ˤ��ƶ����Ȥ�ʤ��ä����������ּ�ͳ��ʿ������פ���ǰ�Ȥ��Υ���ܥ�Ǥ��뻰������³�����ȹͤ���Τ������Ǥ��롣�������ϥե��̿�塢���ܹ�ξ��ǡפȤ������֤����ä��������Υ������ζ���ˤ������ϰ̤η��Ѵ��ˤ⡢Ĺ��ν���ξ���Ĺ�ɥ����դϥ������λ�������Ǥ�³�����ƶ����줿�������˵������鷮�Ϥ�����Ƥ��롣�����������1630ǯ�ʹߡ��֥�������ġפ��鸽�ߤΡ��֡����ġפ��Ѥ�ä��ΤǤ��뤫�顢����ˤϤ����餯���߲桹���Τ��Red White & Blue�ɤ�Trois Coleurs�����Ǥ˸���줿�Ȥ������Ȥ������Ǥ���ΤǤ��롣
�� �ֿ������פθ����Ȥ��ƤΥե��


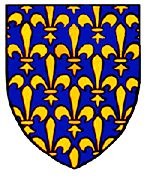
���ǰ����衧
���塧Armes de la Maison des Bourbons de France (avec les Fleurs de Lys : symbole de la royaut? de Charlemagne) @ Histoire et Documents
�塧Philip II the King of France @ Wikipedia
�Х륫��Ⱦ�礫�������������ˤ����ƤΥ衼���åѤDZƶ�����äƤ�����������������ʿ�Ԥ��뤫������Ĺ���ˤ錄�긷����¸�ߤ�³���������ޡ����ȥ�å��θ��Ϥ�����뤿�����¯�����Ȥ��Ƥ��Ρ�ʸ����Ū�ƶ��Ϥ����³�����Τ��ե�Ǥ��롣�����Ƥ�����ֿ������פ�ɽħ���ĥ��³�����Τ��ե�Ǥ��롣
�ե�ˤ����Ƶ����뤽�λ����褹���礭�ʻ���Τ����Ĥ��ϡ����ι�������ħ�����ΤǤ��롣���֤Ϥ�����λ�����̤뤬�����Τ����ΤҤȤĤϡ֥���ӥ��祢�������פȸƤФ���絬�Ϥʷ�����ư��ޤ�ְ�ü�ץ������ɡʥ���ӥ��祢�ɡˤ��Ф���Ű��Ū�ʽ����ư��Ǥ��롣�����12����������13������Ƭ�˳ݤ��ƹԤʤ�줿��Τǡ������Ϥˤ���������ޡ����ȥ�å������Ϥ�θǤ��餷��֥ե�סʲ��ȡˤ����ڳ����⤿�餹����ˡ�¿��ʰ�̣����Ĥȸ�����Ǥ������������Ƥ⤦�����ϥե�Ρ���Ω��ȡפȤ��Ƥκ���δ����ȡ����κݤ��θ����줿�ּ���פȤ��Ƶ���������ΤǤ��롣����ϥ����ꥹ�Ȥδ֤�Ʈ��줿��ɴǯ���� (1337-1453) �פǤλ���Ǥ���ȸ��äƤ����ǤϤʤ���������
�� ���������ư��ΰ�̣���뤳��
�������ɤ��ư��ϡ�����к����Υե���ڤζˤ���礭���ϰϤ��������������Ȥ�Ƥ֤٤�����Ū���ݥå��Ǥ��롣���ꥹ�ȶ�����Ω���˴��˵�Ͽ����Ƥ��륫�����ɤ�¸�ߤϡ����λ���������Ʈ����Ԥ줿����¼�Ū�˥��ȥ�å�¦�������Ū�ˡְ�ü�פȤ�����åƥ��Ž���Ƥ��뤬������ϤҤȤĤ��礭�ʽ�����ư��Ĭή�Ǥ��ä����������ɤϥ��Ρ���������ΰ��Ǥ��ꡢ���Ρ���������Ȥϡ֥�������������������ů�ء�����ӥ��ꥹ�ȶ��λ���Ĭή�ι�ή���˰��֤����礭�ʻ��۱�ư�Ǥ��ä�*�ס�
�����Ƥ��λ��ۤȤ�ñ�㲽�줺�˵����С������Ȱ��������פȤ�����ΤǤ��ä��Ȥ����ͤ�����Ǥ�����������������������ñ�ʤ�������Ǥ��ä����Ǥ���Τϴ����Ǥ��뤬���������ɤλ��ۤϥ��ꥹ�ȶ���Ω�����ˤ��Ǥ˵����Ƥ�������������Ū�����Ѥ�ȿ�Ǥ��������Ʋ����⸽����ְ��ε�ˤθ�������ʪ������*�פȴѤ롣�����ˤϡְ��פ�¸�ߤ����ζȤ����ڤ�Υ����Ƹ����ȼºߤ���Ȥ��������Ѥ����롣�����Ƥ��θ����������Ǥܤ���ʤ���Фʤ餺���椯�椯�Ͽ������ˤλ��ۤ�ˬ���Ǥ��������Ȥ����ͤ��Ǥ��롣
�����������Ρ��������������216ǯ�˥Хӥ��˥������ޤ�ʤ�������Ū�ˤϥڥ륷��͡˥ޥˡʥޥͥ��ˤˤ�äƻϤ��줿�������֥ޥ˶��פ˼����Ѥ���롣�����Ƥ��ν���������������ˤ���ʤ�ο��Ԥ�롣��˥��ꥹ�ȶ��ˡֲ����פ��������������ƥ��̥���ǽ�ϥޥ˶��̤Ǥ��ä����Ȥ�ͤ���С����������Υݥԥ���ƥ�����Ľ����Ǥ���ů�ػ��ۤǤ��ä��ȹͤ��뤳�Ȥ��Ǥ��롣���뤤�ϥޥ˶�����Υ��ꥹ�ȶ��Ȥ������罡���˹�ή����췲�γؼԤ修�Ԥ����٤ޤȤᤢ���뵡ǽ��̤������Ȥ������Ȥ�Ǥ��뤫�⤷��ʤ����ޥ˶����Τϡ��ޥˤ������Ƥ���������Ѷ�Ū�˻ٻ����ѥȥ���λ���ȼ����®�ˤ��αƶ��Ϥ��ΤǤ��뤬�����θ��800ǯ�ʾ���Ϥä��͡��ˡְ�ü�פȷ��Ĥ����륭�ꥹ�ȶ����ɤȤ���̾�Τ��Ѥ��ʤ��顢�ϲ���̮Ū�ʥ��Ρ������λ���ŪĬή�Ȥ���������Ӥ���
���Υޥˤζ��������Ρ�������ΤҤȤĤǤ��뤳�Ȥ���������Ǥ��褦������������ʪ������ʻ¸�����ʤ���ֿ��������ˤ�ʪ�������Ρˤ�����Ū����ʻ¸*�פ�ǽ������Ȥ��롣�Ĥޤ�����Ū¸�ߡʰ��ˤ����ʤηײ�ˤˤ�äƻ��߽Ф��줿��ΤǤϤʤ����ְ��פʤ�����ʪ���פȤ��Ƽ��Ϥ�¸�ߤ��뤳�Ȥ�ǧ��������ʤΤǤ��롣�Ĥޤꤳ�Τդ��Ĥ���Ω�����ܼ�Ū¸�ߤξ�ˡ־�̤ο�*�פ����ꤵ��ʤ��Ȥ����ˤ��λ���ŪĬή����ħ�����롣�����ޤΡ���ή�פ��餹��С����줬�������ɤ����������Ū�ȷ��Ĥ���Ű����Ƚ������¤Ȥʤä��櫓�Ǥ��롣
* ���͡��ե���ʥˡ������ذ�ü�������ɡ١ʥ�������ʸ�ˡˤ��
�����������ޡ����ȥ�å��Τ��θ�˳��֤��붵���Ȥϡ��ޥ˶��ʾ�ˡ֤��ӤġפǤ���Ȥ����פ��ʤ��ֻ���ʤư��ª����סȻ�������Ū�������Ǥ��ä��Τϡ������Τ��Ǥ��Τ�Ȥ����Ǥ��롣��������ŷ��ˤ��������ˤ��Ͼ�Ū¸�ߤǤ���椬�ֿͤλҡפȡ������դ��Ĥ��ӤĤ������פȤ��ƤΡ�����פ�¸�ߤ��Ѷ�Ū��ǧ��뤳�Ȥǡ��֤���ϤҤȤĤο��ʤΤ���ͣ����ʤΤ��פȤ��������ؤ�ȯŸ���ʲ����롣

���ǰ����衧Philip II the King of France @ Wikipedia
��ȴ��˲��Գ��ξ�ħ���������֥ե���åס������她�ȡפȤ�ƤФ�륫�ڡ���ī�β����ɥ��Ĺ����Ϣ�礷�������ꥹ�����̥ե��å�Ԥ�����1214ǯ�˱�ͺ��ɾ������롣�������ɤ��Ф���Ű���ư��Ԥ�������Υ���ƥ�����������̿�ˤ���ȿ����줿�֥���ӥ��祢�������פȤ�����ʩ����ˤ����밭̾�⤭��üƤȲ�����ä�̿�����롣�ºݤ��ؤɤ��ΰ�ü��Ȳ�����Ω�����餺�˲��γ���Ȥ�����̣��ž������ࡣ
���ʤ����12����������13�����˳ݤ��ơ֥ե롼�롦�ǡ���פξ�ħ�������ե���Ȥˤ�äƹԤʤ�줿�֥ͥ����ޥ˶��̡פȤ�ƤФ��٤��������ɤ��Ф���Ű��Ū�ʽ����ư��ϡ��ֿ������פξ�ħ����Ŀ͡��ˤ�롢������������Ĥ�Ρֿ������פ��ݻ��Ԥ��������Ǥΰ�̣�����ä���ª���뤳�Ȥ��Ǥ���ΤǤ��롣
�� �ե�ȡ�ɴǯ�����
14����Ⱦ������1337�ˤ˳��Ϥ��졢�ޤ�ޤ룱�����ʾ���ϤäƷ��깭����줿ɴǯ���褳�������ߤΥե�β��̷Ѿ������ĥ�����֣��͡��ηѾ�����Ԥ��о�ˤ�äƻϤ����ʤ�����ΤҤȤ꤬������Φ�ؤ�����Ū�����äƤ��������ꥹ���ɥ�ɻ����Ǥ��ä��ˡ������ơ�����ɴǯ�ʾ���Ϥä�³����줿�ե�αѹ�Ȥ�Ʈ��ϡ�����������ˤ�����ե��̱²�ȹ��ڤ������θ�ζ����ȥե�ؤ�Ϣ�ʤ����ư������ˤ����ơ��ҤȤĤμ�ΩŪ�ռ������Ū�˺��դ���������ζ�������ä�ʸ���̤�ּ���פβ����Ǥ��ä���
���������Ū�ˤϡ֥����������������ס��᤹������ˤ˻Ϥޤ벦�̷Ѿ������ȯü�Ȥ����ʩ�֤Ƿ��깭����줿���ϹԻȤ�ޤ�Ĺ��Ū����Ω�Ǥ��ꡢ�����Ф��Ϥ�ּ������פ���ѹ���ऱ���αƶ������æ�Ѥ�ʤ���ΤȤ��Ƥΰյ��⤢�롣�����Ƥ���ϥ����̡����륯���о�Ȥ��Ρֵ���Ū����פʤ����ֿͿȶ����פˤ�äƷ�Ū������Ĥ������Ū���ݥå��Ȥʤ롣
�ե�ˤ����ƽ��������ԤȤ��ƹ����ɽ�������ͤȤʤä��Ȥ������¤ϡ��ե�λ��Ĺ�̱���Ȥ⽸��Ū̵�ռ���ȿ�ǤȤ�������������ƾ�ħŪ�Ǥ��롣�����ʡ����ˤ�������ɽŪ�о��ʪ�Ǥ��륭�ꥹ�ȤȻ��̤Τ������δط������ɤ߲���о��ʪ����䤬���衼���åѤζ����ȤΤ����Ĥ������ƤϤ����Ȥ������ȡ������Ƥ��������Ʊ�������dzθǤȤ����ʤ����Ⲽ�ռ�Ū�ʡ������̿Ū��ô�äƤ��벤���ι�ͤ����Ȥ����ե�ˤ�������ɽŪ�οͤ�¾�ʤ�̽����Ǥ��ä��Ȥ����Τϡ�Ǽ���Ǥ��뤳�ȤʤΤǤ��롣����Ͻ����̤Ȥ��ƤΡ֥ޥ�����Υޥꥢ�פȥե�δ֤˰ż������ط�*�ˤĤ��ƤǤ���Ȥ����Ǥϰ줳�ȸ��ڤ��Ƥ������Ȥ�α��롣
* �����ǤϾܽҤǤ��ʤ�����������̾���Ǥ��Τ���Ρ��ȥ����: Notre Dame�ʲ�餬���ؿ͡ˤϡ��̾������ޥꥢ�פ��̣������̾��Ȥ��ƿ������Ƥ��롣�����������ƥꥺ��������ˤ����Ƥ���ͤΥޥꥢ������ޥꥢ�ȥޥ�����Υޥꥢ�ˤδ֤ˤϡ��֥ޥꥢ�פȤ��������ɤ�����뤢���Ρְտޤ��줿��Ʊ�פ����ꡢ�ҤȤĤν���Ū�����ˤ�ä�ɽ�������ΤΡ֤դ��Ĥ�¦�̡פ�ɽ����ΤǤ���ȹͤ���������ΰ������ͳ�����롣�����Ƥ����ʤ��ͭ��̾�ΤǸƤФ�褦�ȡ��֥��ꥹ�ȶ���פȤ���¸���Τ����ְ�©���˵Ҥ��ꥵ���ӥ�����פ��Ȥ���ʤʤ�襤�ˤȤ��Ƥ������ǡ���ʡ����ˤ�����ޥ�����Υޥꥢ�Υ��ԥ����ɤλؤ�������ΤȤθƱ���������ΤǤ��롣
������ˤ��衢�֥ե�פȤ����������ͤ�Ϳ����줿������̾�ˤ�äƤ������ΰ����դ�������Ƥ���ʾ塢���λ���ʡȣ��ɤλ���ˤ�褹����ԤϽ����Ǥʤ�ʤ���Фʤ�ʤ��ä���


���ǰ����衧Joan of Arc @ Wikipedia
�����̡����륯���о�Ȥ��λ� (1430ǯ)�ϡ��礭�����ष���Ѥ����ե���ڤαѹ���ɱҤ���Ω�η����Ȥʤä������η�̡��ե����Ω�ΡȽ���ɤȤ��ƥ����̡����륯��ǧ������Ƥ��롣�������������ä��Τϴ��˸��ڤ����֥ե롼�롦�ǡ���פˤ�äƾ�ħ�����ե���ȤʤΤǤ��ä��������ơ��᤹�����������о����Сפ������ε����ȤʤäƤ���ΤǤ��롣
�ե�ȡȣ��ɤδ�Ϣ�ϡ����̰��Τ�ɽ�����Գ��ʥ����ΰ��ˤ���� (fleurs des lys)���ե���Ȥ���ϤȤʤäƤ��뤳�Ȥ䡢�����ȤȤ��ƤΥե���������������Ƥ���Ȥ������Ȱʳ��ˡ��֥ܥ�ɡ��ν����: the Pilgrim of Bordeaux�פ�������333ǯ�˿����ͭ̾������ΤҤȤġ����å��ޥͤξ��ȿ������Ƥ���֥���ֻ���ϼ�פ����Ϥ�ˬ�줿�Ȥ����Ť���Ͽ�����Ǥ���*��(Catholic Encyclopedia)
* ����ʳ��ǤϹ�����äι��ֹ椬�ե�ϡ�33�פˤʤäƤ��뤳�Ȥ�̵�뤹�뤳�ȤϤǤ��ʤ���
���ȣ��ɤλ���Ȼ��̰��Τ��ܼ��ʤޤȤ��
�����ޡ�������å�����������ȻҤ�����פ����ΤǤ���Ȥ������̰������Doctrine of Holy Trinity�ɤ�ή�ۤ���ĥ�ܿͤǤ���Τϡ��ѤƤ����̤�Ǥ��뤬��������ϻ��Ĥΰۤʤ�¸�ߤ���Ʊ��פǤ���Ȥ����ֿ����פ�������ʤ����ƺ������ˤ�衼���åѤε����˰䤹���Ȥ���Ū�Ǥ��ä����Τ褦�Ǥ������롣���Υ����ʥ����ĥХ��ˤ���Ϥ�Ϥ�Ȥ����������ϡ����λ��Ĥβ��ۤ���Ĥ�«�ͤ��뤽�ο�����ʤơ����Ρְ������פ��ħ���Ƥ���ΤǤ��뤬������ο������Ƥ����Τϡ�ʶ���ʤ��ֿ������פǤ��롣�ֻ��̰��Ρ��⤳������ȻҤ�����פ�Ʊ��Ǥ��롢�Ȥ������Ū��������ʸ����μ�������������ΤǤϤʤ��������ñ�������˸����ơֿ������פ���ˤ˼���������о줷����¾�ʤ�ʤ����˸����Ƥ��롣�����⡢����Ρֻ��̰��Ρ�������������Ǯ�������줬���Ū�ˤ���ʤ����Ĥ����������ˡ������Ƥ��줬˽��Ū�ʤޤǤΡְ�ü����פ��̤��Ƥλ����ư�����ޤ��������ݤ�Ϳ��˰����������ҤȤĤΥ������ħ�ˤȤʤä��������Ƥ��α�ư�����������Ƥ��ܼ��Ȥϴؤ��ʤ�����̣�Τ���ҤȤĤ��Ϸ�Ū������Ȥ��ƿ���˵��������Ȥ������ȤߤˤʤäƤ����Τ���
���˾�ˤҤȤĤλ��夬����ꡢ���λ���ذܹԤ���ݡ��礭�����𤬵����롣�ȣ��ɤλ��夫��ȣ��ɤλ���ؤΰܹԤǤ⤽����㳰�ǤϤʤ��ä�����ˤ�����ϥ衼���å����ڤ��顢�ɡ�������������ۤ��ơ��衼���åѡ��ն������ϡפǤ���֥�ƥ���˰ܤ롣���Ū�ˤ���줬�ʲ�Ȥ����ˤ��С��֥إ�������Υ�����������פΤȤ�����¯Ū��ߤ������ˤʤꡢ�����ޡ�������å��μ�������ƨ���٤��ѹ�ī�ϡ�1534ǯ���Ĥ��˥����ꥹ�����Ω��������롣�����ƺ��٤ϡ�����ǻ���ʿ�������������ħ�������ä��͡��������ꥹ��������ʤ�̡֤���ħ�פ���ᤫ���ʤ��顢�̾���ư�ȾΤ������������Ӳ�롣��餳����������դ�����å��㡼�פȤ��ơ��ܳ�Ū��ư������ΤǤ��롣
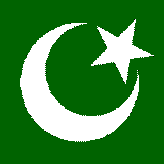
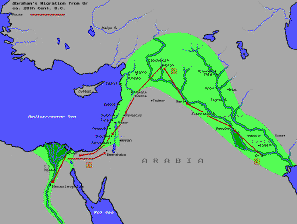
���祹������Ρ�ʬ��: schism�פˤ�äƿ���ο���ǻ�����Ƥ���������������Ū�˼��β������Ǥܤ������Ĥ����װ��Τ�����������ڤؤ�ʪ��Ū�����Ȥ����ˤ��ľ��Ū�ʴ�Ϳ���Τ�����ζ����ȤȤ��ƤΥɥ��Ĥ�¤�륲��ޥ�̱²�ΤϤ��餭�Ǥ��뤬���ä��Ʋ�����̵��Ǥ��ʤ��Τ����Ϥ���礹�륤��������Ǥ��롣�����Ƥ����Ǥ����ϥ�����ඵ���ֻ�����ξ�ħ�פ��ݻ����Ƥ��뤳�Ȥ�פ��Ф��ʤ���Фʤ�ʤ���
�ֻ������ħ�פ�������ඵ�Υ���ܥ�Ǥ��뤳�ȤˤĤ��Ƥϡ������Τ��Ȥʤ���ָ���Ū�������פȤ��������Ū���ԥ����ɤ�ȼ���Ƥ��롣������ඵ�Ȥ���������ʶ���ʤ��ַ�פˤ�äƾ�ħ����뤤���Ĥ�����������«������äƤ��뤳�Ȥϻ���Ǥ��ε��ҤФ����Ȥ��Ǥ��롣�ʥ��ꥢ���ǡإ���ܥ�Ƚ����ٻ��ȡˡ��������줬��Ѳ������Ȥ�����Ⱦ��פ������פǤϤʤ��ֻ�����פǤʤ���Фʤ�ʤ��ä����Ȥˤϡ�ñ�ˡַ�פȤ��Ƥ�ǧ�Τ��䤹���Τߤʤ餺��ʣ��Ū�ʰ�̣�礤������ϸ��Ф����Ȥ��Ǥ��롣
�¸��ԥޥۥ�åȤ˺ǽ�ο�����ˬ�줿�Τ��ֻ�������աפǤ��ä��Ȥ���ͭ̾�����ä��ֻ�����פκ���ΤҤȤĤǤ��롣����������줬�����դ��ʤ���Фʤ�ʤ��Τϡ������������äλ��äƤ�����Ťΰ�̣���Ǥ��롣����ϼºݤˤ��δ��פ����������뤬������ʱ�����ˤ��裳���Ǥ��ä��Ȥ��������Ū���¡פ���ã���뤳�Ȥ�������Ū������ΤǤϤʤ��ʤ��켫�ΤˤϾ�ħŪ��̣�礤���Ƥʤ���significance��ʤ��ˡ��ष����ä��礭�ʤ����Ρ���˻���פˤ����ơ��ޥۥ�åȤ��о�ʥ�����ඵ���ֶ��ˤ��ʾ�ħŪ�ʡˡ��軰���ɤǤ��ä��Ȥ������Ȥ����ã����ΤǤ��롣
�����ᥭ�ꥹ�ȶ����붵���ϲ���̮��é�뤳�Ȥ��ķ�Ū��������Ρֿ����פμºߤ�������Τ���Ū�Ǥ���ΤǤ����ǤϿ����ꤷ�ʤ�����������ඵ��¸�ߤȡ���«���줿���˸����뾭��ˤ������������ϡ����������붵Ū�������ʸ̮����˴������Ȥ߹��ޤ�Ƥ��뤳�ȤǤ���Ȥ����������Ǥϵ����Ƥ������ξ��������Ū�ʾ�������ȡ㻰�������������Ρ٤Ǽ㴳�ξܽҤ�ͽ���
�� �������ȤΡֿ������������������λҶ�������17���� �沤���첤��
�ֿ������פλ������ִ��ˤ������濴�������Τ������θ�����ȤˤʤäƤ������ɥ��Ĥ������첤�����ޤ�ʻ���������ä��˥衼���åѤ���Ǥ������˹��Ϥ����ڤ�ޤ��ϰ�Ǥ��롣����Ϥޤ��ˡ��裳�Υ����ޡɤȤ�����٤��������������Τ��ȤǤ��ꡢ���Τ��λ���ˤ���������̵�뤹��櫓�ˤϤ����ʤ������ΡֺǸ�Υ����ޡפ�Ĺ���ֻ��λ���פκǽ����̤�ޤࡣ���ʤ��962ǯ�˥��åȡ�1��������ˤ��������ĥ�ϥͥ�12���ˤ�äơ�������������ηѾ��ԤȤ��ƹ�����״������Ȥ��˻Ϥޤꡢ������ǯ����פθ塢1648ǯ�Υ������ȥե��ꥢ����ˤ�ä������μ����Ω�縢��ǧ���졢����300���μ��Ȥ�ʬ������ޤ�³�����ۤ�700ǯ��³��������¯������������ζ����Ȥο����߽Ф��ھ��Ȥʤ�����פʤΤǤ��롣
�����ƿ������������ϡ��ɥ��IJ���ʥե����ˡ������ꥢ���֥륰��Ȳ���Ȥ���������֣��Ĥ�Ϣ�粦�������ޤ��뤳�Ȥˤ��������դ�����ʤ���Фʤ�ʤ������Τ褦�ˡ���ޤ�����ʲ���ˤο��פȤ����Τ������������Ʊ���˾�ħ����Ȥ����Τϡ��¤ϥ����ޤ�������Ĥ�ʬ�Ǥ��줿�����˻Ϥޤꡢ���Ρ֣��Ĥ�Ϣ�粦��פ˰����Ѥ��졢��˲ڳ��������濴Ū�����ˤ������ħŪ��ȹ��ۤΡ��ķ��פȤʤäƤ����ΤǤ��롣
���λ���κǽ����̤ˤ����ơ��������ȥե��ꥢ����ˤ�äƲ��Τ��줿�������������ϡ�������ơ���ˤ�äơֿ����ǤϤʤ�����������Ū�Ǥ�ʤ�������ɤ��������Ǥ���ʤ�: The Holy Roman Empire is neither Holy, nor Roman, nor an Empire. / Ce corps qui s'appelait et qui s'appelle encore le saint empire romain n'?tait en aucune mani?re ni saint, ni romain, ni empire.�פȤ�����������餵�줿�����ΡֺǸ�Υ��������פκ�ʬ�������������Ϣ�ʤ�ֿ������פ�����Ū���ݻ������ޤޡ������������μ�������ڤ˼����ΤǤ��롣
�� �����Ȼ���Ρֻ��������ۤλ���

|
�����ꥢ |

|
�٥륮�� |

|
������ |

|
�ϥ |

|
�ɥ��� |

|
�֥륬�ꥢ |
����Ū��Ȥ������ι�ξ�ħŪ���פȤ��ơֿ������פ���äƤ��뤳�Ȥϡ������ǤϤ����Ρ�������̤��ƺǤ�ͺ�ۤ�ɽ������롣���߲����ǿ�����ο����Ȥ߹�碌�������ΤΡ�����������äƤ���ϼ�ˡȣ��ɤ˾�ħ�����ƹ�β����Ф���ˡ���ˤ����״����סʻ�̾�����������ˤ����ꤹ�븢��Ū�ȿ��Ȥ��ƤΥ����ޡ����ȥ�å��ʤ��ʤ�����������ν����ˤˤ����ۤ��������ʸ�˥ץ��ƥ������¦�˰��ؤ������Τ�ޤ�ơˡ��⤷���Ͽ������������ΰ����������Ƥ����Ǥ��롣���Τ��Ȥϡ��ֿ��������������ʤ����ƣ��ˡפ�³���ֿ��οʹԡ������οʹԡפ�ʸ̮��̤�����Ƥ˸��̸������ǤϤˤ狼�ˤ��ʲˤ������ȤǤ�������
�ֹ����֡����פλ������ϡ��ɥ��ġ��٥륮�������С����֡פ������ꥢ���ϥ�����С�������פ���������ɡ�����ɡ��ޤ�������������¹�ˤȤʤäƤ��롣�ü�ʤȤ����Ǥϡ��ġݲ����֡פλ�����*���Ѥ����롼�ޥ˥��ȥ���ɥ餬���롣���ġ����֡פλ������Ĵ�Ȥ����Ȥ˥ե�����������륯����֥륰���ʤ���˵�������������������ˤ����롣
�����ϰ���Ū�˱ѡ��Ƥι����ֻ������פȤϸƤФʤ���������Ǥ���ġ������: Blue, White and Red / Red, White and Blue�פλ������Ĵ�Ȥ��뤳���ʩ���ѡ��Ƥλ���ϡ����ζ�ͭ���뿧�������褦�ˡ��������ޤ��ˡֻ��̰��ΡפǤ��롣�����ơ�������˿�̱�Ϥ���Ĥʤ��������Ф������Ū�Ƹ�������������ĹǤ���ʤ����Ǥϼ��夲�ʤ��ä�����Ʊ�ͤλ���������ĥ�����**�⤽��������Ȥ����ϳ��ʤ��ˡ�����������γƲ��ϴ��ˤ����ƶ����礤���ޤ���������äƤ����ط��������Ȥ�櫓ʩ���ѡ��ƤΣ���Ρְ��δط��פ�20������Ƭ������켡������ξ����������̤���ǻ���ˤʤäƤ�������Ҥ��뤬���ä˥����饨������Ϥ�Ȥ��������������äơ����Σ���δ֤ˤϤ����Ρֿ�����碌�פ�¸�ߤ��뤫�Τ褦�˰��ذ��δ���Ƥ����Ȥ����������ܷ⤷�Ƥ��ꡢ���λ��¤�����ϴ���̵�뤹��櫓�ˤϤ����ʤ����ޤ���ˤ����פ��Ф����Ȥˤʤ�Ǥ�������
* �롼�ޥ˥��ϥ����ͤι���ɥ�ϥե�ȥ��ڥ���˶��ޤ줿�ԥ�͡��ξ����ߤϥե�������Ρ���¯���ˤȥ��ڥ���λʶ����������ˤˤ�ä������������Ƭ���ι�ȡ����λ������ϡ��֥�ϥͤ��ۼ�Ͽ�פˤ����Ƹ��뤵�줿�֣����ε�ʼ��פλ����ζ����Ƥο��˰��פ��뤳�Ȥ����ܤ��٤��Ǥ��롣
** ���ߡ��������λ������Ͼ夫����֡����ġפλ����ˤʤäƤ��뤬�����־�Ρ��֡פϰ����ϡ֥���פǤ��ä����Ȥ��Τ��Ƥ��롣����������ꥢ��ʥ����ꥢ�ࣳ���ˤΥ���ܥ�ˤ��ʤ����Τȸ����Ƥ��뤬��������Υȡ����ݻ�����Τ�����Ū�˺���ǡ�����֤ˡ��ѹ��פ��줿�Ȥ������������롣�������������ե��̿�ˤ��ƶ����Ȥ�ʤ��ä����������ּ�ͳ��ʿ������פ���ǰ�Ȥ��Υ���ܥ�Ǥ��뻰������³�����ȹͤ���Τ������Ǥ��롣�������ϥե��̿�塢���ܹ�ξ��ǡפȤ������֤����ä��������Υ������ζ���ˤ������ϰ̤η��Ѵ��ˤ⡢Ĺ��ν���ξ���Ĺ�ɥ����դϥ������λ�������Ǥ�³�����ƶ����줿�������˵������鷮�Ϥ�����Ƥ��롣�����������1630ǯ�ʹߡ��֥�������ġפ��鸽�ߤΡ��֡����ġפ��Ѥ�ä��ΤǤ��뤫�顢����ˤϤ����餯���߲桹���Τ��Red White & Blue�ɤ�Trois Coleurs�����Ǥ˸���줿�Ȥ������Ȥ������Ǥ���ΤǤ��롣
�� �ֿ������פθ����Ȥ��ƤΥե��


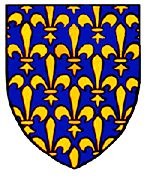
���ǰ����衧
���塧Armes de la Maison des Bourbons de France (avec les Fleurs de Lys : symbole de la royaut? de Charlemagne) @ Histoire et Documents
�塧Philip II the King of France @ Wikipedia
�Х륫��Ⱦ�礫�������������ˤ����ƤΥ衼���åѤDZƶ�����äƤ�����������������ʿ�Ԥ��뤫������Ĺ���ˤ錄�긷����¸�ߤ�³���������ޡ����ȥ�å��θ��Ϥ�����뤿�����¯�����Ȥ��Ƥ��Ρ�ʸ����Ū�ƶ��Ϥ����³�����Τ��ե�Ǥ��롣�����Ƥ�����ֿ������פ�ɽħ���ĥ��³�����Τ��ե�Ǥ��롣
�ե�ˤ����Ƶ����뤽�λ����褹���礭�ʻ���Τ����Ĥ��ϡ����ι�������ħ�����ΤǤ��롣���֤Ϥ�����λ�����̤뤬�����Τ����ΤҤȤĤϡ֥���ӥ��祢�������פȸƤФ���絬�Ϥʷ�����ư��ޤ�ְ�ü�ץ������ɡʥ���ӥ��祢�ɡˤ��Ф���Ű��Ū�ʽ����ư��Ǥ��롣�����12����������13������Ƭ�˳ݤ��ƹԤʤ�줿��Τǡ������Ϥˤ���������ޡ����ȥ�å������Ϥ�θǤ��餷��֥ե�סʲ��ȡˤ����ڳ����⤿�餹����ˡ�¿��ʰ�̣����Ĥȸ�����Ǥ������������Ƥ⤦�����ϥե�Ρ���Ω��ȡפȤ��Ƥκ���δ����ȡ����κݤ��θ����줿�ּ���פȤ��Ƶ���������ΤǤ��롣����ϥ����ꥹ�Ȥδ֤�Ʈ��줿��ɴǯ���� (1337-1453) �פǤλ���Ǥ���ȸ��äƤ����ǤϤʤ���������
�� ���������ư��ΰ�̣���뤳��
�������ɤ��ư��ϡ�����к����Υե���ڤζˤ���礭���ϰϤ��������������Ȥ�Ƥ֤٤�����Ū���ݥå��Ǥ��롣���ꥹ�ȶ�����Ω���˴��˵�Ͽ����Ƥ��륫�����ɤ�¸�ߤϡ����λ���������Ʈ����Ԥ줿����¼�Ū�˥��ȥ�å�¦�������Ū�ˡְ�ü�פȤ�����åƥ��Ž���Ƥ��뤬������ϤҤȤĤ��礭�ʽ�����ư��Ĭή�Ǥ��ä����������ɤϥ��Ρ���������ΰ��Ǥ��ꡢ���Ρ���������Ȥϡ֥�������������������ů�ء�����ӥ��ꥹ�ȶ��λ���Ĭή�ι�ή���˰��֤����礭�ʻ��۱�ư�Ǥ��ä�*�ס�
�����Ƥ��λ��ۤȤ�ñ�㲽�줺�˵����С������Ȱ��������פȤ�����ΤǤ��ä��Ȥ����ͤ�����Ǥ�����������������������ñ�ʤ�������Ǥ��ä����Ǥ���Τϴ����Ǥ��뤬���������ɤλ��ۤϥ��ꥹ�ȶ���Ω�����ˤ��Ǥ˵����Ƥ�������������Ū�����Ѥ�ȿ�Ǥ��������Ʋ����⸽����ְ��ε�ˤθ�������ʪ������*�פȴѤ롣�����ˤϡְ��פ�¸�ߤ����ζȤ����ڤ�Υ����Ƹ����ȼºߤ���Ȥ��������Ѥ����롣�����Ƥ��θ����������Ǥܤ���ʤ���Фʤ餺���椯�椯�Ͽ������ˤλ��ۤ�ˬ���Ǥ��������Ȥ����ͤ��Ǥ��롣
�����������Ρ��������������216ǯ�˥Хӥ��˥������ޤ�ʤ�������Ū�ˤϥڥ륷��͡˥ޥˡʥޥͥ��ˤˤ�äƻϤ��줿�������֥ޥ˶��פ˼����Ѥ���롣�����Ƥ��ν���������������ˤ���ʤ�ο��Ԥ�롣��˥��ꥹ�ȶ��ˡֲ����פ��������������ƥ��̥���ǽ�ϥޥ˶��̤Ǥ��ä����Ȥ�ͤ���С����������Υݥԥ���ƥ�����Ľ����Ǥ���ů�ػ��ۤǤ��ä��ȹͤ��뤳�Ȥ��Ǥ��롣���뤤�ϥޥ˶�����Υ��ꥹ�ȶ��Ȥ������罡���˹�ή����췲�γؼԤ修�Ԥ����٤ޤȤᤢ���뵡ǽ��̤������Ȥ������Ȥ�Ǥ��뤫�⤷��ʤ����ޥ˶����Τϡ��ޥˤ������Ƥ���������Ѷ�Ū�˻ٻ����ѥȥ���λ���ȼ����®�ˤ��αƶ��Ϥ��ΤǤ��뤬�����θ��800ǯ�ʾ���Ϥä��͡��ˡְ�ü�פȷ��Ĥ����륭�ꥹ�ȶ����ɤȤ���̾�Τ��Ѥ��ʤ��顢�ϲ���̮Ū�ʥ��Ρ������λ���ŪĬή�Ȥ���������Ӥ���
���Υޥˤζ��������Ρ�������ΤҤȤĤǤ��뤳�Ȥ���������Ǥ��褦������������ʪ������ʻ¸�����ʤ���ֿ��������ˤ�ʪ�������Ρˤ�����Ū����ʻ¸*�פ�ǽ������Ȥ��롣�Ĥޤ�����Ū¸�ߡʰ��ˤ����ʤηײ�ˤˤ�äƻ��߽Ф��줿��ΤǤϤʤ����ְ��פʤ�����ʪ���פȤ��Ƽ��Ϥ�¸�ߤ��뤳�Ȥ�ǧ��������ʤΤǤ��롣�Ĥޤꤳ�Τդ��Ĥ���Ω�����ܼ�Ū¸�ߤξ�ˡ־�̤ο�*�פ����ꤵ��ʤ��Ȥ����ˤ��λ���ŪĬή����ħ�����롣�����ޤΡ���ή�פ��餹��С����줬�������ɤ����������Ū�ȷ��Ĥ���Ű����Ƚ������¤Ȥʤä��櫓�Ǥ��롣
* ���͡��ե���ʥˡ������ذ�ü�������ɡ١ʥ�������ʸ�ˡˤ��
�����������ޡ����ȥ�å��Τ��θ�˳��֤��붵���Ȥϡ��ޥ˶��ʾ�ˡ֤��ӤġפǤ���Ȥ����פ��ʤ��ֻ���ʤư��ª����סȻ�������Ū�������Ǥ��ä��Τϡ������Τ��Ǥ��Τ�Ȥ����Ǥ��롣��������ŷ��ˤ��������ˤ��Ͼ�Ū¸�ߤǤ���椬�ֿͤλҡפȡ������դ��Ĥ��ӤĤ������פȤ��ƤΡ�����פ�¸�ߤ��Ѷ�Ū��ǧ��뤳�Ȥǡ��֤���ϤҤȤĤο��ʤΤ���ͣ����ʤΤ��פȤ��������ؤ�ȯŸ���ʲ����롣

���ǰ����衧Philip II the King of France @ Wikipedia
��ȴ��˲��Գ��ξ�ħ���������֥ե���åס������她�ȡפȤ�ƤФ�륫�ڡ���ī�β����ɥ��Ĺ����Ϣ�礷�������ꥹ�����̥ե��å�Ԥ�����1214ǯ�˱�ͺ��ɾ������롣�������ɤ��Ф���Ű���ư��Ԥ�������Υ���ƥ�����������̿�ˤ���ȿ����줿�֥���ӥ��祢�������פȤ�����ʩ����ˤ����밭̾�⤭��üƤȲ�����ä�̿�����롣�ºݤ��ؤɤ��ΰ�ü��Ȳ�����Ω�����餺�˲��γ���Ȥ�����̣��ž������ࡣ
���ʤ����12����������13�����˳ݤ��ơ֥ե롼�롦�ǡ���פξ�ħ�������ե���Ȥˤ�äƹԤʤ�줿�֥ͥ����ޥ˶��̡פȤ�ƤФ��٤��������ɤ��Ф���Ű��Ū�ʽ����ư��ϡ��ֿ������פξ�ħ����Ŀ͡��ˤ�롢������������Ĥ�Ρֿ������פ��ݻ��Ԥ��������Ǥΰ�̣�����ä���ª���뤳�Ȥ��Ǥ���ΤǤ��롣
�� �ե�ȡ�ɴǯ�����
14����Ⱦ������1337�ˤ˳��Ϥ��졢�ޤ�ޤ룱�����ʾ���ϤäƷ��깭����줿ɴǯ���褳�������ߤΥե�β��̷Ѿ������ĥ�����֣��͡��ηѾ�����Ԥ��о�ˤ�äƻϤ����ʤ�����ΤҤȤ꤬������Φ�ؤ�����Ū�����äƤ��������ꥹ���ɥ�ɻ����Ǥ��ä��ˡ������ơ�����ɴǯ�ʾ���Ϥä�³����줿�ե�αѹ�Ȥ�Ʈ��ϡ�����������ˤ�����ե��̱²�ȹ��ڤ������θ�ζ����ȥե�ؤ�Ϣ�ʤ����ư������ˤ����ơ��ҤȤĤμ�ΩŪ�ռ������Ū�˺��դ���������ζ�������ä�ʸ���̤�ּ���פβ����Ǥ��ä���
���������Ū�ˤϡ֥����������������ס��᤹������ˤ˻Ϥޤ벦�̷Ѿ������ȯü�Ȥ����ʩ�֤Ƿ��깭����줿���ϹԻȤ�ޤ�Ĺ��Ū����Ω�Ǥ��ꡢ�����Ф��Ϥ�ּ������פ���ѹ���ऱ���αƶ������æ�Ѥ�ʤ���ΤȤ��Ƥΰյ��⤢�롣�����Ƥ���ϥ����̡����륯���о�Ȥ��Ρֵ���Ū����פʤ����ֿͿȶ����פˤ�äƷ�Ū������Ĥ������Ū���ݥå��Ȥʤ롣
�ե�ˤ����ƽ��������ԤȤ��ƹ����ɽ�������ͤȤʤä��Ȥ������¤ϡ��ե�λ��Ĺ�̱���Ȥ⽸��Ū̵�ռ���ȿ�ǤȤ�������������ƾ�ħŪ�Ǥ��롣�����ʡ����ˤ�������ɽŪ�о��ʪ�Ǥ��륭�ꥹ�ȤȻ��̤Τ������δط������ɤ߲���о��ʪ����䤬���衼���åѤζ����ȤΤ����Ĥ������ƤϤ����Ȥ������ȡ������Ƥ��������Ʊ�������dzθǤȤ����ʤ����Ⲽ�ռ�Ū�ʡ������̿Ū��ô�äƤ��벤���ι�ͤ����Ȥ����ե�ˤ�������ɽŪ�οͤ�¾�ʤ�̽����Ǥ��ä��Ȥ����Τϡ�Ǽ���Ǥ��뤳�ȤʤΤǤ��롣����Ͻ����̤Ȥ��ƤΡ֥ޥ�����Υޥꥢ�פȥե�δ֤˰ż������ط�*�ˤĤ��ƤǤ���Ȥ����Ǥϰ줳�ȸ��ڤ��Ƥ������Ȥ�α��롣
* �����ǤϾܽҤǤ��ʤ�����������̾���Ǥ��Τ���Ρ��ȥ����: Notre Dame�ʲ�餬���ؿ͡ˤϡ��̾������ޥꥢ�פ��̣������̾��Ȥ��ƿ������Ƥ��롣�����������ƥꥺ��������ˤ����Ƥ���ͤΥޥꥢ������ޥꥢ�ȥޥ�����Υޥꥢ�ˤδ֤ˤϡ��֥ޥꥢ�פȤ��������ɤ�����뤢���Ρְտޤ��줿��Ʊ�פ����ꡢ�ҤȤĤν���Ū�����ˤ�ä�ɽ�������ΤΡ֤դ��Ĥ�¦�̡פ�ɽ����ΤǤ���ȹͤ���������ΰ������ͳ�����롣�����Ƥ����ʤ��ͭ��̾�ΤǸƤФ�褦�ȡ��֥��ꥹ�ȶ���פȤ���¸���Τ����ְ�©���˵Ҥ��ꥵ���ӥ�����פ��Ȥ���ʤʤ�襤�ˤȤ��Ƥ������ǡ���ʡ����ˤ�����ޥ�����Υޥꥢ�Υ��ԥ����ɤλؤ�������ΤȤθƱ���������ΤǤ��롣
������ˤ��衢�֥ե�פȤ����������ͤ�Ϳ����줿������̾�ˤ�äƤ������ΰ����դ�������Ƥ���ʾ塢���λ���ʡȣ��ɤλ���ˤ�褹����ԤϽ����Ǥʤ�ʤ���Фʤ�ʤ��ä���


���ǰ����衧Joan of Arc @ Wikipedia
�����̡����륯���о�Ȥ��λ� (1430ǯ)�ϡ��礭�����ष���Ѥ����ե���ڤαѹ���ɱҤ���Ω�η����Ȥʤä������η�̡��ե����Ω�ΡȽ���ɤȤ��ƥ����̡����륯��ǧ������Ƥ��롣�������������ä��Τϴ��˸��ڤ����֥ե롼�롦�ǡ���פˤ�äƾ�ħ�����ե���ȤʤΤǤ��ä��������ơ��᤹�����������о����Сפ������ε����ȤʤäƤ���ΤǤ��롣
�ե�ȡȣ��ɤδ�Ϣ�ϡ����̰��Τ�ɽ�����Գ��ʥ����ΰ��ˤ���� (fleurs des lys)���ե���Ȥ���ϤȤʤäƤ��뤳�Ȥ䡢�����ȤȤ��ƤΥե���������������Ƥ���Ȥ������Ȱʳ��ˡ��֥ܥ�ɡ��ν����: the Pilgrim of Bordeaux�פ�������333ǯ�˿����ͭ̾������ΤҤȤġ����å��ޥͤξ��ȿ������Ƥ���֥���ֻ���ϼ�פ����Ϥ�ˬ�줿�Ȥ����Ť���Ͽ�����Ǥ���*��(Catholic Encyclopedia)
* ����ʳ��ǤϹ�����äι��ֹ椬�ե�ϡ�33�פˤʤäƤ��뤳�Ȥ�̵�뤹�뤳�ȤϤǤ��ʤ���
���ȣ��ɤλ���Ȼ��̰��Τ��ܼ��ʤޤȤ��
�����ޡ�������å�����������ȻҤ�����פ����ΤǤ���Ȥ������̰������Doctrine of Holy Trinity�ɤ�ή�ۤ���ĥ�ܿͤǤ���Τϡ��ѤƤ����̤�Ǥ��뤬��������ϻ��Ĥΰۤʤ�¸�ߤ���Ʊ��פǤ���Ȥ����ֿ����פ�������ʤ����ƺ������ˤ�衼���åѤε����˰䤹���Ȥ���Ū�Ǥ��ä����Τ褦�Ǥ������롣���Υ����ʥ����ĥХ��ˤ���Ϥ�Ϥ�Ȥ����������ϡ����λ��Ĥβ��ۤ���Ĥ�«�ͤ��뤽�ο�����ʤơ����Ρְ������פ��ħ���Ƥ���ΤǤ��뤬������ο������Ƥ����Τϡ�ʶ���ʤ��ֿ������פǤ��롣�ֻ��̰��Ρ��⤳������ȻҤ�����פ�Ʊ��Ǥ��롢�Ȥ������Ū��������ʸ����μ�������������ΤǤϤʤ��������ñ�������˸����ơֿ������פ���ˤ˼���������о줷����¾�ʤ�ʤ����˸����Ƥ��롣�����⡢����Ρֻ��̰��Ρ�������������Ǯ�������줬���Ū�ˤ���ʤ����Ĥ����������ˡ������Ƥ��줬˽��Ū�ʤޤǤΡְ�ü����פ��̤��Ƥλ����ư�����ޤ��������ݤ�Ϳ��˰����������ҤȤĤΥ������ħ�ˤȤʤä��������Ƥ��α�ư�����������Ƥ��ܼ��Ȥϴؤ��ʤ�����̣�Τ���ҤȤĤ��Ϸ�Ū������Ȥ��ƿ���˵��������Ȥ������ȤߤˤʤäƤ����Τ���
���˾�ˤҤȤĤλ��夬����ꡢ���λ���ذܹԤ���ݡ��礭�����𤬵����롣�ȣ��ɤλ��夫��ȣ��ɤλ���ؤΰܹԤǤ⤽����㳰�ǤϤʤ��ä�����ˤ�����ϥ衼���å����ڤ��顢�ɡ�������������ۤ��ơ��衼���åѡ��ն������ϡפǤ���֥�ƥ���˰ܤ롣���Ū�ˤ���줬�ʲ�Ȥ����ˤ��С��֥إ�������Υ�����������פΤȤ�����¯Ū��ߤ������ˤʤꡢ�����ޡ�������å��μ�������ƨ���٤��ѹ�ī�ϡ�1534ǯ���Ĥ��˥����ꥹ�����Ω��������롣�����ƺ��٤ϡ�����ǻ���ʿ�������������ħ�������ä��͡��������ꥹ��������ʤ�̡֤���ħ�פ���ᤫ���ʤ��顢�̾���ư�ȾΤ������������Ӳ�롣��餳����������դ�����å��㡼�פȤ��ơ��ܳ�Ū��ư������ΤǤ��롣
03:33:00 -
entee -
TrackBacks
2006-04-01
�������ɿ������Ƚ
�����ָ����ȱ����줿���פȼ����Ū�ķ����� [9]
�ȣ��ɤλ�����ָ���Ū�������ס����
 333 [����1]
333 [����1]
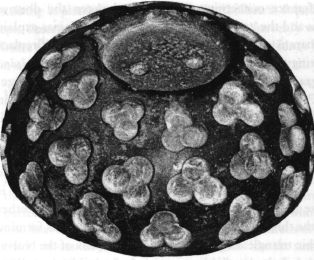 33333... [����2]
33333... [����2]
 33333... [����3]
33333... [����3]
�� ŷ��Ū�ʡȣ��ɤ��Ͼ�Ū�ʡȣ���
����ϡȣ��ɤȤ����ܿ��Ǥ���Ȥ����Ρȣ��ɡʤ����ƾ���Ū�ˡȣ��ɡˤδ֤ˤ���ط���������ݤ˺ƤӼ��夲�뤳�Ȥˤʤ���������������Ǥϴ�ñ�ˡֿ������פ�ᤰ��⤦��Ĥβ���Ȥ��ơ�ŷ��Ū�ʻ��̰��Τ�����ȿ�Ǥ������˸�������Ǹ����������Ͼ�Ū�ʻ��̰��ΤˤĤ��ơ������ơֿ������פ�ȯ������־岼�����Ū����ŷ�ϸƱ���Ū�ʾ�ħ��ǽ�ˤĤ��Ƹ��ڤ��롣
�Τ��ˡֿ������פ��Ͼ�Ū��ɽ�ݲ��Ȥ������Ū�ʡ�ħ��ˤĤ��Ƥ�����������Υ�����ָ����ȱ����줿���פΥơ��ޤ�ľ�ܤĤʤ��꤬������ʬ�ǤϤ��롣�������äơ������ǤϤ���줬��ˡָ���Ū�������פȸƤ֤Ǥ�����Ķ���Ū������Ρֺǽ����פȤʤ����Ū���ݥå��δ����������ˤκݤˡ��Ƥӡ�������Ƥ˸���뤳�Ȥˤʤ��Ͼ�Ū�ʡ�ħ��ȡ������ο���ʤ������κ¡ɡ����¡ˤ�������פʡ��о��ʪ�פ����ˡ������Ͼ�Ū�ʡֿ������פ����������Ф����Ȥ������Ȥ��Ŧ���Ƥ�����α��褦���ȣ��ɤλ���ˤ����ơ����ξ�ħ��ô���꤬�������Ū����˰쵤����·���������Ȥ����ξ�ħ�ηϤ�����ˤ��������ν����ʤΤǤ��롣
���ޤ��˽Ҥ٤��褦�ˡ��Ȥ�櫓���ȥ�å�����ΰ츫���ۤ��ߤ��ֻ��̰��Ρפο�����Ū����ˤĤ��ƿ�����������ʤ�����ʲ�Ǥ��ʤ��褦������Ÿ������������Ū�ǤϤʤ����ޤ��Ƥ俼��ʤ륭�ꥹ�ȶ��λ��̰��ζ�����֤�������褦��ĩ��Ū�����������������ΤǤ�ʤ����������뤳�ȤϤ��ξ����ΰ������ϰϤ��ưפ�Ķ���Ƥ��ޤ������������������ζ������˾���о�ȵ����Ĥˤ��ơ��ȣ��ɤλ���Υ��ݥå����Ϥޤꡢ�ȣ��ˤ��ƣ��ɤȤ������̰��Ρ��Ҥ��Ƥϡֿ������פˤ������դ������٤��뵷������ȡ��͡��β��ռ��ˡ�ʹ�������粻���פ���äƺ��Ѥ��������Ȥϡ��ֽ����͡פν���Ū�����ι���˼����Ǽ¤��礭�ʸ��̤ΤҤȤĤǤ��ä��ȸ���ͤФʤ�ʤ���������������Τ�������ݤˤ��������ֻ��Ĥǰ�ġפȤ����ֻ����ȡ��ȥ饤�����ɡפι������ħŪ�����ƤϤ�ƹԤ����Ȥ����ȱ�����ݤλҡɤΤ褦�ˡ��ޤ��ˤ��λ����˰��Ƥ˳��Ϥ��줿�ΤǤ��롣�����Ϥ��٤ƥ��ꥹ�ȶ�Ū�������̰��Ρ�����ɽ�ʤǤ������ȻҤ�����פȤ����ԲĻĤʳ�ǰ�ΥХꥨ�������Ȥʤä��Ͼ�Ū�ʾ�ħ��������ο������Ҳ�ˤ⤿�餷���ΤǤ��롣
������ʿ��Ū������ι���ʪ�ˤ����ơ��͵Ӥ�껰�Ӥ�ʪ��Ū������ݾڤ��뤳�Ȥ��Τ��뤬����������⤽�Ρȣ��ɤȡȣ����ܿ��ɤ���ߤ���ˡ§�����������Ū�������ˤ����Ѥ���Ƥ���Τ������Ǥ��褦�����뤤�������˸���������ʤ顢���������ԲĻ������ˤ�������꤬������ʪ��Ū�������ˤ������ܤ˸��������ȿ�Ǥ��Ƥ���Ȥ������Ȥ������붵Ū�����ˤ����ƹ�����ͭ�����Ȥ����Ǥ��롣�����ϡ�ŷ��Ū�ʻ��̰��Τ��Ͼ�Ū������פȤ���������Сַ������Ū�����ۡפ�ȿ�Ǥ�����ΤʤΤǤ��롣
�㤨���ܶ�ʤȤ����Ǥϡ�����줬�ַ�ȴ����ޡפȻ��ĤΤ�Τ��¤١��ޤ��ֻ���ο���פȤ������Ĥǰ��ȤȤ����Ȥ߹�碌�ߡ�������ɽ������Ω�������ˤ����Ρְ�����ޤ�䤹���פФ��Ȥ������Ȥ⡢���ߤˤޤǻĤ뤽�����������ΰ�Ĥθ���ȸ����뤫�⤷��ʤ����ޤ��ֻ��Ĥ��줬��Ĥ����Τ�٤���פȤ����褦�ʻ��Ӽ���������*�ϡ�����Ρ�Ωˡ����ˡ�������פλ���ʬΩ�ιͤ��ˤ�ȿ�Ǥ���Ƥ��롣�����ơֻ����ȡפ�������������Ƭ���ϡ��������λ�ƬΩ�Ƥ�����ʤ��ޤ���ˤˤʤ�äơ֥ȥ������פȸƤФ�뤳�Ȥ�פ��Ф���褦��

* ��˸���褦�ʸ������ε�������Ƽ��ˤϻ����ͤΤ�Τ�¿�������롣����ϡְ���פȡ�ɽħ�פΤդ��Ĥε�ǽ�˶�����ȸ����롣��Ǥ���Ƽ���Ť�ˤ�ʸ�ͤ����Ƥ����Ǥ��ꡢ�����Ť�����̤�������ʿ�Ū¸�ߡˤ��ҤȤĤδ����Ф����Ȥˤ�äơ������פ�ɽħ����ŵ��Ū���оο����ȹͤ��뤳�Ȥ��Ǥ��롣��ˡ����ˤ�Ť�ϡ����Ρ������פĤ����٤������ȹͤ��������Ǥ��롣������: axis mundi�Ȥ��������Ȥ�ǻ���ʴ�Ϣ�Τ�����оο����פˤĤ��Ƥϴ�ȯɽ�Ρ�����Ū��������ȡ�Ķ���Ū�����ˤĤ��ơ٤Ǥ���夲����������������˴�Ϣ����֣��ο����פǤ�����ˤλ����ʬ�˸Ʊ�����ֿ������פȤϴؤ�꤬�ʤ��������衧����Ū�ʾ�������ȡ��оΡ���������� [1]����¾
���������衧�����Ť�ʤȤ��ƤĤ��Ƥ���@ ����Թ�Ω��ʪ��
����ˡ��Ҳ�λ����ءּ���̱��ʼ�פȤ�����Τ��������ܤˤ����ơ����夫��������ΤǤ��뤬������ϥҥ�ɥ����Σ��ĤΥ������Ȥξ��ػ���������������ΤǤ��롣���ʤ���֥Х�������ȥꥢ������������פ��ޤ��ˤ���Ǥ��롣�㤨�Фޤ����ե�ˤ�����1302ǯ����Ϥ��줿�㻰�����ϡ�������ʬ�Ǥ��������ԡ������ʬ�Ǥ��뵮²���������軰��ʬ�Ǥ����̱�ǹ��������פΤǤ��ꡢ����ϡȣ��ɤλ�����о줷���ּ�ͳ��ʿ������פλ���Υ�������������֤��Τ餷���ե��̿�������ޤ�³����
������Ͼ�Ū�ʶ��Ȥ����������Ǥ⺣��Τ�����ˤˤ����ơ����Ρֿ������פθ������뤢���Ȥ�����ħ��ͭ���Ρ���������³�ԡפȤʤꡢ��������ֿ������סֿ������פȾ�ħŪ������ǻ���ݻ����Ĥġ���������ˤο�Ÿ�ξ�Ƕˤ�ƽ��פ�����̤��������Ū�פʶ����Ȥ��濴�ȤʤäƹԤ����ʤ���Ϣ³��������Ρֻ�������Τ����ޤ�¯���ˤ�����֥��쥤�ȡ��ȥ饤������: great triad�פ������Ƥ���ΤǤ��롣�ˤ��Ρ������ʡǽ����³�ԤȤ��ơ��ֿ������פ���Ķ����ȤˤĤ��Ƥ䤬��������ʤäƤ����櫓�������������ˤ����Ĥ����ƻ�Ƥ����ʤ���Фʤ�ʤ����Ȥ����롣���������ξ���������ǽ���ϰϤǤ���Ƥ����ʳ��ˤʤ��ΤǤ��뤬...
�� �ֿ������פ˴ؤ�������
��ˤ�쥳���᤹���Ȥˤʤ뤬�����ꥹ�ȶ�����������ιȤ������Τϥƥ��ɥ���������Ǥ��롣�����������ˤ����ơ����θ�β���ʸ���濴Ū�����Ū��Ľ��ľ��Ū�ʱƶ���Ϳ�������������ޤ�㣲�ġ��ʬ�䤷��ͤ�©�Ҥ˷Ѿ��������ΤϤޤ��ˤ��Υ�������Ǥ��롣����380ǯ�ˡֿ������פ��ݻ��������ꥹ�ȶ����Ρ������ƹ�ǧ�ꤵ�줿�Ф���Υ��ꥹ�ȶ���������ʬ��: schism�ˤ�äƻ��¾�֤դ��ĤΥ��ꥹ�ȶ��פؤ�ʬ�Ǥ��줿���춵������������Ǥ��롣�������������ޤΡʤ����ƥ��ꥹ�ȶ��Ρ�����ʬ��Ȥ������η�Ū�ʽ�����������ȣ��ɤλ�����濴��褹�륨�ݥå��Ǥ��ä���
������������ʬ���Τ鷺��ɴǯ���476ǯ����˴�������������������¯�Τ�ָ����ӥ�������פ��뤤�ϡ֥ӥ���ƥ������פȤ��������Ѥ���³������ΤΡ�1453ǯ�˥����ޥ����ˤ�ä����������̾�¶����Ǥ����������������ޡפϡ�����ޤǤ�̾�������֥����ޡפȤ��Ƥι�γʤ������ưݻ����Ƥ�����ΤΡ���ä��ᤤ������̵ͭ̾�²����Ƥ����ΤǤ��롣���¾塢����Ƭ���ɡפΰ��������������������˴���ȣ��ɤλ���ν���ˤۤܰ��פ���ȹͤ��뤳�Ȥ��Ǥ���ΤǤ��롣
�ȣ��ɤλ���Ϥ��Τ褦����������Ū���ݥå��θ�ˡ��ȣ��ɤλ���˰����Ѥ���롣���λ����ܤξ�ħŪ�ʡ������פϥ��ꥹ�ȶ����Ϥ��դ������ν����פؤȾ��ʤ���Ƥ椯ľ���θ��ϥ��ꥹ�ȶ��λ���ˤ��Ǥ˰ż�����Ƥ���������ϸ��ߤǤϿ��������ʡ�������˼㴳�ε��ҤȤ��Ƹ��Ф����Ȥ�����롣���ޤ줿�Ф���Ρֿͤλҥ������פˤϡ����������������㻰�ͤθ��͡䤬�������ˬ��[����3]��������������ʡ���롣���ꥹ�Ȥ�Ϥཽ����̤ϡ����Ͱ��ȤΡ֥ڥ��פȤʤꡢ�����ˤ������������̤ΡֻͶ��ʤ������ˡפ˸����ơ��۶�����ʼ�Ȥ���������롣����Ϥ������Ự�ڵϤΤ褦���ʤ䤸��: spearhead�˾��β����ͤ������λͶ��ʤ褹�ߡˤ˸�����ħ�Ȥ���*�ƽ��͡��ʷ��ǵ�Ͽ����Ƥ��롣���褤�衢�ȣ��ɤλ��夬�볫������ΤǤ��롣
* �������������̤λͶ���ɽ�����뽽���ͤξ�ħ����Ǥ⡢�㤨�в��Ρ֥ޥ륿�����Ĥν����͡פȡ��������ν����͡פ���ϡ�ǻ���ʡֿ������פ����������ʤ��������ͤ����ܤ�������ü����Ԥ�ʬ���졢�����⤽��ϤҤȤĤο�������ǻͲ��֤���뤳�ȤǤ��ο�������Ĵ����롣


���ǰ����衧The Maltese Cross - a sinister design?
�Ȥ�����������ǯ�ˤʤ�Ȳ��˼����褦�ʡֿ������פ������ͤȤ��Ȥ߹�碌���о줹�롣�����Ƥ���ϻͳѤ����������Ρ˥��֥������ȤȤ��Ȥ߹�碌�ˤ�ä�����Ū���о줹���Τǡ������λͶ���ɽ��������פȤ��Ƶ�ǽ���롣
 [1]
[1]  [2]
[2]  [3]
[3] 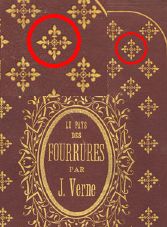 [4]
[4]
�֥ե롼�롦�ɡ���פ��Ͷ��ˤ����館��줿��
���ǰ����衧
[1] ��Wikipedia
[2] Fleur-de-Lys Medieval tiles @ Encaustic Tiles
[3] Richard Butterworth�Υ�����ǥ�����
[4] Le Pays des Fourrures��ɽ�� @ Jules Verne
�� ���̰��ΤΥ��祦�֤����


üŪ�˸����С�����ʸ���ˤ����ƺǤ���ɽŪ�ʡֿ������פξ�ħ�θ����ϡ֥ե롼�롦��(��)����: fleur-de-lys / fleurs des lys�פȤ����֥����סʲ��Գ�: yellow flag*�ˤ���ϤǤ��롣��˥ե�β��Ȥ���ϤȤʤ롢�֤Ǥ���spearhead�����ΰ��ˤǤ���ֻ����Ĥ�«�ͤ������������դȤ��������������ֿ������פ���ã�����Τ���Ū�Ȥ�����ΤʤΤǤ��롣
* �¤ϡ���fleur-de-lys�ɤ����β֤ʤΤ������β֤ʤΤ��Ȥ��������ϸŤ�����¸�ߤ���ΤǤ��뤬��������ܲ��֥����ʤβ��Գ��Ǥ���餷���פȤ������ȤǷ��夷�����Ǥ��롣���������줬�ɤ���Ǥ���Τ��Ȥ����Τϡ��������ä��ɤ���С���ħ������Ū�ˤ��ä˽��פǤϤʤ����ֻ��ۤβ֤Ӥ����ä��֡פ��̤�����ã�������Ƥˤ��������ܤ����뤳�Ȥ��������ξ�ħ�����δ��ܤ�����Ǥ��롣Iris pseudacorus: �����ʥ����°�Ǥ��ꡢIris�ʥ����ꥹ�����ꥹ�ˤȸƤФ��֤ΤҤȤĤǤ��롣Lily�ʥ��ˤǤϤʤ���


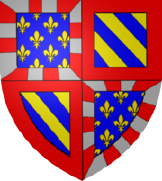
Iris pseudacorus�ʲ��Գ��ˤμ¼̡������������Ƥʻ��ۤβ֤Ӥ餫��¿���λ��ͤ���ϳؼԤ�̥λ���졢������ɽ������ε���Ȥʤä����Ȥ��������Τ����롣�夫�鸫����Τ�������餫�����������˻��٤�ʬ����Ƥ���ʾ屦��
���������衧�ʾ�˥֥르���˥����ϡ�ʩWikipedia���
�ʤ���Heraldica��������fleur-de-lys���ι��ܤ�ͭ�Ѥʾ�������ܤǤ��롣
�����Τ��Ȥʤ��顢�֥ե롼�롦�ɡ���פϻ��̰��Τ�ɽ�ݤ�����ɽŪ�ʿ����ǤϤ��äƤ�ͣ��Τ�ΤǤϤʤ������Ĥ��ؤ��������ѷ��������ʤɤ����Ĥ��θ���Ū�ʴ���Ū�ްƤ�¸�ߤ��뤳�Ȥ��ǤäƤ����ʤ���Фʤ�ʤ�������Ʊ�ͤΰ�̣�����¾�ο����Ȱ�äơ����Ρ֥ե롼�롦�ɡ���פο�����Ȥ�櫓��ö����¾Ū�פ˼��夲��������ʤ��Τϡ����������褦�ˡֶ����ȤȤ��ƤΥե�סʤ�����Τˤϡ���ˡ֥ե�פȤʤäƤ���������μ��ϼ�ã�ˤ����㻰���������������������ʳ��ǤҤ������Ѥ�����ΤǤ���ʤĤޤ���ˤΤ���ᤤ�ʳ��ǽ�̿�դ����Ƥ���ˤȤ������Ȥΰյ������ֻ��֤ȿ����״�Ϣ�ε�������Ǥɤ����Ƥ�̵��Ǥ��ʤ�����Ǥ��롣
¾�λ��̰��Τ�ɽ�ݤ�������ˤϻ����դΥ������С����ȥ�ե�����(trefoil) �������Ƥ�������η�������ä������͡�������¸�ߤ��뤳�ȤϳΤ��Ǥ��ꡢ�ޤ��������оο����δ�Ϣ�Ǥ���夲����������帢���θ������ʪ����ˤ�֣��ο����פ����Ф���뤳�Ȥ����롣�������ʤ��顢�֥ե롼�롦�ɡ���פۤ����Ƥ˽�����Ϣ�����ΤҤȤĤȤ����о줷���ۤȤ�ɽ����ͤ������֤�������ۤɤΰ�̣��: significance��ȯ�������ΤϤʤ�������ϰ츫�����ɬ�����⽡��Ū�Ȥϸ����ʤ��褦�ʨ��������Ǥ����ܼ�Ū�˽���Ū�ʨ����㤨�СֽݡפΤ褦������֥���������ɡפʤɤ˸���륷��ܥ�Ȥ������Ǥ⡢�����ͤ��ֿ������פ���ɽ�Ǥ��ꤨ���褦�˥ե롼�롦�ɡ��꤬�ֿ������פ���ɽ�ʤȤ��Ƥ���줬ª���뤳�Ȥˤϰ����������������ΤǤ��롣
�� ���ο������飳�ο�����
�Τ����ˤҤȤľ��������������
�� �����ħ���������Ū����
���������ͤȤ϶ˤ�ƽ��٤ι⤤�������ݻ�������ã���ʤǤ��롣�����ϤۤȤ�ɲ����ʤ����ˡ����ߥ�˥����Ȥ���ΤǤ��롣̵��ɽ�����줿�ֿ����פ��������Ū�ʳ����̣����Τ����̤ΰ�̣����ä��ֿ��פ��̣����Τ��ϡ����줬ɽħ���줿ʸ̮���Τ�̵�뤹��櫓�ˤ���������Ƚ�Ǥ�ɬ�פǤ��뤬�����������ͤȿ��Ȥ�����Τδ֤ˤ���ط��ϡ�������¿��ʤ���̤�䤤��������ޤǤ�ʤ������Ǥ��ڤäƤ��ڤ��ä����Ȥ��Ǥ��ʤ����Ȥ����餫�Ǥ��롣����ˤĤ��Ƥϡ�����Ū��ã�פ��ܻؤ������Ρ㸵����������ˤĤ����������ֿ�������ˤβ��뵷�פξ��ˤ�����㴳�ε��Ҥް��٤���ĺ���Τ��ɤ����⤷��ʤ���
���ȥ�ե�����: trefoil
���Ƥζ�����Ʋ�ˤ����Ƥ��Ф��ɤ�����������ƺ�ä�Ʃ�����뤬���뤬�������ˤϲ��ۤ��Ϥ����褦�ʻ���Ȥ��ƶ���ʤɤη���ʪ�ʤɤ�¿�����Ф���롣�ȥ�ե�����ȸƤФ����Ϥ��������ˤ����ƻ��Ĥαߤ��Ĥ˹��Τ������褦�ʴݤ����ۤΤ褦�ʷ����ˤʤäƤ��롣[����1]�������Ǥ���ĺ���Τϡ�Ʃ�����פˤʤäƤ��ʤ�����Ǥ��롣Ʃ�����ϵ�ǽ������������Ϳ���뤬����Ʃ�����פˤʤäƤ��ʤ��ʾ塢�±�Ū�ˤϲ�����ˤ�Ω����������������Ϥ��ο��������������ơʥ��˥ե����ˤˤ�����̣������Ȥ������Ȥμ¾ڤˤʤ롣

���ǰ����衧Illustrated Architecture Dictionary @ The Buffalo Free-Net ����Ƭ�ο���1���
��Ĺ�˿�ľ��ŷ��ظ����äƿ�Ĺ���륹�ƥ�ɥ��饹��ȼ����硢���������ȥ�ե��������Ϥ���ĺ���ˤ��Ф��и��Ф����Ȥ��Ǥ��뤷��ñ�ʤ�Ʃ������Ȥ���ñ�ȤǸ���뤳�Ȥ⤢��С���ϭ�褤���ФǤǤ����ꤹ��β��ˡַ����֤��Υѥ�����*�פȤ������ʤ�ʣ������뤳�Ȥ⤢�����Ƭ�ο���2�����ǰ����衧Sarasvati Sindhu (Indus Civilization) �ˡ�
* ��������ڤ����褦�ˡ��ֿ������פ��֣��dz�ä����פ��ʤ����0.333333...�פ��������Ȥ������Ȥ��۵����줿����
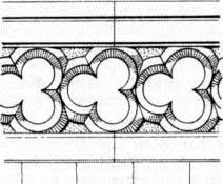 ���ǰ����衧Probert Encyclopaedia
���ǰ����衧Probert Encyclopaedia
�����������ۤ�Ʃ������ϡ������ȥ��ե�����: quatrefoil�����ե�����: cinqfoil �ʤɤΤ褦�˿�����ҤȤĤ���������ȯŸ���ƹԤ��Ȥ���������ʲ�Ǥ���褦�ˡ��ˤ��ñ��������ʬ����䤹����Ū�����λ���ʤΤǤ��롣
Foil�ϡ����ۤ��̣����tre-, quatre-, cinq- �ʤɤϤ��Τޤޤ��β��ۤο����̣����������̣���뤳�Ȥ��Ǥ�ޤǤ�ʤ���
�� �����դΥ������С�
���λ��̰��Τξ�ħŪ�����ϡ����ߤǤϤ�����������ѥȥ�å��Ȥδ�Ϣ�ǥ�������ɤˤ����륫�ȥ�å��ξ�ħ�ȤʤäƤ��뤬�������ˤ�����Ū���Ƥ��������Ū��̣�礤��ǻ����¸�ߤ��Ƥ���ΤǤ��롣�����Ƥ������Ƥϥȥ�ե�������̤��ƿޤ��褦�Ȥ�����ã���Ƥ�Ʊ�ͤΤ�ΤʤΤǤ��롣
 [a]
[a]
 [b]
[b]  [c]
[c]
���������衧
[a] UNDERSTANDING THE TRINITY
[b] Three Leaf Clover Floral Pewter Pin @ Exclusively Yours Gift Shoppe
[c] HIS MISSION OF FAITH @ Father Baker
���٤�Ҥ٤Ƥ���褦�ˡ���ʤ����Ʊ�ͤ˥��ꥹ�ȡʻҡˤ����Ʊ���ֿ����פ���ĤȤ����ֻ��̰��Ρפζ���ϡ�����������ˤȤäƤ�ñ�ʤ����۰ʳ��β���ΤǤ�ʤ���ΤȤ���ª������Ǥ��������º����ꥭ�ꥹ�ȤΡֿ����פ����ꤷ�ơ��㤨�пͤλҥ�������˿���Ʊ��뤹��ʤʤ����ϡ�����˽स����ΤȤ��ƴ������˥��ȥ�å��ζ���ϡ��������������Ѥˤ����Ƥϰ���ο������������ΤǤ���Ȥϸ����褦�������������ʹ֤Ǥ��ä����餳����˹ߤ�ݤ��ä�����˰�̣������Ȥ����ܼ���»�ʤ���Τ��Ȥ�����롣�ޤ����̰��Τζ��⤳�����ʹ֤�ʸ����������ʾ塢ʸ�����ħ�����ħ��˼椭������������������ʸ�����Τ�Τ˹ߤ�ݤ�������Τޤ���μ�����̣���뤳�Ȥ��۵�����Ф��������������Τ���ä�������͡��ˤȤäƽ���ʡ�����Ū�ʹ֡�λؤ�������ħ���ܼ�Ū��̣���ȴ���ˤ����ΤȤʤ롣���ʤ�������Υ��ȥ�å����ǽ�Ū�˺��Ѥ�������ϡ�������������Ū�ʡֿ������פΰտޤ������ΤǤ��롣�������Τ���ˤ������ζ���ϡ�ʣ��Ū�����볢�ʿ������Υ�������ˤ�äƿ��벽: mystify����ʤ���Фʤ�ʤ��ä��������������벽�ϡ���Ū�����פȤ�����Τ��Ф�����Ƚ������礤�����Թ�Ū�������Ѥ���Ƥ�������ˤϷ�ɤ��ο��Ĥ������ߤ�ʤ��Ȥ������¤�����������դ����Υ��������ؤ�̵ȿ�ʤʡֿ��ġפȡֵߺѤε��֡פϡ���������˹ߤ�ݤ��äƤ�����֤ˤĤ��Ƥ���Ǥ�Ȥ���ǧ�����ưפ�˺�Ѥ�����ΤǤ��롣
���ˤ����ο����Ȥ�����Τ�����������Ū�ʰ�̣�ǡ����������ֿ���Ū�ʿ����פΡ�¸������ˤ�äƺǽ�Ū�ˡֵߺѡפ����ˤ��Ƥ⡢������������ʹ֤μ¼�Ū��Ǻ���껦���뤳�ȤϤʤ��Ф��꤫�����ο���ǧ���Ϥ���˿�����Ǻ��⤿�餹�ΤǤ��롣�����Ƥ����丷�ʻ��¤��������Υ�å�����������Ǥ��ꤦ��ͣ�����ͳ�Ǥ��ä��ˤ�ؤ�餺���֥�������������æ¯���פμ¹Ԥˤ�äơ�����������������κ��ޤ��Ⱥᤵ���Ȥ������֤�浯�������������Ƥ������������ѹ����뤳�Ȥ�̵�����Ⱥᤵ�줿����פ����������ʤ���˻���ν��������դ���ΤǤ��롣
���ѥȥ�å�����������ɤˤ����ơֻ����դΥ������С��פ����ƶ������줿�Ȥ����ֻ��̰��Ρפζ������Ťΰ�̣����Ĥ��Ȥˤʤ롣����ϤҤȤ�Ƭ��˹ߤ���������ˤ��Хץƥ��ޤˤĤ��Ƥ��λ����Τ褦�ʷ����Ρ��Ф���פ꤫��������������Ԥ��Ф��ƤҤȤĤο���������ʤ���������ɤϤ䤬�Ʊ餸��Ǥ���������Ǥ��롣����Ͽ��Τ���Ĥ˰��������줿���ͤν���Ū�����������Ф����������Ŀ͡���Ϣ�礹��Ȥ��ˤ����椬�����������Ȧ�Ǥ��롣
�� ��ŷ�������פȤ��Ƥλ��̰��Το�
��˼��夲��ֿ������סֿ������פε��Ҥˤ����ƿ�������뤳�Ȥˤʤ���������������פξ�ħ�Ȥϡ����������������Τ��Ȥʤ��顢���Ф��С�ŷ���פʤ�����ŷ��פ��Ϸ�Ū���������Ѻ��ʡ�����о줹�롣�������ֿ������פˤ����Ƥ⤽����㳰�ǤϤʤ����Ȥ�ʬ���äƤ��롣�ֿ������פξ�ħ�ϡ����η������ü���������פ�ǧ������뤳�ȤϤޤ�Ǥ��롣����ŷ���Ȥ��Ȥ߹�碌�ˤ����Ƥ���ɽħ�κߤ����Ϥ�����������פΤ褦��������Ϳ����줿���Τ褦�Ǥ⤢�롣����ۤ�¿���λ���Ф����ȤϤǤ��ʤ������ܾ���Ƭ�Ǥ�Ǥ������ǣ��Τ褦�ˡ��ֿ������פξ�ħ�Ρ�ŷ���פȤ����餫�ʴؤ�����Τ����뤳�Ȥ��Ŧ���Ƥ����������Ȥ���Ʊ�ͤΥ��������֥르���˥�������Notre-Dame-de-l'Assomption ������ɲ�ο��ǣ��ϤǤ�ѻ����뤳�Ȥ��Ǥ��롣�����ˤ����Ƥϡ����̰��Τξ�ħ�Ǥ�����˼��夲���֥ե롼�롦�ɡ���פ�������ζ����ޤ�ﻡʤ���Сˤ���Ƥ��ꡢ�طʤ���ŷ��פǤ��뤳�Ȥ��ż�����Ƥ��롣�������äơ�������������Ƥ����ħ�������Τ���ŷ�峦�Ǥν�����Ǥ��뤫�Τ褦���κۤ��Ƥ���ΤǤ��롣
���������衧Eglise Notre-Dame-de-l'Assomption @ Montaron (Nievre)
���Τ��Ȥϡ��Ͼ�ο�ʪ�Ǥ��륢���ꥹ�ʤ����ˤˡ�ŷ���˼������������ħ��Ʊ����ǽ�����ʤ���ֿ����פ�ô���Ƥ���Ȥ������Ȥ�¾�ʤ�ʤ����դ˸����С����줫�鸫�Ƥ���Ÿ���ξ�ħ��������ξ�ħ�פˤ�̵�뤹�뤳�ȤΤǤ��ʤ�ǻ���ʿ���������������Ƥ���ΤǤ��롣
�ʡ���פν�����
08:45:00 -
entee -
TrackBacks
2006-02-22
�������ɿ������Ƚ
�����ָ����ȱ����줿���פȼ����Ū�ķ����� [7]
�ȣ��ɤλ�����ָ���Ū�������סʸ�Ⱦ��
�� �ֿ������פȥ��ꥹ�ȶ���δ�Ϣ
�����ͤ���Ȥ��ơ��ֿ������פȶ���δ֤ˤ��뿼���ؤ��ϡ��͡�������Ū�ʻ���Ϻ�ɽ������˼�������Ƥ������Ȥ�櫓���ۤ����Ѥ��̤��Ƥ��Ρֿ����פϷ����֤�ɽ������Ƥ������ֿ������פϡ����ꥹ�ȶ����ֿ������פμ����˼����Ƥ���Ȥ����פ��ʤ��ۤɤ˶�Ĵ���졢ɽ�������٤��оݡʥ��˥ե����ˤ���ʶ���ʤ������Ǥ��뤳�Ȥ�����ǰŪ���ɵᤷ�Ƥ������ȤϤۤȤ�����餫�Ǥ��롣
ʸ���̤�ֽ����ͤι�¤�פ�¿���ζ���ʿ�̥ץ��Ȥ��ƺ��Ѥ��Ƥ���Ȥ����褦�ʥ�������¸�ߤ⡢���ޤ�˴���Ū�ʤ��ȤǤ���ΤǴ������Ǥ�ޤǤ�ʤ����Ȥ��⤷��ʤ���
�� ��ħ�����οʲ��ˤĤ���
�㤨�С��Ҥȸ��ˡֽ����͡פȸ��äƤ⡢�͡��ʼ��ब���뤳�Ȥ�����Ϥ����ǰ�öǧ��ʤ���Фʤ�ʤ��������ƽ����ͤΤ����Τ����Ĥ��ϡ�����ֿ������פ�ɽ���Ƥ���Ȥϸ����褦�ʤ�Τ����롣����Ū�ˤϤ����ϡֿ������פ�ֿ������פʤɤ�ɽ���Ƥ��뤳�Ȥ����롣�����������Ͻ����ͤθ���Ū�ü��Ȥ��ƤΡֿ������פ��ȯ���Ȥ���ȯŸ���ʲ�������ΤǤ��ꡢ�ɤΤ褦�ʾ�ħ��ʬ�����Ƥ��ޤäƤ����Ȥ��Ƥ⡢�ֿ������פ���äȤ��Ƥ���ȸ����٤��Ǥ��롣�����ͤξ�ħ��ºݤο����ˤ����Ƥϡ��㤨�Ф���������ζ�Ĵ���䡢��ʿ�˿��Ӥ벣���ΰ��֡ʹ⤵�ˤ�Ĺ�����Ѥ��뤳�Ȥˤ�äơ������褦�Ȥ����å������ΰ�̣�礤��ֿ����פ���̯���Ѳ����뤳�Ȥ��ʲƤ��ʤ���Фʤ�ʤ���
[1]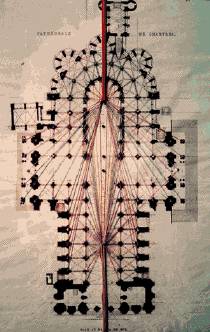 ��[2]
��[2] 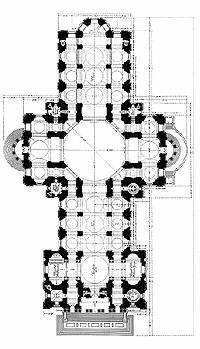
[3]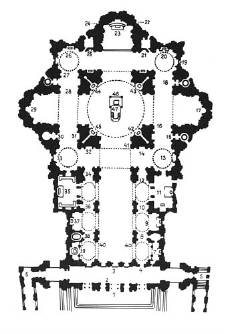
���ǰ����衧
[1] Chartres Cathedral
[2] St. Paul's Cathedral: PATH OF MESSIAH
[3] Plan of San Pietro in Vaticano
�����ͤ������դȤ���ŵ��Ū��Ȥ��ƶ��ƥɥ�����Ʋ�ˤ�ʿ�̥ץ��ʤɤ����뤬������������ˤϡ������뽽���ͤΥ����ꥢ��ȡ��Ѱۼ�ˤ���Ǥ⡢�IJ����ܤ����θ������濴���Ȥ��ƺ������ͤ��Ф��ֲ��ġפ�����������ʬ�ȡ��濴�����˸����ä��ͤ��Ф��ֽ��ġפ�����������ʬ��Ĺ������������硢���Ρ��ͽвս���Τǡֿ������פ�ɽ�����륱���������ꤦ�롣�ޤ���ʿ�̥ץ��ˤ����ơ��ֽ����͡פ�ĺ����ʬ�˥���ڥ�Τ褦�ʾ����ʷ��ߡʥ˥å��˾��ξ��������ߤ��Ƥ����硢�ֿ������פ�ɽ�������;�ˡֿ������פ�����Ƥ��뤫�˸������礬���롣�����ϸ�ˤ�ܽҤ��뤬�������ͤ�ɽ�Ф���ֿ������פ��ֻ����դΥ������Сפ�ɽ�Ф��륱�����Τ褦�ˡֿ������פ�ȯŸ���ʲ������ȸ����٤���ʤΤǤ��롣���Τ褦�ʶ����ʿ�̿ޤ����ˤ˴Ѥ����Τˡ������˴�Ϣ�����ֽ����ͤ��ѰۡפȤ�Ƥ֤٤��㤬¿������*��
* ��˾ܽҤ��뤬�����ΡȽ����͡ɤ��Ѱ�(mutation) �Ȥ����Τϡֿ������פˤޤǵڤ֡�
�� ���ꥹ�Ȥμ�ʡֿ������פ���ֿ������פؤζ��Ϥ��Ȥ��ƤΡ�
��������ʤɤΥ�����(Icon) �϶ˤ�ƾ�ħ���ι⤤������Ū����ä����ɽ�����ʤȤ�����뤬����������������Ļҥ����������ͤ���������������ˤϡ������Ͱʳ��μ�ˡ�ˤ�ä�ɽ�����줿����������̵��Ǥ��ʤ������Ĥ��ο�Ū�ż������롣
[1]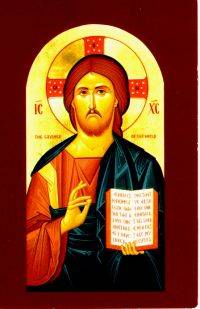 [2]
[2] 
[3] [4]
[4] 
�ҤȤĤ����ϤǤ⸫���������γۤ个�˸��Ф����Ȭ������ǵ�����Ž����סˤǤ��뤬���⤦�ҤȤĤ����ꥹ�Ȥμ�ʻءˤǤ��롣��Ǥ��礭��ʬ���ơ����ꥹ�Ȥμ꤬������Τˤ��礭��ʬ���������ο��������롣������ΰ�ĤϤ��ξϤǼ��夲��٤����ͤΤ����Ω�Ƥ�줿���ܤλءפǤ��ꡢ�⤦��Ĥϸ�˼��夲��٤��ֿ������פ�ɽ����Ω�Ƥ�줿���ܤλءפʤΤǤ��롣
�֥��ꥹ�Ȥμ�פ�ɽ�������̤��ɽ�ݾ���Ϸ���ǧ�����Τϡ����ˤ��줬�����줿������������Ȥ��Ƥ����Τ���Ū��տޤ˴ؤ�꤬���롣���������������̤���ɽ�����줿��Ū�ķ����ֿ������פǤ��뤳�ȤϤ��Ǥˤ����ˤȤäƵ����;�ϤΤʤ���ΤǤ��뤬����˥��ȥ�å��ʵ춵�ˤζ��������ʶ�����Ǥ���ֻ��̰��Ρפζ�����о�ˤ�äơ��ۤ��ʤ�̥������ˡֿ������פ�����碌�륱�������ѽФ��Ƥ���ΤǤ��롣���äơʤ����ǤϿ����ꤷ�ʤ���ΤΡ˻��̰�����ˤ�ä������˾Ҳ𤵤��ֿ������פ�¾�ʤ�̥��ȥ�å������Ѥ���������������֡ȣ��ɤˤ�äƼ��������װ�Ĥλ���Υ��ݥå��Ρ�ħ��Ǥ���ȹͤ���٤��Ǥ��롣����������ϸ�˽Ҥ٤�֡ȣ��ɤλ���פξϤˤ����ƾܽҤ����Ǥ�������
[1] Various Orthodox Prayers
Greek Orthodox Archdiocese of Australia
[2] Mother of God of Vatopedi
���ȥ���������������ȥڥǥ���ƻ��������륤����ˤ����Ȥ�����ץꥫ
[3] Iconography: Wikipedia
Salvator Mundi (Saviour of the World) by Tiziano Vecelli or Vecellio (c. 1488-90 ? August 27, 1576) aka Titan
[4] Christ's Blessing by Bellini, Giovanni (1430?-1516)
���ʿ�������Τ����ͥå����衣
������ˤ��Ƥ⡢�������ܤˤϡ��֥������λءפ��츫���ƿ����Ǥ��뤳�Ȥ�ʬ����ʤ��ۤɹ��ߤʤޤǤˡ��������ɽ�����ʤ���륱������¿������ˡ�;����ŵ��Ū����˱��ɤ��а��ä��ݤˡ�������ɬ�פ�ƶ����ˬ��ʤ����Ȥˤϸ���Ȥ��Ƥ��ޤ����Ȥ���¿��Ȧ�Ǥ��롣��������������ˤ��������ޥꥢ���ֿ������פ�ɽ�����Ļҥ��������ֿ������פ�ɽ���Ȥʤ�С��������ɤ�뤳�ȤΤǤ����å����������餫�Ǥ��롣�֣���= ���ˤ��������߽Ф����פ��ȤǤ��롣���ο���������ˤ�äơֲ����������߽Ф����Τ��פȤ������Ȥ��������ɤ߲�뤳�Ȥˤʤ롣

��ŵ��������Ǥο��Ǥ���Ȥ��ơ��ֿ������פ���ֿ������פΰܹԴ��ǤϤʤ����Ȼפ碌��֥������λءפ����롣
���������衧The Face of Love�ʡ֥������μ�פ˥ե��������������Ĥ��ο��Ǥ뤳�ȤΤǤ��륵���ȡ�
�� �ֿͤλҤ��ķ��ס�����Ҥ��ķ��פλؤ��������
�����������ꥹ�Ȥϡֿͤλ�: the Son of Man�פȸƤФ�롣�����դ��ʤ���Фʤ�ʤ��Τϡ��ब�������Ǥ���¿�ˡֿ��λ�: the Son of God�פȤϸƤФ�Ƥ��ʤ����ȤǤ���ʤ��ΤۤȤ�ɤ��ֿ��λҤȤ����٤��ȡ��פȤ����������о��ʪ�ˤ��ڸ���ո��Ǥ��äơ�ʡ����ȼ��Τη����Ȥ��ƤǤϤʤ��ˡ�����Ū������Ū�ʾ��̤˱����Ƥϡ����ꥹ�ȶ���⤽�Τ褦�˥ե졼�������Ū���֤��������ꤷ�Ƥ��롣�פ���ˡ��������ϲ��ˤ�äƾ���ˡֿ��λҡפǤ��뤳�ȤˤʤäƤ���ʰ��̤ǤϤ�����������ˤȤ���ª���������Ū�ˤ�������������ˤ��Ƥ��餬�����ֿ��λҡפ���¿�˸ƤФʤ����Ȥˤ����ϲ�������դ�¥���٤��Ǥ��롣
�����ܤ˸��äƤ⥤�������ֿͤλҡפǤ���Ȥ������Ҥ����뤳�Ȥˤ����Ͻ�ʬ�����դ�ʧ���٤��Ǥ��롣�ֿ��λҡפȤ������ҤΤۤܣ��ܤ����٤ǽФƤ���*�ֿͤλҡפȤ���ɽ����ɽ�����Ƥϲ����ȸ����С������ˤϲ���α���Ω�ƤⳢ�¤�ʤ�����ΰտޤ������Ƥ��롣�ֿͤλҡפǤ��뤫��ˤϡ�����Ϥ�Ϥ�ֿ͡פǤ��뤫���ֿͤˤ�äƻ��߽Ф��줿�����פǤ��롣�ְ�äƤ���Ͽ����ȤǤϤʤ���
�ֿͤλҡפȸƤְʾ塢��ˤ���Ƥ�¸�ߤ����ꤵ��ʤ���Ф�ʤ�������the Son of Man�ɤǼ�������Man�ɤȤϡ������פΤ��ȤǤ���Τ�Ʊ���ˡ֤Ҥȡפ��ʤ���ֿ���פΤ��ȤǤ��롣�����ǡ���ơʥޥꥢ�ˤ�����Ū�ʸ���ˤ�äƲ��ۤ��Ƥ��ʤ����Ȥ⡢����ε��ҤǤ�����Ȥ��ƶ�Ĵ����Ƥ��롣�Ȥ������Ȥϡ���the Son of Man�ɤ�ɽ����Ƥ��뤳�Ȥϡ��֥ޥꥢ�פȤ��������ɤ�ɽ����밿�����ơפˤ�ä��Ͼ�Ū������Ϳ����줿��ΤǤ��äơ�������֤Ҥ�: Man�פ�ľ�ܴؤ�롣
�����ǡ���äȤ�ñ��˹ͤ��뤳�Ȥˤ�äơ����줬�֤������༫�ȡפǤ��ꡢ������ָ���Ϳ����줿���ࡧʸ��: enlightened man�פΤ��ȤǤ��뤳�Ȥ��ʲ�褦������ϡ������ޤǤ�ʤ������������ޥꥢ�����ʤ����Mother Earth�ɤˤ��ְ�ͻҡפǤ��ꡢŷ�ʤ���ˤ�äƤ��ʡ���줿��Τȹͤ������ΤǤ��롣��������Ρ㿿�¡�Ǥ��롣��Mother Earth�ɤ������ޤ��������̿�������ۤ��Ƥ���Ȥ����Τϡ��ϵ�Ȥ������Ĥ����ϡפ���ǥ���������̿���ळ�Ȥ��Ǥ���������ʤΤǤ��ꡢ����ϤۤȤ������Τ��褦�Τʤ���ʪȯ�����ʲ���λ��¤Ǥ⤢�뤫��Ǥ��롣
*�ֿ��λҡפϡ����������桢43�ս� (43 verses)�˽ФƤ���Τ��Ф����ֿͤλҡפϡ�84�ս� (84 verses)�Ǥ��롣�����ޤ��ȡֿ��λҡ�44�ս���Ф����ֿͤλҡ�94�ս�Ǥ��ꡢ�о����٤��ܰʾ�Ȥʤ롣
�����������Ρ�ʸ���פϡ�����ˤȤäƤΡ�ʡ���פǤ��ꡢ��ʡ���줿��̿�Ǥ����Ʊ���ˡ��ֻϤޤ�⤢�꽪���⤢���Ρסʦ��Ǥ��ꦸ�Ǥ���ˤȤ����о줹�롣�����ƥ��ꥹ�ȼ��Τ����Τ褦�˼��ʤ����Τ���������������ʤ���̿�⡢���������ʾ夤�����ʤʤ���Фʤ�ʤ����������θ¤ꤢ���ʸ���Ρ����ϡ�ʡ����Ǥ�ܤ���Ƥ���褦�ˡ��ʹ֤����ˤ�����ִ��ספ�⤿�餹��������ʤ��ä��¤��������褦�ˤʤꡢ�����ʤ��ä��ܤϸ�����褦�ˤʤꡢΩ�Ƥʤ��ä��Ԥ�Ω�ä��⤯�褦�ˤʤ롣���Ǥ������˻פ���Ԥ�©���֤���
�������������ִ��ספΤ��٤ƤϤޤ��˺����ܷ⤹��褦�ʵ���ʸ���������ˤ⤿�餷����ʡ���פ��Τ�ΤǤϤʤ������ޤ��ˡ֤��ΰ��ڤ����������ʤ顢�����Ϥ����Ǽ���ʤ��Ǥ������פȥ�ϥ����ˤ���ۤɤˡ������������ڤϡ������ʸ���Τ����������������Ƥ���㤢���뤹�٤�: all and everything��Ǥ��롣���������Ρ�ʡ���פϡ�ʸ���ν���������ˤ�������ι���Ƚ跺�ˤˤ�äƽ���롣�ɤ�ʻ��𤬤��ä��ˤ��衢�ֵ�����פ��������оݤȤʤä��������Ƥ����ŷ�����������뤳�Ȥʤ���30��Ⱦ�����Ȥ����㤵�ǡ������ˤ�ä�����Ĥ���ΤǤ��롣���������ҤȤĤ�ͽ����Ĥ��ơ��ֻ�Ϥޤ����äƤ���פȤ���ͽ����
��Ⱦ�Ф˻�ʤʤ���Фʤ�ʤ������Ρʵ��ѡ�ʸ���פȤ�����Τϡ��ޤ��ˤ��������֥������ο����פ��ķ��Ȥ��ƹ��ۤ��줿��ΤȤ������Ȥ��Ǥ��褦��
�� ���ڤ���Ρֿ�������
�㤨�в��ڤ������ˤ����Ƥⶵ���sacred music�γڶʷ����ˤ�ǻ���ʡ�������¤�פ����Ф���롣����ȤΤĤʤ���Τ���ڶʤ�����ھϡ������ʤ��������������ˤʤäƤ��뤳�ȤϤޤä��������ǤϤʤ��������ˤϤդ��Ĥ���ʬ�����ʤ�������ͤο�ʿ���ʲ����ˤȿ�ľ���ʽ����ˤ�ɽ�����褦�Ȥ����տޤ�����Ǥ��롣���줬���ƤϤޤ���ʤ���ˤϡ����Ū�������Ȥ����Ǥϡ�G���ޡ��顼�θ�����裲�֡�����פ���Ӹ�����裸�֡������ƥ�����������裳�֥֡��륬��פʤɤ����롣��������̾�Υ���ե��ˡ��ۡ���DZ��դ���뤳�Ȥ����ꤵ��Ƥ���Ȥ������ϡ����륬��䥯�磻��������˴ޤ����ΤǤ��뤿��ˡ�����ʤǤ���ʤ��饳���ȥۡ�����ϡ����⤽�ⶵ��Ǥα��դ����ꤵ��Ƥ���褦�˻פ��롣�Ĥޤꤳ���ϸ���ڷ�����Ż�ä��������� (sacred music) �ΰ���ȸƤ֤٤���ΤʤΤ��⤷��ʤ���
���Ť��Ȥ����ǤϽ������뽡�����ڤǤ���ХåϤ�¿���Υ��륬��ʡ֥ץ��塼�ɤȥ��顼��ס֥ץ��塼�ɤȥա����ס֥ȥå������ȥա����פʤɤ⡢�����Ρ����������פ���ȹͤ��뤳�Ȥ��Ǥ���Ǥ�������
�ʹ��ʤ���ʤȳ�ĥ��ͽ���
�� �ȣ��ɤλ���ȿ����ؤ��Τ������˸�����ֿ�������
�褯�Τ�줿���¤Ǥ��뤬���ҳ��Ѥˤ�äƿ��ब�Ƥ��糤�˾��Ф��Ƥ�����ҳ�����Τ��������Ȥʤä���ϡ����ڥ���ȥݥ�ȥ���Ǥ��롣������춵���۶��ץ��������Ȥ�ɽ���ΤȤʤä�������ϩ�Ф����Ȥ�������ˡֿ���Φ��ȯ���˷Ҥ����̵�����������餬�ֿ���Φ�פ�¸�ߤ��Τ�ʤ��ä��Ȥ�������Ǥ��äǤ���ˡ�
�����륫�ȥ�å�����Ϥ�Ȥ��ơ֥�ƥ�ʸ���פȸ������Τ��������Ƥ˸��Ф����Τ⡢��������äƹԤʤä��ߥå��������ϤȤ���˼����Ǥ�äƤ��뿢̱�ϻ��ۤη�̤Ǥ��롣��ҳ����夬��餳�Ρ����פˤ�äƿʤ��줿���ȤϾ�ħŪ�Ǥ��롣





�����ơ��ݥ�ȥ���ȥ��ڥ���ι���������פǤ��뤳�Ȥˤ���������դ�¥���٤��Ǥ��롣���Ρ����פȤ��θ���������Ƹ��������Ƥ��λ���Ȥ����Τ���ˤΤ��륨�ݥå���ɽ�ݤ��Ƥ����Τȹͤ���٤��Ǥ��롣
���ߤΥ��ڥ����������Ǥ���ʤ����ʿ�����ˣ�ʬ�䤹��ѥ�����ˤ�äơֻ������פλ���ؤβ��ϴ���ɽ�����Ƥ��롣�ʥ��ڥ������ˤϸ��Ѥ�̱���Ѥ����뤬�����ѹ���ˤϥإ饯�쥹����ˤ��֣��ܤ����פ��ʤ���ֿ������פΰż��⤢�롣��
�����ޡ����ȥ�å������ܻ��Ǥ������������Թ�ι���ʥ��ȥ�å����Ĵ��ˤ����������Ǥ��ꡢ�ޤ����Ǥ���Ȥ������Ȥϡ���ħ�塢�ˤ�ƽ��פʰ�̣����ġ��ֿ������פϡ��ʲ� vs. �� �� �� vs. ��ˤǤ���Ȥ������Ȥ˸��Ф����¾���֥ڥƥ����Ϥ��줿���פξ�ħ�������Ȥ߹�碌���Ƥ��뤳�Ȥˤ⸫�Ф���롣����������X�����פν����������Ϸ��ϡ֥��륿����: saltire�פȸƤФ�롣�ܽҤ��ʤ��������ΡּФώ���פϡ��������������뽽���ͤȤ������ۤʤ��������̣����ġ����θ����Ȥ߹�碌���ϡ��ֽ����פΤ⤦��Ĥ�ɽ�ݤΥѥ��������ơֿ������פ�������ݤˡ��ƤӸ��ڤ����Ǥ�������
�������ι���ˤĤ��ƤϤ����ǾܽҤ��ʤ��������Ѥι���Ȥ��ƻȤ��뤳�ι���ϡ��������Ǥ��ꡢ���η��ˤ�äƥ���������Թ�ι���Τ褦�ʤ�����פ��붵Ū��̣����ã���Ƥ��롣����������ˤĤ��Ƥ��붵Ū���ϺƤӡ֡ȣ��ɤλ���פξϤ���ǺƤ����ڤ���뤳�Ȥˤʤ롣�����Ǥϡ������Ƥ����餵�ޤʡֿ������פ��ݻ������������Ĺ�Ȥ����Ū�˽��פ�����餸�뤳�Ȥˤʤ���������Ȥ���ڤ����α��롣
�� �ֿ������פ��������ֽ����פλϤޤ�ʾϤΤޤȤ��
���Τ�������̿�θ��Ǥ���Mother Earth / Mother Nature���Ĥ��ˤ��ΰ�ͻҤǤ�������ʸ������Ȥ��������ब�����ˡ�ʸ���פȸƤ֤���������ʳ������ä��Ȥ������Ū�ˡȣ��ɤλ���������������Ȥ��������롣�������������Ū���ݥå��פϡ��ҤȤĤλ���ξ�ħ�Ȥ��ơ�ɬ�������ʪ�����Ӥˤʤ���������뤳�Ȥ�ã������롣����ϡ����פ��ӡפΤ褦�ʤ�ΤǤ��롣�������ˤˤ�����ǸŤˤ��ơ�������ޤ��ʤ������˿��������ε����ϡ����褽2000ǯ���˹Ԥ�줿������Ū���������ˡ�Ȥϡ����ܤΡ��ڤ����פˤ�ä�¤��줿�ֶˤ���ü�פʷ����ν跺��ξ���ˤ������̤��ȤǤ��ä��������Ƥ��ο�ʪ�Υݡ��ȥ졼�Ȥϥޥꥢ���������ֿͤλҥ������פȤ��ơ����뤤�����Τ������������Ħ�������������Ǥϻؤ���Ω�Ƥ뤳�Ȥǡ����ߤǤ�������ब�ȣ��ɤξ�ħ�Ǥ��ä����Ȥ�³���Ƥ��롣
���������������ʸ���ȸƤФ���ΤǤ���¤ꡢƱ���ˡֽ����פΡֻϤޤ�פ����롣�ָ��Τ����פˤ��Ƥ�����������פ���ʸ���ˤ��Ƥ⡢�������Ȥ��������Ρפν�̿�Ȥ��ơ��ֻϤޤ�פΤȤ��ˡֽ����פ��μ¤���«�����ΤǤ��롣������Ȥ����Τ��뤳���٤�ʸ���������ħ���륳���ɤǤ���֥����������ꥹ�ȡפϡ�����Ω�Ƥ����ˡֻ�ϥ���ե��Ǥ��ꡢ���ᥬ�Ǥ���פȸ�뤳�ȤǡֻϤޤ꤬���꽪��꤬��������ʸ�����Τ�ΤǤ���פ��Ȥ�����˹��Ƥ���ΤǤ��롣
�����ơ���ϡ��Ǥӱ����֤��ĤƤ�ʸ���פκǽ����̤ˤ�������«�����̤�ֵ��äƤ����פΤ��ä�����������ϡ֤����٤�ʸ���פˤ����Ƥ�Ƥ�Ʊ�������ƻ�����Ǥ���ΤǤ��ꡢ���ĤƤ����Ǥ��ä��褦�˺Ƥ������˽褵����ǽ�����⤤������ˤĤ��Ƥθ��ϡ�ʡ���ֲ����áפǤ����Ʊ����̤���ͽ�������Ρʡ� ʡ��: Gospel�ˤȤ��Ƥ��ɤळ�Ȥ��Ǥ��뤳�ȡ����ʤ��������: Iesus, Jesus�Ȥ���̾�ΰ��������Ū�ʹ֡�ˤĤ��Ƥ��äǤ��뤳�Ȥ������⤿�餹�Ǥ�������
���Υѥ�����ϸź������ο��ä˸�����ֲ��������ķ��פȤ���ɽ������Ƥ�����Ρ��ޤ��Х������ɡ�����������ɽ������Ƥ�����Τ��ܼ�Ū��Ʊ���Ǥ��롣�������ο���Ū�ķ��ˤĤ��Ƥ�����Ȥϡ��ֲ��λ����פȤ������郎������켫�ȡ�����֤��αƶ����Ȥ�뤳�Ȥ��Ǥ��ʤ�����ε��ϡפ�ؤ��ΤȤ��Ƶ����뤳�Ȥ��Ȥ���ʸ̮�Ǽ´����뤳�Ȥ��Ǥ��뤫�ɤ��������ʤ�����֤���켫�Ȥ�����פȤ�������Ǥ��뤫�ɤ����˳ݤ��äƤ���ΤǤ��롣
�����ͤ���Ȥ��ơ��ֿ������פȶ���δ֤ˤ��뿼���ؤ��ϡ��͡�������Ū�ʻ���Ϻ�ɽ������˼�������Ƥ������Ȥ�櫓���ۤ����Ѥ��̤��Ƥ��Ρֿ����פϷ����֤�ɽ������Ƥ������ֿ������פϡ����ꥹ�ȶ����ֿ������פμ����˼����Ƥ���Ȥ����פ��ʤ��ۤɤ˶�Ĵ���졢ɽ�������٤��оݡʥ��˥ե����ˤ���ʶ���ʤ������Ǥ��뤳�Ȥ�����ǰŪ���ɵᤷ�Ƥ������ȤϤۤȤ�����餫�Ǥ��롣
ʸ���̤�ֽ����ͤι�¤�פ�¿���ζ���ʿ�̥ץ��Ȥ��ƺ��Ѥ��Ƥ���Ȥ����褦�ʥ�������¸�ߤ⡢���ޤ�˴���Ū�ʤ��ȤǤ���ΤǴ������Ǥ�ޤǤ�ʤ����Ȥ��⤷��ʤ���
�� ��ħ�����οʲ��ˤĤ���
�㤨�С��Ҥȸ��ˡֽ����͡פȸ��äƤ⡢�͡��ʼ��ब���뤳�Ȥ�����Ϥ����ǰ�öǧ��ʤ���Фʤ�ʤ��������ƽ����ͤΤ����Τ����Ĥ��ϡ�����ֿ������פ�ɽ���Ƥ���Ȥϸ����褦�ʤ�Τ����롣����Ū�ˤϤ����ϡֿ������פ�ֿ������פʤɤ�ɽ���Ƥ��뤳�Ȥ����롣�����������Ͻ����ͤθ���Ū�ü��Ȥ��ƤΡֿ������פ��ȯ���Ȥ���ȯŸ���ʲ�������ΤǤ��ꡢ�ɤΤ褦�ʾ�ħ��ʬ�����Ƥ��ޤäƤ����Ȥ��Ƥ⡢�ֿ������פ���äȤ��Ƥ���ȸ����٤��Ǥ��롣�����ͤξ�ħ��ºݤο����ˤ����Ƥϡ��㤨�Ф���������ζ�Ĵ���䡢��ʿ�˿��Ӥ벣���ΰ��֡ʹ⤵�ˤ�Ĺ�����Ѥ��뤳�Ȥˤ�äơ������褦�Ȥ����å������ΰ�̣�礤��ֿ����פ���̯���Ѳ����뤳�Ȥ��ʲƤ��ʤ���Фʤ�ʤ���
[1]
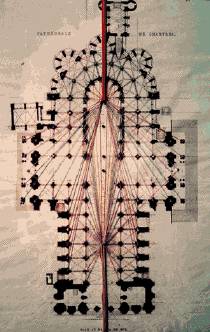 ��[2]
��[2] 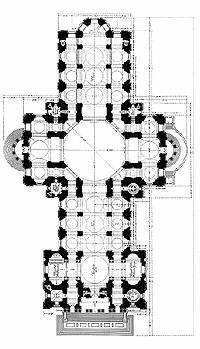
[3]
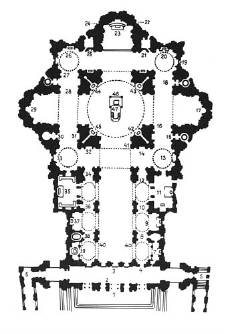
���ǰ����衧
[1] Chartres Cathedral
[2] St. Paul's Cathedral: PATH OF MESSIAH
[3] Plan of San Pietro in Vaticano
�����ͤ������դȤ���ŵ��Ū��Ȥ��ƶ��ƥɥ�����Ʋ�ˤ�ʿ�̥ץ��ʤɤ����뤬������������ˤϡ������뽽���ͤΥ����ꥢ��ȡ��Ѱۼ�ˤ���Ǥ⡢�IJ����ܤ����θ������濴���Ȥ��ƺ������ͤ��Ф��ֲ��ġפ�����������ʬ�ȡ��濴�����˸����ä��ͤ��Ф��ֽ��ġפ�����������ʬ��Ĺ������������硢���Ρ��ͽвս���Τǡֿ������פ�ɽ�����륱���������ꤦ�롣�ޤ���ʿ�̥ץ��ˤ����ơ��ֽ����͡פ�ĺ����ʬ�˥���ڥ�Τ褦�ʾ����ʷ��ߡʥ˥å��˾��ξ��������ߤ��Ƥ����硢�ֿ������פ�ɽ�������;�ˡֿ������פ�����Ƥ��뤫�˸������礬���롣�����ϸ�ˤ�ܽҤ��뤬�������ͤ�ɽ�Ф���ֿ������פ��ֻ����դΥ������Сפ�ɽ�Ф��륱�����Τ褦�ˡֿ������פ�ȯŸ���ʲ������ȸ����٤���ʤΤǤ��롣���Τ褦�ʶ����ʿ�̿ޤ����ˤ˴Ѥ����Τˡ������˴�Ϣ�����ֽ����ͤ��ѰۡפȤ�Ƥ֤٤��㤬¿������*��
* ��˾ܽҤ��뤬�����ΡȽ����͡ɤ��Ѱ�(mutation) �Ȥ����Τϡֿ������פˤޤǵڤ֡�
�� ���ꥹ�Ȥμ�ʡֿ������פ���ֿ������פؤζ��Ϥ��Ȥ��ƤΡ�
��������ʤɤΥ�����(Icon) �϶ˤ�ƾ�ħ���ι⤤������Ū����ä����ɽ�����ʤȤ�����뤬����������������Ļҥ����������ͤ���������������ˤϡ������Ͱʳ��μ�ˡ�ˤ�ä�ɽ�����줿����������̵��Ǥ��ʤ������Ĥ��ο�Ū�ż������롣
[1]

[3]
 [4]
[4] 
�ҤȤĤ����ϤǤ⸫���������γۤ个�˸��Ф����Ȭ������ǵ�����Ž����סˤǤ��뤬���⤦�ҤȤĤ����ꥹ�Ȥμ�ʻءˤǤ��롣��Ǥ��礭��ʬ���ơ����ꥹ�Ȥμ꤬������Τˤ��礭��ʬ���������ο��������롣������ΰ�ĤϤ��ξϤǼ��夲��٤����ͤΤ����Ω�Ƥ�줿���ܤλءפǤ��ꡢ�⤦��Ĥϸ�˼��夲��٤��ֿ������פ�ɽ����Ω�Ƥ�줿���ܤλءפʤΤǤ��롣
�֥��ꥹ�Ȥμ�פ�ɽ�������̤��ɽ�ݾ���Ϸ���ǧ�����Τϡ����ˤ��줬�����줿������������Ȥ��Ƥ����Τ���Ū��տޤ˴ؤ�꤬���롣���������������̤���ɽ�����줿��Ū�ķ����ֿ������פǤ��뤳�ȤϤ��Ǥˤ����ˤȤäƵ����;�ϤΤʤ���ΤǤ��뤬����˥��ȥ�å��ʵ춵�ˤζ��������ʶ�����Ǥ���ֻ��̰��Ρפζ�����о�ˤ�äơ��ۤ��ʤ�̥������ˡֿ������פ�����碌�륱�������ѽФ��Ƥ���ΤǤ��롣���äơʤ����ǤϿ����ꤷ�ʤ���ΤΡ˻��̰�����ˤ�ä������˾Ҳ𤵤��ֿ������פ�¾�ʤ�̥��ȥ�å������Ѥ���������������֡ȣ��ɤˤ�äƼ��������װ�Ĥλ���Υ��ݥå��Ρ�ħ��Ǥ���ȹͤ���٤��Ǥ��롣����������ϸ�˽Ҥ٤�֡ȣ��ɤλ���פξϤˤ����ƾܽҤ����Ǥ�������
[1] Various Orthodox Prayers
Greek Orthodox Archdiocese of Australia
[2] Mother of God of Vatopedi
���ȥ���������������ȥڥǥ���ƻ��������륤����ˤ����Ȥ�����ץꥫ
[3] Iconography: Wikipedia
Salvator Mundi (Saviour of the World) by Tiziano Vecelli or Vecellio (c. 1488-90 ? August 27, 1576) aka Titan
[4] Christ's Blessing by Bellini, Giovanni (1430?-1516)
���ʿ�������Τ����ͥå����衣
������ˤ��Ƥ⡢�������ܤˤϡ��֥������λءפ��츫���ƿ����Ǥ��뤳�Ȥ�ʬ����ʤ��ۤɹ��ߤʤޤǤˡ��������ɽ�����ʤ���륱������¿������ˡ�;����ŵ��Ū����˱��ɤ��а��ä��ݤˡ�������ɬ�פ�ƶ����ˬ��ʤ����Ȥˤϸ���Ȥ��Ƥ��ޤ����Ȥ���¿��Ȧ�Ǥ��롣��������������ˤ��������ޥꥢ���ֿ������פ�ɽ�����Ļҥ��������ֿ������פ�ɽ���Ȥʤ�С��������ɤ�뤳�ȤΤǤ����å����������餫�Ǥ��롣�֣���= ���ˤ��������߽Ф����פ��ȤǤ��롣���ο���������ˤ�äơֲ����������߽Ф����Τ��פȤ������Ȥ��������ɤ߲�뤳�Ȥˤʤ롣

��ŵ��������Ǥο��Ǥ���Ȥ��ơ��ֿ������פ���ֿ������פΰܹԴ��ǤϤʤ����Ȼפ碌��֥������λءפ����롣
���������衧The Face of Love�ʡ֥������μ�פ˥ե��������������Ĥ��ο��Ǥ뤳�ȤΤǤ��륵���ȡ�
�� �ֿͤλҤ��ķ��ס�����Ҥ��ķ��פλؤ��������
�����������ꥹ�Ȥϡֿͤλ�: the Son of Man�פȸƤФ�롣�����դ��ʤ���Фʤ�ʤ��Τϡ��ब�������Ǥ���¿�ˡֿ��λ�: the Son of God�פȤϸƤФ�Ƥ��ʤ����ȤǤ���ʤ��ΤۤȤ�ɤ��ֿ��λҤȤ����٤��ȡ��פȤ����������о��ʪ�ˤ��ڸ���ո��Ǥ��äơ�ʡ����ȼ��Τη����Ȥ��ƤǤϤʤ��ˡ�����Ū������Ū�ʾ��̤˱����Ƥϡ����ꥹ�ȶ���⤽�Τ褦�˥ե졼�������Ū���֤��������ꤷ�Ƥ��롣�פ���ˡ��������ϲ��ˤ�äƾ���ˡֿ��λҡפǤ��뤳�ȤˤʤäƤ���ʰ��̤ǤϤ�����������ˤȤ���ª���������Ū�ˤ�������������ˤ��Ƥ��餬�����ֿ��λҡפ���¿�˸ƤФʤ����Ȥˤ����ϲ�������դ�¥���٤��Ǥ��롣
�����ܤ˸��äƤ⥤�������ֿͤλҡפǤ���Ȥ������Ҥ����뤳�Ȥˤ����Ͻ�ʬ�����դ�ʧ���٤��Ǥ��롣�ֿ��λҡפȤ������ҤΤۤܣ��ܤ����٤ǽФƤ���*�ֿͤλҡפȤ���ɽ����ɽ�����Ƥϲ����ȸ����С������ˤϲ���α���Ω�ƤⳢ�¤�ʤ�����ΰտޤ������Ƥ��롣�ֿͤλҡפǤ��뤫��ˤϡ�����Ϥ�Ϥ�ֿ͡פǤ��뤫���ֿͤˤ�äƻ��߽Ф��줿�����פǤ��롣�ְ�äƤ���Ͽ����ȤǤϤʤ���
�ֿͤλҡפȸƤְʾ塢��ˤ���Ƥ�¸�ߤ����ꤵ��ʤ���Ф�ʤ�������the Son of Man�ɤǼ�������Man�ɤȤϡ������פΤ��ȤǤ���Τ�Ʊ���ˡ֤Ҥȡפ��ʤ���ֿ���פΤ��ȤǤ��롣�����ǡ���ơʥޥꥢ�ˤ�����Ū�ʸ���ˤ�äƲ��ۤ��Ƥ��ʤ����Ȥ⡢����ε��ҤǤ�����Ȥ��ƶ�Ĵ����Ƥ��롣�Ȥ������Ȥϡ���the Son of Man�ɤ�ɽ����Ƥ��뤳�Ȥϡ��֥ޥꥢ�פȤ��������ɤ�ɽ����밿�����ơפˤ�ä��Ͼ�Ū������Ϳ����줿��ΤǤ��äơ�������֤Ҥ�: Man�פ�ľ�ܴؤ�롣
�����ǡ���äȤ�ñ��˹ͤ��뤳�Ȥˤ�äơ����줬�֤������༫�ȡפǤ��ꡢ������ָ���Ϳ����줿���ࡧʸ��: enlightened man�פΤ��ȤǤ��뤳�Ȥ��ʲ�褦������ϡ������ޤǤ�ʤ������������ޥꥢ�����ʤ����Mother Earth�ɤˤ��ְ�ͻҡפǤ��ꡢŷ�ʤ���ˤ�äƤ��ʡ���줿��Τȹͤ������ΤǤ��롣��������Ρ㿿�¡�Ǥ��롣��Mother Earth�ɤ������ޤ��������̿�������ۤ��Ƥ���Ȥ����Τϡ��ϵ�Ȥ������Ĥ����ϡפ���ǥ���������̿���ळ�Ȥ��Ǥ���������ʤΤǤ��ꡢ����ϤۤȤ������Τ��褦�Τʤ���ʪȯ�����ʲ���λ��¤Ǥ⤢�뤫��Ǥ��롣
*�ֿ��λҡפϡ����������桢43�ս� (43 verses)�˽ФƤ���Τ��Ф����ֿͤλҡפϡ�84�ս� (84 verses)�Ǥ��롣�����ޤ��ȡֿ��λҡ�44�ս���Ф����ֿͤλҡ�94�ս�Ǥ��ꡢ�о����٤��ܰʾ�Ȥʤ롣
�����������Ρ�ʸ���פϡ�����ˤȤäƤΡ�ʡ���פǤ��ꡢ��ʡ���줿��̿�Ǥ����Ʊ���ˡ��ֻϤޤ�⤢�꽪���⤢���Ρסʦ��Ǥ��ꦸ�Ǥ���ˤȤ����о줹�롣�����ƥ��ꥹ�ȼ��Τ����Τ褦�˼��ʤ����Τ���������������ʤ���̿�⡢���������ʾ夤�����ʤʤ���Фʤ�ʤ����������θ¤ꤢ���ʸ���Ρ����ϡ�ʡ����Ǥ�ܤ���Ƥ���褦�ˡ��ʹ֤����ˤ�����ִ��ספ�⤿�餹��������ʤ��ä��¤��������褦�ˤʤꡢ�����ʤ��ä��ܤϸ�����褦�ˤʤꡢΩ�Ƥʤ��ä��Ԥ�Ω�ä��⤯�褦�ˤʤ롣���Ǥ������˻פ���Ԥ�©���֤���
�������������ִ��ספΤ��٤ƤϤޤ��˺����ܷ⤹��褦�ʵ���ʸ���������ˤ⤿�餷����ʡ���פ��Τ�ΤǤϤʤ������ޤ��ˡ֤��ΰ��ڤ����������ʤ顢�����Ϥ����Ǽ���ʤ��Ǥ������פȥ�ϥ����ˤ���ۤɤˡ������������ڤϡ������ʸ���Τ����������������Ƥ���㤢���뤹�٤�: all and everything��Ǥ��롣���������Ρ�ʡ���פϡ�ʸ���ν���������ˤ�������ι���Ƚ跺�ˤˤ�äƽ���롣�ɤ�ʻ��𤬤��ä��ˤ��衢�ֵ�����פ��������оݤȤʤä��������Ƥ����ŷ�����������뤳�Ȥʤ���30��Ⱦ�����Ȥ����㤵�ǡ������ˤ�ä�����Ĥ���ΤǤ��롣���������ҤȤĤ�ͽ����Ĥ��ơ��ֻ�Ϥޤ����äƤ���פȤ���ͽ����
��Ⱦ�Ф˻�ʤʤ���Фʤ�ʤ������Ρʵ��ѡ�ʸ���פȤ�����Τϡ��ޤ��ˤ��������֥������ο����פ��ķ��Ȥ��ƹ��ۤ��줿��ΤȤ������Ȥ��Ǥ��褦��
�� ���ڤ���Ρֿ�������
�㤨�в��ڤ������ˤ����Ƥⶵ���sacred music�γڶʷ����ˤ�ǻ���ʡ�������¤�פ����Ф���롣����ȤΤĤʤ���Τ���ڶʤ�����ھϡ������ʤ��������������ˤʤäƤ��뤳�ȤϤޤä��������ǤϤʤ��������ˤϤդ��Ĥ���ʬ�����ʤ�������ͤο�ʿ���ʲ����ˤȿ�ľ���ʽ����ˤ�ɽ�����褦�Ȥ����տޤ�����Ǥ��롣���줬���ƤϤޤ���ʤ���ˤϡ����Ū�������Ȥ����Ǥϡ�G���ޡ��顼�θ�����裲�֡�����פ���Ӹ�����裸�֡������ƥ�����������裳�֥֡��륬��פʤɤ����롣��������̾�Υ���ե��ˡ��ۡ���DZ��դ���뤳�Ȥ����ꤵ��Ƥ���Ȥ������ϡ����륬��䥯�磻��������˴ޤ����ΤǤ��뤿��ˡ�����ʤǤ���ʤ��饳���ȥۡ�����ϡ����⤽�ⶵ��Ǥα��դ����ꤵ��Ƥ���褦�˻פ��롣�Ĥޤꤳ���ϸ���ڷ�����Ż�ä��������� (sacred music) �ΰ���ȸƤ֤٤���ΤʤΤ��⤷��ʤ���
���Ť��Ȥ����ǤϽ������뽡�����ڤǤ���ХåϤ�¿���Υ��륬��ʡ֥ץ��塼�ɤȥ��顼��ס֥ץ��塼�ɤȥա����ס֥ȥå������ȥա����פʤɤ⡢�����Ρ����������פ���ȹͤ��뤳�Ȥ��Ǥ���Ǥ�������
�ʹ��ʤ���ʤȳ�ĥ��ͽ���
�� �ȣ��ɤλ���ȿ����ؤ��Τ������˸�����ֿ�������
�褯�Τ�줿���¤Ǥ��뤬���ҳ��Ѥˤ�äƿ��ब�Ƥ��糤�˾��Ф��Ƥ�����ҳ�����Τ��������Ȥʤä���ϡ����ڥ���ȥݥ�ȥ���Ǥ��롣������춵���۶��ץ��������Ȥ�ɽ���ΤȤʤä�������ϩ�Ф����Ȥ�������ˡֿ���Φ��ȯ���˷Ҥ����̵�����������餬�ֿ���Φ�פ�¸�ߤ��Τ�ʤ��ä��Ȥ�������Ǥ��äǤ���ˡ�
�����륫�ȥ�å�����Ϥ�Ȥ��ơ֥�ƥ�ʸ���פȸ������Τ��������Ƥ˸��Ф����Τ⡢��������äƹԤʤä��ߥå��������ϤȤ���˼����Ǥ�äƤ��뿢̱�ϻ��ۤη�̤Ǥ��롣��ҳ����夬��餳�Ρ����פˤ�äƿʤ��줿���ȤϾ�ħŪ�Ǥ��롣





�����ơ��ݥ�ȥ���ȥ��ڥ���ι���������פǤ��뤳�Ȥˤ���������դ�¥���٤��Ǥ��롣���Ρ����פȤ��θ���������Ƹ��������Ƥ��λ���Ȥ����Τ���ˤΤ��륨�ݥå���ɽ�ݤ��Ƥ����Τȹͤ���٤��Ǥ��롣
���ߤΥ��ڥ����������Ǥ���ʤ����ʿ�����ˣ�ʬ�䤹��ѥ�����ˤ�äơֻ������פλ���ؤβ��ϴ���ɽ�����Ƥ��롣�ʥ��ڥ������ˤϸ��Ѥ�̱���Ѥ����뤬�����ѹ���ˤϥإ饯�쥹����ˤ��֣��ܤ����פ��ʤ���ֿ������פΰż��⤢�롣��
�����ޡ����ȥ�å������ܻ��Ǥ������������Թ�ι���ʥ��ȥ�å����Ĵ��ˤ����������Ǥ��ꡢ�ޤ����Ǥ���Ȥ������Ȥϡ���ħ�塢�ˤ�ƽ��פʰ�̣����ġ��ֿ������פϡ��ʲ� vs. �� �� �� vs. ��ˤǤ���Ȥ������Ȥ˸��Ф����¾���֥ڥƥ����Ϥ��줿���פξ�ħ�������Ȥ߹�碌���Ƥ��뤳�Ȥˤ⸫�Ф���롣����������X�����פν����������Ϸ��ϡ֥��륿����: saltire�פȸƤФ�롣�ܽҤ��ʤ��������ΡּФώ���פϡ��������������뽽���ͤȤ������ۤʤ��������̣����ġ����θ����Ȥ߹�碌���ϡ��ֽ����פΤ⤦��Ĥ�ɽ�ݤΥѥ��������ơֿ������פ�������ݤˡ��ƤӸ��ڤ����Ǥ�������
�������ι���ˤĤ��ƤϤ����ǾܽҤ��ʤ��������Ѥι���Ȥ��ƻȤ��뤳�ι���ϡ��������Ǥ��ꡢ���η��ˤ�äƥ���������Թ�ι���Τ褦�ʤ�����פ��붵Ū��̣����ã���Ƥ��롣����������ˤĤ��Ƥ��붵Ū���ϺƤӡ֡ȣ��ɤλ���פξϤ���ǺƤ����ڤ���뤳�Ȥˤʤ롣�����Ǥϡ������Ƥ����餵�ޤʡֿ������פ��ݻ������������Ĺ�Ȥ����Ū�˽��פ�����餸�뤳�Ȥˤʤ���������Ȥ���ڤ����α��롣
�� �ֿ������פ��������ֽ����פλϤޤ�ʾϤΤޤȤ��
���Τ�������̿�θ��Ǥ���Mother Earth / Mother Nature���Ĥ��ˤ��ΰ�ͻҤǤ�������ʸ������Ȥ��������ब�����ˡ�ʸ���פȸƤ֤���������ʳ������ä��Ȥ������Ū�ˡȣ��ɤλ���������������Ȥ��������롣�������������Ū���ݥå��פϡ��ҤȤĤλ���ξ�ħ�Ȥ��ơ�ɬ�������ʪ�����Ӥˤʤ���������뤳�Ȥ�ã������롣����ϡ����פ��ӡפΤ褦�ʤ�ΤǤ��롣�������ˤˤ�����ǸŤˤ��ơ�������ޤ��ʤ������˿��������ε����ϡ����褽2000ǯ���˹Ԥ�줿������Ū���������ˡ�Ȥϡ����ܤΡ��ڤ����פˤ�ä�¤��줿�ֶˤ���ü�פʷ����ν跺��ξ���ˤ������̤��ȤǤ��ä��������Ƥ��ο�ʪ�Υݡ��ȥ졼�Ȥϥޥꥢ���������ֿͤλҥ������פȤ��ơ����뤤�����Τ������������Ħ�������������Ǥϻؤ���Ω�Ƥ뤳�Ȥǡ����ߤǤ�������ब�ȣ��ɤξ�ħ�Ǥ��ä����Ȥ�³���Ƥ��롣
���������������ʸ���ȸƤФ���ΤǤ���¤ꡢƱ���ˡֽ����פΡֻϤޤ�פ����롣�ָ��Τ����פˤ��Ƥ�����������פ���ʸ���ˤ��Ƥ⡢�������Ȥ��������Ρפν�̿�Ȥ��ơ��ֻϤޤ�פΤȤ��ˡֽ����פ��μ¤���«�����ΤǤ��롣������Ȥ����Τ��뤳���٤�ʸ���������ħ���륳���ɤǤ���֥����������ꥹ�ȡפϡ�����Ω�Ƥ����ˡֻ�ϥ���ե��Ǥ��ꡢ���ᥬ�Ǥ���פȸ�뤳�ȤǡֻϤޤ꤬���꽪��꤬��������ʸ�����Τ�ΤǤ���פ��Ȥ�����˹��Ƥ���ΤǤ��롣
�����ơ���ϡ��Ǥӱ����֤��ĤƤ�ʸ���פκǽ����̤ˤ�������«�����̤�ֵ��äƤ����פΤ��ä�����������ϡ֤����٤�ʸ���פˤ����Ƥ�Ƥ�Ʊ�������ƻ�����Ǥ���ΤǤ��ꡢ���ĤƤ����Ǥ��ä��褦�˺Ƥ������˽褵����ǽ�����⤤������ˤĤ��Ƥθ��ϡ�ʡ���ֲ����áפǤ����Ʊ����̤���ͽ�������Ρʡ� ʡ��: Gospel�ˤȤ��Ƥ��ɤळ�Ȥ��Ǥ��뤳�ȡ����ʤ��������: Iesus, Jesus�Ȥ���̾�ΰ��������Ū�ʹ֡�ˤĤ��Ƥ��äǤ��뤳�Ȥ������⤿�餹�Ǥ�������
���Υѥ�����ϸź������ο��ä˸�����ֲ��������ķ��פȤ���ɽ������Ƥ�����Ρ��ޤ��Х������ɡ�����������ɽ������Ƥ�����Τ��ܼ�Ū��Ʊ���Ǥ��롣�������ο���Ū�ķ��ˤĤ��Ƥ�����Ȥϡ��ֲ��λ����פȤ������郎������켫�ȡ�����֤��αƶ����Ȥ�뤳�Ȥ��Ǥ��ʤ�����ε��ϡפ�ؤ��ΤȤ��Ƶ����뤳�Ȥ��Ȥ���ʸ̮�Ǽ´����뤳�Ȥ��Ǥ��뤫�ɤ��������ʤ�����֤���켫�Ȥ�����פȤ�������Ǥ��뤫�ɤ����˳ݤ��äƤ���ΤǤ��롣
13:29:00 -
entee -
TrackBacks
2006-02-01
���ܤθ��ʸ��λ��֡ˤˤĤ���

 ��
��
������̾�Ρָ��λ��֡פϡ���������Τ�ɽ�����⤷��ʤ����ʤ��ʤ餳��ɽ���ˤϤ�������������ˤϤ��ä��ҤȤĤμ���θ�����¸�ߤ���������ͣ��θ��˻��Ĥ����֤�����פȤ��ɤ����̾������Ǥ��롣�������������Ǥ��褦�Ȥ��Ƥ���Τϡ��ष�������ۤʤ룳�ĤΡָ��סʤ�������̩��Ϣ�Ȥ���äƤ�����ˤˤĤ��Ƥιͻ��Ǥ��롣�����Ƥ��Ρ�Ϣ�ȡפ����뤳�Ȥˤ�äƽ��Ƥ������Ʊ��פ������뤳�Ȥ���ǽ�ʤΤ��Ȥ������ͤǤ��롣�������Ƥ�դߤ�С��ȤƤ⣱��Ǹ�꤭������ƤǤϤʤ�������Ԥ���ơ��ޤο�Ľ�⤢�ꡢ���������˥���������뤳�Ȥ�������ʤ��Τȡ������ˤĤ��Ƥϥ��ꥢ���Ǥˤ�ä����Ū�ʸ��椬����Τȡ�������Ū��������פ����ͥ�����ˤ����Ƥ⤹�Ǥ�ɬ�פʿ��Ǥ��̤��Ƥ������ٴѤ��褿�Τǡ������Ȥ���ĺ�����Ȥˤ��ơ������ǤϽ��פʡָ��פˤĤ��Ƥ�����ζ�ͭ�������ܻؤ����Ȥˤ��롣
�ޤ����ꥢ���Ǥθ��դ�Ҳ𤹤뤳�Ȥ��ܹƤ���Ū�Ǥ�ʤ��Τǡ���䤿����줿�Τ���������˴�Ϣ������ۤɤ���������ʤ�ʸ���������äƤ���ͤ⤤�ʤ��ΤǤ�Ϥ���������Τ����롣
��ά�˸��Ϥ���¸���ͼ����Τ��餷�ơ�ŷ����¤Ū�פǤ��롣�����и�����ޤǤϲ�ʪ��ּºߡפ����ʤ����ʤ���Ρ���˸���褦�ˡ����Ρ������ɤ�ޥ˶��̤ˤ�ä���˾���줿�������Ǥ�ã��������ͣ���ƻ�ϡ�������˻��𤷤�����γ�Ҥ���Ф����ǽ�Ū�ˤϤ����Ķ��Ū��̵����Ū�ֹ�ߡפ˺Ƶۼ������Ȥ���Ĺ��ʣ���ʲ����Ǥ��ä����ˤ�����ȯ���θ�������¤�Ϥϱ��Ҥ��μ��ͤˤȤäƤΤ����Τ��ȤǤ��롣��ά��
�ߥ���������ꥢ���ǡإ�����ƥ����ࡦ��ѡ�ʸ��ή�ԡ���ϻ�ϡ���������͡פ��p. 173�����������Ӿ���������̤��ҡ�
���ιͻ��˲��ͤ�����Ȥ���줬�ͤ���Τϡ��ۤʤä���ΤǤ���Ϥ���ʣ���θ�Ū��¸��ʪ��¸�Ԥ��������˶��̤���¸�ߤ�������������ʤ�Ʊ��̾���ǸƤФ�Ƥ�������ˡ����λ��ݤ��Τ�Τ�ʸ���̤��Ʊ����ΤǤ���פȹͤ�������Ƥ����̤����ꤽ���ʤ��ȡ������Ƥ��κ���ˤ�äƤ���줬�������������Ƥ���ˤ�ؤ�餺����˵��դ����ˤ����ǽ�������뤳�ȡ����ʤ�������Ρָ��פΤ��꤫���ˤĤ��ƤΡ�̵���Ū�ʡ˹���Ūǧ�����̤�����¾���Ρָ��פ��ꤹ�٤���ΤȤ���줬�ͤ��Ƥ��ޤ������ˤʤäƤϤ��ʤ������Ȥ���������Ū�ʴ����פء��ҤȤ����դ�����ɬ�פ�ǧ��뤫��Ǥ��롣
�����ɤ���Τ��Ȥ�������Ū��ǧ���ϡ��������ԤǤʤ��Ƥ�ۤȤ�ɰ���Ū��ǰ�Ǥ���ȸ��äƤ��ɤ��������������ưǤ����ꤵ���٤���ΤǤ���Ȥ�����ʸΧ�ϸ�����ꤹ��������ɽ���ΤˤʤäƤ��롣�Ť��ǤǤϤʤ����뤯�Ȥ餵�줿������ָ�����ۤȤ�ɽ���Ū�ȸƤ�Ǥ��ɤ�����������Ū�����������¿���ϻ��äƤ��롣�������ä�����Ū�ˤ����Ρ���������פϡ�����ޤ����ι���Ū¦�̤ˤĤ��ƤΤߡָ������ơפ����Ǥ��ä��������ơ��Τ��˸���̵���˹��ꤵ���٤���Τȹͤ���������ϡ�¿���ν����Ȥ����Ȥˤ�äơֵ����ʤ���ͭ����Ƥ������˸����롣���������ܼ��Τ����Ĥ��θ��ڤ��Ǥ������Ʊ�ͤθ����ݻ��Ǥ��뤫�ɤ����Ϥ�������ο��ټ���Ǥ��ꡢ�ޤ���̿¸�ߤ��Τ�Τ��Ф������ټ���Ǥ��롣���Ȥ����ºߤ�¿�����Τ��٤ƤΥ����ڥ��Ȥ����ʤ���С����ο������ã���뤳�Ȥ���������������ǧ���פ���ã���뤳�Ȥ����ʤ��ΤǤ��롣
���Ȥ�����Τ�����Ū��̵�뤹�뤳�ȤΤǤ��ʤ������ΤҤȤĤϡ����Ρ�ǽư��: activity��ˤ��롣�����ưǤ������Ȥϡ��ư��: passivity��Ǥ��롣�㤨�и��������ȰǤ��������ɤҤȤĤdz֤Ƥ��Ƥ�������ꤷ�ơ������ɤ˷꤬�����줿�Ȥ���ȡ����ϰǤ����˸����äƼͤ�����ΤǤ��ꡢ�Ǥ�����������ή�����뤳�ȤϤǤ��ʤ����Ĥޤꡢ�ǤϤĤͤ˸��αƶ����˻�����褦�Ȥ��Ƥ���ΤǤ��ꡢ�������Τ�Ʊ�������Τ�Τ������������ۤ��褦�Ȥ��뷹�������롣¿���ο͡�����������ι������Ȥ�ʢ�ˡ����������Ȥ�����ΤϾ��̤ˤ�äƤϤ�����˽��Ū�ǡ�ȴ������������Ū�ǡ�̵����Ǥ������롣���θ���������̵�뤹��ˤϤ��ޤ�˽��פʤ�ΤǤ��롣
�������äơ������Ǥϸ������ꤵ��٤���Ρ����ˤǤ���Ǥ����ꤵ��٤���Ρʰ��ˤǤ���Ȥ��������ͤˤȤäƤ����ˤ�ʬ����䤹��ñ��ʡ���������פ��ö���������ˤ�����ǡ��ֻ��֡פΤ��줾�줬���äƤ������������Ƹ�Ƥ���٤��ʤΤǤ��롣
����줬���̤��ʤ���Фʤ�ʤ����Ρֻ��֡פȤϰʲ��Σ��ĤǤ��롣���ˡ�ʸ���פ��̣���֤ҤȤ���������餷�䤹���Ȥ����ˤ���פȸ���쿮�����Ƥ�������ι٤Ȥ��ƤΡָ��ס��Ͼ�Ū������Ū����¯Ū������Ū�ʸ��ˡ�����������ˤϿ��Ȥ�ǡ��*�Ȥ⥭�ꥹ�ȤȤ�ƤФ졢�ޤ�ŷ��Ū������Ū������Ū����̿���ͥ륮���Ȥ��Ƥ������ָ��סʿ����ˤ��Ƽ�¸Ū���ʱ�Ū�ʸ��ˤǤ��롣�������軰�ˡ�ŷ����Ͼ�Ȥ��ӤĤ��뤿��˸��������˽и�����������Ū��Ķ��Ū�ʡָ��סָ����ס������Σ��ĤǤ��롣�軰�θ��ϡ���ŷ��ΰտޡפȡ��Ͼ�ν�������Ͼ�Ū�ʴ�˾�ˡפȤ���פ����뤿��ˡ֤������ʤξ���ˤ����פ������������ʤ�̸��פȸ��������Ƥ�褤��
* ������ǡ��ʤ��ߤ��ˤ�餤��amitaabha�ˤϡ�������ʩ�������ˤʤɤȤ⤤�������ʩ����ǡ��ΤҤȤꡣ�֥��ߥ����楹(amitaayus)�����ߥ�����(amitaabha)�פ������ơ�̵�̼�ʩ��̵�̸�ʩ�ȸƤФ졢̵���θ����ޤͤ��Ȥ餹����ʩ�Ȥ���롣(by Wikipedia)
�����Ƥ���줬����ˤ���Τϡ�����黰��θ�����������ҤȤĤΤ�ΤȤ��ơʴ����Ƹ����С����ʤ��ΤǤ���פȤ��ơˡ�̵���Ū��̵ȿ��Ū��Ʊ��뤷�Ƥ��䤷�ʤ������Ȥ������ȤʤΤǤ��롣����餬��ߤ�̵�ط��Ǥ���Ȥ����ΤǤϤʤ�����Ʊ��Τ�Ρפȴ�ñ�˼�������Ƥ��ޤä��ɤ��Τ����Ȥ����������������ΤǤ��롣
���θ������ʤ���Ͼ�Ū�����Ū�ʸ������¤ϡ������ȡʥ��ꥹ�ȶ���ʩ������鷺�ˤˤ���۶���ư�������Τؤξ�ư�ʹ��ˤȥ��åȤˤʤäƤ���ʾ塢�������ˤ����ƤϳΤ��ˡֽ����פ�̵�ط��ǤϤ������ʤ��ΤǤ��뤬������ϿͰ٤ˤ���ΤǤ��롣�����Ǥϡֽ����פ�����Ū�˰���������Ȥ�ݽѲȤˤ�äơֵ��ҡפ���Ƥ����֤������ʤ�̸��פ��ص�Ū�ˡֽ���Ū�ʸ��פȸƤ�Ǥ���ΤǤ��뤫�顢��Ϥ���������θ��ϡʰ�ö�ϡ˶��̤���ʤ���Фʤ�ʤ��ΤǤ��롣����������θ����θ��ˤ�äƴ������褦�ȡ����ʤ�ºߤؤ����פ�פ����Ȥ���ʹ֤ξ�ư�䡢���Ū�˹Ԥ��Ƥ������Ԥ�ºݤ��θ��ˤĤ��Ƥε��ҡ�ɽ���ˤ�¿���ο����ʿ���Ȥ����������褿���ȡ��������ɿ�Ԥˤ����θ������θ����ɵ���Ρ��Ͼ�Ū�ʸ��פ���ˤȤ����ζ���Ū�ʰ��פ����̤����뤳�ȤϤҤȤĤ��õ�����ǤϤ�������
�褯������Ͼ�Ū�ʸ��˴ؤ��Ƥϡ����줬ʸ���Ρ����פ���������ʬ�����ءʳ��աˤ��̣����Ѹ�Ρ�enlightenment�ɤ���Ρ�light�פ���������ʬ������ʲ�Ǥ���褦�ˡ��͡���Ǥ��դ��������֤�������뤯�Ȥ餵�줿���֡פ��ʤ���֤�Τθ�������֡פؤȤ��������꤫��Ƴ���Ȥ�����ʸ����⤿�餹¦�פ���½�ʻפ����ߤ����äƤ�������Ω�äƤ����Τ����������ʳ�Ū�ͤ�ʳص��Ѥ���ʪ��Ū�ˤ�֤�����뤤������פ�¤��Ф����Ͼ��ʸ���̤�Ȥ餷�Ф��Ƥ���Ȥ������¤Ȥ��ι���Ū�ʻ�ˡ�����衼���åѤ���⤿�餵�줿���¤϶�̣�������ϵ��ʸ�������줿�ΰ�ϡ��º����ꤽ��ʳ��ν��ϰ�������뤯�Ȥ餷�Ф���Ƥ��롣�������֤ιҶ��̿��ʿ��ǣ��ˤˤ�äƤ��ֳ��������ˤ���Ͼ��Ǯ������������餫�Ǥ��롣ʸ���Ͽ���ο����ܤ�Ϳ������Ʊ���ˡ�ʪ��Ū�ʸ����⤿�餷�Ƥ������Ǥ��롣
�����ơ������Ȥ����Ȥ����ä��ɵᤷ���ޤ����Ҥ����褿�ֿ�������ʤ���ס�����θ��ˤؤο��Ĥϡ��Ͼ�Ū�ǿͰ٤�ͳ�褷�ʤ�������θ��Ȥ��������ʤ���㤹��ʪ��Ū�ʸ����軰�θ��ˤ������ؤȡ������¿�����ߤ�Ω�ƻɷ㤷���褿�ΤǤ��ꡢ�ޤ����ε��Ū�ʷ�̤Ȥ��Ƥ�Ķ��Ū��������Ū�ʡ���䤵�����γ�Ҥ���Сפˤ�äƺǽ�Ū�˳��������������Ƥ��κǽ�Ū�ǺǤ���ʸ�����¤�ϡ��ʹ֤ε��ͤ���̤��뤳�Ȥʤ���̵���̤ˡ�ʿ���ˡ��ָ��θ��˻����פ��Ȥ�ۤ��������ǽ�Ȥ�����
���ꥢ���Ǥθ����Ȥ����Ρָ���ʬΥ�פ�¿��Ū���ͤϡ��ޤ��ˤ��λ��¤��ٳ��뤷�Ƥϰ�̣��ʤ��ʤ����⤦���ٸ�����
�����ϸ��ͤε߽����ǥ�˷������줿������εߺ�ʪ�����Ƽ��夲��Ĥ��Ϥʤ�����������Ū��ǽ�����������ʹ֤ε�����ᤰ�뤳�ο��ä�����Ū����Ǥ��ä����Ȥϸ����ޤǤ�ʤ����ºݡ������ä˽л��ϰ��Ǥ��롣�ʤ��ʤ顢�����ϸ��δƶؾ��֤��¹�����Τ���ˤޤDZ�Ĺ���뤫��Ǥ��롣�ޥ˶��̤ˤȤäơ������ʤ����Ȥ����Ǥξ��������ʤ��ʪ���������ʸ��ˤ�ʬΥ�����ߺѤ�ʪ������θ��η���ŪʬΥ���б������Ĥޤ�Ȥ����������ν�����б����Ƥ����ΤǤ��롣
���С���ϻ�ϡ���������͡פ��p. 176-177
�����ǽ�Ƥ���ָ�����פȤ�����Τ����ְۤʤ뻰�Ĥθ��פ�ᤰ���ΤǤ��뤳�Ȥϡ����ˤ����ˤȤäƤ����餫�ʤΤǤ��롣�������Ͼ������줿���θ��ˤ�ä�ŷ�������θ��˶�Ť������������θ��ε��Ū�ºߤǤ����軰�θ��γ����ϡ�����������������θ���������Ϣ���᤹�Ȥ������ȤʤΤǤ��ä����Ϥ�������������ʤ顢����줬�ָ��פ���̤��ʤ���Фʤ�ʤ���ͳ���ޤ��ˤ����ˤ���ΤǤ��롣
���Ρ��������ޥ˶��⡢�����ϰ���Ū���ϡ����륳�������뤤�Ϥ��λ�Ƴ�ԤǤ���¤ʪ��ʥǥߥ������ˤˤ�ä���¤���줿�ȹͤ���������Ʊ�����륳������˿ʹ֤���¤�����ΤǤ��뤬�������ŷ�����������Ū�������פǤ�����ʥץͥ��ޡˤ�ƶؤ��������¾�ʤ�ʤ��ä�����ά�˵ߺѤȤ��ܼ�Ū�ˤ��ο�Ūŷ��Ū�ʡ���ʤ�ʹ֡פ�ߤ��Ф����ȤǤ��ꡢ������ޤ�ζ��Ρָ��פι��Ϣ���᤹���Ȥ��̣���Ƥ��롣
���С���ϻ�ϡ���������͡פ��p. 179-180
���ǣ������θ���
�Ʒ��ε�����DMSP���������Ƥ���������ϵ�פμ̿���ʸ����ʬ�ۿޤ����Τޤºݤ���֤θ���ɽ����Ƥ��롣
������
���ǣ�������θ���
���Ÿ�̾ĥ�ԡ����ӻ�����¤������ǡ��Ω���ַ�Ĺ����ǯ��1609��Ȭ����ߺ�ν��͵�̣��Ƿ��
������
���ǣ����軰�θ���
ICBM����������Ǥ��夲�¸���������θ��פ������¸���������θ���ʸ���ˡפε��Ū���ʡ���帢��ħʪ��
���͡���ǽ���Ƥ��ʤ���Φ����ƻ�ơ�ICBM�ˤ����䤹�륪����������ȡ�¿ʬ���̡�
13:27:00 -
entee -
TrackBacks
2006-01-19
�ݽѤ˴ؤ��륳���åɤλ���Ū�Ǿ�
Joseph Conrad (1857-1924)
�ǽ���ǤäƤ�������ϥ��祼�ա������åɤΰ��ɼԤǤϤʤ����������äơ��������ˤĤ��Ƥξܤ����μ����դ����ƤΥ��ǤϤʤ����ष���������夭������ɤ�Ǥߤ褦�Ȼפ碌��ü��ΤҤȤĤǤ��롣����ϡ���ζˤ�ƽ��פȻפ������Ū�ǾϤĤθ��Ф����Τǡ��������Ф��뼫ʬ�δ����ȤȤ����˺Ͽ�Ȥ��ƻĤ��Ƥ�����
��Heart of Darkness�ɡʡذǤα��٤Ȥ������������롣�Dz���Ϲ����ۼ�Ͽ�٤θ��ƤȤʤä����Ծ���ˤ�����祼�ա������åɤϤ��Τ褦�ʤ��Ȥ�Ƥ��롣�����ȿ�Ǥ��Ƥ������뤤�ϱѸ줬����Ǥʤ��ͤˤ��꤬���ʤ��ȤȤ��Ƥ�����䳢�¤�ɽ�������̤����ɤ��ĺ����ФȻפ���
All creative art is magic, is evocation of the unseen in forms persuasive, enlightening, familiar and surprising, for the edification of mankind, pinned down by the conditions of its existence to the earnest consideration of the most insignificant tides of reality.
�����ˤϡַ���Ū�פȤ��������ˤⲤ����Ū��ɽ�������ָ������ΤΡ��ष�������ͼ��Ȥ�ޤ�ֿ���סʤȤ�����ꡢ�ष�������ͤ��ؤ��Ƥ���ˤȤ���������ʤ�¸�ߤ����뤿���ɬ�פʲ����Ǥ��ꡢ�������ˡ�ʤΤ��Ȥ�����ĥ�Ǥ��롣����������͡ˤ���ͳ�äơ�«�����줿�����Ǥ�����Τ뤳�Ȥ�Ǥ��ʤ��Ȥ������¤ˤĤ��ƤηŴ㤬���롣�����Ƥ���ϤȤ�櫓����Ūʸ���αƶ��Ǥ˿�����äƤ����������Τ˴ؤ�������Ȥ����ɤ�롣
�ݡ����ɽпȤΥ����åɤ��Ѹ��ʸ�Ϥ�Ϥ�Τϱѹ����˾��Ϥ�ư���Ȥ������顢�����餯17�Фˤʤäưʹߤ��ä�����������äȼ㤤�����DZѸ�θ���ϳ��Ϥ��Ƥ�����ǽ����������������åɤˤȤäƱѸ줬����Ǥʤ����Ȥ��Ѥ��Ϥʤ�����ϱѸ�����ɼԤ���ΡֱѸ�פ��̤���̥λ��������������ã���ʤȤ��ƤΡֱѸ�פϥ����åɼ��ȤˤȤäƤ������軰�����Ǥ��ä�����ϡʤ���칥�ߤθ�������Сˡ��첤�пȼԡפʤΤǤ��ꡢ�褷��������ʤ�ä����ΤˤϱѸ�������ɽ����ȯ���ԡ�ʪ�ˤǤϤʤ��ä��������Ʋ����ͤ����Τ����Τ���𤹤�Ȥ��ξ���⤽��礿��ơ��ޤȤ��Ƥ���ʤ餷���ˡ�
�첤�пȼԤ����������衼���åѡˤ˽в����Τ��ҤȤĤ�ʸ��Ū��Ǥ��롣����ϰ����ˤ���夲�����硼���ա����������Ѷ�Ū�˼��夲���ơ��ޤǤ��롣�����ȤϱѸ��ȤǤϤʤ��ä�������Ρ�������ؤΤޤʤ����ϡ��ˤ�ƶɳ��Ԥ���Τ�Τ˶ᤫ�ä��������������٤��餯�����ΡפǤ���Ȥ�������Ū�������ǽ�ʤ顢��������������첤�ϡ��ޤ�Ω�ɤˡ����Ρפΰ����Τ褦�ʾ��Ǥ��ä��ΤǤ��������������Ƥ��ʤ��Ȥ�����̣�ǡˡ�*
�ä���줿�������åɤ�����ϼºݤ˱��Ǥ���������Ū�ʤ�Τȡֽвפ��Ȥ��Ǥ��ʤ��ä��ۤȤ�ɤ������ͤˤȤäơְۼ��ʤ�ΤȤνв������뿴�פ֤�Ф��ˤ�ƽ��פʰ�̣����ä���ΤǤ��ä��������������ˤȤäƽ��פ��Ŀ����ʤ�װԤι����Ȥʤä��Ϥ��Ǥ��롣
���ߤǤϤۤȤ�ɡֱ���ʸ�ءפΤҤȤĤ�ʬ�व��Ƥ��Ƥ⤪�������ʤ������åɤαѸ�ξ���ϡ����ƿͤ����뤿��Ρ��Ѹ�ǽ줿���������ͤˤ��ʸ�ء����ʤ���Ѹ���ͤˤȤäƤΡֳ���ʸ�ءפ��ä��ΤǤ��롣
���˾夲�����ˤ�Ѹ��ʪ�Ǥ���ʤ��顢���ꤷ�Ƥ����ɼԤϳ���ͤȤ��Ƥα��ƿͤǤ��ä��ΤǤϤʤ����Ȼפ碌��ҤȤĤǤ��롣
... Art itself may be defined as a single minded attempt to render the highest kind of justice to the visible universe, by bringing to light the truth, manifold and one, underlying its every aspect. (from Preface "Children of the Sea")
�Ĥޤ긽�¤Ȥϰۤʤä������Ǽºߤ��뿿�¤���ָ��������Τ������ݽѤ���Ū�Ǥ��ꡢ����������Τ��ǽ�ˤ��褦�Ȥ����ޤä����Ҥ��भ�����Ϥ��������ݽѹ٤ȸƤФ������������Τ��ȥ����åɤϸ��äƤ���Τ���
����줬�����ΤäƤ���褦�ˡ������������ݽѤ�����Ǥ������ǤϤʤ������������¤���ָ������뤳�Ȥ��ݽѤǤ���Ȥ����ݽѤ�����ν�����ʬ�˴ؤ��Ƥϡ������륤���Υ������䥷��ܥ�������ɾ������Ω����ˤ����ˤȤäƤ����ˤ�ƿ���������Ф�����ʬ�Ǥ��롣
�ݽѤϡ��ܤ˸�������̤���¸�����Ƥ��ʤ����餫�����������������ʥ��ǥ��ˤ��γв����뤿��Ρ��ʤ����: a single minded attempt�פǤ���Ȥ���ɽ���ϡ��Ȥ�櫓��ưŪ�Ǥ⤢�롣���Τ褦�˷ݽѤο�����Ū���ΤäƤ����ʪ�ˤ���Ϻ�٤ˤϡ�ɽ���Ȥ�����Τ��̤��ư������Ŀ�Ū�տޤ�¸������褦�Ȥ����褦�����ʼ���ϲ�ߤ��ʤ���
�����ͤ��Ƥߤ�С����⤽�⤳��������ħʪ��¸�ߤȤ����Τϡ���������ɽ����ˡ��ʸˡ�Ȥ⤤���٤���Τ����Ū�������Ф����Ԥˤ�äƤΤ�����Ƥ����ΤǤϤʤ��ơ��ˤ�ƹ�������οʹ֡ʻҶ������Ⱦ㳲�ԡ������ƥ��ޥ��奢��������Ȥޤǡˤ�ɽ���ؤλ��á���������Ū�Ф��ʤ��Ϻ��ư�ˤ�äƼ¸������졢�ޤ���˲�������褿��Τ������̤�Ť餵�ʤ����Ѥ�ɽ��ʪ���ʤ��뤤���������ѤȤϸƤ٤ʤ���ǰ��ޤߤʤ��������Ѥ�ɽ��ʪ�Ȥ��ơ�ǧ������Ĥġ˸Ť�����������졢�����μ��ܤˤ���ΤǤ��롣
������Ū��������פΥ������Ÿ�������褿�֦��ķ��פ˴ؤ�������ᡢ�����Ƥ��θ������ι�¤�β����Ȥ����Τϡ����줬�����ʿ͡��ˤȤäƤϤ�Ϥ�ֲ��פǤ����ʤ����ޤä����ɤ뤮�ʤ��ֵ�§�פȤ�ɾ�������٤���ΤǤ��롣�츫̵�ط��˻פ�����֤���֤�֤Ƥ�¸�ߤ��뤢�����ħɽ������Ʊ��������μºߤ������뤿��ˤ��η�����������¸�����褿��Τ����Ȥ����Τ���������̤��Ƥμ�ĥ���ä���
�����ɽ��ʪ�ι�¤����§��ʸˡ�ˤȤ��ƴ����Ǥ��ʤ��Τϡ��������Ū���İ����뤿���ʬ��Ķ��Ū�ʡ֤������١פ��μ��ȡ�����¤δ��ۤ��ʤ��ä������ʤΤǤ��롣�����ơ��ޤä����ԲIJ�ʤ��Ȥϡ������������ȤˤĤ��ƽ���Ū�˹ͻ�������ʤ��ä��͡��ˤ�äƤ⡢�����ķ�Ū�����αƳ��Τ褦�ʥץ��ե�����ʲ���˥���������ۤȤ�ɶ�����ǰŪ�ʤޤǤ�ȿ��Ū�˶�ͭ����Ƥ���Ȥ������¤ʤΤǤ��롣
�ɤΤ褦�ˤ��Ƥ����������Ȥ���ǽ���ä��Τ��Ȥ�����ã�θ�������ͳ�ˤˤĤ��ƤǤϤʤ�������Υ��ݥå��˸����ä��ʤ�����ब��α��褦�Τʤ����Ρ��ħŪɽ�����Ĭή�μºߤ�Ķ���Ū��ȿ���פ�̵�ռ��Υ�٥�Ǥϼ��äƤ���Ȥ������ȤˤĤ��ơ��������Ƥ��뤤��ΤǤϤʤ����Ȼפ��롣�����ơ������åɤθ��ڤ����̣�Τ�Τ����ݽѤο�����Ū�Ǥ���ȸ����ʤ�ʤ����Ƶ����ʤ������ʤΤ����ˡ��ޤ��ˤ���������ħŪɽ���������ݽѤ�̾���ͤ����Τ��Ȥ������Ȥ��༫�Ȥ��ΤäƤ����Ȥ������ȤʤΤ���
*�ֲ����פϥ���뻳̮�����Τ�����Ǥ����Ū�ʰ�̣�ǤΡ֥衼���å����Ρפ������פϡ����衼���åѡפ�ؤ��������Ρפ������Ȥ��������Τʤ餶���Τ����Ρס��Ȥ�櫓���ʸ������͵サ�ϰ�ʤ������ڤ�ؤ��Τ��⤷��ʤ����������Ǥ��ƹ������ΡפǤ��롣���ʤ��Ȥ������ʸ�����פǤ��롣�����������ΡפȤ������դ�����ϡ����ˤ�äơ����������衼���åѡפȤ�����̣�Ǥ�̵��Ƚ�˻Ȥ����褿��ǽ�������롣�ޤ��դˡ������פ�ñ�ˡ����ΡפȤ��������Ȥ�����̣�礤�ǻȤ����褿��ǽ���⤢�롣���������ǤϤ������٤����٤������ǽ���Ѹ�Ǥ���������פϻ��ѤǤ����ΤȤ��ƹͤ��������ΡפΤ褦��¿��Ū�˲��Ǥ��Ƥ��ޤ��褦���Ѹ��Ǥ�������Ӥ������̤ʰտޤ��ʤ��¤�Ȥ�ʤ����Ȥ���������
�ǽ���ǤäƤ�������ϥ��祼�ա������åɤΰ��ɼԤǤϤʤ����������äơ��������ˤĤ��Ƥξܤ����μ����դ����ƤΥ��ǤϤʤ����ष���������夭������ɤ�Ǥߤ褦�Ȼפ碌��ü��ΤҤȤĤǤ��롣����ϡ���ζˤ�ƽ��פȻפ������Ū�ǾϤĤθ��Ф����Τǡ��������Ф��뼫ʬ�δ����ȤȤ����˺Ͽ�Ȥ��ƻĤ��Ƥ�����
��Heart of Darkness�ɡʡذǤα��٤Ȥ������������롣�Dz���Ϲ����ۼ�Ͽ�٤θ��ƤȤʤä����Ծ���ˤ�����祼�ա������åɤϤ��Τ褦�ʤ��Ȥ�Ƥ��롣�����ȿ�Ǥ��Ƥ������뤤�ϱѸ줬����Ǥʤ��ͤˤ��꤬���ʤ��ȤȤ��Ƥ�����䳢�¤�ɽ�������̤����ɤ��ĺ����ФȻפ���
All creative art is magic, is evocation of the unseen in forms persuasive, enlightening, familiar and surprising, for the edification of mankind, pinned down by the conditions of its existence to the earnest consideration of the most insignificant tides of reality.
���٤Ƥ��Ϻ�ݽѤ���ѤǤ��롣�����¸�ߤξ��ˤ�äƺǤ������ʤ�����������Ĭ���ˤĤ��Ƥ��������ܤ���θ�Τ���˿�ư���Ǥ��ʤ��ʤäƤ��ޤä�����ζ����Τ���Ρ�����Ū�Ǥ���Ƥ��ߤ�ä���⤿�餹�Ȥ��ä������ϤΤ�������ˤ�äơ����������Τ�����˸Ƥӵ�������ΤǤ��롣��������
�����ˤϡַ���Ū�פȤ��������ˤⲤ����Ū��ɽ�������ָ������ΤΡ��ष�������ͼ��Ȥ�ޤ�ֿ���סʤȤ�����ꡢ�ष�������ͤ��ؤ��Ƥ���ˤȤ���������ʤ�¸�ߤ����뤿���ɬ�פʲ����Ǥ��ꡢ�������ˡ�ʤΤ��Ȥ�����ĥ�Ǥ��롣����������͡ˤ���ͳ�äơ�«�����줿�����Ǥ�����Τ뤳�Ȥ�Ǥ��ʤ��Ȥ������¤ˤĤ��ƤηŴ㤬���롣�����Ƥ���ϤȤ�櫓����Ūʸ���αƶ��Ǥ˿�����äƤ����������Τ˴ؤ�������Ȥ����ɤ�롣
�ݡ����ɽпȤΥ����åɤ��Ѹ��ʸ�Ϥ�Ϥ�Τϱѹ����˾��Ϥ�ư���Ȥ������顢�����餯17�Фˤʤäưʹߤ��ä�����������äȼ㤤�����DZѸ�θ���ϳ��Ϥ��Ƥ�����ǽ����������������åɤˤȤäƱѸ줬����Ǥʤ����Ȥ��Ѥ��Ϥʤ�����ϱѸ�����ɼԤ���ΡֱѸ�פ��̤���̥λ��������������ã���ʤȤ��ƤΡֱѸ�פϥ����åɼ��ȤˤȤäƤ������軰�����Ǥ��ä�����ϡʤ���칥�ߤθ�������Сˡ��첤�пȼԡפʤΤǤ��ꡢ�褷��������ʤ�ä����ΤˤϱѸ�������ɽ����ȯ���ԡ�ʪ�ˤǤϤʤ��ä��������Ʋ����ͤ����Τ����Τ���𤹤�Ȥ��ξ���⤽��礿��ơ��ޤȤ��Ƥ���ʤ餷���ˡ�
�첤�пȼԤ����������衼���åѡˤ˽в����Τ��ҤȤĤ�ʸ��Ū��Ǥ��롣����ϰ����ˤ���夲�����硼���ա����������Ѷ�Ū�˼��夲���ơ��ޤǤ��롣�����ȤϱѸ��ȤǤϤʤ��ä�������Ρ�������ؤΤޤʤ����ϡ��ˤ�ƶɳ��Ԥ���Τ�Τ˶ᤫ�ä��������������٤��餯�����ΡפǤ���Ȥ�������Ū�������ǽ�ʤ顢��������������첤�ϡ��ޤ�Ω�ɤˡ����Ρפΰ����Τ褦�ʾ��Ǥ��ä��ΤǤ��������������Ƥ��ʤ��Ȥ�����̣�ǡˡ�*
�ä���줿�������åɤ�����ϼºݤ˱��Ǥ���������Ū�ʤ�Τȡֽвפ��Ȥ��Ǥ��ʤ��ä��ۤȤ�ɤ������ͤˤȤäơְۼ��ʤ�ΤȤνв������뿴�פ֤�Ф��ˤ�ƽ��פʰ�̣����ä���ΤǤ��ä��������������ˤȤäƽ��פ��Ŀ����ʤ�װԤι����Ȥʤä��Ϥ��Ǥ��롣
���ߤǤϤۤȤ�ɡֱ���ʸ�ءפΤҤȤĤ�ʬ�व��Ƥ��Ƥ⤪�������ʤ������åɤαѸ�ξ���ϡ����ƿͤ����뤿��Ρ��Ѹ�ǽ줿���������ͤˤ��ʸ�ء����ʤ���Ѹ���ͤˤȤäƤΡֳ���ʸ�ءפ��ä��ΤǤ��롣
���˾夲�����ˤ�Ѹ��ʪ�Ǥ���ʤ��顢���ꤷ�Ƥ����ɼԤϳ���ͤȤ��Ƥα��ƿͤǤ��ä��ΤǤϤʤ����Ȼפ碌��ҤȤĤǤ��롣
... Art itself may be defined as a single minded attempt to render the highest kind of justice to the visible universe, by bringing to light the truth, manifold and one, underlying its every aspect. (from Preface "Children of the Sea")
�ݽѤ��Τ�Τϡ������Τ���������ˤ�������ߤ��Ƥ��롢¿�ͤˤ��Ƥ���ͣ��Ρ����¤˸������ơ����Ȥ�Ƥ֤٤�������Ƚ�ǤȤ�����Τ�ͭ���ͤ��ܤ˸�������������ؤ������Ф�����Ρ��ʤ���ߤȤ�������Ǥ��뤫�⤷��ʤ�����������
�Ĥޤ긽�¤Ȥϰۤʤä������Ǽºߤ��뿿�¤���ָ��������Τ������ݽѤ���Ū�Ǥ��ꡢ����������Τ��ǽ�ˤ��褦�Ȥ����ޤä����Ҥ��भ�����Ϥ��������ݽѹ٤ȸƤФ������������Τ��ȥ����åɤϸ��äƤ���Τ���
����줬�����ΤäƤ���褦�ˡ������������ݽѤ�����Ǥ������ǤϤʤ������������¤���ָ������뤳�Ȥ��ݽѤǤ���Ȥ����ݽѤ�����ν�����ʬ�˴ؤ��Ƥϡ������륤���Υ������䥷��ܥ�������ɾ������Ω����ˤ����ˤȤäƤ����ˤ�ƿ���������Ф�����ʬ�Ǥ��롣
�ݽѤϡ��ܤ˸�������̤���¸�����Ƥ��ʤ����餫�����������������ʥ��ǥ��ˤ��γв����뤿��Ρ��ʤ����: a single minded attempt�פǤ���Ȥ���ɽ���ϡ��Ȥ�櫓��ưŪ�Ǥ⤢�롣���Τ褦�˷ݽѤο�����Ū���ΤäƤ����ʪ�ˤ���Ϻ�٤ˤϡ�ɽ���Ȥ�����Τ��̤��ư������Ŀ�Ū�տޤ�¸������褦�Ȥ����褦�����ʼ���ϲ�ߤ��ʤ���
�����ͤ��Ƥߤ�С����⤽�⤳��������ħʪ��¸�ߤȤ����Τϡ���������ɽ����ˡ��ʸˡ�Ȥ⤤���٤���Τ����Ū�������Ф����Ԥˤ�äƤΤ�����Ƥ����ΤǤϤʤ��ơ��ˤ�ƹ�������οʹ֡ʻҶ������Ⱦ㳲�ԡ������ƥ��ޥ��奢��������Ȥޤǡˤ�ɽ���ؤλ��á���������Ū�Ф��ʤ��Ϻ��ư�ˤ�äƼ¸������졢�ޤ���˲�������褿��Τ������̤�Ť餵�ʤ����Ѥ�ɽ��ʪ���ʤ��뤤���������ѤȤϸƤ٤ʤ���ǰ��ޤߤʤ��������Ѥ�ɽ��ʪ�Ȥ��ơ�ǧ������Ĥġ˸Ť�����������졢�����μ��ܤˤ���ΤǤ��롣
������Ū��������פΥ������Ÿ�������褿�֦��ķ��פ˴ؤ�������ᡢ�����Ƥ��θ������ι�¤�β����Ȥ����Τϡ����줬�����ʿ͡��ˤȤäƤϤ�Ϥ�ֲ��פǤ����ʤ����ޤä����ɤ뤮�ʤ��ֵ�§�פȤ�ɾ�������٤���ΤǤ��롣�츫̵�ط��˻פ�����֤���֤�֤Ƥ�¸�ߤ��뤢�����ħɽ������Ʊ��������μºߤ������뤿��ˤ��η�����������¸�����褿��Τ����Ȥ����Τ���������̤��Ƥμ�ĥ���ä���
�����ɽ��ʪ�ι�¤����§��ʸˡ�ˤȤ��ƴ����Ǥ��ʤ��Τϡ��������Ū���İ����뤿���ʬ��Ķ��Ū�ʡ֤������١פ��μ��ȡ�����¤δ��ۤ��ʤ��ä������ʤΤǤ��롣�����ơ��ޤä����ԲIJ�ʤ��Ȥϡ������������ȤˤĤ��ƽ���Ū�˹ͻ�������ʤ��ä��͡��ˤ�äƤ⡢�����ķ�Ū�����αƳ��Τ褦�ʥץ��ե�����ʲ���˥���������ۤȤ�ɶ�����ǰŪ�ʤޤǤ�ȿ��Ū�˶�ͭ����Ƥ���Ȥ������¤ʤΤǤ��롣
�ɤΤ褦�ˤ��Ƥ����������Ȥ���ǽ���ä��Τ��Ȥ�����ã�θ�������ͳ�ˤˤĤ��ƤǤϤʤ�������Υ��ݥå��˸����ä��ʤ�����ब��α��褦�Τʤ����Ρ��ħŪɽ�����Ĭή�μºߤ�Ķ���Ū��ȿ���פ�̵�ռ��Υ�٥�Ǥϼ��äƤ���Ȥ������ȤˤĤ��ơ��������Ƥ��뤤��ΤǤϤʤ����Ȼפ��롣�����ơ������åɤθ��ڤ����̣�Τ�Τ����ݽѤο�����Ū�Ǥ���ȸ����ʤ�ʤ����Ƶ����ʤ������ʤΤ����ˡ��ޤ��ˤ���������ħŪɽ���������ݽѤ�̾���ͤ����Τ��Ȥ������Ȥ��༫�Ȥ��ΤäƤ����Ȥ������ȤʤΤ���
*�ֲ����פϥ���뻳̮�����Τ�����Ǥ����Ū�ʰ�̣�ǤΡ֥衼���å����Ρפ������פϡ����衼���åѡפ�ؤ��������Ρפ������Ȥ��������Τʤ餶���Τ����Ρס��Ȥ�櫓���ʸ������͵サ�ϰ�ʤ������ڤ�ؤ��Τ��⤷��ʤ����������Ǥ��ƹ������ΡפǤ��롣���ʤ��Ȥ������ʸ�����פǤ��롣�����������ΡפȤ������դ�����ϡ����ˤ�äơ����������衼���åѡפȤ�����̣�Ǥ�̵��Ƚ�˻Ȥ����褿��ǽ�������롣�ޤ��դˡ������פ�ñ�ˡ����ΡפȤ��������Ȥ�����̣�礤�ǻȤ����褿��ǽ���⤢�롣���������ǤϤ������٤����٤������ǽ���Ѹ�Ǥ���������פϻ��ѤǤ����ΤȤ��ƹͤ��������ΡפΤ褦��¿��Ū�˲��Ǥ��Ƥ��ޤ��褦���Ѹ��Ǥ�������Ӥ������̤ʰտޤ��ʤ��¤�Ȥ�ʤ����Ȥ���������
07:39:00 -
entee -
TrackBacks
2006-01-01
��������������Ϥޤ뿷ǯ
���ȼ���ȷ�ӤĤ��ʤ��¤ꡢ���ܤ䵷��Ȥ�����Τ�̵�̤ʤ�ΤǤϤʤ�������ɤ��������������͡��ʤ��Ȥ��դ����ͤ�����������Ȥʤ롣�����������Ǥϡ����ܡפ�������ȷ�ӤĤ��ʤ��ǤϤ����ʤ��Τǡ��ƻ�סʹ��ºסˤ�����ε���ޤǤ���ȿ���ȼ���Ȥ����֤ۤȤ������Ū���ɿ��פˤ�ä���Ƚ����Ƥ��ޤ����Ȥ����롣�������ٻ������ʤ����ȤǤ���ˤ��Ƥ⡣
��ʬ�����������������ˤĤ��ƤϺ�ǯ����ٸ��ڤ��Ƥ���������ǯ�Σ�������ޤ��ˤ��Ρָ���������: archetypal calendar�פʤΤǤ��롣�������12��25�����������Ǥ��ä�������ʬ���äƤϤ�����
������ˤ��Ƥ⡢��������������äƤ���ȡ���1���������������ʤ���������������ä���������������ˤϡ�6���϶��ˡפ�������������13���϶������פˤʤ롣����ϱﵯ���ɤ��ΰ����ΤȤ��ä����¿��פȤϡʴ���Ū�ˤϡ˴ط����ʤ�������ϡ�����줬�����ķ�Ū�����������鲿���������ɤ�뤫���ʤΤǤ��롣
�ޤ���ä��ꤴ���ˤʤäƤ��ʤ����ϡ����٤ߤ����Ѥ���(?)�����ָ����������פ��軰����������������ɤޤ줿�����Ȥ������������Ҥ���夲������Ū�ʡ־�������ȡ��������������ΡΣ��������꤫�顢�ɤ��ĺ�������������紶�դʤΤǤ��롣
���١ָ����������פ���äƤ���Τ�10��Ǥ��롣����������������������������ǯ�κǽ�η������ˤ˽�äƤ���ΤϤ�������ä��夦���뤳�ȤǤϤʤ����������ޤ��ˡ�����: correct month�פ�̾�������������碌�Ǥ��롣
���ܤ�פ��Ф����Ƥ�������ܤ�����������ķ�Ū����פ���������Τ�����ɤˤ֤鲼���äƤ��뿷�������������ˤ�äƼ�����Ƥ���Ȧ�Ǥ��롣
���� 2006
��ʬ�����������������ˤĤ��ƤϺ�ǯ����ٸ��ڤ��Ƥ���������ǯ�Σ�������ޤ��ˤ��Ρָ���������: archetypal calendar�פʤΤǤ��롣�������12��25�����������Ǥ��ä�������ʬ���äƤϤ�����
������ˤ��Ƥ⡢��������������äƤ���ȡ���1���������������ʤ���������������ä���������������ˤϡ�6���϶��ˡפ�������������13���϶������פˤʤ롣����ϱﵯ���ɤ��ΰ����ΤȤ��ä����¿��פȤϡʴ���Ū�ˤϡ˴ط����ʤ�������ϡ�����줬�����ķ�Ū�����������鲿���������ɤ�뤫���ʤΤǤ��롣
�ޤ���ä��ꤴ���ˤʤäƤ��ʤ����ϡ����٤ߤ����Ѥ���(?)�����ָ����������פ��軰����������������ɤޤ줿�����Ȥ������������Ҥ���夲������Ū�ʡ־�������ȡ��������������ΡΣ��������꤫�顢�ɤ��ĺ�������������紶�դʤΤǤ��롣
���١ָ����������פ���äƤ���Τ�10��Ǥ��롣����������������������������ǯ�κǽ�η������ˤ˽�äƤ���ΤϤ�������ä��夦���뤳�ȤǤϤʤ����������ޤ��ˡ�����: correct month�פ�̾�������������碌�Ǥ��롣
���ܤ�פ��Ф����Ƥ�������ܤ�����������ķ�Ū����פ���������Τ�����ɤˤ֤鲼���äƤ��뿷�������������ˤ�äƼ�����Ƥ���Ȧ�Ǥ��롣
���� 2006
11:31:51 -
entee -
TrackBacks
2005-12-11
���ؤ������
���ķ��Ȥϲ����Σ���
Archetypal Omega or the Omega Archetype
���������
���ꥷ���쥢��ե��٥åȤκǽ�ʸ���Ȧ��ɤΡ�omega�פȤ���̾����ͳ�������Douglas Harper�ˤ��С��ޤ��ϡ�o-mega�פ��ʤ�����礭��O�ס���ʸ����O�פ�����Ƥ��롣�����Ƥ���ϡ֥����פȤ����ֿ��Ф��줿�첻�פ��̣�����Ĺ��O�פ���̣�����Ȥ�����
�ºݡ�����κǽ�θ��դ϶ä��β������ɤ��Ρ֥������פ���Ϥޤä����֥����פϱѸ�Ǥϡ�awe�סʰ��ݡ�����ˤ��̤�������϶�ò�β��Ǥ��롣���줬��awesome�סʰڷɡ������ʡ������餷������̵��ʡˡ���awful�סʤȤƤĤ�ʤ��������������������ޤ����ˤʤɤθ��դ����߽Ф�����
�Ȧ��ɤϤޤ��ˤ���������awe-mega����ʰڷɡ����ݤ�ɽ������Ǥ��롣�����Ƥ��Ǥ˽Ҥ٤��褦�˺ǽ�ȺǸ��ޤ��au-m-ega�פˤ��̤��롣
________________________________________________________
����ϡ��֦��ķ��פ���������������Ū�˾夲�ƹԤ��������Ƥ����ˤȤäƽ��פȸ����٤���ħŪ�����ϡ����־�ֶ�ò���٤��פۤɤ˶�����Ƥ��ꡢ�ۤȤ������Ʊ����ʪ���������ΤǤϤʤ����ȹͤ��뤳�Ȥ������Ǥ��ꡢ�ޤ������ɬ����������ȸ��虜������ʤ��ΤǤ��롣
���ΰ�Ĥκ���ϡ������ο�����ñ�ʤ�����Ū��ɬ�פ��餽�Τ褦�ʷ��֤���������ä��Ȥ����ˤϤ��ޤ�˸ߤ��˶���Ρ�ʸ̮�פˤ����ƽи������ΤǤ��ꡢ�ޤ������ʤ��ΡפȤδ�Ϣȴ���ˤϸ������ʤ��Ȥ������Ǥ��롣
�ޤ��������Ǥޤ��˸��ڤ�����ʸ̮�פȤϡ���帢ɽ��ʪ�Ȥ��ơ��о��������濴�˰��֤����ΤȤ��ơ���Ωʪ�֤ζ��֤�¸�����ΤȤ��ơ����뤤�Ϥ��Ӥ�Ω�Ļ���ξ�˽и������ΤȤ��ơ����뤤�ϸ�����ȯ�����ΤȤ��ơ��̤����ƾ徺�����ߤ����ΤȤ��ơ������Ʋ�����ֽ����פȡֻϤ�פ˴ؤ��Τ����ΤȤ��ơ������Ƥ��Υ��ݥå�������������װ�Ū¸�ߤȤ��ơ��и������ΤǤ��롣
�ʸ塢�����ǰ��Ѥ���������Ϥ��٤ơȦ��ɤη����ʤ��뤤�ϡȦ��ɤη����ؤ�������Ρˤ�������¸�ߤ��륪�֥������ȡ��⤷���Ͽʹ֤κ��Ф����ְ乽�פ����Ѥ��������褦�Ȥ���������Ǥ��롣
�� ����
 ��
�� ��
��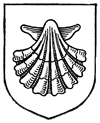
�����Ǽ��夲�볭�̡�shell, scallop, clam�ʤɤȸƤФ��ˤ�ʸ�͡��ݷ�������Ū�˥衼���åѤˤ����Ƥϡֽ���: pilgrimage�פȤδ�Ϣ�����ꡢ�Ȥ��ˡֽ���ԡפȤο����Ĥʤ��꤬���롣���ϼ�ʬ����������ԤǤ���Ȥ�����ħ(���뤷)�פȤ��Ƴ��̤�ι�Գ�����ʪ���դ����������ƽ����ƻ�Ԥ��ˤ����Ʊ�ƻ�ο��Ŀ����ٱ�Ԥϡ�����ħ�ˤ�äƽ���Ԥ�����¾�ο͡�������̤�����
��Ϥˤ����ƤϤ�����Ω���γ��̤�岼ž�ݤ��������ǿ��������줿��������¿�����ޤ�����ˡ֥��ڥ��ɤΥ������פǤ���ڤ����ͤˡ����γ��̤���ϼ��Τ���ˡ���Ƭ�����δ����夬�뱲��������Ƭ�����ˤ�ޤ����Τ����롣
�� ���̡����糭�ˤ�ŵ��Ū����� (heraldry)
���̤���ϡʻ��͡ˤȽ���Ȥδ�Ϣ
����ϥ͡������ƽ���ԤΥ���ܥ�
���䥳�֤Υ���ܥ�
�����Baptism�ˤΥ���ܥ롦��ˤ���̲ᵷ��
���ܤθλ��ˤ�����ֳ��̤Ƚ���פδ�Ϣ�����Ф����Ȥ�����롣
�����������Ǹ�����Ȥ����Ρֽ���פȤϡ�ñ�ʤ�ºߤ����ͤȴ�Ϣ�Ť���줿���Ϥؤλ��ؤΤ����ƻ�Ԥ��Ȥ������ȤФ���ǤϤʤ��������ʤ����ϡ��ϵ�ˤؤν���פǤ��ꡢ����Ϥ��ĤƤο��ब�����Τ�Ʊ��ƻ�����줬�����Ǥ���פ��Ȥ��Ф��뼫�Ф�ɽ���Ǥ��롣���줬�ֵ����ˤ�ä��������줿���ϡ������ν����ϵ�פȤ�����̩�ؤλ�������륷��ܥ�ʤΤǤ��롣
 ��
��
���������å������롧100 years of the Pecten
�� �������� thistle
�����åȥ��ɤΥʥ���ʥ롦�ե��Ǥ��������ߡ�thistle�ˤˤĤ��ƤϤ��Ǥ˼㴳���夲�Ƥ������������ŵ��Ū�ʡ֦��ķ��פ�����������Ȥ������Ѥ���Ƥ��롣¿������Ϥˤ����Ƥ⤽�β֤��ն�ޤǡ��ӡפФ����������դˤ�äơ���Ƭ�ȥե��˥���פΥХꥢ��ȤȤ��Ƥ��оο����������Ƥ���Τ��ѻ�����롣
˿�ϥ�ɥ���եȥ�����Υ������Υ����ߤ⥢������Ϥ�������Ƨ�ޤ�����Ρ�
 ��
��
Periwinkle Promises �˷Ǥ����Ƥ���ɽ��ǥ�����⡢��������⡢���Υ���ȥ륳�å����Ρ־ݷ��פ������̤�������뤳�Ȥ˷������Ƥ��롣���γ���̿���Ѥ�ȡ����Υ����ߤβ֤���ˤ���˾����ʥ����ߤ��ޤޤ�Ƥ��뤳�Ȥ�ʬ���롣�����ŵ��Ū�ʦ��ķ�Ū�ʡ�����ҹ�¤�פ��ݻ���������Ǥ���ȴѤ뤳�Ȥ��Ǥ��롣
 ����
����
��������Ϥˤ����ơ����������ߤβ֤��֥ե��˥���פǤ��롣�����Ƥ�������ˡ֦��פ�ž�ݤ��ƽ��Ϥˤ�äƹ߲����褦�Ȥ��Ƥ���ֲ������Υ���ȥ륳�å��פǤ��ꡢ�����ܡʥ����ˤ��٤���Ȥ��������Ǥ��ꡢ����С�����Ȥ����٤������֡ʤ����Фʡˡפδط��������Ƥ���ΤǤ��롣���ܤΡ֥ե��˥�������ȡ�
����Dariune��ߤ���Ϥˤ�Ѥ����ͤ˥������Τ��ֻ�帢�פ�ɽ����ħ�ȤʤäƤ��ꡢ�������Ϥ�ĺ�������פ����ΤȤ���������롣

����˼���Duncan MacFlandry�ν����ϡʺ����ˤˤ����ƤϤ��Υ����ߤβ֤������Ȥ߹�蘆�ꡢ�����餵�ޤˡֻ��̰��Ρפ�ɽ�����Ƥ��롣������Сפ���Ĵ�Ǥ��롣�ޤ���������March of the Thistle�˻�äƤϡ������ߤ�Ϣ�뤷�����ʾ岼�ˡ����ʤ��ξü�����˰����礦���ˤʤäƤ��롣����ϤۤȤ�ɻ��ڵϤ��Τ�Τȸ��äƤ⤤�����������Ϥ��濴�μ����ȸڵϤʤ�Ϥ��Τ�Ρˤ�������Τϡ������ߤβּ��ΤȤ������Ȥˤʤ롣
 ��
��
�� ��������«: a sheaf (sheaves) of wheat
���Ϥ��줿����«�ͤ���Τϡ���A sheaf of wheat���ȸƤФ����ϤΤҤȤĤΥѥ�����Ǥ��롣������ü���ݤ��ʤäƤ������������ǹʤ��Ƥ��롣����˵��������椬���������������Ƥ��뤫�˸����뤳�η��ݤϡֻ���ȸ����פ��Ϸ��ˤ����ƶᤤ��ΤǤ��뤬�����δ��ܤ�������ʲ����ʤ��������ˤ������Ƥ�������Ǥ��ꡢ�ֳ��̡פ佽����̤ΤҤȤ����ޥ����Ρָ����ޡס�moneybag, moneysack�ˤȤ�����Τ�ΤǤ��롣���͡�������̤�¾�Υ���ܥ��Ѥ뤳�ȤΤǤ��륵����
 ��
��
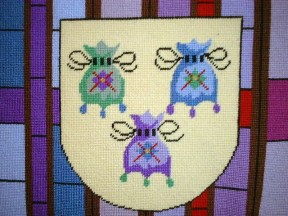
�ޥ������Ǽ��ȤȤȤ��Ƥ����Ȥ����λ����襤�����Υ�����ɾ�����Ϥ⣳�Ĥζ���Τ褦�ʸ����ޤ���Υ���ܥ�ޡ����ȤʤäƤ���ʹʤ��Ƥ���ս�Ͼ����Ǥ���ˡ�Ʊ����������̤ΤҤȤ���䥳�֤Υ���ܥ뤬���Ĥγ���(escallop)�Ǥ���褦�ˡ��츫�����Ȥ������Σ��Ĥ�;��㤤���ʤ��褦�˸����롣
���˴Ѥ�Τϡּ�������«�פ���ϤȤʤä���Ǥ��롣�ڥ�����˥����ν����Ǥ��롣�ۤȤ�ɰվ��ξܺ٤�ʬ����ʤ���硢�ۤȤ�ɡָ���פ��ͤˤ��������ʤ��������ĤΡ�«�פ�������������ळ�Ȥǻ��̰��Τ�ɽ������ȶ��ˡ����ΰտޤ�Ĵ���Ƥ��롣�ʤष�������ξܺ٤�����줿���ˤ��η��ݤ��ܼ����⤫�Ӿ夬��ΤǤ��롣���ޡ��֤����ǰϤޤ줿�Ȥ�����
 ��
�� ��
��
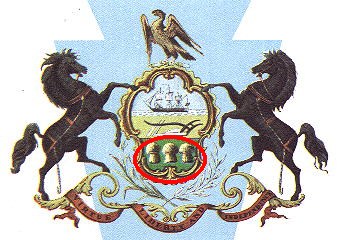 ��
��
�塧�ڥ�����˥��������
�� ��������ʥ��㥹�ߥ���ȥ���
�ֲ���פȸƤФ�������ϡ��ֲФ����̤��̤������θŤ�������������ϥ�ɥ���եȤΰ�ʬ����ɤ�Ǥ��ɤ��褦�������Ǥ��롣������Τ���������鷺�ҤȤĤΰ�̣��������Ȥ��ƻϤޤꡢ�ޤ��֤���δ֡פˤƿƤ��ޤ�Ƥ�����ΤǤ��뤬�������������ˤ⤳�Τ褦�ʡ֦��ķ��פ�վޤ����Ƥ�����Τ�¸�ߤ���ΤǤ��롣���ҤǤϤʤ���������Τˤ��η��ݤ��Ĥ�������Ƥ��������㥹�ߥ��㤬����轡פ�ɽ������뤳�ȼ��Τˤ⤵�ޤ��ޤʥȥԥå�Ω�Ƥ���ǽ�ʤΤǤ��뤬�������ˤϿ����ꤻ���������ǤϤ���Ǯ�����ǡ�Ÿ���פ�����β֤�餫��������������ͻҤβ���������ڤ����ĺ�����ȤȤ��롣

��˿�����������������ʲֲФ��ƴݤΤ褦�Ǥ⤢���

��˿������Ʋ�줿���ơפ�����Dz֤������ͻҡ��߷��ǽŤߤΤ�������������������������������ֲ֡פ�餫���롣����Ϲʤ�줿�ޤޤǡ��ޤ��ˡּ�������«�פ�Ʊ��������ݻ����롣�������Ǥʤ����Ū�ˤ��ʤ��������ΤΤ��������Ǥ��롣
�� �ǽФξ���
���Ǥ��Фξ��ȡפ�ޤ����ڤ껥��Ū������̤����ҤȤĤδ��פ�ƻ��Ǥ��ꡢ�ɥ�ޤκǽ����̤ǡֲ��פ�⤿�餹Deus ex machina�Ȥ���Ư�����Ҥ�Ķ������ǽ�������롣�����Ƥ���ϥ��ԥ�������Ǥ�ֶ�פȤδ�Ϣ�����롣����Ū�ˤ�Ƭĺ���ȴ�������������ʬ���줿�ֻ��ڵϡפ��뤤�ϡ֥ȥ饤�ǥ�ȡ��������פ�פ碌���Τǡ����ξ�Ⱦʬ���Ӥ��줿���ȡפˤʤ롣
 ��
��

���ο��Ǥˤ⤢��褦�ˡ����ξ��ȼ��Τ�������פǤ���Ȥ�������Ū�����ȿ�Ǥ����롣�����ơ��Ǥ��Фξ��ȡ��Τ��֦��ķ��פ������뤿��Ρֻ���ȸ����פ�ɽ�ݥѥ����������Ѥ��Ǥ��롣�����Ʋ������Ȥ��������ܤΥե��˥���פΡֵ�������פˤ��֤�������ΤȤ������ˤ��о줹�롣���ȤϹ⤤ŷ��ˤƤ�����Ƭ��ˡֲ����פ�ߤ������٤��ֿ��겼�������פΤǤ��롣

�� ����ξ�ħ
 ��
��
Martin Layton�Υ������ˤ�Ѥ����ͤ˹�ʪ���餯��̤��������ŷ�����鲼�ߤ���ֿ��Τη뾽�פȤʤ롣
�����ơ����θ�����η��ϥ���ꥫ�轻̱�Υ������ȸƤФ�뵷���Ѥη����ˤ�Ѥ��롣���㥳ʸ����Ω�������Casa Rinconada�Υ������ϡ����Τޤޡ֥����ۡ��롦�������פȸƤФ��ΤǤ��롣���η����������褦�Ȥ����Τ����ε������Ū�ʤΤǤ��롣
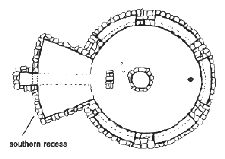
�� �������ʯ
�����Ʀ��ķ��ΤҤȤĤȤ��Ƥ���줬˺��ƤϤʤ�ʤ��Τ������������Ρ�ʯ��פȤ�ƤФ�뤳�ȤΤ������ŷ���ͤ�Ϥ�Ȥ��롢��������������ʯ�פǤ��롣
��������ߡפȤ���̾����ϸ����äƾ�������������������סʳ�ĥ�ä����ˤǤ��ꡢ���ˤ�����Τ��ֱߡפȹͤ����Ƥ��뤳�Ȥ��Ǥ��뤬����������ߡפʤΤ��ָ������ߡפʤΤ��ϵ�����;�ϤΤ���Ȥ����Ǥ��롣��������Ǥ�ʤ���������ŷ�Ϥ�ɤΤ褦�˹ͤ��뤫�Ϥ��κݡ������ε����ˤϤ��ޤ�ط����ʤ��ʤ��뤤�ϸ����äƼ����ˤ����Τ������פǤ��ꡢ���ˤ����Τ��ָ�פǤ���Ȥ����ͤ���Ǥ��ʤ��櫓�ǤϤʤ��ˡ��Τ��ˤ��줬�ɤ�������˼��������٤��Ǥ���Τ��Ȥ����Τϡ���ħ��̣��̵�뤷�Ƥ����櫓�ǤϤʤ��������ǤϿ����ꤷ�ʤ��������¡����ķ���������ʤΤ��������ʤΤ��Ȥ������Ȥϡ��������ã���褦�Ȥ����ΤˤȤäƤʤˤ������ΰ�̣�����ä�����Ǥ��롣
������������ζ������줿���Ǥ�ȡֱߡפ�����������ˤ˰��֤���Ƥ���ΤǤ��롣���������줬�ɤΤ褦�˸ƤФ�褦�ȡ����ο������̾�Ρָ�����θ����ˤۤȤ�ɿ͡���ª���Ƥ���Ȥ������Ȥ����դ�¥�����Ȥ�̵�̤ʤ��ȤǤϤ���ޤ���

����ŷ����
�������ʤˤ�����פʤΤϡ���������������ʯ�פΤ��θ���Τ褦�ʷ����ˤĤ��Ƥϡ����ΰ�̣�����������줿��������줿���Ȥ��ʤ��Ȥ������ȤǤ��롣���������֦��ķ��פȤ�����Ϣ�ο������Τ�ʸ̮��Ǥ����ѻ��������������Ƥ��Ρ�ʯ��פ������˴ޤ�Ǥ�����Ρʾ��ؤʤɡˤ�ѻ�����������Ϥ䲿�ε�����ʤ��ְ�Ĥ����Ƥʷ����ʸ����좤�����褦�ʡˡפ������뤿������ˤ��줬�絬��¤�Ĥˤ�äƷ��ߤ��줿��������̵��Ǥ��ʤ���ħŪ������Ǥ��뤳�Ȥ����餫�ˤʤ롣����ϥ����ץȤΥԥ�ߥåɤ������褦�Ȥ��Ƥ��뤳�Ȥ���������������ޤ�������Ǥ��롣�����ơ�����ϡ֦��ķ��פ������뤿��Ρ�����ε���¤��ʪ�Ǥ��ä��Ȥ������ȤǤ��롣
�� �۷�����
 ��
�� ��
��
�����ơ���Ρ֦��ķ�����ã�ΰտޤ��դ��뤫���ͤˡ�������������ʯ�Ǥ������ŷ���ͤ��顢�۾��ξ��ء��۷��ϥ˥�ˤ�ȯ������롣����ŷ���ͤȤ�������ʡȦ��ɤ���Ρ�����ҡפȤ��Ƥξ����ʡȦ��ɤ�ȯ�����줿�ΤǤ��롣�ۤη����ϡ���äƤ��꤬���ʤ�ΤǤ���ȸ������Ȥ�Ǥ��롣�������ٻ���ʤ����������ʤɤ��ʤ���м�ΩŪ��Ω�Ƥ뤳�ȤΤǤ��ʤ��ִ�����ۡפȤ�����Τϼ��Ѥ��̤Ǥϵ��䤬���롣���η����˼����̰ʳ��ΰտޤ�������Ƥ���ȸ������ȤǤ��롣
�� ���Ĥ��뷲���ʽ���ԡˤκ�릸����
����������Ѥˤ����ơ֥�å��������п��¤ο���*�פȤ��������뤬¸�ߤ��뤬�����Ρֿ�פ����Τ��֦��ķ��פ����դ������ΤǤ���Τ����餫�Ǥ��롣�����п��¤Ȥ������Ϥζˤˤ����ơ�̵���οʹ֤�����η����ȤʤäƤ��αߤ��濴�ˤ���ֿ��βȡפμ��Ϥ��ͤ˲��ʤ��鵧��櫓�Ǥ��뤬�����α��γˤˤʤ�Τ����Ρָ���פξ�Ⱦʬ�ˤ�����ߤ��濴���Ǥ��롣
* 2005ǯ���������ë���ѴۤΡص��¤ȥ⥹��Ÿ�٤Ǥ⤽�λ��㤬Ÿ������Ƥ����Τ������ε����ˤϿ�������
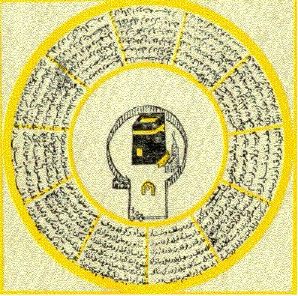
La face de Dieu
���λ����˵�����Ƥ��뤳�Ȥ��᤹��ʤ�С������п��¤Ȥ����Τ��������ʹ֤������Ȥʤäƺ��Ф��֦��ķ��פο����Ǥ���ȸ������Ȥˤʤ롣�����Ƥ��줬�ֿ��δ�פǤ���Ȥ����Τ����ޤ������Ρֿ�פμ��Ϥ��ͤ˥���ӥ���Υƥ����Ȥ��ۤ���Ƥ��뤬�����줬ŵ��Ū�ʡֱ���פ������Ƥ��롣����������Ҥ��̤��ƶ��������ֽ�뵨�������פ��Ȥ߹�碌��פ碌���ΤǤ��뤬������Ū�ʡ־�������ȡ���������������ǷǺܤ���������αߴĿ������Ϥ��������������Ȥ��Ϸ���ͭ���롣
�� �����ޡ����ȥ�å������ܻ�

�����ǤϤۤȤ�ɤɸ��ɬ�פ�ǧ��ʤ��������Ƥʦ��ķ���ħ�����Ф����ΤǤ��롣�����п��¤Ȥ�ǻ���ʶ������Ȥϡ����������ܻ�������������Ρ������ν������Ƥ��뵬�Ϥι���Ǥ���Ȥ������ȤǤ��롣
�⤦��Ĺ��㤬���Ф��줿�ΤǤ����˼�Ͽ���Ƥ�����

���ǰ����衧UNIVERSITE (Francois - Rabelais Tours)
�� ���ڥ��ɤΥ�����

���ڥ��ɤȤϡ�Ƨ�߷��ʥ���٥�ˡפΤ��ȤǤ��ꡢ������䤫�餹������衢���Ϥ����Ĥ�ΡפǤ���Ϥ����������η�����ž�ݤ���ü���������Ƥ��롣�����Ƥ���̾�λؤ�������ΤȤ�̵�ط��ˡ������dz��Ω�Ĥ褦�ʼ��ڤΤ褦�ʹ����ץ��ե������ܥ�Ȥ��Ƹ��夷����
���衢�ȥ��פΥ���ܥ�ˤĤ��Ƹ��ڤ��Ϥ��Х����ɤΣ��ĤΥ���ܥ뤬���줾����ݻ����Ƥ���ֿ����פ˿���ʤ��櫓�ˤϤ����ʤ�������������ˤĤ��ƤϤ�����ê�夲�����Ȥ���С��������ü�����äƤ��릸�ķ��Υ����ꥢ��Ȥȸ������Ȥ��Ǥ��롣�⥹���Υɡ�����β����Υ�ʡ��������ˤ���������Υɡ���ˤ�������Υ��ڥ��ɵ���Ϥޤ������ɽ����Τ�Ʊ����ΤǤ��롣����ϡ����Υ�ʡ��췿��������ä������Τߤʤ餺�����������٤��봬���夬�ä������Υѥ����餷�Ƥ⡢������Ф���ȼ��������ֱ����פ�Ϣ�ۤ��������Ƭ�����ε��漫�Τ��ޤ����ΤȴѤ뤳�Ȥ��Ǥ��롣

�����������ƤȤ���������������Υ�ʡ���Ȼ��̰��Τ�ɽ�����Ĥ�������������衧islamfact.com

���Ļ���ȬȨ���Ҥˤ⸫�������̤�����ˤʤäƤ������ơ��̳��Ҥμһ��ˤ�¿����������Τ�Ρ������Ȥ��л��ĤβФζ̤��⤫�Ӿ夬�롣����Ƭĺ���ˤϥ��ޥͥ���������������롣��������ǤΥ������⥹���Υ�ʡ���ȣ��Ĥ���������Ʊ��������������뤿��ξ�ħ�����ʤΤǤ��롣
�ϡ��Ȥ䥯��֡������ƥ������Υ����������Τ褦�ʥǥ�����ˤ���Ƥ��ʤ��Τ��Ф����֥��ڥ��ɤΥ������פ��������������㳰Ū�ʰ�����Ϳ�äƤ��롣�����ơ�����줬���Υ����ɤˤ�äƴ��������Ϣ�ۤȤϲ���������Ϥ��Υ����ɤ��֥�����פˤ����ƶˤ�ƶ������ڤ껥�פǤ���ʤ���֤������Թ���(misfortune)�Ȥ��Ϣ�Ť����Ƥ��뤳�ȤǤ��롣����ϻפ��Ф����ͤΤ��뤳�ȤǤ��롣
�Σ��ϡʺǽ���ˤ�³��
���ꥷ���쥢��ե��٥åȤκǽ�ʸ���Ȧ��ɤΡ�omega�פȤ���̾����ͳ�������Douglas Harper�ˤ��С��ޤ��ϡ�o-mega�פ��ʤ�����礭��O�ס���ʸ����O�פ�����Ƥ��롣�����Ƥ���ϡ֥����פȤ����ֿ��Ф��줿�첻�פ��̣�����Ĺ��O�פ���̣�����Ȥ�����
�ºݡ�����κǽ�θ��դ϶ä��β������ɤ��Ρ֥������פ���Ϥޤä����֥����פϱѸ�Ǥϡ�awe�סʰ��ݡ�����ˤ��̤�������϶�ò�β��Ǥ��롣���줬��awesome�סʰڷɡ������ʡ������餷������̵��ʡˡ���awful�סʤȤƤĤ�ʤ��������������������ޤ����ˤʤɤθ��դ����߽Ф�����
�Ȧ��ɤϤޤ��ˤ���������awe-mega����ʰڷɡ����ݤ�ɽ������Ǥ��롣�����Ƥ��Ǥ˽Ҥ٤��褦�˺ǽ�ȺǸ��ޤ��au-m-ega�פˤ��̤��롣
________________________________________________________
����ϡ��֦��ķ��פ���������������Ū�˾夲�ƹԤ��������Ƥ����ˤȤäƽ��פȸ����٤���ħŪ�����ϡ����־�ֶ�ò���٤��פۤɤ˶�����Ƥ��ꡢ�ۤȤ������Ʊ����ʪ���������ΤǤϤʤ����ȹͤ��뤳�Ȥ������Ǥ��ꡢ�ޤ������ɬ����������ȸ��虜������ʤ��ΤǤ��롣
���ΰ�Ĥκ���ϡ������ο�����ñ�ʤ�����Ū��ɬ�פ��餽�Τ褦�ʷ��֤���������ä��Ȥ����ˤϤ��ޤ�˸ߤ��˶���Ρ�ʸ̮�פˤ����ƽи������ΤǤ��ꡢ�ޤ������ʤ��ΡפȤδ�Ϣȴ���ˤϸ������ʤ��Ȥ������Ǥ��롣
�ޤ��������Ǥޤ��˸��ڤ�����ʸ̮�פȤϡ���帢ɽ��ʪ�Ȥ��ơ��о��������濴�˰��֤����ΤȤ��ơ���Ωʪ�֤ζ��֤�¸�����ΤȤ��ơ����뤤�Ϥ��Ӥ�Ω�Ļ���ξ�˽и������ΤȤ��ơ����뤤�ϸ�����ȯ�����ΤȤ��ơ��̤����ƾ徺�����ߤ����ΤȤ��ơ������Ʋ�����ֽ����פȡֻϤ�פ˴ؤ��Τ����ΤȤ��ơ������Ƥ��Υ��ݥå�������������װ�Ū¸�ߤȤ��ơ��и������ΤǤ��롣
�ʸ塢�����ǰ��Ѥ���������Ϥ��٤ơȦ��ɤη����ʤ��뤤�ϡȦ��ɤη����ؤ�������Ρˤ�������¸�ߤ��륪�֥������ȡ��⤷���Ͽʹ֤κ��Ф����ְ乽�פ����Ѥ��������褦�Ȥ���������Ǥ��롣
�� ����
 ��
�� ��
��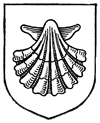
�����Ǽ��夲�볭�̡�shell, scallop, clam�ʤɤȸƤФ��ˤ�ʸ�͡��ݷ�������Ū�˥衼���åѤˤ����Ƥϡֽ���: pilgrimage�פȤδ�Ϣ�����ꡢ�Ȥ��ˡֽ���ԡפȤο����Ĥʤ��꤬���롣���ϼ�ʬ����������ԤǤ���Ȥ�����ħ(���뤷)�פȤ��Ƴ��̤�ι�Գ�����ʪ���դ����������ƽ����ƻ�Ԥ��ˤ����Ʊ�ƻ�ο��Ŀ����ٱ�Ԥϡ�����ħ�ˤ�äƽ���Ԥ�����¾�ο͡�������̤�����
��Ϥˤ����ƤϤ�����Ω���γ��̤�岼ž�ݤ��������ǿ��������줿��������¿�����ޤ�����ˡ֥��ڥ��ɤΥ������פǤ���ڤ����ͤˡ����γ��̤���ϼ��Τ���ˡ���Ƭ�����δ����夬�뱲��������Ƭ�����ˤ�ޤ����Τ����롣
�� ���̡����糭�ˤ�ŵ��Ū����� (heraldry)
���̤���ϡʻ��͡ˤȽ���Ȥδ�Ϣ
����ϥ͡������ƽ���ԤΥ���ܥ�
���䥳�֤Υ���ܥ�
�����Baptism�ˤΥ���ܥ롦��ˤ���̲ᵷ��
���ܤθλ��ˤ�����ֳ��̤Ƚ���פδ�Ϣ�����Ф����Ȥ�����롣
�����������Ǹ�����Ȥ����Ρֽ���פȤϡ�ñ�ʤ�ºߤ����ͤȴ�Ϣ�Ť���줿���Ϥؤλ��ؤΤ����ƻ�Ԥ��Ȥ������ȤФ���ǤϤʤ��������ʤ����ϡ��ϵ�ˤؤν���פǤ��ꡢ����Ϥ��ĤƤο��ब�����Τ�Ʊ��ƻ�����줬�����Ǥ���פ��Ȥ��Ф��뼫�Ф�ɽ���Ǥ��롣���줬�ֵ����ˤ�ä��������줿���ϡ������ν����ϵ�פȤ�����̩�ؤλ�������륷��ܥ�ʤΤǤ��롣
 ��
��
���������å������롧100 years of the Pecten
�� �������� thistle
�����åȥ��ɤΥʥ���ʥ롦�ե��Ǥ��������ߡ�thistle�ˤˤĤ��ƤϤ��Ǥ˼㴳���夲�Ƥ������������ŵ��Ū�ʡ֦��ķ��פ�����������Ȥ������Ѥ���Ƥ��롣¿������Ϥˤ����Ƥ⤽�β֤��ն�ޤǡ��ӡפФ����������դˤ�äơ���Ƭ�ȥե��˥���פΥХꥢ��ȤȤ��Ƥ��оο����������Ƥ���Τ��ѻ�����롣
˿�ϥ�ɥ���եȥ�����Υ������Υ����ߤ⥢������Ϥ�������Ƨ�ޤ�����Ρ�
 ��
��
Periwinkle Promises �˷Ǥ����Ƥ���ɽ��ǥ�����⡢��������⡢���Υ���ȥ륳�å����Ρ־ݷ��פ������̤�������뤳�Ȥ˷������Ƥ��롣���γ���̿���Ѥ�ȡ����Υ����ߤβ֤���ˤ���˾����ʥ����ߤ��ޤޤ�Ƥ��뤳�Ȥ�ʬ���롣�����ŵ��Ū�ʦ��ķ�Ū�ʡ�����ҹ�¤�פ��ݻ���������Ǥ���ȴѤ뤳�Ȥ��Ǥ��롣
 ����
����
��������Ϥˤ����ơ����������ߤβ֤��֥ե��˥���פǤ��롣�����Ƥ�������ˡ֦��פ�ž�ݤ��ƽ��Ϥˤ�äƹ߲����褦�Ȥ��Ƥ���ֲ������Υ���ȥ륳�å��פǤ��ꡢ�����ܡʥ����ˤ��٤���Ȥ��������Ǥ��ꡢ����С�����Ȥ����٤������֡ʤ����Фʡˡפδط��������Ƥ���ΤǤ��롣���ܤΡ֥ե��˥�������ȡ�
����Dariune��ߤ���Ϥˤ�Ѥ����ͤ˥������Τ��ֻ�帢�פ�ɽ����ħ�ȤʤäƤ��ꡢ�������Ϥ�ĺ�������פ����ΤȤ���������롣

����˼���Duncan MacFlandry�ν����ϡʺ����ˤˤ����ƤϤ��Υ����ߤβ֤������Ȥ߹�蘆�ꡢ�����餵�ޤˡֻ��̰��Ρפ�ɽ�����Ƥ��롣������Сפ���Ĵ�Ǥ��롣�ޤ���������March of the Thistle�˻�äƤϡ������ߤ�Ϣ�뤷�����ʾ岼�ˡ����ʤ��ξü�����˰����礦���ˤʤäƤ��롣����ϤۤȤ�ɻ��ڵϤ��Τ�Τȸ��äƤ⤤�����������Ϥ��濴�μ����ȸڵϤʤ�Ϥ��Τ�Ρˤ�������Τϡ������ߤβּ��ΤȤ������Ȥˤʤ롣
 ��
��
�� ��������«: a sheaf (sheaves) of wheat
���Ϥ��줿����«�ͤ���Τϡ���A sheaf of wheat���ȸƤФ����ϤΤҤȤĤΥѥ�����Ǥ��롣������ü���ݤ��ʤäƤ������������ǹʤ��Ƥ��롣����˵��������椬���������������Ƥ��뤫�˸����뤳�η��ݤϡֻ���ȸ����פ��Ϸ��ˤ����ƶᤤ��ΤǤ��뤬�����δ��ܤ�������ʲ����ʤ��������ˤ������Ƥ�������Ǥ��ꡢ�ֳ��̡פ佽����̤ΤҤȤ����ޥ����Ρָ����ޡס�moneybag, moneysack�ˤȤ�����Τ�ΤǤ��롣���͡�������̤�¾�Υ���ܥ��Ѥ뤳�ȤΤǤ��륵����
 ��
��
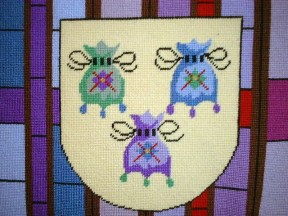
�ޥ������Ǽ��ȤȤȤ��Ƥ����Ȥ����λ����襤�����Υ�����ɾ�����Ϥ⣳�Ĥζ���Τ褦�ʸ����ޤ���Υ���ܥ�ޡ����ȤʤäƤ���ʹʤ��Ƥ���ս�Ͼ����Ǥ���ˡ�Ʊ����������̤ΤҤȤ���䥳�֤Υ���ܥ뤬���Ĥγ���(escallop)�Ǥ���褦�ˡ��츫�����Ȥ������Σ��Ĥ�;��㤤���ʤ��褦�˸����롣
���˴Ѥ�Τϡּ�������«�פ���ϤȤʤä���Ǥ��롣�ڥ�����˥����ν����Ǥ��롣�ۤȤ�ɰվ��ξܺ٤�ʬ����ʤ���硢�ۤȤ�ɡָ���פ��ͤˤ��������ʤ��������ĤΡ�«�פ�������������ळ�Ȥǻ��̰��Τ�ɽ������ȶ��ˡ����ΰտޤ�Ĵ���Ƥ��롣�ʤष�������ξܺ٤�����줿���ˤ��η��ݤ��ܼ����⤫�Ӿ夬��ΤǤ��롣���ޡ��֤����ǰϤޤ줿�Ȥ�����
 ��
�� ��
��
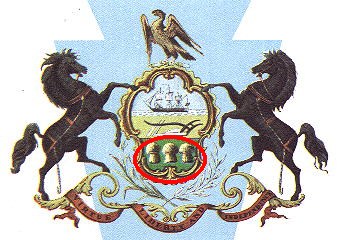 ��
��
�塧�ڥ�����˥��������
�� ��������ʥ��㥹�ߥ���ȥ���
�ֲ���פȸƤФ�������ϡ��ֲФ����̤��̤������θŤ�������������ϥ�ɥ���եȤΰ�ʬ����ɤ�Ǥ��ɤ��褦�������Ǥ��롣������Τ���������鷺�ҤȤĤΰ�̣��������Ȥ��ƻϤޤꡢ�ޤ��֤���δ֡פˤƿƤ��ޤ�Ƥ�����ΤǤ��뤬�������������ˤ⤳�Τ褦�ʡ֦��ķ��פ�վޤ����Ƥ�����Τ�¸�ߤ���ΤǤ��롣���ҤǤϤʤ���������Τˤ��η��ݤ��Ĥ�������Ƥ��������㥹�ߥ��㤬����轡פ�ɽ������뤳�ȼ��Τˤ⤵�ޤ��ޤʥȥԥå�Ω�Ƥ���ǽ�ʤΤǤ��뤬�������ˤϿ����ꤻ���������ǤϤ���Ǯ�����ǡ�Ÿ���פ�����β֤�餫��������������ͻҤβ���������ڤ����ĺ�����ȤȤ��롣

��˿�����������������ʲֲФ��ƴݤΤ褦�Ǥ⤢���

��˿������Ʋ�줿���ơפ�����Dz֤������ͻҡ��߷��ǽŤߤΤ�������������������������������ֲ֡פ�餫���롣����Ϲʤ�줿�ޤޤǡ��ޤ��ˡּ�������«�פ�Ʊ��������ݻ����롣�������Ǥʤ����Ū�ˤ��ʤ��������ΤΤ��������Ǥ��롣
�� �ǽФξ���
���Ǥ��Фξ��ȡפ�ޤ����ڤ껥��Ū������̤����ҤȤĤδ��פ�ƻ��Ǥ��ꡢ�ɥ�ޤκǽ����̤ǡֲ��פ�⤿�餹Deus ex machina�Ȥ���Ư�����Ҥ�Ķ������ǽ�������롣�����Ƥ���ϥ��ԥ�������Ǥ�ֶ�פȤδ�Ϣ�����롣����Ū�ˤ�Ƭĺ���ȴ�������������ʬ���줿�ֻ��ڵϡפ��뤤�ϡ֥ȥ饤�ǥ�ȡ��������פ�פ碌���Τǡ����ξ�Ⱦʬ���Ӥ��줿���ȡפˤʤ롣
 ��
��

���ο��Ǥˤ⤢��褦�ˡ����ξ��ȼ��Τ�������פǤ���Ȥ�������Ū�����ȿ�Ǥ����롣�����ơ��Ǥ��Фξ��ȡ��Τ��֦��ķ��פ������뤿��Ρֻ���ȸ����פ�ɽ�ݥѥ����������Ѥ��Ǥ��롣�����Ʋ������Ȥ��������ܤΥե��˥���פΡֵ�������פˤ��֤�������ΤȤ������ˤ��о줹�롣���ȤϹ⤤ŷ��ˤƤ�����Ƭ��ˡֲ����פ�ߤ������٤��ֿ��겼�������פΤǤ��롣

�� ����ξ�ħ
 ��
��
Martin Layton�Υ������ˤ�Ѥ����ͤ˹�ʪ���餯��̤��������ŷ�����鲼�ߤ���ֿ��Τη뾽�פȤʤ롣
�����ơ����θ�����η��ϥ���ꥫ�轻̱�Υ������ȸƤФ�뵷���Ѥη����ˤ�Ѥ��롣���㥳ʸ����Ω�������Casa Rinconada�Υ������ϡ����Τޤޡ֥����ۡ��롦�������פȸƤФ��ΤǤ��롣���η����������褦�Ȥ����Τ����ε������Ū�ʤΤǤ��롣
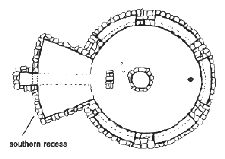
�� �������ʯ
�����Ʀ��ķ��ΤҤȤĤȤ��Ƥ���줬˺��ƤϤʤ�ʤ��Τ������������Ρ�ʯ��פȤ�ƤФ�뤳�ȤΤ������ŷ���ͤ�Ϥ�Ȥ��롢��������������ʯ�פǤ��롣
��������ߡפȤ���̾����ϸ����äƾ�������������������סʳ�ĥ�ä����ˤǤ��ꡢ���ˤ�����Τ��ֱߡפȹͤ����Ƥ��뤳�Ȥ��Ǥ��뤬����������ߡפʤΤ��ָ������ߡפʤΤ��ϵ�����;�ϤΤ���Ȥ����Ǥ��롣��������Ǥ�ʤ���������ŷ�Ϥ�ɤΤ褦�˹ͤ��뤫�Ϥ��κݡ������ε����ˤϤ��ޤ�ط����ʤ��ʤ��뤤�ϸ����äƼ����ˤ����Τ������פǤ��ꡢ���ˤ����Τ��ָ�פǤ���Ȥ����ͤ���Ǥ��ʤ��櫓�ǤϤʤ��ˡ��Τ��ˤ��줬�ɤ�������˼��������٤��Ǥ���Τ��Ȥ����Τϡ���ħ��̣��̵�뤷�Ƥ����櫓�ǤϤʤ��������ǤϿ����ꤷ�ʤ��������¡����ķ���������ʤΤ��������ʤΤ��Ȥ������Ȥϡ��������ã���褦�Ȥ����ΤˤȤäƤʤˤ������ΰ�̣�����ä�����Ǥ��롣
������������ζ������줿���Ǥ�ȡֱߡפ�����������ˤ˰��֤���Ƥ���ΤǤ��롣���������줬�ɤΤ褦�˸ƤФ�褦�ȡ����ο������̾�Ρָ�����θ����ˤۤȤ�ɿ͡���ª���Ƥ���Ȥ������Ȥ����դ�¥�����Ȥ�̵�̤ʤ��ȤǤϤ���ޤ���

����ŷ����
�������ʤˤ�����פʤΤϡ���������������ʯ�פΤ��θ���Τ褦�ʷ����ˤĤ��Ƥϡ����ΰ�̣�����������줿��������줿���Ȥ��ʤ��Ȥ������ȤǤ��롣���������֦��ķ��פȤ�����Ϣ�ο������Τ�ʸ̮��Ǥ����ѻ��������������Ƥ��Ρ�ʯ��פ������˴ޤ�Ǥ�����Ρʾ��ؤʤɡˤ�ѻ�����������Ϥ䲿�ε�����ʤ��ְ�Ĥ����Ƥʷ����ʸ����좤�����褦�ʡˡפ������뤿������ˤ��줬�絬��¤�Ĥˤ�äƷ��ߤ��줿��������̵��Ǥ��ʤ���ħŪ������Ǥ��뤳�Ȥ����餫�ˤʤ롣����ϥ����ץȤΥԥ�ߥåɤ������褦�Ȥ��Ƥ��뤳�Ȥ���������������ޤ�������Ǥ��롣�����ơ�����ϡ֦��ķ��פ������뤿��Ρ�����ε���¤��ʪ�Ǥ��ä��Ȥ������ȤǤ��롣
�� �۷�����
 ��
�� ��
��
�����ơ���Ρ֦��ķ�����ã�ΰտޤ��դ��뤫���ͤˡ�������������ʯ�Ǥ������ŷ���ͤ��顢�۾��ξ��ء��۷��ϥ˥�ˤ�ȯ������롣����ŷ���ͤȤ�������ʡȦ��ɤ���Ρ�����ҡפȤ��Ƥξ����ʡȦ��ɤ�ȯ�����줿�ΤǤ��롣�ۤη����ϡ���äƤ��꤬���ʤ�ΤǤ���ȸ������Ȥ�Ǥ��롣�������ٻ���ʤ����������ʤɤ��ʤ���м�ΩŪ��Ω�Ƥ뤳�ȤΤǤ��ʤ��ִ�����ۡפȤ�����Τϼ��Ѥ��̤Ǥϵ��䤬���롣���η����˼����̰ʳ��ΰտޤ�������Ƥ���ȸ������ȤǤ��롣
�� ���Ĥ��뷲���ʽ���ԡˤκ�릸����
����������Ѥˤ����ơ֥�å��������п��¤ο���*�פȤ��������뤬¸�ߤ��뤬�����Ρֿ�פ����Τ��֦��ķ��פ����դ������ΤǤ���Τ����餫�Ǥ��롣�����п��¤Ȥ������Ϥζˤˤ����ơ�̵���οʹ֤�����η����ȤʤäƤ��αߤ��濴�ˤ���ֿ��βȡפμ��Ϥ��ͤ˲��ʤ��鵧��櫓�Ǥ��뤬�����α��γˤˤʤ�Τ����Ρָ���פξ�Ⱦʬ�ˤ�����ߤ��濴���Ǥ��롣
* 2005ǯ���������ë���ѴۤΡص��¤ȥ⥹��Ÿ�٤Ǥ⤽�λ��㤬Ÿ������Ƥ����Τ������ε����ˤϿ�������
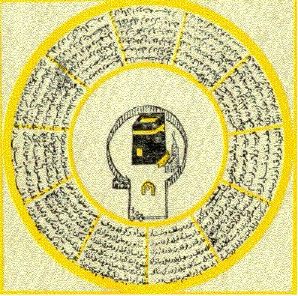
La face de Dieu
���λ����˵�����Ƥ��뤳�Ȥ��᤹��ʤ�С������п��¤Ȥ����Τ��������ʹ֤������Ȥʤäƺ��Ф��֦��ķ��פο����Ǥ���ȸ������Ȥˤʤ롣�����Ƥ��줬�ֿ��δ�פǤ���Ȥ����Τ����ޤ������Ρֿ�פμ��Ϥ��ͤ˥���ӥ���Υƥ����Ȥ��ۤ���Ƥ��뤬�����줬ŵ��Ū�ʡֱ���פ������Ƥ��롣����������Ҥ��̤��ƶ��������ֽ�뵨�������פ��Ȥ߹�碌��פ碌���ΤǤ��뤬������Ū�ʡ־�������ȡ���������������ǷǺܤ���������αߴĿ������Ϥ��������������Ȥ��Ϸ���ͭ���롣
�� �����ޡ����ȥ�å������ܻ�

�����ǤϤۤȤ�ɤɸ��ɬ�פ�ǧ��ʤ��������Ƥʦ��ķ���ħ�����Ф����ΤǤ��롣�����п��¤Ȥ�ǻ���ʶ������Ȥϡ����������ܻ�������������Ρ������ν������Ƥ��뵬�Ϥι���Ǥ���Ȥ������ȤǤ��롣
�⤦��Ĺ��㤬���Ф��줿�ΤǤ����˼�Ͽ���Ƥ�����

���ǰ����衧UNIVERSITE (Francois - Rabelais Tours)
�� ���ڥ��ɤΥ�����

���ڥ��ɤȤϡ�Ƨ�߷��ʥ���٥�ˡפΤ��ȤǤ��ꡢ������䤫�餹������衢���Ϥ����Ĥ�ΡפǤ���Ϥ����������η�����ž�ݤ���ü���������Ƥ��롣�����Ƥ���̾�λؤ�������ΤȤ�̵�ط��ˡ������dz��Ω�Ĥ褦�ʼ��ڤΤ褦�ʹ����ץ��ե������ܥ�Ȥ��Ƹ��夷����
���衢�ȥ��פΥ���ܥ�ˤĤ��Ƹ��ڤ��Ϥ��Х����ɤΣ��ĤΥ���ܥ뤬���줾����ݻ����Ƥ���ֿ����פ˿���ʤ��櫓�ˤϤ����ʤ�������������ˤĤ��ƤϤ�����ê�夲�����Ȥ���С��������ü�����äƤ��릸�ķ��Υ����ꥢ��Ȥȸ������Ȥ��Ǥ��롣�⥹���Υɡ�����β����Υ�ʡ��������ˤ���������Υɡ���ˤ�������Υ��ڥ��ɵ���Ϥޤ������ɽ����Τ�Ʊ����ΤǤ��롣����ϡ����Υ�ʡ��췿��������ä������Τߤʤ餺�����������٤��봬���夬�ä������Υѥ����餷�Ƥ⡢������Ф���ȼ��������ֱ����פ�Ϣ�ۤ��������Ƭ�����ε��漫�Τ��ޤ����ΤȴѤ뤳�Ȥ��Ǥ��롣

�����������ƤȤ���������������Υ�ʡ���Ȼ��̰��Τ�ɽ�����Ĥ�������������衧islamfact.com

���Ļ���ȬȨ���Ҥˤ⸫�������̤�����ˤʤäƤ������ơ��̳��Ҥμһ��ˤ�¿����������Τ�Ρ������Ȥ��л��ĤβФζ̤��⤫�Ӿ夬�롣����Ƭĺ���ˤϥ��ޥͥ���������������롣��������ǤΥ������⥹���Υ�ʡ���ȣ��Ĥ���������Ʊ��������������뤿��ξ�ħ�����ʤΤǤ��롣
�ϡ��Ȥ䥯��֡������ƥ������Υ����������Τ褦�ʥǥ�����ˤ���Ƥ��ʤ��Τ��Ф����֥��ڥ��ɤΥ������פ��������������㳰Ū�ʰ�����Ϳ�äƤ��롣�����ơ�����줬���Υ����ɤˤ�äƴ��������Ϣ�ۤȤϲ���������Ϥ��Υ����ɤ��֥�����פˤ����ƶˤ�ƶ������ڤ껥�פǤ���ʤ���֤������Թ���(misfortune)�Ȥ��Ϣ�Ť����Ƥ��뤳�ȤǤ��롣����ϻפ��Ф����ͤΤ��뤳�ȤǤ��롣
�Σ��ϡʺǽ���ˤ�³��
04:44:00 -
entee -
TrackBacks
2005-11-29
���ؤ������
����Ū�ʡ־�������ȡ����������������
��ʪ�Ȥ��ƤΥե��˥���Ȥ��μ���
 ��
��
�� ���ϡʥ��������ˤ��оΥǥ������ͳ��
���ڵϡ��ڵϤ��濴�����ϡ�������帢��ɽ���濴���������ˤǤ���ȤȤ�ˡ���ħŪ�ʡֲ֡פλ�ɡʥ�١ˤǤ��롣����ϸڵϤǤ���С������λ����������濴���������Ȥ���ʣ����ͺ�ɡʥ����١�Ʊ�Τλ�帢�����˴�Ϣ����Ʈ��Ǥ��ꡢ���ڵϤǤ���������ʤʤ������̡ˤ����濴���������Ȥ����ܶ�ȳ�Υ�ʶ�Ť����ĤĤ�Υ����Ƥ���ˤ����֤Ȼ�뤳�Ȥ����롣
���Ǥ˴ѤƤ����褦�˻��ڵϡ��ڵϤ���ϡ����켫�Τ����Ť�����������֥��ѡ����ץ饰�פǤ��뤬��Ʊ�����濴����ɽ���ե��˥���Ȥ�����������Ȥ������̤������Ƭ�פΥѥ����Τ�Τ����Τˤʤ����ΤǤ⤢�롣�Ĥޤꡢ������Ū�ˤ��Ǥˤ������ߤ��оι��ޤˤ���Ȥ�����̣�Ǥ��Ŷˤΰ�����ʣ���ʣ��ܤʤ������ܡˤǤʤ���Фʤ�ʤ��ä���
���Τ褦�˹ͤ������������������оι�¤����ͳ�ΤҤȤĤ����������ΤǤ��롣�ץ饰�ȹͤ����Ȥ����Ŷˤϥץ饹���ޥ��ʥ����줾�죱�ܤ��ĤǤ���е�ǽŪ�ˤϽ�ʬ�ʤΤǤ��뤬�����ϤΡ��Ŷˡפ��Ű���ä��ơ����줾�����ü����ʬ���濴�ؤ��ܶᤷ�ƺǸ���ܿ�����ľ���˲в֤����롢��������ϡ����Ĥʤ������Ĥ��۶ˤΤ����Τɤ줫����֥��ѡ����פ�ȯ������ΤǤ��롣
���Ϥˤ��ȯ�Фϻ�帢�γ�����³���������Ͼ�Ū�ʤ��ΤˤȤäƤΰ��祤�٥�ȤȤʤ롣���Ϥˤ�륹�ѡ����ʲв֡ˤ�ȯ����ͺ�ɤλ�ɤȤ��ܿ��ʤ��ʤ����ʴ�ˤϡ�Ʊ�����ݥå���褹�륤�٥�ȤǤ��롣�֤ϼ�ʴ�ȤȤ�ˤ��������롣�֤ϸϤ졢�¤����ꡢ��ʪ�Ȥ��ƤΥ饤�ե�������Ͻ����ޤ��������γ��Ϥޤǡּ�ҡפȤ���Ĺ����©�˽��������ѡ����ץ饰�������ˤ�����ֲФˤ�빹���פ�ü��Ȥʤꡢŷ����Ϥ��ۤɤΡ��礭�ʲ֡פ�餫���롣������ɽ�̾�ˤ���ֳ�ư�פ٤Ƴ��ξ��֤��ᤷ�������γ��Ϥޤ�Ĺ����©�ؤȽ������롣�����Ƥ��Υ��饤�ޥå���Ū������ϡ��ޤ����Ͼ�Ū�����ȸƤФ������������
�� ��ʪ�Ȥ��ƤΥե��˥���
�ʾ�Τ褦�ˡ��ե��˥����ʪ������ˤʤ��館��ʤ�С���ʴ����ʲ�ʴ����������˥�٤Ǥ��뤬��ưʪ�η���Ū�ˤϥե��˥���Ϥޤ�������������Τ���Ǥ��뤳�Ȥ�ȿ������ԤϤۤȤ�ɤ��ʤ��������ʤ��������ۡפΰż������ΤϾ�ˡֱʱ�˽���Ū�ʤ��ΡפȤ��Ƥ���ϲ�ǽ�Ǥ���ˡ������ƥե��˥��뤬��������ʤ��뤤��ñ������ˤȷ���Ū�˻��Ƥ���Τ϶����ǤϤʤ����֤�¡ʲ�ʪ�ˤȤ��ä���ʪŪ����ܥ���֤�����뤳�ȼ��Τ�����äƤ⡢��ǽ��Ρ������Ū��¦�̤���Ĥ��Ȥ����餫�Ǥ��롣
ʸ���ο�ʪŪȯŸ�����������Ρ���Ū�ʡ�ʸ���١�ŷ���Ϥ��褦�ʹ⤤�����ŷϰ����Ƥ��������Ū�١�ŷ��ã����褦�����Ե�������Ǥ��夲�����������Ū��ơˤ˸�����Ȥ����Ρ��־����˿�Ĺ��ŷ���ؤ��न��ס־����ؤ����Ƥ�ŷ������������ס��֤��⤯�פ��ѥ������äˤ��ο�Ĺ�����ִȡפ���ü���������פ���Ȥ����ѥ�������˺�����ʪ��Ū������*�Ȥ����Τ����ꤹ�뤳�Ȥ�����ʤ���
�ޤ��������ˤȤäƤΡ���˻���פȤ���ʸ����ư���ΤΤ�����������Ū����λ���ˤ����ʤϡ����ޤ��ޤʤȤ����Ǥ��Ǥ��������Ƥ��ꡢʸ�ؤ����Ѥ��̤��Ƥ�ɽ������Ƥ�������**�Ǥ��뤳�Ȥ��۵����뤳�Ȥ�ͭ�פǤ�������
* ���͡��������������θ�����˸������� + �� + ����������פξ�ħ
�֦��ķ��פȡ��� + ����������פ�ξ��������Ū�ʤ�Τ�ª�����������Ѥΰ��㡧Gilbert & George ��DICK SEED, 1988��
** �⡼�ĥ���Ȥ�����ū: Magic Flute�٤�ɽ���������Ȥ�ֱ��פ�����ۡפ������ؤλ������ħŪ����������ͺ���Ǥ��롣��ν���: The Queen of Night ��ò��ˤ�äơ�ڼ��줿̼�ε߽Ф˸��������������ɤ�̼�����᤹�ɤ����������餬�������οȤˤʤäƤ���̼�Ȱ��˰츫�ְ�����������ۿ��ʥ��饹�ȥ�: �ĥ���ȥ����ȥ�ˤ������˼����ޤ�Ƥ��ޤ������ɤ�뤢�����������Ǥ��롣�����ˤ��������ʤ����֤��뤬�ޤޤΤ����������פ�ø���Ⱦ�ħŪ������������Ū̾��Ǥ��롣
�� �����פȤ��Ƥ�����
��������������פȡ����פδ�Ϣ�Ȥ����Τϡ����ޤ��ޤʤȤ����ǰż�����Ƥ��������ä�������Ƚơ���ˤ��gun, pistol, canon�ˤˤ�����ȡ�����̾���ǡ�������ΰż��פȤ���Τϡ��Τ������ǹ����Ѥ����ΤǤ��롣�����ܼ��ϡ����ơפ����ӽФ�Ĺ�������ä������Ǥ��롣��Ū�ʤ�Τȡ����Ρֽ����: final, finish, finale�פ�魯¤��ʪ�δ֤ˤϡ��������ӥɡ�Ū�Ȥ��������褦�Τʤ�������в��̰ռ��Υ�٥�ǤΤĤʤ��꤬���ꤽ�����Ȥϡ������ǰ�ö�õ����Ƥ����Ƥ�̵�̤Ǥ���ޤ����Ĥޤꤽ��������ɽ�����褦�Ȥ������ƤȤϡ��ʿ���Ȥʤ�б���Ū�ȤǤ�ƤӤ����ʡ��������ϤΡֺ����������פȤ��������ε���ʤΤǤ��ꡢ����ϸ��¤ε���Ū�뺧�������ˤ��̤����������Ƥ�����ΤǤ⤢�롣����Ū�����������Ȥε���Ū����ˤˤĤ��Ƥ⥨�ꥢ���Ǥ�������Ȥ����Ǹ��ڤ��Ƥ��롣

ʼ�˸����ڴ���ҤΡ��˺���ɡ���ϻ�åᥬ�ꥹ�פΤҤȤ�
�����ˤ��������������ʤ��ꡢ��ħŪɽ�����ʷ��ˤ����ơ���Ū�פʾ�ħ�����������Ƥ��뤿��˰���Ū��ª��������Ū���䤽�κ���Ū��ɵ����ͳ������ΤǤ���ʤ��٤Ƥ����Ū�פ˲�᤹�뤳�Ȥ������������ȹͤ����ӥɡ����⡢����Ū��������Ŧ���뤳�Ȥ��������Ѥ���ȹͤ�����λ��Ū����ˡ�����������ħ����������ʿ��ΡˤȤ��������ǽ��������ǡ������ο����������ȹͤ��뤳�Ȥϡ��Ϥ���Ǥ����Ҽ�����ȸ����٤��ǡ��������ɽ���Ƥ���פȤ���Ǽ�������Ǥϼ¤������Խ�ʬ�ʤΤǤ��롣�����ε�����ʣ����ȯŸ����ʸ���٤˱����ơ����줬ǡ���ʤ����Ρ�����סֿ��Ρפ�ɽ���Ƥ���Τ��Ȥ������Ȥޤ�����������ʤ���С����Υե����ǥ�����Ū����Ū��Ϣ���ο��˽���ʰյ��Ͻ��������줺���������Ū�ʡֳ��פ���ǡ����ؤǡ����Ǥ��ʤ���Ф��ޤ��Ѥ�ʤ��ʤ�������������ˤĤ��ƿ����ꤹ��Τϡ�����餫��ֵ��Ū�ˡײ����ɤ���Τ��Ȥ������Ȥ��濴Ū����Ȥ����ܹƤ���Ū�ˤ�����ʤ���
 ��
��
�����֥Хͥ����롢�ѥ饹�顦��������Υ����ʪ��
�����ݥ���ʥ�Siva Devala�Υ����ʪ��
������פ�ɽ�����Ȥϡ����K�Τ����̤˴ؿ�������ΤǤϤʤ������郎���η��Τ��̤��ƾ�ħŪ�˻ؤ������֤�Ρפȡ������������������ؤ������֤��ȡפ�ξ���˶�ͭ����뤳�Ȥ�¸����˲�ʤ����Ȥ��Ŧ�����α��褦��
�� �ֽ���餻���ΡפȤ��Ƥ����
�������������ʶ��ϡˤ�����Ǻ���Ǥ��������ζ줷�ߤ�ֽ���餻����: terminate�פȤ���ǧ������Ƥ��뤳�Ȥϡ��ष���ܹƤˤ���������ε����ʾ�ˡ����˹����ֿ��ļԡפ�λ�Ƥ���Ȥ����Τ�ΤǤ��롣�ޤ����������������ߤ����������뤳�ȤǸ�������Ǻ����Ρֲ����פ�ޤ�Ȥ����Τ⡢���Ǥ˿��ļԤˤȤäƤ������ߤΤ���ͤ��Ǥ�������
�������оο������濴�˰��֤����finial�פȤ����Τ���ʪ�ʤ���Ʈ��β̤Ƥκǽ�Ū�ʳ���ʪ�Ǥ��ꡢƮ��ξ��Ԥ�Ϳ�������Ρ����ʤ���ֻ�帢�פ��ħ�����ΤǤ��뤳�Ȥ⤹�Ǥ˴ѤƤ����������������оο������濴���֤�����Τȡ���κ����Ƥ��֤�����Τ���Ʊ����Ʊ���ʪ�Ǥ��뤳�Ȥ⤹�Ǥˤ�����λ�Ƥ��롣���ʤ���������ȼ����ζ��֤��ħ�������Ū����Ǥ�������ˡ���κ������ۤ�����羾�䤽�Τۤ��μ������ꡢ�����Ƽһ�ʩ�դλ���κ������ۤ�������ϻΤ����ƹ����⡢�ֺǽ�פǤ���ֺǸ�פǤ�����֤η������Ǥ��ꡢ����϶��������ֳ֤����֤���뵼�����Ʊ����̣����ġ�
�Ȥ�櫓�����ܤ����ݤ�«�ͤ��羾�������ν����ʦ��ˤȻϤ�ʦ��ˤȤ�����Ĥμ����ζ��֡�ǯ��ǯ�ϡˤ˸�����ħʪ�Ǥ��뤳�ȤϤ��Ǥ˸������������֤��褦�ˤ������ݤ�ּФ���ڤ�פȤ������Ȥ����������Ū��̣�ϡ�����פȤ������Ǥ��롣�����ˤ���������Ǥ���褦�˻��̰��Τ�ǻ���ʴ�Ϣ�Τ�����ɸ��פʤ��������פΰż��Ǥ��롣�����ơ���Ĥ���Ƭ�ʤʤ�����ʪ��̢�ˤ���帢���äƶ����礦�����Ϥ��濴���न��Τ��ե��˥���Ȥ������ۡפʤ������աפǰż�����뤢���ξ�ħ�Ǥ��뤳�Ȥ⸫�Ƥ�����
�����λ�帢����Ʈ��ϡ����λ�帢��������ƼԤ��ֳ����פ��뤳�Ȥˤ�äư츫����뤫�˸����롣�������Ƹ���Ʈ���餻��Ȥ������̤��ˤ��Ф����Ǥ��ä������������Ȥ��ʤ����Ϥʤ����Ȥ�Ʊ���Ǥ��롣�������줿�����ۡ��աˤϻȤ�줺�˺Ѥޤ���뤳�ȤϤʤ�������ϳ��������Ԥˤ�ä����ꤵ�챣ƿ����褦�Ȥ��뤬�������뵷��ɬ����ϳ�̤���ΤǤ��롣�����Ƥ��λ�帢�����ꤷ�����˸������Ƹ��Ԥ����䤬�Ƥ��γ���ʪ�ˤ�ä���������뱿̿�ˤ���ʥХ������åɡ������������Dz���Ϲ����ۼ�Ͽ�١��ե졼�����ض���ӡ١�¾�ˡ�����Ϻ��絬�Ϥ�˽�Ϥ�ʿ���ˤȤäƤΡ�ʿ�³����μ��ʤȤ���Ԥ����ν�̿�Ǥ��롣
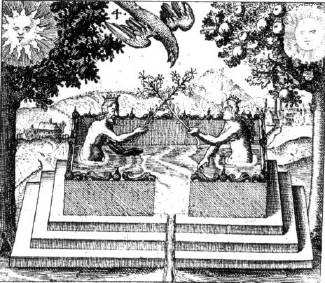
���ۤȷ�κ����Ȥϡ�����Ū���ϵ嵬��Ū�ˤʱ����ۤ������Ǥ��롣����������Ƥˤ�ż��Τ����붵����붵�Ǥ��롣���������Ǿ�ħ�������֤Ȥϡ��ޤ��ˤ������ۤȷ�Ρֺ����פ������������Ȥ�ż����Ƥ��롣���������Ȥ��������ۤ���ˤ�äƱ��������ݤϡ����ꥹ�Ȥ������ष���Ȥ��˸������ħŪ���ݤǤ⤢�ä�������ϡ��ۤ������Ȥ��ƤΤ⤦��Ĥλ�帢��ħ�Ȥ��Ƥ����ۤ����ַ�פʤ��Τ˱����졢�������Ť��ʤ뤳�Ȥؤΰż������롣���ε��祹������κ����ϡ�����Ūϣ��Ѥ��������������̮���ȼ����Ѥ���Ƥ�����Τ��������κ�������������������ζ�Ʈ����Ǻ��������餻���ۤ������ν���ȡ�Ĺ�����פλ���ؤ�Ͷ������ʻ�������ϤΡַ��פνִ֤Ǥ⤢�롣


�����ơʺ��������ȷ�η꤬�ۤ����ˡ���������¾���η��Ѥ�ȡֿ�: eclipse�פȤʤ롣�ͺ����ͤˤ����Ҥ��ͤˤ⸫����ֱ����פ��������Ƥˤ�ѻ�����롣

�ܥåƥ������å� ��Venus��Mars�ס�̲�äƤ����ͤ˸�����ޥ륹��������ʵ�����֡ˤˤ��롣�ե�����Ϲ�ף��ͤ��뤬�������ˤ�٤���ե�����ο��ϣ���������餫�����Ǥ��뤬��������ü��ˡ�泭�ˤ�äƵ�������Ƥ��롣

�������ķ��Ȥ��Ƥ�ϣ���Ū�ֺ�����Johann Daniel Mylius ��Philosophia reformata��
23:00:00 -
entee -
TrackBacks
2005-11-23
���ؤ������
����Ū�ʡ־�������ȡ����������������
�ָ����������פ��軰��������

��������ͤ���ʤ����ˤ��ᴤؤ�ƤΤ�����Ҥ����˸����Ҥ���������ˤƻ��٤ʤꡣ�ʥ�ϥ���ʡ���� ���� 14���
��������塢���褷�����ꥹ�Ȥ���Ҥ��������˸��줿�Ȥ��ε��ҡ�
�� ����Ū���¤Ȥ��Ƥο���
�֤����١פ������ܤ������ʤΤ���ï�ˤ�ʬ����ʤ������ˡּ������פ��������Ƥ���ְ���ʽ����ȡפˤ��Ƥ⡢����Ū�ˤϥ����ޥ��ȥ�å��ο����������ˤ������̤����Ƥ����������Ȥ����Τ����Τ˰��β����ܤʤΤ���ֲʳ�Ū���¡פȤ��ơ��ڵ�ȶ��˼������ȤϤǤ��ʤ����������������ˡפ�ȿ�������¤Ǥ��ä�*�Ȥ��Ƥ⡢��ǰ�ʤ��餽��Ϥɤ��ޤǹԤäƤ�ֿ���Ū���¡פǤ����ʤ����֤��ĤƤ�������Ʃ�뤷���פȼ�ĥ�����Ϣ�Τ�����ֿ���ȡפǤ�ʤ���Сʤ��뤤��...�Ǥ�����...�����ˡ����Τ��Ȥθ��¤ξ����ϥ�Ǥ��äƤ⥨�ꥢ���ǤǤ��äƤ��ǽ���Ȥϻפ�ʤ��ä��Ǥ����������˽��褿���ȡʤ�����ɮ�Ԥ˽���뤳�ȡˤǤ������פ碌�֤�ʻ��¤��ʪ�Ȥ��ä���facts�פ�������Ѥ߾夲�Ǥ����ʤ��������Ƥ�����ĤΡֿ���: truth, veritas�פȤ��ƷҤ����碌��Τ�ƶ���Ǥ����ʤ����������ַ����֤��Ƥ���פȤ��������Ķ���Ū�ʼ������ϡ�������ħ������̾�����ָ��աפ��̤��ơ����������ȶ��֤�Ķ���ơָ���ơפ����������Ƥ�����ɽ���פ���ˤ����äơ����̡��������ܤʤΤ��Ȥ����Τ�ַ��Ƥ����פ��Ȥϡ����Ρֱ����줿��ΡפˤĤ��Ƹ��Τ��ص���ͭ�ѤʤΤǤ��롣����ʾ�Ǥ�ʲ��Ǥ�ʤ��������ơ����η����֤�ɽ�Ф��뤢���Ρֿ����סʶ���Ū�ֿ����ס˼��Τ����ֲ��ٷ����֤��줿�Τ�ʬ����ʤ������Ȥˤ��������֤��줿�Τ��פȤ�������Ū���¤�ؤ��֥����ɡ������פȤʤä���
* �ष�����褹�������Ȥ���¸�ߤ����¤ϡֻ�Ⱥ����פ��֤��������Τ�Τξ�ħ�Ǥ���Ȥ�������ϡ��뵷�����ԤˤȤäƿ�������ز��ɡ٤δ��ܤǤ��롣���������λ����Τ�ʹ������ʤ��ʼ��������˸���Ǥ��뤫�⤷��ʤ�¿�����ɼԤˤȤäƤϡ����Τ褦���ɤ��뤳�Ȥκ�������Ǥ������������Ƥ���ϼ����ʤ��Ȥ����������������¤μ��Ť������������ؤᡢ�����ζ줫�鳫�����٤����줿�����������줿��: Messiah�פȤ���¸�ߤ������嵻��ʸ�����Τ�Τ�ã�����褦�Ȥ��Ƥ�����Ū�ȡ���ˡŪ����ħ�פȤ˹��פ��Ƥ��뤳�ȡʥ�ۥ磻�ȡص����ȿ��ٻ��ȡˡ������Ʋʳؤ䵻�Ѥ��ֶ����פȤ��ƿ��Ҥ��оݤȤʤäƤ��Ƥ��뤫��ʸ���ؤο��Ĥȿ����Ʊ�ص����ȿ��١�ȯ�ŵ��Ȥ��ƤΥ����ʥ⤬���Ҥ��оݤȤʤäƤ��븽�������ˡ������Ƥ��Ρָ���ͤȤ��ƤΤ����ˤȤäƤμ�פ����椯�椯�Ϥ���줬��ǯ̴�����褿���Ȥ���������ʹ�˸����ζ줫��ֳ����פ��������⤿�餹̤��Ρ־徺�����ߤ�������פȤʤ뤳�Ȥ����ۤȤ����«����Ƥ��뤫�˸�����ʾ塢���Ρֵ�����פξ�ħŪ��ǽ��ñ�˥ǥ����ʲ��Ǥ�����ô��Ǥ���ۤ�ñ��ʵ����Ǥʤ����Ȥ�ʬ����Ǥ�����������������帢���Ƽԡʲ��ˤλ����Ȥ�������ʤ⤷�����Ƹ�å��ˤȤ����ѥ�����ϡ����ꥢ���Ǥ����Ҥ���Ω�Ĥ��ȡض���ԡ٤��Ԥ���ե졼�������ˤ�äƤ��Ŧ����Ƥ��ꡢ�������β�: The King of Kings�פȤ��Ƥμ祤���������ꥹ�Ȥλ����Ȥ�������ϡ��ޤ��ˤ��������ķ�Ū���㻦���פΥѥ�����Τޤް����Ѥ��Ǥ����ΤǤ��ꡢ�ޤä������ûˤ��㳰�ǤϤʤ��ΤǤ���ʥХ������åɡ�����������פ��Ф��ˡ���������˽�Ƥ���ֵ��ҡפϡ��ޤ��ˤ��������Ū�ѡ����ڥ��ƥ��֤���ǡֺǿ����ءפ�°���롢���������ˤ�������äȤ�ȶ�ʿ����ʤΤǤ��롣���������Ϥ��ο��ä���Ω���ǽ�ˤ���2000ǯ���Ρֻ˼¡פ�����Ȥ���ȯŸ������ǽ���⤢�ꡢ���Ū�ºߤȤ��ƤΡ֥ʥ���Υ������פ�����Ū�����ꤹ�����Ǥ�ʤ��ΤǤ��롣��������������Ǻ�줫��ֳ����פ��ߤ��������ޡ����å����륿����ʩ�������ˤ����Ƥ������Ū�ºߤ䤽�α�����ů�ؤȤϤޤä����̸Ĥˡ��������γ��ϤǤ��Ρְ��Ρפ�Ǽ��ȸ����륹�ȥ����ѡ�ʩ������ˤη����פ�Ĥ����ҤȤĤΡ�ʸ���פ�ɽ���륳���ɡʵ���ˤȤʤä����Ȥ⤳�����۵����٤��Ǥ��롣
���Ρ������פϡ�æ�������ʤ�������������ˤ����Ƥ⡢�����뤳�Ȥ虜��������Ȥ��������ĤäƤ��ꡢ�����ϸĿͤޤ��������ˤ��������Ū�ʷи��ˤĤ���Ǽ���Ǥ���֤ޤ��ʤ��פΤ褦�������ˤʤäƤ���ΤǤ��롣�㤨�С������٤��뤳�Ȥϻ��٤���*�סֻ����ܤ���ľ**�פʤɤ�����Ǥ��롣
���Υ����ɥʥ�С��Ȥϡ������ޤ����и����ޤǤ�ʤ����ֻ��פǤ��롣�֣��פȤ��������˶ˤ�ƹ⤤������������Ƥ��뤳�Ȥ�¿���ο͡����Τ�Ȥ����Ǥ��롣�����Ƥ��Ρ֣��פˤ����ֱʱ����פζ����ʴްդ����롣
�� �����ȡָ��������ס�
���dz�ä����ο����ϡ�0.3333333....�פȣ����ʱ��Ϣ�ʤ�ֽ۴ġ����Ǥ��롣���Ȥ����������ԲĻ����ȡֱʱ����פϤ����դ�λ���ˤ�ä�����蘆�줿�̤�ҤȤĤˤϤ��������Ȥ���������롣����ϤȤ⤫����G��I�����른���դ�����θ��Ȥ������������Ȥ��ơ˥������Ĥ����������졢��Ρ��붵Ū��������פ����̤����˶������줿�Ȥ����ֱʱ�Υ��˥������פˤ��Ƥ������������ܿ��ȣ��dz�ä������ˤ�ä�������۴Ŀ� (142857142857142857......)�����Ȥ�����ΤǤ��롣�����ⶽ̣�������Ȥ˸�Ԥ�3, 6, 9�Σ��Ĥο�����3���ܿ��ˤ�ޤޤʤ�������ˤ�äƥ�������Τ褦�˱���˿������꿶�ꡢ���Τ褦�ʥ��˥��������������Ȥ���ǽ�ˤʤ롣���줬�֣���ˡ§�ס֣���ˡ§�פȤ����Τ�줿�뵷�Ǥ��ꡢ���Υ��˥������ˤ�äƿ������������������줿�餷����������ˤ��Ƥ⡢������Ĥο����֣��ס֣��פϡ��Ȥ�櫓�����ᥭ�ꥹ�ȶ����붵Ū�����������ˤ����Ƥ�������פȤ��ƶ�ͭ����Ƥ���ΤǤ��롣
���른���դξҲ𤷤��֥��������֤�ˡ§�פȤ����Τ��Ƥ��뤳�Τ��Ȥϡ����ˡ֣��פǷ����֤��������������ʤ���֣����äƣ��Ȥ���פȤ����������θ����ʤΤǤ��롣����ˤĤ��ƤϤ��ޤ��ޤʱ�������������른�����ܿ͡������Ƥ��ο����Ԥʤɤβ���ˤ�äƤ�������Ƥ��뤬������Ū�ʲ�������ä���������륰�른���դΡ֥��������֤θ����פϡ��ºݤβ����ʥ������ȥ˥å���������Ȥ�����ɽŪ���β����ˡ����ʤ��Ⱦ���Υ���������Ĵޤ�����δ���Ƥ���������������֤μºݤȤ��ä�����פ��Ƥ���櫓�Ǥ�ʤ��������������Τ˼�����ɬ�פ�;�괶�����ʤ��ΤǤ��롣�ʤ���ˤĤ��Ƥϥ�������륽��ˤ�äƤ�Ʊ�ͤλ�Ŧ�����롣��
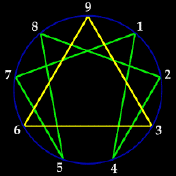
������Ĥο����֣��ס֣��פϡ����줫�鸫�ƹԤ������ˤȤäƤΡָ����������ס���ˤ���ˤ�äȤ�Ϫ���ʷ��Ǹ��������ΤǤ��롣
* disasters come in three // never two without a third // Why only two without three? �ʤɤʤ�
** Third time does it. // Third time does the trick. // Third time is lucky. // Third time is the charm. �ʤɤʤɡ�
�ָ������������ˤϰ��ٸ��ڤ����ΰ����Ƥ�����������Ϥ��Ρּ������פ�Ƥ��������ΤҤȤĤȤ��Ƥ����ե�����롣�ص�Ū���裴���ʽ��ˤޤǤ�ޤ�����������ˤȤä�����ˤʤ�Τϡ��裳���ޤǤǤ��롣�����ϡ�ϻ���֤�������¤�Ƽ����ܤ˵٤���פȤ���������ͣ����������ķ����������¤�ķ�����������赬�ϤȤ��ƺ��Ѥ��Ƥ������Ǥ��뤬�����μ��������Ȥ�����Τ�����ʸ��������ǡ������Ի��䤽��¾�ν����ˤ�ȿ�Ǥ���Ƥ����ΤǤ��롣���Υ���䶵�ˤ��θ�ή�����ꤽ���ʼ��������ˡ��֥��ꥹ�ȡפ������ˤ�äƻ�ˡ������ܤ�ᴤä��Ȥ������������ΰ��äˤĤ��Ƽ㴳�β��Ƥ�����
������������������������С����塡���ڡ����⡡������
�裱��������������������������������������������������
�裲��������������������������������������������������
�裳��������������������������������������������������
�裴��������������������������������������������������
�ʲ��Τ��Ȥϡ֥������פ����Ū�ºߤ�̵���Ū������Ȥ��Ƥ����äǤϤʤ��ơ���ħŪ��¸�ߤΰ�̣���������ʤ���ΤȤ��Ƥ⡢�����Ƥ���뤳�Ȥ˽�ʬ�ʲ��ͤ����뤿��Ǥ��롣
�� ��13���ζ������פΰ�̣���뤳��
��������������������˴�����Τ���13���ζ������Ǥ���פȤ������Ҥ�������ˤ���ľ�ܤ��о줷�ʤ������������������ֲ�ۤκפ�: Pesach, Passover�פǥ�����ã��˻�����ä��Ȥ������Ȥ��顢���줬��ۤλϤޤ����������������ä��ä����Ȥ�ʬ���äƤ��롣�����ơ���ۺפ�������Τ�Nisan��ʥ��������ߤ�3-4��ˤ���14���Υ��֡�����������ˤȤ������Ȥˤʤ�Τǡ����ߤΥ��쥴�ꥪ��Ȥϴط����ʤ���ΤΡ��ҤȤĤη�ʱ���ˤ�13���ܤˤ����뤳�Ȥ����Ҥβ������꤬�ʤ������������ߤ���줬����ǧ�����Ƥ��������Ρֶ������פˤĤ��Ƥϡ��ֻष�ƻ����ܤ�ᴡפä��Τ��������Ǥ��ꡢ���줬���ꥹ�ȶ����ԤˤȤäƤ����� (holy day)�ȤʤäƤ��븽�¤�ͤ���С���Ϥ������Ǥ��롣�����Ƥ���Ϻ�����������Ρ���������: Good Friday�פȤʤäƤ��롣
���ơ����ߤΤ����ˤȤä�ʬ����䤹������Ū�ʥ������������ꤹ�뤳�ȤϺ�����͡��������Τ���ˤ�ͭ�פǤ��롣�����Ƥ������13�����������Ȥʤ륫�����������ꤹ����ɤ����ȤǤ��롣�����Ƥ���������Τ��Ȥʤ��顢�������콵����������������Ȥʤ�ָ����������פȤ������Ȥˤʤ롣���θ����������ˤ��С�13���ζ��������������ʤ����餯����*�ˤ����ΰ�©����������: ���Хȡˤ������Ǥ��롣���Υ�����������äˤ��θ�Ρ֥��ꥹ�ȡפ�ư����ͤ���С��ब�����̤������Τ�15�����������Ȥ������Ȥˤʤ롣�����Ƥ��Ρ�15���ν��ס��軰���ˤ������������Ȥ������Ȥˤʤ롣
* �����;�ǻबˬ�줿�������������Ǥ���ˤ⤫����餺�ְŤ��ʤä��פȤ������Ҥ����뤿�ᡣ�����餯�������ż�����Ƥ��롣��������ˤ����Ū���¤Ȥ��ƤΥ����������ꤹ��ɬ�פΤʤ���ħŪ���ҤȤ��Ƽ�����äƤ����ʲ뤳�ȤΤǤ����뵷�����롣
�����Ƥ����������ϥ���������: Easter Sunday�Ȥʤ롣�ʾ�ε����ή��Ϻ�����������ȤϤʤ��ΰ��פ�ʤ��Τǡ�����Ū�ʵ��������ˤ�����ǯ�Ѥ�롣�������äƸ����ޤǤ�ʤ�����������ɬ�������13���פˤʤ����ǤϤʤ��������������Υ��������˱���ʷ�������礱�ˤ����ƤϤ��С��ɤΤ褦�ʡ��ķ�Ū�ʻ����פ�ȿ��Ū�ˤʤ����ΤʤΤ������뤳�Ȥ��ưפˤʤ롣
�����Ƥ⤷�����ꥹ�Ȥλब��¯�֤ˤ�����������ǡ������13���ζ������פǤ���Ȳ��ꤹ��ȡ����ߤΤ���줬���θ����������Ǽ����줿���Ū���֤Ρ֤ɤ������פˤ���Τ�����̤��뤳�Ȥ�����ǽ�ˤʤ롣�����ǤϾܽҤ��ʤ�����������������С������λ���Ū�ʾ�ħ���λؤ������Ȥ����ˤ��С��ۤܡ�20���ζ������פ˶ᤤ�ʤ��뤤�Ϥ��Ǥ�20���ζ������ʡˤΤǤ��롣�������������軰���ζ������˺����ݤ��äƤ��뤳�Ȥˤʤ롣�Ĥޤꤳ������ֿ����ΰ�©���פ϶ᤤ���Ĥޤ�����ˤȤäƤΡֵ�©�פ�����ϻ��֤�����Ǥ���������ˤȤ���������Ƴ����ǽ�Ȥʤ롣
����ˤν����פ��������Τ��ꤦ����ˤϡ������طʤˡ��ķ���ȿ���פΥѥ�����Ȥ�����Τ�ǧ��������Ȥʤ롣�ޤä���ȿ���Τʤ�ľ��Ū�ʻ��֤���¸�ߤ��ʤ��ȹͤ��������Ѥ���ˤ�̤���ͽ¬���ꤤ����Ω���ʤ��ΤǤ��롣�Ĥޤ�����Ū�ʽ���������Ū�ˤ��¸��Ȥ�����Τˤϡ�������������Ū���֤Ȥ������֤��ķ�Ū�ѥ�������Ф��붯��ǧ���ȼ��Ф�ȼ�äƤ���ȹͤ���٤��ʤΤǤ��롣
���Τ褦�˹ͤ����������λ���ˤ��褽���������ο����������Τ��о줷��������Ū�ȡ����ͽ�����ФƤ���Τϡ��������٤ޤǡ����ˤ��ʤä����ȡפȸ��äƤ��ɤ������ˤϤ��������ּ���Ū���֡פ��Ф��붯�����Ф����롣�����ơ����κ���Ͻ����ˤ�äƤ��줾��Ǥ������������ο������Ϥ��κ���������Ԥ����Ū�����뤳�Ȥ�����Ǥ��뤫��˳��ʤ�ʤ��ΤǤ��롣�����������ǹԤäƤ����Ϣ�ξ�ħ���ϡ������Ĥ����븰����Ǥ⡢������ǽ�ˤ���֤⤦�ҤȤĤ�ü��: another one of clues�פʤΤǤ��롣
�� ��ˤλ��ع�¤
�ޤ��������軰���ˤ�����Ȥ�����ˤ��Ѥ߾夲�����ع�¤��ħ�Ȥ����Τϥ����ޥ��ȥ�å���Ϥ�Ȥ���¿���ν���Ū�ʾ�ħ��������˸��Ф����Ȥ��Ǥ����ޤ����ޤ��ޤʸ������Ѥ���ˤ⸫�Ф����Ȥ��Ǥ��롣
������ˡ���Υƥ�����μ̿�
 ��
��
����������ˡ�����쥴�16���Υƥ����顡�����ƥ�����������ˡ���ԥ���12��

�塧��������ģ�ν����� (Court of Arm)���ƥ����餬���˼礿�����ǤȤʤäƤ��롣����ۤɤΡְ�̣�פ�������Ĵ��ʤΤǤ��롣
�����ֻ��Ŵ��פȤ��Ƥ��Τ���ֶ��Ĵ����ϡ���ƥ��ǡ֥ȥ�졼�̥�ס������ꥢ��ǡ֥ȥ�졼�˥�פȸƤФ졢���Ф��������줿���ع�¤�δ��Ǥ��롣�ӥ�������뤤�ϥڥ륷��˸�ή�����ꡢ�����������Ǥϡֶ������٤ξ�ħ�פȹͤ����Ƥ��롣
The Papal Tiara, also known as the Triple Tiara, in Latin as the 'Triregnum', or in Italian as the 'Triregno',[1] is the three-tiered jewelled papal crown of Byzantine and Persian origin that is the symbol of the papacy.
�Ĥޤꡢ��Tiara�פθ츻���Τˡ֣��פΰ�̣�礤�����롣�����ꥢ��Ρ�tertio�פϡֻ����ܤ�: third�פΰ�̣��
�ޤ������ܸ����ϸ����ι�긦���ˤ�TIARA (Takasaki Ion Accelerators for Advanced Radiation Application)�Ȥ������ߤ����֤��Ƥ��뤳�Ȥ���ɮ���٤��Ǥ��롣
��ꥤ����ȼ�������Υ����֥�����
��������ΤǤϡ����λ��ع�¤���ʤ����֣��ο����פ��ݤä���Τ���ϡ��ͤΰդ�����Ȥ������뿷���������Τη����ʪ��̾�������롣

�ե�����åѤΥ���Х��Civilization Phase III��
�� �������λ��ع�¤
�����Ƥ�äȤ⸵��Ū�ȸƤ֤���������ּ������פ�ȿ�Ǥ��������ʡʸ�ʸ��ˤ��������ʥ����åȡˤǤ��롣����϶��: The Fool�λ����֤��Ϥ�ֻ��֤�ι�פȡ����δ֤ˤ��������ܤ��٤���ʪ�ȤΡ����סְռ�����Ĺ�סַ��ߡס���þ�פʤɤλ���Ū�������������ΤǤ��롣����������Ǥ���ˤȤʤ�֥�㡼���륫�ʡפȸƤФ��22��Υ��åȤϡ��ޤ��ˤɤΥ����ɤˤ�°���ʤ�����Ū�ʡ֥��硼�����פȤ��Ƥ�The Fool�Ȥ����������21��Υ����ɤˤ�ä����롣�����Ƥ���21��Ȥϣ��λ��ܡ����ʤ�������λ��ַв��ɽ���ΤǤ��롣����ϲ��˼����褦�ˤޤ��ˡָ����������פΤ褦���¤�ľ�����Ȥ���ǽ�Ǥ��롣
�����ˤ⤽�줾��ν��ʼ��ˤˤ�������ϻ���ʶ������ˤˤ�����ս꤬���ֻ�סʤ⤷���ϡ������סˤȤζ�����Ϣ�����뤳�Ȥ���������Ƥ��롣����ϡ��֡פȡ��ġפλ���Ҥ����������ס��ֲСפȡֿ�פΤ֤Ĥ���礤�������ۡפȡַ�פι��Ρ��Ȥ����Ǵ�Ū�ʥ��٥�ȤǤ��뤫�顢���η�礳���ϡ�����ʼԤκ�������ĺ�ˡ������ƾ������ԡʤ����ˤ�̵���λ�ʤΤǤ��롣�ֲ����λब���ˤȤäƤαɸ��Ǥ���פȤ����������Ū�ʿ��Ĥ�Ʊ��������ġ�
�� �ֻ����ܤ���ľ�פȤ��ƤΤ���������
�ֳ����ؤ������������ȣ����֤����ȿ���ȴ�Ϣ�����뤳�ȤϤ��Ǥ˸��ںѤߤǤ��롣�����ˤ�Ķ���Ūʸ�����֣����֤����פȲ�ᤵ��Ƥ⤪�������ʤ�ħ�����롣������������С���Ƭ�˰��Ѥ����֥�ϥͤˤ��ʡ����פΰ���ϡ����ͤ���������������Υ������˴ؤ��뵭�ҤǤ��롣����ϳΤ��˥���������������Ҥ�����������Ѥ�ä��Ƥޤ������Τ��ٷ����֤����Ȥ��ɤ�롣�����⤷�����������ʤ�д����Ƶ��Ҥ����̣���ʤ��������褷�Ƹ塢��Ҥ��������˸��줿�פΤǤ˻��ٷ����֤��Ƥ���Ȳ�ᤷ�ʤ���С������ˤϲ���ο�����̣�Ф��������ʤ��������Ƥ���ϸ��첽����ʤ���Фʤ�ʤ��ä��Τ���̵��̣�ʵ��Ҥʤɣ��Ԥ�ʤ�����줿���Ρ֥�ϥ����פǤ��뤳�Ȥ�פ��Ф��ͤФʤ�ʤ���
���������ξ�ǡ���������ʤΤϡ����β���ǤϤʤ��������֤���Ƥ������Ū�ķ������롢�Ȥ��������ʤΤǤ��롣
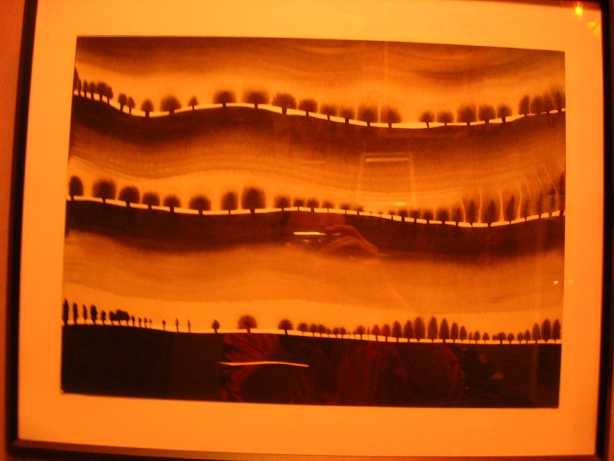
��The End�����ͽ����ʸ���Ͻ�ë�Υ��ԥ��ˤƴѤ뤳�Ȥ�������
16:15:00 -
entee -
TrackBacks
2005-11-12
���ؤ������
����Ū�ʡ־�������ȡ����ȸ��������������
�������������θ�����˸������� + ��+ ����������פξ�ħ
 ��
��
 ��
��
�庸���ָ��������������������ͻԶⲰ ���������������
�屦��������������饤�ʽ��ν����֥ѥ��åȤȷ�פΥ���С����֥�å�
ľ�塧40�ե����Ȥ�����Ρ֥�ȥ��Cathedral of Seville
�� ���� + ����������פθ���Ū����
���ΤĤ����ա��⤷�����ۡ����Τˤ����ơ֥ե��˥���פ�̾�Τ��Τ���ִ�פο����������Ϥ��줬ͭ�Ѥʻ��Ѥ˶������Ȥ������γ��ϳ������ʤ���Фʤ�ʤ����դˤ��衢�ۤˤ��衢��������¦�ˤϡ���ȡפ����롣���ϳ������ơ���Ȥ����ˡֳ����פ���Ƥ��������δ���Ѥ���������ΤǤ��롣�����Ƹź������δ��ơ��ޤȤ����ʤ��뤤�ϴޤ���˿����ˤϤ�����ȤˤĤ��ƤΡʸ���ˤʤ餶��ˡָ��ڡפФ����Ȥ�����롣����Ƥ����Τ�����Τ������Ҥ���Ū�Ǥ��롣
�Ȥ����ǡ���˾ܤ��������뤳�Ȥˤʤ�֦��ķ��פΤ⤦�ҤȤĤ�¦�̤ˡ��� + ��������ĺ���פȤ�������Ū�ѥ������롣Ω�����äƹԤ����������������Ȥ�����Ū�ǡ�ʬ����䤹���ץ�����Ǥ��롣���Υ������������ζˤ�ƹ������ꥢ�Ǵѻ��Ǥ��롣�ä����Τˤ����Ƥ���ϳ�Ū���������¿�����Ф���롣�����Ƥ�����¿���Ͽ�ʪ�Ȥδ�Ϣ��ǻ���Ǥ���*��
* ��������ޤ졢����ǯ����ᤴ������ǯ��ǯ����Фơ��¤λ��������ꡢ�䤬�Ƽ��Ĥ����Ǥ֡ʼ��Ǥ���ˡפȤ��������ʸ���ʲ��Υѥ�����¾�Ǥ�ʤ������̤�ȯ���פ�����˳��Ϥ��줿ʸ�����������˻��夽�Τ�Τȴ�Ϣ���Ƥ��ꡢ�ޤ����ο���ˤ���ʪ�Σ�ǯ�Ȥ���Ĺ���饤�ե�������ȸƱ�����Ȥ������Ǥ⡢����ʾ��ɬ��������äƤ���ΤǤ��롣�ʿ�ʪŪʸ�������뿢ʪ�Υ饤�ե�������Ȥ�������ҹ�¤��
ŷ���ؤȿ���ľ���ˡʿ�ľ�ˡ˿�Ĺ���뿢ʪ�Υ�����ϡ��ź��������ˤ����ƽ��פʾ�ħŪ��å���������ã��������̤������褿�������Ƥ�����¿���Ͽ���ˤ����붵Ū�ʡ����������������Ȥ��ơ����뤤��¿��Ū�ʰ�̣���������ΤȤ��Ƽ���������Ƥ�����������: axis mundi, etc.)�������ơ���˼㴳���ڤ���褦�˶ˤ��ʬ����䤹������ʪŪ���ȡפˤ������Ƥ��롣�����ϡ�ʩ���ˤ������ϡ�β֡ס����ܤΡֵƤβ֡פ����߲֡ס����ΤΡ֥�����: thistle�ס����뤤�ϡּ��Ϥ���«�ͤ�줿��*�פȤ��ä��Хꥨ���������롣�ޤ�����������֤��������ȡ��ѡ���ĥ�ʥ�����ˡ��ѥ��åȡ��ե��˥å���������¾�Υ䥷����ʤɤμ��ڤη��Ǹ���롣�����Τɤ�⤬����Ϥ����η���Τꡢ��ά�����줿�ץ��ե���������������Ȥ����ǤϹ���ʽ����ˤ䤽��¾�ξ�ħŪ�����Ȥ��Ƥ⸽���ΤǤ��롣
���ڡʥ�����ˤ���Ϥ佣���Ȥʤä��㡧
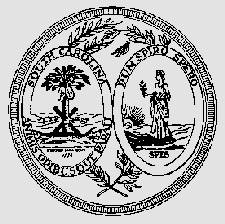 ��
��
�庸��������Υե������㡼���줿�����ʥ������
�屦����ͭ���ξ�ħ�ס���ŷ�ȡ����ŷ�Ȥξ�ħ�����Хϥ�ȸ��Υѡ���ĥ

�塧������������饤�ʽ���

�俩��֥����ǥ����ǥ��å���ץѥ��åȤη�����פ碌��ʥ�����������饤�ʽ���Palmetto�Ȥ���̾�ι�ơ���ξ��ʡ�
������������饤�ʤν����ϡ֥ѥ��åȡפȸƤФ�Ƥ��륷����ΰ��Ǥ��롣�����ڤϽ��ԥ��㡼�륹�ȥ�Գ��λ���Ǹ��Ф����Ȥ�����롣�ä˳������ն�ˤϸ��ߤǤ⳹ϩ���Ȥ���¿���������Ƥ��ꡢ�ä����Ĵ��Į�¤ߤ��Ф����Τˤ�ʤäƤ��롣���줬�����Ȥʤä�����ϡ����줬�ֻ��¡פǤ��뤫�ݤ��ϤȤ⤫���Ȥ��ơ����Τʥ��ԥ����ɤ�ȼ�äƤ��ꡢ�ϸ��Ǥϸ��ߤǤ������դ��롣����Ͽ���Φ�ο�̱�Ϥ�13������������Ф�����Ω�����ĩ������ΰ��äȤʤäƤ��롣�ѹ���⤬���㡼�륹�ȥ�γ���ˤ�⤷���ݡ��줷�Τ��Ǻ�ä��֤Ϥ����դ��¿���ФäƤ����ѥ��åȤ��ڤ��ڤäƺ�ä���¤���ä�������Ϥ����Ϥ�¾���ںब˭�٤ˤʤ��ä��������������롣�������������δ��⤫���ˤ�⤬���ä��Ȥ�����������Τ���ѥ��åȤ��ڡפδ��Ƿ��ߤ��줿�ɸ��ɤ���ˤ�Ƥ�ķ���֤����פ��������Ƥ��롣�����ˡ����Υѥ��åȤ��ڤˡ��ɱ��ϡפȤδ�Ϣ�����Ф����ΤǤ��롣�����������ͳ������н����ȤʤäƸ塹������ޤǤ��Υ��ԥ����ɤ�������������ζ�������ä���ΤȤʤ롣
�����Τɤ�ˤⶦ�̤ʤΤϡ��ۤܿ�ľ�ˤޤä����ˤ��δ��Ф���ĺ����ʬ���դ�ޤʤɤ�����Ȭ��������Ū�˹�����Ȥ���������Ǥ��롣���Υ�����Ϥ��줬�줬���Ȥ��Ƥ��ޤ�˻��̤äƤ��뤿�ᡢ���οްƲ������ά�����줿�ץ��ե����뤫��Ϥ��줾��ο�ʪ�μ��¬���������ꤹ�뤳�Ȥ����ۤɤǤ��롣���줾�줬����Ϥ䤽��¾�ξ�ħŪʪ�ʤȤ��ƺ��Ѥ����˻�ä���ͭ�Υ��ԥ����ɤ���ˡ����ä���Ĥ���ˡ�������ϡʾ�ħ�ˤ�ǧ���Ǥ����������ʿ͡��ˤȤäƤϡ������ϡ����ꤵ����ɬ�פ��ʤ��ۤɤ˼����Ƕ���Ū�ʿ�ʪ��ɽ���Ƥ��ꡢ�ޤ����̤ʴ����������������ΤǤ���ˤ�ؤ�餺�������Ϥ���������ͭ�θ���Ū�ʥ��ԥ����ɡʾ��ˤ�äƤϸ����סˤ�Ķ���ơ�����ҤȤĤ����Ƥʤ������������ã���褦�Ȥ��Ƥ���Ȥ����פ��ʤ��ۤɤˡ�Ʊ���褦�ʷ���Ū��ħ*�������Ƥ���ΤǤ��롣
 ��
��
�庸�������åȥ��ɤ���Ϥʤɤ����ˤ��о줹�륢���ߡ��屦���ե�ᥤ��������Ź�ʤɤˤ褯����Ƥ���٥�ȤΥХå��롣�����ߤϡ��구�ȥ���ѥ��פ���Ϥʤɤ�ʻ�����о줹������Ǥ��롣�֦��ķ��פ˴ؤ���������ݤ˺ƤӼ��夲�롣
�����Ǥ�¿���ο��������ʤ������ּ��Ϥ��줿���ס����������ޡס��֥����ߤβ֡פʤɤ���Ϥϡ����������Ϥ���٤ơ����Ρ��졿�ȡפ���ʬ����ü��û��*����������ĺ����ʬ���������ϡ��ۤȤ�ɤ���餬�ʥ����ߤʤ饢���ߡ����ʤ����Ȥ����褦�ˡ˶���Ū�ʲ������������褦�Ȥ������ϡ�����ˤ褯���������η�����Ϣ�ۤ����뤳�Ȥ����ܤǤ��ä����Τ褦�Ǥ��롣����ϲ�������ʤ����Ȥ���ʬ�����뤫��ɳ��«�ͤ�����������ʤ��Ƥ���Ȥ����������Ȥ��ƶ��̤ʤΤǤ��롣����ϡ�����˸�ˤ���줬�֦��ķ��פȸƤ֤��Ȥˤʤ��Ⱦ�ʤ�������ΥХꥢ��Ȥ�Ƥ������˺ƤӼ��夲����Ǥ�������
* �����ߤ˴ؤ��Ƥϡ���ʪ���ΤȤ��Ƥϥ��������߲֡�ϡ�˶��̤ο�Ĺ����ֻ���פ�ĺ��ˤ�����ָ����פΥѥ�����Ǥ��뤬����Ϥοްƾ�Ϥ�äѤ餽�β֤����ʤȳܡˤ����夲���롣���Τ褦�ʤ��Ȥˤʤä����Ȥˤϡ��ּ��Τη����Ȥ����̤���ħ��̵��Ǥ��ʤ�����Ǥ��롣
�� ��߲֡��ؼ�ڡ�

���������衧�����ΤĤФ�
��̾���ؼ�ڡפȤ�ƤФ��ŷ��β֡פȤ��Ƥ�Ƥ��ޤ����߲֤��Ф��Ƥ⡢���β�Ŧ�ߤ��Ф��Ƥϡ��֤���ʤ�μ�äƤ�����Ȥ��л��ˤʤ�פȷٲ����봷���������餷�����������θ������ˤ��������β֤λؤ��������Ƥ��Ф���ۤȤ��̵�ռ�������Ȥ�����٤�ƶ���������ꡢ���⤢��ʤ��Ǽ���Ǥ����ΤǤ��롣��ľ�˿���ľ�����Ӥ�ԡ���������������Ū�˻���Ȭ���ˤ��β��ۤȳܤ��롣�ޤ��ˡֻ���ȸ����פξ�ħ���ķ���ô����ʪ�Ǥ��롣

���������衧�����ᡢ��߲֣�
�� ���ȥ�å����θ�����θ���Ū����
���� + ��������ĺ���פȤ��ä���ħ��������Ǹ��ڤ����ʤ��Τ������ȥ�å�����˱����Ƥ��Ф����о줹�����θ�����Ǥ��롣������ˡ���������ξ��������ۤ��դ�˷Ǥ������餹��Ѥϼ̿�������Ǥ⤷�Ф���ª�����Ƥ��롣
 ��
�� ��
��
���θ�����Ȥ�������餹�������ˡ��
http://aquinas-multimedia.com/adoration/
http://www.agdei.com/Commentary.html
�����θ�����פ����ܤ�������Ƥ����Τϡ���monstrance: ��ȥ�פȸƤФ���ΤǤ��롣��̾�Ȥ��Ƥϡ�sunburst, sunbeam: ���������������ء����۸����פʤɡ����Ƥ��̤�����ۿ��ġפ�פ碌��褦�ʹ����Ȱվ��ˤʤäƤϤ���ʼºݤ˥��ȥ�å����������Τ�Ť��۶� (paganism) �����ۿ��Ĥȷ�ӤĤ��Ƥ����������������ؼԤ�¸�ߤ���ˡ�������monstrance�פ��Ƥ�̾�Ȥ��Ƥ��������İ���Ū���Ȥ������Ȥˤ����Ͻ�ʬ�����ܤ��٤��Ǥ��롣
����Ϥ��Ρ�monstrance�פȤ���ñ��θ츻�Ǥ��롣���ߡ���demonstrate�פ��remonstrate�פʤ�"monstrate"��촴�˻���ñ�줬�����Ĥ�����ˤϤ��뤬�������ϡָ����롢�������롢�����롢Ϫ�ˤ���פʤɤΰ�̣�Ȥδ�Ϣ����ġ����������⿼����Ϣ�Τ���ñ��ϡ�monster�פǤ��롣���θŤ���ˡ��1300ǯ���ˤȤ��Ƥϡִ����ưʪ�סֽ����۾�ˤ�����ŷŪ�˸��ɤ���ä�ưʪ�פȤ�����̣�Ȼ���ñ��Ǥ��ꡢ���θ塢���������䥰��ե���Ȥ��ä��������ʿ��á˾�νáפΰ�̣��ž���롣1500ǯ���ˤϤܸۤ��ߤ���줬�Τ�Ȥ����ΰ�̣������ʹ�Ū�ʻĵ�����ٰ�������Ĥ�Ρ������������ʪ�פȤʤ롣
���θ����椬�ֽáʤ���Ρˡפȴ�Ϣ�դ�������ͳ�ϡ��ֽ���: zodiac�פȤδ�Ϣ�����餫����Ťΰ�̣�����θ����Ƚ��Ӥε�ǽ��ξ���ˤ����ʪ�ʤ�¸�ߤ�����¤Τ���Ǥ��롣�������δ�Ϣ���ϡ�monstrance�פξ�ħ�տޤΥ��ꥸ��ˤĤ��ƺ����⤿�餹���ǤȤ���Ư���Ƥ���Ȥ�����롣���ӤˤĤ��ƤϳΤ��ˡֶ��۾������ʪ��12���ߴľ�����֤�����Τ��Ȥ�������������Ω�ġ��Ĥޤꤳ������ΤΥۥ��������פ��Τ�ΤǤ��롣�����ơ����αߴľ��Υۥ��������פ���������Τ�ΤȤ��ƥǥ������줿�Ȥ�������ϸ��ߤ����θ�����Τ褦�ʸ�������Ȥ�Τ��Ǥ��롣���ˡ�����������ȯ�������θ�����Ȥ��Ƥε�ǽ�˲ä��ơֽ��Ӥε�ǽ�פ�������줿���㤬����Τ�Τ��Ǥ��롣
�����ΤȽ��Ӥ��ͤ������㡧TBA��
�Ȥ����ǡ����������ꥢ�β�ȡ����������ˡ��ǥ����ѥ����Ρ�ŷ����¤�ȳڱ������פΥƥ�ڥ��(1400ǯ��ˤϡ��֥ץȥ�ޥ������α���פΥ�ǥ뤬���Τޤ������������˼�������줿�����λ���ˤ��������ֱ���Ū���ʤǤ��ꡢ�������Τ�Ⱦʬ�ʾ�줬���롣�����Ƥ��γ�����ʬ��������ֽ��ӡפ�ޤ�Ǥ������Ȥ����餫�Ǥ��롣���ߤǤ⤽�κ��פ�ǧ��뤳�Ȥ��Ǥ��롣�����������ν��Ӥ����ۡʤ��뤤�ϡֵ�����ΡסˤȤδ�Ϣ�����ϡ��������ʱ�����ϿޡˤȤδ�Ϣ�ǽФƤ����ΤǤ��롣�����ŷ�Τα��Ԥ�ޤ���ɽ���Τ�������ƻ�������Ǥ��롣
�ʿ��ǡ����������ˡ��ǥ����ѥ����Ρ�ŷ����¤�ȳڱ������ס�
�������äơ���monstrance�פθ츻�����θ�Ρֽ��ӡפȤδ�Ϣ��������ꡢ���⤽������Ū�ˡ֥����������ʪ�פΰ�̣���Ƥ路����Τǡ���ˤ��줬̵�ռ������줿�ȹͤ���Τ������ʤΤǤ��롣�Ĥޤꡢ���ȥ�å����������餬������Ρ����ҡפ����ΤʤΤ��Ȥ������Ȥؤζ�̣���������������ˤϤ��롣
monster
c.1300, "malformed animal, creature afflicted with a birth defect," from O.Fr. monstre, from L. monstrum "monster, monstrosity, omen, portent, sign," from root of monere "warn" (see monitor). Abnormal or prodigious animals were regarded as signs or omens of impending evil. Extended c.1385 to imaginary animals composed of parts of creatures (centaur, griffin, etc.). Meaning "animal of vast size" is from 1530; sense of "person of inhuman cruelty or wickedness" is from 1556. In O.E., the monster Grendel was an agl?ca, a word related to agl?c "calamity, terror, distress, oppression."
�� ���������θ���Ū����
���ơ����˸�Ƥ����Τ����ܤ����Ҥ��оݤȤʤ밦�������ˤĤ��ƴѤƤ������Ȥˤ��롣
http://www.city.obama.fukui.jp/section/sec_sekaiisan/Japanese/data/084.htm

���������Ϥ��줬�Dz�Ǥ��뤫���Ǥ��뤫�ζ��̤ȴط��ʤ���������¿����ʿ�̺��ʤȤ����������ݡ�����餬�������ΤλѤǤϤʤ������븲����Ȥ���˺ܤ������Ȥ�����¸��Ω�κ��ʤ����������褦�ʴ���Ū����Ū��ɽ���Ȥ��ƽФƤ��륱������¿�����Ĥޤꡢ���Τ褦�ʡָ�����פ��ޤ����äơ����Ρָ�����ס��⤷�����������Τ�ΤΤޤ�Ω��Ū�˺Ƹ�����ʾ�ˡ��������Ū��ʿ�̤��ϼ̤��Ƥ����Τ��ֺ��ʡפȤʤäƤ���褦�˸����롣����С����θ����漫�ΤǤϤʤ��ơ������������θ������Ѥ��ͤ������ʿ��Ū�����������褦���㤬¿���Ȥ����褦�ʤ��Ȥȹͤ���Ф����������Ƥ����������Τ��ְ��������οޡפȤ��Ƥ����ˤ��Τ����礬¿������Ȥ����櫓�Ǥ��롣
 ��
��
����Ĺ��������º�������������������塢��ʩ�ա����Ͼ���
�������ɹ�Ω��ʪ�ְۡ������������׳��һ���ʷ�Ĺ8ǯ��1256��
̵����Ω��ɽ���Ȥ�����Ħ�ʤɤΰ��������Ȥ����Τϳ��Ϥ�¸�ߤ��Ƥ��롣�������������Ȥʤ�������������ʿ��Ū�����������Ȥ��˸��ˤ���줬����褦�ʤ����������������Τ��Ȥ�����ͳ�����餫�ˤʤäƤ��롣�Ĥޤꡢ��¾�˾�äƤ��밦���������Τ����Ǥʤ������줬�ܤäƤ�����¡��������������ν��פ����ǤȤ������̤���뤳�Ȥ������Τΰ�̣����ã���������̵��Ǥ��ʤ��ۤ��礭�ʰ�̣����äƤ��뤫��Ǥ��롣�⤷���������������Τ��������̤��оݤǤ���Τʤ�С������������פ��������Dz�䳨��Τ褦��ʿ�̺��ʤ���äȤ��äƤ���Ȧ�ʤΤǤ��롣����Ǥ⤽���㤬���ʤ��Ȥ������Ȥϡ���¼��Τ��������Τ�Ʊ���ۤɤν���������äƤ��롢�Ĥޤ���¤�ޤ���������������������ʤ��ä��Ȥ������ȤʤΤǤ��롣
�ޤ������������κ����������¤ξ夫��ֿ�ľ�˿���ľ�����Ӥ���פξ�Ǥ��ꡢ�����Ȥ����������֡�Ū�ʻ���ϡ�ں¡ˤξ�ʤΤǤ��롣���η���Ū����ħ����䤷�̤�ˡ����������Ϥ��켫�Τ������Ƥ�ĺ���˺ܤäƤ��������פε�ǽ��̤����Ƥ���Ȥ���������ΤǤ��롣
�ʾ��ǡ��������������פ���ޤǤ�ʤ��������Ĥ����ǤǴѤ�ĺ���ְ����������פ�������餫�ʤ褦�ˡ��������פȡ���¡פ��Բ�ʬ�Ǥ��ꡢ��¤Υǥ��ơ��뼫�Τˤ����ܤ�椯�����η��־����ħ���������äƤ��뤳�Ȥ˵��դ��Ǥ�������
�����Ӥ˳褱��줿ϡ�ں¾���֤��������ؤˤ��Ʒ�������פ�������̤����������������������¾�˰��֤���ͥ���դˤ�������ۡפ���ʮ�ͤ��졢����ĺ�����ĥ���Ƥ��뤫���ͤ˸����롣�����������ۡפȡ������פΥѥ�����ϡ����饸����ԻĤʥ��פȤ��Υ��פ���ФƤ������ͥ��ˡ��פȤδط�������Ϣ�ۤ������ΤǤ��롣�۵��֤�������ޤǡ����ˡ��Ͼ����ʥ�������Ĥ�������Ƥ��ơ��������Ȥ�����Ȥ��Υ��פزä������ȿ��Ū�ʻɷ�פ˸Ʊ����ƥ��פ�����������ֿ�ФƤ���פ櫓�Ǥ��롣�����������饸��Υ��פ˸������ħŪ�����Ρ��ۡס����ӡˤ�ô�äƤ���Ȥ���С����������ϡֶ۵��֡פ˼�ͤθƤӳݤ��������뤫�����dz���ʮ�Ф��ƽ����롢�Ȥ������ε�ǽ��ô�äƤ������ʤ��Ȥ������Ǥ���ΤǤ��롣�ޤ�����������Ȥ�����������⡢��Ū�ǰ���Ū��¸�������⡢�����μ��ʤ륢�������ʹ١ˤ�ż���������ʥߥå���ưŪ�ˤDz���Ū��¸��������äƤ��뤳�Ȥ����������Ǥ�������
http://ja.wikipedia.org/wiki/��������
http://www.linkclub.or.jp/~argrath/goa.html
�����������֥顼���顼����פȸƤФ�륤��ɤο��Ǥ��ꡢ���ܸ�ˡְ����פ�������Ƥ���褦�ˡְ��ߡפȴ�Ϣ�դ����Ƥ��뤳�ȤϹ����Τ��Ƥ��롣�����������ä���Ǻ���Ǥġʰ�����Ǻ¨����ˤȤ�����̱�ֿ��Ĥ��Ѷ�Ū�˻ٻ����롣�����ˤϡ������פ���ꤹ�뤢������Ū�פʰż���˭�����ݻ�����̩���Ȥδ�Ϣ������ΤǤ��롣
���ȥ�å������θ������Monstrance�ˤ�̩���ΰ����������⡢����Ū�ˤϡ���¡ס����ͥ����Ū���ۡˡס�����������פȤ������Ƕˤ�ƻ�����ΤǤ��롣�����ơ��������Ԥʤ�����ΰż��ⶦ�̤Ȥ������Ȥ�����롣�����⤳����������пʹ֤�����Ū�ռ���Ķ������������Ǥ���ֽ����פ�ž������Ǻ��־Ƥ��Ԥ����ơ���Ū�ʶ�Ǻ�����������Ȥ������Ǥ⤽�ε�ǽ�϶��̤��Ƥ���Ȥ������Ȥ������ΤǤ��롣
�����Ƥ����Ϥ�����������ɸ�ˤȤδ�Ϣ������졢���ߤǤ�����Ū�ʾ�ħ������������������ȡָ����פ���Ƥ��롣����� + ��+ ����������פȤ��������ϡ��ӡ�= ���μ�줿�ۡˤȤ�����������Ū�˿�Ĺ���뿢ʪ���֤��������⤢�ꡢ���ο��������˲ˤ��ʤ�������ϥڥ륷���ȥ륳�Υ����ڥåȡ�������ʤɤ����륤����ߥå��Ϥ���¾�Ρֺ����оΡפ�����Ū���ʤ���ˤ⸫�Ф���ѥ�����Ǥ��롣�����Ƥ����ϻ���������ˤλ��Ź�¤��ȯ�ꤷ�ƿ�Ĺ�����徺����ˤĤ졢�����뿢ʪŪ����Ĺ�ʲ��Υѥ������ľ��Ū��ɽ�ݤ������ʤǡ��췲�ο������롼�פ������Ƥ��롣
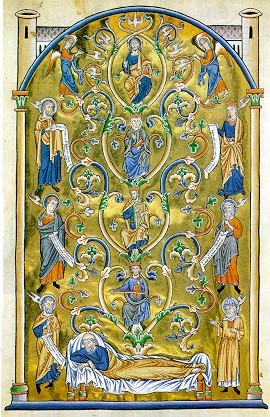 ��
��
�Ǹ�˸���Τϸ��¤������ˤ�����徺�ȡ������פ���Ǥ��롣���夽���Ϥ�긽�¤�Ÿ�����줿�ۤȤ�����ȤˤĤ��Ƥθ��ڤ���Ť��֤��Ƥ������Ȥˤʤ뤬�����ΤҤȤĤξ�ħŪ���㡢�����Ƥ��ΰ�̣�ˤĤ��ƾ�ħ���Ԥ������̵�ռ�Ū��ǧ�����Ƥ���Ȥ�������Ǥ��롣
 ��
��
�Ǥ��夲���������ȯ���Τ����ä����ڡ�������ȥ�֥����㡼�פξ��Ȱ������餹�륵����������饤�ʽ��Υ����졼�����Ρ��ġʺ��ˡ�Ʊ���пȤα������ԻΤ����Ȱ��Ǥ��ä����ᡢ̾������̱�Ȥʤä������ν�������ħ����ǡ�������Ȱ������ϡ��־徺���������������ζ̡פȤʤä��Τ��ä���
23:39:00 -
entee -
TrackBacks
2005-11-09
���ؤ������
����Ū�ʡ־�������ȡ��оΡ�symmetry����������ΡΣ���
ĺ���Ρ��ۡפȡ�̤���β����סʥ��쥹�ȡ�
 ��
�� ��
��
�� ���Ρ�����Υե��˥���
���Ρ�����κ����оο����ε����θŤ��ˤĤ��ƤϤ��Ǥ˽Ҥ٤��������餯�����ˤȤäƤ���˻���Ȥ�Ƥ֤٤����֤ΡֻϤޤ�פˤޤ��̤��ΤǤϤʤ����Ȥ����פ��Ƥ�������ΤҤȤĤǤ��롣�����Ǥϡ������餯�����Ρֵ�Ͽ���줿����פˤ����ơֺǸšפȻפ����оο����Τ����Ĥ�����ˡ����Ρ��濴Ū�����ǤǤ���ե��˥��뤽�Τ�Τξܺ٤����롣
���������ʤ���˸��Ф���������ʡ֥ե��˥���פ��������оΡ����̤��������Ǥ�ۤ��㳰�ʤ�ȼ�����ȡ��ޤ��ֶ���Ū���ǡפȤ��ƤΥե��˥���ˡ��ɤΤ褦���붵Ū�ʰ�̣����ä�ʪ�ʤ����夲��졢�������ʡפȤ��Ƶ�������Ƥ���Τ��Ȥ����ΤƹԤ���
��ϡ���¿�����뤳�ȡפǤϤʤ����Ȥ����Ƥˤʤ���������������ʡ������켫�Τ��̾����λ��äƤ�����ã�ϰʾ�Ρ��ۤȤ�����Ū�ȸ��äƤ��ɤ��褦�ʿ����Ϥ�ȯ�����뤫��Ǥ��롣�������äơ������ޤ��ɤ߿ʤ�Ǥ������������������ˡ�Ȥ��ơ���ǽ�ʸ¤ꤳ�������ֿ��Ǥ��Τ�Τ˸�餻��פȤ����Τ��¤ϸ����ʤΤǤ��롣
�ʥХ�������ʸ�������κ������ӡ˥ڥȥ�Ρ�ʯ��װ���
�ڥȥ�ϡִ仳�פΰա��ڥƥ��ʥԡ������ˤȸ츻��Ʊ�����ڥȥ���ԻԤ�¸�ߤ����Τϵ�����300ǯ��������⥭�ꥹ�ȶ���������˷�Ω���줿�ȹͤ����Ƥ��롣���ĺ���˿�����줿����ʡ��ۡפϡ������Ȥ������β��������Ĥ���ˤ�äƻ٤����Ƥ��ꡢ�ޤ��˥ȥ��ե����θ����Ȥʤ��Τ��Ȥ������Ȥ�ʬ���롣����ͥ���դ˺�����������Τ��֥��쥹�ȡפǤ��롣

���ɡ��ǥ���ʽ�ƻ����

���롦�����͡Υ��롦�ϥ��͡ϡ���ʪ�¡�
����ʥե��˥���Ǥ�����ۡפˤ���ʪ�����äƤ���ȹͤ����٥ɥ�����ˤ�äƽƤǼͷ⤵�줿���Ȥ�����ȸ����ʸ��ߤ��˲����줿�ޤޡˡ�ư���ϤȤ⤫���Ȥ��ơ���������Τ����ä��Τϼ¤˾�ħŪ�ʹ٤Ǥ��롣
�ӤȸƤӽ��魯���Ϥष�����ۡפ��ɤ������Ŭ�ڤʤΤǤϤʤ����Ȼפ��뤳�Ρ��աפθ���Ū�ʤΤ���������ʤ��뤤�Ϥ�������ˤΥե��˥���ȥ��쥹�Ȥ��Ȥ߹�碌�Ǥ��롣����ˤĤ��Ƥϡ���Ƭ�������Ͻ����оΤʹ��ޤȡ��濴�˿����դ����Ƥ��������۾��Υե��˥������ã���褦�Ȥ�����ĤΡ��ӡפȤ�����٤��ֲ����פ���ħ�Ǥ��롣���β����ʥ��쥹�ȡˤϡ��̾�β�����Ʊ�͡��濴�˶�Ť��ˤĤ�ƹ⤯�ʤ�ˤ�ؤ�餺�������ľ���ΤȤ��������䤵��Ƥ���Ȥ�����ˡ����ʷ�����Ȥ롣���줬�ֲ����פȸƤФ��ˤ�ؤ�餺�������ε�ǽ��̤����Ƥ��ʤ����Ȥ����餫�ǡ��Ȥ������Ȥ�����ΰ�̣���Ƥ������뤿��Ρ�����Ū��ǽ���������ʤ���ΤǤ��뤳�Ȥ⡢�ۤȤ���������Ԥ��ʤ�������ϥե��˥��������������פˤ�����̣�����뤫��Ǥ��롣
��Ϣ
�������������
��Υ��饹��
�� ��ͥ����Ū�����פȤ��Ƥκ���Ū�����ʡ�modern arts��
���Ǥ˥ȥ��ե�����ͥ���աˤ���˾�����ͥ���դ��ޤޤ��褦�ˡ��ե��˥��뼫�Τˤ�ޤ��������ʥե��˥��뤬�ޤޤ��Ȥ����ͤʰ��Ρ�����ҹ�¤�פ����뤳�ȤˤĤ��Ƥϴ�ñ�˸��ڤ�����������ˤĤ��Ƥ⤤���Ĥ��μ���Ƥ�������
ͥ���ռ��Τϥ�������Ȥ�������Ū���ۡʤ��뤤�ϳ�����ä��ӡˤ�����Ū�ʤ������������Ƥ��롣ͥ���դȥ�������ϡ��ۤ�Ʊ����ΤǤ���ȸ��äƤ��ɤ��ۤɻ�����¤����äƤ��롣�����˶��̤ʤ��ȤϤ��켫�Τ��֥ե��˥���פȤ����礭���������Ǥΰ�����ʤ��Ƥ��ʤ��顢���켫�Ȥ������ˤ����Ƭ�ȥե��˥���פȲ��Ǥ����������Ǥ�ޤॱ������¿���Ȥ������Ǥ��롣�Ĥޤꡢ�ۡʥ�������ˤκ������ۤ�����ü�ʥϥ�ɥ�ˤϴ������о�����Ĵ�������ǤȤ������Τ���°���Ƥ��ꡢ�ޤ��������̤Ǥ�;���Ѥ������ʤ��褦�ʤ���¿�ʰվ�����ĥϥ�ɥ�ˤϡ�¿���ξ�硢ǻ���ʡ���Ƭ���������������Ѥ��롣�����������ĺ���˰��֤����ۤγ��ΤĤޤߡʥΥ֡ˤϡ����Ф��в�ʪ�Τ��������Ϥ����ե��˥��뤬�դ��Ƥ���ΤǤ��롣�Ĥޤꡢ�ե��˥���Ȥ��ƤΥ������뤬�����ʥե��˥����ޤ�Ǥ���ΤǤ��롣
 ��
��
�����ե�μ��﹩˼��19������������Ȥ�����������(Sevre)
����19�����ե�Υڥ��Υ������롣Onyx�θƤФ�����դ�����¤˾褻��줿��Ρ�������⤽�켫�Τ��ե��˥�����Ǥ��ꡢ������˾����ʡ֥ե��˥���פȤ�����������Ȥ��뿢ʪ��̢�ʤĤ�ˤΤ褦�ʡ���Ƭ�����Υϥ�ɥ�ʤ⤷���������ˤ�ȼ���Ƥ��롣
�������뤿��˻Ȥ������������ο���˸���������Ū�ʥ����� (samovar)�ʤɤ⡢����������������Ū�ʸ�����ޤ��ۤ䳸����ä��ӤΥХꥨ�������ΤҤȤĤǤ���������˸���18-19����������줿��������Ȱ�äơ�������ϼ±פ˶�����ƻ��Ǥ��뤬������Ū�ˤ���¤ˤ����벼���Ͼ���������ľ�¤����륻�åȤ�����줿�������ȤΤ褦�˹ʤ��Ƥ��ꡢ�Ƥ�ʪ�ˤ�������ʬ�������Ĥ��Ǥ��롣�����Ƥ������ξ���������Ū�ʺ����оΤΥϥ�ɥ뤬�դ������Υϥ�ɥ�Υǥ�������Ƭ��ռ����Ƥ��롣�����������Τ˹����������ۡ��ӡˤ���ϡ��ޤ��ˤ�������ͥ���դΤ��������ķ��ȸ����٤���������Ȥɤ�Ƥ���ΤǤ��롣
 ��
��
�������ˤ��������ε����פ˷礫���ʤ������ƥࡢ�����롣������⡢�����μ�ü�ʥϥ�ɥ�ˤϡ���Ƭ������̾�Ĥ����뤬������������ϼ������������뤿�ᡢ���٤˥����ʥ��ˤϤʤäƤ��ʤ���
�庸��ŵ��Ū�ʥ����������Υ����롣�����о�������ħ�������������Ф��뤿��μظ����Ĥ��Ƥ���Τ�ʬ����ʤ�����ظ��μ�ü�ϥȥ�˥ƥ��魯�ָ��פΤ褦�ʻ��ؼ��ǥ�����ȤʤäƤ���ˡ����줬�ʤ���С�ͥ���աפ��Τ�ΤǤ��롣
�屦�������뿩���̤������ʤȤ��ƤΥ����롣���ĺ������ʬ�ϡ��ݥåȤ��ݲ����뤿��λ����Ĥ��Ƥ��ꡢ�ݥåȤ���ꤹ��ȹ⤯�ݥåȤ��न����ˤʤ롣�ݥåȤ��ܤ����뤳�Ȥ�������κ������ħ�ȸ��äƤ褤������Ū�ǤϤ��뤬�����ΰ��ͤʻ�����ˡ�ϡ���ħ����Ū�ˤϡ��礭�ʥե��˥���סʥ�����ˤξ�ˡ־����ʥե��˥���סʥݥåȡˤ��ܤ�������Ȥʤ롣
 ��
�� ��
��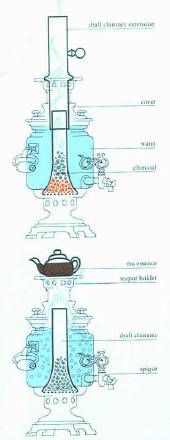
�庸��Ƽ���Υ����롣������ü�Ρ���Ƭ������̾�Ĥ������롣
������ۤȤ�ɥ������벽��������Ū�ʥ����롣����ǤϤ����餯�֤����ʨ�����פ��ȤϽ���ޤ���
�����ŵ����ˤʤ����Ρ�ú�Ф����Ѥ��Ƥ������Υ�����θ����������˲Ф����졢ͯ����������ϼظ����ͳ���ƥݥåȤء���������ä��ݥåȤ������ĺ���ء������ƽФƤ����Ϥ�����ݲ��ˡ��Ȥ������ˤ�Ƽ���Ū�Ǥ��ʤ���ɤ�����ƻ����Ū�Ǥ��ϣ��ѡ�Ū�Ǥ⤢�롢�뵷�����������δ֡פ�ƻ��
����
Samovars: Truly Cultural Symbols of the Rus
The Russians are Here! What's Samovar
23:23:00 -
entee -
TrackBacks
2005-10-29
���ؤ������
����Ū�ʡ־�������ȡ��оΡ�symmetry����������ΡΣ���
���ܤΡ֥ե��˥����

�� ���ܤΡ֥ե��˥����
�����Ƥ�ƻ�����ۤ������Ѥ�ȿ�ǤǤ��뤳�Ȥϴ��˽Ҥ٤����ޤ����줬�Dz�������Ǿ����˳ݤ��ơ��ϡ��塦�С��������פ�ɽ�����Ƥ���餷�����Ȥ�����Τ�줿���ȤǤ��롣�Dz��������ϡפ�ɽ�����Ȥ��������פ��ޤ����������ƤȸƤФ���ؤι⤤�����ƤΡִ��á���ʬ�ˤϡ��ֲ֡פȸƤФ�����������Ф�����礬���롣�Τ��˲����飲���ܤΡֿ�פ�����Ū�ˤ����Ƥ��˷礤����ΤǤ���ʤȸ�����ꡢ�ɤ����餬�����ܤʤΤ��������ƤǤ���ˤˤ��衢���ΡִȡפȸƤФ����ξ�ˤ���ֲСפ���ʬ�����Ƥε�ǽ��ʬ�����ʤ���ºݤ˥��������ʤɡֲСפ������ս�Ǥ���*���Ȥ��Ǥ�ޤǤ�ʤ������줬�ֲ��ޡפǤ��롣�����Ƥ��ξ�β����Ρָ���פ���������ʬ�������פȤʤ롣����ϡֱ����פ�ɽ���Ƥ������ʤ��ȤϤ�����ħ�Τ���վ�����������Ǥ��롣����ϡֱ��η����ڤ�ȴ�������Ϥ����ˤ�Τǡ����ۤ���Ҥʤɤ�ȼ�ä�������Ķ����Ū�ʱ��ס��缭�� �����Ǥ��ˤ���������뤤��������ݤʤɤǻȤ����������֤Ǥ��롣���줬�����פˤ�äƱ����������Ƥ��뤵�ޤǤ��롣���Ρֲ����פ���ʬ�������ƤǤϡֳޡפȸƤӡ�������ʬ����ϼ�פȸƤ֡�����ϡ��������ͤʤɱ����ΰվ��ѥ�������̤�����ʬ�����뤳�Ȥϸ�ƨ�����Ȥ��Ǥ��ʤ��������Ƥ��ξ�ˡֶ��פ����������ʡ�������פ������֤���롣��������ϡ����֡������ФʡפȸƤФ��ֻ��פ˺ܤ����Ƥ��뤳�Ȥ����롣
����
* ���ƤβФ�Ƥ٤���ޤ����̤��鸫��ȡֻ��Ĥη�פ��������Ƥ����Τ����ˤ�äƤϸ��Ф���롣�Ĥޤ�Ф��������Ȥ����ˤϡֻ��ĤβФζ̡סʻ������ˤ��⤫�Ӿ夬��Ȥ�������ˤʤäƤ���ΤǤ��롣���ޤ����̤��̾�Ф�Ƥ٤뤿��Υ��������ˤʤäƤ��롣���������̤��ֻ��ķ깽¤�פˤʤäƤ��ʤ���ΤǤ⡢���ΡֲСפκ����ˡ����פȡַ�פ�ɽ�������η꤬���줾�쳫�����Ƥ���ΤϤ�����Ū�Ǥ��롣�ҤȤĤϤۤܿ��߷��ǡ��⤦�ҤȤĤϻ�����η�Ǥ��롣�Ĥޤ������˾��ַ�פȡ����ס����ʤ���ֱ��ۡפ���ħ����Ƥ���ΤǤ��롣���������η꤫��������¾���η�뤳�Ȥ�����롣����ϡֿ�: eclipse�פ��������ۡ������Ƥ��ο��ˤĤ��ơ������Ρ�Ķ�˼�Ū���פˤĤ��Ƥϡ��Τ��˻��֤�ݤ��ƹͻ��뤳�Ȥ⤢��Ǥ�������
�����ƤκǾ����ˤ�������ʶ��ˡ������Ƥ��Τ������β�����פ碌�������ʤʤ���ϻ�ѷ��ˤγޤη����ϡ����Ҥη�Ωʪ�β����δ��ܹ�¤��Ʊ���Τ�ΤǤ��롣����ϲ�������ü��������ޤΡָ���פ�ķ�;夬�ä���������Ƭ�����ˤǤ��ꡢ����ķ�;夬�äƱ����Ƥ����ϼ�ξ��Ƭĺ���˵�����ʤ����餫��������Ϥ��������ʥե��˥�������ˤ���ĤȤ��������������Ф���롣
���Τβȶ櫓�Ƥ�����פ�٥åɤ˸�����֥��쥹�ȡפȡ֥ե��˥���פ��Ȥ߹�碌�Ȥΰ㤤�ϡ������Ƥ��о��̤��������̤Σ������ʤʤ���ʣ�������ˤ˻��ĤΤ��Ф������ΤΥ�ǥ���о��̤�����Ū�����̤��鸫��줿�Ȥ��Σ������ˤ��������ʤ��Ȥ������Ǥ��롣
�ޤ��������Ƥϸ���С�����Ū�ʡֻͶ��������ѡפ˻�����¤���㳰Ū�˻��äƤ���Ȥ������Ȥ�Ǥ��뤬��������������ɹ������������̤���Ω���ħ���Ƥ���褦�ˤ⸫�뤳�Ȥ�����롣���쥹�Ȥȥե��˥���Υѥ�����ϡ������Ƥˤ����Ƥϻ�����Ū�ʱ��Ԥ��ȹ��������äƤ���ΤǤ��롣
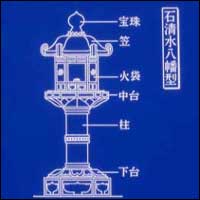 ��
��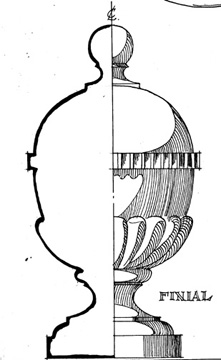
������̣�������Ȥˡ���Τ褦����Ӥ�Ԥ��ȡ������Ƥ��Τ�Τ����ΤȤ��ƤҤȤĤΡ֥ե��˥���פȤ��Ƹ�������롣�Ĥޤꡢ�緿�Υե��˥���ˡ�����פȤ��������Υե��˥��뤬�ޤޤ�뤳�Ȥ�ʬ���롣���������ΤΥե��˥�����оο�������ζ���Ū���å��Ȥ��Ƥ����Ǥʤ�������Ū����������ޤ��Τˤ⸫������롣�����ơ����Ρפ�ޤ��ΤȤ���ª����ȡ����Ū�緿���������ǤȤ��ƤΥե��˥���ˤϡ�����˾����Υե��˥����ޤ�����ҹ�¤�ˤʤäƤ��뤳�Ȥ�ʬ���롣����������¤�ϡ���ˡ֦��ķ��פȸƤ֤��Ȥˤʤ��Ϣ�ξ�ħŪ������ˡ§�ΰ�Ĥ���¤ˤʤ����ΤǤ��뤳�Ȥ�λ����������
�� �����Ȥ���������
�����Ƥȼһ�ʩ�դη�������������餫�Ǥ��뤬���һ�ʩ�շϤη���ʪ�β������ˤ�Ʊ�ͤ����Ǥ������롣����Ϥ���礭��Ʊ���������Ѥ���ˤ�侮���Υ�ǥ뤬������Ҿ��פ˴ޤޤ����Ǥ��롣�äˡֵ����פ�̾���ǿƤ��ޤ���褿������ü�����ü�ʴ�����ˤ����������˽स������Υѥ������Ф���롣�����Ƥ�Ϥ괤�ΰվ����Τ�Τ����ֱ��������ˡפ�ơ��ޤˤ�����ΤǤ��뤳�Ȥ�����̤Ǥ��롣
���餫�ʡֵ��δ�פο�������������Ū�Ǥ����ΤΡ���ˤϤ��δ������������Ρּ�����ʬ�פ�����䲰�桦�ȹ��ʸ���ˤ��֤�����륱�����⸫���롣
�㤨����Ƭ�ˤ�Ǥ������Ϥ�����ˤʤäƤ��������Ȥι���˻Ȥ��Ƥ���ֵ���ʵ������⤽����Ǥ��롣�����Τ褦�����̤δ�ϡֲȹ�פ��֤�����äƤ��롣���Ρ����ӡפȤ���̾����ޤ��ŵ��Ū�оο����ȤʤäƤ��롣�����ηפ餤�ˤ��Ƥ⡢���ӡפζ�ʸ������������ڥ������ڵ��Τ褦�˸����뤳�Ȥ϶�̣�������ޤ����ε����Ϥ��η��������Ƥ��μ�����ʬ�β���������Ƥ���ֱ����פΤ褦�ʱ�������褯��Ƽ�뤳�Ȥ��Ǥ��롣���ԡ��ϡֹ�ˡ���Ѥ�äƤ��Ϥ륹�ԥ�åȤ��Ѥ��ʤ��פȤ��롣�����ƥ����ƥ�å��ʥ�å������Ǥ��롣

������ʬ���ֲ���פ��֤�����ä��������������Ϥ������ʬ�η��������ܡ���ˤ���줬��ͭ���뤳�Ȥˤʤ�֦��ķ��פ������ˤ⸫�Ф���롣

ʿ��Ū�ʥ��վ��ε����Ǥ��뤬���Υ����ȥꥫ��ʵ���ɽ��ˤϡַ����פ��Ϥ����褦�ʡֱ����פα������Ф���롣�����̼��Τ�������ޤ�Ǥ���ѥ��������������̤��̤���ɽ��������оο����ϡ�����������Ƽ��˸���������ʤȤ��Ƥġˡפʤɤˤޤ��̤뤳�Ȥ��Ǥ��롣���̿������оΤε����ˤĤ��Ƥ����Ӹ��ڤ����Ǥ������������Ǥϡ�����Ω���ɹ��פ��뺸���ʱ��ۡˤ����Ϥ�����Ƭ������α��Ȥ���ɽ���졢���줬��Ĥο�Ū¸�ߤΡִ�פ���Ф��Τ��Ȥ������Ȥ���α��롣

���μ�����ʬ�����ǽФξ��ȡפȤ����ե��˥��빽¤��ΤäƤ��롣�����϶ˤ�����Ƥ˵����μ��դ�־��äơפ��롣���α������־��ȡפȤ���������帢������֥��쥹�ȡפ�����̤����Ƥ��롣

�̾�ε���ɽ�������������Ʊ�ͤι����ˤʤäƤ��뤬��������ʬ��ñ�ʤ���ΤǤ��ꡢ���ε��Τ�������褦�ʷ����ˤʤäƤ��롣�������ֱ����פϤ����ޤǤ⺸���оΤˤ��ε��Τ����롣

���쥹�ȡʥڥ�����Ω�����ˤȥե��˥���ʻ�帢�ˤλ��ΰ�Ȥε������оΤ˥ڥ��������ֱ����פϤ�����ֻ�ҡסʹ����ˤ�פ碌������ˤ�ʤäƤ���Τ����ܤ��٤��Ǥ��롣

�ۤȤ�ɵ����Ȥ��Ƥθ�����α��ʤ��ۤɤ˼�ͳ�˥ǥե���ᤵ�줿�����������о����ϴ����ˤʤäƤ����ΤΡ�����Ƭĺ��ʬ�˻��̰��Τ�ɽ�����룳�Ĥα߷����͵�ʪ����Ω�ġ�
�ʾ�Τ褦�ˡ����ܤ������Ƥ˱����������סʵ�����ˤ��ϼ�ʱ�����Ƭ�ˤ��Ȥ߹�碌�˸����о������ֵ������Ȥ˸�����ֲ��桦�ȹ�פʤɤΡֻ�帢Ū��ħ�ȱ������Ȥ߹�碌�˸����о����ϡ����餫�Ǥ��ꡢ��������Τ��������ݤˤ�����֥ե��˥���פȡ֥��쥹�ȡפ��Ȥ߹�碌�˸����о�����Ʊ����Τ�ɽ���Ƥ���ΤǤ��롣
���ۡ�������Ϣblog
��������ʸ�������ϼ�ŵ��
18:38:00 -
entee -
TrackBacks
2005-10-26
���ؤ������
����Ū�ʡ־�������ȡ��оΡ�symmetry����������ΡΣ���
��Ƭ�ȥե��˥���
�� ��Ƭ�ȥե��˥���
��帢���äƶ��褹�뺸���оΤ��ķ�Ū�ѥ��������Ť�é�äƹԤ��ȡ���������ޤη���ʪ�˹Ԥ������롣�����оΤΡ���Ƭ�סʤ��뤤�ϡֱ��פ��̢�סˤ�����˿���������ա��ۡפΥѥ�����Ǥ��롣��������̤������Ǥ��ͤ�Ļ�ä������������ȡפ��֤�����ä������Τ�Τǡ��������ã���褦�Ȥ������Ƥ�Ʊ���Ǥ��롣�����Ȥ߹�碌�Υѥ������̵����������������θ�����פ�������ǤϤʤ������Ƥ�ޤ�ۤȤ��������Τɤ��ϰ�ˤ⸫�Ф���롣���ܤ˱�����һ�ʩ�դδ�����������������˸��ڤ������ˤ���夲�������Ƥˤ⸫�Ф��롣�������������Ǥ����ܤΡ���Ƭ���աס���Ƭ������פ�ޤ��оο����˴ؤ��Ƥϸ�Ⱦ�Ǽ��夲�뤳�Ȥˤʤ�����
�������������оΤι��ޤϤ������Τ˸��Ф���롣
 ��
��
�ʾ�ˡ֥����ɥե��������������å��פȸƤФ���ؤι⤤����һ��ס��������줬��ħŪ�����֤ȡֻ��֤ν����פδ�Ϣ��ǻ���˸����롣�ʲ��˥����˥��롦�٥åɤȸƤФ��ե��˥����դ��٥åɡ���̲���Ƭ��˥ե��˥��뤬���Ӥ���ΤǤ��롣

���Τβȶ������פ˱����Ƥ⤽���оι��ޤ��������ˤ˽и����롣�����ʥǥ�����Ǥϴ�ά���⤷���ϴ����˼����Ƥ��뤳�Ȥ�¿���Τǡ�������������Ƭ�ȥե��˥���פ����Ǥϸ��Ф����Ȥ�����������äȸŤ�����ƥ��å��ʤɤ��ǧ����ȡ�������Ǥ⸫�Ф����ȤΤǤ����ΤǤ��롣�����Ƹ���ΰ��פϤ��κ��פ������ĤĤ����Τ�¿�����ޤ����Τ�����¿���������ˤ�äƺƸ����줿��Τ���
���������������ȶ�ˤ����ơ����η����Ͽ���ã�������ˤ�äƼ����Ѥ��줿�䤨����ħ�Ȥ������Τ˳�ǧ�Ǥ���ΤǤ��롣�������ħ�ΰ�̣�ͤ�λ�Ƥ������ɤ���������оݤˤĤ��Ƽ���Ū�Ǥ��ä����ɤ�����������ʤΤǤ��롣������������ä��褿�վ�����¤ˤʤ���Ȥ������Ȥˤ�ä��������������Ū����Ȥ�����Τ���������¸�ߤ���Ȥ������Ȥǽ�ʬ�Ǥ��롣����Ϥ��٤Ƥ������μ����Ԥ�������ʬ�����ΰ��äƤ������ƤˤĤ��ơ��ȤˤĤ�����ˡ�ʾ�ο�������Ƥ��뤫�ɤ�����������Ǥ���Τ�Ʊ�ͤΤ��ȤǤ��롣
���Υ������˱�����finial����������Ƭ�����˥��ʥ�������Ǥ��롣�֥���ǥ�: Sundae*�������ߤ�Ʀ�ˤˤ����������Τ褦�Ǥ���פȤ��롣�Ĥޤꡢ���Υ������ȤϤޤ��ˤ��ۻҤˤ��ȥ��ե�����¤�ˤʤäƤ���ΤǤ��롣����ϥ�������祳�졼�ȥ����������κ��Ф�����ĺ����֤�����֤��֥�����פˤ�äƴ������롣
* ��Ū�ˤ���Sunday����Ʊ����
���������ʪ�Τ˰�������ޤ��������Ȥ�����ʬ�ϡ���Ƭ����������Ū�Ǥ��ꡢ�����ȶ�������Ǥ���ϡ�crest�פȸƤФ�롣����������Ρ�ʪ�Ρפϥե��˥���(finial) �ȸƤФ�롣�ե��˥���ϡ��ȶ�����Ǥʤ�������ס��ޥ�ȥ�ԡ��������ۡ����ڤʤ��羮���ޤ��ޤ��������ͤΰ����Ϻ�ʪ����о줹�롣�ޤ���Finial*�ϡ��Ѹ�Ρ�finish, final�פ�Ʊ���츻����ġ�Fin��ʩ�ˡ�Finito�ʰˡˤϡֽ����פΰ�̣����ġ��Ĥޤꡢ�濴��������Ƭ�ϡֽ������פؤκǸ�Ρ�ľ���Ρ˰���������Ƥ���ΤǤ��롣�ȶ����ۤ˱����뤳�Ρ֥ե��˥���פ����ϡ���������Ρֻž夲�פ��̣���Ƥ���ΤǤ��äơ����٤Ƥι������Ƥ��褤����ʤδ����Ȥ������ˡ����κ��ʤ�����˿����դ�����ΤǤ��롣
�������ʾ�Τ褦�ʡָ���Ū�פ������ϡ����Υ��֥������ȼ��Τ����������̡�̵�ռ���ˤˤۤȤ��ľ٣���ʤ����������褦�Ȥ��Ƥ������ƤȤΤ���������̯�ʰ��פ��ʤ���⡢���⤽�⤽�줬�ֲ��λž夲�ʤΤ��פȤ����־�ħ������Ρ��Τ��ܼ������Ƥ����餫�ˤ��ʤ��������������⤽��ȶ�ʤȤ�櫓�ֻ��ססˤȤ��ä�ƻ���Τˡִ�λ�פ�ֽ����פ��̣�����Τ��ַǤ�������ͳ�פϡ����Υ��֥������Ȱʳ��˵�����ΤǤ���ʤ��ޤ�˼����ʤ��ȤǤ��뤬�ˡ����ʤ�����־�ħ�����Ρפϡ��־�ħ������Ρפ��뤤�ϡ־�ħ����������פ�ؤ�������¾�ʤ�ʤ��������Ƥ�����ñ�ʤ륪���ʥ��ȡ������ʡ˰ʾ�ΰ�̣����ĤΤǤ��ꡢ�ֻؤ���������ΡפȤ����Τ��Ǥ��Ƴ��ߤ���Ȥ������ȤʤΤ���
* ���ˤ�äƤϥ����å�(crop)�ȸƤФ�롣�ֺ�ʪ�סּ���ʪ�פΰ�̣�Ǥ��롣���Υե��˥��뤬�ѥ��ʥåץ�䤽��¾�β�ʪ���֤�����뤳�ȤΤǤ�����ͳ�������ΰ�̣�ֻ�帢�פ��鲱¬���뤳�Ȥ��Ǥ��롣


�ȶ����ץ������ɤ��դ���ե��˥���ʺ��ˡ�����ʪ�˻Ȥ���ե��˥���ʱ���
 |
|
�ѥ��ʥåץ�˻Ѥ��Ѥ����ե��˥��롣�֥����åס�����ʪ�פ�̾�Ǥ�ƤФ��ե��˥��롣�����������饤�ʽ����㡼�륹�ȥ�˱����른�硼�����亮��ȥ��ľ���ᤴ�����Ȥ���ʪ�ۤˤʤäƤ��롣���βȤβȶ�ΤۤȤ�ɤ˥ѥ��ʥåץ���Υե��˥��뤬�դ��Ƥ��롣��������Υ����ɤ˰�̣��Ҥͤ�ȡ���Pineapple means hospitality.�סʥѥ��ʥåץ������Ƥʤ��ΰ�̣�ˡפǤ��ä���
��Ⱦ�Ǥϥե��˥���ΥХꥢ��ȡ����������ܤˤ����뤽������ʪ�Ƥ������Ȥˤ��롣����ϡ�������˸��Ф���롢��ˤ���줬�㦸�ķ���ȸƤ֤��Ȥˤʤ���������ؤȤĤʤ��äƤ����ΤǤ��롣
��帢���äƶ��褹�뺸���оΤ��ķ�Ū�ѥ��������Ť�é�äƹԤ��ȡ���������ޤη���ʪ�˹Ԥ������롣�����оΤΡ���Ƭ�סʤ��뤤�ϡֱ��פ��̢�סˤ�����˿���������ա��ۡפΥѥ�����Ǥ��롣��������̤������Ǥ��ͤ�Ļ�ä������������ȡפ��֤�����ä������Τ�Τǡ��������ã���褦�Ȥ������Ƥ�Ʊ���Ǥ��롣�����Ȥ߹�碌�Υѥ������̵����������������θ�����פ�������ǤϤʤ������Ƥ�ޤ�ۤȤ��������Τɤ��ϰ�ˤ⸫�Ф���롣���ܤ˱�����һ�ʩ�դδ�����������������˸��ڤ������ˤ���夲�������Ƥˤ⸫�Ф��롣�������������Ǥ����ܤΡ���Ƭ���աס���Ƭ������פ�ޤ��оο����˴ؤ��Ƥϸ�Ⱦ�Ǽ��夲�뤳�Ȥˤʤ�����
�������������оΤι��ޤϤ������Τ˸��Ф���롣
 ��
��
�ʾ�ˡ֥����ɥե��������������å��פȸƤФ���ؤι⤤����һ��ס��������줬��ħŪ�����֤ȡֻ��֤ν����פδ�Ϣ��ǻ���˸����롣�ʲ��˥����˥��롦�٥åɤȸƤФ��ե��˥����դ��٥åɡ���̲���Ƭ��˥ե��˥��뤬���Ӥ���ΤǤ��롣

���Τβȶ������פ˱����Ƥ⤽���оι��ޤ��������ˤ˽и����롣�����ʥǥ�����Ǥϴ�ά���⤷���ϴ����˼����Ƥ��뤳�Ȥ�¿���Τǡ�������������Ƭ�ȥե��˥���פ����Ǥϸ��Ф����Ȥ�����������äȸŤ�����ƥ��å��ʤɤ��ǧ����ȡ�������Ǥ⸫�Ф����ȤΤǤ����ΤǤ��롣�����Ƹ���ΰ��פϤ��κ��פ������ĤĤ����Τ�¿�����ޤ����Τ�����¿���������ˤ�äƺƸ����줿��Τ���
���������������ȶ�ˤ����ơ����η����Ͽ���ã�������ˤ�äƼ����Ѥ��줿�䤨����ħ�Ȥ������Τ˳�ǧ�Ǥ���ΤǤ��롣�������ħ�ΰ�̣�ͤ�λ�Ƥ������ɤ���������оݤˤĤ��Ƽ���Ū�Ǥ��ä����ɤ�����������ʤΤǤ��롣������������ä��褿�վ�����¤ˤʤ���Ȥ������Ȥˤ�ä��������������Ū����Ȥ�����Τ���������¸�ߤ���Ȥ������Ȥǽ�ʬ�Ǥ��롣����Ϥ��٤Ƥ������μ����Ԥ�������ʬ�����ΰ��äƤ������ƤˤĤ��ơ��ȤˤĤ�����ˡ�ʾ�ο�������Ƥ��뤫�ɤ�����������Ǥ���Τ�Ʊ�ͤΤ��ȤǤ��롣
���Υ������˱�����finial����������Ƭ�����˥��ʥ�������Ǥ��롣�֥���ǥ�: Sundae*�������ߤ�Ʀ�ˤˤ����������Τ褦�Ǥ���פȤ��롣�Ĥޤꡢ���Υ������ȤϤޤ��ˤ��ۻҤˤ��ȥ��ե�����¤�ˤʤäƤ���ΤǤ��롣����ϥ�������祳�졼�ȥ����������κ��Ф�����ĺ����֤�����֤��֥�����פˤ�äƴ������롣

* ��Ū�ˤ���Sunday����Ʊ����
���������ʪ�Τ˰�������ޤ��������Ȥ�����ʬ�ϡ���Ƭ����������Ū�Ǥ��ꡢ�����ȶ�������Ǥ���ϡ�crest�פȸƤФ�롣����������Ρ�ʪ�Ρפϥե��˥���(finial) �ȸƤФ�롣�ե��˥���ϡ��ȶ�����Ǥʤ�������ס��ޥ�ȥ�ԡ��������ۡ����ڤʤ��羮���ޤ��ޤ��������ͤΰ����Ϻ�ʪ����о줹�롣�ޤ���Finial*�ϡ��Ѹ�Ρ�finish, final�פ�Ʊ���츻����ġ�Fin��ʩ�ˡ�Finito�ʰˡˤϡֽ����פΰ�̣����ġ��Ĥޤꡢ�濴��������Ƭ�ϡֽ������פؤκǸ�Ρ�ľ���Ρ˰���������Ƥ���ΤǤ��롣�ȶ����ۤ˱����뤳�Ρ֥ե��˥���פ����ϡ���������Ρֻž夲�פ��̣���Ƥ���ΤǤ��äơ����٤Ƥι������Ƥ��褤����ʤδ����Ȥ������ˡ����κ��ʤ�����˿����դ�����ΤǤ��롣
�������ʾ�Τ褦�ʡָ���Ū�פ������ϡ����Υ��֥������ȼ��Τ����������̡�̵�ռ���ˤˤۤȤ��ľ٣���ʤ����������褦�Ȥ��Ƥ������ƤȤΤ���������̯�ʰ��פ��ʤ���⡢���⤽�⤽�줬�ֲ��λž夲�ʤΤ��פȤ����־�ħ������Ρ��Τ��ܼ������Ƥ����餫�ˤ��ʤ��������������⤽��ȶ�ʤȤ�櫓�ֻ��ססˤȤ��ä�ƻ���Τˡִ�λ�פ�ֽ����פ��̣�����Τ��ַǤ�������ͳ�פϡ����Υ��֥������Ȱʳ��˵�����ΤǤ���ʤ��ޤ�˼����ʤ��ȤǤ��뤬�ˡ����ʤ�����־�ħ�����Ρפϡ��־�ħ������Ρפ��뤤�ϡ־�ħ����������פ�ؤ�������¾�ʤ�ʤ��������Ƥ�����ñ�ʤ륪���ʥ��ȡ������ʡ˰ʾ�ΰ�̣����ĤΤǤ��ꡢ�ֻؤ���������ΡפȤ����Τ��Ǥ��Ƴ��ߤ���Ȥ������ȤʤΤ���
* ���ˤ�äƤϥ����å�(crop)�ȸƤФ�롣�ֺ�ʪ�סּ���ʪ�פΰ�̣�Ǥ��롣���Υե��˥��뤬�ѥ��ʥåץ�䤽��¾�β�ʪ���֤�����뤳�ȤΤǤ�����ͳ�������ΰ�̣�ֻ�帢�פ��鲱¬���뤳�Ȥ��Ǥ��롣


�ȶ����ץ������ɤ��դ���ե��˥���ʺ��ˡ�����ʪ�˻Ȥ���ե��˥���ʱ���
 |
|
�ѥ��ʥåץ�˻Ѥ��Ѥ����ե��˥��롣�֥����åס�����ʪ�פ�̾�Ǥ�ƤФ��ե��˥��롣�����������饤�ʽ����㡼�륹�ȥ�˱����른�硼�����亮��ȥ��ľ���ᤴ�����Ȥ���ʪ�ۤˤʤäƤ��롣���βȤβȶ�ΤۤȤ�ɤ˥ѥ��ʥåץ���Υե��˥��뤬�դ��Ƥ��롣��������Υ����ɤ˰�̣��Ҥͤ�ȡ���Pineapple means hospitality.�סʥѥ��ʥåץ������Ƥʤ��ΰ�̣�ˡפǤ��ä���
��Ⱦ�Ǥϥե��˥���ΥХꥢ��ȡ����������ܤˤ����뤽������ʪ�Ƥ������Ȥˤ��롣����ϡ�������˸��Ф���롢��ˤ���줬�㦸�ķ���ȸƤ֤��Ȥˤʤ���������ؤȤĤʤ��äƤ����ΤǤ��롣
23:39:00 -
entee -
TrackBacks
2005-10-25
���ؤ������
����Ū�ʡ־�������ȡ��оΡ�symmetry����������ΡΣ���
�� �ʹ֤ο��������˱������о���
�Ĥ��躢���ּ������˴����ʤ��оο��Ϥʤ��פȤ���̾����ʹ�������Ĥޤ깭���������ˤ����ơ����оΡפȤ����վ������Ͱ�Ū�������Ū�ʤ�ΤǤ��ꡢ���ʤ������Ū�ˡִ�ǰŪ�פʤ�ΤǤ��ꡢ�������ܤˤ�ˤ�ƶ�������ѥ��Ȥ���ä�Ω���������롣���������ֶ����פ���ä��������뵷�������뤿��λ��Ū��ˡ�Ȥ��ƺ��Ѥ���ʤ��Ϥ���ʤ����ʹֳ��ˤ������оο���������Ȥϡ������̣ɬ��Ū�ʷ�̤Ǥ��ä��Ȥ��������٤��Ǥ����������ۤΤ褦�ʵ��絬�ϤΤ�ΤǤϥ���ɤΥ������ޥϡ��롢����ܥǥ����Υ������åȤʤɤ�ͭ̾�Ǥ��ꡢ����餬������̥λ�������ο���ϡ��ޤ��ǽ�ˤ��κ����оΤι����ʤ��뤤��ñ���оΤǤ���Ȥ������ϡ����о����פ�Ĵ����վ��ˤˤ���ȸ��äƤ����Ǥʤ��ۤɤǤ��롣
�� Ʈ��Ⱦ��Ԥγ���ʪ
������θ������ˤ�ͥ���դ�ȥ��ե������դ�ʪ�Ǥ��뤬��ͥ�����åפ��ʤ����աפ⤷���Ϥ���˽स����ˤʤäƤ���Τ����ȥ��ե������ɤ����Ƥ��Τ褦�ʡ��աפ��줬�٤�����⤷���Ϥ���˽स����ˤʤäƤ���Τ����Ȥ������ȤˤĤ��ơ�����Ū�ˤ��Ρ��䤤�פ˽в��Ȥ�������פ˽в��Ȥ�ۤȤ�ɤʤ��������Ρֻ�帢�פ�ᤰ��Ʈ��ˤ����ơ��ǽ�Ū���ƼԤ��������٤���Τ�����: �����Ť�, �շ�פǤ��뤳�Ȥϡ���������������Ȥ��Ƽ���α����Ƥ��뤳�ȼ��Τ�����ɮ���٤����ȤǤ��롣���������ε�����õ�뤳�ȤϤ���˶�̣������ȤȤʤ���������Ȥ˵����Ϥʤ���
�פ���ˡ��ȥ��ե����ϡ�ͥ���աפǤ��롣������֥���������ɡץ����פΥȥ��ե����ϡ�ͥ���դĤ���ǻ٤���Ȥ�����������ɽ������ΤǤ��롣
���λ�帢����Ʈ��ϡ�����Ū�ˡֺ����оΤ����̤���դ��Ĥ����פˤ�ä�ɽ������롣�Ȥ�櫓����������̤��룲�ͤΤҤȡ��⤷�������̤��룲Ƭ��Ļ���ˤ�äƾ�ħ������Ƥ���������ϰ������㳰������ƤϤۤȤ�ɾ�硢Ʊ���ʹ֡�Ʊ��Ļ�ä����̤�������ˤ�äơ�������¿���ξ�硢��������ɽŪ���Ԥ��������餽�줾���о줷����帢���ħ����㤢��ʪ�ʡ�ˡ֤ɤ��餬�����ã�Ǥ��뤫�פ����̤���������ΤǤ��롣�Ĥޤꡢ�ֺ����оΤ����֤������Ωʪ�ʥڥ��ˡפ˲ä��Ƥ�������ˤ��Ӥ���ֻ�帢�פ��ħ�����Ρʥ���ˤȤ����Ȥ߹�碌���о줹�롣���������оο����������λ���ˡ������ƿ���Τ��������˸��Ф���뤬�������Ϥۤ�Ʊ�ͤΡ�����Ū�������ã���뤳�Ȥ�����˰տޤ��Ƥ�����
�����õ�����ʤΤ��⤷��ʤ��������ޤΤȤ������������ֻ�帢����Ʈ�褪��ӳ���ʪ�פȤ����������оݿ����ˤĤ���������줿���Ҥˤ��ܤ˳ݤ��ä����ȤϤʤ���
���ܤˤ����Ƥ���������餽�줾�����ɽŪ��Τ�����ʤ��뤤�ϡֹ���*�פ�ʬ����ˡ������Ϥ���äƾ�������Ȥ���Ʈ����ķ�Ū�ѥ������Ф�����Τ����Ф����롣�����Ƥ�������ϡ���ɶ�פȸƤФ��ֱ���Ϥθ³����Ƕ��ڤ�줿�������פǷ��깭������**�����Ρ������פ��ƼԤ���ꤹ�뤿���Ĺ���ץ������Ͼܺ٤˵��鲽����Ƥ��ꡢ�����������ܷ⤹�����Ф⡢����п��ʤ��뤤�Ͽ��ʤ���ĤȤ���벦�ˤθ����ǹԤʤ�����Ǽ�ε����Ǥ��뤳�ȤϹ����Τ�줿�Ȥ����Ǥ��롣�����ʩ�����ƻ�������Ȥ������ϡ����ε����ι������ǤϤष������Ϥä��褿ƻ���ˤ������ε�����������***�������Τ��Ȥʤ��顢���ܤο�ƻ����Ⱥ��¤��Ƥ��뤳�Ȥ����ꤹ�٤���ʤ��������Фˤϡ��ڲ��ڶ��פ����Ƥʸ��ǡ�����ӡ������פˤ�äƾ�ħ�����ֱ��ۡפ����Ǥ����Ƥ˸������������Ʊ�������ֱ��۸ԡפ������Ѥ�ǻ����ȿ�Ǥ���Ƥ��롣
* ���Фˤ����ơ��֡ʹȡˤϡ���˼�פβ���������γѡʼ���ζ��ˡ���ϡ���˼�פβ���������γѡ���פζ��ˤǤ��롣
** �ޤ������ƹ�Ǹ��Ф�����Ʈ�ʥܥ����ˤϡ������פ�ɽ���������Ρ֥�פ����ꤵ�졢���λͶ�����������red corner / blue corner�ˤ�����Τ����졢�����λ�帢�η���롣�ƼԤ����������Τϡ֥����ԥ���٥�ȡפȤ����ֻ���Ū����סʡ���˻���ˤǤ��롣�����ᥭ�ꥹ�ȶ��Ϥ��������ϡ��ߤ����������̤�ɽ���ͳѷ��˿Ƥ��ߤ����롣��All corners of the world�פȸ����С����������š������פȤ����˥奢��ɽ������From the four corners of the world�פϡ��������ζ�������פȤʤ롣���Τ褦�˸��դ����ܥ������ͼ�����⡢�����ˡֶ��פ�����Ȥ����ۤȤ��̵�ռ�������Ū�����Ѥ�ȿ�Ǥ����Ф���롣
*** ���Τ���ɽŪ�������붵�ȡ֡ʻ���Ū��ϣ��ѡפ������Ȥδط���̩���ȡ�ƻ����Ū�����Ȥδط��ˤϤ�����ʿ�Դط������롣���������Ǥϥơ��ޤ�ñ�㲽���뤿��˾ܽҤϤ��ʤ����Ȥꤢ�����������ǤϤ��줾����������ˡ�����ζ��٤�ȯã���������ݽѤ佡���������˼��������Ƥ��뤳�Ȥˤ��ԻĤϤʤ��Ȥ������Ȥ������ǤäƤ�������


�Ĥ��躢���ּ������˴����ʤ��оο��Ϥʤ��פȤ���̾����ʹ�������Ĥޤ깭���������ˤ����ơ����оΡפȤ����վ������Ͱ�Ū�������Ū�ʤ�ΤǤ��ꡢ���ʤ������Ū�ˡִ�ǰŪ�פʤ�ΤǤ��ꡢ�������ܤˤ�ˤ�ƶ�������ѥ��Ȥ���ä�Ω���������롣���������ֶ����פ���ä��������뵷�������뤿��λ��Ū��ˡ�Ȥ��ƺ��Ѥ���ʤ��Ϥ���ʤ����ʹֳ��ˤ������оο���������Ȥϡ������̣ɬ��Ū�ʷ�̤Ǥ��ä��Ȥ��������٤��Ǥ����������ۤΤ褦�ʵ��絬�ϤΤ�ΤǤϥ���ɤΥ������ޥϡ��롢����ܥǥ����Υ������åȤʤɤ�ͭ̾�Ǥ��ꡢ����餬������̥λ�������ο���ϡ��ޤ��ǽ�ˤ��κ����оΤι����ʤ��뤤��ñ���оΤǤ���Ȥ������ϡ����о����פ�Ĵ����վ��ˤˤ���ȸ��äƤ����Ǥʤ��ۤɤǤ��롣
�� Ʈ��Ⱦ��Ԥγ���ʪ
������θ������ˤ�ͥ���դ�ȥ��ե������դ�ʪ�Ǥ��뤬��ͥ�����åפ��ʤ����աפ⤷���Ϥ���˽स����ˤʤäƤ���Τ����ȥ��ե������ɤ����Ƥ��Τ褦�ʡ��աפ��줬�٤�����⤷���Ϥ���˽स����ˤʤäƤ���Τ����Ȥ������ȤˤĤ��ơ�����Ū�ˤ��Ρ��䤤�פ˽в��Ȥ�������פ˽в��Ȥ�ۤȤ�ɤʤ��������Ρֻ�帢�פ�ᤰ��Ʈ��ˤ����ơ��ǽ�Ū���ƼԤ��������٤���Τ�����: �����Ť�, �շ�פǤ��뤳�Ȥϡ���������������Ȥ��Ƽ���α����Ƥ��뤳�ȼ��Τ�����ɮ���٤����ȤǤ��롣���������ε�����õ�뤳�ȤϤ���˶�̣������ȤȤʤ���������Ȥ˵����Ϥʤ���
 ��
��
�פ���ˡ��ȥ��ե����ϡ�ͥ���աפǤ��롣������֥���������ɡץ����פΥȥ��ե����ϡ�ͥ���դĤ���ǻ٤���Ȥ�����������ɽ������ΤǤ��롣
���λ�帢����Ʈ��ϡ�����Ū�ˡֺ����оΤ����̤���դ��Ĥ����פˤ�ä�ɽ������롣�Ȥ�櫓����������̤��룲�ͤΤҤȡ��⤷�������̤��룲Ƭ��Ļ���ˤ�äƾ�ħ������Ƥ���������ϰ������㳰������ƤϤۤȤ�ɾ�硢Ʊ���ʹ֡�Ʊ��Ļ�ä����̤�������ˤ�äơ�������¿���ξ�硢��������ɽŪ���Ԥ��������餽�줾���о줷����帢���ħ����㤢��ʪ�ʡ�ˡ֤ɤ��餬�����ã�Ǥ��뤫�פ����̤���������ΤǤ��롣�Ĥޤꡢ�ֺ����оΤ����֤������Ωʪ�ʥڥ��ˡפ˲ä��Ƥ�������ˤ��Ӥ���ֻ�帢�פ��ħ�����Ρʥ���ˤȤ����Ȥ߹�碌���о줹�롣���������оο����������λ���ˡ������ƿ���Τ��������˸��Ф���뤬�������Ϥۤ�Ʊ�ͤΡ�����Ū�������ã���뤳�Ȥ�����˰տޤ��Ƥ�����
 ��
�� ��
�� ��
��
�����õ�����ʤΤ��⤷��ʤ��������ޤΤȤ������������ֻ�帢����Ʈ�褪��ӳ���ʪ�פȤ����������оݿ����ˤĤ���������줿���Ҥˤ��ܤ˳ݤ��ä����ȤϤʤ���
���ܤˤ����Ƥ���������餽�줾�����ɽŪ��Τ�����ʤ��뤤�ϡֹ���*�פ�ʬ����ˡ������Ϥ���äƾ�������Ȥ���Ʈ����ķ�Ū�ѥ������Ф�����Τ����Ф����롣�����Ƥ�������ϡ���ɶ�פȸƤФ��ֱ���Ϥθ³����Ƕ��ڤ�줿�������פǷ��깭������**�����Ρ������פ��ƼԤ���ꤹ�뤿���Ĺ���ץ������Ͼܺ٤˵��鲽����Ƥ��ꡢ�����������ܷ⤹�����Ф⡢����п��ʤ��뤤�Ͽ��ʤ���ĤȤ���벦�ˤθ����ǹԤʤ�����Ǽ�ε����Ǥ��뤳�ȤϹ����Τ�줿�Ȥ����Ǥ��롣�����ʩ�����ƻ�������Ȥ������ϡ����ε����ι������ǤϤष������Ϥä��褿ƻ���ˤ������ε�����������***�������Τ��Ȥʤ��顢���ܤο�ƻ����Ⱥ��¤��Ƥ��뤳�Ȥ����ꤹ�٤���ʤ��������Фˤϡ��ڲ��ڶ��פ����Ƥʸ��ǡ�����ӡ������פˤ�äƾ�ħ�����ֱ��ۡפ����Ǥ����Ƥ˸������������Ʊ�������ֱ��۸ԡפ������Ѥ�ǻ����ȿ�Ǥ���Ƥ��롣

* ���Фˤ����ơ��֡ʹȡˤϡ���˼�פβ���������γѡʼ���ζ��ˡ���ϡ���˼�פβ���������γѡ���פζ��ˤǤ��롣
** �ޤ������ƹ�Ǹ��Ф�����Ʈ�ʥܥ����ˤϡ������פ�ɽ���������Ρ֥�פ����ꤵ�졢���λͶ�����������red corner / blue corner�ˤ�����Τ����졢�����λ�帢�η���롣�ƼԤ����������Τϡ֥����ԥ���٥�ȡפȤ����ֻ���Ū����סʡ���˻���ˤǤ��롣�����ᥭ�ꥹ�ȶ��Ϥ��������ϡ��ߤ����������̤�ɽ���ͳѷ��˿Ƥ��ߤ����롣��All corners of the world�פȸ����С����������š������פȤ����˥奢��ɽ������From the four corners of the world�פϡ��������ζ�������פȤʤ롣���Τ褦�˸��դ����ܥ������ͼ�����⡢�����ˡֶ��פ�����Ȥ����ۤȤ��̵�ռ�������Ū�����Ѥ�ȿ�Ǥ����Ф���롣
*** ���Τ���ɽŪ�������붵�ȡ֡ʻ���Ū��ϣ��ѡפ������Ȥδط���̩���ȡ�ƻ����Ū�����Ȥδط��ˤϤ�����ʿ�Դط������롣���������Ǥϥơ��ޤ�ñ�㲽���뤿��˾ܽҤϤ��ʤ����Ȥꤢ�����������ǤϤ��줾����������ˡ�����ζ��٤�ȯã���������ݽѤ佡���������˼��������Ƥ��뤳�Ȥˤ��ԻĤϤʤ��Ȥ������Ȥ������ǤäƤ�������
02:39:00 -
entee -
TrackBacks
2005-10-17
���ؤ������
����Ū�ʡ־�������ȡ��������������
����äȵ����ᤤ�Ȼפ����⤤��ä�������������������ɤ�Ǥ��ΰյ������줿�����ˤϡ����줫���äƤ���֥��ꥹ�ޥ��ס������ơ�����פ��Ԥ������ʤ�Ǥ�������
���������ʡ�
���֣��פ�ȯ��
�֥����פ�ȯ��������ɤǹԤʤ�줿�Ȥ����äϡ����̶���Ū��ǰ�Ȥ���¿���ο͡��ˤ�äƶ�ͭ����Ƥ����ΤǤ��롣�Τ��ˡ֣��פγ�ǰ�Ρ�ȯ���פ����θ�ο��ؤ�ȯŸ���줫���Ѥ�����ΤǤ��뤳�Ȥ��������ʤ��������Ƥ��줬����ɤˤ�������ؤΡֶ�ü�ʿ����פκ����װ������������Τ��Ȥ������ȤϽ�ʬ�ˤ�������������������������Ǽ��夲����֣���ȯ���פϡ������������¤ȤϤ�����ʹط����ʤ�������������ط����ʤ����ǤϤʤ����������Ǥ������ñ�㲽���뤿��ˡ����Τ��ȤϤ��Ф������֤��Ƥ����Ƥ��ʤ���������
��ˤ��뵷�˴ؤ��ʬ��ˤ����Ƥϡ����줬�ˤ��Ĺ���ˤ錄�äơ�ͽ�𤵤줿�פ�ΤǤ��ä��ˤ��衢�����������������ˤ��������Ū�ʡ֣���ȯ���פϡ�20�����˹Ԥʤ�줿�Τ������Ρ�ȯ���פʤ����ֺ�ȯ���פ�ͽ�𤹤��Τϡ���ħ��������˶ˤ�ƹ��Ϥ˸��Ф����Ȥ��Ǥ��롣�����Ƥ�����ͽ��פϡ��ɤ�⤬���������ʤ��ΡˤȤδط���ǻ���Ǥ��ꡢ�����ƤȤ�櫓�ֻ�Ⱥ����ε���פ����ơֱʱ�פγ�ǰ��ȼ�äƷ����֤��ФƤ����ΤʤΤǤ��롣
�����Ƥ����ܼ�Ū��̣�Ǥ����̵�סֶ�*�פϡ�ʸ�����Τ�ΤΡַ��� O�פˤ�äƤ���ʾ�ΰ�̣�����ʤ����������館���Ƥ������ˡפ�ֻ��֡פȤ�����Τ�������üŪ��ɽ����ħ�Ȥʤä��ΤǤ��롣
* �ֶ��פϡ������Ƥΰ��־�˺ܤ����Ƥ�����������ʪ�Τˤ�ä�ɽ������Ƥ��뤳�Ȥ��۵����줿����
�� �ƻ�ꤽ���Ʊ���
���ܤ�����˸�����ΤȤ��Ƽ�������ʡ�����ˤ��ब���ꡢ��Ҥ��羾�ʤ��ɤޤġˤ�����������������ΰ��ȹͤ�����ΤǤ��뤬���Ȥ��˿��Ҥʤɤ˸����ֱ���פ���ϡ������ι����פλ�����ǯ��ǯ�ϡ���κ��ˤΤ��礦��ϻ�����������ʤ���ƻ�κ�����������6��24, 25������30�����ˤ����Ƹ�����Τǡ�����Ͽ�ǯ��Ʊ�͡��ҤȤĤμ�������֤λ����˸����Τ����������ΤǤ��롣����ϡֳ����ء����Τ�פȸƤФ���Τǡ����λ����˿��Ҥ˻��ؤ����͡��ϡ����ܺǸŤν��������ε��������뤳�Ȥˤʤ롣���Ρֱߴġפ�����ä����㱤����־����פ��줿���Ȥ��θ����롣���������ˤ���Ҥʤɤˤ�äƤϾܤ���������ˡ����������Ƥ��ꡢ����¿���ϡ֣��λ��סʡ� ̵�µ���Τ褦��ž�ݤ��Ƥ��뤬�ˤ������ʤ��顢���Ū�ˡֹ�ף���פ�����ΤǤ��롣���ε��餬�ߴĤ�����ˡ������붵Ū��ˤ˴ؤ�꤬���뤳�Ȥϵ�����;�Ϥ��ʤ���

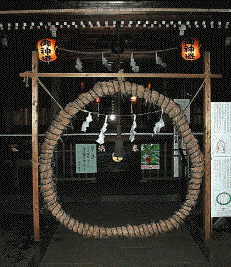

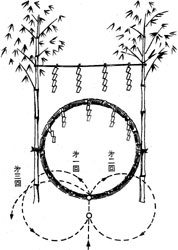
�֤ߤʤĤ��Ρ��ʤ����ΤϤ館����ҤȤϡ����Ȥ��Τ��Τ����Τ֡ʱ�ˤȤ����ʤ�ס����Ρֳ����ؤ�����פϡ��ǽ��Ⱦǯ��©�Ҥ˲ᤴ�������ȡ��Ĥ��Ⱦǯ��̵���˲ᤴ����Ⱦǯ��Ρֿ�ǯ�פ�ޤ������Ȥ����������θ���Ǥ���ȹͤ�������䤹����ΤΡ�����Ͻ����������������Ƥ��ꡢ����������Ĺ��������Ǥ���Ȥ������Ȥ����Τ��ľ�ħŪ�ʳ�ǧ�Ǥ��ꡢ��������������û���ʤäƤ����פ��ʤ���ֻ�˸����äƹԤ������Ǥ��롣���������줬���λ����˹Ԥʤ���Τϡ������Ρ�̵���ˤ�Ȥΰ��֤���ä��褿���פȤ����ꤤ��ȿ�ǤȤ������Ȥ�Ǥ����������
�ޤ������ܤǡֲƱ�㱡ʤʤ����ΤϤ館�ˡפ��Ԥ��룶��ܤΤޤ��ˤ��λ���6/24-25�ϥ��ꥹ�ȶ�ʸ�����ˤ����Ƥϡ�����ϥͺס������פ����������롣�ޤ��ˡ֥������ι��ºספȼ�������Ƥ���12��25����Ⱦǯ������������ֲƤΥ��ꥹ�ޥ��פȤǤ�ƤӤ����ʤ��ΤǤ��롣�ޤ�����ϥͺפ���Ϥޤ��˥����������ԥ��Ρֿ��Ƥ����̴: Midnight Summer's Dream�פ�������������Ǥ��ꡢ���ͤˡֲִġ��ִ��פ�£�ä��ꡢ������������ΰ����ˤ�꺲�����Τ���ͷΥ�������������Τ����Ű���ƲФ�ʲ���������ʹ�����*���������ˤʤɤΤ��Ȥ��Ԥʤ������Ǥ⤢�롣
* �����פϿ�ƻ��ʩ��ʸ�����ϡ�¾���͡��ʡֿ����פ�Ʊ�ͤˤष��������������褿ƻ�� (Taoism)�ȿ�����Ϣ�����롣��������ܤˤ�����ƻ�����ۤ����ܤθſ�ƻ����Φ����Ʊ����������ä�̩���Ϥ�ʩ�����ۤȺ��¤����������뤤�Ϥ��Ǥ˺��¤�����ΤȤ������ܤ�����ä���ǽ�����⤤��
�� ���ܤα���
�ֳݤ����פʤɤδվ��ʤȤ��Ƥ������ܤ˿��졢�ޤ����������������Ǥ��о줹���ħʪ������ν�Ǥ���ʿ���3�ˡ�����ϤۤȤ�ɥХ��Х������ۤɤ�ñ��ʡ�ɮ���ϤǤ����ߤ������������Ρֽ�פǤ��뤬�����ο����Ϥ����ƿ�����ħŪ��̣����ġ��ޤ��˱ʱ�ΰ�̣�礤��ֱ����ʤ���������פȤ�������̤������褿�Τ���
���ο��Ǥ��դ����褿����ˤ��С��ֱ���ϸ��դ�ɽ���Ǥ��ʤ����Фο����˰�ߤ��äƾ�ħŪ��ɽ��������ΡפȤ��롣�����ֻϤ��ʤ���н�����ʤ����������Ǥ���פȤ��ꡢ����Ū�ˤϡְ��Ǥ����פ�ΤȤ��ư����Ҽ��Ԥ����ͭ������褦��������������Ƥ���ΤǤ��롣
�� ���Ƥα���
�ֱ���ϤǤ�����ǯ��ǯ�Ϥ˴ط��Τ���ǥ��졼�����ȸ����Х��* (wreath: �ִġ��ִ�) �����ꡢ����ˤĤ��Ƹ��ʤ��ǺѤޤ���櫓�ˤϤ����ʤ��������Ǥϥ��ꥹ�ޥ��Ȥδ�Ϣ����ǯƱ�������˽и������ΤǤ��뤬�����⤽�⤳�Υ��ꥹ�ޥ����Ȥ��������ι����פ��뤤�ϡֺ���������פ��Բ�ʬ�ʤ�ΤǤ��롣


�ۤȤ�ɡֳ��˽��褦�ʡ�ŵ��Ū���ꥹ�ޥ���������֣��ĤβФζ̡פ����Ǥ�����긫���˶�ݲ����Ƥ��롣
�ҤȤĤˤϤ��Ρ֥��ꥹ�ޥ��פȤ��Ƹ����Τ���ֵ���Ū�Ի��פ����ꥹ�ȶ��������β������ϤǸ��Ф��줿�ڥ����˥���ʰ۶��������¿���������˥ߥ������ˤδ��������褿��Τǡ���Ȥδ�Ϣ������Ȥ�����Ϥ��Ǥ˹��������������Ȥ����ˤʤäƤ��롣���������줬���⤽�⥭�ꥹ�ȤΡֹ��ºספȺ��¤������ȼ��Ρ�ξ�Ԥκ��Τ��������ܼ�Ū�ʶ��̹ब���ä����Ȥ�ɽ���Ƥ��롣����ϡ�����פ���ɤȤ��벿���ʤΤǤ��롣
* ���������ִĤϲ��Ƥˤ����Ƥ�οͤ�̿���ʤɤ��軲�����ݤˡ����οͤ�ǰ������˶��������ΤǤ⤢�롣����ϻ�Ԥؤηɰդ�ɽ�����Ʊ���ˡ���Ԥ����٤����Ρ�����: return, resurrection�פ�ǰ���������Ǥ���ȹͤ��뤳�Ȥ��Ǥ��롣
���ʤ����ϰ�ǯ����ǺǤ�����û�����Ǥ��äơ������������פλ�Υԡ������̣���롣�����ԡ�����ۤ��������������פϺ����ʷաˤ˸����äƤޤä�����˿ʤ�ΤǤ��롣�����������ꥹ�ޥ��ˤ���ʬ�佩ʬ�Ȥ��ä��ü�ʰ�̣����Ķ�ʬ�ʤɤ�Ʊ�ͤ�ǯ�ΡֻϤޤ�פ⤷���ϡֽ����פλ��������ꤵ��뤳�Ȥˤϰ����ɬ����������ΤǤ��롣
�� 12��25���Ȥ��������ֹ��ºספǤ�����ͳ������
�ºݤϡ����������ּ祤�������������פǤ��뤳�Ȥˤϲ�������Ū����⡢�ޤ��Ƥ�����ˤ����뵭�Ҥ���ʤ��ΤǤ��뤬���ֹ��ºספ��������12��25���Ȥ�������Ū���ˤ������ꤷ�����Ȥϡ��̤��̤ǹ���Ū�ȸ����롣�����˴�ά�����줿���������ΰ������Ѱդ��롣���̤���ŵ�˵����Τ��룳�Ĥν����ˤ����Ƥ���������: holy day�פ������������줾�졢����䶵���������ˡ����ꥹ�ȶ����������ˡ�������ඵ�ʶ������ˤȤ������˰ۤʤ뤳�Ȥ⤢�ꡢ��������ֽ��λϤޤ�פˤ���Τ��Ȥ����Τϵ����Ȥʤꤨ��Ȥ����Ǥ��롣������������������������Ǥ���Ȥ���������������פ������˴�Ť�����������������������Ȱ��פ���ʤĤޤ�����������������Ǥ���˥����������Ѱդ���ʺ����Ʊ�ͤ��������礤�˽Ф����Ȥ�����Τǡ��ɼԤ����ˤϤ��ΡԸ����������դ˴����ĺ��ɬ�פ�����ˡ����ξ��ΰ�©�����������ʥ��ХȡˤȤʤ롣
���ξ�ǥ��ꥹ�Ȥ�����������ˤ����ˤǤ���Ȥ������Ȥ�Ƨ�ޤ��ơ����º�12��25�����������Ǥ���Ȳ��ꤹ��ȼ��Τ褦�ˤʤ롣
����������������������С����塡���ڡ����⡡����
�����������������������������������������������
�����������������������������������������������
�Ĥޤꡢ��ǯ��������ʸ�ö����ǯ�κǽ�����ˤ��������Ȥʤ�Ը����������դ˰��פ��뤳�Ȥ�ʬ���롣����ϥ��ꥹ�ȡֹ��¡פ��������ָ�ʣ����ܡˤˡֺ��ספ���Ȥ����ּ����ּ����θ��ѥ�����פ˰��פ���ΤǤ��롣�Ĥޤ���¤����ֲ����פϡ�ϻ����˳�����ޤ��ֲ�ۤ��פ�и���������Ū�־������餬�����ܤ˵����롣�����֤�����õ����٤��ֹ��¡������פ����٤�äƤ�������Ȥ����ΤϤ��λ��ˤ�����¾�ˤʤ�������Ϸ��Ū�˥��ꥹ�ޥ����鿷ǯ�ˤ����ƥ��ߥ�졼�Ȥ���뼷���֤�ʪ��Ȥʤ롣�����Ƥ���ϡֿ�ǯ��⡢�ʱ�ˡֻ�Ⱥ����סʤ��뤤�����ȷ��������ˤμ����������֤�³����ΤǤ��롣
�ä���줿���⤷��ʤ���������ä��᤹���ֱߴĤ�����ˡפȤ�����ΤΥ�����ζˤ�ƥ��륫���å��ʿ����������åȤ˵����뤳�Ȥϡ������Ǥ���٤ϸ��ڤ��Ƥ���ɬ�פ�����������������åȤΡ��祢�륫�ʡס�Major Arcane�ˤ�22��Υ����ɤ�21���ʣ����֡ˤ��Ϥ�ֶ�Ԥ�ι�פǤ��뤳�Ȥ���������Τ������ǤΥơ��ޤǤϤʤ����۴Ĥ��륤������ʤ������ƹԤ��Ȥ������Ȥ��������ޤǤ⤳���ǤΥơ��ޤǤ��롣��������ܤ����Ը����������դƤ����ݤˡ����Ρֻ����֤�ι�פˤĤ��ƤϺƤӸ��ڤ���Ǥ�������
�� �����åȤΡ�����: The World�פΥ����ɤ˸������
�ߴĤ�ޤ������Ƥ�ɽ�Ф����祢�륫�ʤκǸ��21����*���軰���κǽ��ˤΥ����ɡ�The World / Le Monde�פǸ����������ϡ��ޤ��ˡֳ����ؤ�����פƤ���褦�˸����롣�ֻ�Ⱥ����פȤ�̵�ط��˱ʱ��̿��������������פȤ����Ϥ�褦�ˡֱʹ�λ�Ⱥ������֤���ʪ�ο���ʤ��ߴĤξ�ħ�ʱ���ˤ��Ȥ߹�碌�ȤʤäƤ��롣�����ɤλͶ��˸�����ħ�ϡ��ֻ���: �Ͼ�Ū�ʻ��縵�ǡ�����ŷ�ȡ���ŷ�������ͤ�ʡ����ȡפʤɤξ�ħ�Ǥ���ʾܽҤϤ��ʤ��ˡ��ߤΤĤʤ��ܤˤϡ�X�ץޡ����Τ褦�ʷ��Ρ��֤���ܥ�פ������롣���������Ĥʤ��ܤϣ�����Ǥ��ꡢ����������Ȳƻ�Σ�������ܥ�ǷҤ��������ͤǤ⤢�롣���ξ�硢��ɤ�μؤ��ߤ��ο�������߹�äƤ���褦�ʱߴĤˤ⸫���롣
* �ֶ�ԡ�The Fool�פΥ����ɤ�ι����ΤǤ���֥������֤������Ƥ��Ƥ���Τǡ����22����祢�륫�ʤΥ��åȤǤ��뤬���������פ�21���ܤȹͤ��롣
�ޤ����ߤ��濴��������뤳�αʱ��������¸�ߤϡ��ֱʱ�˽���Ū�ʤ��ΡפǤ��ꡢ������ۤ���ޥꥢ������������뤤��˭���ο��Ȥ��Ƥ�����ô�äƤ����������ʥ��ʥ����̥��ˤ�魯���Ǥ��롣����Ϥޤ��ˡ���������餹�������פ��Τ�Τ�¾�ʤ�ʤ���

�����鸶��Ū�ʡ֥ޥ륻����ץ��åȡ���äȤ�����Ѥ���Ƥ���Ȥ����֥������ȡܥ�����ޥ��ߥ��ץ��å�(1910)�����ڥ������Υڡ��˥㡦���ˤ��֥��롦��������å��������ƥꥳ�ץ��åȡ�

������ȥ�����Ρ֥���ƥ����������å��������ƥ���ץ��åȡ������Ƥ����§����̾�⤭�ȥ�����ƥ����ȡɥ��쥤����������������Ρ֥ȡ��ȡץ��åȡ������ʡֲ��פȴ������褦�������Υ�����ο�ʪ���ݤΡֱ���פϡ����Υ��åȤˤ����Ƥϴ����˼ءʤʤ��������ܥ����ˤοްƤ��֤�����äƤ��롣����Ϥष�����Ϥξ�ħ�ؤβȸƤФ��٤����ݤǤ��롣

���ǤΥ����åȡ�The Wolrd�פο�����������ľ٣�˼����Ѥ������˸����륯�ꥹ�ޥ�������Ƚ�����ŷ�ȡ������ä������ܤ��٤����Ȥˡ��ֶ�פ���̤���Ƥ����ܥ�ˤ��֤ϡ���Ϥꤳ���Ǥ⣳�����֤��֤⤷����ɢ�μ¤ϡ������ǤϿ����Ѥ�äơֶ�פˤʤäƤ��뤬���ֶ�פǤ��뤳�ȤϤ��Ρֻ��̰��Ρפ�������褯ȿ�Ǥ��Ƥ��롣
�� ������Ϥ��Ƥ����Ρʿ��ˤĤ��ơ�
���ο�ʪ���ݤΤ褦�����ߴĤˤ��ƷҤ��Ǥ�������Ȥ����ΤϤޤ��˥���ΤȤ����dz�ǧ�����̤�θ�����ɽ�����Ƥ��롣����ŵ��Ū����ʲִġˤˤ����ơ��Ȥ�櫓���������դ�ª���������ʤ����ȤϤ��δ��ܿ��Ǥ��롣�Ĥޤ���¯Ū�ˡ֥��ꥹ�ޥ����פȤ���ǧ������Ƥ�����С��֡פΤ��ȤǤ��롣���ο����Ф��뤿��˿�ʪ���Ф��Ĵ�Ȥ����ؤ����졢�֤���ɢ�μ¡פ�֥�ܥ�פʤɤ��������졢���֡פ����Ǥ��ɲ�Ū��ɽ������롣

���СפΥܥȥ�Ǻ��줿����ʥ����ǡ�����Ǻ�ο������פǤ��뤫��ʬ���롣
��������ǯ��ǯ�ϤΥ���ο��ȷ�������ɤ����Ƥ�Ϣ�ۤ�����ʤ���Τ������ܥ����ο����Ǥ��롣����ϡֲ椬���鿩�����Ф��ء�ζ�פǤ���ο���2�ϡ�
�����ܥ����ο����ϡ�ϣ��ѿ����Ƭ������פ˰�������뤳�Ȥ������ȤʤäƤ��롣�ޤ��˻�Ūϣ��Ѥο����Τ����������褦�Ȥ������Ȥ������ΰ�����ñ��ʿ�˶Ž̤���Ƥ���Ȥ��äƤ����Ǥʤ��ۤɡ��ۤȤ�ɡֵ���Ū�ʺ�ˡ�פȤ���ϣ��Ѵ�Ϣ�����˸���Ƥ���ΤǤ��롣���Ρּءפο�����¿���β���������褿�������餫�αߴĤ�ż������ΤȤ���������褿���Ȥ˰㤤�Ϥʤ���������Ǥϡֲ��βפʤΤ��Ȥ������Ȥ���ȸ��첽�������Ҥ��ܤˤ����뤳�ȤϾ��ʤ���
��������Ƭ�ˡֱߴĤ����Ρפ����ơ��ʹ֤Ρ�ϣ��פȤ����٤�����⤿�餹��Τǡ�����ʪ�����ɤΤ褦�ˡ���Ĺ�ʲ��פ��ƹԤ������줬�ɤΤ褦�ʡַ����פ�ޤ���Τ��Ȥ������Ȥ��ħ˭���������Ƥ���ȹͤ��뤳�Ȥǡ����ΡֱߴĤ����Ρפ����Ƥ�Ū�Τ�ƶ�����뤳�Ȥ�����ǽ���ȸ�����ΤǤ��롣
���������Υ����ܥ����ΰż������ΤȤϡ�����ο��Τ���Ĥ���¸���뤳�ȡ����뤤�ϼ��ʤΡ���¸�פ����ʤΡֵ����פʤ��ˤ������ʤ����ȤΥ������ˡ����ޤޤ�롣
���Υ����ܥ����˵�������ĤΤ����ꥹ�ޥ����˸��ؤΡ���פʤɤ˾��������ʲִġˤǤ��롣����Ϥ��Υ����ܥ������֤��Ф��ڤ��褯ɽ�����줿�ߴĤμؤΥ����ꥢ��Ȥȹͤ��뤳�Ȥ��Ǥ��롣������¿���ξ�硢���αߴĤΥȥåפ��դ������ܥ�Ϥ��Υ����ܥ����δ�ʸ��ˤȤ���γ����դ��Ƥ�������ƿ����Ʊ���ˡֻϤޤ�פȡֽ����פ��ӤĤ�������̤����Ƥ��롣�����Ƥ��Υ�ܥ�ʤʤ�������˽स�����ǡˤϡ������ҡפˤ����뤢���Ρֱ�פ�����ʪ�Ǥ��롣


��ܥ���ʬ���Ф����ä��֥��������פ��֤�����ä����
����ΥХꥨ�������ܥ�Υ����ꥨ�������Ȥ��ƤΥ������������Υ��������Ϥष����ܥ������ʪ�ȹͤ�����⡢����ܼ�Ū�ʿ����ε�������äƤ���ȹͤ��뤳�Ȥ���ǽ�Ǥ��롣�ä˺�¦�Ρ�Ŵ������פϡ����θ�����Ȥ�����⸲���Ǥ��롣
����ˡ����ꥹ�ޥ��������¿�����Ф����褦�ˡ�����ˤϻ��Ĥ��֤����ǡ�������֤��֤Ǥ��ä��ꡢɢ�ʥҥ��饮�ˤμ¤Ǥ��ä��ꤹ��ΤǤ��뤬���ֻ��ĤβФζ̡פ�̾�Ĥ�α��Ƥ���ȹͤ��뤳�Ȥ��Ǥ���ΤǤ��롣�ޤ�ɢ�䤽��˽स��ɤ�����դ��Ѥ�������ͳ�ϡ����줬�ھ��˸�����Ȥ������ȡ������Ƥޤ��������˥�������Ƭ�˶���Ū���碌��줿����������֥��Х�δ��פ�Ϣ�ۤ����뤫��Ǥ��롣�Ĥޤꤽ�δ��ϡ��ּ�������פλ����Ǥ��Ǥ˽�������Ƥ���ΤǤ��롣�ޤ��ˡ��֥��Х�δ��פȤϡ������ν������������ʤ���ְ�α���פʤΤǤ��롣

���Х�δ� �� ��α��� = �����ν�������
�� �Ǹ����äƤ���ֱ���פȤ��ƤΡ֥�����
�����Ƥ��αߴĤ��륤����Ȥ����Τ�20�����������������κǽ����̤˱����ƺƤӸ���뤳�Ȥˤʤ롣������夲���˥塼�ᥭ����������⥴��ɤΡ�Trinity Site�פ������Ϥ���Ground Zero: ���������פȽ��ƸƤФ줿�ΤǤ��롣���ߤǤϡ������ϡ����̤����Τ褦�˸ƤФ��ΤǤ��뤬������Ϥष����æ�Ǥ��롣���Ρֻ˾��פγ���ȯ�����Ϥ��֣� : zero�פȤʤä��Τϼ¸��ΰŹ�̾�Τ��֣��פǤ��ä�����Ǥ��롣�ޥ�ϥå���ײ�ε��𤫤鹭�硦Ĺ��θ����겼�ޤǤ�ֽ������Ԥ�Ω��Ǥ��٤Ƥ����Ω��ˤ��ä�W��L��������θ��դ������
����ϡ���ˤι����פλϤޤ���֤Ȥ�����������ֺ�ɸ���ȶ��ֺ�ɸ���Ρ֣��פȤ����ΤǤ��롣�����⤳�줫��������������Ȥ��Ƥ��뤳�Ȥΰ�̣��褯���Ƥ���ʪ���ؼԤ������ۤ�̵���˼������줿�ֻϤޤ�סʤ����ơֽ����סˤ�������ɽ����ħ�Ǥ��ä��Τ���
���СפȤ��������äˡ�ϣ��ѡפ����ƱߴĤ��Ĥ������������֤β������ξ�ħ���п��Ȥζ�����Ϣ����ĤȤ�����ͳ���ʲ��Υ���������Ҥ���˸��Ф��롣
�����ˤ������羾�����ݤ侾�դ��С����ꥹ�ޥ���������С������ܥ������ڤ��С�����������С������Ƥ����ǤϤޤ����ʤ�����ʸ����θ٤�����Фλ�ҡס�������ϣ��������ˤ���������ۤ���Green Lion�פ��Фο����ʤɤʤɤΡ��ķ����դ���ͳ������ΤǤ��롣
�ѽ���ζ��ŷ߷��Ʋ�����ա�������?��1754-1817�ˤα����˵��˽�Ƥ����å������ϡֿ���ɱߡ������ݤ�ޤ�פʤΤǤ��롣
���������ʡ�

����1
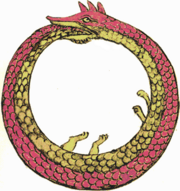
����2
 ������
������
����3
���֣��פ�ȯ��
�֥����פ�ȯ��������ɤǹԤʤ�줿�Ȥ����äϡ����̶���Ū��ǰ�Ȥ���¿���ο͡��ˤ�äƶ�ͭ����Ƥ����ΤǤ��롣�Τ��ˡ֣��פγ�ǰ�Ρ�ȯ���פ����θ�ο��ؤ�ȯŸ���줫���Ѥ�����ΤǤ��뤳�Ȥ��������ʤ��������Ƥ��줬����ɤˤ�������ؤΡֶ�ü�ʿ����פκ����װ������������Τ��Ȥ������ȤϽ�ʬ�ˤ�������������������������Ǽ��夲����֣���ȯ���פϡ������������¤ȤϤ�����ʹط����ʤ�������������ط����ʤ����ǤϤʤ����������Ǥ������ñ�㲽���뤿��ˡ����Τ��ȤϤ��Ф������֤��Ƥ����Ƥ��ʤ���������
��ˤ��뵷�˴ؤ��ʬ��ˤ����Ƥϡ����줬�ˤ��Ĺ���ˤ錄�äơ�ͽ�𤵤줿�פ�ΤǤ��ä��ˤ��衢�����������������ˤ��������Ū�ʡ֣���ȯ���פϡ�20�����˹Ԥʤ�줿�Τ������Ρ�ȯ���פʤ����ֺ�ȯ���פ�ͽ�𤹤��Τϡ���ħ��������˶ˤ�ƹ��Ϥ˸��Ф����Ȥ��Ǥ��롣�����Ƥ�����ͽ��פϡ��ɤ�⤬���������ʤ��ΡˤȤδط���ǻ���Ǥ��ꡢ�����ƤȤ�櫓�ֻ�Ⱥ����ε���פ����ơֱʱ�פγ�ǰ��ȼ�äƷ����֤��ФƤ����ΤʤΤǤ��롣
�����Ƥ����ܼ�Ū��̣�Ǥ����̵�סֶ�*�פϡ�ʸ�����Τ�ΤΡַ��� O�פˤ�äƤ���ʾ�ΰ�̣�����ʤ����������館���Ƥ������ˡפ�ֻ��֡פȤ�����Τ�������üŪ��ɽ����ħ�Ȥʤä��ΤǤ��롣
* �ֶ��פϡ������Ƥΰ��־�˺ܤ����Ƥ�����������ʪ�Τˤ�ä�ɽ������Ƥ��뤳�Ȥ��۵����줿����
�� �ƻ�ꤽ���Ʊ���
���ܤ�����˸�����ΤȤ��Ƽ�������ʡ�����ˤ��ब���ꡢ��Ҥ��羾�ʤ��ɤޤġˤ�����������������ΰ��ȹͤ�����ΤǤ��뤬���Ȥ��˿��Ҥʤɤ˸����ֱ���פ���ϡ������ι����פλ�����ǯ��ǯ�ϡ���κ��ˤΤ��礦��ϻ�����������ʤ���ƻ�κ�����������6��24, 25������30�����ˤ����Ƹ�����Τǡ�����Ͽ�ǯ��Ʊ�͡��ҤȤĤμ�������֤λ����˸����Τ����������ΤǤ��롣����ϡֳ����ء����Τ�פȸƤФ���Τǡ����λ����˿��Ҥ˻��ؤ����͡��ϡ����ܺǸŤν��������ε��������뤳�Ȥˤʤ롣���Ρֱߴġפ�����ä����㱤����־����פ��줿���Ȥ��θ����롣���������ˤ���Ҥʤɤˤ�äƤϾܤ���������ˡ����������Ƥ��ꡢ����¿���ϡ֣��λ��סʡ� ̵�µ���Τ褦��ž�ݤ��Ƥ��뤬�ˤ������ʤ��顢���Ū�ˡֹ�ף���פ�����ΤǤ��롣���ε��餬�ߴĤ�����ˡ������붵Ū��ˤ˴ؤ�꤬���뤳�Ȥϵ�����;�Ϥ��ʤ���

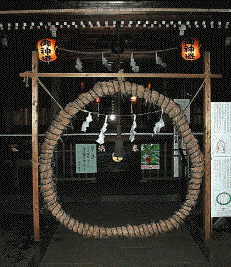

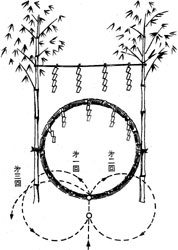
�֤ߤʤĤ��Ρ��ʤ����ΤϤ館����ҤȤϡ����Ȥ��Τ��Τ����Τ֡ʱ�ˤȤ����ʤ�ס����Ρֳ����ؤ�����פϡ��ǽ��Ⱦǯ��©�Ҥ˲ᤴ�������ȡ��Ĥ��Ⱦǯ��̵���˲ᤴ����Ⱦǯ��Ρֿ�ǯ�פ�ޤ������Ȥ����������θ���Ǥ���ȹͤ�������䤹����ΤΡ�����Ͻ����������������Ƥ��ꡢ����������Ĺ��������Ǥ���Ȥ������Ȥ����Τ��ľ�ħŪ�ʳ�ǧ�Ǥ��ꡢ��������������û���ʤäƤ����פ��ʤ���ֻ�˸����äƹԤ������Ǥ��롣���������줬���λ����˹Ԥʤ���Τϡ������Ρ�̵���ˤ�Ȥΰ��֤���ä��褿���פȤ����ꤤ��ȿ�ǤȤ������Ȥ�Ǥ����������
�ޤ������ܤǡֲƱ�㱡ʤʤ����ΤϤ館�ˡפ��Ԥ��룶��ܤΤޤ��ˤ��λ���6/24-25�ϥ��ꥹ�ȶ�ʸ�����ˤ����Ƥϡ�����ϥͺס������פ����������롣�ޤ��ˡ֥������ι��ºספȼ�������Ƥ���12��25����Ⱦǯ������������ֲƤΥ��ꥹ�ޥ��פȤǤ�ƤӤ����ʤ��ΤǤ��롣�ޤ�����ϥͺפ���Ϥޤ��˥����������ԥ��Ρֿ��Ƥ����̴: Midnight Summer's Dream�פ�������������Ǥ��ꡢ���ͤˡֲִġ��ִ��פ�£�ä��ꡢ������������ΰ����ˤ�꺲�����Τ���ͷΥ�������������Τ����Ű���ƲФ�ʲ���������ʹ�����*���������ˤʤɤΤ��Ȥ��Ԥʤ������Ǥ⤢�롣
* �����פϿ�ƻ��ʩ��ʸ�����ϡ�¾���͡��ʡֿ����פ�Ʊ�ͤˤष��������������褿ƻ�� (Taoism)�ȿ�����Ϣ�����롣��������ܤˤ�����ƻ�����ۤ����ܤθſ�ƻ����Φ����Ʊ����������ä�̩���Ϥ�ʩ�����ۤȺ��¤����������뤤�Ϥ��Ǥ˺��¤�����ΤȤ������ܤ�����ä���ǽ�����⤤��
�� ���ܤα���
�ֳݤ����פʤɤδվ��ʤȤ��Ƥ������ܤ˿��졢�ޤ����������������Ǥ��о줹���ħʪ������ν�Ǥ���ʿ���3�ˡ�����ϤۤȤ�ɥХ��Х������ۤɤ�ñ��ʡ�ɮ���ϤǤ����ߤ������������Ρֽ�פǤ��뤬�����ο����Ϥ����ƿ�����ħŪ��̣����ġ��ޤ��˱ʱ�ΰ�̣�礤��ֱ����ʤ���������פȤ�������̤������褿�Τ���
���ο��Ǥ��դ����褿����ˤ��С��ֱ���ϸ��դ�ɽ���Ǥ��ʤ����Фο����˰�ߤ��äƾ�ħŪ��ɽ��������ΡפȤ��롣�����ֻϤ��ʤ���н�����ʤ����������Ǥ���פȤ��ꡢ����Ū�ˤϡְ��Ǥ����פ�ΤȤ��ư����Ҽ��Ԥ����ͭ������褦��������������Ƥ���ΤǤ��롣
�� ���Ƥα���
�ֱ���ϤǤ�����ǯ��ǯ�Ϥ˴ط��Τ���ǥ��졼�����ȸ����Х��* (wreath: �ִġ��ִ�) �����ꡢ����ˤĤ��Ƹ��ʤ��ǺѤޤ���櫓�ˤϤ����ʤ��������Ǥϥ��ꥹ�ޥ��Ȥδ�Ϣ����ǯƱ�������˽и������ΤǤ��뤬�����⤽�⤳�Υ��ꥹ�ޥ����Ȥ��������ι����פ��뤤�ϡֺ���������פ��Բ�ʬ�ʤ�ΤǤ��롣


�ۤȤ�ɡֳ��˽��褦�ʡ�ŵ��Ū���ꥹ�ޥ���������֣��ĤβФζ̡פ����Ǥ�����긫���˶�ݲ����Ƥ��롣
�ҤȤĤˤϤ��Ρ֥��ꥹ�ޥ��פȤ��Ƹ����Τ���ֵ���Ū�Ի��פ����ꥹ�ȶ��������β������ϤǸ��Ф��줿�ڥ����˥���ʰ۶��������¿���������˥ߥ������ˤδ��������褿��Τǡ���Ȥδ�Ϣ������Ȥ�����Ϥ��Ǥ˹��������������Ȥ����ˤʤäƤ��롣���������줬���⤽�⥭�ꥹ�ȤΡֹ��ºספȺ��¤������ȼ��Ρ�ξ�Ԥκ��Τ��������ܼ�Ū�ʶ��̹ब���ä����Ȥ�ɽ���Ƥ��롣����ϡ�����פ���ɤȤ��벿���ʤΤǤ��롣
* ���������ִĤϲ��Ƥˤ����Ƥ�οͤ�̿���ʤɤ��軲�����ݤˡ����οͤ�ǰ������˶��������ΤǤ⤢�롣����ϻ�Ԥؤηɰդ�ɽ�����Ʊ���ˡ���Ԥ����٤����Ρ�����: return, resurrection�פ�ǰ���������Ǥ���ȹͤ��뤳�Ȥ��Ǥ��롣
���ʤ����ϰ�ǯ����ǺǤ�����û�����Ǥ��äơ������������פλ�Υԡ������̣���롣�����ԡ�����ۤ��������������פϺ����ʷաˤ˸����äƤޤä�����˿ʤ�ΤǤ��롣�����������ꥹ�ޥ��ˤ���ʬ�佩ʬ�Ȥ��ä��ü�ʰ�̣����Ķ�ʬ�ʤɤ�Ʊ�ͤ�ǯ�ΡֻϤޤ�פ⤷���ϡֽ����פλ��������ꤵ��뤳�Ȥˤϰ����ɬ����������ΤǤ��롣
�� 12��25���Ȥ��������ֹ��ºספǤ�����ͳ������
�ºݤϡ����������ּ祤�������������פǤ��뤳�Ȥˤϲ�������Ū����⡢�ޤ��Ƥ�����ˤ����뵭�Ҥ���ʤ��ΤǤ��뤬���ֹ��ºספ��������12��25���Ȥ�������Ū���ˤ������ꤷ�����Ȥϡ��̤��̤ǹ���Ū�ȸ����롣�����˴�ά�����줿���������ΰ������Ѱդ��롣���̤���ŵ�˵����Τ��룳�Ĥν����ˤ����Ƥ���������: holy day�פ������������줾�졢����䶵���������ˡ����ꥹ�ȶ����������ˡ�������ඵ�ʶ������ˤȤ������˰ۤʤ뤳�Ȥ⤢�ꡢ��������ֽ��λϤޤ�פˤ���Τ��Ȥ����Τϵ����Ȥʤꤨ��Ȥ����Ǥ��롣������������������������Ǥ���Ȥ���������������פ������˴�Ť�����������������������Ȱ��פ���ʤĤޤ�����������������Ǥ���˥����������Ѱդ���ʺ����Ʊ�ͤ��������礤�˽Ф����Ȥ�����Τǡ��ɼԤ����ˤϤ��ΡԸ����������դ˴����ĺ��ɬ�פ�����ˡ����ξ��ΰ�©�����������ʥ��ХȡˤȤʤ롣
���ξ�ǥ��ꥹ�Ȥ�����������ˤ����ˤǤ���Ȥ������Ȥ�Ƨ�ޤ��ơ����º�12��25�����������Ǥ���Ȳ��ꤹ��ȼ��Τ褦�ˤʤ롣
����������������������С����塡���ڡ����⡡����
�����������������������������������������������
�����������������������������������������������
�Ĥޤꡢ��ǯ��������ʸ�ö����ǯ�κǽ�����ˤ��������Ȥʤ�Ը����������դ˰��פ��뤳�Ȥ�ʬ���롣����ϥ��ꥹ�ȡֹ��¡פ��������ָ�ʣ����ܡˤˡֺ��ספ���Ȥ����ּ����ּ����θ��ѥ�����פ˰��פ���ΤǤ��롣�Ĥޤ���¤����ֲ����פϡ�ϻ����˳�����ޤ��ֲ�ۤ��פ�и���������Ū�־������餬�����ܤ˵����롣�����֤�����õ����٤��ֹ��¡������פ����٤�äƤ�������Ȥ����ΤϤ��λ��ˤ�����¾�ˤʤ�������Ϸ��Ū�˥��ꥹ�ޥ����鿷ǯ�ˤ����ƥ��ߥ�졼�Ȥ���뼷���֤�ʪ��Ȥʤ롣�����Ƥ���ϡֿ�ǯ��⡢�ʱ�ˡֻ�Ⱥ����סʤ��뤤�����ȷ��������ˤμ����������֤�³����ΤǤ��롣
�ä���줿���⤷��ʤ���������ä��᤹���ֱߴĤ�����ˡפȤ�����ΤΥ�����ζˤ�ƥ��륫���å��ʿ����������åȤ˵����뤳�Ȥϡ������Ǥ���٤ϸ��ڤ��Ƥ���ɬ�פ�����������������åȤΡ��祢�륫�ʡס�Major Arcane�ˤ�22��Υ����ɤ�21���ʣ����֡ˤ��Ϥ�ֶ�Ԥ�ι�פǤ��뤳�Ȥ���������Τ������ǤΥơ��ޤǤϤʤ����۴Ĥ��륤������ʤ������ƹԤ��Ȥ������Ȥ��������ޤǤ⤳���ǤΥơ��ޤǤ��롣��������ܤ����Ը����������դƤ����ݤˡ����Ρֻ����֤�ι�פˤĤ��ƤϺƤӸ��ڤ���Ǥ�������
�� �����åȤΡ�����: The World�פΥ����ɤ˸������
�ߴĤ�ޤ������Ƥ�ɽ�Ф����祢�륫�ʤκǸ��21����*���軰���κǽ��ˤΥ����ɡ�The World / Le Monde�פǸ����������ϡ��ޤ��ˡֳ����ؤ�����פƤ���褦�˸����롣�ֻ�Ⱥ����פȤ�̵�ط��˱ʱ��̿��������������פȤ����Ϥ�褦�ˡֱʹ�λ�Ⱥ������֤���ʪ�ο���ʤ��ߴĤξ�ħ�ʱ���ˤ��Ȥ߹�碌�ȤʤäƤ��롣�����ɤλͶ��˸�����ħ�ϡ��ֻ���: �Ͼ�Ū�ʻ��縵�ǡ�����ŷ�ȡ���ŷ�������ͤ�ʡ����ȡפʤɤξ�ħ�Ǥ���ʾܽҤϤ��ʤ��ˡ��ߤΤĤʤ��ܤˤϡ�X�ץޡ����Τ褦�ʷ��Ρ��֤���ܥ�פ������롣���������Ĥʤ��ܤϣ�����Ǥ��ꡢ����������Ȳƻ�Σ�������ܥ�ǷҤ��������ͤǤ⤢�롣���ξ�硢��ɤ�μؤ��ߤ��ο�������߹�äƤ���褦�ʱߴĤˤ⸫���롣
* �ֶ�ԡ�The Fool�פΥ����ɤ�ι����ΤǤ���֥������֤������Ƥ��Ƥ���Τǡ����22����祢�륫�ʤΥ��åȤǤ��뤬���������פ�21���ܤȹͤ��롣
�ޤ����ߤ��濴��������뤳�αʱ��������¸�ߤϡ��ֱʱ�˽���Ū�ʤ��ΡפǤ��ꡢ������ۤ���ޥꥢ������������뤤��˭���ο��Ȥ��Ƥ�����ô�äƤ����������ʥ��ʥ����̥��ˤ�魯���Ǥ��롣����Ϥޤ��ˡ���������餹�������פ��Τ�Τ�¾�ʤ�ʤ���

�����鸶��Ū�ʡ֥ޥ륻����ץ��åȡ���äȤ�����Ѥ���Ƥ���Ȥ����֥������ȡܥ�����ޥ��ߥ��ץ��å�(1910)�����ڥ������Υڡ��˥㡦���ˤ��֥��롦��������å��������ƥꥳ�ץ��åȡ�

������ȥ�����Ρ֥���ƥ����������å��������ƥ���ץ��åȡ������Ƥ����§����̾�⤭�ȥ�����ƥ����ȡɥ��쥤����������������Ρ֥ȡ��ȡץ��åȡ������ʡֲ��פȴ������褦�������Υ�����ο�ʪ���ݤΡֱ���פϡ����Υ��åȤˤ����Ƥϴ����˼ءʤʤ��������ܥ����ˤοްƤ��֤�����äƤ��롣����Ϥष�����Ϥξ�ħ�ؤβȸƤФ��٤����ݤǤ��롣

���ǤΥ����åȡ�The Wolrd�פο�����������ľ٣�˼����Ѥ������˸����륯�ꥹ�ޥ�������Ƚ�����ŷ�ȡ������ä������ܤ��٤����Ȥˡ��ֶ�פ���̤���Ƥ����ܥ�ˤ��֤ϡ���Ϥꤳ���Ǥ⣳�����֤��֤⤷����ɢ�μ¤ϡ������ǤϿ����Ѥ�äơֶ�פˤʤäƤ��뤬���ֶ�פǤ��뤳�ȤϤ��Ρֻ��̰��Ρפ�������褯ȿ�Ǥ��Ƥ��롣
�� ������Ϥ��Ƥ����Ρʿ��ˤĤ��ơ�
���ο�ʪ���ݤΤ褦�����ߴĤˤ��ƷҤ��Ǥ�������Ȥ����ΤϤޤ��˥���ΤȤ����dz�ǧ�����̤�θ�����ɽ�����Ƥ��롣����ŵ��Ū����ʲִġˤˤ����ơ��Ȥ�櫓���������դ�ª���������ʤ����ȤϤ��δ��ܿ��Ǥ��롣�Ĥޤ���¯Ū�ˡ֥��ꥹ�ޥ����פȤ���ǧ������Ƥ�����С��֡פΤ��ȤǤ��롣���ο����Ф��뤿��˿�ʪ���Ф��Ĵ�Ȥ����ؤ����졢�֤���ɢ�μ¡פ�֥�ܥ�פʤɤ��������졢���֡פ����Ǥ��ɲ�Ū��ɽ������롣

���СפΥܥȥ�Ǻ��줿����ʥ����ǡ�����Ǻ�ο������פǤ��뤫��ʬ���롣
��������ǯ��ǯ�ϤΥ���ο��ȷ�������ɤ����Ƥ�Ϣ�ۤ�����ʤ���Τ������ܥ����ο����Ǥ��롣����ϡֲ椬���鿩�����Ф��ء�ζ�פǤ���ο���2�ϡ�
�����ܥ����ο����ϡ�ϣ��ѿ����Ƭ������פ˰�������뤳�Ȥ������ȤʤäƤ��롣�ޤ��˻�Ūϣ��Ѥο����Τ����������褦�Ȥ������Ȥ������ΰ�����ñ��ʿ�˶Ž̤���Ƥ���Ȥ��äƤ����Ǥʤ��ۤɡ��ۤȤ�ɡֵ���Ū�ʺ�ˡ�פȤ���ϣ��Ѵ�Ϣ�����˸���Ƥ���ΤǤ��롣���Ρּءפο�����¿���β���������褿�������餫�αߴĤ�ż������ΤȤ���������褿���Ȥ˰㤤�Ϥʤ���������Ǥϡֲ��βפʤΤ��Ȥ������Ȥ���ȸ��첽�������Ҥ��ܤˤ����뤳�ȤϾ��ʤ���
��������Ƭ�ˡֱߴĤ����Ρפ����ơ��ʹ֤Ρ�ϣ��פȤ����٤�����⤿�餹��Τǡ�����ʪ�����ɤΤ褦�ˡ���Ĺ�ʲ��פ��ƹԤ������줬�ɤΤ褦�ʡַ����פ�ޤ���Τ��Ȥ������Ȥ��ħ˭���������Ƥ���ȹͤ��뤳�Ȥǡ����ΡֱߴĤ����Ρפ����Ƥ�Ū�Τ�ƶ�����뤳�Ȥ�����ǽ���ȸ�����ΤǤ��롣
���������Υ����ܥ����ΰż������ΤȤϡ�����ο��Τ���Ĥ���¸���뤳�ȡ����뤤�ϼ��ʤΡ���¸�פ����ʤΡֵ����פʤ��ˤ������ʤ����ȤΥ������ˡ����ޤޤ�롣
���Υ����ܥ����˵�������ĤΤ����ꥹ�ޥ����˸��ؤΡ���פʤɤ˾��������ʲִġˤǤ��롣����Ϥ��Υ����ܥ������֤��Ф��ڤ��褯ɽ�����줿�ߴĤμؤΥ����ꥢ��Ȥȹͤ��뤳�Ȥ��Ǥ��롣������¿���ξ�硢���αߴĤΥȥåפ��դ������ܥ�Ϥ��Υ����ܥ����δ�ʸ��ˤȤ���γ����դ��Ƥ�������ƿ����Ʊ���ˡֻϤޤ�פȡֽ����פ��ӤĤ�������̤����Ƥ��롣�����Ƥ��Υ�ܥ�ʤʤ�������˽स�����ǡˤϡ������ҡפˤ����뤢���Ρֱ�פ�����ʪ�Ǥ��롣


��ܥ���ʬ���Ф����ä��֥��������פ��֤�����ä����
����ΥХꥨ�������ܥ�Υ����ꥨ�������Ȥ��ƤΥ������������Υ��������Ϥष����ܥ������ʪ�ȹͤ�����⡢����ܼ�Ū�ʿ����ε�������äƤ���ȹͤ��뤳�Ȥ���ǽ�Ǥ��롣�ä˺�¦�Ρ�Ŵ������פϡ����θ�����Ȥ�����⸲���Ǥ��롣
����ˡ����ꥹ�ޥ��������¿�����Ф����褦�ˡ�����ˤϻ��Ĥ��֤����ǡ�������֤��֤Ǥ��ä��ꡢɢ�ʥҥ��饮�ˤμ¤Ǥ��ä��ꤹ��ΤǤ��뤬���ֻ��ĤβФζ̡פ�̾�Ĥ�α��Ƥ���ȹͤ��뤳�Ȥ��Ǥ���ΤǤ��롣�ޤ�ɢ�䤽��˽स��ɤ�����դ��Ѥ�������ͳ�ϡ����줬�ھ��˸�����Ȥ������ȡ������Ƥޤ��������˥�������Ƭ�˶���Ū���碌��줿����������֥��Х�δ��פ�Ϣ�ۤ����뤫��Ǥ��롣�Ĥޤꤽ�δ��ϡ��ּ�������פλ����Ǥ��Ǥ˽�������Ƥ���ΤǤ��롣�ޤ��ˡ��֥��Х�δ��פȤϡ������ν������������ʤ���ְ�α���פʤΤǤ��롣

���Х�δ� �� ��α��� = �����ν�������
�� �Ǹ����äƤ���ֱ���פȤ��ƤΡ֥�����
�����Ƥ��αߴĤ��륤����Ȥ����Τ�20�����������������κǽ����̤˱����ƺƤӸ���뤳�Ȥˤʤ롣������夲���˥塼�ᥭ����������⥴��ɤΡ�Trinity Site�פ������Ϥ���Ground Zero: ���������פȽ��ƸƤФ줿�ΤǤ��롣���ߤǤϡ������ϡ����̤����Τ褦�˸ƤФ��ΤǤ��뤬������Ϥष����æ�Ǥ��롣���Ρֻ˾��פγ���ȯ�����Ϥ��֣� : zero�פȤʤä��Τϼ¸��ΰŹ�̾�Τ��֣��פǤ��ä�����Ǥ��롣�ޥ�ϥå���ײ�ε��𤫤鹭�硦Ĺ��θ����겼�ޤǤ�ֽ������Ԥ�Ω��Ǥ��٤Ƥ����Ω��ˤ��ä�W��L��������θ��դ������
�������֤˴ؤ��뤢�����Ψ�����������֤���Ƥ���������������ȯ�ηײ���﨡�������¸��ΰŹ�̾�Ρ֥����פǤޤˤ��蘆��Ƥ�����������ط��ԤˤȤäơ��֣��פ��������濴�Ȥʤä������֤���֤⥼�����˻Ϥޤꥼ�����˽���ä��������褬����0�˽��椵�줿�����٤Ƥοͤ������������ȥ��������֡�����ɤ��餫�ȸ����С�������Ķ�ֻ��Τ��Ȥ�ͤ�����
W��L������������أ��ζǡٺ����Ϲ� ��
����ϡ���ˤι����פλϤޤ���֤Ȥ�����������ֺ�ɸ���ȶ��ֺ�ɸ���Ρ֣��פȤ����ΤǤ��롣�����⤳�줫��������������Ȥ��Ƥ��뤳�Ȥΰ�̣��褯���Ƥ���ʪ���ؼԤ������ۤ�̵���˼������줿�ֻϤޤ�סʤ����ơֽ����סˤ�������ɽ����ħ�Ǥ��ä��Τ���
���СפȤ��������äˡ�ϣ��ѡפ����ƱߴĤ��Ĥ������������֤β������ξ�ħ���п��Ȥζ�����Ϣ����ĤȤ�����ͳ���ʲ��Υ���������Ҥ���˸��Ф��롣
���礦�ɤ��νִ֡��Ϥα����餳�����ʤ�̸���Ω�����ä�������Ϥޤ�ǡ�̵�������ۤ�����˵������褦�ʸ����ä������������ˤ��ĤƸ���줿���ȤΤʤ��ä�������п���Ķ����������ʬ�ΰ��ä��δ֤������ɴ��ȥ�ι⤵�ޤ�Ω�����ꡢ����˹⤯�⤯����ã���ơ��ܤΤ����Ф���θ�����ŷ�Ϥ�Ȥ餷���褦�����νФ��ä���
������ά�ˤ��ο��ϳ��������λ��ˤΤ߸����뤢���䤫���п����褷������ά�ˤ�����ŷ����¤�ΤȤ��������ָ��赱���פȶ�������νִ֤ˤ����碌���褦�ʴ����Ǥ��줿�Τ��ä���
W��L������������أ��ζǡٺ����Ϲ� ��
�����ˤ������羾�����ݤ侾�դ��С����ꥹ�ޥ���������С������ܥ������ڤ��С�����������С������Ƥ����ǤϤޤ����ʤ�����ʸ����θ٤�����Фλ�ҡס�������ϣ��������ˤ���������ۤ���Green Lion�פ��Фο����ʤɤʤɤΡ��ķ����դ���ͳ������ΤǤ��롣
�ѽ���ζ��ŷ߷��Ʋ�����ա�������?��1754-1817�ˤα����˵��˽�Ƥ����å������ϡֿ���ɱߡ������ݤ�ޤ�פʤΤǤ��롣
23:39:00 -
entee -
TrackBacks
2005-10-13
�ֶ��פؤ������
����Ū�ʡ־�������ȡ��������������ΡΣ���

����ϡֿ�ǯ�ס�����פ����ơֻ��ĤβФζ̡פ˴ؤ��Τ����á��äˡֻ��̰��Ρ������ݲ����Ƥ���ȹͤ�����������ħŪ̾�ΤʤɤΤ����Ĥ��ˤĤ��Ƹ��ڤ��롣
���ܤμһ�ʩ�շϤΡ����ʤ��Ͻ�פ�ˬ���Ȥ���줬���Ф����̲ᤷ�ʤ���Фʤ�ʤ��ǽ�ξ��Ȥ��ơ���פ����롣�ä˻���κ������⤷��������äƤ��餷�Ф餯���ƺ����ˡ��оΡפ����֤��줿��Ĥ����˵��դ��Ǥ�������¿���ξ��ϡ����ܤǤϹ����ʤ��ޤ��̡ˤʤɤǿƤ��ޤ�Ƥ�����Ƭ�νáʤ���Ρˤ������Ǥ��롣����ϼ¤�¿���ξ��Ǹ��뤳�Ȥ��Ǥ��롣�����������Τ˸��������֤�����Ƥϡ��оΡפǤϤʤ��������ϡ֤������פβ���ȯ��������Ƥ��ꡢ¾���ϡ֤�����פβ���ȯ��������η��Ƥ��롣�Ĥޤꡢ�֤�������פ���Ĥ˶��ޤ줿����������š��ȿʤ�ǹԤ��Ȥ������Ȥˤʤ롣���νä��¤ϡֻ�ҡפǤ���Ȥ������Ȥ�ñ�Ȥ��õ����뤳�Ȥ��ǽ�����������Ǥϥơ��ޤδط��夢�ޤ꿼���ꤷ�ʤ���
���⤽�⡢���ν����ˤ������������ʥ����ꥢ��Ȥ����äƹ�����= ��ҡˤ����Ǥʤ���ͭ̾��Ǥϡֶ���ϻ����פΥ�����������졢�ޤ���ٿ��ҤǤ���к����θѡʥ��ĥ͡���*�Ǥ��ä���⤹��ΤǤ��롣�����������Τɤ�⺸�������������褦�Ȥ��Ƥ��뵭��ϡ֤�������פʤΤǤ��롣
* �����⤽�ο����η�����ǥե���ᤵ���뤳�Ȥǡ�����פ��ͤ˸�Ω�Ƥ��륱���������롣�Ĥޤ꺸���Ρ�����פǤ��롣
�֥�ϥͤ��ۼ�Ͽ�פˤϼ��Τ褦�˽�Ƥ��롣�ָ��衢�錄���Ϥ�������롣��Ȥ��Ƥ��Ƥ��줾��Τ��虜�˱������褦���錄���ϥ���ѡʥ���ե��ˤǤ��ꡢ���ᥬ�Ǥ��롣�ǽ�μԤǤ��ꡢ�Ǹ�μԤǤ��롣���Ǥ��ꡢ�����Ǥ��롣�פ�������ˤ�������Ρֻ��֤ؤδ��ס���ˤγ��ϡפ˴ؤ��Ƥξ�ħŪ�Ƿٹ�Ū��ɽ���Ǥ��롣���ꥹ�Ȥ����Τ褦�˽Ҥ٤��Ȥ������Ҥϼ¤ΤȤ��������Ĥ�ʡ����������ʤ��������ο���κǸ�˼�����Ƥ�����ۼ�Ͽ�פˤϡ����ꥹ�ȶ����Ѥ䶵�������������ǥ��ꥹ�����ȤȤ�ˤ��κ����˥���ե��ʦ��ˤȥ��ᥬ�ʦ��ˤ��ۤ���뺬��ȤʤäƤ���Ȼפ��뵭�Ҥ����Ф���롣�������ֻ�ϵ����Ժߤ��ˤ����ޤ��Ƥ���ä����פȻ��̤����˸����ä���«�����������ʥ��ꥹ�ȡˤȡ����Ρ֥���ե��٥åȤξ�ħ�פȤ����Ҥȥ��åȤˤʤäƤ���ʾ塢�¤�ɬ��Ū�ʤ��Ȥȸ��虜������ʤ���
������ɤޤ�������ˤȤäƤϡ�����Ƥ��Ȥ��ޤǤ�ʤ��֥���ե������פȡ֥��ᥬ�����פϥ��ꥷ���Υ���ե��٥åȤκǽ�ȺǸ��ʸ���Ǥ��롣�Ѹ�Ǹ����Ф��������A�Ǥ���Z�Ǥ���פȤ������ȤǤ��롣����ˤϺ��������ä���Ťΰ�̣�����롣���֡���ˡˤ����Ф��졢���줬�Ϥޤä��ʾ塢������֤���פˤϽ���꤬��ʤ���Фʤ�ʤ��Ȥ�������ˤ������˴ؤ��Ƥ����Ȥε�ǽ�����Ǥ��롣�ޤ��Ѹ�Ρ�(from) A to Z�פȤ���ɽ����������褦�ˡ�����ˤϡ֤����뤹�٤�: all and everything�פȤ����ްդ����롣�ǽ餫��Ǹ�ޤǤΡ֤��٤ơפ�ޤ�Ǥ���Ȥ�����̣�Ǥ��롣�ޤ��˿Ͱ٤ο����Ȥ������Ф����Ȥ����Ͼ�ʸ����ˤ˵�����֤��٤ơפΤ��Ȥ����礷�ƸƤ�Ǥ������Ǥ���*��
* �֥������Τʤ������Ȥϡ����Τۤ��ˤޤ���¿�����롣�⤷���������Ĥ���ʤ�С������⤽�ν줿ʸ������ʤ��Ǥ��������סʥ�ϥͤˤ��ʡ����21:25�ˤȤ������Ҥ��۵����줿����
���ơ������֤�������פϤɤ�������̣�ʤΤ���Ĵ�٤Ƥߤ�ȡ������Ǥϡְ��ߡפΤ褦�˵����졢��ñ�˸����Ф���ϡֺǽ�β��פȡֺǸ�β��פǤ���Ȥ������������Ƥ��롣���첻����¿��12���ȻҲ�����ʸ��35���ǹ��������פȤ�������ʥ�����åȡˤλ���Ǥ��꼽�ޡʤ��ä���ˤ��ʤ��������*���ȾͤΰաפʤΤǤ��롣�����ơְ��ߡפϡְ֡��פϼ���(���Ĥ���)����κǽ�β��dz����������ߡפϺǸ�β����ĸ����פȤ��ꡢ���äƤߤ�Х���ե��٥åȤΡ�A��Z�פ���������ΤǤ��ä�������ϡ��ҥ�š����Υޥ�ȥ��A-UM�פȤ�Ʊ�ͤΤ�ΤǤ��롣�Ĥޤꥤ��ɡ��衼���åѽ�̱²�ζ�ͭ��Ȥ��ơ�����ե��٥åȡ�ʸ���ˤ����ꥷ����ˤ����Ƥ⥵����åȤˤ����Ƥ�ǽ�ȺǸ�ϡ֥���ե������פȡ֥��ᥬ������פȡ����̤ʤΤǤ��롣
�Ȥʤ�С�����줬�һ�������̲᤹��ֹ����ס��ϻ����פȤϡ��ޤ��ˤ��νá��ϻΤθ��η����ˤ�äơ֥���ե��פȡ֥��ᥬ�פ��������ã���뤳�Ȥ���Ū�����ꡢ���ΡֻϤ�פȡֽ����פδ֤��⤤�ƹԤ��Ȥ���������Τ餺�Τ餺�˶����ˬ���͡���Ƨ��Ǥ������Ǥ��롣
���ܤ�ǯ��ǯ�ϤȤδؤ����ä��ʤ���Фʤ�ʤ����ȤȤ��ơ��Ȥ���������뤢���ε���Ū����Ȥ��Ƹ��ؤ˸������羾�����ɤޤġפ����롣����ˤ⤢�����٤ΥХꥨ�������¸�ߤ����ΤΡ����δ���Ū�����ϴ�ñ�˵��Ҳ�ǽ�ʤ�ΤǤ��롣�ֻ��ܤ����ݤ�������ä�«�ͤ���ΡפǤ��롣�����⤽�Ρ����ݤϼФ�˱Ԥ��Ǥ��ڤ�줿��Ρפǡ����αԳѤΤ��η����ϡ�������Ǥ����礤������ż������ΤˤʤäƤ��롣���줬������θ��ؤκ������֤����פ�Τǡ������оΤǤϤ��뤬������˴��Ԥ�����ħŪ��ǽ�ϼһ�����˸�����ֹ����פ�Ʊ�ͤǤ��롣���ʤ���֥���ե��פȡ֥��ᥬ�פ�Ʊ�ͤ˺��������֤���Ȥ����٤ʤΤǤ��롣�Ĥޤ�����βȤϡ֥���ե��פȡ֥��ᥬ�פζ��֤˷��Ƥ��Ƥ��ơ������Ϥ����ˡֽ���Ǥ���פȤ������Ȥ���ã����ΤǤ��롣��������������Ƥ���褦�ˡֿ����ɤ���פ���ΤǤ���Ȥ�������Ū���������ꤹ���ΤǤϤʤ���
 ��
��
�� ŵ��Ū���羾�פκߤ����ʥ��饹�ȤϺǤ⥷��ץ�˸�����ȿ�Ǥ��䤹����
�������ɤ����Ƥ��ΰ�Ĥ�Ĺ������ä����֤Ρֺǽ�פȡֺǸ�פˡ���������ݤĤ�«�ͤ���Ρפ��и�����Τ��Ȥ������Ȥ�ͻ����ʤ���Фʤ�ʤ����ե���ȡʥ֥�ܥ�ȡˤβ���Ǥ��ꡢŷ�ȥ��֥ꥨ��Ȥζ�����Ϣ�Τ���֥ե롼�롦�ɥ�����: Fleurs de lys�פ�ɴ��ʤ⤷���ϥ��������ĥХ��ʤɣ��ۤβ֡ˤ���ϡ����ѥȥ�å������������ȸ����뻰���դΥ������С��η��Ƥ���ϡ��֡��������å�: Shamrock���ե���� (club, clover)�����ꥷ��������Υݥ����ɥ�λ��Ļ�������ʥȥ饤�ǥ��: Trident�ˡ������Ȥβ���ʻ��ܤ���ˤʤɤ�Ʊ�ͤˡ��ֻ��Ĥ�«�ͤ�줿��Ρפ����̰��Τ�ɽ�����Ȥϸ����Ԥ��ʤ���������ξ�������פȤ����Ƥʴ�Ϣ�����뤳�ȤˤϺ�������ܤ�ʧ���٤��Ǥ��롣�����Ϥ��٤ƴ���Ū�����Ȥ�����й����뤿����ɸ��Ȥ�������뤳�Ȥ����롣

���ξϤ���Ƭ�˷Ǥ����褦�ˡ��ե롼�롦�ɥ������ϡ������ü�פ˸����ѥ�����Ǥ��ꡢ�ޤ����ˤ��ɸ��ɡʺ��ˤ��ʥ�����ɡˤ˸��������Ǥ��롣�ȥ��פ��Τ���ֻ����աפξ�ħ�������֥���֡פΤ��ȤǤ��ꡢ���겼������Ũ��Ƭ��դ�����Ū�����Ǥ���ʤޤ�����̱�ξ�ħ�Ǥ⤢��ˡ��ޤ���������ϸ��ߡ����פη��Ǹ�¸�����ΤǤ��뤬���ݥ����ɥ������ޤǤ�ʤ����ΰ��ȹͤ��뤳�Ȥ��Ǥ��롣�����Ȥβ���ʤ����⤸�ˤߤĤۤ��ˤˤĤ��Ƥϸ�Ҥ��롣
 �� �����Ȥβ���֤����⤸�ˤߤĤۤ���
�� �����Ȥβ���֤����⤸�ˤߤĤۤ���
���������ʤ복ǰ�Ȥ��ƤΡֻ��̰��ΡפȤϲ������Ȥ����䤤�ˤ�������������ʤ���Фʤ�ʤ�������ˤϡ������̰��ΡפȤ�����Τ������餫�Ρִ���Ū���ϡסֿҾ�ʤ餶���˲��ϡפȤη�ӤĤ�����Ĥ�ΤǤ���Ȥ��������Ĥ���̵��Ǥ��ʤ�����⤢�롣
�����Ĺ��˸������겼��������ˡ��罣����ǰ�Ĥθ����¸����Ԥ��Ƥ��뤳�ȤϹ����Τ��Ƥ��롣�˥塼�ᥭ����������⥴��ɤκ����������������Ρֻ˾��פθ����ˤϥ����ɥ͡��ब�դ����Ƥ������ޥ�ϥå���ײ��κǸ�ζ��̤˱������ǽ�λŪ�����ˤĤ���줿̾���ϡ֥ȥ�˥ƥ�: Trinity�פǤ��ä��������Ƹ��ߤǤ⤽�����������Ф��줿���ˤϡ�Trinity Site�פ����Ǥä����꤬�����֤���Ƥ������Ĥޤ�֤����Ϥϡ����̰��Τΰ��סʸ���ˤʤ�פȡ�
 ��
��
�� ��ϣ��פ����ä����֦��ʥ��ᥬ�ˤζǡץ���⥴��ɤκ������Ĥ�夬��Фζ� (fireball)�μ̿���
�� �� ��
�Ĥޤ�ϣ��Ѥκǽ�Ū����ɸ�Ǥ��ä��Ͱ٤ˤ��ֻ��̰��Ρפμ¸��ʶ�������ˤȤ�����Τ�������ʪ���ؤ���ɸ�ʳ˥��ͥ륮������С����ҳ��Ѵ��ˤȤδ֤ˤʤ�餫�ζ���Ū�ʰ��ס��⤷���ϡʤ������̤ˤȤäƤϡ����Ƥʰ��פ�����Ȥ������ȤǤ��롣���Τ�ϣ����Ѹ�����Τ�̩���Ѹ�ˤȳ˳�ȯ��Ϣ�Ѹ�Ȥδ֤ε����褦�Τʤ��ط��ˤĤ��ƤϤ����Ĥ��μ����뤳�Ȥ��ǽ�Ǥ��롣
�����ƥ��ʣ�����Ȱ������ݤ˾��ۤ������뤿��˳ƹ���ܺá��⤷����ű�ष�Ƥ���˻��ߤ˹�®����ϧ�Ȥ�����Τ����롣������̾�ϧ��dz���Ǥ��륦����dz�������ʳ��ˤˤ�����ץ�ȥ˥����ֺ����ѡפ��Ƥ�����礭�ʥ��ͥ륮�������뤳�Ȥ��Ǥ���Ȥ�����̴��ȯ�Ż��ߡפǤ���餷�������ƹ�ˤ�������ޤ����Ǥ�ȿ�Фˤ�ؤ�餺�����ܤǤϰ����Ȥ��Ƴ�ȯ��³�����Ƥ��롣���ι�®����ϧ�ˤϡ֤դ���פȡ֤��פ����ե�˱�����Ʊ�ͤμ¸�ϧ�ϡ֥ե��˥å����ס֥����ѡ��ե��˥å����פȤ���̾�����դ����Ƥ������Ĥޤ����ܤ˱������淿�μ¸�ϧ�ˤ��ḭ���̾��������Ƥ��ꡢ����緿�ξ��Ѥ�����ϧ�ˤϡ��ҷŤβ��ȡפ���ʸ���: Manjushri ��̾��������Ƥ��롣ʸ��ȸ��������ܤǤϡֻ��ͤ���ʸ����ηáפȤ�����?���Τ��Ƥ��뤳�Ȥ����դ����٤��Ǥ��������ֻ˾��פθ������ƤΥ����ɥ͡��ब�ֻ��̰���: Trinity�פǤ��ä��褦�ˡ������ˤ�ֻ��̰��Ρפΰż�������ΤǤ��롣�����ƺǽ�˿ͤξ����Ȥ��줿�������Ƥΰ�ĤϹ���*����Ȥ���Ƥ��ꡢ�����Ϥϡֻ��ܤ���פθλ���䤷���Ȥ���������Ȥȿ����Ĥʤ��꤬���롣
�������ե��˥å������Ի�Ļ�ˤˤϡֳ��פ���ᴤ�����ɡפΥ�����Ȥ���ϣ��ѿ��Ǥˤ⸽����ΤǤ��롣
* ������ϸ��Ȥ��륵�å�����������֥���ե�å�������̿̾���줿�Τˤϡ����ե�å��������ʤ���ˡפȤ�����ƥ�ʥ����ꥢ�˸��פ碌�벻��Τä���Ʊ���ˡ֣��ե�å����פĤޤ�ֻ��ܤ���פˤ��ʤ�Ǥ���Ȥ����ä�ͭ̾���äǤ��롣����������५�顼�ϡ��֡פȡ��ġפκ��硢���ʤ���ֲФȿ�������פη�̤ˤ�ä�������ֺǸ�ο��ס����뤤�ϥ��ꥹ�ȶ���Υ��Ȥλ����ʥ��ꥹ�������塢���������λ����ˤ˻Ȥ������ʤ뿧�ֻ�פ���Ѥ��Ƥ��뤳�Ȥˤ����ܤ��٤��Ǥ��롣����ˤϡֻ��̰��Ρפθλ��ȤȤ�˳ˤ�ż������ħ�����Ǥ˸�����ΤǤ��롣
�����ƤҤȤĤΡ������䤬�դ��Ĥΰ�̣����ġ����ʤ���ֻϤޤ�פǤ���ֽ����פǤ���Ȥ������Ȥϡ�����������ҡפǸ��Ƥ����褦�ˡ�Ʊ��Τ��Ȥ���������ɽ���Ƥ��롣����ϡ���Ĥλ���Ū�ʼ����ι�֡פ�����ΤȤ������Ȥ��Ǥ��롣����ˡ��ݤ������ˤʤäƤ��������Ҥ��������ʬ���ڤ���ߤ�����ơ����������ǤǤ��Ƥ����ΤǤ��뤫�Τ褦��ʿ�̤ؤȡ�Ÿ���פ���С������Τ��Ȥʤ��餽���������ʬ��������ֻϤޤ�פǤ���ֽ����פǤ�����ʬ�Ϻ����оΤ����֤����ΤǤ��롣��̩�˻��֤��ֲפ����ΤǤϤʤ���ľ��Ū�����Բĵ�Ū�˿ʹԤ����ΤǤ���ȹͤ���С����Ρ�����פ϶����˸����뵼����Τ褦�ˡ��ۤ����ֳ֤�������Ǥ��������Ȥ��������ʤ���
������סֹ����ס��羾�פ��͡���ɽ�ݤǾ�ħ������ΤȤ�Ʊ��Τ�ΤǤ���Ȥ������Ȥ��Ǥ��롣
23:19:48 -
entee -
TrackBacks
2005-10-11
�ֶ��פؤ������
����Ū�ʡ־�������ȡ��������������ΡΣ���
�������ƻ�βȸ��ε����ΰ�Ĥˡֽ���פȤ�����Τ����롣ǯ�Ϥˤ���������ޤ�ú������Ф�����������Ω�Ƥƾ��Ԥ�������������Ȥ�����ΤǤ��롣�⤦���줳�콽ǯ�ʾ������äˤʤ뤬�������ޤ�ζ��ˤ�ؤ�餺��α���褫�鵢�äƤ��ƴ֤�ʤ��Ρ�������ʹ����Τ����٤ƿ����˴�����줿�����ˡ�������Ȥβȸ��γ��Ť������ε����˾���ĺ���Ȥ����ޤ��Ȥʤ������˷äޤ줿�ΤǤ��ä�����Τ褦�ʤޤä��������ƻ�������Ԥ����������ΰ�������֤ߤ뤳�Ȥε������ֳ����줿�ײ�ʤΤǤ��롣
���Ρֵ����פκ���ˤ����Ĥ�����ɮ���٤�ȯ�������ä�����������Ǥ�˺��뤳�Ȥν���ʤ������ʪ�ʡפ����ν�����о줷��������ϡ������ҡפȸƤФ���ΤǤ��ä������ҤˤϤ��������ʼ��ब����褦���������������ҤȸƤФ���Τϡ��������Ҥγ��������̾�����⤷���Ϥ���˽स��ʸ����ɮ�ǽ�Ƥ��ꡢ���줬����äȰ�䤹��褦�ˤʤäƤ��롣��ǯ���������ȡ��ޤ��ǽ餫��Ʊ��������Ȥ����ߴľ��ˤʤäƤ��ơ��֤����̣�פ���ã����Τ�����������ޤ��ˤ����ҤΡʱ��Ρ˷������褫���줿�ǥ�����ȤʤäƤ���ΤǤ��ä���
�Ȥ�櫓����ܤ���館�������ʤ��ä��Τϡ��������Τ⤽���Ǥ��ä�������䤹��Ȥ��������ʤ����ΡֻϤ�פȡֽ����פνвȤ�����������Ƥ�������ο����Ǥ��ä������줬���ޤ�˶�ò���٤���ΤǤ��ä��Τǡ��ְ��Τ���Ϥɤ��������Ȥ��פ��š��ȿʹԤ������ε����κ���˻פ鷺���ּ��֤�餸����

����ϼ̿��Ǥ����ˤʤä�ʬ����褦�ˡ�����פǤ��ä�����ΰ��ͤʤޤǤδؿ��˴����ۥ��Ȥ������������������٤ˤ�ؤ�餺����ˤ�����餵��ˤ����Ĥ��������Ҥ���äƤ��ơ��̤���Ƥƻ�˲Ƥ������ä��ΤǤ��ä��������Ƥ��㤬��äƤ�������������פ�¸ʬį��뤳�Ȥ����褿�Τ��ä���
���Ҥη����俧�������ƽ�Ƥ���ʸ���ζ���Ū���ƤϤ��ޤ��ޤ��ä������ɤ�ⶦ�̤��ƺߤ�Τ����������ħ�ʤΤǤ��ä�������ϡֻ��ĤβФζ�*�פΤ褦��������Ƥ��뤳�Ȥ⤢��С���Ĥ������夹��褦��������Ƥ����Τ⤢�äơ���ʬ�ΥХꥨ��������ǧ�����ΤǤ��뤬�����λϤޤ�Ƚ�������������Ȥ����˽и�����֤���פϡ��ɤ��dz����褦��������������פǤ��뤳�Ȥ϶��̤ʤΤǤ��ä���
* ���Ρ֣��ĤǤҤȤĤΥڥ��פ������Ƥ�������ο����ˤĤ��ƤϤޤ��̤ε����������Ǥ�������


�� ���ȥ�å�����˱��������θ�����֥�ȥ������ӡ���פˤ⸫�Ф�����α���Ȥ����٤������¡פΥѥ�����
����Ǥϡ�����Ȥϲ����ס�̵�����λ��ˤ���ʤ��������������ΤǤ��뤬�����줬���ν��פ��ܼ��˿���������Ǥʤ��ä��Ȥ��Ƥ�ۥ��Ȥ��դ�뤳�ȤϤǤ��ʤ��������ۥ��Ȥˤ��С�����Ȥϡ���ʪ�ζ̡ʤ��礯�ˡפǤ��ꡢ��ƴ���ʤƳ������ܻؤ��٤�º�������פʤΤǤ��ä��������ʹ�����Ȥ���������Ϣ�ۤ����Τ�ϣ��Ѥˤ����Ƴ������ܻؤ��٤���Ūʪ�Ǥ���ֶ�ס����뤤�ϡֶ�פΥ����ɤ�ɽ������ΤǤ��ä����缭�Ӥˤ��С��֡�ʩ�� �������Ȥ��ꡢ�б꤬dz���夬�äƤ����ͻҤ�ɽ�����̡�����ˤ�äƻפ����Ȥ����ʤ�������⤯��ǡ����������
�ޤ�����ϡ�������ȹͤ����ŷ���ؤȡ־徺�פ����Τ�ż���������ȤȤ뤳�Ȥ��Ǥ��뤬��Ʊ���˿�ũ�Τ褦��ª������硢������Ͼ�˸����äơֲ��ߡפ��벿����ż����뤳�Ȥˤʤ롣���ξ�ħ�ˤϿ�ľ�����ؤα�ư�����ʤ���־徺�פȡֲ��ߡפȤ���������Ƥ���ΤǤ��롣������դ����ΤȤ��Ʋ��Τ褦�ʵ��Ҥ����롣
ǡ�������ͳ��ˤϼ���⤬����餷������ʩ�������Ѳ�������Ρ�ζ����Ƭ���椫����Ф��줿��Ρ��������Asura�ˤȤ��襤�κݤ����ŷ����郎�դ��ƿʹֳ����������Ρ��ʹ֤����Ԥ��ɤ�������Ȥ��ƤҤȤ�ǤˤǤ�����ΡפʤɤȤ���������Ƥ��롣�äˤ��������ܤ��٤��ϡ����Ρֻ����פ������ŷ��Indra: ����ɥ�ˤȴؤ�꤬����Ȥ��������Ƥ��뤳�ȤǤ�������Ϥε��ҡ��ֶ��פؤ�����⥨�ꥢ���Ǹ�Ͽ #3 �����ˡ������⤽���ˤ϶��������פΰż������롣�����ơֱ�פȤδ�Ϣ�ϡ����η�����������������ϵ������Ƥ��;�ϤΤʤ���ΤǤ��롣
�Ĥޤ�ɤ�������˸��äƤ�֤������Ĥλ���Ū�ʼ����ι�֡פ����֤���Ƥ��ơ�����Ϥޤ��ˤ��Ρּ����ι�֡פ������롢ήưŪ�ǡ֥�����Ū�ʡ��֡ס����С����ꥢ���ǡˤΡ��ħ��θ���Ū�����ν��פʤҤȤĤȻ�Ƽ����Τ˰㤤�ʤ��ä��ΤǤ��롣
����������η����Ȥ����ΤϤ���줬�Ǥ�ֿƤ���Ǥ���פ�ΤȤ��Ƥϡ������뵼����ʤ��ܤ������ܤ����ˤȤ���������ʩ�դβ����ʤɤ˿����դ����Ƥ��륿�ޥͥ��ʥͥ��β֡��ͥ�˷��˾��Ρ־���פǤ��롣�����Ĥ������Υ��Τ褦�ʷ���פ碌���Τϡ��¤��������Ϥ˸��Ф���롣�ä����ʤ��Ͻ�ˤ����ơ����������ܤǤ��㤨�ж��ʲ���������ƻ���β����ξ�˺ܤ����Ƥ�������ʡֲ���Τ��ޤͤ�����ͭ̾�Ǥ��롣�����餯���ܤǺ���������ΤҤȤĤȸ����뤫�⤷��ʤ������줬����ƻ�פ�Ԥʤ�����ξ��ˡֵ���Ū�ˡ����Ƥ��뤳�Ȥˤ����ܤ��٤��Ǥ��롣�ޤ����������ǤϤ��Τ褦�ʥɡ������ä��⥹���Ϥ�����Ǥ⤢�롣������¿�����ֶ�פ���̤���Ƥ���ֶ�פȤδ�Ϣ���ż�����Ƥ���*�ΤǤ��롣
���ܹ�����ܤ��᤻�С������������ҤǸ��Ф���������Ƥ�ĺ�����֤���Ƥ����ΤǤ��롣����ˤϤޤ��̤����������ꡢ�����Ƥι�¤�ϲ����顢�ϡ��塦�С��������ν���ǿ�ľ���¤٤��Ƥ���ΤǤ��롣�������餹��Ф��������ƾ�ε�����ϡ��ֶ��פ����������Ǥ��롣

�������������
* ����ɥ������������ǡ��ѥ�������γ�ʼ����¤�˴ؤ�ä�����ʪ������Τ���ؤ����̤����Ǻǽ�Ū����Ū�����ʤ���ֳ˥��ͥ륮������С�����ȯ�פμ¸��Υץ��������Ľ��Ȥ������Υ��硼���ˤ�ä������줿���Υ����η������ޤ��ˡ�����פǤ��ä����Ȥ�̵�ռ��Ǥ��ä��ˤ��衢�ҤȤĤ��ķ��ζ�ͭ��ɽ���Ƥ���Ȥ����ͤ����ʤ��ä������α����Ǥ��ζ������뤫����٤Υ⥹���Υ��ޥͥ�����������˸��äƤ���Τ��Ǥ��Ф��줿�Τ��ϸ�ƨ���ʤ��ä���
������������С������Ǥ��Ρַ����פ������˼��������Τ���memento mori�סʻ���ۤ��Ф����Ȥ�����å�������¾�ʤ�ʤ������ʤ���ֻϤޤ�פ����äơֽ����פ�����֤���פ����ʱ�Ǥʤ����Ȥ��۵�����Ȥ�����å������ʤΤǤ��ꡢ¿���οͤˤ�ä�į��뤳�Ȥ��Ǥ�����ʲ����ξ�ʤɡˤ�Ʋ���ȷǤ����Ƥ���ΤǤ��롣�⥹������ƻ�ۤȤ��ä����ߤΡ�Ƭ��פˡ������ơ�������ĺ���פ˿����֤����ΤǤ��롣
����ϸĿͤλ� (small death) �˴ؤ�꤬�ʤ��ȸ����и���Ǥ��뤬������Ū�ˤϽ���Ū�ʤ���礭�ʿ���ηи��������ȤΤ���ֻ�פؤε�����Ƥӵ�������ΤǤ��롣�����Ƥ����Ʊ���ˡֱߴġפǤ���ʾ塢̤���ؤ�������ΤǤ��롣���줬����Ū�ʸĿͤλ�ǤϤʤ�������Ū�ʻ�Ǥ���Ȥ����ˤ��Ρ������䤬��˽���Ū�ʤ�Τ˽���Ƥ�����ͳ�����롣�����ƽ����ϡʤȤ�櫓�������ν����ˤ����ơˤ��Ρֻ�פβ�����ηä������ΤȤ���ȯŸ�������������λ�ε����ζ�ͭ�ʤ������������٤��뵷�⤢�����ʤ��ΤǤ��롣
���ơ��������ä������
����������տ�������������椵�줿ú�ȱꡢ�����ƲФˤ�ä��ä���줿Ŵ�ӡ�����Ѥ����̤ΤҤȤġˤ���Ǽ�Ω�Ƥ�쵷��Ū���������줿�ֿ�פϡ��Ǵ��ˡ��Сפ��դμѽ�����Ф��롣�����ơ��������ˤ��٤�����פλܤ��줿ƻ���������տ��������줿�п��Τɤ��ɤ��αաʤ�ǻ����ˤ�γ��ǺǴ��˲������ߤ�Ȥ����������礤�ʤ뿨ȯ��������Τ��ä�������ϤۤȤ�ɡ��Ǥ����٤���������
���ƻ������ۤɤޤǤ˷ɰդ�ʤ���¸������褿�Τϡ��ޤ��ˤ��αʱ���뵷�Ȥ��ζ�ͭ�˴ؤ��������Τ�����¾�ʤ�ʤ��Ȥ����ο���������������Ϥޤ�����̩�ζ�ͭ�ʶ��ȴط��ؤλ����ˤε����ʤΤǤ��롣���ˡ������Ȥ϶��������ޤǤ�̵�̤ʤ����������줿ư���ƻ����̤����ݻ����줿�ۥ��Ȥȥ����ȤȤΤ������δ����ʤ����ҵ���Ǥ����뵷�����ʤΤǤ��ä��������ˤϤ��뤤�Ϥޤ����ե�ᥤ����ε��餵��ο�魯��褦�ʾ�ħ�ηϤ��ݻ��������Ρַ�ҡפȹͤ���٤���ͳ�����롣
�����ƻ�ˤȤäƤϡ�����ͪ�פ��Τ���³���Ƥ���ؤ��̲ᵷ��ʥ��˥����������ˤ����ޤ��������ԤؤΥ��˥����������Ȥ��Ƶ�ǽ�����ִ֤��ä��ΤǤ��롣
��Ϣ���Ȳв֡ɤ餻�������ֶ��פؤ�������³�ԡ�
���Ρֵ����פκ���ˤ����Ĥ�����ɮ���٤�ȯ�������ä�����������Ǥ�˺��뤳�Ȥν���ʤ������ʪ�ʡפ����ν�����о줷��������ϡ������ҡפȸƤФ���ΤǤ��ä������ҤˤϤ��������ʼ��ब����褦���������������ҤȸƤФ���Τϡ��������Ҥγ��������̾�����⤷���Ϥ���˽स��ʸ����ɮ�ǽ�Ƥ��ꡢ���줬����äȰ�䤹��褦�ˤʤäƤ��롣��ǯ���������ȡ��ޤ��ǽ餫��Ʊ��������Ȥ����ߴľ��ˤʤäƤ��ơ��֤����̣�פ���ã����Τ�����������ޤ��ˤ����ҤΡʱ��Ρ˷������褫���줿�ǥ�����ȤʤäƤ���ΤǤ��ä���
�Ȥ�櫓����ܤ���館�������ʤ��ä��Τϡ��������Τ⤽���Ǥ��ä�������䤹��Ȥ��������ʤ����ΡֻϤ�פȡֽ����פνвȤ�����������Ƥ�������ο����Ǥ��ä������줬���ޤ�˶�ò���٤���ΤǤ��ä��Τǡ��ְ��Τ���Ϥɤ��������Ȥ��פ��š��ȿʹԤ������ε����κ���˻פ鷺���ּ��֤�餸����

����ϼ̿��Ǥ����ˤʤä�ʬ����褦�ˡ�����פǤ��ä�����ΰ��ͤʤޤǤδؿ��˴����ۥ��Ȥ������������������٤ˤ�ؤ�餺����ˤ�����餵��ˤ����Ĥ��������Ҥ���äƤ��ơ��̤���Ƥƻ�˲Ƥ������ä��ΤǤ��ä��������Ƥ��㤬��äƤ�������������פ�¸ʬį��뤳�Ȥ����褿�Τ��ä���
���Ҥη����俧�������ƽ�Ƥ���ʸ���ζ���Ū���ƤϤ��ޤ��ޤ��ä������ɤ�ⶦ�̤��ƺߤ�Τ����������ħ�ʤΤǤ��ä�������ϡֻ��ĤβФζ�*�פΤ褦��������Ƥ��뤳�Ȥ⤢��С���Ĥ������夹��褦��������Ƥ����Τ⤢�äơ���ʬ�ΥХꥨ��������ǧ�����ΤǤ��뤬�����λϤޤ�Ƚ�������������Ȥ����˽и�����֤���פϡ��ɤ��dz����褦��������������פǤ��뤳�Ȥ϶��̤ʤΤǤ��ä���
* ���Ρ֣��ĤǤҤȤĤΥڥ��פ������Ƥ�������ο����ˤĤ��ƤϤޤ��̤ε����������Ǥ�������


�� ���ȥ�å�����˱��������θ�����֥�ȥ������ӡ���פˤ⸫�Ф�����α���Ȥ����٤������¡פΥѥ�����
����Ǥϡ�����Ȥϲ����ס�̵�����λ��ˤ���ʤ��������������ΤǤ��뤬�����줬���ν��פ��ܼ��˿���������Ǥʤ��ä��Ȥ��Ƥ�ۥ��Ȥ��դ�뤳�ȤϤǤ��ʤ��������ۥ��Ȥˤ��С�����Ȥϡ���ʪ�ζ̡ʤ��礯�ˡפǤ��ꡢ��ƴ���ʤƳ������ܻؤ��٤�º�������פʤΤǤ��ä��������ʹ�����Ȥ���������Ϣ�ۤ����Τ�ϣ��Ѥˤ����Ƴ������ܻؤ��٤���Ūʪ�Ǥ���ֶ�ס����뤤�ϡֶ�פΥ����ɤ�ɽ������ΤǤ��ä����缭�Ӥˤ��С��֡�ʩ�� �������Ȥ��ꡢ�б꤬dz���夬�äƤ����ͻҤ�ɽ�����̡�����ˤ�äƻפ����Ȥ����ʤ�������⤯��ǡ����������
�ޤ�����ϡ�������ȹͤ����ŷ���ؤȡ־徺�פ����Τ�ż���������ȤȤ뤳�Ȥ��Ǥ��뤬��Ʊ���˿�ũ�Τ褦��ª������硢������Ͼ�˸����äơֲ��ߡפ��벿����ż����뤳�Ȥˤʤ롣���ξ�ħ�ˤϿ�ľ�����ؤα�ư�����ʤ���־徺�פȡֲ��ߡפȤ���������Ƥ���ΤǤ��롣������դ����ΤȤ��Ʋ��Τ褦�ʵ��Ҥ����롣
ǡ�������ͳ��ˤϼ���⤬����餷������ʩ�������Ѳ�������Ρ�ζ����Ƭ���椫����Ф��줿��Ρ��������Asura�ˤȤ��襤�κݤ����ŷ����郎�դ��ƿʹֳ����������Ρ��ʹ֤����Ԥ��ɤ�������Ȥ��ƤҤȤ�ǤˤǤ�����ΡפʤɤȤ���������Ƥ��롣�äˤ��������ܤ��٤��ϡ����Ρֻ����פ������ŷ��Indra: ����ɥ�ˤȴؤ�꤬����Ȥ��������Ƥ��뤳�ȤǤ�������Ϥε��ҡ��ֶ��פؤ�����⥨�ꥢ���Ǹ�Ͽ #3 �����ˡ������⤽���ˤ϶��������פΰż������롣�����ơֱ�פȤδ�Ϣ�ϡ����η�����������������ϵ������Ƥ��;�ϤΤʤ���ΤǤ��롣
�Ĥޤ�ɤ�������˸��äƤ�֤������Ĥλ���Ū�ʼ����ι�֡פ����֤���Ƥ��ơ�����Ϥޤ��ˤ��Ρּ����ι�֡פ������롢ήưŪ�ǡ֥�����Ū�ʡ��֡ס����С����ꥢ���ǡˤΡ��ħ��θ���Ū�����ν��פʤҤȤĤȻ�Ƽ����Τ˰㤤�ʤ��ä��ΤǤ��롣
����������η����Ȥ����ΤϤ���줬�Ǥ�ֿƤ���Ǥ���פ�ΤȤ��Ƥϡ������뵼����ʤ��ܤ������ܤ����ˤȤ���������ʩ�դβ����ʤɤ˿����դ����Ƥ��륿�ޥͥ��ʥͥ��β֡��ͥ�˷��˾��Ρ־���פǤ��롣�����Ĥ������Υ��Τ褦�ʷ���פ碌���Τϡ��¤��������Ϥ˸��Ф���롣�ä����ʤ��Ͻ�ˤ����ơ����������ܤǤ��㤨�ж��ʲ���������ƻ���β����ξ�˺ܤ����Ƥ�������ʡֲ���Τ��ޤͤ�����ͭ̾�Ǥ��롣�����餯���ܤǺ���������ΤҤȤĤȸ����뤫�⤷��ʤ������줬����ƻ�פ�Ԥʤ�����ξ��ˡֵ���Ū�ˡ����Ƥ��뤳�Ȥˤ����ܤ��٤��Ǥ��롣�ޤ����������ǤϤ��Τ褦�ʥɡ������ä��⥹���Ϥ�����Ǥ⤢�롣������¿�����ֶ�פ���̤���Ƥ���ֶ�פȤδ�Ϣ���ż�����Ƥ���*�ΤǤ��롣
���ܹ�����ܤ��᤻�С������������ҤǸ��Ф���������Ƥ�ĺ�����֤���Ƥ����ΤǤ��롣����ˤϤޤ��̤����������ꡢ�����Ƥι�¤�ϲ����顢�ϡ��塦�С��������ν���ǿ�ľ���¤٤��Ƥ���ΤǤ��롣�������餹��Ф��������ƾ�ε�����ϡ��ֶ��פ����������Ǥ��롣

�������������
* ����ɥ������������ǡ��ѥ�������γ�ʼ����¤�˴ؤ�ä�����ʪ������Τ���ؤ����̤����Ǻǽ�Ū����Ū�����ʤ���ֳ˥��ͥ륮������С�����ȯ�פμ¸��Υץ��������Ľ��Ȥ������Υ��硼���ˤ�ä������줿���Υ����η������ޤ��ˡ�����פǤ��ä����Ȥ�̵�ռ��Ǥ��ä��ˤ��衢�ҤȤĤ��ķ��ζ�ͭ��ɽ���Ƥ���Ȥ����ͤ����ʤ��ä������α����Ǥ��ζ������뤫����٤Υ⥹���Υ��ޥͥ�����������˸��äƤ���Τ��Ǥ��Ф��줿�Τ��ϸ�ƨ���ʤ��ä���
������������С������Ǥ��Ρַ����פ������˼��������Τ���memento mori�סʻ���ۤ��Ф����Ȥ�����å�������¾�ʤ�ʤ������ʤ���ֻϤޤ�פ����äơֽ����פ�����֤���פ����ʱ�Ǥʤ����Ȥ��۵�����Ȥ�����å������ʤΤǤ��ꡢ¿���οͤˤ�ä�į��뤳�Ȥ��Ǥ�����ʲ����ξ�ʤɡˤ�Ʋ���ȷǤ����Ƥ���ΤǤ��롣�⥹������ƻ�ۤȤ��ä����ߤΡ�Ƭ��פˡ������ơ�������ĺ���פ˿����֤����ΤǤ��롣
����ϸĿͤλ� (small death) �˴ؤ�꤬�ʤ��ȸ����и���Ǥ��뤬������Ū�ˤϽ���Ū�ʤ���礭�ʿ���ηи��������ȤΤ���ֻ�פؤε�����Ƥӵ�������ΤǤ��롣�����Ƥ����Ʊ���ˡֱߴġפǤ���ʾ塢̤���ؤ�������ΤǤ��롣���줬����Ū�ʸĿͤλ�ǤϤʤ�������Ū�ʻ�Ǥ���Ȥ����ˤ��Ρ������䤬��˽���Ū�ʤ�Τ˽���Ƥ�����ͳ�����롣�����ƽ����ϡʤȤ�櫓�������ν����ˤ����ơˤ��Ρֻ�פβ�����ηä������ΤȤ���ȯŸ�������������λ�ε����ζ�ͭ�ʤ������������٤��뵷�⤢�����ʤ��ΤǤ��롣
���ơ��������ä������
����������տ�������������椵�줿ú�ȱꡢ�����ƲФˤ�ä��ä���줿Ŵ�ӡ�����Ѥ����̤ΤҤȤġˤ���Ǽ�Ω�Ƥ�쵷��Ū���������줿�ֿ�פϡ��Ǵ��ˡ��Сפ��դμѽ�����Ф��롣�����ơ��������ˤ��٤�����פλܤ��줿ƻ���������տ��������줿�п��Τɤ��ɤ��αաʤ�ǻ����ˤ�γ��ǺǴ��˲������ߤ�Ȥ����������礤�ʤ뿨ȯ��������Τ��ä�������ϤۤȤ�ɡ��Ǥ����٤���������
���ƻ������ۤɤޤǤ˷ɰդ�ʤ���¸������褿�Τϡ��ޤ��ˤ��αʱ���뵷�Ȥ��ζ�ͭ�˴ؤ��������Τ�����¾�ʤ�ʤ��Ȥ����ο���������������Ϥޤ�����̩�ζ�ͭ�ʶ��ȴط��ؤλ����ˤε����ʤΤǤ��롣���ˡ������Ȥ϶��������ޤǤ�̵�̤ʤ����������줿ư���ƻ����̤����ݻ����줿�ۥ��Ȥȥ����ȤȤΤ������δ����ʤ����ҵ���Ǥ����뵷�����ʤΤǤ��ä��������ˤϤ��뤤�Ϥޤ����ե�ᥤ����ε��餵��ο�魯��褦�ʾ�ħ�ηϤ��ݻ��������Ρַ�ҡפȹͤ���٤���ͳ�����롣
�����ƻ�ˤȤäƤϡ�����ͪ�פ��Τ���³���Ƥ���ؤ��̲ᵷ��ʥ��˥����������ˤ����ޤ��������ԤؤΥ��˥����������Ȥ��Ƶ�ǽ�����ִ֤��ä��ΤǤ��롣
��Ϣ���Ȳв֡ɤ餻�������ֶ��פؤ�������³�ԡ�
22:53:00 -
entee -
TrackBacks
2005-10-06
��Ĥμ����Υ�쥤�������ۤ�
���ꥢ���Ǹ�Ͽ #4
��������ޤ���Ǥ�����ǯ�κǸ�η�Ǥ��ä����ᡢ�������Ĥλ���Ū�ʼ����ι�֤������롢ήưŪ�ǡ֥�����Ū�ʡ����碌��äƤ��������Ϥϰ������ǽ����ߤ�����Ԥ��Ͼ�˵��뤳�Ȥ�����롣�ޤ�����ڥ륫�ꥢ�κפ꤬���Ԥ����Τ��Ϥ����ǡ�������ֿ�ǯ�פˤ�äƾ�ħ����������ι����ʡ������ε���Ū����¤�ˤ�������롢����Ū�ʾ��������Ǥ��ä���
���ܤ�����ˤ������Ū��������פ����Ǥ���ǻ���Ĥ���Ƥ��롣�����������ε���Ū����¤�פǤ���Ȱռ����Ʋᤴ���ͤϡ�æ�������ʹԤ����������ܤǤ϶Ϥ��Ǥ������������������ε���Ū�����Ϻ��ˤ���ȴ�����������äƤ��롣
��Ĥκ���Ƚ���ꡢ�����ƶϤ��ʿ��Υ��Х��С�����¸�ԡˤˤ�����������ε���ϡ�����������ʸ������Ǥϡ�������Ū�ʷ��������Ƥ��롣���κǤ����Τ����ֲ�ۤ��סʥڥ��ϡ�: Passover�פǤ��롣�ֲ�ۤ��פȤϸ����ޤǤ�ʤ�����ΡֽХ����ץȵ��פǵ��Ҥ���Ƥ����������Ƹ���ȥ����ץȤ���Υ⡼��Ψ��������̱²������æ�Ф�̱²���Ϥ�����ɶ��ֲ�ۤ��פ����ȵ�ǰ����Ի��Ǥ��롣���������ߤΡֲ�ۤ��ספϤ����ǰ���뤳�Ȥ���¤ˤ�������С֥��ꥹ�ޥ���������ˤ�äƤ����褦�ʡס�Exodus: æ��������ˤ��˽˺�Ū��ʷ�ϵ�����ġֻ�Ū���Ȳ����Ƥ��롣�����⡢�ɤ���餽�Τ褦�ʰ�̣�礤���Ѽ����Ƥ����Τϥ��������������ֿ���λ���פˤ��Ǥˤ����Ǥ��ä��褦�Ǥ��ꡢ�����ͻҤΰ�ü����ʡ����פ���ˤ⸫�Ф���롣
�ޤ��˥������������������ֶ������פȤϡ������ο͡����ֲ�ۺספ�ˤ�����ν����˵ޤ������������פǤ��ä����Ȥ�ʬ���äƤ���櫓�Ǥ��롣���⤽�⥤�����η��ब��13���ζ������פǤ��ä����Ȥʤ�����ε��Ҥ˵������ΤǤϤʤ��������ޤǤ�̱�������ˤ�äƤǤ����ʤ���������13���Ǥ��ä��פȤ������Ȥξ�ħŪ��̣������������ǤϤʤ��ΤǤ����ǾܽҤ��ʤ������㤽��䤬�������Τ��ֶ������פǤ��ä����Ȥˤϡ�����������������ˤ�����ֲ�ۺס��Ҥ˺����ä����Ǥ���ʻ˼¤Ȥ��Ƥ��ϡ������ޤǤ��ħŪ�ʰ�̣�ǡˡ������ơ�������ĤΡ㥤�٥�ȡ�ʡ֥��ꥹ�Ȥη���ڤ�����פȡ֥����̱²��æ�Х��Х��Х�סˤΡֵ���Ū���ספϡ�����ޤ������ǤϤʤ����������������ι������ָ�������������Ū���ݡפȤ��ƶ�ͭ����Ƥ��뤳�Ȥ��̣���Ƥ���ΤǤ��롣
���ơ��ݤä����ܤˤ���������Ȥϡ���ǯ�������Ƥ��ޤ��б��Τ褦�ʡ��ż�פȸ��������������פ�����ǯ�֤Ǥ��ü�ʰ�̣�礤����ġ����ʤ�����פȤʤ�櫓�Ǥ��뤬�����ε������Ť��˲ᤴ������ˡ�ǯ�����äˡֳ����ס��糢���פΣ����ϡ���䲼�ؤ���˻�����ֻ��֤Ȥ��襤�פ�������褹���ΤȤʤ롣�ޤ�Ǥ���ŵ��Ū�ʡֻ��������ʡפ����������ʶ������ˤ����װʹߤϡֲФ����ƤϤʤ�ʤ��סֲФ��̤�����ʪ����ˤ��ƤϤʤ�ʤ��פȤ������ʤʥ�����Χˡ�Ȥ��ƤǤ��뤿��ˡ�ɬ��ˤʤäƺפο����ȵ����ο����ν������ʤ���Фʤ�ʤ�¿���Υ����Ͳ�²��פ碌��ۤɤΤ�ΤǤ��롣��۸�Ρʿ�ǯ�Ρ˿����ϲФ�ä����ʤ��Τ��䤿���ʲФ��̤��ʤ��Ƥ��ɤ��褦�ʡ˿���ʪ�Ȥʤ롣����ϡ����ܤ�����ξ��ϡָ���ʤ������������סʤȤ���̾�ζ۵ޥ����ܥå����ˤȤʤ롣����⤳����۸�ο���������ˤ��Ť��˲��⤻���ʻŻ����ˤ˲ᤴ�����Ȥ��ˤ�ƽ��פ��Ȥ�����ǰ��ͭ���Ƥ������Ǥ��롣
�����Ρֲ�ۤ��פǽ��פʿ���ʪ�ˤϥ����襦�掠�Ӥ��ݼ�ʤɤ����Ĥ������Ǥ����뤬��������ΤҤȤĤˡ֥ޥåĥ��פȸƤФ��ּ�̵���ѥ�: unleavened bread, azyme�פ����롣����ϡ��������ȶݡʹ���ˤ������ȯ�ڤ����Ĥ�ޤ����̾�Υѥ�Ȱۤʤ�ޤä����դä��餷�Ƥ��ʤ����������ᥪ���ɥ֥�Υ���å����Τ褦�ʼ¤�̣���ʤ��ѥ�ѥ�����äڤ餤�緿�ѥ�Ǥ��롣����ϡֽХ����ץȡפȤ����������פˤ�����ɶ�δ����桢ȯ�ڤ��������̾�Υѥ������ã�����٤��ʤ��ä��פȤ���̱²�ε�����α��褦�Ȥ����տޤ����롢�ȡʲ�Ĺ�ˤ�äơ���������뵷���ΰ����Ǥ��ꡢ��ۺפδ����桢���äȥơ��֥�ξ�ˡֽŤͤ����֤��֤���Ƥ��ꡢ�������֤ۤ��Ƥ���ΤǤ��롣
�����ɤ����ͳ�Ǥ������ܤˤϿ�ǯ�����Ƥ��Ф餯���̾�Ρ��Ȥ����ơʤ��ӡˤ٤ʤ��פȤ������������������Ū�ˤϤۤȤ�ɶػߤ���ƥ֥졼����ݤ�������줿�褦�ʴ����Ǥ⤢��ˡ��������ꡢ���Ƥ�ȤäƤ��餫������ʤġˤ��Ƥ���֥���פ٤�ΤǤ��롣����⤪���餯��Ȥ�Ȥϡ��Ф�Ȥ�ʤ��Ǥ�٤�����¸���Τ褦�ʤ�ΤȤ��ơ�ǯ�֤Ǥ�����δ��ָ�����о줹�롢�ˤ�Ƶ���Ū���Ǥζ�������ʪ�Ǥ��롣��¸�ΤΤ褦�ˡ����Υޥåĥ��ʤ�̥���ϽŤͤ����ʤ���ˤ�����٤�����Ū���֤������֤����ΤǤ��롣
�����ޤǵ��Ҥ�����Ǥ⡢�����̱²�����ܿͤȤδ֤Ρ��ԲĻĤʰŹ�פ�Ĵ����Τ���������Ū�ǤϤʤ����¤äݤ������ʡ���ͱƱ�����פ�Ÿ�����褦�ȸ����ΤǤ�ʤ��������äϤ��Τ褦���ä����ڤ����礭�ʥե졼����äʤΤǤ��롣
�����ǤϤʤ��ơ��֡�ǯ�κǸ�η�ɤΡ���Ĥλ���Ū�ʼ����ι�֡ɤ������롢ήưŪ�ǡȥ�����Ū�ʡɾ��֡פ���¤ʺƸ��������ܿͤȥ����ͤ�ξ���˸��Ф����Ȥ������Ȥ�¾�ʤ餺�������������ν���ʳ��Ǥϡּ��Ǥʤ�Τ������˽���ʤ��פȤ������֤Ǥ��ä����Ȥ������Ǥ���Ȥ������ȤʤΤǤ��롣�����ơ�����ϲ��β��餫�Ρֶ���פ�ǰ�����ΤȤ��ƽ���夬�ä��ҤȤĤΡֵ����ѡפ˴ط��Τ����ΤʤΤǤ��롣
���ꥢ���ǡ�����������II�١ֻ�Ū�������ڥʥƥ�����쥹���ޥͥ���
page 125���������ϰ��ѼԤˤ���
page 125���������ϰ��ѼԤˤ���
���ܤ�����ˤ������Ū��������פ����Ǥ���ǻ���Ĥ���Ƥ��롣�����������ε���Ū����¤�פǤ���Ȱռ����Ʋᤴ���ͤϡ�æ�������ʹԤ����������ܤǤ϶Ϥ��Ǥ������������������ε���Ū�����Ϻ��ˤ���ȴ�����������äƤ��롣

��Ĥκ���Ƚ���ꡢ�����ƶϤ��ʿ��Υ��Х��С�����¸�ԡˤˤ�����������ε���ϡ�����������ʸ������Ǥϡ�������Ū�ʷ��������Ƥ��롣���κǤ����Τ����ֲ�ۤ��סʥڥ��ϡ�: Passover�פǤ��롣�ֲ�ۤ��פȤϸ����ޤǤ�ʤ�����ΡֽХ����ץȵ��פǵ��Ҥ���Ƥ����������Ƹ���ȥ����ץȤ���Υ⡼��Ψ��������̱²������æ�Ф�̱²���Ϥ�����ɶ��ֲ�ۤ��פ����ȵ�ǰ����Ի��Ǥ��롣���������ߤΡֲ�ۤ��ספϤ����ǰ���뤳�Ȥ���¤ˤ�������С֥��ꥹ�ޥ���������ˤ�äƤ����褦�ʡס�Exodus: æ��������ˤ��˽˺�Ū��ʷ�ϵ�����ġֻ�Ū���Ȳ����Ƥ��롣�����⡢�ɤ���餽�Τ褦�ʰ�̣�礤���Ѽ����Ƥ����Τϥ��������������ֿ���λ���פˤ��Ǥˤ����Ǥ��ä��褦�Ǥ��ꡢ�����ͻҤΰ�ü����ʡ����פ���ˤ⸫�Ф���롣
�ޤ��˥������������������ֶ������פȤϡ������ο͡����ֲ�ۺספ�ˤ�����ν����˵ޤ������������פǤ��ä����Ȥ�ʬ���äƤ���櫓�Ǥ��롣���⤽�⥤�����η��ब��13���ζ������פǤ��ä����Ȥʤ�����ε��Ҥ˵������ΤǤϤʤ��������ޤǤ�̱�������ˤ�äƤǤ����ʤ���������13���Ǥ��ä��פȤ������Ȥξ�ħŪ��̣������������ǤϤʤ��ΤǤ����ǾܽҤ��ʤ������㤽��䤬�������Τ��ֶ������פǤ��ä����Ȥˤϡ�����������������ˤ�����ֲ�ۺס��Ҥ˺����ä����Ǥ���ʻ˼¤Ȥ��Ƥ��ϡ������ޤǤ��ħŪ�ʰ�̣�ǡˡ������ơ�������ĤΡ㥤�٥�ȡ�ʡ֥��ꥹ�Ȥη���ڤ�����פȡ֥����̱²��æ�Х��Х��Х�סˤΡֵ���Ū���ספϡ�����ޤ������ǤϤʤ����������������ι������ָ�������������Ū���ݡפȤ��ƶ�ͭ����Ƥ��뤳�Ȥ��̣���Ƥ���ΤǤ��롣
���ơ��ݤä����ܤˤ���������Ȥϡ���ǯ�������Ƥ��ޤ��б��Τ褦�ʡ��ż�פȸ��������������פ�����ǯ�֤Ǥ��ü�ʰ�̣�礤����ġ����ʤ�����פȤʤ�櫓�Ǥ��뤬�����ε������Ť��˲ᤴ������ˡ�ǯ�����äˡֳ����ס��糢���פΣ����ϡ���䲼�ؤ���˻�����ֻ��֤Ȥ��襤�פ�������褹���ΤȤʤ롣�ޤ�Ǥ���ŵ��Ū�ʡֻ��������ʡפ����������ʶ������ˤ����װʹߤϡֲФ����ƤϤʤ�ʤ��סֲФ��̤�����ʪ����ˤ��ƤϤʤ�ʤ��פȤ������ʤʥ�����Χˡ�Ȥ��ƤǤ��뤿��ˡ�ɬ��ˤʤäƺפο����ȵ����ο����ν������ʤ���Фʤ�ʤ�¿���Υ����Ͳ�²��פ碌��ۤɤΤ�ΤǤ��롣��۸�Ρʿ�ǯ�Ρ˿����ϲФ�ä����ʤ��Τ��䤿���ʲФ��̤��ʤ��Ƥ��ɤ��褦�ʡ˿���ʪ�Ȥʤ롣����ϡ����ܤ�����ξ��ϡָ���ʤ������������סʤȤ���̾�ζ۵ޥ����ܥå����ˤȤʤ롣����⤳����۸�ο���������ˤ��Ť��˲��⤻���ʻŻ����ˤ˲ᤴ�����Ȥ��ˤ�ƽ��פ��Ȥ�����ǰ��ͭ���Ƥ������Ǥ��롣


�ޥåĥ��ʺ��ˤȥޥåĥ����С��ʱ���

�Ťͤ��֤��줿�ޥåĥ��ʾ��
�����Ρֲ�ۤ��פǽ��פʿ���ʪ�ˤϥ����襦�掠�Ӥ��ݼ�ʤɤ����Ĥ������Ǥ����뤬��������ΤҤȤĤˡ֥ޥåĥ��פȸƤФ��ּ�̵���ѥ�: unleavened bread, azyme�פ����롣����ϡ��������ȶݡʹ���ˤ������ȯ�ڤ����Ĥ�ޤ����̾�Υѥ�Ȱۤʤ�ޤä����դä��餷�Ƥ��ʤ����������ᥪ���ɥ֥�Υ���å����Τ褦�ʼ¤�̣���ʤ��ѥ�ѥ�����äڤ餤�緿�ѥ�Ǥ��롣����ϡֽХ����ץȡפȤ����������פˤ�����ɶ�δ����桢ȯ�ڤ��������̾�Υѥ������ã�����٤��ʤ��ä��פȤ���̱²�ε�����α��褦�Ȥ����տޤ����롢�ȡʲ�Ĺ�ˤ�äơ���������뵷���ΰ����Ǥ��ꡢ��ۺפδ����桢���äȥơ��֥�ξ�ˡֽŤͤ����֤��֤���Ƥ��ꡢ�������֤ۤ��Ƥ���ΤǤ��롣

���Τʤ����ů��ʤ����ߤˡ��ֱ���סֻ�帢��ħʪ�סֱ���ۡˡס��оΡס���ˤλ��ع�¤�פʤɤʤɡ����줫���˸��Ƥ椯�������ķ�Ū���Ǥ��ޤޤ�Ƥ��롣
�����ɤ����ͳ�Ǥ������ܤˤϿ�ǯ�����Ƥ��Ф餯���̾�Ρ��Ȥ����ơʤ��ӡˤ٤ʤ��פȤ������������������Ū�ˤϤۤȤ�ɶػߤ���ƥ֥졼����ݤ�������줿�褦�ʴ����Ǥ⤢��ˡ��������ꡢ���Ƥ�ȤäƤ��餫������ʤġˤ��Ƥ���֥���פ٤�ΤǤ��롣����⤪���餯��Ȥ�Ȥϡ��Ф�Ȥ�ʤ��Ǥ�٤�����¸���Τ褦�ʤ�ΤȤ��ơ�ǯ�֤Ǥ�����δ��ָ�����о줹�롢�ˤ�Ƶ���Ū���Ǥζ�������ʪ�Ǥ��롣��¸�ΤΤ褦�ˡ����Υޥåĥ��ʤ�̥���ϽŤͤ����ʤ���ˤ�����٤�����Ū���֤������֤����ΤǤ��롣
�����ޤǵ��Ҥ�����Ǥ⡢�����̱²�����ܿͤȤδ֤Ρ��ԲĻĤʰŹ�פ�Ĵ����Τ���������Ū�ǤϤʤ����¤äݤ������ʡ���ͱƱ�����פ�Ÿ�����褦�ȸ����ΤǤ�ʤ��������äϤ��Τ褦���ä����ڤ����礭�ʥե졼����äʤΤǤ��롣
�����ǤϤʤ��ơ��֡�ǯ�κǸ�η�ɤΡ���Ĥλ���Ū�ʼ����ι�֡ɤ������롢ήưŪ�ǡȥ�����Ū�ʡɾ��֡פ���¤ʺƸ��������ܿͤȥ����ͤ�ξ���˸��Ф����Ȥ������Ȥ�¾�ʤ餺�������������ν���ʳ��Ǥϡּ��Ǥʤ�Τ������˽���ʤ��פȤ������֤Ǥ��ä����Ȥ������Ǥ���Ȥ������ȤʤΤǤ��롣�����ơ�����ϲ��β��餫�Ρֶ���פ�ǰ�����ΤȤ��ƽ���夬�ä��ҤȤĤΡֵ����ѡפ˴ط��Τ����ΤʤΤǤ��롣
03:00:16 -
entee -
TrackBacks
2005-09-11
����ˤ˴ط��Τʤ�������ۤʤɤȤ�����ΤϤʤ�
�����ƿ����̾�դ�����ˤդ��路�����Ȥ�ͣ��ĤǤ���
�����Ʊ���˿���ǤϤʤ��Ȥ������ȤˤĤ���
�θ����Τϻ����°���뤳�ȤǤϤ��롣α�����1991ǯ�Σ������˻�˵����ä�����̾�������θ��ϡ���ο����ˤ����Ƹ������٤����������Ū���Ѥ��Ƥ��ޤä��������μ�����ä����Ƥ���ǡ���˥��������åɤʥ������ȼ����ΤǤ��ä��ˤ�餺����������Ϥ����Ȥ�������Ū�˹��ꤷ����Ǽ����ߤ�뤳�Ȥ����ʤ�������礤�˿���졢���Ϥοͤ����ΤΡˡ���λפ����ߤʤΤǤϤʤ����Ȥ��������ȤϹ��������碌�Ǥ��ä����Ȥ�����Ǥ��ʤ�������������Ϥ��θ塢��ǯ�ʾ���Ϥäƻ�������˵�¤�³�������֤��뤳�ȡפ��Ф��빱��Ū�ʰڷɤȤ���ݤȤ�Ƥ֤٤��ʤΤ���ʬ����ʤ��������֤�ţ�դ��ˤ�������ʬ�Ρִ���Ū���θ����դ���褦�ʾڸ�����������濴Ū����Ȥ��������Ƥ���褦�ʤޤ�������ͤ��ɤ����ˤ���Ϥ��ʤ����Ȥ����פ��ʤ��뤤�����ꤵ����ߤ����ä����⤷��ʤ��ˤ����������줫��кѤε����¤�������䥷��ܥ�Υ�����μ������Ϥޤä���
������������Ϣ��˶��̤�����ϡ��ۤȤ�ɤɤ�⤪�ʤ��������褦�ʿ��Ǥ�ʣ����������ʤ����ʪ��Ū��ɬ����¤β�����Ѱդ��Ƥ���ˤ�ؤ�餺�����ִο��ʤȤ������������Ƥ��ʤ��ȴ�����줿���Ȥ��ä����Ĥޤꡢ�����������ǽ��ϤۤȤ�ɲ���������ʤ��ˡ��������ο��Ǥ��ɼԤ˸�����ʤ����ƾ���˹ͤ�������ˤ��Ȥ���Ū�ʤΤǤϤʤ����Ȼפ���ۤɡ����פ������ڤ귿�Ǥ��뤫ñ������Ū���ä��������ơ�����äȤޤ��ʲ���˽в�äƤ⡢��Ϥ�ο��ʤȤ����˸��ڤ���Ȥʤ�ȡ���������ۣ�椫�ı����ɽ���ˤʤ�Ȥ������̤η����Ϥ�Ϥ��ݤ�ʤ��ΤǤ��ä���
�����ǻ䤬�ͤ����Τϡ��Ҥ�äȤ���Ȥ����������Ǥ��Լ��Ȥ�����ʬ�Ρָ����Ƥ����Ρפΰ�̣��ޤä������ƤϤ��ʤ��ΤǤϤʤ������Ȥ������ȡ����뤤�Ϥ���������˸������Ǥ����Ƥ����פǤ���Ф���ۤɡ����줬�����ϲ����̣���Ƥ���Τ����Τ����ܿͤ��֤���餤�פ��Ƥ���ΤǤϤʤ����Ȥ������ȡ����Τɤ��餫�Ǥ���Ȥ������ȤǤ��ä������줬�������λ�ʤ��軰�Ԥ��ܤˤϡ��ɤ����ֿ������פǤ���ȱǤ롣
�������ä�ͭ̾�ʺ�Ȥ���ˤϡ���ʪ��Ū���������˴٤äƤ���Ȥ����פ��ʤ�����Ϣ�Τ��ꤽ���ʤ�Τ��٤Ƥ����츫���ƴ�Ϣ�����ꤽ���ʰ��ݤ�ʤơ��ɤ�⤳����Ʊ�����ΤĤ����ޤ���˻�¿�˵ͤ������褦�ʰ��ݤ�Ϳ�����Τ⤢�äơ�������ʪ�ؼ��ܿͤ���ʬ�ΰ��äƤ����оݤν��פ����ٹ礤�Ƥ��Ƥ���Ȥϻפ��ʤ����Ȥ�������ΤǤ��ä���
��ˤȤäƤ���������Ϣ�ο��ǤȤ����ȼ�ʬ�ʤ�μ�õ���õ��Ȥϡ��������Ū���Ƥ˴�Ϣ���Ƥ���Ȼפ��롢�ź����������ʤ����ޤ������Ū���Ҥ���Ρ־ڸ�õ���פλ�ߤǤ⤢�ä��Τ�����1994ǯ���ε���塢ľ���˳��Ϥ�����ˤ佡������Ȥˤ����������Ƥ�����Ҥ�������ɤ���ǡ��٤�Ф��˽в�ä��Τ��롼�ޥ˥��пȤν����˲ȡ���ӽ����ؼԤΥߥ���������ꥢ���ǤǤ��ä���
������������������ˡ٤�������Ρ֥إ�˥����ϣ��ѡפξϤˤ����뵭�Ҥˡ����Ѥ�餺�Ρ�������������¾ڼ��Ū���丷�����١פ��Բķ�˵�����餷�����ᤷ���ۤɤ˥����ǥߥå��ʳؼԤ����Ҥ���ˡ������Բ�ǽ�ʤ������ƤˤĤ��ƤΡ����餫�ʰż��פ��Դ֤˻Ĥ���Ƥ���Τ�ȯ�������ΤǤ��ä�������ϤۤȤ�ɻ��ͤˤ����θ��դȤ���ʹ�����Ƥ���褦�ʥȡ���ȷپ�ζ��������������ʥ�å������Ȥ��ƻ�ˤ��Ϥ����ΤǤ��롣
����������θĿ�Ū�θ��ˤ�ä����������Υӥ���������ηϤ�����Ϥ�ֻ�Ȥ����Ŀ͡פ�°���븸�ۤ���Ǥʤ����Ȥ��θǤȤ��Ʒ����դ���줿�Τ��ä������ä����ɤ�����Ť���������Ĥ�ΤʤΤ���ʬ����ʤ��褦�ʾ�ħ���ηϤ�������ͤ���˺�������ƹ��ۤ��줿�ΤǤ��ä��������ƥ��ꥢ���Ǽ��Ȥν��Ҥ�Ϥ�Ȥ��ơ�Ω��³���˴��ͤ�������Ԥˤ����դο�������ˤ⡢Ʊ�ͤΡ����ơפˤĤ��Ƥΰż��䡢���餫�ʸ��ڤ��˸��Ф����Τ��ä��������ϡ����褽���դˤǤ��ʤ����Ȥ���첽����Ȥ���������ʤ���ͤ��������Ϥλ�ʪ�Ǥ��ä���
�Τ��äơ����ߡ������ܤ����ɤ�Ԥ��Ϥ�����������ˡ٤Ǥ��뤬�������裱���δ����ˤ������ԡʹ�������ͺ�ˤˤ��������ǡ��ƤӶä��٤����Ҥ�ȯ������������ϥ��ꥢ���Ǥ��⤯ɾ�����礤��̥�����Ƥ����Ȥ����ϥ��ǥ��Ρ���ˤ˴ؤ��������ʲ���פȤ�����ΤǤ��ä������ڻ�ˤ��м��Σ��ĤˤޤȤ����Ȥ�����
��̡�����볢�˴������뤫�⤷��ʤ����������äƤ���Τ�������Ǥ���ͤˤ����Ƥˤ��ΰ�̣����������ƤǤ��롣
�ʰ��ѳ��ϡ�
����ǧ����Ū�ʥ������Ǥϡ���ˤβ��ؤϡ�����������פ�ɬ��Ū�ʤ�ΤȤ��롣
������ˤ���Ȥϡ����Ū�����ο������������Ȥ��Ƥ��롣��������ϡ�����Ū�ˡ����ʤ롢���뤤�Ͼ�ħŪ�ʤ�Ķ���Ū����ΰ�̣�ؤΥ��˥����������ʤΤǤ��롣���μ�������ʪ��Ȥ��Ƥ���ˤβ��ͤ��ӽ������ΤǤϤʤ�������Ū��ʸ���䶦Ʊ�Τ������롢����Ū�ʽ����θ��ν�������ǧ����������᤹�롣�����ơ������ζ���Ū���θ��ϡ�����ȥ���ܥ�ˤ����Ƹ���ˤ���Ƥ����ΤǤ��롣�������ϰ��ѼԤˤ���
�������ݤε����˵��뤳�Ȥν������Ǥ��롣����ϡ����Ū��������¬��Ǥ��뵯���ȸ������ȤǤϤʤ���¸��Ū�ʽ������¸�ߤ�Ϳ����줿�������뤤����¤�κǽ���θ����̣���Ƥ��롣���ʤ븽�ݤκ���Ū�ʰյ����İ����뤳�Ȥˤ�äơ���������ˤβ�᤹�뤳�Ȥ��Ǥ���褦�ˤʤ롣�ʤ��ʤ顢�����������β������Τ����߽Ф���Ƴ�����ηϲ������̣�Ρ��濴�פ��Ѱդ����ΤǤ��뤫���Ǥ��롣�������ϰ��ѼԤˤ���
�ʰ��ѽ�λ��
Ĺ�����Ѥ���������ˤϡ���ˤ�(��̩�ؤ�)����פ������Ȥ������Ū�ֻ����פؤ����Τ��ȼ��Τ˸��ڤ��롢����ʾ�ˤ褯�줿���Ҥ��������뤳�Ȥ��Ǥ��ʤ����������äơ����ˤ��٤����Τ��Ǹ���Ƥ��롣��������θ��դ������������������¾ڼ����Ū�ʥޥʡ���§�ä����ҡ��Ȥ����ֶ��������פ������ͼ�����Ǥ��äǤ��뤬��
�ɤ����Ӻ���ʤۤɽ��פʤ��Ȥ���Ƥ���ΤǤ��뤬���ä�ɮ�Ԥ����ܤ������Ҥϣ������ƣ��Ǥ��롣�����Ǥϡ��֥��˥����������פȸƤФ�Ƥ����θ������ޤ��ˡ���ˡפȤ��ε����ؤ�����Ȥ������Ȥ��Բ�ʬ�Ǥ��뤳�Ȥ�ǡ���ʤ�ۣ�椵���ӽ������ȡ���Ǹ�äƤ���Τ���
�����ǻ䤬��������������ˤ���̩�פȤϡ��ޤ��ˡ֥����ե��롦�ϡ�ϡ���סʸ����ν�ˤ˽�Ƥ���֤��������ϡ�������̩�ˤ�äƤΤ�¸³����פ˴ؤ���ΤǤ��ꡢ����ϡ����줬����̩�פǤʤ��ä��顢���ޤ���줬��¸����ֲ���ĤĤ��������פϡ����ޤη���¸�ߤ��뤳�ȼ��Τ��Ǥ��ʤ��ä��Ȥ�����̣�ǤΡ���̩�פǤ��롣���줬����̩�פȲ������Ȥʤ�����¿���Ρ���¸�ԡפˤȤä���������������Ǥ��ä������ʻ���ˤϡ�����줬�������ܷ⤷�Ƥ���褦�ʥ�������ǡְִ㤦�פ��Ȥ��ʤ��ä������������줬����̩�פˤʤä����ˡ��Ϥޤ꤬���äƽ���꤬���������Ȥ�����ΤΡֵ����פؤε������Ӥ�줿�������ơ����ޤ�����������Ω�����뤿��ˤϡ����줬���ඦͭ�κ�Ǥ��äƤϤʤ�ʤ��Ȥ������Ȥˤʤä�˺�Ѥ��줿�������뤤�ϡ����Ρּ����ʽ�����פ�����οʹ�����������������տ�����ƿ���줿�����뤤�ϡ�¯�����줿��������Ҥˤ������̲ᵷ��η��ǡ����ΰ�̣���뤳�Ȥʤ��������뤳�ȤȤʤä���
�����ơ����α�ƿ���⤷�����Ӽ���������������̲����̣��������������ʤ�������ʤ�ۤɤη���ˤ��Ƥ���Τ����Ĥޤꡢ������������ϡ��ܳФ�ơפ����Τˡ���������Τ����ϡ�̲�äơפ���Τ�������̲�꤬������ְִ�碌�ơפ���Τ���
�����������α�ƿ�϶���Ū�ʤ�ΤǤ��ä����������Ͽ��ä������ۤ����ѤȤ��ä�ɽ���������¸����֤���פ�λ��뤳�Ȥʤ��ˡ������餵�ޤˡ�Ϫ�Ф���ʤ�����ã���줿������Ϥ��������亮�����ǡ��ҤȤ��ﵱ��ħ�Ȥ��ơ����ޤǤ����Ū������³���Ƥ��롣�ʻ䤬���ޤ⤳����������³���Ƥ���Τϡ�¯������פȤ����⤬�������餳�����̤�����뤳�Ȥ�ǧ����뤫�������
�����ˤ������ָ��ݤε����˵��뤳�Ȥν������פȤ���˻��ָ���פ����롣�Ĥޤꡢ����������Ω���������̩�Ȥ��Ƥ����Ū���¡פκƶ�ͭ�����������������ò�ᡦ���������Ū����δ��ܤʤΤǤ��롣�Ĥޤꡢ�֤���Ϥ�Ϥ���̩�ǤϤʤ��פȤ����褦�ʡ����ǧ���פβ������������ֺ���������פĤƵ����ä�ǡ������餻�뤫�ݤ��Ρ������˥ݥ���ȤȤ��Ƶ����롣���ʤ�������ꥢ���Ǥˤ�äƳ�������褦�Ȥ����������ܼ�Ū���Ȥ�����Τϡ�����ۤɤ��褦�˶۵������ӤӤ���ΤǤ��ꡢ����Ϥ��ʤ�������������Ĥ��ľ��Ϣ�ؤ�����ΤǤ��äơ������ʤ�ʳص��Ѥˤ��ֲ����פˤ⡢�����ˤ�������Ū���פˤ�ڤӤ�Ĥ��ʤ��ۤɤν��Ƥʰ�̣����ä����ƤʤΤǤ��롣�����ơ��ִ���Ū�ʽ����θ��ν�������ǧ����פȤ�����������Τ�������ɾ�������ޤ���������ΤǤ��롣
���뤤�ϡ����٤Ȥ��ν������Ͼ�ǧ����뤳�Ȥʤ�����æ�����������ʤ����餬ʸ���Ρ����ι���Ѳ����뷹���ˤ�äƤΤߡ��Ǵ�Ū�����ı�Ū�ʡ������פδ�ߤ���������Ǥ�������������¯���ε�ˤλѤ�����������ˤ���������ʤ��Ͻ�פ�������¤����Ǥ�������
�����ǡ�������Ǹ��ڤ�����¸��Ū�ʽ������¸�ߤ�Ϳ����줿�������뤤�Ϲ�¤�κǽ���θ��פ�����ʬ���Ƥ�ֹ�¤�κǽ���θ��פȤϡ�����������С������ߤΤ褦�ˤ��餷��Ƥ��빽¤�Ρ�ü��פ��ۤ������Ĥƿ���ξ�˸��¤˹ߤ�ݤ��ä��ֺǽ�Ρ��θ��Τ��ȤǤ��ꡢ�ۤ���«���줿���˸���������ˤȤäƤΡֺǸ�Ρ��θ��Ȥ��֤äƸ����Ƥ����������̤�ŷ����̵���˳��褦�ʡ���ספǤ��롣�Ǹ�Ǥ����Ʊ���ˤ���Ϻǽ���θ��Ȥʤꡢ����������ϵ嵬�Ϥ��θ��ϡ�������������������פȤ����и���ɤŨ�����Τˤ����������
�����θ��ϡ����������Ȥ����ޤ�˼����ʻ���ˤ����Ƥ���̩�ˤʤ�褦���ʤ��ä������������η�Ū�θ���ľ�ܻ��äƤ���͡��ϵ�®�ˤ��ʤ��ʤ����夬���夵���˽��äƤ���ϡָ���������줿��Ρפء������ƿ��äؤ����Ƥ����ʥҥ����ޤ�ʥ������ˤ����������θ��ε����������������ˤ�äƤ����˵�®�˼��������Τ��Ȥ������Ȥ��Ǥˤ������ܷ⤷�Ϥ�Ƥ���ˡ�����줬�����ܤˤ��Ƥ�����ε���ʸ���β��ä�����뤳�ȤΤʤ������ο͡������ºݤˤ��������ʿ����ˤξ�˹ߤ�ݤ��ä����Ȥ����Ū������������ˡ����դϤ����˼����뤬���ػ���ʥ��֡��ˤȤ��Ƽ������Χ����Χˡ�ˤ�붯��Ū�����Ȥ������ǡ���˻���ʾ��Ĺ������ä��ҤȤĤΡ���λ���פ��������������������ơ������Ѳ����뤳�Ȥȵ��Ҥ��뤳�ȼ��Τ�ؤ������λϤޤꤳ����������Ϥޤ��ʤ�����λϤޤ�ʤΤǤ��롣
�������������줿���Ȥ�����̩�פȤʤꡢ��Ķ���Ū����ΰ�̣�פ����˥������������̤��ƤΤ�������졢�����ͭ����͡��δ֤ˡֶ��ȴط��פΤߤ��ۤ��褦�ˤʤ�ޤǤϡ�
������������Ϣ��˶��̤�����ϡ��ۤȤ�ɤɤ�⤪�ʤ��������褦�ʿ��Ǥ�ʣ����������ʤ����ʪ��Ū��ɬ����¤β�����Ѱդ��Ƥ���ˤ�ؤ�餺�����ִο��ʤȤ������������Ƥ��ʤ��ȴ�����줿���Ȥ��ä����Ĥޤꡢ�����������ǽ��ϤۤȤ�ɲ���������ʤ��ˡ��������ο��Ǥ��ɼԤ˸�����ʤ����ƾ���˹ͤ�������ˤ��Ȥ���Ū�ʤΤǤϤʤ����Ȼפ���ۤɡ����פ������ڤ귿�Ǥ��뤫ñ������Ū���ä��������ơ�����äȤޤ��ʲ���˽в�äƤ⡢��Ϥ�ο��ʤȤ����˸��ڤ���Ȥʤ�ȡ���������ۣ�椫�ı����ɽ���ˤʤ�Ȥ������̤η����Ϥ�Ϥ��ݤ�ʤ��ΤǤ��ä���
�����ǻ䤬�ͤ����Τϡ��Ҥ�äȤ���Ȥ����������Ǥ��Լ��Ȥ�����ʬ�Ρָ����Ƥ����Ρפΰ�̣��ޤä������ƤϤ��ʤ��ΤǤϤʤ������Ȥ������ȡ����뤤�Ϥ���������˸������Ǥ����Ƥ����פǤ���Ф���ۤɡ����줬�����ϲ����̣���Ƥ���Τ����Τ����ܿͤ��֤���餤�פ��Ƥ���ΤǤϤʤ����Ȥ������ȡ����Τɤ��餫�Ǥ���Ȥ������ȤǤ��ä������줬�������λ�ʤ��軰�Ԥ��ܤˤϡ��ɤ����ֿ������פǤ���ȱǤ롣
�������ä�ͭ̾�ʺ�Ȥ���ˤϡ���ʪ��Ū���������˴٤äƤ���Ȥ����פ��ʤ�����Ϣ�Τ��ꤽ���ʤ�Τ��٤Ƥ����츫���ƴ�Ϣ�����ꤽ���ʰ��ݤ�ʤơ��ɤ�⤳����Ʊ�����ΤĤ����ޤ���˻�¿�˵ͤ������褦�ʰ��ݤ�Ϳ�����Τ⤢�äơ�������ʪ�ؼ��ܿͤ���ʬ�ΰ��äƤ����оݤν��פ����ٹ礤�Ƥ��Ƥ���Ȥϻפ��ʤ����Ȥ�������ΤǤ��ä���
��ˤȤäƤ���������Ϣ�ο��ǤȤ����ȼ�ʬ�ʤ�μ�õ���õ��Ȥϡ��������Ū���Ƥ˴�Ϣ���Ƥ���Ȼפ��롢�ź����������ʤ����ޤ������Ū���Ҥ���Ρ־ڸ�õ���פλ�ߤǤ⤢�ä��Τ�����1994ǯ���ε���塢ľ���˳��Ϥ�����ˤ佡������Ȥˤ����������Ƥ�����Ҥ�������ɤ���ǡ��٤�Ф��˽в�ä��Τ��롼�ޥ˥��пȤν����˲ȡ���ӽ����ؼԤΥߥ���������ꥢ���ǤǤ��ä���
������������������ˡ٤�������Ρ֥إ�˥����ϣ��ѡפξϤˤ����뵭�Ҥˡ����Ѥ�餺�Ρ�������������¾ڼ��Ū���丷�����١פ��Բķ�˵�����餷�����ᤷ���ۤɤ˥����ǥߥå��ʳؼԤ����Ҥ���ˡ������Բ�ǽ�ʤ������ƤˤĤ��ƤΡ����餫�ʰż��פ��Դ֤˻Ĥ���Ƥ���Τ�ȯ�������ΤǤ��ä�������ϤۤȤ�ɻ��ͤˤ����θ��դȤ���ʹ�����Ƥ���褦�ʥȡ���ȷپ�ζ��������������ʥ�å������Ȥ��ƻ�ˤ��Ϥ����ΤǤ��롣
����������θĿ�Ū�θ��ˤ�ä����������Υӥ���������ηϤ�����Ϥ�ֻ�Ȥ����Ŀ͡פ�°���븸�ۤ���Ǥʤ����Ȥ��θǤȤ��Ʒ����դ���줿�Τ��ä������ä����ɤ�����Ť���������Ĥ�ΤʤΤ���ʬ����ʤ��褦�ʾ�ħ���ηϤ�������ͤ���˺�������ƹ��ۤ��줿�ΤǤ��ä��������ƥ��ꥢ���Ǽ��Ȥν��Ҥ�Ϥ�Ȥ��ơ�Ω��³���˴��ͤ�������Ԥˤ����դο�������ˤ⡢Ʊ�ͤΡ����ơפˤĤ��Ƥΰż��䡢���餫�ʸ��ڤ��˸��Ф����Τ��ä��������ϡ����褽���դˤǤ��ʤ����Ȥ���첽����Ȥ���������ʤ���ͤ��������Ϥλ�ʪ�Ǥ��ä���
�Τ��äơ����ߡ������ܤ����ɤ�Ԥ��Ϥ�����������ˡ٤Ǥ��뤬�������裱���δ����ˤ������ԡʹ�������ͺ�ˤˤ��������ǡ��ƤӶä��٤����Ҥ�ȯ������������ϥ��ꥢ���Ǥ��⤯ɾ�����礤��̥�����Ƥ����Ȥ����ϥ��ǥ��Ρ���ˤ˴ؤ��������ʲ���פȤ�����ΤǤ��ä������ڻ�ˤ��м��Σ��ĤˤޤȤ����Ȥ�����
��̡�����볢�˴������뤫�⤷��ʤ����������äƤ���Τ�������Ǥ���ͤˤ����Ƥˤ��ΰ�̣����������ƤǤ��롣
�ʰ��ѳ��ϡ�
����ǧ����Ū�ʥ������Ǥϡ���ˤβ��ؤϡ�����������פ�ɬ��Ū�ʤ�ΤȤ��롣
������ˤ���Ȥϡ����Ū�����ο������������Ȥ��Ƥ��롣��������ϡ�����Ū�ˡ����ʤ롢���뤤�Ͼ�ħŪ�ʤ�Ķ���Ū����ΰ�̣�ؤΥ��˥����������ʤΤǤ��롣���μ�������ʪ��Ȥ��Ƥ���ˤβ��ͤ��ӽ������ΤǤϤʤ�������Ū��ʸ���䶦Ʊ�Τ������롢����Ū�ʽ����θ��ν�������ǧ����������᤹�롣�����ơ������ζ���Ū���θ��ϡ�����ȥ���ܥ�ˤ����Ƹ���ˤ���Ƥ����ΤǤ��롣�������ϰ��ѼԤˤ���
�������ݤε����˵��뤳�Ȥν������Ǥ��롣����ϡ����Ū��������¬��Ǥ��뵯���ȸ������ȤǤϤʤ���¸��Ū�ʽ������¸�ߤ�Ϳ����줿�������뤤����¤�κǽ���θ����̣���Ƥ��롣���ʤ븽�ݤκ���Ū�ʰյ����İ����뤳�Ȥˤ�äơ���������ˤβ�᤹�뤳�Ȥ��Ǥ���褦�ˤʤ롣�ʤ��ʤ顢�����������β������Τ����߽Ф���Ƴ�����ηϲ������̣�Ρ��濴�פ��Ѱդ����ΤǤ��뤫���Ǥ��롣�������ϰ��ѼԤˤ���
�ʰ��ѽ�λ��
Ĺ�����Ѥ���������ˤϡ���ˤ�(��̩�ؤ�)����פ������Ȥ������Ū�ֻ����פؤ����Τ��ȼ��Τ˸��ڤ��롢����ʾ�ˤ褯�줿���Ҥ��������뤳�Ȥ��Ǥ��ʤ����������äơ����ˤ��٤����Τ��Ǹ���Ƥ��롣��������θ��դ������������������¾ڼ����Ū�ʥޥʡ���§�ä����ҡ��Ȥ����ֶ��������פ������ͼ�����Ǥ��äǤ��뤬��
�ɤ����Ӻ���ʤۤɽ��פʤ��Ȥ���Ƥ���ΤǤ��뤬���ä�ɮ�Ԥ����ܤ������Ҥϣ������ƣ��Ǥ��롣�����Ǥϡ��֥��˥����������פȸƤФ�Ƥ����θ������ޤ��ˡ���ˡפȤ��ε����ؤ�����Ȥ������Ȥ��Բ�ʬ�Ǥ��뤳�Ȥ�ǡ���ʤ�ۣ�椵���ӽ������ȡ���Ǹ�äƤ���Τ���
�����ǻ䤬��������������ˤ���̩�פȤϡ��ޤ��ˡ֥����ե��롦�ϡ�ϡ���סʸ����ν�ˤ˽�Ƥ���֤��������ϡ�������̩�ˤ�äƤΤ�¸³����פ˴ؤ���ΤǤ��ꡢ����ϡ����줬����̩�פǤʤ��ä��顢���ޤ���줬��¸����ֲ���ĤĤ��������פϡ����ޤη���¸�ߤ��뤳�ȼ��Τ��Ǥ��ʤ��ä��Ȥ�����̣�ǤΡ���̩�פǤ��롣���줬����̩�פȲ������Ȥʤ�����¿���Ρ���¸�ԡפˤȤä���������������Ǥ��ä������ʻ���ˤϡ�����줬�������ܷ⤷�Ƥ���褦�ʥ�������ǡְִ㤦�פ��Ȥ��ʤ��ä������������줬����̩�פˤʤä����ˡ��Ϥޤ꤬���äƽ���꤬���������Ȥ�����ΤΡֵ����פؤε������Ӥ�줿�������ơ����ޤ�����������Ω�����뤿��ˤϡ����줬���ඦͭ�κ�Ǥ��äƤϤʤ�ʤ��Ȥ������Ȥˤʤä�˺�Ѥ��줿�������뤤�ϡ����Ρּ����ʽ�����פ�����οʹ�����������������տ�����ƿ���줿�����뤤�ϡ�¯�����줿��������Ҥˤ������̲ᵷ��η��ǡ����ΰ�̣���뤳�Ȥʤ��������뤳�ȤȤʤä���
�����ơ����α�ƿ���⤷�����Ӽ���������������̲����̣��������������ʤ�������ʤ�ۤɤη���ˤ��Ƥ���Τ����Ĥޤꡢ������������ϡ��ܳФ�ơפ����Τˡ���������Τ����ϡ�̲�äơפ���Τ�������̲�꤬������ְִ�碌�ơפ���Τ���
�����������α�ƿ�϶���Ū�ʤ�ΤǤ��ä����������Ͽ��ä������ۤ����ѤȤ��ä�ɽ���������¸����֤���פ�λ��뤳�Ȥʤ��ˡ������餵�ޤˡ�Ϫ�Ф���ʤ�����ã���줿������Ϥ��������亮�����ǡ��ҤȤ��ﵱ��ħ�Ȥ��ơ����ޤǤ����Ū������³���Ƥ��롣�ʻ䤬���ޤ⤳����������³���Ƥ���Τϡ�¯������פȤ����⤬�������餳�����̤�����뤳�Ȥ�ǧ����뤫�������
�����ˤ������ָ��ݤε����˵��뤳�Ȥν������פȤ���˻��ָ���פ����롣�Ĥޤꡢ����������Ω���������̩�Ȥ��Ƥ����Ū���¡פκƶ�ͭ�����������������ò�ᡦ���������Ū����δ��ܤʤΤǤ��롣�Ĥޤꡢ�֤���Ϥ�Ϥ���̩�ǤϤʤ��פȤ����褦�ʡ����ǧ���פβ������������ֺ���������פĤƵ����ä�ǡ������餻�뤫�ݤ��Ρ������˥ݥ���ȤȤ��Ƶ����롣���ʤ�������ꥢ���Ǥˤ�äƳ�������褦�Ȥ����������ܼ�Ū���Ȥ�����Τϡ�����ۤɤ��褦�˶۵������ӤӤ���ΤǤ��ꡢ����Ϥ��ʤ�������������Ĥ��ľ��Ϣ�ؤ�����ΤǤ��äơ������ʤ�ʳص��Ѥˤ��ֲ����פˤ⡢�����ˤ�������Ū���פˤ�ڤӤ�Ĥ��ʤ��ۤɤν��Ƥʰ�̣����ä����ƤʤΤǤ��롣�����ơ��ִ���Ū�ʽ����θ��ν�������ǧ����פȤ�����������Τ�������ɾ�������ޤ���������ΤǤ��롣
���뤤�ϡ����٤Ȥ��ν������Ͼ�ǧ����뤳�Ȥʤ�����æ�����������ʤ����餬ʸ���Ρ����ι���Ѳ����뷹���ˤ�äƤΤߡ��Ǵ�Ū�����ı�Ū�ʡ������פδ�ߤ���������Ǥ�������������¯���ε�ˤλѤ�����������ˤ���������ʤ��Ͻ�פ�������¤����Ǥ�������
�����ǡ�������Ǹ��ڤ�����¸��Ū�ʽ������¸�ߤ�Ϳ����줿�������뤤�Ϲ�¤�κǽ���θ��פ�����ʬ���Ƥ�ֹ�¤�κǽ���θ��פȤϡ�����������С������ߤΤ褦�ˤ��餷��Ƥ��빽¤�Ρ�ü��פ��ۤ������Ĥƿ���ξ�˸��¤˹ߤ�ݤ��ä��ֺǽ�Ρ��θ��Τ��ȤǤ��ꡢ�ۤ���«���줿���˸���������ˤȤäƤΡֺǸ�Ρ��θ��Ȥ��֤äƸ����Ƥ����������̤�ŷ����̵���˳��褦�ʡ���ספǤ��롣�Ǹ�Ǥ����Ʊ���ˤ���Ϻǽ���θ��Ȥʤꡢ����������ϵ嵬�Ϥ��θ��ϡ�������������������פȤ����и���ɤŨ�����Τˤ����������
�����θ��ϡ����������Ȥ����ޤ�˼����ʻ���ˤ����Ƥ���̩�ˤʤ�褦���ʤ��ä������������η�Ū�θ���ľ�ܻ��äƤ���͡��ϵ�®�ˤ��ʤ��ʤ����夬���夵���˽��äƤ���ϡָ���������줿��Ρפء������ƿ��äؤ����Ƥ����ʥҥ����ޤ�ʥ������ˤ����������θ��ε����������������ˤ�äƤ����˵�®�˼��������Τ��Ȥ������Ȥ��Ǥˤ������ܷ⤷�Ϥ�Ƥ���ˡ�����줬�����ܤˤ��Ƥ�����ε���ʸ���β��ä�����뤳�ȤΤʤ������ο͡������ºݤˤ��������ʿ����ˤξ�˹ߤ�ݤ��ä����Ȥ����Ū������������ˡ����դϤ����˼����뤬���ػ���ʥ��֡��ˤȤ��Ƽ������Χ����Χˡ�ˤ�붯��Ū�����Ȥ������ǡ���˻���ʾ��Ĺ������ä��ҤȤĤΡ���λ���פ��������������������ơ������Ѳ����뤳�Ȥȵ��Ҥ��뤳�ȼ��Τ�ؤ������λϤޤꤳ����������Ϥޤ��ʤ�����λϤޤ�ʤΤǤ��롣
�������������줿���Ȥ�����̩�פȤʤꡢ��Ķ���Ū����ΰ�̣�פ����˥������������̤��ƤΤ�������졢�����ͭ����͡��δ֤ˡֶ��ȴط��פΤߤ��ۤ��褦�ˤʤ�ޤǤϡ�
23:55:24 -
entee -
TrackBacks
2005-08-18
��¨���פ��������в�����Ȥ�������
�Υ����ߥ������ߥ����顢���줬�������Ф����ȿ���פȻפ��뤫�⤷��ʤ�����ȿ����տޤ��Ƥ��ʤ�����ȿ���ˤʤäƤ��ʤ�����
�����Ĺ��Ĺ���ʷ������Ū�ͻ��˴ؤ���������Ū�������������������ˤ���줬�ޤ�������Ȥ���λ�Ƥ��Ƥ��»�Ϥ��ʤ����äΰ�ĤǤ��롣
�⤦�����դ�ϡ������ʤ�Ƭ�Ǥ�ͤ��Ԥ������Ԥ������������ꡢ���ޤ��鲿���դ��ä��뤳�Ȥ�����Τ�ʬ����ʤ���������ľ�ʤȤ��������������ơ��Τ�ʤ���ʬ�פ�⤦���������Ф�����˼��ʤˤ����ݤ����ޤ����ص�Ū�ˡ�ª�����������פ٤ƾʤ������˸����̤Ǥ��ä롣�ʤ�������Ǥ�Ĺ���ʸ�Ϥˤʤ�����β��꤬���롣��
���ˡ�����Ū�ʲ���ɽ���˱����ơ����μ�ˡ����¨�������ץ�פȤ����Τϡ���ɤϡ����٤�����פˤۤ��ʤ�ʤ��ΤǤ��äơ��ִ�����¨���פǤ��뤫�ִ����˥ץ��פǤ��뤫�Ȥ����褦������Ǹ�뤳�ȼ��Τ��ʥˤʤäƤ��롣��������¨���פȤ������ȤϤ��������ä������������Υץ��פȤ������Ȥ�Ʊ�ͤˤ��������äʤΤ����Ĥޤꡢ¨�����Ф��ơ�����̵���פȤ����褦�������줬����ΤǤϤʤ��ơ�������ɤ��֥֥��ɡפ���Τ����Ĥޤ�ɤ��������¨���פȤ������Ǥ��̣������Ǥ���Τ��Ȥ������Ȥ�������¨���ԤˤȤäƤμ�ͳ���ٹ礤�Ǥ⤢��Ϥ������ޤ��ˤ���Ϥ����ο������Τ�Τ�Ʊ�ͤˡ�
�������Ƕ������Ƹ����С���ˡ�Ȥ��ƤΡʤ��뤤�ϥ��ƥ���Ȥ��ƤΡˡ�¨�����ڡפ˲��θ��ۤ����ʴ��Ԥ�ʤ��ʼ¤ϡ���˸��ڤ��롩�褦�ˡ��������ʬŪ�ˤϱ��ʤ�����ɡˡ��ʲ��˽Ҥ٤�褦�ˡ���¨���פȤϡ�¨�����ڤ䤽��¾�ηݽ��Ϻ���������ž�ǤϤʤ�����Ǥ��롣�����뤳�Ȥ��Τ�Τ���������¨���Ǥ���Ȥ������Ȥ�λ�Ƥ���Ф������ʤ�����˲��ڤ�¨������¦�̤����˲���ɾ����ä��뤳�Ȥ��Ф��ơ���Ͼ�ˡ֤���ϸ�ʿ���˷礤���������Ǥ���פ���Ƚ�����褿�ΤǤ��롣¨�������л롿���̻뤹����Ρ��������פ��ȸ�����̣�ǡ�������¨����������Ƥ���¿���οͤ����ȿ�����������������Ȥϳи�ξ�ǡ�
�ǽ�˲��ڤ˸¤ä��ä�С���ŵ�ڶʤ�ֳ����̤���դ��Ƥ���פ���ʹ��������դǤ⡢�����줿���դǤ���ȴ��������Τϡ������ơ�¨����Ū�ǡ�������ͭ��Ū�Ǥ��롣�Ĥޤ�ֺ�ʤ��줿���ڤ��ʹ֤��դ��Ƥ���פȤ����פ��ʤ��褦�ʡ��ðۤ�ɬ�����פ�����Ƥ����礬�ҤȤġ������Ƥ⤦�ҤȤĤϡ��ֳ����̤�פȤϸ��äƤ⡢���ڤ����Ƥ����褵��뤳�Ȥ����ꤨ�̰ʾ塢�����Τ��Ȥʤ��顢®�١����̡������å��������Ĺ��������������¾�Ρ������벻��ɽ�����Բķ�ʡ���̩�ʵ��褬�Բ�ǽ�����ǤˤĤ��Ƥϡ��ۤ��Բ���Ū�ˤ��ξ줽�ξ��Ƚ�ǤǤ��Ρֺ��ø��פ�����Ƥ������¤ϡ����줳�����ष�����ڤΡּ��פ���ʬ�פǤ��롣�Ǥ���ʾ塢��ŵ�˴ؤ��Ƥϡֲ��פ�ɬ�ܤȤʤꡢ��ŵ�ڶʤα��չ٤������չ٤νִ֤˱����Ƥϡ�¨���١פ����Բ�ʬ�����Ǥ��롣�����ǽ�ʤɤ����ܤ�������ǽ�˴ؤ��Ƥ�Ʊ�ͤΤ��Ȥ�������Ϥ��Ǥ��롣
�ޤä�����äơ����褵��Ƥ��뤳�ȼ��Τ����ʼ��ΤΤ��������鷺������ʬ�ʤΤ����顢���ڲȤˤȤäƤϡ�������ɤ���ᤷ���ɤ��ºݤι٤�ž������Τ��Ȥ�����ʬ������ɽ�������ΤʤΤǤ��롣�����Ǹ��ä��ֲ��פȤϱ��չ٤���Ω�äƹԤʤ���Ρ����պ���˥��ݥ�ƥ��˥����˹Ԥʤ����Ρ�����ξ���Ǥ��롣��Ԥξ�硢�ֲ��פ�¨��Ū�˹Ԥ��롣
�����顢��ŵ�ڶʱ��դ����ˡ�¨�������Ρפȹͤ���ʤ�С����λ����Ǵ��˺���������ʤ���ʤ��Ȥ�����ͤ�����Τ��ɤ����������路���Τ����ˡ��Ҥ뤬���äơ��Ҳ���ǰŪ�ˡ�¨�����ڡפȹͤ����Ƥ��뤵�ޤ��ޤʥ�����ˤĤ��Ƹ����С�����餬���٤ƽ��������¨���פǤ���Τ����ȸ�����ɬ�����⤽���Ȥϸ����ڤ����ʬ������ΤǤ��äơ��դˤ��Τ��Ȥΰ�̣��ط��Ԥϻ�³Ū���䤤³����ɬ�פ����롣��ʬ�Τ�äƤ��뤳�Ȥϡ�¨���פ����������ˡ�¨����ʤΤ�...�ȡ�
�����⡢��������¨���ʤΤ��פȤ����䤤�ˤĤ��Ƥ⡢�����ܼ������������ˤ˻�����ʳ��Ȥ��ơ�����ؤγƼ��δؤ�����ο����˸���ä����䤬������Ū������Ǥ��롣�������������͡��Ǥ������褦��
�㤨�С�ͭ�¤ʵ�����Ρְ����Ф��פ����Ѥ��뵤�ޤ���ʡּ���ȿ�����פ��ˡ��°פ�¨�����¨����ȴ������ʤ����ʤ�¨����Ρֻ��ۡפ�ֶ����פ�����Τ��ΤäƤ��뤷��ɽ���Ԥˤ��ֶ����פ�ǽưŪ�������Բ�ǽ����ˡ����⤽��¨�����դ��ɽ���Ȥ��Ƥβ��ڡפȸ��ʤ��٤����ɤ����Ȥ�������Ū�ʡʤ����Ƹ�ŵŪ�ʡ��䤤�����뤳�Ȥ��ΤäƤ��롣���������ڤ�ɽ���Ԥΰջפȴ����ʰռ��Υ���ȥ�����β����֤��褦��¨�����¨����ȸƤ֤٤����ɤ������䤦�����⤢�롣���˶�ȯŪ���Ǥξ��ʤ���¨�������פʤɤ������褵��Ƥ��ʤ��ˤ�ؤ�餺������Ÿ�����ۤȤ�������ϰϡ�ͽ�۲�ǽ���ϰϡˤǤ���Ȥ��������¨���ȸƤ֤٤��ʤΤ����Ȥ����䤤�����롣�������Ȥ��Ƥ⡢����Ϥ���������ǽ�Ǥ��롣����������ˡ�ͽ�۲�ǽ�Ǥ���פ���ȸ��äơ����β��ͤ������ʤƷפ��Ȥ�����ΤǤʤ��Ȥ�����ʬ�⤢�롣�⤷��ͽ���Բ�ǽ���פ��������ڤβ��ͤǤ�����Ǥ���С����ޤ�¸�ߤ������Ƥ�ȿ��Ū�˱��ղȤ����ˤ�äƼ��夲���Ƥ�����ŵ�ڶʤˤϲ��ͤ��ʤ����Ȥˤʤ뤬������Ϥ�����ǧ����ȿ���븫��Ǥ��롣��ͽ���Բ�ǽ���פϡ��������Τ������Ǥ��äơ������ؤ˲��ڤ����˵�����٤����ž�Ǥ�����Ū��ǽ�Ǥ�ʤ��ΤǤ��롣
������������̤äƤ⤦���١ֲ��ڤ���ˡפȤ�����Τ�Ļ�פ����Ȥ�����ɡ�¨���פϲ����Ϻ��Ρ֤ۤȤ��ͣ�����ˡ�פ��ä����������Ĺ�������ڤˡֺ�ʼԡפ�������������ξ��֤�פ��⤫�٤Ƥߤ�Ȥ���������Ū�ʡֺ�ʲȡפ����줿�ΤϤ�������400ǯ�ۤ����դ꤫��Ǥ��롣̾���Τ���ֺ�ʲȡפ�ǧ������Ϥ��Τ����θĿͼ����˨��Ϥۤܰ��פ��롣�������㳰�������ΤΡ����������ֺ���Ժߡפβ��ڻ���ϡ��ۤ��500ǯ����1000ǯ�����������������ä������ˤ�äƤϤۤ�ο���ǯ���ޤǤ����Ǥ��ä���⤢�롣Ĺ�����Ѥ�äƤ�ֺ�ʼԡפ��о�ϡ���˻���ʹߡ�ͭ�˰���ˤ��äʤΤǤ��롣��˰����λ���β��ڤϡ��ۤܤ��٤Ƥ�̵̾�γڻդ⤷���ϡȥ��㡼�ޥ�ɤˤ��¨���ȱ��աɤǤ��ä��Ϥ��Ǥ��롣���뤤�ϡ����褵�줿���Ȥ�ʤ��ֵ������줿��Χ�פ���פȤ��ƤΥ��ɥ�֤Ǥ��ä��Ϥ��Ǥ��롣���뤤�Ͻ��������dzڴ�ʤɤˤ����Χ��ȼ��ʤ�¨�������ʤ��[����]��[¨��]���ä������Τ��Ȥ�פ��������С����ߤ���줬�ƤӲ����Ϻ��μ�ˡ�Ȥ��ơ�¨���פ���夲�뤳�ȼ��Τˡ����Ρֿ��������פ�ʤ��ΤǤ��롣����Τϡ�¨����ֺƤӼ��夲��פˤ����äơ��������������פ��ʤ���кѤޤʤ������Ρֻ���Ū�����פǤ��롣
���������ʾ�Τ��Ȥ٤�����ȹͤ�����ǡ������Ԥ�����ʤ����Ȥ��ޤ��ޤ�����������Τ��Ȥʤ���ˡ��ޤ����嵭���äˤϡ�����������̤Ǥ��������ä����Ƥ��ʤ�����������ϰռ�Ū������Ƥ��뤳�Ȥ�����¨���פȤ������դΤ�äȤ�ʿ�Ĥ���ˡ���äƤΡ��������ʾ�Ǥ�ʲ��Ǥ�ʤ��������Ӥ�¨���٤Ρ���������ǵ��ֻ�����פ�����ʤ����ä��ꡢ����Ū�ʻװԤμ�³����Ф��˰���ξ�Ǥ���������˴٤뤳�Ȥ��Ф��ơ���ˤ��礤�ʤ�ٲ������뤫��Ǥ��롣�ष���������������ʬ��������������Ȥ��Ƥ������ޤ�����Ƥ��ʤ���ʬ�������ǽ�ʸ¤ꤢ�֤�Ф����Ȥ������Ͼ�����ʤ���Ԥ����פ˲ݤ���줿����Ǥ��ꡢ�����˻���ƻ�Ǥ��뤫��ʤΤǤ���ʤȡ������ʤꤳ���դ�ǡ���������Ū�ʿ��̤��ӤӤƤ��롪�ˡ�
�ʾ塢����Ū�����夷����¨����¿�����ˤĤ��Ƥϡ���ʬ�������˼���Ū��������Ū�˹ͻ����褿�Ĥ������äˡ���˼�ʬ���ɵ᤹����Ρ�¨���䤬�Ԥʤ��Ƥ��뤫�Ȥ������ȤˤĤ��Ƥ������ϡ����������ꤿ�����������⤷��¨���פ����ʤǤϤ��äƤ����Ū�פǤϤʤ���ɬ�������ӤӤ��ַ�Ū�����ζ�������ɽ���Υ�����Ǥ���С����μ�ˡ����¨���פ���ޤ����֥ץ��פǤ��äƤ�褤�����ץ�줿��ΤǤ��äƤ⡢�ǽ�Ū�ˤϡ֤��ξ��¨�����줿��ΤȤ����פ��ʤ��פȤ����褦�ʡ�ɬ���������ӤӤ����Τ�Τ��ɤ�������������������ˤ����ơ��㲻�ڡ䤬��̤Ǥ��ꡢ¨�������̤ʤΤǤ��롣
�����ơ���ä��ߤ�����С�����ˤȤäƤΡ�����Ū�����ɽ�������Ȥ����פ��ʤ���Τ�¨�����ڤ��̤��ƺ��夲�뤳���Ǥ��롣����ˤ�äơ�İ�Ԥϲ���̤��ػ��ҤȤĤΡֳ��פ�������������줬�����줿�Ȥ��˽��ơȥ��㡼�ޥ�ɤȤ��ơ㲻�ڡ�ä����Ȥˤʤ��������
��������Ƭ�ǡ����٤�����פ��Ǥä���¨���פ������ڤ˸¤�̤���礭������ؤ��ä���礷�Ƥ��äƤ⡢�����������Ѥ����ä����Ȥ��Ť��줿�����������ֲ桹�ˤȤä�������Ȥ������ȼ��Τ�¨���פǤ��äơ�ͽ¬�Բ�ǽ�������ˤ����ƴ������������ĤĤ��뤢������֤���ֵ���ơ������Ρ����١פ������ϤȤδط�����Ǽ��ʤι٤��Ŭ��Ŭ��פ������٤����ɤ��ޤǽ��𤫤�ľ��Ū�ǡ��ޤ����֤˾���٤�ʤ��������Ҿ�����ȯ���Ǥ��뤫���Ȥ����������뤿��ε��ѡפȤ��ä�ʸ̮�Ǥ��뤳�Ȥ��Ǥ��롣����������Ǥ�ʤ��������Ƥ�¨���פȤ����褦�������ؤΡ�Ʊ��Ū�б��פȰ���ξ�ǤǤ���ۤɡ����¤�ñ����äǤϤʤ���
������ͳ��������¨���פ������٤�����פǤ���Ȥ����Ƹ�����ʤǤ��롣�ʤ��ʤ�С���������˱����Ƥ����Ƥ�¨���Ǥ������ǤϤʤ����ץ���Ȥ������ꡢ���������Ф����֤����ꡢ�פä��̤�β���Ф����Ȥ��뽤�������ꡢ����Ф���������Ρʥ�ɤ��ä���Ȥ�������ƻ�ʸĿ�Ū���Ϥ����롣����餬�֤��٤�¨���פȤ������դǸƤФ������������ΤǤ���Τ��ϡ�����Ƚ�Ǥ������ɤ���������������ɮ�Ԥϡ�¨����Ȥ�¾�Ԥ�Ķ������äƤΡ��Ҳ�Ū������Ū���⤷���ϳ����ȤΡִؤ��פ���Ǥ�����θ�������ˡ�Ǥ��äơ�������������Ū�ʸ��դ���ˡ���������θ��դΡ������פ����ܼ�Ū���������Τ��ȿ����롣
�������äơ����Τ褦��ʸ̮�˱����ơ��ष�����ơ�¨���ȸ���������١פ����Ʋ��ڤˡȻ�������ɤ��ȤΡ��������פ��ĥ���뤳�Ȥ�����롣�����ơ������ˤ�����˱�����Τ�Ʊ�ͤΥꥹ���������ƥꥹ�����餦�ʹ֤��������뤳�Ȥν�������������Ū���̡ʼ��Ԥ�������ޤ�ơˤȤ����̼¤�Ϳ������ΤǤ��롣
����ˤĤ��Ƥϡ�����ޤ��Ȥ��Ť��줿���������⤷��̤����ֿͻ���Ԥ�����ŷ̿���ԤġפȤ�������ʾ�Τ��ȤΤȤ�����ϻפ��Ĥ��ʤ��ΤǤ��롣
�����Ǥϡ��ǽ�˼����ʹ١ˤ��꤭���Ǥ��ꡢ�������פϸ夫��ȯ��������Τ��Ȥ����ͤ������Ȥ�����ʤ��ΤǤ��롣�ǽ�˲��ڤ����äơ����줬�������פ�ƤӴ�ΤǤ��롣
�ʤȡ������˻�äƤ褦�䤯��¨�������פȤ�����ΤˤĤ��ƥե�����������Ω�����֤�����ΤǤ��롣��
�����Ĺ��Ĺ���ʷ������Ū�ͻ��˴ؤ���������Ū�������������������ˤ���줬�ޤ�������Ȥ���λ�Ƥ��Ƥ��»�Ϥ��ʤ����äΰ�ĤǤ��롣
��
�⤦�����դ�ϡ������ʤ�Ƭ�Ǥ�ͤ��Ԥ������Ԥ������������ꡢ���ޤ��鲿���դ��ä��뤳�Ȥ�����Τ�ʬ����ʤ���������ľ�ʤȤ��������������ơ��Τ�ʤ���ʬ�פ�⤦���������Ф�����˼��ʤˤ����ݤ����ޤ����ص�Ū�ˡ�ª�����������פ٤ƾʤ������˸����̤Ǥ��ä롣�ʤ�������Ǥ�Ĺ���ʸ�Ϥˤʤ�����β��꤬���롣��
���ˡ�����Ū�ʲ���ɽ���˱����ơ����μ�ˡ����¨�������ץ�פȤ����Τϡ���ɤϡ����٤�����פˤۤ��ʤ�ʤ��ΤǤ��äơ��ִ�����¨���פǤ��뤫�ִ����˥ץ��פǤ��뤫�Ȥ����褦������Ǹ�뤳�ȼ��Τ��ʥˤʤäƤ��롣��������¨���פȤ������ȤϤ��������ä������������Υץ��פȤ������Ȥ�Ʊ�ͤˤ��������äʤΤ����Ĥޤꡢ¨�����Ф��ơ�����̵���פȤ����褦�������줬����ΤǤϤʤ��ơ�������ɤ��֥֥��ɡפ���Τ����Ĥޤ�ɤ��������¨���פȤ������Ǥ��̣������Ǥ���Τ��Ȥ������Ȥ�������¨���ԤˤȤäƤμ�ͳ���ٹ礤�Ǥ⤢��Ϥ������ޤ��ˤ���Ϥ����ο������Τ�Τ�Ʊ�ͤˡ�
�������Ƕ������Ƹ����С���ˡ�Ȥ��ƤΡʤ��뤤�ϥ��ƥ���Ȥ��ƤΡˡ�¨�����ڡפ˲��θ��ۤ����ʴ��Ԥ�ʤ��ʼ¤ϡ���˸��ڤ��롩�褦�ˡ��������ʬŪ�ˤϱ��ʤ�����ɡˡ��ʲ��˽Ҥ٤�褦�ˡ���¨���פȤϡ�¨�����ڤ䤽��¾�ηݽ��Ϻ���������ž�ǤϤʤ�����Ǥ��롣�����뤳�Ȥ��Τ�Τ���������¨���Ǥ���Ȥ������Ȥ�λ�Ƥ���Ф������ʤ�����˲��ڤ�¨������¦�̤����˲���ɾ����ä��뤳�Ȥ��Ф��ơ���Ͼ�ˡ֤���ϸ�ʿ���˷礤���������Ǥ���פ���Ƚ�����褿�ΤǤ��롣¨�������л롿���̻뤹����Ρ��������פ��ȸ�����̣�ǡ�������¨����������Ƥ���¿���οͤ����ȿ�����������������Ȥϳи�ξ�ǡ�
�ǽ�˲��ڤ˸¤ä��ä�С���ŵ�ڶʤ�ֳ����̤���դ��Ƥ���פ���ʹ��������դǤ⡢�����줿���դǤ���ȴ��������Τϡ������ơ�¨����Ū�ǡ�������ͭ��Ū�Ǥ��롣�Ĥޤ�ֺ�ʤ��줿���ڤ��ʹ֤��դ��Ƥ���פȤ����פ��ʤ��褦�ʡ��ðۤ�ɬ�����פ�����Ƥ����礬�ҤȤġ������Ƥ⤦�ҤȤĤϡ��ֳ����̤�פȤϸ��äƤ⡢���ڤ����Ƥ����褵��뤳�Ȥ����ꤨ�̰ʾ塢�����Τ��Ȥʤ��顢®�١����̡������å��������Ĺ��������������¾�Ρ������벻��ɽ�����Բķ�ʡ���̩�ʵ��褬�Բ�ǽ�����ǤˤĤ��Ƥϡ��ۤ��Բ���Ū�ˤ��ξ줽�ξ��Ƚ�ǤǤ��Ρֺ��ø��פ�����Ƥ������¤ϡ����줳�����ष�����ڤΡּ��פ���ʬ�פǤ��롣�Ǥ���ʾ塢��ŵ�˴ؤ��Ƥϡֲ��פ�ɬ�ܤȤʤꡢ��ŵ�ڶʤα��չ٤������չ٤νִ֤˱����Ƥϡ�¨���١פ����Բ�ʬ�����Ǥ��롣�����ǽ�ʤɤ����ܤ�������ǽ�˴ؤ��Ƥ�Ʊ�ͤΤ��Ȥ�������Ϥ��Ǥ��롣
�ޤä�����äơ����褵��Ƥ��뤳�ȼ��Τ����ʼ��ΤΤ��������鷺������ʬ�ʤΤ����顢���ڲȤˤȤäƤϡ�������ɤ���ᤷ���ɤ��ºݤι٤�ž������Τ��Ȥ�����ʬ������ɽ�������ΤʤΤǤ��롣�����Ǹ��ä��ֲ��פȤϱ��չ٤���Ω�äƹԤʤ���Ρ����պ���˥��ݥ�ƥ��˥����˹Ԥʤ����Ρ�����ξ���Ǥ��롣��Ԥξ�硢�ֲ��פ�¨��Ū�˹Ԥ��롣
�����顢��ŵ�ڶʱ��դ����ˡ�¨�������Ρפȹͤ���ʤ�С����λ����Ǵ��˺���������ʤ���ʤ��Ȥ�����ͤ�����Τ��ɤ����������路���Τ����ˡ��Ҥ뤬���äơ��Ҳ���ǰŪ�ˡ�¨�����ڡפȹͤ����Ƥ��뤵�ޤ��ޤʥ�����ˤĤ��Ƹ����С�����餬���٤ƽ��������¨���פǤ���Τ����ȸ�����ɬ�����⤽���Ȥϸ����ڤ����ʬ������ΤǤ��äơ��դˤ��Τ��Ȥΰ�̣��ط��Ԥϻ�³Ū���䤤³����ɬ�פ����롣��ʬ�Τ�äƤ��뤳�Ȥϡ�¨���פ����������ˡ�¨����ʤΤ�...�ȡ�
�����⡢��������¨���ʤΤ��פȤ����䤤�ˤĤ��Ƥ⡢�����ܼ������������ˤ˻�����ʳ��Ȥ��ơ�����ؤγƼ��δؤ�����ο����˸���ä����䤬������Ū������Ǥ��롣�������������͡��Ǥ������褦��
�㤨�С�ͭ�¤ʵ�����Ρְ����Ф��פ����Ѥ��뵤�ޤ���ʡּ���ȿ�����פ��ˡ��°פ�¨�����¨����ȴ������ʤ����ʤ�¨����Ρֻ��ۡפ�ֶ����פ�����Τ��ΤäƤ��뤷��ɽ���Ԥˤ��ֶ����פ�ǽưŪ�������Բ�ǽ����ˡ����⤽��¨�����դ��ɽ���Ȥ��Ƥβ��ڡפȸ��ʤ��٤����ɤ����Ȥ�������Ū�ʡʤ����Ƹ�ŵŪ�ʡ��䤤�����뤳�Ȥ��ΤäƤ��롣���������ڤ�ɽ���Ԥΰջפȴ����ʰռ��Υ���ȥ�����β����֤��褦��¨�����¨����ȸƤ֤٤����ɤ������䤦�����⤢�롣���˶�ȯŪ���Ǥξ��ʤ���¨�������פʤɤ������褵��Ƥ��ʤ��ˤ�ؤ�餺������Ÿ�����ۤȤ�������ϰϡ�ͽ�۲�ǽ���ϰϡˤǤ���Ȥ��������¨���ȸƤ֤٤��ʤΤ����Ȥ����䤤�����롣�������Ȥ��Ƥ⡢����Ϥ���������ǽ�Ǥ��롣����������ˡ�ͽ�۲�ǽ�Ǥ���פ���ȸ��äơ����β��ͤ������ʤƷפ��Ȥ�����ΤǤʤ��Ȥ�����ʬ�⤢�롣�⤷��ͽ���Բ�ǽ���פ��������ڤβ��ͤǤ�����Ǥ���С����ޤ�¸�ߤ������Ƥ�ȿ��Ū�˱��ղȤ����ˤ�äƼ��夲���Ƥ�����ŵ�ڶʤˤϲ��ͤ��ʤ����Ȥˤʤ뤬������Ϥ�����ǧ����ȿ���븫��Ǥ��롣��ͽ���Բ�ǽ���פϡ��������Τ������Ǥ��äơ������ؤ˲��ڤ����˵�����٤����ž�Ǥ�����Ū��ǽ�Ǥ�ʤ��ΤǤ��롣
������������̤äƤ⤦���١ֲ��ڤ���ˡפȤ�����Τ�Ļ�פ����Ȥ�����ɡ�¨���פϲ����Ϻ��Ρ֤ۤȤ��ͣ�����ˡ�פ��ä����������Ĺ�������ڤˡֺ�ʼԡפ�������������ξ��֤�פ��⤫�٤Ƥߤ�Ȥ���������Ū�ʡֺ�ʲȡפ����줿�ΤϤ�������400ǯ�ۤ����դ꤫��Ǥ��롣̾���Τ���ֺ�ʲȡפ�ǧ������Ϥ��Τ����θĿͼ����˨��Ϥۤܰ��פ��롣�������㳰�������ΤΡ����������ֺ���Ժߡפβ��ڻ���ϡ��ۤ��500ǯ����1000ǯ�����������������ä������ˤ�äƤϤۤ�ο���ǯ���ޤǤ����Ǥ��ä���⤢�롣Ĺ�����Ѥ�äƤ�ֺ�ʼԡפ��о�ϡ���˻���ʹߡ�ͭ�˰���ˤ��äʤΤǤ��롣��˰����λ���β��ڤϡ��ۤܤ��٤Ƥ�̵̾�γڻդ⤷���ϡȥ��㡼�ޥ�ɤˤ��¨���ȱ��աɤǤ��ä��Ϥ��Ǥ��롣���뤤�ϡ����褵�줿���Ȥ�ʤ��ֵ������줿��Χ�פ���פȤ��ƤΥ��ɥ�֤Ǥ��ä��Ϥ��Ǥ��롣���뤤�Ͻ��������dzڴ�ʤɤˤ����Χ��ȼ��ʤ�¨�������ʤ��[����]��[¨��]���ä������Τ��Ȥ�פ��������С����ߤ���줬�ƤӲ����Ϻ��μ�ˡ�Ȥ��ơ�¨���פ���夲�뤳�ȼ��Τˡ����Ρֿ��������פ�ʤ��ΤǤ��롣����Τϡ�¨����ֺƤӼ��夲��פˤ����äơ��������������פ��ʤ���кѤޤʤ������Ρֻ���Ū�����פǤ��롣
���������ʾ�Τ��Ȥ٤�����ȹͤ�����ǡ������Ԥ�����ʤ����Ȥ��ޤ��ޤ�����������Τ��Ȥʤ���ˡ��ޤ����嵭���äˤϡ�����������̤Ǥ��������ä����Ƥ��ʤ�����������ϰռ�Ū������Ƥ��뤳�Ȥ�����¨���פȤ������դΤ�äȤ�ʿ�Ĥ���ˡ���äƤΡ��������ʾ�Ǥ�ʲ��Ǥ�ʤ��������Ӥ�¨���٤Ρ���������ǵ��ֻ�����פ�����ʤ����ä��ꡢ����Ū�ʻװԤμ�³����Ф��˰���ξ�Ǥ���������˴٤뤳�Ȥ��Ф��ơ���ˤ��礤�ʤ�ٲ������뤫��Ǥ��롣�ष���������������ʬ��������������Ȥ��Ƥ������ޤ�����Ƥ��ʤ���ʬ�������ǽ�ʸ¤ꤢ�֤�Ф����Ȥ������Ͼ�����ʤ���Ԥ����פ˲ݤ���줿����Ǥ��ꡢ�����˻���ƻ�Ǥ��뤫��ʤΤǤ���ʤȡ������ʤꤳ���դ�ǡ���������Ū�ʿ��̤��ӤӤƤ��롪�ˡ�
�ʾ塢����Ū�����夷����¨����¿�����ˤĤ��Ƥϡ���ʬ�������˼���Ū��������Ū�˹ͻ����褿�Ĥ������äˡ���˼�ʬ���ɵ᤹����Ρ�¨���䤬�Ԥʤ��Ƥ��뤫�Ȥ������ȤˤĤ��Ƥ������ϡ����������ꤿ�����������⤷��¨���פ����ʤǤϤ��äƤ����Ū�פǤϤʤ���ɬ�������ӤӤ��ַ�Ū�����ζ�������ɽ���Υ�����Ǥ���С����μ�ˡ����¨���פ���ޤ����֥ץ��פǤ��äƤ�褤�����ץ�줿��ΤǤ��äƤ⡢�ǽ�Ū�ˤϡ֤��ξ��¨�����줿��ΤȤ����פ��ʤ��פȤ����褦�ʡ�ɬ���������ӤӤ����Τ�Τ��ɤ�������������������ˤ����ơ��㲻�ڡ䤬��̤Ǥ��ꡢ¨�������̤ʤΤǤ��롣
�����ơ���ä��ߤ�����С�����ˤȤäƤΡ�����Ū�����ɽ�������Ȥ����פ��ʤ���Τ�¨�����ڤ��̤��ƺ��夲�뤳���Ǥ��롣����ˤ�äơ�İ�Ԥϲ���̤��ػ��ҤȤĤΡֳ��פ�������������줬�����줿�Ȥ��˽��ơȥ��㡼�ޥ�ɤȤ��ơ㲻�ڡ�ä����Ȥˤʤ��������
��
��������Ƭ�ǡ����٤�����פ��Ǥä���¨���פ������ڤ˸¤�̤���礭������ؤ��ä���礷�Ƥ��äƤ⡢�����������Ѥ����ä����Ȥ��Ť��줿�����������ֲ桹�ˤȤä�������Ȥ������ȼ��Τ�¨���פǤ��äơ�ͽ¬�Բ�ǽ�������ˤ����ƴ������������ĤĤ��뤢������֤���ֵ���ơ������Ρ����١פ������ϤȤδط�����Ǽ��ʤι٤��Ŭ��Ŭ��פ������٤����ɤ��ޤǽ��𤫤�ľ��Ū�ǡ��ޤ����֤˾���٤�ʤ��������Ҿ�����ȯ���Ǥ��뤫���Ȥ����������뤿��ε��ѡפȤ��ä�ʸ̮�Ǥ��뤳�Ȥ��Ǥ��롣����������Ǥ�ʤ��������Ƥ�¨���פȤ����褦�������ؤΡ�Ʊ��Ū�б��פȰ���ξ�ǤǤ���ۤɡ����¤�ñ����äǤϤʤ���
������ͳ��������¨���פ������٤�����פǤ���Ȥ����Ƹ�����ʤǤ��롣�ʤ��ʤ�С���������˱����Ƥ����Ƥ�¨���Ǥ������ǤϤʤ����ץ���Ȥ������ꡢ���������Ф����֤����ꡢ�פä��̤�β���Ф����Ȥ��뽤�������ꡢ����Ф���������Ρʥ�ɤ��ä���Ȥ�������ƻ�ʸĿ�Ū���Ϥ����롣����餬�֤��٤�¨���פȤ������դǸƤФ������������ΤǤ���Τ��ϡ�����Ƚ�Ǥ������ɤ���������������ɮ�Ԥϡ�¨����Ȥ�¾�Ԥ�Ķ������äƤΡ��Ҳ�Ū������Ū���⤷���ϳ����ȤΡִؤ��פ���Ǥ�����θ�������ˡ�Ǥ��äơ�������������Ū�ʸ��դ���ˡ���������θ��դΡ������פ����ܼ�Ū���������Τ��ȿ����롣
�������äơ����Τ褦��ʸ̮�˱����ơ��ष�����ơ�¨���ȸ���������١פ����Ʋ��ڤˡȻ�������ɤ��ȤΡ��������פ��ĥ���뤳�Ȥ�����롣�����ơ������ˤ�����˱�����Τ�Ʊ�ͤΥꥹ���������ƥꥹ�����餦�ʹ֤��������뤳�Ȥν�������������Ū���̡ʼ��Ԥ�������ޤ�ơˤȤ����̼¤�Ϳ������ΤǤ��롣
����ˤĤ��Ƥϡ�����ޤ��Ȥ��Ť��줿���������⤷��̤����ֿͻ���Ԥ�����ŷ̿���ԤġפȤ�������ʾ�Τ��ȤΤȤ�����ϻפ��Ĥ��ʤ��ΤǤ��롣
�����Ǥϡ��ǽ�˼����ʹ١ˤ��꤭���Ǥ��ꡢ�������פϸ夫��ȯ��������Τ��Ȥ����ͤ������Ȥ�����ʤ��ΤǤ��롣�ǽ�˲��ڤ����äơ����줬�������פ�ƤӴ�ΤǤ��롣
�ʤȡ������˻�äƤ褦�䤯��¨�������פȤ�����ΤˤĤ��ƥե�����������Ω�����֤�����ΤǤ��롣��
23:39:00 -
entee -
TrackBacks
2005-08-02
ʹ�����Ƥ����Τ���ˡ�ʹ�����ʤ���Τ�ʹ�����Ȥ��뤹��פ��פ��뤳�ȡ�
�����ࡢ���ä��Ǥ⤳�ä��Ǥ�ĥʥ��äơ��֥����������Ϲ����㡪
�椬��ͧ�����ɥ����������� �� ������ɾ�� �� GPS�Ͼ峨�դ��������blog�ˡ��ʤ�Ȥ�ɷ�Ū�ǡ���������ܥ����Ф��ơ��ɤ�פ�ȯ�����Ƥ��Ƥ���褦�ʡ��ҤȤ����ܤ�椯��̾���ꡣ
�ءָ������Τ���ˡ������ʤ���Τ褦�Ȥ���פ��פ���Ȥ������ȡ���
���������¹�����װ��Ѥ��Ƥ����ƣŵ�Τ��������Ȥ����Τˡ���ߤ�פƻפ鷺�ɤ����äƤ��ޤä��������Ǥ��ä�����Ѥ���ȡ���¹�����פˤʤäƥ辰��ʬ����ʤ����Ȥˤʤ�Τǡ�����blog���ɤߤ����ϡ����������ɤ��ĺ�������ʤ��äƤ��������Τ���ñ�ˤǤ���Τ����ͥåȵ��Ѥʤ������ˡ����ڤˤĤ��Ƥ�¿�Ťˤ��Ρ֥�������ޥ�פȡ֥ǥ�������ޥ�פ�Ŭ�Ѥ��줽���ʤ��Ȥ˵��դ���������������Ϥ�����ñ�����ƤϤ���ʤ�����⤢�롣
����ϡ��ʹ֤���դ���Ϳ���ʤ�����Ȥ��ƤΡ����ʡפȡ��ʹ֤���դ���Ϳ����Τ�����Ȥ��Ƥ���ֲ��ڡפ����ưפ�Ʊ��˸��ʤ��Ȥ����Ҳ���ǰ��λ��������뤫�����������������Ǥ⡢���Ȥ��ܤι⤵�ʿ���Ū��٥�ˤ��Ѥ��Ƥߤ�ȡ����줬Ŭ�Ѥ��줦������̡פ������ڤˤ����Ƥ��⤫�Ӿ夬�äƤ���Ȥ�����̣�������¤ˤ�פ���ä���
���Ĥ�Τ褦�ˡ�����Ρ�¹�����פ���������Ŭ����ʸ�Ϥ���롣�ʺǶᡢ�������������ʡ��ܥ�...��
�ޤ��ǽ�����ϡ��ֲ��������ˤĤ��Ƥ��áפȤ����ɤ���ˡ��ɬ�סˤ����롣���Ȥ��в��ʤɤϡ��ưפ�����Ǥ���Ŭ�������
<<
�º����ꡢ��ü���������İ�Ԥ������Υ��С����ä��ꤹ��ȡ�¾�Υ�����İ���Ƥ��Ƥ⼫ʬ������ô�����Ƥ���ڴ�Υ����Ȥ������뤤��������������Ū��İ���Ƥ����ꤷ�ơ����ΤȤ��ơʺ�ʲȤΰտޤ��Ƥ����̣�ǤΡ˲��ڤ�İ���Ƥ���Ȥ����������θ��Ȥϰ�ä���ΤˤʤäƤ��ޤ��ʤ�����վޤ�ã�ͤˤʤäƤ���ȡ������������ʤʤ�ʹ�����ˤ���������ּ��פ�ȴ���Ф��ơ�������ɡ��������������������ѡ��Ȥ�ڤ���ʤ�Ƥ������ݺ������ɲ��ڤγڤ������⤢��������...�ˡ�����ʡ���ü�����ʤ��Ƥ⡢�Ƴ��褯���뤳�Ȥʤ�ǤϤʤ������������Ĥޤꡢ�ȡֲ��ڡפ�İ���Ƥ���Ȥ����ռ��������ʤ��ɤȤ����Τϡ����äƤߤ�Сֲ��ڴվް����פξ��֤Ȥ������Ǥ��롣
<<
�դ�դࡣ�ޡ��Ǹ�����������������äǤϡ����롣���ڤ����ΤȤ��ơְ�Ĥι�¤�פȤ���İ����롢�Ȥ������Ȥ����ޤ��ˡֲ��ڤ�İ�������٤Ǥ����θ����������������������������������Ω����Τϡ������ޤǤ���
���������ֲ��ڡפ���Ω�Τ����ˡ������������ֲ��ڡפϾä����ΤǤ��� <<
�����ˡֲ��ڤϾä���פΤ��ȸ����ȡ����ڤ��Τ�Τ��������äƤ���¤ꡢ���뤤�ϲ��ڤ��Τ�Τ����������˴ؿ���������Ƥ���¤ꡢ������ñ�˲��ڤ��־ä��ơפ��ޤ����ȤϤʤ������ڤϤ����Ƥ��ξ�硢�ä����β��ڤξ�硢�̾��ʲȤ���ղȤϡ����̤˽������Ĥ餵���٤��������Τ�Τ�İ���Ƥ���פ����äƤ��뤫��Ǥ��롣�ʾ��ʤ��Ȥ⡢���Τ褦�˻פ��Ƥ���褦�˸�����ʡ��糵�����β��ڤϡ���
�������äơ�����������٥�Ǥϡ���ȿ������ĤΤ�Τ�Ʊ���ֲ��ڡפ�̾�ǸƤ֤��Ȥ���������ֲ������κ���פȤ����Τϡ����ޤ�����ˤʤ�ʤ������������㳰Ū��¨�����ڤˤ����Ƥϡ������������Ȥ��礤�ˡʴվޤˤȤäơ˲���Ȥʤ�θ�ҡϡ������ơ������ü��İ�Ԥο������֤ˤ����Ƥϡ��ۤȤ�ɲ���Ū�θ��ȸƤ֤���������餶��ֲ����θ��פȤ�����Τ�����Τ�Τ�����
�Ĥޤꡢ����ڤ�ޤ����äȹ����Ķ��������Ȥ����Ȥ����ޤdz��礹��ȡ������Ȥ�������Τ����ĤޤꡢŬ�ѤǤ��ʤ��ä��Ǹ����ʬ����Ŭ�Ѳ�ǽ�Ǥ��ꡢ���줳���������ڤ�վޤ����θ�����Ǥ⡢�Ǥ�������ʬ�Ȥ������Ȥˤʤ롣
<<
���Ȥ��С����ڲ�Dz��ڤ��椷��İ���Ƥ��ơ����뤤���Ť��ʴĶ��Ǥ�ä��꤯�Ĥ����ǥ쥳���ɤ�İ���Ƥ��ơ��ֲ��ڤ��ä���פȤ����θ����۵�����Τ����ʥ����ǥ����ޥ˥��������������ɤ����ϡ������ǥ������֤��ä���פȤ��������������������Ȥˡ������ǤϿ����ꤷ�ʤ����ˤ��ʤ�������ڤˤ���줬��������Ƭ�����Ȥ��ˡ��桹�������˲��ڡʲ��ˤ�İ��³���Ƥ���Τ����Ȥ�������Ǥ��롣�����餷�������θ��Ȥϡ�������ä�����Ū�ʿ���Ū�ˤʤ�Τǡ�����ϡֲ��ڼ��Τ���δ�ư�פȤ���ʪ�Ǥ��뤳�Ȥ�����ʤ��뤫�ʤ����ߤ�ʡ��ˡ����ڤ����ä����Ȥʤäơ��桹���̤ξ��˾������ã���Ƥ��ޤ�����Ǥ��롣���������θ�������ֲ��ڤ��θ��פ�Ʊ�����դǸƤ�Ǥ��ޤ��ȡ��Τ��˺��𤬤��롣
���ڲȤ����Ф����ʡʲ��ˤޤǤϲ��ڲȤ���Ǥ������������̤������Ƥ��ޤ���İ��¦��ǽưŪ�ʤϤ��餭�פˤ���θ��ϡ�ɬ�����ⲻ���θ����Τ�ΤȤϸ¤�ʤ�������������������Ȥ�İ��¦�������ǵ���������ڴ�ҤȤĤҤȤĤβ��������ǥ����ϡ��ִ��ΤΤ�ΡפǤ���ʤ��顢�θ��Ȥ��Ƥϡ�̤�Τ��ΰ�פ����äƤ���ִ֤��������ơ����˸����ȡ��վԤ�������Ū����˿�����Ū�θ�������Ȥ���С���������ˤ�����äƤ����Τ���
��������ϡ��դ���������θ��դؤΡ������פȤʤ롣
<<
���뤤�ϡ��̥ƥ�����
<<
�ä�æ�����뤬��
�����ʸ�ϡ�
<<
����ʬ�ϡ�������ִĶ����ڡס֥���ӥ���ȷϲ��ڡפʤɤ˴ط�������ĥ��ŵ���Ȥ����ɤळ�Ȥ����롣�Ĥޤꡢ������ɥ������פ�ȥ������������ɤ�Ω�������
�֥�����ɥ������ספϡ��ʲ���ˡ˥ǥ�����֤Ǥ��ʤ��פ�Τ��֤���פȤ������Ȥ�����ˤ��롣���ڤ��ΰ�ˤ����ơ֡ȥ��ɥ������ס�Ū���ץ������פ�Ȥ�ʤ顢������ޤ��Ϥ����ˡ��Ķ��������ʤ�����饹���Ĥ����������������Ʀ�岰��ū�β�����ǯʪ���Ȳ��γ��������Ҷ��ε㤭������ž�֤Υ֥졼���β����ʤɤʤɤΡ֥ǥ�����Ǥ��ʤ���Ρפ�¸�ߤ�ǧ���Ȥ�������Ϥ�롣�����ơ������֥ǥ�����Ǥ����Ρפ��֤��������ꡢʤ�ä��ꤹ��ΤǤϤʤ������������֥ǥ�����Ǥ��ʤ���Ρס֥���ȥ�������ǽ�ʤ�Ρפ����뤳�Ȥ������ࡣ
�Ȥ����櫓�����ʤ��ʤ�������Ū�����פȤʤ뤾������ϡ�
���ơ���¨���פˤĤ��ơ��̾ﲻ�ڤȶ��̤��Ƹ�äƤ������𤫤�����ȡ��Ǹ�ˤ������ڤ��ʤ��ǺѤޤ������ˤϹԤ��ޤ����������餬����ä����֤���
¨�����ڤ����ʤ�������ˤĤ��ơ㤳�Ȥ�����ȯ���������ʤ���ͳ�ΤҤȤĤȤ��ơ������˶��̤ʥꥢ�륿�����������ݥ�ƥ��˥����������롣�Ĥޤꡢ¨�����ڲȤ����ϡ�����¨���ˤ����Ƥ��äˡ����줾�줬�������ټ�ʬ�ˤȤäƴ��ΤΡֻ������ס�����γڴ��ƥ��˥å��ˤ���äƥ��ơ������о줹�롣�������ҤȤ��Ӳ����Ф����䡢��ʬ�Ȥ�������Ф����ΰʳ��Ρ�̤�Τ����ǡס�ͽ���Բ�ǽ�����ǡפȤ����Τˡ�ɬ��Ū���������롣�����ơ��ܿͤα��դ��Ϥ�ƽ���ʬ�������Ĵ��ǧ���פ��������롣�����ơ�����ؤΥꥢ�륿����Ρ��б��פ������롣�礭��ʬ����С�����������̤�Τʤ����ǡפ��Ф��ơ�������̵�뤷�ƿʤ�פȤ����Τȡ����������Ѥ��ƿʤ�פȤ������٤Ρ����������פ�������ִ֤˽и���������ؤ�Ƚ�Ǥ�˻�����Ԥʤ�ʤ���Фʤ�ʤ�����������ʪ�����顢�ԤäƤ���ʤ��ΤǤ��롣�ޤ�ǡ����ʤΤ褦���������⡢�ɤΤ褦��̵�뤹��Τ������Τ褦�����Ѥ���Τ����Ȥ����ۤȤ��̵�¤��������椫�顢��äȤ⥫�å�������ˡ��ʤۤȤ����ǽŪ�ˡ��ֻ��ˡ����ʤ���Фʤ�ʤ���
̵�뤹�뤳�Ȥˤ�ä���������ĤΡʻ��ĤΡ�����ʾ�Ρ������Ρ�Ʊ��Ū�ʸ��������ޤ�Ǽ̿�����šʻ��š�¿�š�Ϫ�ФΤ褦�ʸ��̤�ʤ����������ȤƤĤ�ʤ���ħŪ�ʲ�����ۤ��Ƥ��ޤ����Ȥ⤢��С�ñ�ʤ�䤫�ޤ����������Ĥ��뤳�Ȥ⤢�롣��������̤�Τʤ����ǡפ��Ф��ơ��ߤ������Ѥ��ƿʤ�Ȥ������ȤǤ���ȯ�����ʤ����ꥢ�륿����˾�������붨��Ū��Ĵ��Ū�ִ֤�----�ޤ�ǡֿ����פΤ褦��----����Ū�ˡְ�̣�����Ρפ������뤳�Ȥ����롣
������ˤ��Ƥ⡢�����ʤΥǥ�����פ�Ʊ���褦�ˡ�¾�Ԥ�¸�ߤ�����Ȥ��������Բ�ǽ�����������뤳�Ȥˤ�äƤ�����Ω���Ԥ��ʤ����Ϻ�פκߤ�������¨�����ڤˤϤ���Τ���
¨�����ڤˤ����Ƥϡ��֤�������ޤ��Ķ��Τ�����֡�������ؤ��Ƥ����ΤǤ��äơ����ξ����Τ�Ȥˤ����ƥǥ�����Ȥ����٤�ɽ�ݤ����Τȡ�ɽ�ݤ��ظ������оݤδ֤ˡ��䤨�֤ʤ���ĥ�δط����ۤ���롣
���...
<<
�ȡ����ߤ�������äƤ���褦�ˡ����ڤˤ����Ƥ��¨�����ڤǤ���ФȤ�櫓�ˡ����ռԤϡ������˰�̣�Τ���Ĥʤ���Ф��ѻ��ԡʲ��ڴվԡˤˤ��ֲ��ڤ����ʲ����ɥ���פΡַ����פ��������ߤƤ��롣�Ĥޤꡢ¨�����ڲȤ����֥ǥ�����פ�����Τϼ¤ϡֲ��ڡפ��켫�ΤǤϤʤ����ΤǤ��롣
�վԤ������椫��ꥢ��ʡַ�ס����뤤�ϡ�ʪ��פȸƤ֤����������ΤФ��ַ����פ�¨�����ڲȤϡ����뤤�ϲ��ڲȤϡ���ߤ�ΤǤ��롣�����ˤϡ�ͽ��Ĵ��Ū�����ıߤϤʤ������⤷��ʤ����������ޤ�ʥ���ǡ������������̤˥ץ�줿�Ȥ����פ��ʤ��褦�ʡ�ϲ̡��Ū�ʡִ����ʪ��פ�ꥢ�륿��������߽Ф���ǽ�������Ƥ���ΤǤ��롣
�����ˤ�����¨�����ڤ����̣�������entee�ϡ��ͤ���ΤǤ��롣
�������ơ���������Υ��Ĥ�Ƴ���ˤ�äơ���ǯ�����إ��ɥ���������ɾ����١�INAX���ǡ��˴�����ʸ��¨�����ȷײ����˸������ʤȲ��ڤΥ��ʥ�����������¨�����ڲȤ�̴��Ū�����ʡ����ˤϡ��Ƥ������ܤ�ΤǤ��ä����ʤȡ����������Ȳ�������ɤ��ơ������ΤǤ��ä�������
[Read More!]
�椬��ͧ�����ɥ����������� �� ������ɾ�� �� GPS�Ͼ峨�դ��������blog�ˡ��ʤ�Ȥ�ɷ�Ū�ǡ���������ܥ����Ф��ơ��ɤ�פ�ȯ�����Ƥ��Ƥ���褦�ʡ��ҤȤ����ܤ�椯��̾���ꡣ
�ءָ������Τ���ˡ������ʤ���Τ褦�Ȥ���פ��פ���Ȥ������ȡ���
���������¹�����װ��Ѥ��Ƥ����ƣŵ�Τ��������Ȥ����Τˡ���ߤ�פƻפ鷺�ɤ����äƤ��ޤä��������Ǥ��ä�����Ѥ���ȡ���¹�����פˤʤäƥ辰��ʬ����ʤ����Ȥˤʤ�Τǡ�����blog���ɤߤ����ϡ����������ɤ��ĺ�������ʤ��äƤ��������Τ���ñ�ˤǤ���Τ����ͥåȵ��Ѥʤ������ˡ����ڤˤĤ��Ƥ�¿�Ťˤ��Ρ֥�������ޥ�פȡ֥ǥ�������ޥ�פ�Ŭ�Ѥ��줽���ʤ��Ȥ˵��դ���������������Ϥ�����ñ�����ƤϤ���ʤ�����⤢�롣
����ϡ��ʹ֤���դ���Ϳ���ʤ�����Ȥ��ƤΡ����ʡפȡ��ʹ֤���դ���Ϳ����Τ�����Ȥ��Ƥ���ֲ��ڡפ����ưפ�Ʊ��˸��ʤ��Ȥ����Ҳ���ǰ��λ��������뤫�����������������Ǥ⡢���Ȥ��ܤι⤵�ʿ���Ū��٥�ˤ��Ѥ��Ƥߤ�ȡ����줬Ŭ�Ѥ��줦������̡פ������ڤˤ����Ƥ��⤫�Ӿ夬�äƤ���Ȥ�����̣�������¤ˤ�פ���ä���
���Ĥ�Τ褦�ˡ�����Ρ�¹�����פ���������Ŭ����ʸ�Ϥ���롣�ʺǶᡢ�������������ʡ��ܥ�...��
�ޤ��ǽ�����ϡ��ֲ��������ˤĤ��Ƥ��áפȤ����ɤ���ˡ��ɬ�סˤ����롣���Ȥ��в��ʤɤϡ��ưפ�����Ǥ���Ŭ�������
<<
�º����ꡢ��ü���������İ�Ԥ������Υ��С����ä��ꤹ��ȡ�¾�Υ�����İ���Ƥ��Ƥ⼫ʬ������ô�����Ƥ���ڴ�Υ����Ȥ������뤤��������������Ū��İ���Ƥ����ꤷ�ơ����ΤȤ��ơʺ�ʲȤΰտޤ��Ƥ����̣�ǤΡ˲��ڤ�İ���Ƥ���Ȥ����������θ��Ȥϰ�ä���ΤˤʤäƤ��ޤ��ʤ�����վޤ�ã�ͤˤʤäƤ���ȡ������������ʤʤ�ʹ�����ˤ���������ּ��פ�ȴ���Ф��ơ�������ɡ��������������������ѡ��Ȥ�ڤ���ʤ�Ƥ������ݺ������ɲ��ڤγڤ������⤢��������...�ˡ�����ʡ���ü�����ʤ��Ƥ⡢�Ƴ��褯���뤳�Ȥʤ�ǤϤʤ������������Ĥޤꡢ�ȡֲ��ڡפ�İ���Ƥ���Ȥ����ռ��������ʤ��ɤȤ����Τϡ����äƤߤ�Сֲ��ڴվް����פξ��֤Ȥ������Ǥ��롣
<<
�դ�դࡣ�ޡ��Ǹ�����������������äǤϡ����롣���ڤ����ΤȤ��ơְ�Ĥι�¤�פȤ���İ����롢�Ȥ������Ȥ����ޤ��ˡֲ��ڤ�İ�������٤Ǥ����θ����������������������������������Ω����Τϡ������ޤǤ���
���������ֲ��ڡפ���Ω�Τ����ˡ������������ֲ��ڡפϾä����ΤǤ��� <<
�����ˡֲ��ڤϾä���פΤ��ȸ����ȡ����ڤ��Τ�Τ��������äƤ���¤ꡢ���뤤�ϲ��ڤ��Τ�Τ����������˴ؿ���������Ƥ���¤ꡢ������ñ�˲��ڤ��־ä��ơפ��ޤ����ȤϤʤ������ڤϤ����Ƥ��ξ�硢�ä����β��ڤξ�硢�̾��ʲȤ���ղȤϡ����̤˽������Ĥ餵���٤��������Τ�Τ�İ���Ƥ���פ����äƤ��뤫��Ǥ��롣�ʾ��ʤ��Ȥ⡢���Τ褦�˻פ��Ƥ���褦�˸�����ʡ��糵�����β��ڤϡ���
�������äơ�����������٥�Ǥϡ���ȿ������ĤΤ�Τ�Ʊ���ֲ��ڡפ�̾�ǸƤ֤��Ȥ���������ֲ������κ���פȤ����Τϡ����ޤ�����ˤʤ�ʤ������������㳰Ū��¨�����ڤˤ����Ƥϡ������������Ȥ��礤�ˡʴվޤˤȤäơ˲���Ȥʤ�θ�ҡϡ������ơ������ü��İ�Ԥο������֤ˤ����Ƥϡ��ۤȤ�ɲ���Ū�θ��ȸƤ֤���������餶��ֲ����θ��פȤ�����Τ�����Τ�Τ�����
�Ĥޤꡢ����ڤ�ޤ����äȹ����Ķ��������Ȥ����Ȥ����ޤdz��礹��ȡ������Ȥ�������Τ����ĤޤꡢŬ�ѤǤ��ʤ��ä��Ǹ����ʬ����Ŭ�Ѳ�ǽ�Ǥ��ꡢ���줳���������ڤ�վޤ����θ�����Ǥ⡢�Ǥ�������ʬ�Ȥ������Ȥˤʤ롣
<<
���Ȥ��С����ڲ�Dz��ڤ��椷��İ���Ƥ��ơ����뤤���Ť��ʴĶ��Ǥ�ä��꤯�Ĥ����ǥ쥳���ɤ�İ���Ƥ��ơ��ֲ��ڤ��ä���פȤ����θ����۵�����Τ����ʥ����ǥ����ޥ˥��������������ɤ����ϡ������ǥ������֤��ä���פȤ��������������������Ȥˡ������ǤϿ����ꤷ�ʤ����ˤ��ʤ�������ڤˤ���줬��������Ƭ�����Ȥ��ˡ��桹�������˲��ڡʲ��ˤ�İ��³���Ƥ���Τ����Ȥ�������Ǥ��롣�����餷�������θ��Ȥϡ�������ä�����Ū�ʿ���Ū�ˤʤ�Τǡ�����ϡֲ��ڼ��Τ���δ�ư�פȤ���ʪ�Ǥ��뤳�Ȥ�����ʤ��뤫�ʤ����ߤ�ʡ��ˡ����ڤ����ä����Ȥʤäơ��桹���̤ξ��˾������ã���Ƥ��ޤ�����Ǥ��롣���������θ�������ֲ��ڤ��θ��פ�Ʊ�����դǸƤ�Ǥ��ޤ��ȡ��Τ��˺��𤬤��롣
���ڲȤ����Ф����ʡʲ��ˤޤǤϲ��ڲȤ���Ǥ������������̤������Ƥ��ޤ���İ��¦��ǽưŪ�ʤϤ��餭�פˤ���θ��ϡ�ɬ�����ⲻ���θ����Τ�ΤȤϸ¤�ʤ�������������������Ȥ�İ��¦�������ǵ���������ڴ�ҤȤĤҤȤĤβ��������ǥ����ϡ��ִ��ΤΤ�ΡפǤ���ʤ��顢�θ��Ȥ��Ƥϡ�̤�Τ��ΰ�פ����äƤ���ִ֤��������ơ����˸����ȡ��վԤ�������Ū����˿�����Ū�θ�������Ȥ���С���������ˤ�����äƤ����Τ���
��������ϡ��դ���������θ��դؤΡ������פȤʤ롣
<<
���뤤�ϡ��̥ƥ�����
<<
�ä�æ�����뤬��
�����ʸ�ϡ�
<<
����ʬ�ϡ�������ִĶ����ڡס֥���ӥ���ȷϲ��ڡפʤɤ˴ط�������ĥ��ŵ���Ȥ����ɤळ�Ȥ����롣�Ĥޤꡢ������ɥ������פ�ȥ������������ɤ�Ω�������
�֥�����ɥ������ספϡ��ʲ���ˡ˥ǥ�����֤Ǥ��ʤ��פ�Τ��֤���פȤ������Ȥ�����ˤ��롣���ڤ��ΰ�ˤ����ơ֡ȥ��ɥ������ס�Ū���ץ������פ�Ȥ�ʤ顢������ޤ��Ϥ����ˡ��Ķ��������ʤ�����饹���Ĥ����������������Ʀ�岰��ū�β�����ǯʪ���Ȳ��γ��������Ҷ��ε㤭������ž�֤Υ֥졼���β����ʤɤʤɤΡ֥ǥ�����Ǥ��ʤ���Ρפ�¸�ߤ�ǧ���Ȥ�������Ϥ�롣�����ơ������֥ǥ�����Ǥ����Ρפ��֤��������ꡢʤ�ä��ꤹ��ΤǤϤʤ������������֥ǥ�����Ǥ��ʤ���Ρס֥���ȥ�������ǽ�ʤ�Ρפ����뤳�Ȥ������ࡣ
�Ȥ����櫓�����ʤ��ʤ�������Ū�����פȤʤ뤾������ϡ�
���ơ���¨���פˤĤ��ơ��̾ﲻ�ڤȶ��̤��Ƹ�äƤ������𤫤�����ȡ��Ǹ�ˤ������ڤ��ʤ��ǺѤޤ������ˤϹԤ��ޤ����������餬����ä����֤���
¨�����ڤ����ʤ�������ˤĤ��ơ㤳�Ȥ�����ȯ���������ʤ���ͳ�ΤҤȤĤȤ��ơ������˶��̤ʥꥢ�륿�����������ݥ�ƥ��˥����������롣�Ĥޤꡢ¨�����ڲȤ����ϡ�����¨���ˤ����Ƥ��äˡ����줾�줬�������ټ�ʬ�ˤȤäƴ��ΤΡֻ������ס�����γڴ��ƥ��˥å��ˤ���äƥ��ơ������о줹�롣�������ҤȤ��Ӳ����Ф����䡢��ʬ�Ȥ�������Ф����ΰʳ��Ρ�̤�Τ����ǡס�ͽ���Բ�ǽ�����ǡפȤ����Τˡ�ɬ��Ū���������롣�����ơ��ܿͤα��դ��Ϥ�ƽ���ʬ�������Ĵ��ǧ���פ��������롣�����ơ�����ؤΥꥢ�륿����Ρ��б��פ������롣�礭��ʬ����С�����������̤�Τʤ����ǡפ��Ф��ơ�������̵�뤷�ƿʤ�פȤ����Τȡ����������Ѥ��ƿʤ�פȤ������٤Ρ����������פ�������ִ֤˽и���������ؤ�Ƚ�Ǥ�˻�����Ԥʤ�ʤ���Фʤ�ʤ�����������ʪ�����顢�ԤäƤ���ʤ��ΤǤ��롣�ޤ�ǡ����ʤΤ褦���������⡢�ɤΤ褦��̵�뤹��Τ������Τ褦�����Ѥ���Τ����Ȥ����ۤȤ��̵�¤��������椫�顢��äȤ⥫�å�������ˡ��ʤۤȤ����ǽŪ�ˡ��ֻ��ˡ����ʤ���Фʤ�ʤ���
̵�뤹�뤳�Ȥˤ�ä���������ĤΡʻ��ĤΡ�����ʾ�Ρ������Ρ�Ʊ��Ū�ʸ��������ޤ�Ǽ̿�����šʻ��š�¿�š�Ϫ�ФΤ褦�ʸ��̤�ʤ����������ȤƤĤ�ʤ���ħŪ�ʲ�����ۤ��Ƥ��ޤ����Ȥ⤢��С�ñ�ʤ�䤫�ޤ����������Ĥ��뤳�Ȥ⤢�롣��������̤�Τʤ����ǡפ��Ф��ơ��ߤ������Ѥ��ƿʤ�Ȥ������ȤǤ���ȯ�����ʤ����ꥢ�륿����˾�������붨��Ū��Ĵ��Ū�ִ֤�----�ޤ�ǡֿ����פΤ褦��----����Ū�ˡְ�̣�����Ρפ������뤳�Ȥ����롣
������ˤ��Ƥ⡢�����ʤΥǥ�����פ�Ʊ���褦�ˡ�¾�Ԥ�¸�ߤ�����Ȥ��������Բ�ǽ�����������뤳�Ȥˤ�äƤ�����Ω���Ԥ��ʤ����Ϻ�פκߤ�������¨�����ڤˤϤ���Τ���
¨�����ڤˤ����Ƥϡ��֤�������ޤ��Ķ��Τ�����֡�������ؤ��Ƥ����ΤǤ��äơ����ξ����Τ�Ȥˤ����ƥǥ�����Ȥ����٤�ɽ�ݤ����Τȡ�ɽ�ݤ��ظ������оݤδ֤ˡ��䤨�֤ʤ���ĥ�δط����ۤ���롣
���...
<<
�ȡ����ߤ�������äƤ���褦�ˡ����ڤˤ����Ƥ��¨�����ڤǤ���ФȤ�櫓�ˡ����ռԤϡ������˰�̣�Τ���Ĥʤ���Ф��ѻ��ԡʲ��ڴվԡˤˤ��ֲ��ڤ����ʲ����ɥ���פΡַ����פ��������ߤƤ��롣�Ĥޤꡢ¨�����ڲȤ����֥ǥ�����פ�����Τϼ¤ϡֲ��ڡפ��켫�ΤǤϤʤ����ΤǤ��롣
�վԤ������椫��ꥢ��ʡַ�ס����뤤�ϡ�ʪ��פȸƤ֤����������ΤФ��ַ����פ�¨�����ڲȤϡ����뤤�ϲ��ڲȤϡ���ߤ�ΤǤ��롣�����ˤϡ�ͽ��Ĵ��Ū�����ıߤϤʤ������⤷��ʤ����������ޤ�ʥ���ǡ������������̤˥ץ�줿�Ȥ����פ��ʤ��褦�ʡ�ϲ̡��Ū�ʡִ����ʪ��פ�ꥢ�륿��������߽Ф���ǽ�������Ƥ���ΤǤ��롣
�����ˤ�����¨�����ڤ����̣�������entee�ϡ��ͤ���ΤǤ��롣
�������ơ���������Υ��Ĥ�Ƴ���ˤ�äơ���ǯ�����إ��ɥ���������ɾ����١�INAX���ǡ��˴�����ʸ��¨�����ȷײ����˸������ʤȲ��ڤΥ��ʥ�����������¨�����ڲȤ�̴��Ū�����ʡ����ˤϡ��Ƥ������ܤ�ΤǤ��ä����ʤȡ����������Ȳ�������ɤ��ơ������ΤǤ��ä�������
[Read More!]
20:51:05 -
entee -
TrackBacks
2005-07-11
�Ť��Ǥ��뤳�ȤΡֶ����ϡפȡֲ��ؤΰ���
���뤤�ϡ�¨�����աפȤ���̾�����ΰ�ؤ���
�����Υ��å����Ǥϵ����ꤦ��ʵ����꤬�����ˤ��Ȥ��������Ф�����Υ��С������Τ��椫����ͽСפ��뤳�Ȥ�����ʤ��褦�ʡ��Ť����פ��ä�����¨���Ȥ�����Τ����롣���뤤��©���Ǥ��ʤ��褦�ʶ�ĥ����ȼ���ż�Ȥ�����Τ����롣�����������Τ���ϡ������̣�ǡָ�������ȼ�ä����פΤ褦�ʤ�ΤǤ��ä������뤤�ϰ������פȤ��Ƥ��븷�����ȤǤ⤤����ΤǤ��������������������Ρָ������פϡ������˽�ʬ��©�Ѥ������ΤǤ��ä������������٤��̤��ƶ���Ԥ˰��ۤ�������줿��ΤǤ��ä��������������ʡְ��פϡ��¤��Ф��줿��İ�Ĥβ����Τ����α��ؤȸ������������Ƥ��β���ʹ��ƨ�����������߰����뤳�Ȥ����ռ���ߤ�º�Ťȷɰ��ؤȤĤʤ��äƹԤ��Τ���
���줬���������˹Ԥä�Carl Bergstroem-Nielsen�ʥ����롦�٥����ȥ���ˡ��륻��˻�ȤΡ֥���ե����ޥ��¨�����å����פǤ��ä���
���üԡ�
�����롦�٥����ȥ���ˡ��륻�� French horn, ���ץϡ���˥���prepared harmonica, voice, etc.
�Ӿ彨�� bass, voice����ꥷ���䥹��� cello�������Ƽ�ʬ voice, oboe, English horn, piano
��ꡧ�������åɥޥ�
�פ��С���Ϥ��⤽�⤤����������ϡפ�¨���ˤϱ郎�ʤ������ޤ�ؤ�äƤ��ʤ��ä���������Ǥ⺣�ޤǤϿ���Ū�ˤ����Ū�ָ������ʷ㤷���ˡפ��Ȥ��濴�ˤ�ä��褿��Τ��Ȼפ��֤��줿�������뤵���¨����������ϡ����������֥��ꥮ���ʥ�פDZ��褦��¨���Ǥʤ���¨���פȤ�����¦�̤��������ˤ���Τ����Ȥ������Ȥ�ʹͤ��Ƥߤ�����������ʤΤ����˲�����Τ餷��Ƥ�����ΤǤ��ä��褦�˻פ���ΤǤ��롣
�����뤵��Ȥ�¨�����å����ϡ������������Ť��פǤϤ���ʤ��������դ��褦�ʶ�ĥ�פȤ����Τ���⡢�ۤɱ�Τ����Ť��Ǥ��ꡢ������ͥ������³�ϤʤΤǤ��롣�����ơ�Ĺ���û�������γƥ��åȡ���ˤȤäƤϡ����ڤȤ�����ΤΤ���������ΤҤȤĤޤ餺�����ˡ�Ϥ�¨���ԡפ��鶵��ä��Ȥ��������������Τ��ä��Τ����Ҥ��ܤʤ�ʣ���γڴ��դ�դ���Ϥ��⤤�ƹԤ���α��դΥ�������⡢��Ĥγڴ�Ǥ��뤳�ȤΡָ³��פ��ɵ椷��ʬ���ɤ����ࡢ�Ȥ����褦�ʥ��ȥ��å��ǵ�ƻ��Ū�ʤ�ΤǤϤʤ��������ޤǤ�̵���ʤ����Ҥ����鼫�ߤˡ��֤���֤˰ܤ��ϤäƹԤ�ij�Τ褦�˱��դ��ƹԤ��Τ���
��ʬ�Τ��뤳�Ȥ伫ʬ�ο��Τ��᤹��¨���Υ�������Ȥ�����Τϡ�������ñ�˸��˻��ˤʤ��ΤǤϤʤ��������λ��ʤ���¨���ˤ⤤����������ˡ�����롣���ռԤϡ���ʤ꾮�ʤ��ɼ�ʬ�˰��֤��ä���������Ȥ�����Τ˰��夹��������������뤤�ϼ�ʬ�ˤ��ä������οʹ�Ʊ�Τ����롼�פȤ��ƽ��ޤ�ΤǤ��롣����������ʬ�ϡ������������äƤ��������뤵��ȤΥ��å������̤��ơ���ʬ���礿��ơ��ޤȤ����ɵᤷ�Ƥ��ʤ��ä�¨���Υե�����ɤȤ����Τ����鷺���˳������Ƥ����⤫�鸫����Ҥ����ı����ʤΤ褦�˸��������������Τ���
��ȤΥ��å��������鼫��˾��Ԥ����磻�����ߤʤ���ο�����Ȥʤä��������κݤ⡢�����뤵��⼫ʬ�ˤȤä�̤�Τʤ��Τؤν��ʹ��Υ���ƥʤ����ä�ư��³���Ƥ���Τ�ʬ���ä����䤿���Ϥ����餯����Τ�ʤ���Τ�����ʹ�������ˤΤ�������ϻ䤿�����Τ�ʤ���Τ���˸������Τ�������ϡ��֤��β���İ�����פ����ä�����ʪ�̡פ�ֲ����פ��̤��ƤǤϤʤ��ơ���ˡ֤��Τ��٤���������դä��ߤ����פȹ�������֤���벻�Ρ�ȩ�礤�פ�������Ť��ȤäƤ�餪���ȤǤ⤷�Ƥ���褦�ˡ����ʤ��Ȥ����ɵᤷ���褿�������Ȥ����餫�˰ۼ��ʤ�Τ��������ּ�ʬ�η����פȰۤʤ��Ρ��Ȥ����ऱ����ϴ�ñ�ʤΤ������������ʤ��Ԥˤ����⤿�餵��륮�եȤȤ�����Τ������ˤϤ��롣
�ֲ�����ˡ: music therapy�פˤ����뤢���Ρ֥��å����פȤ����Τϡ���ǯ���ˡֲ�����ˡ�פ������˰��Ū�����ͤù���Ǥ�������ᤷ��ͧ�ͤ��顢���γ��פ���줿��ʹ�����줿�ꤷ���������ä��Τǡ��ʤ�Ȥʤ��ΤäƤ���褦�ʵ������Ƥ������������뤵����̤��ơ������θ�ǽ�Τ褦�ʤ�Τ�ʬ���٤�Ф�����ʬŪ���δ������ΤǤϤʤ������Ȼפ�줿��
�ǥ�ޡ�������ؤDz�����ˡ�Τ��Ƥ륯�饹����������ܿͤ����ˡ�פ�ɬ�פȤ��Ƥ���֥��饤����ȡ����˲�����ˡ��������Ƥ��륫���뤵���Ω�줫��䤷�̤�С����å���������꤬�ֲ��ڲȡסʲ�������ȡ�¨�����ռԡˤǤ��뤫�ɤ����Ȥ����Τ��ɤ��Ⱝ�����ö���ˤ��������Ѥʤ����ܤ��褦�Ȥ��Ƥ���褦�Ǥ��ꡢ�������äư�Χ�˥��饤����Ȥ���Ȥ��ơֿǤ��ơפ����̤⤢��Τ��ʡ��ʤɤȼٿ䤷�Ƥ��ޤ��ִ֤⤢�ä����������ǡ���ľ����䤢���Ρֵ�Ϥΰ����פ����Τ������դˡ��䤬�֤ɤΤ褦�˥ۥ����˻�ä��Τ��פ�Ҥͤ����ˡ��פ���ˡ��ץ��Υۥ���ռԤȤ��ƤΥ���ꥢ������Τ���䤬�פ鷺ʹ���Ф����Ȥ��Ƥ��ޤä����ˡ��ब���������⤷��ʤ���Ϥΰ������������Ƥ���ΤǤ��롣���Τʤ顢�������ˡ�ȤȤ��ƤϽФʤ�����������μ��䡢�Ĥޤ�ֲ��ڲȡפ�Ω�����ʹ֤��餳���Ф�����ŵ��Ū�ʼ��������ä��������������
�����������������ߤ��θߤ���䤷�̤��Ϥΰ����ϡ����å�����Ͽ����İ���֤����괿�̤��̤��ƤۤȤ�ɱ���������¨��������Ū�˼������Ƥ���Ȥ�������Τ����ʤ����ˤˤϡ����������ֵ��Ԥȼ��ּԤδ֤ˤ��꤬���ʴط�����ǤνвϤ�������Ǥ��ä����⤷��ʤ���������ϻ��֤��ưפ˲�褹����Ǥ������Ȼפ���
���ٺƲ���ˤɤΤ褦��Ÿ���ˤʤ뤫��������ڤ��ߤǤ��롣
�ޤ�������η�Ǥϥ����뤵���Ҳ𤷤Ƥ��줿������ɧ���������礤�ʤ뿴�դ��ȵ�������ȯ�����Ʋ����ä��Ӿ彨�פ���ˤϡ��紶�դǤ��롣
[Read More!]
���줬���������˹Ԥä�Carl Bergstroem-Nielsen�ʥ����롦�٥����ȥ���ˡ��륻��˻�ȤΡ֥���ե����ޥ��¨�����å����פǤ��ä���
���üԡ�
�����롦�٥����ȥ���ˡ��륻�� French horn, ���ץϡ���˥���prepared harmonica, voice, etc.
�Ӿ彨�� bass, voice����ꥷ���䥹��� cello�������Ƽ�ʬ voice, oboe, English horn, piano
��ꡧ�������åɥޥ�
�פ��С���Ϥ��⤽�⤤����������ϡפ�¨���ˤϱ郎�ʤ������ޤ�ؤ�äƤ��ʤ��ä���������Ǥ⺣�ޤǤϿ���Ū�ˤ����Ū�ָ������ʷ㤷���ˡפ��Ȥ��濴�ˤ�ä��褿��Τ��Ȼפ��֤��줿�������뤵���¨����������ϡ����������֥��ꥮ���ʥ�פDZ��褦��¨���Ǥʤ���¨���פȤ�����¦�̤��������ˤ���Τ����Ȥ������Ȥ�ʹͤ��Ƥߤ�����������ʤΤ����˲�����Τ餷��Ƥ�����ΤǤ��ä��褦�˻פ���ΤǤ��롣
�����뤵��Ȥ�¨�����å����ϡ������������Ť��פǤϤ���ʤ��������դ��褦�ʶ�ĥ�פȤ����Τ���⡢�ۤɱ�Τ����Ť��Ǥ��ꡢ������ͥ������³�ϤʤΤǤ��롣�����ơ�Ĺ���û�������γƥ��åȡ���ˤȤäƤϡ����ڤȤ�����ΤΤ���������ΤҤȤĤޤ餺�����ˡ�Ϥ�¨���ԡפ��鶵��ä��Ȥ��������������Τ��ä��Τ����Ҥ��ܤʤ�ʣ���γڴ��դ�դ���Ϥ��⤤�ƹԤ���α��դΥ�������⡢��Ĥγڴ�Ǥ��뤳�ȤΡָ³��פ��ɵ椷��ʬ���ɤ����ࡢ�Ȥ����褦�ʥ��ȥ��å��ǵ�ƻ��Ū�ʤ�ΤǤϤʤ��������ޤǤ�̵���ʤ����Ҥ����鼫�ߤˡ��֤���֤˰ܤ��ϤäƹԤ�ij�Τ褦�˱��դ��ƹԤ��Τ���
��ʬ�Τ��뤳�Ȥ伫ʬ�ο��Τ��᤹��¨���Υ�������Ȥ�����Τϡ�������ñ�˸��˻��ˤʤ��ΤǤϤʤ��������λ��ʤ���¨���ˤ⤤����������ˡ�����롣���ռԤϡ���ʤ꾮�ʤ��ɼ�ʬ�˰��֤��ä���������Ȥ�����Τ˰��夹��������������뤤�ϼ�ʬ�ˤ��ä������οʹ�Ʊ�Τ����롼�פȤ��ƽ��ޤ�ΤǤ��롣����������ʬ�ϡ������������äƤ��������뤵��ȤΥ��å������̤��ơ���ʬ���礿��ơ��ޤȤ����ɵᤷ�Ƥ��ʤ��ä�¨���Υե�����ɤȤ����Τ����鷺���˳������Ƥ����⤫�鸫����Ҥ����ı����ʤΤ褦�˸��������������Τ���
��ȤΥ��å��������鼫��˾��Ԥ����磻�����ߤʤ���ο�����Ȥʤä��������κݤ⡢�����뤵��⼫ʬ�ˤȤä�̤�Τʤ��Τؤν��ʹ��Υ���ƥʤ����ä�ư��³���Ƥ���Τ�ʬ���ä����䤿���Ϥ����餯����Τ�ʤ���Τ�����ʹ�������ˤΤ�������ϻ䤿�����Τ�ʤ���Τ���˸������Τ�������ϡ��֤��β���İ�����פ����ä�����ʪ�̡פ�ֲ����פ��̤��ƤǤϤʤ��ơ���ˡ֤��Τ��٤���������դä��ߤ����פȹ�������֤���벻�Ρ�ȩ�礤�פ�������Ť��ȤäƤ�餪���ȤǤ⤷�Ƥ���褦�ˡ����ʤ��Ȥ����ɵᤷ���褿�������Ȥ����餫�˰ۼ��ʤ�Τ��������ּ�ʬ�η����פȰۤʤ��Ρ��Ȥ����ऱ����ϴ�ñ�ʤΤ������������ʤ��Ԥˤ����⤿�餵��륮�եȤȤ�����Τ������ˤϤ��롣
�ֲ�����ˡ: music therapy�פˤ����뤢���Ρ֥��å����פȤ����Τϡ���ǯ���ˡֲ�����ˡ�פ������˰��Ū�����ͤù���Ǥ�������ᤷ��ͧ�ͤ��顢���γ��פ���줿��ʹ�����줿�ꤷ���������ä��Τǡ��ʤ�Ȥʤ��ΤäƤ���褦�ʵ������Ƥ������������뤵����̤��ơ������θ�ǽ�Τ褦�ʤ�Τ�ʬ���٤�Ф�����ʬŪ���δ������ΤǤϤʤ������Ȼפ�줿��
�ǥ�ޡ�������ؤDz�����ˡ�Τ��Ƥ륯�饹����������ܿͤ����ˡ�פ�ɬ�פȤ��Ƥ���֥��饤����ȡ����˲�����ˡ��������Ƥ��륫���뤵���Ω�줫��䤷�̤�С����å���������꤬�ֲ��ڲȡסʲ�������ȡ�¨�����ռԡˤǤ��뤫�ɤ����Ȥ����Τ��ɤ��Ⱝ�����ö���ˤ��������Ѥʤ����ܤ��褦�Ȥ��Ƥ���褦�Ǥ��ꡢ�������äư�Χ�˥��饤����Ȥ���Ȥ��ơֿǤ��ơפ����̤⤢��Τ��ʡ��ʤɤȼٿ䤷�Ƥ��ޤ��ִ֤⤢�ä����������ǡ���ľ����䤢���Ρֵ�Ϥΰ����פ����Τ������դˡ��䤬�֤ɤΤ褦�˥ۥ����˻�ä��Τ��פ�Ҥͤ����ˡ��פ���ˡ��ץ��Υۥ���ռԤȤ��ƤΥ���ꥢ������Τ���䤬�פ鷺ʹ���Ф����Ȥ��Ƥ��ޤä����ˡ��ब���������⤷��ʤ���Ϥΰ������������Ƥ���ΤǤ��롣���Τʤ顢�������ˡ�ȤȤ��ƤϽФʤ�����������μ��䡢�Ĥޤ�ֲ��ڲȡפ�Ω�����ʹ֤��餳���Ф�����ŵ��Ū�ʼ��������ä��������������
�����������������ߤ��θߤ���䤷�̤��Ϥΰ����ϡ����å�����Ͽ����İ���֤����괿�̤��̤��ƤۤȤ�ɱ���������¨��������Ū�˼������Ƥ���Ȥ�������Τ����ʤ����ˤˤϡ����������ֵ��Ԥȼ��ּԤδ֤ˤ��꤬���ʴط�����ǤνвϤ�������Ǥ��ä����⤷��ʤ���������ϻ��֤��ưפ˲�褹����Ǥ������Ȼפ���
���ٺƲ���ˤɤΤ褦��Ÿ���ˤʤ뤫��������ڤ��ߤǤ��롣
�ޤ�������η�Ǥϥ����뤵���Ҳ𤷤Ƥ��줿������ɧ���������礤�ʤ뿴�դ��ȵ�������ȯ�����Ʋ����ä��Ӿ彨�פ���ˤϡ��紶�դǤ��롣
[Read More!]
23:15:25 -
entee -
TrackBacks
2005-06-17
�����ܤη���ٵ���͵���ʴ��ȿ���ˤ��ɤ�
����Ρ����פ�¦�̤��Τ�Ȥ������Ȥˤϰ�̣�����롣�����¦�̤ʤɺ�����Ĵ����ޤǤ�ʤ��Ȥ��������...�ˤ������ֿ������������������פ�������������˼����ɤ���ߤ�����
�����������ȤǤ����Ĥޤꡢ������Ϥߤ�ʤ��ͤ���ۤɰ�����ΤǤϤʤ�����פȤ�����ĥ��ͤ��ˡ��ɤ����������丽��ǧ�����ֻٻ��פ�Ϳ���Ƥ���Τ�������Τɤ�����¦�̤�����������Ԥˡ�ͦ�����ϡפ�Ϳ���Ƥ��ޤ��Τ����Ȥ������Ȥ뤳�ȤˤĤʤ��뤫�顢�������̣������ΤǤ���
��������¦�̤ˤĤ��Ƥϡ������٤���̵������˲��Ⱥ��𡢤����ƿ�̿��ʹ֤�º����å�����˽�Ϥ��ȿ�Ū�ʤȤ�����������̵����Ǻ��𤷤������ˤ��ˤʹԻȤǤ��뤫�顢�Ĥޤ껦�ͤȤ�������֤��ΤĤ��ʤ�����ܼ���ǡ���ʤ���ͳ�ˤ����Ƥ��������Ǥ��ʤ����Ȥ�����ͳ�ʾ�Τ��Ȥ餿��Ƹ��ɬ�פ����ʤ�������ۤɺ��ͤˡ����Ǥ˼����Τ��ȤǤ���ʤ�����ɤ������ä��äƤ���ǡ֤������פȤ�����ΤǤ�ʤ��ۤɤˡ����Ѥ��ͤФʤ�ʤ����Ȥ�̵���ˤ���Τϸ����ޤǤ�ʤ��ˡ�
�������äơ������ˤ�������������������β��ͤ���Ȥ�������¸�ߤ��������������줿�Τ����Τ뤳�Ȥˤϲ��ͤ����롣�㤨�С��Ľջ����������������Ӥ�פ��ȤDzᤴ���Ƥ��������褷���Τ�ʤ��ʤ��ĤƤΡˤ��ɤ����ǯ�ˤ����פ�������ǡ���ˤ���̵��������Τ����Ȥ�����Ƚ���������뤳�ȤˤĤʤ���ΤǤ��롣�����ơ�������������������ԡʰ����������Ԥ�ޤ�ˤθ���ʬ��ñ��˿�����ʤ��뤤�Ϥ��Ρָ���ʬ�פ��Ф���Ʊ��Ū�ʡ˿͡���¸�ߡ����뤤��������Ỵ����ʬ������Ȥ��������Ǥ��ʤ������ʤΤǤϤʤ����Ȼפ���褦�ʡ�����Ū�������������ָ������פ���㤤����ο͡�����������¸�ߤ��������ĤĤ���Ȥ������Ȥ�ͤ���ˤĤ������ֹ������ԡפ�����������������Τɤ��˷���Ū�ʷ꤬����Τ����Ȥ������Ȥ��Τ�Ԥ���ɬ�פ�����Τ������������͡���Х��ƤФ�ꤷ�Ƥ⡢�ͳ����ꤷ�Ƥ⡢����Ϲ������ԡ��������ԤΤɤ���Υ���ˤ�ʤ�ʤ��Τ���
����Ȥ�����ΤΡ�¿�����ɤ����Ťʸ������Ƥ�����ܤη���١ʴ��ȿ���ˤˤ��С���������äƽ������ʣ��٤ο����ˤ���Ĥ����Ȥ�����ǯ��������������Ȥ��������켫�Τ���ˤȤäƤϾ�Ǥ��ä��������ܤ����ڡפε��ҤǤ��ä����������롢������������������¼�Ρ��Ϻ��ءפ�°����͡����餹��С�����Ǥ�����Ϥ���ޤǤǤϹͤ����ʤ��ۤɤ������Ǥ��겸���Ǥ��ꡢ������ϫ��Ⳬ�����줿�������ΰ³������Ǥ��ä��Ȥ��������Τʼ´�����ĸ�ʼ��ã�����롣���뤤�ϡ��Ҳ�Ȥϴط��ʤ�������Ȥ����ȿ��ϡ���ʬŪ���Ȥ��Ƥ�ˡ�ǽ�ϼ���פ��¸����Ƥ��������Ρָ�ʿ�ʤ�Ҳ�פǤ��äơ�����ε����塢�����������Τʾ�̲����Ρּ罾�ط��פϤ��ä���ΤΡ����ٰ�ʼ´�Ȥ������ꤷ�������Ǥϡ����������������ʤ����������²����¼�Ф⡢���٤ƤμԤ�Ʊ���Ӥ���Ʊ����������֤��������������Ϸ���γ��������Ǥϡ������ޤ��ּ¸����Ƥ��ʤ��ä����ȡפ��Ȥ����ΤǤ��롣
�����ơ�����������������Ԥ����̤�����ֵ���ʤ���Фʤ�ʤ��Τϡ���������ͳ��ʤƷ������ꤻ��������ʤ��ͤ����롢�Ȥ������¤Ǥ��롣
����Ф���ǤϤʤ������ޤ��ޤ���ͳ��ʤơ��ʤ�ۤɷ��⤬�֤褤���פ��ȴ����뤳�ȤˤϤ����Ĥ�Ρֺ���פ����ä�������
������ˡ�������������Τ�İ�Ϣ�Ρ�Ĺ��פ�ʤƷ����ʼ��ˤȤ�����Τ˲ݤ����Ƥ��뵡ǽ�����Ԥ���Ƥ�����䡢�����Ʋ������˲���˽�Ϥ��ǽ�ˤ���ƻ��Ǥ�ä��������Ƥ����ȿ��Ǥ���Ȥ������ȡ������ơ��ɱҤΤ����ƻ��Ǥ���פȼ�ĥ���ưݻ�����뷳�����Τ�Τ������Ū�ˤϡ�¾�ԡ�¾��ˤ��鸫��ж��Ҥ����оݤ��Τ�Τ�¾�ʤ�ʤ��Ȥ������������ơ����ɱҡפȱ���̾�Τ�Ȥ˿�ά*�����¸���ǽ�ˤ���Ȥ��������ǽ�Ū�ˤ�̿����ФǤ���Ȥ����ȥåץ������̿����֡������������ȸ�����Τΰ��ڤ�˽��Ū�ܼ����ܤ�������Ƥ��ޤ���褦�ʡֲ��͡פʤΤǤ���������
* ���Ĥ��ɱҤȤ�������ʤ��˹Ԥ�줿����Ȥ�����Τ����ä��������������٤Ƥ�����Ϥ����Ϥ��ͤ����ˤ�äơ��ɱҼ��ʡפǤ���ȼ�ĥ����Ƥ���ΤǤ��롣����ϸ��ߥ���ꥫ�罣�����ܤˤ�ä�������Ƥ�����������Ǥ��餽���Ǥ��롣���ܿͤ�ī��Ⱦ������������Τⷳ���Ÿ���������Τ⡢�֥�����������ζ��Ҥ��Ф��������ɱҤΤ���פȤ������������롣���ʤ�������ɱҡפʤɤȤ����������ϡ�ï�ˤ�äƤ��ǽ�Ǥ���Ȥ�����ͳ�ǡ����Ǥ�̵���Ǥ��ꡢ����ˤޤȤ�˼����ߤ�ɬ�פ��ʤ��ۤɤǤ��롣�ֹ��⤷�Ƥ��뤫�⤷��ʤ��פȰ����Ƕ��Ҥ����Ф�Ƥ���˿��˴ؤ��ơ�����¦���餹������Ƥ���Ƥη���������طʤ˳����Ÿ���������ܤ�ڹ���Ф��붼�Ҥ��Ƥ������ǡ����Ĺ��ɱҤΤ������������פȤ������¤���äƤ������Ǥ��롣���κݤɤ���ˡ������פ����ä��Τ����ȸ������Ȥ��䤦�ޤ����������μ¤ʤΤ�ī�����褬���������������������ȤΥХå����åפ�������������Ψ������ī��̱������̱���¹��¦�ˤ⡢����������Ф����ɱҤ�����˶���Ǥ����罣��˥Хå����åפ��줿���̱���¦�ˤ⡢�������������ؤδ��Сפ����ä��櫓�Ǥ��롣�ߤ������ɱҡפ������夲�Ʒ��ή����ä����Ǥ��롣
�����Ĺ��ˤ�äơ������������������ˤȤ�����Τϰ�����ΤǤϤʤ��פȤ�������Ѥϡ��������ᡢ��ɬ�װ��פ��ĥ����������̾��¾�ʤ�ʤ���������ɬ�װ�����ˤ���Ԥϡ��ְ��פ��ɬ�ספˤ�ä����դǤ���ȹͤ��Ƥ��롣�����Ф��뺬��Ū��̵�����뤤���Ỵ�ؤ������Ϥȴ������η�ǡ�����롣����Ф��꤫���Ū�ˤϺ���Ū�ʺ��̼����ȯϪ��¾�ʤ�ʤ��ΤǤ��롣
�Ĥޤꡢɬ�װ��Ǥ�äơ�ɬ�ספ����������͡�����������ǡ��ְ��פε����ˤʤäƻ�ʤʤ���Фʤ�ʤ��ͤ��Ф�Ȥ����Ծ���������Ȥ��ƹ��ꤷ�Ƥ��뤫��Ǥ��롣�����ˤ����Τˡ���¸�Ǥ���ʹ֡פȡ������Ϳ��ʤ��ʹ֤Υ��롼�פ˿ʹ֤�ʬ�ĺ��̹�¤��ǧ��Ƥ��ޤ�����Ū�ʼ夵�����롣�����ˤϡ���ɬ�װ��פˤ�äơ�ɬ�ספ����������¦�ˤ����������ʬ�ʤ��뤤�Ͽ���*�ˤؤΰ��ȡ����ˤ�ä��Ǥܤ���뤫�⤷��ʤ�¦�ˤ���ʹ֡�¾�ԡˤؤ����餫��̵�ؿ��Ȥ������ο������̰ռ��ʤ��ˤϤ������ʤ����ۤʤΤǤ��롣
�ޤ�������Ȥϵ��Ū�ʿʹ֤����̤Ȥ�����ǽ�ˤ���ȴ�����̰ռ��ʤ��ˤϼ¸��Բ�ǽ�ʡ������פʤΤǤ��롣�����Ƥ��������ϡ����Ĥλ���Ǥ⡢�������ˤ��Ƽ�ʬ�ʤ伫ʬ�ο���ˤ������Ĥ��ã������ʬ�����ΰ�����̵���Ū������Ȥ���¤��夲����ΤǤ��롣
�����������̤���־��ספ����¦���Ф���̵�ؿ��ϡ���ɬ�װ��פ�ڡ��������ˤ���ʹ֤����δ֤���Ω�äƸ��Ф������ħ�Ǥ��롣ɬ�װ���ǧ��뼫ʬ�ϡ�¾�Ǥ�ʤ��ּ�ʬ�פε����Ȥ����������٤���ǽ���˴ؤ��ơ��ɤ���������Ϥ�Ư�����뤳�Ȥ��Ǥ��Ƥ���ΤǤ��������������˼�ʬ�����ε����˿Ȥ��ꤲ�Ф����Ȥ������ˤǤ����Ȥ��Ƥ⡢�����¾�Ԥε������Ʊ���˶���������Ρּ��ʵ����פǤϤʤ��Τ�������Ȥ�����ΤϤҤȤ�ǤϤǤ��ʤ��ΤǤ��롣
* ����ؤ�̵���ΰ��ϡ����ʰ��Ȥɤ�ۤɤ˰㤦�ΤǤ��������������λҶ��䰦����ʹ֤�ͥ��Ū����¸������ȸ�����ǽŪ�٤Τɤ��˥ҥ塼�ޥ˥���ο����������ΤǤ���������
�ɤ�ʤ�ͦ�ޤ�������ˤ����뼫�ʵ����������ʻ�ˤǤ��äƤ⡢����פ�ǡ��ɤ���Ϻ��⡢�ɤ���Ỵ�⡢��������Сֻ���Ϥޤ��פȻפ����⤷��ʤ��ǤϤʤ��������䡢��ϻפ��˰㤤�ʤ���
����ʤ��Ȥ�ͤ������Ƥ�����ɽ�Ȥ��ơ�ɮ�Ԥϡ����ܤη���٤�ɾ������ΤǤ��롣
�����������ȤǤ����Ĥޤꡢ������Ϥߤ�ʤ��ͤ���ۤɰ�����ΤǤϤʤ�����פȤ�����ĥ��ͤ��ˡ��ɤ����������丽��ǧ�����ֻٻ��פ�Ϳ���Ƥ���Τ�������Τɤ�����¦�̤�����������Ԥˡ�ͦ�����ϡפ�Ϳ���Ƥ��ޤ��Τ����Ȥ������Ȥ뤳�ȤˤĤʤ��뤫�顢�������̣������ΤǤ���
��������¦�̤ˤĤ��Ƥϡ������٤���̵������˲��Ⱥ��𡢤����ƿ�̿��ʹ֤�º����å�����˽�Ϥ��ȿ�Ū�ʤȤ�����������̵����Ǻ��𤷤������ˤ��ˤʹԻȤǤ��뤫�顢�Ĥޤ껦�ͤȤ�������֤��ΤĤ��ʤ�����ܼ���ǡ���ʤ���ͳ�ˤ����Ƥ��������Ǥ��ʤ����Ȥ�����ͳ�ʾ�Τ��Ȥ餿��Ƹ��ɬ�פ����ʤ�������ۤɺ��ͤˡ����Ǥ˼����Τ��ȤǤ���ʤ�����ɤ������ä��äƤ���ǡ֤������פȤ�����ΤǤ�ʤ��ۤɤˡ����Ѥ��ͤФʤ�ʤ����Ȥ�̵���ˤ���Τϸ����ޤǤ�ʤ��ˡ�
�������äơ������ˤ�������������������β��ͤ���Ȥ�������¸�ߤ��������������줿�Τ����Τ뤳�Ȥˤϲ��ͤ����롣�㤨�С��Ľջ����������������Ӥ�פ��ȤDzᤴ���Ƥ��������褷���Τ�ʤ��ʤ��ĤƤΡˤ��ɤ����ǯ�ˤ����פ�������ǡ���ˤ���̵��������Τ����Ȥ�����Ƚ���������뤳�ȤˤĤʤ���ΤǤ��롣�����ơ�������������������ԡʰ����������Ԥ�ޤ�ˤθ���ʬ��ñ��˿�����ʤ��뤤�Ϥ��Ρָ���ʬ�פ��Ф���Ʊ��Ū�ʡ˿͡���¸�ߡ����뤤��������Ỵ����ʬ������Ȥ��������Ǥ��ʤ������ʤΤǤϤʤ����Ȼפ���褦�ʡ�����Ū�������������ָ������פ���㤤����ο͡�����������¸�ߤ��������ĤĤ���Ȥ������Ȥ�ͤ���ˤĤ������ֹ������ԡפ�����������������Τɤ��˷���Ū�ʷ꤬����Τ����Ȥ������Ȥ��Τ�Ԥ���ɬ�פ�����Τ������������͡���Х��ƤФ�ꤷ�Ƥ⡢�ͳ����ꤷ�Ƥ⡢����Ϲ������ԡ��������ԤΤɤ���Υ���ˤ�ʤ�ʤ��Τ���
����Ȥ�����ΤΡ�¿�����ɤ����Ťʸ������Ƥ�����ܤη���١ʴ��ȿ���ˤˤ��С���������äƽ������ʣ��٤ο����ˤ���Ĥ����Ȥ�����ǯ��������������Ȥ��������켫�Τ���ˤȤäƤϾ�Ǥ��ä��������ܤ����ڡפε��ҤǤ��ä����������롢������������������¼�Ρ��Ϻ��ءפ�°����͡����餹��С�����Ǥ�����Ϥ���ޤǤǤϹͤ����ʤ��ۤɤ������Ǥ��겸���Ǥ��ꡢ������ϫ��Ⳬ�����줿�������ΰ³������Ǥ��ä��Ȥ��������Τʼ´�����ĸ�ʼ��ã�����롣���뤤�ϡ��Ҳ�Ȥϴط��ʤ�������Ȥ����ȿ��ϡ���ʬŪ���Ȥ��Ƥ�ˡ�ǽ�ϼ���פ��¸����Ƥ��������Ρָ�ʿ�ʤ�Ҳ�פǤ��äơ�����ε����塢�����������Τʾ�̲����Ρּ罾�ط��פϤ��ä���ΤΡ����ٰ�ʼ´�Ȥ������ꤷ�������Ǥϡ����������������ʤ����������²����¼�Ф⡢���٤ƤμԤ�Ʊ���Ӥ���Ʊ����������֤��������������Ϸ���γ��������Ǥϡ������ޤ��ּ¸����Ƥ��ʤ��ä����ȡפ��Ȥ����ΤǤ��롣
�����ơ�����������������Ԥ����̤�����ֵ���ʤ���Фʤ�ʤ��Τϡ���������ͳ��ʤƷ������ꤻ��������ʤ��ͤ����롢�Ȥ������¤Ǥ��롣
����Ф���ǤϤʤ������ޤ��ޤ���ͳ��ʤơ��ʤ�ۤɷ��⤬�֤褤���פ��ȴ����뤳�ȤˤϤ����Ĥ�Ρֺ���פ����ä�������
������ˡ�������������Τ�İ�Ϣ�Ρ�Ĺ��פ�ʤƷ����ʼ��ˤȤ�����Τ˲ݤ����Ƥ��뵡ǽ�����Ԥ���Ƥ�����䡢�����Ʋ������˲���˽�Ϥ��ǽ�ˤ���ƻ��Ǥ�ä��������Ƥ����ȿ��Ǥ���Ȥ������ȡ������ơ��ɱҤΤ����ƻ��Ǥ���פȼ�ĥ���ưݻ�����뷳�����Τ�Τ������Ū�ˤϡ�¾�ԡ�¾��ˤ��鸫��ж��Ҥ����оݤ��Τ�Τ�¾�ʤ�ʤ��Ȥ������������ơ����ɱҡפȱ���̾�Τ�Ȥ˿�ά*�����¸���ǽ�ˤ���Ȥ��������ǽ�Ū�ˤ�̿����ФǤ���Ȥ����ȥåץ������̿����֡������������ȸ�����Τΰ��ڤ�˽��Ū�ܼ����ܤ�������Ƥ��ޤ���褦�ʡֲ��͡פʤΤǤ���������
* ���Ĥ��ɱҤȤ�������ʤ��˹Ԥ�줿����Ȥ�����Τ����ä��������������٤Ƥ�����Ϥ����Ϥ��ͤ����ˤ�äơ��ɱҼ��ʡפǤ���ȼ�ĥ����Ƥ���ΤǤ��롣����ϸ��ߥ���ꥫ�罣�����ܤˤ�ä�������Ƥ�����������Ǥ��餽���Ǥ��롣���ܿͤ�ī��Ⱦ������������Τⷳ���Ÿ���������Τ⡢�֥�����������ζ��Ҥ��Ф��������ɱҤΤ���פȤ������������롣���ʤ�������ɱҡפʤɤȤ����������ϡ�ï�ˤ�äƤ��ǽ�Ǥ���Ȥ�����ͳ�ǡ����Ǥ�̵���Ǥ��ꡢ����ˤޤȤ�˼����ߤ�ɬ�פ��ʤ��ۤɤǤ��롣�ֹ��⤷�Ƥ��뤫�⤷��ʤ��פȰ����Ƕ��Ҥ����Ф�Ƥ���˿��˴ؤ��ơ�����¦���餹������Ƥ���Ƥη���������طʤ˳����Ÿ���������ܤ�ڹ���Ф��붼�Ҥ��Ƥ������ǡ����Ĺ��ɱҤΤ������������פȤ������¤���äƤ������Ǥ��롣���κݤɤ���ˡ������פ����ä��Τ����ȸ������Ȥ��䤦�ޤ����������μ¤ʤΤ�ī�����褬���������������������ȤΥХå����åפ�������������Ψ������ī��̱������̱���¹��¦�ˤ⡢����������Ф����ɱҤ�����˶���Ǥ����罣��˥Хå����åפ��줿���̱���¦�ˤ⡢�������������ؤδ��Сפ����ä��櫓�Ǥ��롣�ߤ������ɱҡפ������夲�Ʒ��ή����ä����Ǥ��롣
�����Ĺ��ˤ�äơ������������������ˤȤ�����Τϰ�����ΤǤϤʤ��פȤ�������Ѥϡ��������ᡢ��ɬ�װ��פ��ĥ����������̾��¾�ʤ�ʤ���������ɬ�װ�����ˤ���Ԥϡ��ְ��פ��ɬ�ספˤ�ä����դǤ���ȹͤ��Ƥ��롣�����Ф��뺬��Ū��̵�����뤤���Ỵ�ؤ������Ϥȴ������η�ǡ�����롣����Ф��꤫���Ū�ˤϺ���Ū�ʺ��̼����ȯϪ��¾�ʤ�ʤ��ΤǤ��롣
�Ĥޤꡢɬ�װ��Ǥ�äơ�ɬ�ספ����������͡�����������ǡ��ְ��פε����ˤʤäƻ�ʤʤ���Фʤ�ʤ��ͤ��Ф�Ȥ����Ծ���������Ȥ��ƹ��ꤷ�Ƥ��뤫��Ǥ��롣�����ˤ����Τˡ���¸�Ǥ���ʹ֡פȡ������Ϳ��ʤ��ʹ֤Υ��롼�פ˿ʹ֤�ʬ�ĺ��̹�¤��ǧ��Ƥ��ޤ�����Ū�ʼ夵�����롣�����ˤϡ���ɬ�װ��פˤ�äơ�ɬ�ספ����������¦�ˤ����������ʬ�ʤ��뤤�Ͽ���*�ˤؤΰ��ȡ����ˤ�ä��Ǥܤ���뤫�⤷��ʤ�¦�ˤ���ʹ֡�¾�ԡˤؤ����餫��̵�ؿ��Ȥ������ο������̰ռ��ʤ��ˤϤ������ʤ����ۤʤΤǤ��롣
�ޤ�������Ȥϵ��Ū�ʿʹ֤����̤Ȥ�����ǽ�ˤ���ȴ�����̰ռ��ʤ��ˤϼ¸��Բ�ǽ�ʡ������פʤΤǤ��롣�����Ƥ��������ϡ����Ĥλ���Ǥ⡢�������ˤ��Ƽ�ʬ�ʤ伫ʬ�ο���ˤ������Ĥ��ã������ʬ�����ΰ�����̵���Ū������Ȥ���¤��夲����ΤǤ��롣
�����������̤���־��ספ����¦���Ф���̵�ؿ��ϡ���ɬ�װ��פ�ڡ��������ˤ���ʹ֤����δ֤���Ω�äƸ��Ф������ħ�Ǥ��롣ɬ�װ���ǧ��뼫ʬ�ϡ�¾�Ǥ�ʤ��ּ�ʬ�פε����Ȥ����������٤���ǽ���˴ؤ��ơ��ɤ���������Ϥ�Ư�����뤳�Ȥ��Ǥ��Ƥ���ΤǤ��������������˼�ʬ�����ε����˿Ȥ��ꤲ�Ф����Ȥ������ˤǤ����Ȥ��Ƥ⡢�����¾�Ԥε������Ʊ���˶���������Ρּ��ʵ����פǤϤʤ��Τ�������Ȥ�����ΤϤҤȤ�ǤϤǤ��ʤ��ΤǤ��롣
* ����ؤ�̵���ΰ��ϡ����ʰ��Ȥɤ�ۤɤ˰㤦�ΤǤ��������������λҶ��䰦����ʹ֤�ͥ��Ū����¸������ȸ�����ǽŪ�٤Τɤ��˥ҥ塼�ޥ˥���ο����������ΤǤ���������
�ɤ�ʤ�ͦ�ޤ�������ˤ����뼫�ʵ����������ʻ�ˤǤ��äƤ⡢����פ�ǡ��ɤ���Ϻ��⡢�ɤ���Ỵ�⡢��������Сֻ���Ϥޤ��פȻפ����⤷��ʤ��ǤϤʤ��������䡢��ϻפ��˰㤤�ʤ���
����ʤ��Ȥ�ͤ������Ƥ�����ɽ�Ȥ��ơ�ɮ�Ԥϡ����ܤη���٤�ɾ������ΤǤ��롣
19:39:00 -
entee -
TrackBacks
2005-05-31
�֤���դ줿�ե�������סʤ���Dz��Ȥλ�����ƶ����
����������Ū��̵�ؿ��䤽��˿���������ä����ա��Ѱ첽��Ʊ�����ؤδ��ԡ�Ʊ���Ǥʤ����Ȥؤ�̵�ռ��δ������������Ȥ������ι�ư����դ���˸���롣
���ܡ��ա����륯���ԡإ��������ա١�����������p. 200
<<
�����������θ��դϡ������ο����夤��������������˸�����Ф롣����ĥ���Ǥʤ����äơ������ϻ��Ȥ��ơ������ȤΤ褦�˸�롣�֤ߤ�ʤ��������äƤ���פȸ�����롣����Ϥ�����������°���Ƥ���ռ��ȡ�������°���ʤ���Τؤΰ��η�ǡ������������Τ���
�����ϸĿͤΰ�������ϳ��ФƤ�����դˤ������Ŀͤθ��դ�ʹ����롣ï�ब���äƤ������ߤ�ʤ����äƤ������Ȥ�������������㤢�ʤ��䤬���֤���ɽ���뤫�θ���ʬ�ǤϤʤ����㤢�ʤ��䤬�㤢�ʤ��伫�Ȥθ��դǡ�����ä������뤳�Ȥ��Ǥ�����������ϸĿͤθ��դ�ʹ����뤳�Ȥˤʤꡢ����ˤȤäƤο��¤Ȥʤ롣�ޤ���ޤ����äƤ��θ����ʤ�������¿����ï����㤢�ʤ��䤬��ɽ�Ǥ��뤫�θ��ۤƤϤ����ʤ���
�ʡ��Ⱥ�ԡפФ��⤷���㤭�⤷���ˤߤⴶ����֤ҤȡפȤ���ª����˿�ɥ�����ե����˴ؤ��Ƥ���������˿�Dz��Ȥ��ꤲ������줿���ա�
�վԡ��Ⱥ���ﳲ�Ԥ������Ѥ���ɤ��פ��Ȼפ���Ǥ�������
��ȡ֤�������ﳲ�Ԥ���������ä�����Ǥ�������
�վԡ�... �����ˤϤ��ʤ����⤷��ޤ����⤷�Ѥ����ܤ����Ȼפ��ޤ�����
��ȡ��ܤ���뤫�⤷��ʤ����������ʤ����⤷��ʤ����Ǥ⡢�����ˤϤ��ʤ��Ǥ���͡�����Ȥ⤤��ä�����Ǥ�������
�վԡ֤��ʤ����⤷��ޤ����⤷�����Ȥ�����ɤ�������Ȼפ����֤��Ƥ����Ǥ�����
��ȡֻ�Ϥ��αDz���̤��ơ��Ⱥ��ﳲ�Ԥ����ˤǤϤʤ��ơ����ʤ����������Ѥơ���ʬ�Ǥɤ��פä������ʤ����˿֤��Ƥ����Ǥ����
��ϡ����Τ�������ۤ��Ƥ������ä����֤����Ѥ����β��ˤ���ߤ�ʤ���ˡ������Ⱥ��ﳲ�Ԥ����Ϥ���ä����ʤ����Ⱥ��ﳲ�ԤǤʤ����ʤ��������Ⱥ��ﳲ�Ԥε��������������������������ɽ�Ǥ��뤫�Τ褦�˻פ�����ǡ������ƻ�κ��ʤ���Ƚ���롣���ʤ����ϡ������ˤ��⤷�ʤ�����ä����Ȥ�ʤ��͡��ε��������狼��ȻפäƤ��ơ������ʡ����Τ��ʤ����⤷��ʤ��ͤβͶ��θ��դ�ʤơ��ͤκ��ʤ����롣�ɤ��Ǥ����������������ԥ����ɤ������Ǥ��������Τ�礤�������������ǻ����θƤӤ����ν�̾��ư���äƤ�������������ȡ�ɬ�������Ǥ��衢�����������Ȥ�����ͤ����ؤ���ʤ��Ȥ�äơ����Ⱥ�ε����Ԥβ�²���������ʤ��Τ�äƤ��뤳�Ȥ���ɤ��פ��Ȼפ���Ǥ������٤ȡ��������顢���ν�̾��ư���äƤ����������������������Ǥ����ػ��©�Ҥ��Ⱥ�ε����Ԥˤʤä���Ǥ����١�
�����������Ǥ��Ƥ���Ĥ��ǡ���ʬ�������Ǥ��Ƥ��ʤ��������ͤƤ����ι�ư���ߤ�Ω�Ƥ�Τ������������ʷаޤ䵤�����Ȥ�����Τ���������������������Ⱥ���ﳲ�Ԥβ�²�����ó��ԤεߺѤ��ĥ���뤳�Ȥ��̤��ơ֤�����˽�ϡʻ��͡ˤ����ꤹ��פȤ������ʻ��ۤδ�Ű�褦�Ȥ������Ȥ����롣
���������ɿ�Ū�Ǹ�ʿ���ȻפäƤ����ﳲ�Ԥ�Ω��Ǥ�Τ������������ȻפäƤ��ơ�������ɽ������������褦�Ȥ��������οͤ����롣���������οͼ��Ȥ�����ʬ������θ��դ��餺�ˡ��罰��֤ߤ�ʡפΰո��Ȥ��ơ��������ĥ��������ɽ����Ω����Ф����ư��˼���ߤ�����ʬ�������ư���¦�ˤ��뤳�Ȥ��ưפ�˺��롣�֤���դ줿�ե�������פϡ����������������ο͡פ���ˤ��ưפ��㿩�����롣
���ܡ��ա����륯���ԡإ��������ա١�����������p. 200
<<
�����������θ��դϡ������ο����夤��������������˸�����Ф롣����ĥ���Ǥʤ����äơ������ϻ��Ȥ��ơ������ȤΤ褦�˸�롣�֤ߤ�ʤ��������äƤ���פȸ�����롣����Ϥ�����������°���Ƥ���ռ��ȡ�������°���ʤ���Τؤΰ��η�ǡ������������Τ���
�����ϸĿͤΰ�������ϳ��ФƤ�����դˤ������Ŀͤθ��դ�ʹ����롣ï�ब���äƤ������ߤ�ʤ����äƤ������Ȥ�������������㤢�ʤ��䤬���֤���ɽ���뤫�θ���ʬ�ǤϤʤ����㤢�ʤ��䤬�㤢�ʤ��伫�Ȥθ��դǡ�����ä������뤳�Ȥ��Ǥ�����������ϸĿͤθ��դ�ʹ����뤳�Ȥˤʤꡢ����ˤȤäƤο��¤Ȥʤ롣�ޤ���ޤ����äƤ��θ����ʤ�������¿����ï����㤢�ʤ��䤬��ɽ�Ǥ��뤫�θ��ۤƤϤ����ʤ���
�ʡ��Ⱥ�ԡפФ��⤷���㤭�⤷���ˤߤⴶ����֤ҤȡפȤ���ª����˿�ɥ�����ե����˴ؤ��Ƥ���������˿�Dz��Ȥ��ꤲ������줿���ա�
�վԡ��Ⱥ���ﳲ�Ԥ������Ѥ���ɤ��פ��Ȼפ���Ǥ�������
��ȡ֤�������ﳲ�Ԥ���������ä�����Ǥ�������
�վԡ�... �����ˤϤ��ʤ����⤷��ޤ����⤷�Ѥ����ܤ����Ȼפ��ޤ�����
��ȡ��ܤ���뤫�⤷��ʤ����������ʤ����⤷��ʤ����Ǥ⡢�����ˤϤ��ʤ��Ǥ���͡�����Ȥ⤤��ä�����Ǥ�������
�վԡ֤��ʤ����⤷��ޤ����⤷�����Ȥ�����ɤ�������Ȼפ����֤��Ƥ����Ǥ�����
��ȡֻ�Ϥ��αDz���̤��ơ��Ⱥ��ﳲ�Ԥ����ˤǤϤʤ��ơ����ʤ����������Ѥơ���ʬ�Ǥɤ��פä������ʤ����˿֤��Ƥ����Ǥ����
��ϡ����Τ�������ۤ��Ƥ������ä����֤����Ѥ����β��ˤ���ߤ�ʤ���ˡ������Ⱥ��ﳲ�Ԥ����Ϥ���ä����ʤ����Ⱥ��ﳲ�ԤǤʤ����ʤ��������Ⱥ��ﳲ�Ԥε��������������������������ɽ�Ǥ��뤫�Τ褦�˻פ�����ǡ������ƻ�κ��ʤ���Ƚ���롣���ʤ����ϡ������ˤ��⤷�ʤ�����ä����Ȥ�ʤ��͡��ε��������狼��ȻפäƤ��ơ������ʡ����Τ��ʤ����⤷��ʤ��ͤβͶ��θ��դ�ʤơ��ͤκ��ʤ����롣�ɤ��Ǥ����������������ԥ����ɤ������Ǥ��������Τ�礤�������������ǻ����θƤӤ����ν�̾��ư���äƤ�������������ȡ�ɬ�������Ǥ��衢�����������Ȥ�����ͤ����ؤ���ʤ��Ȥ�äơ����Ⱥ�ε����Ԥβ�²���������ʤ��Τ�äƤ��뤳�Ȥ���ɤ��פ��Ȼפ���Ǥ������٤ȡ��������顢���ν�̾��ư���äƤ����������������������Ǥ����ػ��©�Ҥ��Ⱥ�ε����Ԥˤʤä���Ǥ����١�
�����������Ǥ��Ƥ���Ĥ��ǡ���ʬ�������Ǥ��Ƥ��ʤ��������ͤƤ����ι�ư���ߤ�Ω�Ƥ�Τ������������ʷаޤ䵤�����Ȥ�����Τ���������������������Ⱥ���ﳲ�Ԥβ�²�����ó��ԤεߺѤ��ĥ���뤳�Ȥ��̤��ơ֤�����˽�ϡʻ��͡ˤ����ꤹ��פȤ������ʻ��ۤδ�Ű�褦�Ȥ������Ȥ����롣
���������ɿ�Ū�Ǹ�ʿ���ȻפäƤ����ﳲ�Ԥ�Ω��Ǥ�Τ������������ȻפäƤ��ơ�������ɽ������������褦�Ȥ��������οͤ����롣���������οͼ��Ȥ�����ʬ������θ��դ��餺�ˡ��罰��֤ߤ�ʡפΰո��Ȥ��ơ��������ĥ��������ɽ����Ω����Ф����ư��˼���ߤ�����ʬ�������ư���¦�ˤ��뤳�Ȥ��ưפ�˺��롣�֤���դ줿�ե�������פϡ����������������ο͡פ���ˤ��ưפ��㿩�����롣
23:23:00 -
entee -
TrackBacks
2005-05-29
�֥��������դΥ�����ʥ��ȡפȤ����θ�
����Ū�˥ϡ��ɤʡֱDz�Υ�����ʥ��ȡפʤɤۤȤ�ɹԤä����Ȥ�ʤ�������˥��������դ�Dz�ۤǴѤ�Τϡ�����Ǥޤ������ܤˤ����ʤ�����ǰȯ�����ơ���������10:30pm������ī�Σ�����ޤ����ޤαDz�ۤDzᤴ����̵�Ťʤ룸���֤��ޤꡣ
�¤ϡ����������դ�1994ǯ�����ܤ�ˬ�䤷���Ȥ��ΰ��ݤ������αDz軨��˽����Ƥ���Ȥ����������ͥå��Ǹ��Ĥ��������θ��դ��鴶������ƶ���ο����˿���ư�����Τǡ����Τޤ�ž�ܤ��롣���줾��κ��ʤ˴ؤ�����������ʬ�ΰ��ݤ�Ĥ�Ť�˽������ˤҤȤĤθ��դ���Ѥ�������
��... ��ϡ����ܤ��鵢�ä��Ф���Ǥ����ä������Ȥˡ�������ܤǤ����ʤ�۹���ⴶ���ޤ���Ǥ����������Ϥǻ�ϡ������Τɤ�ʹ�Ǥ⸫�����ȤΤʤ��ۤ�¿������줿�͡����ܤˤ��ޤ������⤷�������ͤ������ܿͤΤ褦�����Ƥ���Τʤ顪������ʤ���줿̱²���ޤޤǤ˰��٤⸫�����Ȥ�����ޤ�����ϫ�Τ��ޤ�͡����㤯�Τ��ܷ⤷�ޤ�������ϫ����Ǥ��衣�����⺣�����ڤˤʤ�ʤ��椨�ˡ��������������⺣���Τ褦�˿ɤ��椨�ˡ����äȥ������Ǥ�������Ĥ��ʤ��Ǥ��礦 ... ��ͤοʹ֤����Ƥ���ΤϤ狼��ޤ����Ǥ⡢̱²���Τ����Ƥ���ʤ�� ... ���Ϸ����ˤ��������ޤ����Ͼ�ζ��֤Ǥ����ï������ϫ�ν����ͤ�����äƤ��뤳�Ȥϡ������ƽ��פʤΤǤ��������餯�䤿���ߤ�ʤΤ���ˡ����Ϥ��ν����ͤ�����äƤ���ΤǤ��礦�����������ޤ����ºݤʤ�κ��ʤ��Τˡ����ʤ��Ȥ��������ˡ��������ν��ͤ���٤����ܿͤΤۤ��������äȺ�Ͼ������ΤǤ����䤿���������ͤ����Ƥ���ȸ����ޤ��������ܿͤˤϵڤӤޤ���
���䤿���ϡ�����ʻ���������Ƥ��ޤ����ʤ��ʤ顢�͡��Τ��Τ褦����ϫ������װ��������ߤۤɥɥ�ޥ��å��ǵ�����ä����Ȥϡ����ޤ����ĤƤʤ��ä�����Ǥ������Τ褦�ʸ��ݤθ�ˤϡ����äȤʤˤ���������Ǥ��礦������ʤ��Ȥ�Ĺ��³���Ϥ����ʤ�... �ʤˤ���������ˤ���������ޤ���
����ϡ�������ͽ�������ʹ֤θ��դȤ��ƤǤϤʤ�������̱²�����Ȥ��������ˤ�����ֵ�ǽ�פؤ�ƶ���������Ƥ���̱²�ؤο��������Τޤʤ�������������դǤ��롣���Τ褦�ˡ�¾�ͤ�¾��̱²���Ĥ�뤳�Ȥν���뿴�Ȥϡ�������줳���������Τ褦�ʷݽѲȤ�������۶����Ϥ�ʸ���Ȥ�����Τ˿����������Ƹ�������ؤФʤ���Фʤ�ʤ���
[Read More!]
�¤ϡ����������դ�1994ǯ�����ܤ�ˬ�䤷���Ȥ��ΰ��ݤ������αDz軨��˽����Ƥ���Ȥ����������ͥå��Ǹ��Ĥ��������θ��դ��鴶������ƶ���ο����˿���ư�����Τǡ����Τޤ�ž�ܤ��롣���줾��κ��ʤ˴ؤ�����������ʬ�ΰ��ݤ�Ĥ�Ť�˽������ˤҤȤĤθ��դ���Ѥ�������
��... ��ϡ����ܤ��鵢�ä��Ф���Ǥ����ä������Ȥˡ�������ܤǤ����ʤ�۹���ⴶ���ޤ���Ǥ����������Ϥǻ�ϡ������Τɤ�ʹ�Ǥ⸫�����ȤΤʤ��ۤ�¿������줿�͡����ܤˤ��ޤ������⤷�������ͤ������ܿͤΤ褦�����Ƥ���Τʤ顪������ʤ���줿̱²���ޤޤǤ˰��٤⸫�����Ȥ�����ޤ�����ϫ�Τ��ޤ�͡����㤯�Τ��ܷ⤷�ޤ�������ϫ����Ǥ��衣�����⺣�����ڤˤʤ�ʤ��椨�ˡ��������������⺣���Τ褦�˿ɤ��椨�ˡ����äȥ������Ǥ�������Ĥ��ʤ��Ǥ��礦 ... ��ͤοʹ֤����Ƥ���ΤϤ狼��ޤ����Ǥ⡢̱²���Τ����Ƥ���ʤ�� ... ���Ϸ����ˤ��������ޤ����Ͼ�ζ��֤Ǥ����ï������ϫ�ν����ͤ�����äƤ��뤳�Ȥϡ������ƽ��פʤΤǤ��������餯�䤿���ߤ�ʤΤ���ˡ����Ϥ��ν����ͤ�����äƤ���ΤǤ��礦�����������ޤ����ºݤʤ�κ��ʤ��Τˡ����ʤ��Ȥ��������ˡ��������ν��ͤ���٤����ܿͤΤۤ��������äȺ�Ͼ������ΤǤ����䤿���������ͤ����Ƥ���ȸ����ޤ��������ܿͤˤϵڤӤޤ���
���䤿���ϡ�����ʻ���������Ƥ��ޤ����ʤ��ʤ顢�͡��Τ��Τ褦����ϫ������װ��������ߤۤɥɥ�ޥ��å��ǵ�����ä����Ȥϡ����ޤ����ĤƤʤ��ä�����Ǥ������Τ褦�ʸ��ݤθ�ˤϡ����äȤʤˤ���������Ǥ��礦������ʤ��Ȥ�Ĺ��³���Ϥ����ʤ�... �ʤˤ���������ˤ���������ޤ���
����ϡ�������ͽ�������ʹ֤θ��դȤ��ƤǤϤʤ�������̱²�����Ȥ��������ˤ�����ֵ�ǽ�פؤ�ƶ���������Ƥ���̱²�ؤο��������Τޤʤ�������������դǤ��롣���Τ褦�ˡ�¾�ͤ�¾��̱²���Ĥ�뤳�Ȥν���뿴�Ȥϡ�������줳���������Τ褦�ʷݽѲȤ�������۶����Ϥ�ʸ���Ȥ�����Τ˿����������Ƹ�������ؤФʤ���Фʤ�ʤ���
[Read More!]
23:39:00 -
entee -
TrackBacks
2005-05-23
���ư��פ���β�������ʡ�
�㤨�Ф��������äǤ��롣
ï���������ۤ��ϡפ��˸��Ф��������ηݽѳ�ư�褦�Ȥ��ơ��ǽ��Ʊ�Ϥ˹�ˡ�ʼ��ʤ��������θ塢�ӥ��θ��Ϥ����餫����ͳ���ڤ�Ƥ��ޤ��Ȥ��褦���ʳ�����������פ����ͤ������Ƥ���ʾ塢���Τ褦�ʤ��Ȥ�������Τ��������˵����äƤ��Ƥ��ԻĤϤʤ����֤Ǥ��롣�ˤ��Ф餯�Ͻ����������Υ����å���ʤ��������ʤ��вᤷ�Ƥ����Ȥ��ơ������������餫�εͤޤ�ʤ���ͳ�ǡ���ˡ�ںߡפ�����¦�˥Х�Ƥ��ޤ��Ȥ��褦�������ơ��䤬�Ƥ϶���Ū�ʹ����̿����롣����ϡ�����˴̿����̱�Ǥʤ��¤ꡢ�ݽѤ������ȡ�������ʸ����ư�������ȡ��ӥ��ͥ��ǰ���Ȥ��褦�ȡ��ɤ����ͳ��Ʊ����Ϥä����ˤ�餺�������ñ�ʤ�ָĿ�Ū��ˡŪ�ʼ�³���������Ǥ���פȸ����롣
�����Ǥ���ñ�ʤ�Ŀ�Ū�ʡ�ˡŪ��³���ߥ��פʤΤˡ�����ˤ�ä��������ȥ�֥�˲��ȿ�����ơ����꤬����������ʸ���ư����פ�����Ω�Ƥ�Ȥ��롣����ȡ��ɤ��ʤ뤫������ϡ�ñ�ʤ�Ŀ�Ū�ʡֻ��Ρפ��Ƚ�ǥߥ��פǤ��ä����⤷��ʤ��Τˡ����Τ��Ȥϡ�ʸ���ư��פǤ���Ȥ�������ƥ����Ȥ��ɤ��֤��졢�Ʋ�ᤵ��뤳�Ȥˤʤꡢ����ϡּҲ�Ū�ʻ���פȤʤ롣
�ֵ��������¡פȡֿʹ֤Τ��������������פδ֤˥���åפ������롣������Ǥ⤳����Ǥⵯ���롣�����Ƥ��κݡ��ֲ��פϤ����餯�ϹҤ����ܿͤνп��Ϥ��ܿͤ��������Ƥ������Ϥ�ξ���ǡ����뤤��Ω��ΰ㤤�ˤ�äơ����ޤ��ޤʥ���åפν�����뤳�Ȥˤʤ롣��������ʬ�˰ռ�������ʤ���Фʤ�ʤ��Τϡ���ʸ���ư��Ǥ���פȹͤ������͡��λפ��̤�ˡ���̤Ȥ��ơ��������꤬�ָ��²����Ƥ����פȤ�����ǽ���ˤĤ��ƤǤ��롣�Ĥޤꡢ��ͽ���μ������������Τ褦�ˡ��ֻ��ݡפ�������ĥ����������˶��äƤ������Ȥ�����Ҥ�ſ�ݤ������롣
���ʤ�������ΡָĿ�Ū�ߥ��פ����礭�ʥߥ��פؤ�ȯŸ�����ǽ�������롣
�����ʤä��Ȥ����顢�����ˤ�����ʸ����ư�μ������פ������Ȥ���¦�ˤȤäƤ⡢�������ɼԤ�¦�ˤȤäƤ⡢�ɤ���ˤȤäƤ��Թ��ʷ�̤��ԤäƤ����ǽ��������Τ���
�Ĥޤꡢ���������������ư�Ȥ�ȿ�б�ư�����֡����μ�ͳ����פȥ����뤹�뤳�Ȥǡ�����¦�ˡ��������ư��פ뤭�ä����ʸ��¡ˤ�Ϳ���Ƥ��ޤ��Ȥ������ȤǤ��롣���ϼ�¦���äơ��ʹ֤ν��ޤ�Ǥ���ʾ塢�֤����ʢ����פ�õ����д���Ū�ˤ�ȿ�����뤷����ö����Ū�ˤ����������������Ȥ������Ȥˤʤ�С����⼫���ݿȤ�������ư���Ƥ���ΤǤ��뤫�顢�ֲФμ�פ��礭���ʤ�ʤ������ˡ����ư��פ����ơ���Ȥ�ȤϤ���⤷�ʤ��ä����Ρֱ�ư�פ��ޤ��褦�Ȥ��뤫�⤷��ʤ����ǽ�Ϥɤ��ˤ�����Ϥʤ��ä��Τˤ�ؤ�餺������������С���ư��¦���餷�Ƥ�֤��츫�����Ȥ������줬���Ϥ����Τ��פȰ��ؤα�ư�η㲽��ƤӤ����뤫�⤷��ʤ��������ơ��ư�����¦�Ϥ����Ϥ�˹��롣�����ְ��Ϥ�ĥ��礤�פȸƤ֡�
����ϡ��̤����Ʒݽѳ�ư�褦�Ȥ��Ƽºݤ�¾����Ϥä�ɽ�������ͤ�Ω���褯���뤳�ȤʤΤ������������Ϥä�ɽ���Լ��Ȥ�������ư��Ÿ�����뤿��ˡ��տ�Ū�ˡ֥ӥ����ڤ����ˡ�ںߤ���פ��Ȥ�פä����ȤǤ�����Τ�������������Ͻ���Ȭ��㤦���ࡿ����ˤȤäƤϡ����ޤ��̤�ˤ��ι���ںߤǤ��ơ�������ɽ����ư��³�����ơ������ϤǸ��Ĥ���ͧ���οͤ����ȳڤ�����äƤ������ȡ��������Ȼ���ưפ��������롣
�������Ϥ˴ؤ������Ȥϡ��������������¸�ߤ��롣�������ʤ�Ǥ⤫�Ǥ�֤���פǤ���ȥ�ǥ������ȿ�����뤳�Ȥ����ɤ�������̤�⤿�餹�Τ����Ȥ������Ȥޤǥ�����������������Ϥ�ɬ�פʤΤǤϤʤ�����
���Ȥ��С��̤����ơ����Τ��Ȥ����������פȤ����ɤ��ؤ��뤳�Ȥ�������οͼ��Ȥ�ʡ���ˤʤ�Τ��ɤ��������뤤�ϡ����夽���Ϥ�ɽ����ư�����ȻפäƤ������켫�Ȥ�ʡ���ˤʤ�Τ��ɤ����������ޤǹͤ���������Ĥޤ��Ʈ�褻���˾���������פȤ�����������ά�Ȥ���ʬ�˶�̣���Ƥ�����������������������Ȱ��ڤ��餿��ƽϹͤ���ɬ�פ����롣
�ե륹������Ρ�����Ʈ��פȤʤä�����Τ�ï�ʤΤ��������ơ�ï��������˳����������Τ����ͤ��Ƥ����ư���������ݼ�Ū�˶���ȯ�����������ϡ֤��α���ˤ���͡פ��ɤΤ褦�ˤ��Ƥ��Υȥ�֥뤫��Υæ�Ǥ���Τ���ͥ�褷�ƹ�ư����ʤ��뤤�ϡ���ư������ˤ٤��ǤϤʤ����������������ϤҤȤĿ����ʥ˥塼�������ޤ��ۤäƸ��Ƥ��롢�Ȥ����Τ��ɤ����ʤȤ�����ʬ��������ʤ�Τ��̷��ˤϡ��ɤ����������ܤ�Ĥ֤äƲ����졣��
�ޤä�����äơ����Ū�ʡ��㤨�Сפ��äʤ����͡�����ϡ�
ï���������ۤ��ϡפ��˸��Ф��������ηݽѳ�ư�褦�Ȥ��ơ��ǽ��Ʊ�Ϥ˹�ˡ�ʼ��ʤ��������θ塢�ӥ��θ��Ϥ����餫����ͳ���ڤ�Ƥ��ޤ��Ȥ��褦���ʳ�����������פ����ͤ������Ƥ���ʾ塢���Τ褦�ʤ��Ȥ�������Τ��������˵����äƤ��Ƥ��ԻĤϤʤ����֤Ǥ��롣�ˤ��Ф餯�Ͻ����������Υ����å���ʤ��������ʤ��вᤷ�Ƥ����Ȥ��ơ������������餫�εͤޤ�ʤ���ͳ�ǡ���ˡ�ںߡפ�����¦�˥Х�Ƥ��ޤ��Ȥ��褦�������ơ��䤬�Ƥ϶���Ū�ʹ����̿����롣����ϡ�����˴̿����̱�Ǥʤ��¤ꡢ�ݽѤ������ȡ�������ʸ����ư�������ȡ��ӥ��ͥ��ǰ���Ȥ��褦�ȡ��ɤ����ͳ��Ʊ����Ϥä����ˤ�餺�������ñ�ʤ�ָĿ�Ū��ˡŪ�ʼ�³���������Ǥ���פȸ����롣
�����Ǥ���ñ�ʤ�Ŀ�Ū�ʡ�ˡŪ��³���ߥ��פʤΤˡ�����ˤ�ä��������ȥ�֥�˲��ȿ�����ơ����꤬����������ʸ���ư����פ�����Ω�Ƥ�Ȥ��롣����ȡ��ɤ��ʤ뤫������ϡ�ñ�ʤ�Ŀ�Ū�ʡֻ��Ρפ��Ƚ�ǥߥ��פǤ��ä����⤷��ʤ��Τˡ����Τ��Ȥϡ�ʸ���ư��פǤ���Ȥ�������ƥ����Ȥ��ɤ��֤��졢�Ʋ�ᤵ��뤳�Ȥˤʤꡢ����ϡּҲ�Ū�ʻ���פȤʤ롣
�ֵ��������¡פȡֿʹ֤Τ��������������פδ֤˥���åפ������롣������Ǥ⤳����Ǥⵯ���롣�����Ƥ��κݡ��ֲ��פϤ����餯�ϹҤ����ܿͤνп��Ϥ��ܿͤ��������Ƥ������Ϥ�ξ���ǡ����뤤��Ω��ΰ㤤�ˤ�äơ����ޤ��ޤʥ���åפν�����뤳�Ȥˤʤ롣��������ʬ�˰ռ�������ʤ���Фʤ�ʤ��Τϡ���ʸ���ư��Ǥ���פȹͤ������͡��λפ��̤�ˡ���̤Ȥ��ơ��������꤬�ָ��²����Ƥ����פȤ�����ǽ���ˤĤ��ƤǤ��롣�Ĥޤꡢ��ͽ���μ������������Τ褦�ˡ��ֻ��ݡפ�������ĥ����������˶��äƤ������Ȥ�����Ҥ�ſ�ݤ������롣
���ʤ�������ΡָĿ�Ū�ߥ��פ����礭�ʥߥ��פؤ�ȯŸ�����ǽ�������롣
�����ʤä��Ȥ����顢�����ˤ�����ʸ����ư�μ������פ������Ȥ���¦�ˤȤäƤ⡢�������ɼԤ�¦�ˤȤäƤ⡢�ɤ���ˤȤäƤ��Թ��ʷ�̤��ԤäƤ����ǽ��������Τ���
�Ĥޤꡢ���������������ư�Ȥ�ȿ�б�ư�����֡����μ�ͳ����פȥ����뤹�뤳�Ȥǡ�����¦�ˡ��������ư��פ뤭�ä����ʸ��¡ˤ�Ϳ���Ƥ��ޤ��Ȥ������ȤǤ��롣���ϼ�¦���äơ��ʹ֤ν��ޤ�Ǥ���ʾ塢�֤����ʢ����פ�õ����д���Ū�ˤ�ȿ�����뤷����ö����Ū�ˤ����������������Ȥ������Ȥˤʤ�С����⼫���ݿȤ�������ư���Ƥ���ΤǤ��뤫�顢�ֲФμ�פ��礭���ʤ�ʤ������ˡ����ư��פ����ơ���Ȥ�ȤϤ���⤷�ʤ��ä����Ρֱ�ư�פ��ޤ��褦�Ȥ��뤫�⤷��ʤ����ǽ�Ϥɤ��ˤ�����Ϥʤ��ä��Τˤ�ؤ�餺������������С���ư��¦���餷�Ƥ�֤��츫�����Ȥ������줬���Ϥ����Τ��פȰ��ؤα�ư�η㲽��ƤӤ����뤫�⤷��ʤ��������ơ��ư�����¦�Ϥ����Ϥ�˹��롣�����ְ��Ϥ�ĥ��礤�פȸƤ֡�
����ϡ��̤����Ʒݽѳ�ư�褦�Ȥ��Ƽºݤ�¾����Ϥä�ɽ�������ͤ�Ω���褯���뤳�ȤʤΤ������������Ϥä�ɽ���Լ��Ȥ�������ư��Ÿ�����뤿��ˡ��տ�Ū�ˡ֥ӥ����ڤ����ˡ�ںߤ���פ��Ȥ�פä����ȤǤ�����Τ�������������Ͻ���Ȭ��㤦���ࡿ����ˤȤäƤϡ����ޤ��̤�ˤ��ι���ںߤǤ��ơ�������ɽ����ư��³�����ơ������ϤǸ��Ĥ���ͧ���οͤ����ȳڤ�����äƤ������ȡ��������Ȼ���ưפ��������롣
�������Ϥ˴ؤ������Ȥϡ��������������¸�ߤ��롣�������ʤ�Ǥ⤫�Ǥ�֤���פǤ���ȥ�ǥ������ȿ�����뤳�Ȥ����ɤ�������̤�⤿�餹�Τ����Ȥ������Ȥޤǥ�����������������Ϥ�ɬ�פʤΤǤϤʤ�����
���Ȥ��С��̤����ơ����Τ��Ȥ����������פȤ����ɤ��ؤ��뤳�Ȥ�������οͼ��Ȥ�ʡ���ˤʤ�Τ��ɤ��������뤤�ϡ����夽���Ϥ�ɽ����ư�����ȻפäƤ������켫�Ȥ�ʡ���ˤʤ�Τ��ɤ����������ޤǹͤ���������Ĥޤ��Ʈ�褻���˾���������פȤ�����������ά�Ȥ���ʬ�˶�̣���Ƥ�����������������������Ȱ��ڤ��餿��ƽϹͤ���ɬ�פ����롣
�ե륹������Ρ�����Ʈ��פȤʤä�����Τ�ï�ʤΤ��������ơ�ï��������˳����������Τ����ͤ��Ƥ����ư���������ݼ�Ū�˶���ȯ�����������ϡ֤��α���ˤ���͡פ��ɤΤ褦�ˤ��Ƥ��Υȥ�֥뤫��Υæ�Ǥ���Τ���ͥ�褷�ƹ�ư����ʤ��뤤�ϡ���ư������ˤ٤��ǤϤʤ����������������ϤҤȤĿ����ʥ˥塼�������ޤ��ۤäƸ��Ƥ��롢�Ȥ����Τ��ɤ����ʤȤ�����ʬ��������ʤ�Τ��̷��ˤϡ��ɤ����������ܤ�Ĥ֤äƲ����졣��
�ޤä�����äơ����Ū�ʡ��㤨�Сפ��äʤ����͡�����ϡ�
20:39:00 -
entee -
TrackBacks
2005-05-06
���åۤΡֲ���פ����Ƴ���Ϻ�θ�����ݦݨ�פε���
���ѻ���Σ����ܡ�������������...��
�����Υ饤���ǥԥ��Τξ�����֤������ۤˡ��������ơ�Ω����ä�����Ǥ��뤬�����Ϥηٻ��𤫤��Ϣ���Ǻ��ۤ��������줿�����Τ���롣�ФƤ����ΤǤ��롣��������Ω����ä�������ʬ���ǻ�ΤȤ����ˤ���äƤ�������������ͤ˽����ơ�������ФƤ�����꤬������ë�ǤϤʤ����䤬�Ԥä����Ȥ�ʤ�˿�꤫��Ǥ��롣�¤����ʡ��ż֤ȥХ�����Ѥ��ǡֱ����פηٻ���˽и�����������ˤ��Ƥ⡢���Ǥ���뤷�Ƹ�������ʤ��ʤäƤ����ԤΥ���å��奫���ɤ�顢��Ϥ���¤��ڤ�ƻȤ��ʤ��ʤä���ž�ȵ���顢�������Υ������ब���ΤޤޤˤʤäƽФƤ����ΤǤ��롣�������������Ͼ�����ޤ�Ƥ��줤���äѤ���Ǥ��Ф��줿���֤Ǥ��ä������ۤ��Τ�Τ���äƤ����Τ��ɤ��ä�����������������Ū�˺��ۤ��椫����ʤ��ʤ��ʤäƤ��������Թ���ι����פȿͤ���ϸ���줿�������������������������ޤǡ������ɤ�����Τ�ʤ��ͤλ����鲿��餬�Ĥ��Ƥ��뤷�������������ä���ʤ���
ݵƫ�������ȵ�ʬ��ž�����٤����ض�����결�����ä��ʤ��夯�ȡ����åۤ�ʣ���褬�ܤ����ˤ��롣������ľ���ơ��ݶ��ι�Ω�������Ѵۤإ��å�Ÿ��Ѥˤ������Ȥˡ������ߤäƤ������Ȥ˲ä��ơ�ʿ���פǤ��ä����ᤫ��5/3�˽����褿��������������Ǥ��ʤ��ä��ΤϹ������Ȥꤢ��������ƻ�ޤǰ���ۤɤι���Ȥ��Ϥʤ��ä���������äƤߤ�ȳΤ��ˤʤ��ʤ��ʤޤʤ����ͤ�Ƭ�ǴѤŤ餤�Ȥ����Ϥ��ä��������饤�餷�����Ѥ����ʤ��ۤɤǤϤʤ����ޤ������ޤ���Υ�ǴѤ����ʤ����⤢�äơ���Υæ�����ꡢ��֤ζ����Ƥ���Ȥ�����Ŭ���˰�ư���ʤ���IJ��˴վޤ��뤳�Ȥ��ǽ���ä��Τǡ����οͤο��������ޤ굤�ˤʤ�ۤɤǤϤʤ��ä���������ͤϾ��ʤ��ˤ��������ȤϤʤ�������⤽�������ΤҤȤ��������ʿ����äƤ�������ʤ���
���åۤθ���Ȥ����ΤϺ��ޤǤ��ñ�ʡפǤ��������Υߥ塼������ξ���Ÿ���Ȥ��Ǥ����Ĥ���Ѥ����ȤϤ��ä���������ۤɤΤޤȤޤä����ǡ�������Ŭ�٤�Ĵ�����줿���β��ǴѤ��ΤϽ��ƤǤ��롣�ޤ���Ʊ����β�Ȥˤ����ʤȤ�ʻ��Ÿ���⤢�äƤ�����������٤���Τϡ���Τ褦�����Ѥ˴ؤ��ƥ������ȤˤȤäƤϡ����������ʤ��Ȥ�¬������ؽ����뤳�Ȥ��Ǥ���ͭ���ΤǤ��롣
�褯��¸�Τ����ʤ�ȿ���⤢�뤫�⤷��ʤ���������ˤ��Ƥ⡢���åۤβ������ޤä�����ǡ�Ȥ��������ѰۤΤ褦�����˽и������Ȥ������ϡ�������Ʊ����κ�ȤΤ��ޤ��ޤʼ�ˡ���㤨�������ʤɡˤ�ʬ�ʤ�˻���������줿�ꡢ���������ꡢ�Ϥ��ޤ��ߥ졼�ʤɤΡָ�ŵ�פ�Ǯ�����ϼ̤�Ԥä��ꡢ�Ȥ�����Ժ����β̤Ƥ���ã������Τ����Ȥ����������������ޤ������̤Τʤ������<<����>
����ˤ��Ƥ⡢�����ζ�Ρ־Ȥ�פȵ����褦�ʿ��α�䤫���ϡ��ȤƤ�ɴ��ǯ���θ�ŵ�����褦�ʴ����Ϥ��ʤ�����Ϥޤ����γ��ζ�Ρ��Ĥ����������줿�褦�˸����뤽�ο������ˡ����褫�餷�����������ʤ���ư��Ф���������ϡ��ǽ���õ����Ƥ����������Ȥ���
�� ���� �� ��������� (1884)
���̤�����̤��Ʋ���θ���������������Ƥ��ơ��ո�����ǿ�ʪ�뿦�ͤδ���سԤ�夬�����ȿ�ͤ��Ʋ���˵����Ƥ��롣����ϡ�1889ǯ����Ϥޤ륵����ߤ�dz����褦�ʰ�Ϣ�κ��ʷ�����Ω�Ĥ��ȣ�ǯ���κ��ʤ���������˵����֤�����������פθ���˨�꤬����褦�˻פä���
�� �쥹�ȥ������� (1887)
ʻ��Ÿ���Υ��˥�å����她�Ȥ��ä������β�Ȥ������ɵᤷ���Τ�Ʊ�ͤκ�����ǻ���˸�������ʡ��ʤ�ȸ��äƤ�쥹�ȥ����ɤˤ������Ƥ���ե����åۼ��Ȥγ��Ȥ����Τ���Ʊ���������결�Ǹ����褦�ˡ��������⸽�ߥ��åۤ�ʣ���褬���������Τ褦�˥쥹�ȥ������Ź���ɤ˳ݤ����Ƥ���Τ��¸����뤫�Τ褦�ʺ��ʡ�Aquikhonne۩���ˤǡ��ڤ��������뤤�쥹�ȥ������������ʤϡ��ºݤΥ��åۤο�����פ��ˡ������äƤ�뤻�ʤ��������ˤ������ΤǤ��롣���åۤΰ����Ϥ����餯�༫�Ȥε�ǰ��ȿ�Ǥ��Ƥ��롣
�� �ݽѲȤȤ��Ƥμ����� (1888)
��˥ѥ�åȤ���ļ�����������ˤ��ȡ����Υѥ�åȾ�Ρֳ��ζ����̤礹�뤳�Ȥʤ��Ѥ���줿���פ�Ĥ��Ƥ���ΤǤ��ꡢ����ϤĤޤ���ݼ���俷���ݼ���αƶ���ʪ��äƤ���餷���������դ�ϡ��ɤ�������ݥå��ᥤ���ʤ��ȤʤΤ��Ϥ褯�狼��ʤ������������뤳�Ȥʤ����ζ�Ÿ������Ƥ��뤳�ȤϳΤ��˥����Х��夫���Ǥ��롣�������䤬���ݿ����������ΤϤ��������ƥ��˥å��Τ��ȤǤϤʤ��ơ��ե����åۼ��Ȥ������äƤ��롢�ܥ���ΤҤȤĤ����դ����ޥ�ȤΤ褦�ʰ����Ǥ��ä������줬�¤ˡ�Ʊǯ�������줿<<��Υ��ե��ƥ饹>
�� ��Υ��ե��ƥ饹 (1888)
����Ρ֥��å�Ÿ�פΥݥ������ˤ�ʤä�������Ÿ������̤ܶΤҤȤġ����γ��Ƥ����ҤȤĤ��������Ŀ�Ū�ʤ��ȤȤϡ�����Ϻ�Ρ�ݦݨ�פμ��Τ�����Ǥ��롣����ä�Ĺ���ʤ뤬���Τޤް��Ѥ��롣
�֤������Ϥ����Ťʤ��ᡢŹƬ��������줿���Ĥ���������屫�Τ褦����Ӥ������밼।ϡ����Ϥβ��Ԥˤ�å���뤳�Ȥʤ����ۤ����ޤޤˤ�������į��Ȥ餷�Ф���Ƥ���Τ��������������Ĺ���������꤭������ػɤ�����Ǥ�������Ω�äơ��ޤ����ˤ���ﭲ����ξ˻��������į����β�ʪŹ��į��ۤɡ����λ��ɤ��λ���餻����Τϻ�Į����Ǥ���ä���
����������Ϥ��Ĥˤʤ�����Ź����ʪ�����Ȥ����ΤϤ���Ź�ˤ�������ݦݨ���ФƤ����Τ�����
�Ǹ����Ƥ��ɤ������ե����åۤ�������Τȳ���Ϻ��������Τϡ��ۤȤ��Ʊ���Τ��������ƴ�Ϻ��̥����ݦݨ�ε��������������屫�Τ褦����Ӥ������밼ॡס����ŵ夬��Ĺ���������꤭������ؼͤ�����Ǥ���פ���Ȥϡ����åۤ�����³�����ֲ���פ�¾�ʤ�ʤ��������ϡ����ο���̥�����롣
�� ������ߤ����ܱ����� (1889)
���ޤ������˹Ԥ��Ϥ��Ƥ��ʤ��褦�ʻ��������Фꡢ�֤�Ĥ����ڡ����դΤҤȤĤҤȤĤ���̿��©���ȯ�����Ƥ��ơ��ۤȤ�ɡ֤䤫�ޤ����פФ���Ǥ��롣�٥����������줽���ʤۤɤμ�����ιԤ��Ϥ��Ƥ��ʤ����Τ褦�������Τ����Ǥ������������Τ��ϤޤäƤ��ꡢ��֤䤬�Ƶ����ηʿ��פȲ����Ƥ��ޤ��椬�ȼ��դ��ԱĽ������Ҽ��դ����ͽ���Ϥ������פ��Ф����롣���åۤ϶����������ζ��֤ǡ���������©������Ф��Ƥ����Τ���
�� ��������θ�����ƻ (1890)
����ˤ��Сʤ��뤤�ϥ��åۼ��Ȥε��Ҥˤ��Сˡ��������ʤǤ��뤽�������������Τ���ϡ�������Ƥ������α���ˤ���ֻ�����פ��餫�������ƿ�¬�Ǥ����Τ������������줬��ʤǤ�����ʲʤ���Фʤ�ʤ���ͳ����ˤ�ʬ����ʤ�����äݤ�ƻ�⡢������Ԥ��͡��λѤ⡢���줬���ƻ�Ǥ���Ȥ����ʤ�ξڤˤ�ʤäƤ��ʤ��ʻ�ˤϡˡ�������Ǥ���С�ƻ��ۤɤ����뤵�ǾȤ餹�ַ�������פǤ���Ϥ����ʤ�����̾����Ǥ�������פ⡢���ε����ϡ���ĥ����Ƥ���Ȥϸ������ޤ�����ۤΤ褦�����������������ʸ���ȯ���Ƥ���褦�˸����뤽��ŷ�Τϡ����餫�ˡ����ۡפ�ռ�������Τ������Τ��Ȥ���Ϥ��ʻ���μ��ι𤲤�Ȥ����ϡ����γ���������Ƥ����Τ�����ʤǤ���֤ηʿ��Ǥ�ʤ����������Ū�ʡʤȤ����������¤ˤʤ������ʤǤ���Ȥ������ȤǤ��롣����ϡ������Ʋ���ȿ����դ���줿dz��Ω�Ļ���ˤ�äƺ�����ʬ�Ǥ���롣�����Ƥ��줾��������ϡ�����������ۤΤ褦�˵����⤦�ҤȤĤ�ŷ�Ρ��ˤ�äƾ�ħ����롣����Ϥޤ��ˡ������ν�������оΤ������פ��Τ�ΤǤ��롣
����Ф���ǤϤʤ����ַ�β��פˤ��뱦��α��������顢�����ۤβ��פˤ��뺸��ζ�ʤؤȼعԤ��ʤ���ʹԤ�������Ǥϡ��ͤ�����ή����Ƥ���οޤʤΤǤ��롣�����ơ���ƻ�θ�������������Ƥ��벫��������˼¤餻���Ȫ�γ��ءפϡ��������麸�����ؤȶ�Ť��˽��äƤޤ�ǥ���դΤ褦���������ʤꡢ�ּ��ϡפ��ᤤ���Ȥ�𤲤Ƥ��롣���줬��ñ�ˡ���ʡפˤۤ��ʤ餺���ۼ�ϿŪ�ʤ�ΤǤʤ��Ȱ���ï�������褦��
�� ���ΤȤ��ơʤ��뤤�ϡֿ��ò��Ρפؤ�Ω����
����Υ��å�Ÿ�ϡ�Ÿ�����ʤο��ǽ��˼�Ͽ����Ƥ��륨�ե���ȡ��ե������ƥ�Ȥˤ����ʸ����Ƭ�Ǥ��ǤäƤ���褦�ˡ��֥��åۤ˴ؤ�����áפεҴѲ������ޤ��ޤʸ���ˤ�äƿʹԤ���*���Ȥ��������������ȿ�Ǥ�����ΤǤ��ä��ΤǤϤʤ��������줬������Ρ֥��å�Ÿ�פ���ħ�Ȥ���������ΤǤϤʤ������������ɤ���������äƤ���ΤǤϤʤ������åۿ��äȤϡ������ƥ�Ȥˤ��Сֶ���ݽѤ��Ҳ��ɾ�������뤿��ζ�Ʈ����Ǥ����줿���ԡסּҲ�ˤ�äƼ���������줿�����ԡפȤ���ŷ�Ͳ�ȤΥ�����Ǥ��롣���ä�����ͳ��аޡʤ������ġˤ⡢�����δ֤ˤ��������ޤ��ޤ�������������������ν��ԤΥ�����Ȥ����Τ������������¤���Թ��ʲ�ȡʽ��ԡˤ˼�ʬ���Ȥ�Ť͡��ե����åۤ�̾��ڤ�ʤ��顢���ְ��̤ν��������Ф��Ƥ����¤���ܤ��֤Ĥ����ʥ����ƥ�ȡˡפ餷������ȡ��Τ褦�ˡ������Ϻ�Ȥ��Ф���ɾ�������ˤ���Τ���ʬ�Ǥ⤢��Τ��Ȥ����顢��Ϥ���Τޤ����̤��������뤳�ȤϤǤ��ʤ��������ʤ��Ȥ⡢���Ρָ�ŵŪ���å����פǥ��åۤ��Τ�˻������Ȥ���Τϡ���Ϥ꽽ʬ�ǤϤʤ��ȹͤ���Τ���
* �ֺ����Ǥϡ��ե���Ȥκ��ʤ����ĤɤΤ褦�����졢���̾�����ۤ��夲��³�����뤿��˰�²�������ʤ����Ϥ�ʧ�ä�����ޤ�ơ���������Ȼ���ɾ���η��������Τˤ��ɤ�����Ǥ���ס�Ʊ�����ƥ�ȡˤȤ����Τ���
���ʤ�������äȤȤ�ˤ����Ȥθ��Ƥ�ʬ�μ������줿�����Ǽ�������Ƥ�����֤��⡢���ä����Τ���ơ��ƤӺ��ʤȳƼ��������礦�Ȥ������֤��������ڤ��˷����Ǥ���Ȼ�ˤϻפ��뤫�顣��ϡ���Ȥؤθ��ۤ��Ӽ��ʡȸ��ǡɤȸ��äƤ��ޤäƤ��ɤ��ˤˤ�äơ����ʤ��ܤ��Ѥ�뤯�餤�ʤ顢��������λ����ä��櫓�������ե����åۤκ��ʤ����ָ��ۤ��Ӽ��פˤ�äƤ��μ����Τ���ñ�˼����Ƥ��ޤä���ֺ�ɾ���פ���Ƥ��ޤ��ۤ��ȼ�ʤ�ΤȤ�פ��ʤ����Ĥͤˡ����Ƥ���˽а��ä��褦���ܤǡ�����켫�Ȥ����٤Ǥ���ʤȡֽа����Ф褤���ȡפ��ȿ����Ƥ��롣
�����Υ饤���ǥԥ��Τξ�����֤������ۤˡ��������ơ�Ω����ä�����Ǥ��뤬�����Ϥηٻ��𤫤��Ϣ���Ǻ��ۤ��������줿�����Τ���롣�ФƤ����ΤǤ��롣��������Ω����ä�������ʬ���ǻ�ΤȤ����ˤ���äƤ�������������ͤ˽����ơ�������ФƤ�����꤬������ë�ǤϤʤ����䤬�Ԥä����Ȥ�ʤ�˿�꤫��Ǥ��롣�¤����ʡ��ż֤ȥХ�����Ѥ��ǡֱ����פηٻ���˽и�����������ˤ��Ƥ⡢���Ǥ���뤷�Ƹ�������ʤ��ʤäƤ����ԤΥ���å��奫���ɤ�顢��Ϥ���¤��ڤ�ƻȤ��ʤ��ʤä���ž�ȵ���顢�������Υ������ब���ΤޤޤˤʤäƽФƤ����ΤǤ��롣�������������Ͼ�����ޤ�Ƥ��줤���äѤ���Ǥ��Ф��줿���֤Ǥ��ä������ۤ��Τ�Τ���äƤ����Τ��ɤ��ä�����������������Ū�˺��ۤ��椫����ʤ��ʤ��ʤäƤ��������Թ���ι����פȿͤ���ϸ���줿�������������������������ޤǡ������ɤ�����Τ�ʤ��ͤλ����鲿��餬�Ĥ��Ƥ��뤷�������������ä���ʤ���
ݵƫ�������ȵ�ʬ��ž�����٤����ض�����결�����ä��ʤ��夯�ȡ����åۤ�ʣ���褬�ܤ����ˤ��롣������ľ���ơ��ݶ��ι�Ω�������Ѵۤإ��å�Ÿ��Ѥˤ������Ȥˡ������ߤäƤ������Ȥ˲ä��ơ�ʿ���פǤ��ä����ᤫ��5/3�˽����褿��������������Ǥ��ʤ��ä��ΤϹ������Ȥꤢ��������ƻ�ޤǰ���ۤɤι���Ȥ��Ϥʤ��ä���������äƤߤ�ȳΤ��ˤʤ��ʤ��ʤޤʤ����ͤ�Ƭ�ǴѤŤ餤�Ȥ����Ϥ��ä��������饤�餷�����Ѥ����ʤ��ۤɤǤϤʤ����ޤ������ޤ���Υ�ǴѤ����ʤ����⤢�äơ���Υæ�����ꡢ��֤ζ����Ƥ���Ȥ�����Ŭ���˰�ư���ʤ���IJ��˴վޤ��뤳�Ȥ��ǽ���ä��Τǡ����οͤο��������ޤ굤�ˤʤ�ۤɤǤϤʤ��ä���������ͤϾ��ʤ��ˤ��������ȤϤʤ�������⤽�������ΤҤȤ��������ʿ����äƤ�������ʤ���
���åۤθ���Ȥ����ΤϺ��ޤǤ��ñ�ʡפǤ��������Υߥ塼������ξ���Ÿ���Ȥ��Ǥ����Ĥ���Ѥ����ȤϤ��ä���������ۤɤΤޤȤޤä����ǡ�������Ŭ�٤�Ĵ�����줿���β��ǴѤ��ΤϽ��ƤǤ��롣�ޤ���Ʊ����β�Ȥˤ����ʤȤ�ʻ��Ÿ���⤢�äƤ�����������٤���Τϡ���Τ褦�����Ѥ˴ؤ��ƥ������ȤˤȤäƤϡ����������ʤ��Ȥ�¬������ؽ����뤳�Ȥ��Ǥ���ͭ���ΤǤ��롣
�褯��¸�Τ����ʤ�ȿ���⤢�뤫�⤷��ʤ���������ˤ��Ƥ⡢���åۤβ������ޤä�����ǡ�Ȥ��������ѰۤΤ褦�����˽и������Ȥ������ϡ�������Ʊ����κ�ȤΤ��ޤ��ޤʼ�ˡ���㤨�������ʤɡˤ�ʬ�ʤ�˻���������줿�ꡢ���������ꡢ�Ϥ��ޤ��ߥ졼�ʤɤΡָ�ŵ�פ�Ǯ�����ϼ̤�Ԥä��ꡢ�Ȥ�����Ժ����β̤Ƥ���ã������Τ����Ȥ����������������ޤ������̤Τʤ������<<����>
����ˤ��Ƥ⡢�����ζ�Ρ־Ȥ�פȵ����褦�ʿ��α�䤫���ϡ��ȤƤ�ɴ��ǯ���θ�ŵ�����褦�ʴ����Ϥ��ʤ�����Ϥޤ����γ��ζ�Ρ��Ĥ����������줿�褦�˸����뤽�ο������ˡ����褫�餷�����������ʤ���ư��Ф���������ϡ��ǽ���õ����Ƥ����������Ȥ���
�� ���� �� ��������� (1884)
���̤�����̤��Ʋ���θ���������������Ƥ��ơ��ո�����ǿ�ʪ�뿦�ͤδ���سԤ�夬�����ȿ�ͤ��Ʋ���˵����Ƥ��롣����ϡ�1889ǯ����Ϥޤ륵����ߤ�dz����褦�ʰ�Ϣ�κ��ʷ�����Ω�Ĥ��ȣ�ǯ���κ��ʤ���������˵����֤�����������פθ���˨�꤬����褦�˻פä���
�� �쥹�ȥ������� (1887)
ʻ��Ÿ���Υ��˥�å����她�Ȥ��ä������β�Ȥ������ɵᤷ���Τ�Ʊ�ͤκ�����ǻ���˸�������ʡ��ʤ�ȸ��äƤ�쥹�ȥ����ɤˤ������Ƥ���ե����åۼ��Ȥγ��Ȥ����Τ���Ʊ���������결�Ǹ����褦�ˡ��������⸽�ߥ��åۤ�ʣ���褬���������Τ褦�˥쥹�ȥ������Ź���ɤ˳ݤ����Ƥ���Τ��¸����뤫�Τ褦�ʺ��ʡ�Aquikhonne۩���ˤǡ��ڤ��������뤤�쥹�ȥ������������ʤϡ��ºݤΥ��åۤο�����פ��ˡ������äƤ�뤻�ʤ��������ˤ������ΤǤ��롣���åۤΰ����Ϥ����餯�༫�Ȥε�ǰ��ȿ�Ǥ��Ƥ��롣
�� �ݽѲȤȤ��Ƥμ����� (1888)
��˥ѥ�åȤ���ļ�����������ˤ��ȡ����Υѥ�åȾ�Ρֳ��ζ����̤礹�뤳�Ȥʤ��Ѥ���줿���פ�Ĥ��Ƥ���ΤǤ��ꡢ����ϤĤޤ���ݼ���俷���ݼ���αƶ���ʪ��äƤ���餷���������դ�ϡ��ɤ�������ݥå��ᥤ���ʤ��ȤʤΤ��Ϥ褯�狼��ʤ������������뤳�Ȥʤ����ζ�Ÿ������Ƥ��뤳�ȤϳΤ��˥����Х��夫���Ǥ��롣�������䤬���ݿ����������ΤϤ��������ƥ��˥å��Τ��ȤǤϤʤ��ơ��ե����åۼ��Ȥ������äƤ��롢�ܥ���ΤҤȤĤ����դ����ޥ�ȤΤ褦�ʰ����Ǥ��ä������줬�¤ˡ�Ʊǯ�������줿<<��Υ��ե��ƥ饹>
�� ��Υ��ե��ƥ饹 (1888)
����Ρ֥��å�Ÿ�פΥݥ������ˤ�ʤä�������Ÿ������̤ܶΤҤȤġ����γ��Ƥ����ҤȤĤ��������Ŀ�Ū�ʤ��ȤȤϡ�����Ϻ�Ρ�ݦݨ�פμ��Τ�����Ǥ��롣����ä�Ĺ���ʤ뤬���Τޤް��Ѥ��롣
�֤������Ϥ����Ťʤ��ᡢŹƬ��������줿���Ĥ���������屫�Τ褦����Ӥ������밼।ϡ����Ϥβ��Ԥˤ�å���뤳�Ȥʤ����ۤ����ޤޤˤ�������į��Ȥ餷�Ф���Ƥ���Τ��������������Ĺ���������꤭������ػɤ�����Ǥ�������Ω�äơ��ޤ����ˤ���ﭲ����ξ˻��������į����β�ʪŹ��į��ۤɡ����λ��ɤ��λ���餻����Τϻ�Į����Ǥ���ä���
����������Ϥ��Ĥˤʤ�����Ź����ʪ�����Ȥ����ΤϤ���Ź�ˤ�������ݦݨ���ФƤ����Τ�����
�Ǹ����Ƥ��ɤ������ե����åۤ�������Τȳ���Ϻ��������Τϡ��ۤȤ��Ʊ���Τ��������ƴ�Ϻ��̥����ݦݨ�ε��������������屫�Τ褦����Ӥ������밼ॡס����ŵ夬��Ĺ���������꤭������ؼͤ�����Ǥ���פ���Ȥϡ����åۤ�����³�����ֲ���פ�¾�ʤ�ʤ��������ϡ����ο���̥�����롣
�� ������ߤ����ܱ����� (1889)
���ޤ������˹Ԥ��Ϥ��Ƥ��ʤ��褦�ʻ��������Фꡢ�֤�Ĥ����ڡ����դΤҤȤĤҤȤĤ���̿��©���ȯ�����Ƥ��ơ��ۤȤ�ɡ֤䤫�ޤ����פФ���Ǥ��롣�٥����������줽���ʤۤɤμ�����ιԤ��Ϥ��Ƥ��ʤ����Τ褦�������Τ����Ǥ������������Τ��ϤޤäƤ��ꡢ��֤䤬�Ƶ����ηʿ��פȲ����Ƥ��ޤ��椬�ȼ��դ��ԱĽ������Ҽ��դ����ͽ���Ϥ������פ��Ф����롣���åۤ϶����������ζ��֤ǡ���������©������Ф��Ƥ����Τ���
�� ��������θ�����ƻ (1890)
����ˤ��Сʤ��뤤�ϥ��åۼ��Ȥε��Ҥˤ��Сˡ��������ʤǤ��뤽�������������Τ���ϡ�������Ƥ������α���ˤ���ֻ�����פ��餫�������ƿ�¬�Ǥ����Τ������������줬��ʤǤ�����ʲʤ���Фʤ�ʤ���ͳ����ˤ�ʬ����ʤ�����äݤ�ƻ�⡢������Ԥ��͡��λѤ⡢���줬���ƻ�Ǥ���Ȥ����ʤ�ξڤˤ�ʤäƤ��ʤ��ʻ�ˤϡˡ�������Ǥ���С�ƻ��ۤɤ����뤵�ǾȤ餹�ַ�������פǤ���Ϥ����ʤ�����̾����Ǥ�������פ⡢���ε����ϡ���ĥ����Ƥ���Ȥϸ������ޤ�����ۤΤ褦�����������������ʸ���ȯ���Ƥ���褦�˸����뤽��ŷ�Τϡ����餫�ˡ����ۡפ�ռ�������Τ������Τ��Ȥ���Ϥ��ʻ���μ��ι𤲤�Ȥ����ϡ����γ���������Ƥ����Τ�����ʤǤ���֤ηʿ��Ǥ�ʤ����������Ū�ʡʤȤ����������¤ˤʤ������ʤǤ���Ȥ������ȤǤ��롣����ϡ������Ʋ���ȿ����դ���줿dz��Ω�Ļ���ˤ�äƺ�����ʬ�Ǥ���롣�����Ƥ��줾��������ϡ�����������ۤΤ褦�˵����⤦�ҤȤĤ�ŷ�Ρ��ˤ�äƾ�ħ����롣����Ϥޤ��ˡ������ν�������оΤ������פ��Τ�ΤǤ��롣
����Ф���ǤϤʤ����ַ�β��פˤ��뱦��α��������顢�����ۤβ��פˤ��뺸��ζ�ʤؤȼعԤ��ʤ���ʹԤ�������Ǥϡ��ͤ�����ή����Ƥ���οޤʤΤǤ��롣�����ơ���ƻ�θ�������������Ƥ��벫��������˼¤餻���Ȫ�γ��ءפϡ��������麸�����ؤȶ�Ť��˽��äƤޤ�ǥ���դΤ褦���������ʤꡢ�ּ��ϡפ��ᤤ���Ȥ�𤲤Ƥ��롣���줬��ñ�ˡ���ʡפˤۤ��ʤ餺���ۼ�ϿŪ�ʤ�ΤǤʤ��Ȱ���ï�������褦��
�� ���ΤȤ��ơʤ��뤤�ϡֿ��ò��Ρפؤ�Ω����
����Υ��å�Ÿ�ϡ�Ÿ�����ʤο��ǽ��˼�Ͽ����Ƥ��륨�ե���ȡ��ե������ƥ�Ȥˤ����ʸ����Ƭ�Ǥ��ǤäƤ���褦�ˡ��֥��åۤ˴ؤ�����áפεҴѲ������ޤ��ޤʸ���ˤ�äƿʹԤ���*���Ȥ��������������ȿ�Ǥ�����ΤǤ��ä��ΤǤϤʤ��������줬������Ρ֥��å�Ÿ�פ���ħ�Ȥ���������ΤǤϤʤ������������ɤ���������äƤ���ΤǤϤʤ������åۿ��äȤϡ������ƥ�Ȥˤ��Сֶ���ݽѤ��Ҳ��ɾ�������뤿��ζ�Ʈ����Ǥ����줿���ԡסּҲ�ˤ�äƼ���������줿�����ԡפȤ���ŷ�Ͳ�ȤΥ�����Ǥ��롣���ä�����ͳ��аޡʤ������ġˤ⡢�����δ֤ˤ��������ޤ��ޤ�������������������ν��ԤΥ�����Ȥ����Τ������������¤���Թ��ʲ�ȡʽ��ԡˤ˼�ʬ���Ȥ�Ť͡��ե����åۤ�̾��ڤ�ʤ��顢���ְ��̤ν��������Ф��Ƥ����¤���ܤ��֤Ĥ����ʥ����ƥ�ȡˡפ餷������ȡ��Τ褦�ˡ������Ϻ�Ȥ��Ф���ɾ�������ˤ���Τ���ʬ�Ǥ⤢��Τ��Ȥ����顢��Ϥ���Τޤ����̤��������뤳�ȤϤǤ��ʤ��������ʤ��Ȥ⡢���Ρָ�ŵŪ���å����פǥ��åۤ��Τ�˻������Ȥ���Τϡ���Ϥ꽽ʬ�ǤϤʤ��ȹͤ���Τ���
* �ֺ����Ǥϡ��ե���Ȥκ��ʤ����ĤɤΤ褦�����졢���̾�����ۤ��夲��³�����뤿��˰�²�������ʤ����Ϥ�ʧ�ä�����ޤ�ơ���������Ȼ���ɾ���η��������Τˤ��ɤ�����Ǥ���ס�Ʊ�����ƥ�ȡˤȤ����Τ���
���ʤ�������äȤȤ�ˤ����Ȥθ��Ƥ�ʬ�μ������줿�����Ǽ�������Ƥ�����֤��⡢���ä����Τ���ơ��ƤӺ��ʤȳƼ��������礦�Ȥ������֤��������ڤ��˷����Ǥ���Ȼ�ˤϻפ��뤫�顣��ϡ���Ȥؤθ��ۤ��Ӽ��ʡȸ��ǡɤȸ��äƤ��ޤäƤ��ɤ��ˤˤ�äơ����ʤ��ܤ��Ѥ�뤯�餤�ʤ顢��������λ����ä��櫓�������ե����åۤκ��ʤ����ָ��ۤ��Ӽ��פˤ�äƤ��μ����Τ���ñ�˼����Ƥ��ޤä���ֺ�ɾ���פ���Ƥ��ޤ��ۤ��ȼ�ʤ�ΤȤ�פ��ʤ����Ĥͤˡ����Ƥ���˽а��ä��褦���ܤǡ�����켫�Ȥ����٤Ǥ���ʤȡֽа����Ф褤���ȡפ��ȿ����Ƥ��롣
23:59:00 -
entee -
TrackBacks
2005-04-15
���ܤΡ�̱�٤ι⤵�פ˴��ա�
�ٹ�ˤ��ȿ����ư��ؤ��ơ��֤�Ϥ�̱�٤��㤤���ڤʹ���פȤ���ȯ�������ä����֤�äѤ�ʤ�����������¾��Υͥ��Ǽ����ͥ�ۤ��Ƥ��ޤ��ҤȤ����ܤˤϤޤ��ޤ����äѤ������������ʤ��פȴ������¤˻�ǰ��
�ɤ����ͳ�Ǥ���ˤ��衢�¤ϡ����������ͤ��������������θ��ݤ������ξ�Ǥ˹����Τ�ʤ��뤤��̱²���Τ�˱���Ū��Ƚ�Ǥ��ƺѤޤ��뤪��ڤʻ�ˡ��ŵ���Ǥ��롣�������������ϡ������餯�����ȿ����ư���ʤ��Ƥ⡢���⤽�⤽���ٹ���Ф��ƴ�������Υͥ�������Ȥ�����Τ���äƤ��ơ����줬�դ�����褦�˻פä��Τǡ���ȿ����ư�פΤ褦�ʺ���Ū���ݤ�ʤ�Ǽ��夲�������ˡ��Ȥꤴ����ΤǤ��롣�����⡢�����ܤǤϡ�¾��ι����dz�䤷���ꡡ����������䡡�ե������Ź�⤷����פ��ʤ��Ȥ����褦����Ӥǡ������ٹ�˾��äƤ���ȤǤ�פ������Ǥ��롣
�����������ϡ����⤽��ɤ����Ƥ��Τ褦��ȿ����ư������Τ����Ȥ����褦����ˤ��ΤܤäƸ��ڤ���Ȥ����褦����Ū��Ȥˤϡ���Ȥ��̵�ؿ��ʤΤǤ����������������������Ϥ��ȼ�ʬ�θ�������˻��äƤ���������Ū�ּ��ֻ˴ѡ����Τ�Τκ������뤫��Ǥ��롣
����������٥�Ǥ�¾��Ȥ���Ӥ伫��ͥ�۴��������������ϡ��ɤ�������ܿͤϡ�̱�٤��⤤�פȤ����פäƤ�ä����Τ������������ܿͤΡ�̱�١פ���䡢���μ��֤��Τ���ܤ�ʤ�������ʤ�ۤɡ֤����Ǥ����פ�ΤǤ��롣�Ȥ�����ꡢ���Ρ��������줿�⤤̱�١פ�����������ؤΡ��Ӥη���פΤ褦��Ⱦ����ǯ�ʾ�˵ڤ��䤨�֤ʤ���°�ȡֿ�̱��Ū����ۡפ��ǽ�ˤ��Ƥ����Τ��ʤ����⤽�������ۼԤ˵��դ������������ˡˡ������ơ���̱²�δ����ʤɡ�ɬ�פ����äƤ�����夲����������������Ƥ褷�Ȥ������Ū�ʽ����ؤ����Ťϡ��к�Ū�ʤ��ȤΤߤʤ餺�����줫��Ͽ�̿�ˤ�äƤ��ʧ���롢��������������ܤϤʤäƤ����ΤǤ���ʤ��ΤޤޤǤϳμ¤ˡˡ����������������Ʒ��ؤ��֤��⤤���ͽ�����ǻ�ʧ���Ƥ��뤢�ζ�ۤϰ��β����������������Τʤ��֥��饯����פ˹�����Τ褦�˿ʤ�Dz�ô�����������ܤ����ƻ���ϰ��Τɤ�������̱�١פʤΤ����������Ʒ�ˡ��̵�뤷�ơ�����Ū���Ҹ��פ��ȡ������줬���ܿͤΡ�̱�١פ����٤ʤΤ���
�к�Ū�ʤ��Ȥ�����ȤäƤ⡢���߿ʤ���ĤĤ��������Ȥ�̱�IJ��ʤ��ʤ�������ܹ�̱�ο���ǯ���Ϥä����������Ƥ���Ϸ��Τ����ý���¶�ʤɤΥꥹ�����ˤˤ�äơ�Ĺ��������ե���ɤˤ����㤤á���פɤ����Υ�������Ǥʤ�������ʤ��礭���ǡ�����褢���Ȥ����֤������ؤξ�Ǽ��Ȥʤ�Ǥ������������ֹ�ˡŪ�פʼ�³���ˤ�äơ��ˡ����Τ���ˡ��塹�Ⱦ������������кѺ�������̱�IJ�ô����ϡ�����ۤȤ�ƤФ줺�ˡˤ��Υץ�������ʤ�Ƥ���������������������ʬ�����κ������������ñ�˹�Ȥ˾����Ϥ��Ƥ��ޤ��褦�ʰռ����㤵���������ܤ�̱�٤ι⤵�פʤΤǤ��롣����ǤȤ���
�Ф��äơ��ƹ���ȴۤ��ꤲ�Ĥ��뤯�餤�Ρ�̱�٤��㤵�פˤ����Ϥष���������٤��ǤϤʤ��Τ������ʤ�Ƹ����ȡ��ޤ���˲��٤ˤҤȤ��äƤ���ߤ�������������ʤ��Ȥ�Ƭ����������������ʤ�ۤɡ����ܿͤι����������Ф���̵�ؿ��������ơֽ���פ����椬��̱�٤ι⤵�פ�٤��Ƥ���ΤǤ��롣Fuck our mindo!
[Read More!]
�ɤ����ͳ�Ǥ���ˤ��衢�¤ϡ����������ͤ��������������θ��ݤ������ξ�Ǥ˹����Τ�ʤ��뤤��̱²���Τ�˱���Ū��Ƚ�Ǥ��ƺѤޤ��뤪��ڤʻ�ˡ��ŵ���Ǥ��롣�������������ϡ������餯�����ȿ����ư���ʤ��Ƥ⡢���⤽�⤽���ٹ���Ф��ƴ�������Υͥ�������Ȥ�����Τ���äƤ��ơ����줬�դ�����褦�˻פä��Τǡ���ȿ����ư�פΤ褦�ʺ���Ū���ݤ�ʤ�Ǽ��夲�������ˡ��Ȥꤴ����ΤǤ��롣�����⡢�����ܤǤϡ�¾��ι����dz�䤷���ꡡ����������䡡�ե������Ź�⤷����פ��ʤ��Ȥ����褦����Ӥǡ������ٹ�˾��äƤ���ȤǤ�פ������Ǥ��롣
�����������ϡ����⤽��ɤ����Ƥ��Τ褦��ȿ����ư������Τ����Ȥ����褦����ˤ��ΤܤäƸ��ڤ���Ȥ����褦����Ū��Ȥˤϡ���Ȥ��̵�ؿ��ʤΤǤ����������������������Ϥ��ȼ�ʬ�θ�������˻��äƤ���������Ū�ּ��ֻ˴ѡ����Τ�Τκ������뤫��Ǥ��롣
����������٥�Ǥ�¾��Ȥ���Ӥ伫��ͥ�۴��������������ϡ��ɤ�������ܿͤϡ�̱�٤��⤤�פȤ����פäƤ�ä����Τ������������ܿͤΡ�̱�١פ���䡢���μ��֤��Τ���ܤ�ʤ�������ʤ�ۤɡ֤����Ǥ����פ�ΤǤ��롣�Ȥ�����ꡢ���Ρ��������줿�⤤̱�١פ�����������ؤΡ��Ӥη���פΤ褦��Ⱦ����ǯ�ʾ�˵ڤ��䤨�֤ʤ���°�ȡֿ�̱��Ū����ۡפ��ǽ�ˤ��Ƥ����Τ��ʤ����⤽�������ۼԤ˵��դ������������ˡˡ������ơ���̱²�δ����ʤɡ�ɬ�פ����äƤ�����夲����������������Ƥ褷�Ȥ������Ū�ʽ����ؤ����Ťϡ��к�Ū�ʤ��ȤΤߤʤ餺�����줫��Ͽ�̿�ˤ�äƤ��ʧ���롢��������������ܤϤʤäƤ����ΤǤ���ʤ��ΤޤޤǤϳμ¤ˡˡ����������������Ʒ��ؤ��֤��⤤���ͽ�����ǻ�ʧ���Ƥ��뤢�ζ�ۤϰ��β����������������Τʤ��֥��饯����פ˹�����Τ褦�˿ʤ�Dz�ô�����������ܤ����ƻ���ϰ��Τɤ�������̱�١פʤΤ����������Ʒ�ˡ��̵�뤷�ơ�����Ū���Ҹ��פ��ȡ������줬���ܿͤΡ�̱�١פ����٤ʤΤ���
�к�Ū�ʤ��Ȥ�����ȤäƤ⡢���߿ʤ���ĤĤ��������Ȥ�̱�IJ��ʤ��ʤ�������ܹ�̱�ο���ǯ���Ϥä����������Ƥ���Ϸ��Τ����ý���¶�ʤɤΥꥹ�����ˤˤ�äơ�Ĺ��������ե���ɤˤ����㤤á���פɤ����Υ�������Ǥʤ�������ʤ��礭���ǡ�����褢���Ȥ����֤������ؤξ�Ǽ��Ȥʤ�Ǥ������������ֹ�ˡŪ�פʼ�³���ˤ�äơ��ˡ����Τ���ˡ��塹�Ⱦ������������кѺ�������̱�IJ�ô����ϡ�����ۤȤ�ƤФ줺�ˡˤ��Υץ�������ʤ�Ƥ���������������������ʬ�����κ������������ñ�˹�Ȥ˾����Ϥ��Ƥ��ޤ��褦�ʰռ����㤵���������ܤ�̱�٤ι⤵�פʤΤǤ��롣����ǤȤ���
�Ф��äơ��ƹ���ȴۤ��ꤲ�Ĥ��뤯�餤�Ρ�̱�٤��㤵�פˤ����Ϥष���������٤��ǤϤʤ��Τ������ʤ�Ƹ����ȡ��ޤ���˲��٤ˤҤȤ��äƤ���ߤ�������������ʤ��Ȥ�Ƭ����������������ʤ�ۤɡ����ܿͤι����������Ф���̵�ؿ��������ơֽ���פ����椬��̱�٤ι⤵�פ�٤��Ƥ���ΤǤ��롣Fuck our mindo!
[Read More!]
20:20:00 -
entee -
TrackBacks
2005-04-13
����������פ��Ф�����Ƚ���������ĤǤϤʤ�
��ȸ���ˤ��������һ��Ҥ��Ф�����Ƚ�ϡ����Τߤʤ餺���ܹ���⳰��ï�ˤ�ä�������Ƥ�ľФ����Ϥʤ���ΤǤ��롣�ष�����֤ʤ��פ��Τ褦����Ƚ���ʤ����Τ����Ȥ������Ū�аޤˤĤ��ơ����ܹ���Ǥ��μ���ǧ�����ʤ���롣���������ϡ����ܤν�����������ʬ��������ʬΥ�θ�§��ȿ�����ˡ��ȿ�Ǥ���Ȥ�������������ޤब�������Ȥꤢ����ê�夲���Ƥ⡢���⤽����������������ǤϤʤ����ޤ������ܤγ����������Τ�ΤΤ⤿�餷����̤ȸ��ä��ɤ����褽�ι�κ��꤬��Ƚ����Ȥ������Ȥ���������Ĥ��פȸƤ֤Τϡ����ܤ������䤽�μ�괬������Ƚ�魯����˺ΤäƤ������ɽ���Ǥ��äơ����������Τ褦�ʰ��̿ͤ�̵ȿ�ʤ˷����֤����Ȥϡ�ñ�ʤ����ܤ����ۼԤˤʤäƤ���˲������ʬ�ǹͤ�����Ĵ�٤��ꤷ�Ƥ�Τ���äƤ������٤���Ϥۤɱ�
���⤽�⡢�ɤ��������ܤ������Ȥˤ�������Ҥ��Ф�����Ƚ������Τ����Ȥ������ȤˤĤ��ơ������Ϥɤ����ʬ���äƤ���Τ���������
1978ǯ������֤����뤵�줿������ʿ��ͧ������פȤ����Τ����뤬�����κݡ��������ܤؤ�������Ḣ���������������塢�����ܤ�������Ǥ���������Ȥ��濴�Ȥ�������ο͡��ˤ��ꡢ���ܹ�̱��¿���ϵ����ԤǤ��ä����ȡ��������ͤβ��뤳�Ȥ�����Ǥ���Ƥ���ΤǤ��롣����츽������������ܿͤ��������������ܹ�̱��¿���ϵ����Ԥ˲�ʤ��ä��פȤ����ͤ����Τޤޱ��ݤߤˤ��٤����ɤ����ϡ��ޤ��̤β���Ǥ��뤬���Ȥˤ�������������������������ܤϡ���β���ʤơ���������Ū�ˤ�¿���ε����Ԥ䤽�ΰ�²������������̱��Ǽ���������ۤ餻�ˡ�����Ū�ˤϰ����βó������ܤȤΡ���������̤��ָ��פδط����֤��Ȥ�������Τ���
������ˡ����������ΰ����Ǥ������ܤˤ����ƤϤɤ�������ñ�ʤ��ĿͤȤ��Ƥʤ�ޤ����⡢��ȸ�����꤬�����ͤȤ��ƣ������Ȥ�פäƤ������ܤ�����������ħ���롢����������ҡʻ�Ū����ˡ�ͤǤ���ˤ˻��Ҥ���Ȥ������Ȥϡ���ͤ�Ƚ�Ǥ�����������ܤ����ť���ɤ��Ȥ������ȤʤΤ��������������ܤ������¤��Ф�����ܤ�Ȥ����Τϡ���˿������ʤ��ȤǤ��롣�Ĥޤꡢ�������꤬ñ�ʤ����ܤ�����������Ǥ���Ȥ����Τϡ�������ǧ�����Ǥ��äơ��ޤä�����ä����ܤγ���������ΰ���������٤Τʤ��˵������٤�����ʤΤǤ��롣
���ȡ���������ˡ���˴ѡɤϤ���Τ������ǥ�¥���Ρ�������˽���ס�
�����ϡ���̱�ϻ��۲����ް����줿�и����ʤ����������⤷������Ω�줬�����դǡ�˽��Ū�����ް�Ū�ʿ�̱�ϻ��ۤ�Ƥ����Ȥ�����ɤ��������������⤽�λ��۹����Ʈ���¿����Ʊ˦�η��ή������������Ω����ä���⡢���ο�̱�������βó���Ǥ���������������餱����Ǥ�̤���ˤ��βó���Ǥ�ˤĤ���̵���ФǤ���Ф��꤫��������Ǥ�Ԥ��ֿ��פȤʤäƺפ��Ƥ���Ȥ����ˡ����ޤ��˸����θ��������... �����������Ȥ��������Ȥ�����ɤ��������������������٤������ܤˤϡ������¤Ǥ���ȿ�ʤ��Ƥ��ʤ��פȱǤ�Ǥ��������Ȥ��������ʤ����ޤ��Ƥ䡢ͧ���ط���Ω�ˤ����äơ�����줬�������äƤ������������겼��������ˡ������ο�̱����������Ǥ�Ԥ�ɤ��Τϡֺ�����ڻߤ���פȵ���Τ������Ǥ����������������Ω���Ω�äƹͤ����뤫���Ȥ����ޤ��������Ϥ�����ʤΤǤ��롣
�ä��ơ�������Ҥϡ��Ǥ���ñ�ʤ����Ԥ���ä������ι�Ω�������������ǤϤʤ����⤷����������ΤǤ���ʤ顢���ܿ͡�����͡���������ͤ���鷺�����뤤�϶����ˤ�뤫��Ʈ�ˤ�뤫����鷺�����褬�����ǻ���������͡������֤���ΤǤʤ��ƤϤʤ�ʤ���������������ҤϤ���������ΤǤϤʤ�������ο��Ĥ���ɽ�����Ū�콡�����ΤDz�ʤ��Ф���Ǥʤ���������ܤ�����������������Ϥˤ���ष�����ͤ������Ȥ��ƺפ�夲����ǡ����ܤ�������Ǥ�ʤɤϤʤ����ʤɤ�̤������ʤ����֡ˤ��Ƥ��������ʤΤǤ��롣�����ơ��������ȤȤ��ƺۤ��줿������Ǥ�Ԥ�������¾�ΰ�ʼ´�Ȥ���Ʈ�äƻ���ʼ��ȶ��˹�㫤���Ƥ���ΤǤ��롣ɴ����äơ���Ū����ˡ�ͤ������ˤ����������ɤ�������Ԥ�褦�ȡ�����Ϥ���ˡ�ͤξ�������������˹�ȸ���ͤȤ��ƤǤϤʤ������ͤȤ��ƻ��Ҥ�Ȥ������Ȥϡ���������ˤʤä������ʤΤǤ��롣
���γ����������Ϥ�Ƥ���Ȥ������Ȥˤϡ�������פ�ֶ��ʽ�����פ����Ǥʤ�����������������Ū�طʤ�ư�����������������������ˤ��餹�Ȥ����տޤ��ʤ��Ȥϸ�������ʤ���������������ܼ��Ϥ����ǤϤʤ������Τ褦�������ġ���Ȥ��Ƴ�����ư�����Ѥ���Ƥ���Ȥ��Ƥ⡢ȯü�Ȥʤ���ޤ����Τ�¾�Ǥ�ʤ����ܤʤΤǤ��롣�������äơ����塢���ܤ��б�������ˤ�äƤϤ�äȷ㲽���Ƥ⤪�������Ϥʤ������Ǥ��롣�����餯�����ܤ�������Τ�����������ޤǤ�����٤Ǥ⤳��������ĩȯ�פȤ�Ȥ���ư�˽ФƤ��ԻĤϤʤ�����������Ǥ���ʾ塢�������ܼ�Ƴ�ˤ�뱢�Ť������ä��ä��ԻĤϤʤ�������������ϡ����ߤ��ͤǤ��롣
������������ɤ����Ƥ��뤫���Ȥ������ȤǤϤʤ������ܤ�����ޤ������Ф������뤤�Ϥ���¾�ο�̱�ϻ��ۤ��������ν�����Ф��ɤ���������¤Ǥ��ä����Ȥ������Ȥ������⤽��κ��ܸ����Ǥ���Ȥ������Ȥ�������������Ф���ɬ�פ����롣¾��λĹ�ʿ�̱����������ʤ�Ȥ�ƨ�줿�ᄀ��ʤ顢�������äƤ���������Ḣ����Ū����������������ܤ�������ˤ�ä�ͧ���ط����ۤ����Ȥ������顢�ʤ�����������Ǽ���Ǥ�����������ԤǤ��ʤ��Ф��꤫��̤����������Ǥ�ԤȤ��ƺۤ��줿���λ�Ƴ�Ԥ����Ҥ��Ƥ���Ȥʤ�С��Ǹ�ϡ֤�Ϥ伫��̱���ۤ餻�Ƥ���ɬ�פ��ʤ��פ�Ƚ�Ǥ����Ȥ��Ƥ��ԻĤϤʤ�������ϡ���餬�������Ǽ���Ǥ��Ƥ��ʤ������ܤäƤ����Ȥ�������������äƤ��Ƥ���Ȥ������ȤʤΤ����ܤäƤ���¦�μ�ĥ�˼�������ʬ�����˲����Ǥ���Τ���ͤ��뤳�Ȥ��������ٹ����鷺���ٿͤȤ��ƶ�¸���ƹԤ��������ΰ�̣�ǤΡ�̤��ָ��פǤ���Ϥ��ʤΤ���
������Ʊ�Ǥ������ǤϤʤ����ɡ��ޤ��������������������������ޤ��ޤ����Ȥ��⤦��Ǥ���͡�
���⤽�⡢�ɤ��������ܤ������Ȥˤ�������Ҥ��Ф�����Ƚ������Τ����Ȥ������ȤˤĤ��ơ������Ϥɤ����ʬ���äƤ���Τ���������
1978ǯ������֤����뤵�줿������ʿ��ͧ������פȤ����Τ����뤬�����κݡ��������ܤؤ�������Ḣ���������������塢�����ܤ�������Ǥ���������Ȥ��濴�Ȥ�������ο͡��ˤ��ꡢ���ܹ�̱��¿���ϵ����ԤǤ��ä����ȡ��������ͤβ��뤳�Ȥ�����Ǥ���Ƥ���ΤǤ��롣����츽������������ܿͤ��������������ܹ�̱��¿���ϵ����Ԥ˲�ʤ��ä��פȤ����ͤ����Τޤޱ��ݤߤˤ��٤����ɤ����ϡ��ޤ��̤β���Ǥ��뤬���Ȥˤ�������������������������ܤϡ���β���ʤơ���������Ū�ˤ�¿���ε����Ԥ䤽�ΰ�²������������̱��Ǽ���������ۤ餻�ˡ�����Ū�ˤϰ����βó������ܤȤΡ���������̤��ָ��פδط����֤��Ȥ�������Τ���
������ˡ����������ΰ����Ǥ������ܤˤ����ƤϤɤ�������ñ�ʤ��ĿͤȤ��Ƥʤ�ޤ����⡢��ȸ�����꤬�����ͤȤ��ƣ������Ȥ�פäƤ������ܤ�����������ħ���롢����������ҡʻ�Ū����ˡ�ͤǤ���ˤ˻��Ҥ���Ȥ������Ȥϡ���ͤ�Ƚ�Ǥ�����������ܤ����ť���ɤ��Ȥ������ȤʤΤ��������������ܤ������¤��Ф�����ܤ�Ȥ����Τϡ���˿������ʤ��ȤǤ��롣�Ĥޤꡢ�������꤬ñ�ʤ����ܤ�����������Ǥ���Ȥ����Τϡ�������ǧ�����Ǥ��äơ��ޤä�����ä����ܤγ���������ΰ���������٤Τʤ��˵������٤�����ʤΤǤ��롣
���ȡ���������ˡ���˴ѡɤϤ���Τ������ǥ�¥���Ρ�������˽���ס�
�����ϡ���̱�ϻ��۲����ް����줿�и����ʤ����������⤷������Ω�줬�����դǡ�˽��Ū�����ް�Ū�ʿ�̱�ϻ��ۤ�Ƥ����Ȥ�����ɤ��������������⤽�λ��۹����Ʈ���¿����Ʊ˦�η��ή������������Ω����ä���⡢���ο�̱�������βó���Ǥ���������������餱����Ǥ�̤���ˤ��βó���Ǥ�ˤĤ���̵���ФǤ���Ф��꤫��������Ǥ�Ԥ��ֿ��פȤʤäƺפ��Ƥ���Ȥ����ˡ����ޤ��˸����θ��������... �����������Ȥ��������Ȥ�����ɤ��������������������٤������ܤˤϡ������¤Ǥ���ȿ�ʤ��Ƥ��ʤ��פȱǤ�Ǥ��������Ȥ��������ʤ����ޤ��Ƥ䡢ͧ���ط���Ω�ˤ����äơ�����줬�������äƤ������������겼��������ˡ������ο�̱����������Ǥ�Ԥ�ɤ��Τϡֺ�����ڻߤ���פȵ���Τ������Ǥ����������������Ω���Ω�äƹͤ����뤫���Ȥ����ޤ��������Ϥ�����ʤΤǤ��롣
�ä��ơ�������Ҥϡ��Ǥ���ñ�ʤ����Ԥ���ä������ι�Ω�������������ǤϤʤ����⤷����������ΤǤ���ʤ顢���ܿ͡�����͡���������ͤ���鷺�����뤤�϶����ˤ�뤫��Ʈ�ˤ�뤫����鷺�����褬�����ǻ���������͡������֤���ΤǤʤ��ƤϤʤ�ʤ���������������ҤϤ���������ΤǤϤʤ�������ο��Ĥ���ɽ�����Ū�콡�����ΤDz�ʤ��Ф���Ǥʤ���������ܤ�����������������Ϥˤ���ष�����ͤ������Ȥ��ƺפ�夲����ǡ����ܤ�������Ǥ�ʤɤϤʤ����ʤɤ�̤������ʤ����֡ˤ��Ƥ��������ʤΤǤ��롣�����ơ��������ȤȤ��ƺۤ��줿������Ǥ�Ԥ�������¾�ΰ�ʼ´�Ȥ���Ʈ�äƻ���ʼ��ȶ��˹�㫤���Ƥ���ΤǤ��롣ɴ����äơ���Ū����ˡ�ͤ������ˤ����������ɤ�������Ԥ�褦�ȡ�����Ϥ���ˡ�ͤξ�������������˹�ȸ���ͤȤ��ƤǤϤʤ������ͤȤ��ƻ��Ҥ�Ȥ������Ȥϡ���������ˤʤä������ʤΤǤ��롣
���γ����������Ϥ�Ƥ���Ȥ������Ȥˤϡ�������פ�ֶ��ʽ�����פ����Ǥʤ�����������������Ū�طʤ�ư�����������������������ˤ��餹�Ȥ����տޤ��ʤ��Ȥϸ�������ʤ���������������ܼ��Ϥ����ǤϤʤ������Τ褦�������ġ���Ȥ��Ƴ�����ư�����Ѥ���Ƥ���Ȥ��Ƥ⡢ȯü�Ȥʤ���ޤ����Τ�¾�Ǥ�ʤ����ܤʤΤǤ��롣�������äơ����塢���ܤ��б�������ˤ�äƤϤ�äȷ㲽���Ƥ⤪�������Ϥʤ������Ǥ��롣�����餯�����ܤ�������Τ�����������ޤǤ�����٤Ǥ⤳��������ĩȯ�פȤ�Ȥ���ư�˽ФƤ��ԻĤϤʤ�����������Ǥ���ʾ塢�������ܼ�Ƴ�ˤ�뱢�Ť������ä��ä��ԻĤϤʤ�������������ϡ����ߤ��ͤǤ��롣
������������ɤ����Ƥ��뤫���Ȥ������ȤǤϤʤ������ܤ�����ޤ������Ф������뤤�Ϥ���¾�ο�̱�ϻ��ۤ��������ν�����Ф��ɤ���������¤Ǥ��ä����Ȥ������Ȥ������⤽��κ��ܸ����Ǥ���Ȥ������Ȥ�������������Ф���ɬ�פ����롣¾��λĹ�ʿ�̱����������ʤ�Ȥ�ƨ�줿�ᄀ��ʤ顢�������äƤ���������Ḣ����Ū����������������ܤ�������ˤ�ä�ͧ���ط����ۤ����Ȥ������顢�ʤ�����������Ǽ���Ǥ�����������ԤǤ��ʤ��Ф��꤫��̤����������Ǥ�ԤȤ��ƺۤ��줿���λ�Ƴ�Ԥ����Ҥ��Ƥ���Ȥʤ�С��Ǹ�ϡ֤�Ϥ伫��̱���ۤ餻�Ƥ���ɬ�פ��ʤ��פ�Ƚ�Ǥ����Ȥ��Ƥ��ԻĤϤʤ�������ϡ���餬�������Ǽ���Ǥ��Ƥ��ʤ������ܤäƤ����Ȥ�������������äƤ��Ƥ���Ȥ������ȤʤΤ����ܤäƤ���¦�μ�ĥ�˼�������ʬ�����˲����Ǥ���Τ���ͤ��뤳�Ȥ��������ٹ����鷺���ٿͤȤ��ƶ�¸���ƹԤ��������ΰ�̣�ǤΡ�̤��ָ��פǤ���Ϥ��ʤΤ���
������Ʊ�Ǥ������ǤϤʤ����ɡ��ޤ��������������������������ޤ��ޤ����Ȥ��⤦��Ǥ���͡�
23:27:11 -
entee -
TrackBacks
2005-03-15
�Dz�إѥå����٤�¤롧
�����ˤϤ⤦���Τ褦�ʵ���ʥ�����ʰ亨�ˤ��פ�ʤ�
�Dz�إѥå���� The Passion of the Christ�٤αDz�μ���������ؤ������Ϥ��Ϻ��Ϥη�ǡ�ϡ����ޤ�����餫�Ǥ��롣��롦���֥����ȥ�å��ο��ԤǤ���Ȥ�����ۤλ����ꤸ���Ȥ��������뤳�αDz�����ⲽ����¿�������������Ѥ������⤬���졢���ܤǤ⡢��줿���Ȥˡ����������Ū�ˤ��Ρ־�פ��������Ƥ��뤫�˸����뤬���������ڤ��ܺ��ʤ��ܼ����뤳�ȤȤ�̵�ط��Ǥ��롣
���αDz�Ͽʹ֤������Ϥο�������Ū���䤦�Ȥ�����Ū���������Ǥ���ȤǤ���������ʡ��������μ¡��͡��������Ϥη�ǡ�ˤष���Ĥ�������Dz�Ǥ���Ȥ��������롣�Dz褬���ʹ֥�����������Ū���ˡʤ����ˤ˥ե��������������Ȥϡ�ʡ����αDz貽�Ȥ������ĤƤ�¸�ߤ��������Ĥ��Υץ��������Ȥ���Ǥ⡢�Τ��˺��ޤǤˤʤ����ץ������Ǥ��뤳�Ȥ�ǧ��Ƥ��ɤ����������ʹ֥��������̲ᤷ������Ū���ˤα���Ū�ʺƸ��Ȥ��ζ�Ĵɽ���Ȥ�����Τ��̤���ã�����������פΥ�����Ȥϡ��ܤ���ᤷ�ߡ������ơ���������������������Υ��롼�פؤΰ亨�Ȥ����ͥ��ƥ��֤ʴ���ξ����Ǥ����ʤ������������η�̤Ȥ��Ƥʤ���뤳�ȤȤϡ��ֿͤȿͤ�ʬ�ġפȤ������ȤǤ��롣
�Τ��ˡ����Τ�Τˡ����������ͥ��ƥ��֤ʴ������Ф�¦�̤�����Ȥ������Ȥ������κݤ�����餫�ˤʤä��Ȥ�����̣�ǡ��̤�ɾ���������Τ��⤷��ʤ��ʤ���������ؤζ�ü��ȿ�����Dz���͡��ˤ�븽�������������ͤؤ�������ж�ʤȤ�������������ͽ¬��ǽ���ä��۾�ʻ��֤Ǥ���ˡ��������ܹƤϡ����Τ�ΤΡ����뤤�ϥ��ꥹ�ȶ����Τ�Τؤ���Ƚ����ܤȤ�����ΤǤϤʤ������Τ褦�ʹͻ����ưפˤ�����ɾ���ϰϤ�Ķ���롣*
��* �ޤ��Ƥ䥢������ꥹ�ȶ����ļԤǤ�ʤ��Ф��꤫�����ꥹ�ȶ��Τ⤿�餷����ħŪ�����Ρ�¸���Τޤ��˱���ˤ���켫�Ȥ�����ʾ塢���ν����ؤΰ¤äݤ���Ƚ�ϡ��¤ΤȤ��������ξ�ħŪ�ʽ�����Ρ�������˼���ߤ����ȤˤϤʤäƤ⡢����ɾ�Ǥ���ʾ�Ҵ�Ū�Ǥ���פȤ������Ȥˤ�����Ȥ��Ƥʤ餺�����ĤޤǷФäƤ⤽�αƶ�������ȴ���Ф����Ȥ�����ʤ��Ȥ����ѥ�ɥå����˴٤�ΤߤǤ��롣�����顢�����ǤϱDz���Ф�����ɾ�ˤ��μ�����ʤ뤳�Ȥˤ��롣��
��������������ˤߤ���¸�� -- �ʹ֤Ǥ���ʾ塢�ब�θ���������Ū���ˤȤ����Τϡ������������ޤǤ�ʤ������������ʡ������ɤߡ������λ��夫�鷫���֤�������Ƥ������ꥹ�Ȥμ��������������ʥ�����ˤ�С���ʬ������������ΤǤ���*���Dz貽���줿����å��ʱ������̤��ƽ��ƥ������˵��������Ȥ���Ȥ����ΤǤϡ��ޤ��Ͽ��ļԤȤ��Ƥ��ޤ�ˤ������Ȥ����ʳ��ˤʤ����������Dz�Ϥ�����������ͤ������Ϥη�ǡ�����¤����Ѥ��ơ��ष���������Ф���Ǯ���ʤФ�������ƤǤ���³�����뼫�ο��ļԤ��ưפ˴ְ�ä�������Ƴ����ΤǤ��롣
��* ���������ʹ֤Ǥ��롢�ȡʤȤꤢ���������ꤹ�뤳��ʸ�Ϥ������ο��ʤ⤷���Ϥ���˽ऺ��¸�ߡˤǤ���ȿ����뿮�ļԤ�¦���餹��С��лߤʤ�ΤǤ���ȼ�������ǽ�������뤬���֥��������ʹ֤ǤϤʤ��פȿ��������͡��˵դ˿֤������Τϡ��⤷�ʹ֤Ǥʤ��Ȥ����顢����θ������ˤߤ˰��Τɤ�ʰ�̣�����ä����Ȥˤʤ�Τ������� �ब������Ʊ�����Τ���ä��ʹ֤Ǥ��ä����餳�������Ρּ���פ˰�̣������ΤǤϤʤ�������������
�Dz�إѥå����٤ϡ���������Ρ�ʡ����Ρ����������륤����������Ū�ʼ������������Ǵ���12���֤���������Ū�˱�����������ΤǤ��롣�����ơ�����ȴ���Ф������Τ�Τ���ˡ�����Ԥζ���Ū�տޤ����롣�����ޤǤ�ʤ�����������Ȥ���ȴ���Ф��줿��ʬ����������Τ��٤ƤǤϤʤ������������������������Ū�˥ɥ���������Ȥˤ�äơ�����黲�Ȥ��뤳�Ȥ����ޤ��������ʤ��ˤ��¿���ΰ���Ū�ʡʼ��Ρ˥��ꥹ����⤷���ϼ㤤���ꥹ������������Ϳ����ƶ���̵�뤹�뤳�Ȥ�����ʤ��ۤ�����Ǥ���ȸ���ʤ���Фʤ�ʤ���
����ξܺ٤��ʬ�ʤ��Τ�Ԥ����䡢�������٤μ��Ф�ʤ��ɤ���Ԥ����ȤäƤϡ��Dz����Ⱦ��������������˽ФƤ��뤤���Ĥ��Υ��ԥ����ɤϡ����̶��ܤΥ�٥���ΤäƤ��뤳�ȤǤ����������Dz�ǽ����Τ�Ȥ����Τ˶ᤤ�ꥹ�ȶ����ΤۤȤ�ɤδվԡ������Ƥ����餯�ۤȤ������Ū��������ɤळ�ȤΤʤ�����¿���Υ��ꥹ�ȶ����δվԤˤȤäƤ��顢�����ʤ��ˤ��줬�ɤΤ褦�ʰ�̣����ä����ԥ����ɤǤ���Τ���ʬ����褦�ʱ��������ˤ�ʤäƤ��ʤ��ΤǤ��롣
�ʹ֤λĹȤ��������륤�������ˤߤȤ�������Ū������������ȤˤҤ����鷹�����Ƥ��뤳�αDz�ϡ�«�δ֡��ե�å���Хå�Ū���������ֲ��ν�����פȤ��ơ�����Ǹ��ڤ���뤤���Ĥ��ν��פʥ��ԥ����ɤ�����Ū�˸���������Ǥ��롣�����������������ΤäƤ���ͤˤ��Ҥä���ʤ������ɬ�פʤۤɡ��Դ��������Կ��ڤ�������Ƥ��롣�������������θ����ȡ��Ǵ���12���֤˵����뤤���Ĥ��Υ��ԥ����ɤΰ����������������٥١����å����μ��Ȥ���λ�Ƥ���վԤ����åȤ����ꤷ�Ƥ���Ȥ�ͤ�����ΤǤ��롣�ޤ�����ü��˽�ϥ������Ϣ³�Ǥ��뤳�αDz�ϡ��ĵԤ�˽�ϥ������ޤ�Dz���Ф��Ƥ�äѤ鸷�����쥤�ƥ���ܤ��罣��Ǥϡ���Ⱦ�λҶ����Ѥ뤳�Ȥ�����ʤ��ä����������Ȥ��������ʤ������Σ���������äƤ⡢�������μ���������λ�Ƥ���͡ʤ��Ȥʡˤ�����ʬ�������θ�����������θ������뤤�Ϻ�ȯ�����褦�Ȥ����Τ����վԤˤȤäơإѥå����٤�Ѥ�ư���Ǥ���褦�˻פ��롣�������⤷���줬�������Ȥ���С����Τ��Ȥϥ������˵���������Ū�ʼ��֤ɤ�ۤɤˤҤɤ���ΤǤ��ä��Τ��פȤ��������äʶ�̣���������̤θ��̤����ʤ����Ȥˤʤ롣ʬ����䤹�������С����αDz褫��ؤ٤뤳�ȤϤۤȤ�ɤʤ������ǥ������ޥ��ҥ������������Dz�ʤΤǤϤʤ����ȼٿ䤷�����ʤ�ۤ����٤��㤤��ΤʤΤǤ��롣
�������äơ��դˤ��αDz�ǽ�����������������äƤ���Ȥ����͡��ˤȤäơ����줬Ŭ�ڤʥ���ȥ����������ˤʤ����뤫�Ȥ������Ȥϡ���ʬ�˸�Ƥ����ʤ���Фʤ�ʤ���
���αDz��Ѥ����ȴѤ���ǡ������Ϥɤ���������ʤäƤ��뤫�����Τ��Ȥ��䤦ɬ�פ����롣���αDz�Ϥ����˲���������ů��Ū�ʻ���ü������Ƥ�����������������뤤�ϡ�����佡�����Ф��뤢�餿�ʻ����Ȥ�����Τ����Ƥ����������������������Ȥ����ֿ�ʪ�פλ��äƤ��뺬��Ū��̷��䡢�������Τ⤿�餹��å�������Υ��֥륹��������ɡ����ޤ��ޤʿʹֽ���Ǻ�ߡ������Ƥ䤬�ơֵ�����פ����äƤ������Ȥ��տ魯��ѥ�ɥå����������Χˡ�Ԥ䥤��������Ҥ����Υ��ߥ�˥ƥ���ȯ��������Ω�交��ͧ���ڤꡣ�������ä����ΰʳ��Ρּ���ס��ʹ������ˤ⤿�餵������αDz�������Ƥ�����������������뤤�ϥݥ�ƥ������ԥ�ȼ��Ȥ�Ω���������ն����Ϥ�����Ū�طʤ�������Ƥ���������������ޥ�����Υޥꥢ�����Τɤ���������̤������Τ����������������ڤ�������Ƥ��ʤ����Dz���о줹��͡���Ⱦʬ�����ܤ��¸��Ԥ˶줷�ߤ�Ϳ���뤳�Ȥ˴�Ӥ����Ĥ��Ⱦʬ�϶��夹��Ф���Ǥ��뤬�������Ǻ���Ƥ���Τ���ʬ����ʤ�����Ǻ���Ƥ���餷�����Ȥ�����ޥꥢ�δ���䤨�֤ʤ������ޤ���ˤ�ɽ����̤���ɽ�����������Ǥ��롣�����Ǥ�¨��Ū�ʶ�Ǻ��ɽ������뤬���ʹ֤Υɥ�ޤ�������뤳�ȤϤʤ���©�Ҥ��ˤ�Ĥ����ƶ�Ǻ���뤳�Ȥ������Τʤ顢����Ū�˸��ߤǤ������λ���ǵ����Ƥ���ΤǤ��ꡢ����������ޥꥢ�Ǥʤ��Ƥ⤤���Ϥ��ʤΤ���
�ʾ�Τ褦�������ʹ֥������μ��դ˸���뤢����̷����Ǻ�������Ʋ����⥤�������Ȥ��̲ᤷ�ʤ���Фʤ�ʤ��ä�����Ū�ʼ�������ơ������������Ƥ��դ�����������ޤ�Ƥ���Τ����˥��������������θ���˥ޡ��ƥ��������å��ˤ�äƴ��ġ��Dz貽���줿�غǸ��Ͷ�� The Last Temptation of Christ�٤Ǥ��롣
�͡������ǡ���The Last Temptation of Christ�٤ϡ���롦���֥���Ρ�Passion�٤�ο���Ǥ��롣�ۤȤ����Ӥ���Τ�Х��Х������ۤɤǤ��롣������ɥȥ�å��β��ڤ˴ؤ��Ƥ������äƤ⡢��ԤΤϡ����ԤΥ�����ɥȥ�å��ˤ����Ƽ¸����줿�����륢���ǥ����Ѥ��٤����Ѥ�ɾ���������ʤ�ۤɡ��֤����Ȥ����פǤ��롣�����ΤαDz�ˤ��Τ褦�ʲ��������Ƥ뤳�Ȥ�ͤ��Ĥ����Τϡ�Peter Gabriel�ζ��ӤʤΤǤ��롣
��롦���֥���۩�����ֻ��˾�ߤϡ������ͤ����뤳�ȤǤϤʤ������ꥹ�Ȥ��桹�κ����������̣��ä���������������ܤˤ������뤳�Ȥǡ��ͤο��ο����Ȥ����˱ƶ���������˾�������Ϥ��Υ�å��������Ϥ����뤳�Ȥ��סʸ��������Ȥ���ΰ��ѡˡ��츫��������Ǥ��ɿ�Ū�˲��Ǥ������ʥ����Ȥ�������ϼ�ʬ�θ��Ȥ����Ρ֥��ꥹ�Ȥ������κ����������̣��ä�������������פȤ�����ʤ�����������פ��뤳�Ȥǡ��ޤ餺�⸽��ˤ�����ŵ��Ū���ꥹ�ȶ����Ԥ˶��̤��Ƹ��Ф���륭�ꥹ�ȶ����Ф�����礤�ʤ봪�㤤�פ��ΰ褫������Ƨ�߽Ф��Ƥ��ʤ����Ȥ�Ϫ�褹�롣��롦���֥����ޤ�ơ����Ρּºߤο�ʪ�פ˵����ä���������̤���������ֺ����Τ����κ�פޤǽ������Ȥˤʤ�Ȥ������Թ��Ū�ʵ��֡����ߤΤ�����Τʤ��Ⱥ᤹�����������þ������ξ�Ԥ��ưפ˸�ƨ�������ꥹ�Ȥ˵����ä�����Ȥϡ����Ρ֣��Ĥ�ʡ����פ��̤����¸����줿�㸽�ߡ������������ˤ��줫�鵯���롢�����ƴ��˻ϤޤäƤ�������ħŪ��ɽ���Ƥ����ΤǤ���Ȥ������Ȥˤޤä������դ��Ƥ��ʤ���
�������äƤ���ʤ��ۤɤ������Dz輫�Τ�ʤ��������Τ�Τ��������ɾŪ�˴վޤ��뤳�Ȥʤ��ˡ����αDz褬������ů��Ū�ʻ���Ƴ�����ȤϤʤ����������⤷�ͤȿͤ�ʬ�Ĥ��Ȥ�Ư���ʤ�Сʤ����ơ������餯���Τ褦�ˤ���Ư���ʤ��ˡ��������������ΰտޤ������Ȥ����礭����æ������Τȸ��虜������ʤ���
�����Τ��Ǹ�ˤ����ǤäƤ��롣�֤��ν���¸��θ��դ�ʹ�����٤Ƥο͡����Ф��ơ���Ϸٹ𤹤롣�⤷����˽ä����Τ�����С����Ϥ��οͤˡ����ν�˽�Ƥ���ҳ���ä����롣�ޤ����⤷�����¸��ν�θ��դ��������Τ�����С����Ϥ��οͤμ����٤�ʬ���ν�˽�Ƥ��뤤�Τ����ڤ����ʤ��Ԥ��顢�Ȥ�������סʥ�ϥͤ��ۼ�Ͽ22-18�ˤȡ�����ϡ�����Ǹ���¸���Ρ����Τޤ��Ǹ�˽줿�ٹ�Ǥ��뤬������ϡ��������Τ��Ф���ּ�갷���˴ؤ������աפΤ褦�ˤ⸫���롣�����������Ѥ��Ƥ����ֺ��ʲ��פ����Dz��Passion�٤ϡ��������Ǥϥ��ꥹ�ȶ���������Ԥ��Ф��褦���κۤˤϤʤäƤ��Ƥ⡢�����Τ����������Ȥ��Ƥ��ʤ��Ȥ������ǡ����Ǥ˸����ʸ�ŵ�˼��Ū���ץ����������ۤɱΤǤ��롣�������������μ���Dz�غǸ��Ͷ�ǡ٤ϡ����Ȥ��Ƥ���Τ������ʤ���˥���������������ů��Ū�ʻ����Ȥ˺��ʲ��������Ȥ�������Ⱥǽ����������롣�������Dz��Passion�٤ϡ����Τ褦���Ǥ��ʤ����礤�˸���Ū�ʥץ쥼���ΤǤ��롣�������褯���äƤ⡢�����ޤǤ⣲���֤��ϤäƱ䡹��������롢��롦���֥���λ��27���ߤ�Ĥ������¤��줿������������ʡֶ줷�ߤΥ��������¤�ץ��������Ȥ˲�ʤ��ä��ΤǤ���ʱ�������Ū�ˤ�¿�������Ѥ����ˤǤ�������¤�Ǥ��뤬�ˡ��������۶��λ�ä��Ǹ�κ��ʤ������ꥹ�Ȥμ�����ä��Ȥ����Τϡ������ˤ⤢�ꤽ���ʤ��ȤǤϤ��롣
�������ȴ���Ф������Τ�Τ���ˡ�����Ԥζ���Ū�տޤ�����ǽ�˸��ä��ΤϤޤ��ˡ����Τ���Ǥ��롣
���αDz�Ͽʹ֤������Ϥο�������Ū���䤦�Ȥ�����Ū���������Ǥ���ȤǤ���������ʡ��������μ¡��͡��������Ϥη�ǡ�ˤष���Ĥ�������Dz�Ǥ���Ȥ��������롣�Dz褬���ʹ֥�����������Ū���ˡʤ����ˤ˥ե��������������Ȥϡ�ʡ����αDz貽�Ȥ������ĤƤ�¸�ߤ��������Ĥ��Υץ��������Ȥ���Ǥ⡢�Τ��˺��ޤǤˤʤ����ץ������Ǥ��뤳�Ȥ�ǧ��Ƥ��ɤ����������ʹ֥��������̲ᤷ������Ū���ˤα���Ū�ʺƸ��Ȥ��ζ�Ĵɽ���Ȥ�����Τ��̤���ã�����������פΥ�����Ȥϡ��ܤ���ᤷ�ߡ������ơ���������������������Υ��롼�פؤΰ亨�Ȥ����ͥ��ƥ��֤ʴ���ξ����Ǥ����ʤ������������η�̤Ȥ��Ƥʤ���뤳�ȤȤϡ��ֿͤȿͤ�ʬ�ġפȤ������ȤǤ��롣
�Τ��ˡ����Τ�Τˡ����������ͥ��ƥ��֤ʴ������Ф�¦�̤�����Ȥ������Ȥ������κݤ�����餫�ˤʤä��Ȥ�����̣�ǡ��̤�ɾ���������Τ��⤷��ʤ��ʤ���������ؤζ�ü��ȿ�����Dz���͡��ˤ�븽�������������ͤؤ�������ж�ʤȤ�������������ͽ¬��ǽ���ä��۾�ʻ��֤Ǥ���ˡ��������ܹƤϡ����Τ�ΤΡ����뤤�ϥ��ꥹ�ȶ����Τ�Τؤ���Ƚ����ܤȤ�����ΤǤϤʤ������Τ褦�ʹͻ����ưפˤ�����ɾ���ϰϤ�Ķ���롣*
��* �ޤ��Ƥ䥢������ꥹ�ȶ����ļԤǤ�ʤ��Ф��꤫�����ꥹ�ȶ��Τ⤿�餷����ħŪ�����Ρ�¸���Τޤ��˱���ˤ���켫�Ȥ�����ʾ塢���ν����ؤΰ¤äݤ���Ƚ�ϡ��¤ΤȤ��������ξ�ħŪ�ʽ�����Ρ�������˼���ߤ����ȤˤϤʤäƤ⡢����ɾ�Ǥ���ʾ�Ҵ�Ū�Ǥ���פȤ������Ȥˤ�����Ȥ��Ƥʤ餺�����ĤޤǷФäƤ⤽�αƶ�������ȴ���Ф����Ȥ�����ʤ��Ȥ����ѥ�ɥå����˴٤�ΤߤǤ��롣�����顢�����ǤϱDz���Ф�����ɾ�ˤ��μ�����ʤ뤳�Ȥˤ��롣��
��������������ˤߤ���¸�� -- �ʹ֤Ǥ���ʾ塢�ब�θ���������Ū���ˤȤ����Τϡ������������ޤǤ�ʤ������������ʡ������ɤߡ������λ��夫�鷫���֤�������Ƥ������ꥹ�Ȥμ��������������ʥ�����ˤ�С���ʬ������������ΤǤ���*���Dz貽���줿����å��ʱ������̤��ƽ��ƥ������˵��������Ȥ���Ȥ����ΤǤϡ��ޤ��Ͽ��ļԤȤ��Ƥ��ޤ�ˤ������Ȥ����ʳ��ˤʤ����������Dz�Ϥ�����������ͤ������Ϥη�ǡ�����¤����Ѥ��ơ��ष���������Ф���Ǯ���ʤФ�������ƤǤ���³�����뼫�ο��ļԤ��ưפ˴ְ�ä�������Ƴ����ΤǤ��롣
��* ���������ʹ֤Ǥ��롢�ȡʤȤꤢ���������ꤹ�뤳��ʸ�Ϥ������ο��ʤ⤷���Ϥ���˽ऺ��¸�ߡˤǤ���ȿ����뿮�ļԤ�¦���餹��С��лߤʤ�ΤǤ���ȼ�������ǽ�������뤬���֥��������ʹ֤ǤϤʤ��פȿ��������͡��˵դ˿֤������Τϡ��⤷�ʹ֤Ǥʤ��Ȥ����顢����θ������ˤߤ˰��Τɤ�ʰ�̣�����ä����Ȥˤʤ�Τ������� �ब������Ʊ�����Τ���ä��ʹ֤Ǥ��ä����餳�������Ρּ���פ˰�̣������ΤǤϤʤ�������������
�Dz�إѥå����٤ϡ���������Ρ�ʡ����Ρ����������륤����������Ū�ʼ������������Ǵ���12���֤���������Ū�˱�����������ΤǤ��롣�����ơ�����ȴ���Ф������Τ�Τ���ˡ�����Ԥζ���Ū�տޤ����롣�����ޤǤ�ʤ�����������Ȥ���ȴ���Ф��줿��ʬ����������Τ��٤ƤǤϤʤ������������������������Ū�˥ɥ���������Ȥˤ�äơ�����黲�Ȥ��뤳�Ȥ����ޤ��������ʤ��ˤ��¿���ΰ���Ū�ʡʼ��Ρ˥��ꥹ����⤷���ϼ㤤���ꥹ������������Ϳ����ƶ���̵�뤹�뤳�Ȥ�����ʤ��ۤ�����Ǥ���ȸ���ʤ���Фʤ�ʤ���
����ξܺ٤��ʬ�ʤ��Τ�Ԥ����䡢�������٤μ��Ф�ʤ��ɤ���Ԥ����ȤäƤϡ��Dz����Ⱦ��������������˽ФƤ��뤤���Ĥ��Υ��ԥ����ɤϡ����̶��ܤΥ�٥���ΤäƤ��뤳�ȤǤ����������Dz�ǽ����Τ�Ȥ����Τ˶ᤤ�ꥹ�ȶ����ΤۤȤ�ɤδվԡ������Ƥ����餯�ۤȤ������Ū��������ɤळ�ȤΤʤ�����¿���Υ��ꥹ�ȶ����δվԤˤȤäƤ��顢�����ʤ��ˤ��줬�ɤΤ褦�ʰ�̣����ä����ԥ����ɤǤ���Τ���ʬ����褦�ʱ��������ˤ�ʤäƤ��ʤ��ΤǤ��롣
�ʹ֤λĹȤ��������륤�������ˤߤȤ�������Ū������������ȤˤҤ����鷹�����Ƥ��뤳�αDz�ϡ�«�δ֡��ե�å���Хå�Ū���������ֲ��ν�����פȤ��ơ�����Ǹ��ڤ���뤤���Ĥ��ν��פʥ��ԥ����ɤ�����Ū�˸���������Ǥ��롣�����������������ΤäƤ���ͤˤ��Ҥä���ʤ������ɬ�פʤۤɡ��Դ��������Կ��ڤ�������Ƥ��롣�������������θ����ȡ��Ǵ���12���֤˵����뤤���Ĥ��Υ��ԥ����ɤΰ����������������٥١����å����μ��Ȥ���λ�Ƥ���վԤ����åȤ����ꤷ�Ƥ���Ȥ�ͤ�����ΤǤ��롣�ޤ�����ü��˽�ϥ������Ϣ³�Ǥ��뤳�αDz�ϡ��ĵԤ�˽�ϥ������ޤ�Dz���Ф��Ƥ�äѤ鸷�����쥤�ƥ���ܤ��罣��Ǥϡ���Ⱦ�λҶ����Ѥ뤳�Ȥ�����ʤ��ä����������Ȥ��������ʤ������Σ���������äƤ⡢�������μ���������λ�Ƥ���͡ʤ��Ȥʡˤ�����ʬ�������θ�����������θ������뤤�Ϻ�ȯ�����褦�Ȥ����Τ����վԤˤȤäơإѥå����٤�Ѥ�ư���Ǥ���褦�˻פ��롣�������⤷���줬�������Ȥ���С����Τ��Ȥϥ������˵���������Ū�ʼ��֤ɤ�ۤɤˤҤɤ���ΤǤ��ä��Τ��פȤ��������äʶ�̣���������̤θ��̤����ʤ����Ȥˤʤ롣ʬ����䤹�������С����αDz褫��ؤ٤뤳�ȤϤۤȤ�ɤʤ������ǥ������ޥ��ҥ������������Dz�ʤΤǤϤʤ����ȼٿ䤷�����ʤ�ۤ����٤��㤤��ΤʤΤǤ��롣
�������äơ��դˤ��αDz�ǽ�����������������äƤ���Ȥ����͡��ˤȤäơ����줬Ŭ�ڤʥ���ȥ����������ˤʤ����뤫�Ȥ������Ȥϡ���ʬ�˸�Ƥ����ʤ���Фʤ�ʤ���
���αDz��Ѥ����ȴѤ���ǡ������Ϥɤ���������ʤäƤ��뤫�����Τ��Ȥ��䤦ɬ�פ����롣���αDz�Ϥ����˲���������ů��Ū�ʻ���ü������Ƥ�����������������뤤�ϡ�����佡�����Ф��뤢�餿�ʻ����Ȥ�����Τ����Ƥ����������������������Ȥ����ֿ�ʪ�פλ��äƤ��뺬��Ū��̷��䡢�������Τ⤿�餹��å�������Υ��֥륹��������ɡ����ޤ��ޤʿʹֽ���Ǻ�ߡ������Ƥ䤬�ơֵ�����פ����äƤ������Ȥ��տ魯��ѥ�ɥå����������Χˡ�Ԥ䥤��������Ҥ����Υ��ߥ�˥ƥ���ȯ��������Ω�交��ͧ���ڤꡣ�������ä����ΰʳ��Ρּ���ס��ʹ������ˤ⤿�餵������αDz�������Ƥ�����������������뤤�ϥݥ�ƥ������ԥ�ȼ��Ȥ�Ω���������ն����Ϥ�����Ū�طʤ�������Ƥ���������������ޥ�����Υޥꥢ�����Τɤ���������̤������Τ����������������ڤ�������Ƥ��ʤ����Dz���о줹��͡���Ⱦʬ�����ܤ��¸��Ԥ˶줷�ߤ�Ϳ���뤳�Ȥ˴�Ӥ����Ĥ��Ⱦʬ�϶��夹��Ф���Ǥ��뤬�������Ǻ���Ƥ���Τ���ʬ����ʤ�����Ǻ���Ƥ���餷�����Ȥ�����ޥꥢ�δ���䤨�֤ʤ������ޤ���ˤ�ɽ����̤���ɽ�����������Ǥ��롣�����Ǥ�¨��Ū�ʶ�Ǻ��ɽ������뤬���ʹ֤Υɥ�ޤ�������뤳�ȤϤʤ���©�Ҥ��ˤ�Ĥ����ƶ�Ǻ���뤳�Ȥ������Τʤ顢����Ū�˸��ߤǤ������λ���ǵ����Ƥ���ΤǤ��ꡢ����������ޥꥢ�Ǥʤ��Ƥ⤤���Ϥ��ʤΤ���
�ʾ�Τ褦�������ʹ֥������μ��դ˸���뤢����̷����Ǻ�������Ʋ����⥤�������Ȥ��̲ᤷ�ʤ���Фʤ�ʤ��ä�����Ū�ʼ�������ơ������������Ƥ��դ�����������ޤ�Ƥ���Τ����˥��������������θ���˥ޡ��ƥ��������å��ˤ�äƴ��ġ��Dz貽���줿�غǸ��Ͷ�� The Last Temptation of Christ�٤Ǥ��롣
�͡������ǡ���The Last Temptation of Christ�٤ϡ���롦���֥���Ρ�Passion�٤�ο���Ǥ��롣�ۤȤ����Ӥ���Τ�Х��Х������ۤɤǤ��롣������ɥȥ�å��β��ڤ˴ؤ��Ƥ������äƤ⡢��ԤΤϡ����ԤΥ�����ɥȥ�å��ˤ����Ƽ¸����줿�����륢���ǥ����Ѥ��٤����Ѥ�ɾ���������ʤ�ۤɡ��֤����Ȥ����פǤ��롣�����ΤαDz�ˤ��Τ褦�ʲ��������Ƥ뤳�Ȥ�ͤ��Ĥ����Τϡ�Peter Gabriel�ζ��ӤʤΤǤ��롣
��롦���֥���۩�����ֻ��˾�ߤϡ������ͤ����뤳�ȤǤϤʤ������ꥹ�Ȥ��桹�κ����������̣��ä���������������ܤˤ������뤳�Ȥǡ��ͤο��ο����Ȥ����˱ƶ���������˾�������Ϥ��Υ�å��������Ϥ����뤳�Ȥ��סʸ��������Ȥ���ΰ��ѡˡ��츫��������Ǥ��ɿ�Ū�˲��Ǥ������ʥ����Ȥ�������ϼ�ʬ�θ��Ȥ����Ρ֥��ꥹ�Ȥ������κ����������̣��ä�������������פȤ�����ʤ�����������פ��뤳�Ȥǡ��ޤ餺�⸽��ˤ�����ŵ��Ū���ꥹ�ȶ����Ԥ˶��̤��Ƹ��Ф���륭�ꥹ�ȶ����Ф�����礤�ʤ봪�㤤�פ��ΰ褫������Ƨ�߽Ф��Ƥ��ʤ����Ȥ�Ϫ�褹�롣��롦���֥����ޤ�ơ����Ρּºߤο�ʪ�פ˵����ä���������̤���������ֺ����Τ����κ�פޤǽ������Ȥˤʤ�Ȥ������Թ��Ū�ʵ��֡����ߤΤ�����Τʤ��Ⱥ᤹�����������þ������ξ�Ԥ��ưפ˸�ƨ�������ꥹ�Ȥ˵����ä�����Ȥϡ����Ρ֣��Ĥ�ʡ����פ��̤����¸����줿�㸽�ߡ������������ˤ��줫�鵯���롢�����ƴ��˻ϤޤäƤ�������ħŪ��ɽ���Ƥ����ΤǤ���Ȥ������Ȥˤޤä������դ��Ƥ��ʤ���
�������äƤ���ʤ��ۤɤ������Dz輫�Τ�ʤ��������Τ�Τ��������ɾŪ�˴վޤ��뤳�Ȥʤ��ˡ����αDz褬������ů��Ū�ʻ���Ƴ�����ȤϤʤ����������⤷�ͤȿͤ�ʬ�Ĥ��Ȥ�Ư���ʤ�Сʤ����ơ������餯���Τ褦�ˤ���Ư���ʤ��ˡ��������������ΰտޤ������Ȥ����礭����æ������Τȸ��虜������ʤ���
�����Τ��Ǹ�ˤ����ǤäƤ��롣�֤��ν���¸��θ��դ�ʹ�����٤Ƥο͡����Ф��ơ���Ϸٹ𤹤롣�⤷����˽ä����Τ�����С����Ϥ��οͤˡ����ν�˽�Ƥ���ҳ���ä����롣�ޤ����⤷�����¸��ν�θ��դ��������Τ�����С����Ϥ��οͤμ����٤�ʬ���ν�˽�Ƥ��뤤�Τ����ڤ����ʤ��Ԥ��顢�Ȥ�������סʥ�ϥͤ��ۼ�Ͽ22-18�ˤȡ�����ϡ�����Ǹ���¸���Ρ����Τޤ��Ǹ�˽줿�ٹ�Ǥ��뤬������ϡ��������Τ��Ф���ּ�갷���˴ؤ������աפΤ褦�ˤ⸫���롣�����������Ѥ��Ƥ����ֺ��ʲ��פ����Dz��Passion�٤ϡ��������Ǥϥ��ꥹ�ȶ���������Ԥ��Ф��褦���κۤˤϤʤäƤ��Ƥ⡢�����Τ����������Ȥ��Ƥ��ʤ��Ȥ������ǡ����Ǥ˸����ʸ�ŵ�˼��Ū���ץ����������ۤɱΤǤ��롣�������������μ���Dz�غǸ��Ͷ�ǡ٤ϡ����Ȥ��Ƥ���Τ������ʤ���˥���������������ů��Ū�ʻ����Ȥ˺��ʲ��������Ȥ�������Ⱥǽ����������롣�������Dz��Passion�٤ϡ����Τ褦���Ǥ��ʤ����礤�˸���Ū�ʥץ쥼���ΤǤ��롣�������褯���äƤ⡢�����ޤǤ⣲���֤��ϤäƱ䡹��������롢��롦���֥���λ��27���ߤ�Ĥ������¤��줿������������ʡֶ줷�ߤΥ��������¤�ץ��������Ȥ˲�ʤ��ä��ΤǤ���ʱ�������Ū�ˤ�¿�������Ѥ����ˤǤ�������¤�Ǥ��뤬�ˡ��������۶��λ�ä��Ǹ�κ��ʤ������ꥹ�Ȥμ�����ä��Ȥ����Τϡ������ˤ⤢�ꤽ���ʤ��ȤǤϤ��롣
�������ȴ���Ф������Τ�Τ���ˡ�����Ԥζ���Ū�տޤ�����ǽ�˸��ä��ΤϤޤ��ˡ����Τ���Ǥ��롣
00:28:07 -
entee -
TrackBacks
2005-02-22
ȿ�������β����� ���뤤�ϡ�����Ū������
�����ʤ���Τ��Ȥǡ������ƻ䤬�����褦�ʤ��ȤǤ�ʤ���������������������ˤϡֲ��ڡפȸƤФ���Τ��¤�¿�����äƤ⡢�֤��褽���ڤȸƤФ������������ΡפΤʤ��ˡ������ס��Ⱥ����ʱ��դ����ˤ�ΤϤʤ������������Ρ����פˤϤ��������ʼ��ब���äơ���������Ф��Τ����Ǥ����Ȥ�����ȯ���ץ�٥�����⤢��С��ؤ��Ӥߤ�ư�������Ȥ����⤢�롣�ޤ��������䲻�̤���뺤���롣�����Τ��ȤȤ��ڤ�Υ���ʤ�̩�ܤʴؤ��Τ���Τ����ե졼�������Ȥ����ֲ���Ф���סֻؤ�ư������פȤ�����٥�μ����Ԥ������Ƥ��뺤��Ǥ��롣����ˤϡ�¾�ͤνФ����ȤɤΤ褦�˹�碌�Ƥ����Τ��ʤ��뤤�ϡֹ礻�ʤ��פΤ��ˡ��Ȥ����֥���֥��κ���Ȥ�����Τ⤢����֥���֥�פˤĤ����ϰ��ٽ����Ȥ�����ˡ�������ξ��⡢�ɤΤ褦�ʲ����ܻؤ��Τ��ȸ�������ö���Τγ�����¸�ߤ������ȤΤ��롢����Сִ�¸�ˤߤȤ��줿���ȤΤ��벻���ؤ��ܶ�פȤ��������ռԤˤȤä����̤�ʤ����꤬¸�ߤ��뤫�餳���������äƤ��뺤��Ǥ���Ȥ������Ȥ����뤫�⤷��ʤ����������ơ�����ϥ�����ʷ��ˤؤ��ܶ�Ȥ�������ȤߤǤ��롣���Ρ֥�����פ��ص�Ū�˻�ϡֳ��ߤ������ȤΤ����ΡפȸƤ�Ǥ���ΤǤ��롣Ƨ�߹���Ǹ����С�����������Ϣ�Ρֺ���פϡ�����Ȥ���ͤ����ΤǤ��뤷���ɵ᤹���ɬ����Ӥ�ȼ����ΤǤ⤢�롣�Ĥޤꡢ���κ���ȴ�Ӥ��������ڤˤ����Ƥޤ���ɽ���ΤΤ�ΤʤΤǤ��롣
�����ֺ���פ��ִ�ӡפ��Ȥ��������ϡ����κݡ�������оݤǤϤʤ�����������߽Ф����Ȥ��Ƥ���������̤ˤ�äƤɤ���ˤǤ�ž�������Τ������֤ɤ��餬�����פȤ����褦������ǤϤʤ�����Ǥ��롣���������ʲ��Τ��Ȥϵ������ͤ������ƤǤ���ȿ����롣����ϡ��ֺ���פ����ưפ˲��ڲȤˤ����������פ˷�ӤĤ��Ƥ��ޤ��Ȥ�������ˤĤ��ơ��Ǥ��롣
�� �֤������������벻�ڡפؤ�ȿ�ʤȤ������
�ͤˤ�äƤϰճ��ʤ��ȤǤ��뤫�⤷��ʤ��������ڤ˴ؤ��Ƥ������٤ν��Ϥ����Ƥ���Ԥ����ˤȤäƤϡ��ֳ��ߤ��벻�����ܻؤ��פȤ������ȼ��Τ������Ǥˡֵ�����оݡפȤʤäƵפ����Ȥ������Ȥ����롣������ܻؤ���Τ����ֳ��ߤ������Υ�����פǤϤʤ��ơ������ޤǤ�����Ū�ʥ�����פǤ���Ȥ������������٤ΤޤȤޤä����ο͡������ˤ��Ϥ�Ƥ����̤Ρ������פΤ����Ǥ⤢��Τ����Ĥޤꡢ���ߤ�����������ɵ�ϡ��֤��������鲻�ڤ�����ΤϤɤ����פȤ��������ˤ������ϤΤ���������Ǵ��줬���ʤ��ȤǤ⤢��櫓�������������֤������������벻�ڡפ���ȽŪ��ª���Ƥ��벻�ڲȤȤ����Τϡ���������٤����������������ߤ�����ΤǤ���٤������ȸ�����������������ˤ�äƻ٤����Ƥ��롣
���ٳ��ߤ������Ʊ�Τ�¸�ߤ���ҤȤĤҤȤĤΰ㤤�ʸ����ˤϤ��κݡ�����ˤʤ�ʤ�������ϡ�������̤�˶������������Ȥʤ���üŪ�ʰ㤤��¾�ʤ�ʤ�����Ǥ��롣¾�Τ��٤Ƥ����̤�˳��߲��Ǥ������餳����������ˤʤ��٥���äǤ��롣
�����ǤҤȤ�˺��ƤϤʤ�ʤ��Τϡ����褽����������פ䲻�ڤ˴ؤ��뤢���Ρ��ηáפȤ����Τϡ��ɤΤ褦�ʥ�٥�ν��ԼԤˤ�������������ɤ���ΤǤϤʤ��Ȥ������Ȥ����ҤȤĤζ���������ҤȤΤ������٥�����ƤϤ�Ƥ��ޤ��Ȥ������Ȥϡ��¤ϥߥ��ȥ�������̤��ʤ����㤤���纹���ʤ����������ǤäƤ����������Ǹ������ηáפȤ����Τϡ����꾯���οͤˤΤ߸�������Ƥ����뵷�Ȥϴط����ʤ���
�� ���������� vs. ��Ū������
ȿ����и�Ƿ����֤��С������벻�ڤϡ�ʪ�ޤ͡פ���Ϥޤ롣�Ĥޤ곰�ߤ��륤���������Ǥ��롣���뤤�ϡ��֤��ĤƳ��ߤ������Υ�����פ�����ȸ��äƤ��ɤ���������ˡ����ڤϿ������ʤ�ɽ�����뤳�Ȥ��Ȥ�������Ū��ư���Ȥ��������ޤǤ�ʹ֡ʱ��ռԡˤ���Ū¸�ߤζ����Ȥ����Ϥ��ޤ���ʬ��°���뤢������Ū¸�ߤؤ����ŤǤ���Ȥ��������ޤä�����ä�ȿ���Τ�����Ω�ɤ��������פ�¸�ߤ��Ƥ��뤷�������������������¿���α��ղȤ�����ʳ��Ω�����Ƥ��������ǡ��礤���Ǥ路�Ƥ�������ΤҤȤĤ褦�ˤ�פ���櫓�Ǥ��롣
�ä�����������ˤ������Τϡ����Ȥ��С�����������ˤϲ��ڰ����˱��ղȤ��ɤ�ʶ��ڤ���äƤ���Τ��Ǥ���Ȥ����ɤ��̱²Ū�Хå�����ɤ���äƤ���Τ��ʤɤȤ������ޤ���ְ㤨�С�����οʹ֤ˤϤ���˼���Ȥळ�Ȥ�Ǥ��ʤ��ʼ���Ȥ��ʤ��ʤ��ˤȤ������줫�ͤʤ����Ƥ�ޤळ�Ȥ��̤Ȼפ鷺�ˡʤ��뤤�ϼ��ʤ�ͥ�۰ռ��Ф����ˡ�ʿ���ȸ����ڤ��ͤ����롣��������ڤ˼���Ȥ�ˤ����äƤΡ������������������ᾮ��ɾ�����褦�Ȥ���̵��̣���Ȥ������Ĥ���ʤ�������ˤĤ��Ƥϸ�Ҥ��롣
��������Ū��������ϡ��¤�줿���ε����̲�Ԥ������ʤ�¸�߲��ͤʤκ��Ф����ڤ��Τ�Τ������褦�Ȥ��������ʤ����Ρ���ߤιˡפȤ��롢�������̱�ռ��ʥ���Ȱռ��ˤ��ͤʤ�ΤȤ���Ư���������餯�����Ƥ��ξ�硢���Τ褦�ʰռ���������������ܿͤϡ����Τ��Ȥ�̵���ФʤΤǤ��롣
�º����ꡢ��ʬ�δؤ�벻���Ϻ����οʹ֤ˤ��������줿�ø�Ū�ʡֺ�ȡפǤ���Ȥ����ͤ����ʻ��ۡˤϡ���ˤ������٤ε��Ѥ���ä��ͤˤȤäƹ�����̥�ϤǤ��ä��Ȥ������Ȥ�����Ǥ��ʤ���ʤ�������ϡ���ã������ҤؤΡ�����Ū�ʡ�����ˤϲ��ڤ���Ѥ������Ū�ʡ������Υ��˥���������������Ū���̲ᵷ��ˤ�Фơ����ʤ��������Ƥ����ǽ�������롣���������̲ᵷ��Ū�θ��������������Τ�Τ��Ȥ�����ǽ���ⴰ���ˤ�����Ǥ��ʤ������ष��������ܿͤδؤ�äƤ��뤢���β��ڤؤΥ��ߥåȥ��ȡʸ���Ū����Ȥߡˤ����뤿��Ρ������Ƹ���Ū����ˡ�ΤҤȤĤȹͤ������������ʤΤ���
[Read More!]
�����ֺ���פ��ִ�ӡפ��Ȥ��������ϡ����κݡ�������оݤǤϤʤ�����������߽Ф����Ȥ��Ƥ���������̤ˤ�äƤɤ���ˤǤ�ž�������Τ������֤ɤ��餬�����פȤ����褦������ǤϤʤ�����Ǥ��롣���������ʲ��Τ��Ȥϵ������ͤ������ƤǤ���ȿ����롣����ϡ��ֺ���פ����ưפ˲��ڲȤˤ����������פ˷�ӤĤ��Ƥ��ޤ��Ȥ�������ˤĤ��ơ��Ǥ��롣
�� �֤������������벻�ڡפؤ�ȿ�ʤȤ������
�ͤˤ�äƤϰճ��ʤ��ȤǤ��뤫�⤷��ʤ��������ڤ˴ؤ��Ƥ������٤ν��Ϥ����Ƥ���Ԥ����ˤȤäƤϡ��ֳ��ߤ��벻�����ܻؤ��פȤ������ȼ��Τ������Ǥˡֵ�����оݡפȤʤäƵפ����Ȥ������Ȥ����롣������ܻؤ���Τ����ֳ��ߤ������Υ�����פǤϤʤ��ơ������ޤǤ�����Ū�ʥ�����פǤ���Ȥ������������٤ΤޤȤޤä����ο͡������ˤ��Ϥ�Ƥ����̤Ρ������פΤ����Ǥ⤢��Τ����Ĥޤꡢ���ߤ�����������ɵ�ϡ��֤��������鲻�ڤ�����ΤϤɤ����פȤ��������ˤ������ϤΤ���������Ǵ��줬���ʤ��ȤǤ⤢��櫓�������������֤������������벻�ڡפ���ȽŪ��ª���Ƥ��벻�ڲȤȤ����Τϡ���������٤����������������ߤ�����ΤǤ���٤������ȸ�����������������ˤ�äƻ٤����Ƥ��롣
���ٳ��ߤ������Ʊ�Τ�¸�ߤ���ҤȤĤҤȤĤΰ㤤�ʸ����ˤϤ��κݡ�����ˤʤ�ʤ�������ϡ�������̤�˶������������Ȥʤ���üŪ�ʰ㤤��¾�ʤ�ʤ�����Ǥ��롣¾�Τ��٤Ƥ����̤�˳��߲��Ǥ������餳����������ˤʤ��٥���äǤ��롣
�����ǤҤȤ�˺��ƤϤʤ�ʤ��Τϡ����褽����������פ䲻�ڤ˴ؤ��뤢���Ρ��ηáפȤ����Τϡ��ɤΤ褦�ʥ�٥�ν��ԼԤˤ�������������ɤ���ΤǤϤʤ��Ȥ������Ȥ����ҤȤĤζ���������ҤȤΤ������٥�����ƤϤ�Ƥ��ޤ��Ȥ������Ȥϡ��¤ϥߥ��ȥ�������̤��ʤ����㤤���纹���ʤ����������ǤäƤ����������Ǹ������ηáפȤ����Τϡ����꾯���οͤˤΤ߸�������Ƥ����뵷�Ȥϴط����ʤ���
�� ���������� vs. ��Ū������
ȿ����и�Ƿ����֤��С������벻�ڤϡ�ʪ�ޤ͡פ���Ϥޤ롣�Ĥޤ곰�ߤ��륤���������Ǥ��롣���뤤�ϡ��֤��ĤƳ��ߤ������Υ�����פ�����ȸ��äƤ��ɤ���������ˡ����ڤϿ������ʤ�ɽ�����뤳�Ȥ��Ȥ�������Ū��ư���Ȥ��������ޤǤ�ʹ֡ʱ��ռԡˤ���Ū¸�ߤζ����Ȥ����Ϥ��ޤ���ʬ��°���뤢������Ū¸�ߤؤ����ŤǤ���Ȥ��������ޤä�����ä�ȿ���Τ�����Ω�ɤ��������פ�¸�ߤ��Ƥ��뤷�������������������¿���α��ղȤ�����ʳ��Ω�����Ƥ��������ǡ��礤���Ǥ路�Ƥ�������ΤҤȤĤ褦�ˤ�פ���櫓�Ǥ��롣
�ä�����������ˤ������Τϡ����Ȥ��С�����������ˤϲ��ڰ����˱��ղȤ��ɤ�ʶ��ڤ���äƤ���Τ��Ǥ���Ȥ����ɤ��̱²Ū�Хå�����ɤ���äƤ���Τ��ʤɤȤ������ޤ���ְ㤨�С�����οʹ֤ˤϤ���˼���Ȥळ�Ȥ�Ǥ��ʤ��ʼ���Ȥ��ʤ��ʤ��ˤȤ������줫�ͤʤ����Ƥ�ޤळ�Ȥ��̤Ȼפ鷺�ˡʤ��뤤�ϼ��ʤ�ͥ�۰ռ��Ф����ˡ�ʿ���ȸ����ڤ��ͤ����롣��������ڤ˼���Ȥ�ˤ����äƤΡ������������������ᾮ��ɾ�����褦�Ȥ���̵��̣���Ȥ������Ĥ���ʤ�������ˤĤ��Ƥϸ�Ҥ��롣
��������Ū��������ϡ��¤�줿���ε����̲�Ԥ������ʤ�¸�߲��ͤʤκ��Ф����ڤ��Τ�Τ������褦�Ȥ��������ʤ����Ρ���ߤιˡפȤ��롢�������̱�ռ��ʥ���Ȱռ��ˤ��ͤʤ�ΤȤ���Ư���������餯�����Ƥ��ξ�硢���Τ褦�ʰռ���������������ܿͤϡ����Τ��Ȥ�̵���ФʤΤǤ��롣
�º����ꡢ��ʬ�δؤ�벻���Ϻ����οʹ֤ˤ��������줿�ø�Ū�ʡֺ�ȡפǤ���Ȥ����ͤ����ʻ��ۡˤϡ���ˤ������٤ε��Ѥ���ä��ͤˤȤäƹ�����̥�ϤǤ��ä��Ȥ������Ȥ�����Ǥ��ʤ���ʤ�������ϡ���ã������ҤؤΡ�����Ū�ʡ�����ˤϲ��ڤ���Ѥ������Ū�ʡ������Υ��˥���������������Ū���̲ᵷ��ˤ�Фơ����ʤ��������Ƥ����ǽ�������롣���������̲ᵷ��Ū�θ��������������Τ�Τ��Ȥ�����ǽ���ⴰ���ˤ�����Ǥ��ʤ������ष��������ܿͤδؤ�äƤ��뤢���β��ڤؤΥ��ߥåȥ��ȡʸ���Ū����Ȥߡˤ����뤿��Ρ������Ƹ���Ū����ˡ�ΤҤȤĤȹͤ������������ʤΤ���
[Read More!]
08:13:00 -
entee -
TrackBacks
2005-02-02
�Dz�������ʤ��١������ơ������褦�Ȥ�����Ͽ�����Ⱦ���ȡ�
�� �ӥǥ��վ��裱�ơ��������ʤ���
�ڶ��������¿�ۤ���̿�ݸ�����������˾�Ρ�ͭ�֡פ�����13�ͽ��ޤäơ����Τ����ä������������פ��Ԥ��뤿��˴�褷���ֲ���Х��ĥ����ס����Τʤ��ˡ��Ԥ��ʤ��ʤä��ͤ������ͤȤ��ƻ�����Τ餺�˥ĥ����˻��ä��Ƥ��ޤ��㤯�������ʽ����������ɤ��ʤ롩���Ȥ��������Ρ�������Ρ������ʤ��٤�վޡ����Ĥϡ�����������夵�����¨����˼��äƤ���ȻפäƤ����顢����ʱDz��ϤäƤ����������뤸����Ф餷������Ǥ����ʤʤ�ơ�������
����ˤ��Ƥ⡢��̤ˤ����Ϥȹ��פ��פ�ޤ��ʡ���̤�������Ϥȹ�ư�ϡ����Τȸ��������뤿��ι��פȷײ衣�¤�������������ι�ư�Ϥ�̤��������������Ϥ�����С��ܥ���긵�������������ʡ��Ȥ�����������˸����äƼ�������Х�����ǡ����뼫���ִ�Ԥ�ȯ��Ǥ롣����ȳ���ɬ��˲������롣��Τ��Ȥ���ۤɤˡ����������Ȥ����������ꡢ�����褦�Ȥ����Ȥ��˻��������äƤ��롣����ϡ��¤��ɤ��ơ��ޤǤ����ʤ��ߥ夫���ե��ξ�����ɤ���褦�ʴ���������äơ����Ƥ����ȸ�����Ǥ������ϤޤäƤޤ����͡��ɤ����ʤǤ���
�� �ӥǥ��վ��裲�ơ������Ⱦ���ȡ�
���θ塢�����Ѥ��������ˤαDz�ؤޤ��������βڡ������ä����ǡ���������ӥǥ���Ͽ�äƤ��������Ⱦ���ȡ٤�ֺ��ɡפ��뤳�Ȥˡʰ��Τ��Ŀ�̲�Ȥ������ˡ������ܤδվޤΤ����������٤Ϥ��α�����ª�������Ƥ��������Ƭ�����äƤ��롣�ܤ��ɤ�Ȥ���Ʊ�������������Ȥ����ͤ����Ԥ��ä��Τ����������ɤ�Ǥ��ʤ��������Ϥ��줬ʬ���뵤�����롣
¿������Ҥ��������ǡ����Ҽ����Ȥ��Ƥ��뤬�Τ����ˤǤϤʤ����ष���֤䤫�ˡ������ơ��ƼϤʤ���ĩȯŪ����Ҥ�����ӣ���롣�ۤ��15, 6ǯ���α����Ǥ���ˤ�ؤ�餺���ȤƤ�Ť���������ܿͤ�Ѥ�褦�ʵ��⤹�롣��ӣ���졢���ꤵ�졢����Ǥ⤽�������˴������դ��Ƥ������Ȥ���褦�˸�������Ҥ����������������ƥ��Ȥ����Τϡ����ܿͤˤȤäƤϰƳ��ޤ����������˻���ط�����ˤ������Ƥ���������������������ʬ����ˤ�֤���ʼ�ʬ�����ꤷ�Ƥ�餤�����פȤ��������ޥ��ҥ���˶ᤤ���ƥ������ޤ����㿩�äƤ��ʤ��Ȥϸ����ڤ�ʤ���
���Τʸ����ϳФ��Ƥ��ʤ����������������������ä��Τϡ�����μ�ʬ��ȯ������פȤ����褦�ʤ��Ȥ��ä��Ȼפ��ʤ����ơ��ºݤ���Ҥ���������Ψ�褷�ƥ��ȥ�åפƤߤ��롣����Ͼ�ħŪ�ʡˡ��֤ޤ��ޤ��ʥˤ�����äȥ����פȸ��äƤ����褦�ˤ�ʹ������������Ϸ�ɥܥ��Ȥ����ե��륿���̤��Ƽ�ʬ������ˤ��αDz褫�������ä���å������Ǥ���Τ����ɡ�
�����Τ������������Ѥ�������줿�����ǡ��ब�¿ͤˤʤäƤ����������ޤ��𡹤������ˡ�����������Ƥ��롣�±��Ȳ�²���ܿͤΥ��åץ��Ȥ�����̰��Τ��¿ͤ��¿ͤ餷��¤���Ƥ���������ʤ��礭����¡��Ȥ�줿�顢�ɤ�ʤ˸����ʿͤǤ��ȴ���ˤʤ�������Ȥ����褦�ʡ�Ŧ�Ф��줿��¡�Τʤ�Ȥ��礭���ä����ȡ����⤽���¿ͥɥ������Ĥ��Ϥʤ��ä��Τ��⤷��ʤ����������¿ͥɥ�����ˤʤäƤ���ʤ����Ϣ��礤���ۡˡ�
�¿ͤ��Ф��ơִ鿧�ɤ�����ʤ��פȤ��֤��䤤�丵���������͡פȸ����Ť��Ƥ��븫�οͤ����ͤ�ǤƤ��뤬���������䤽�θ����������ˤʤä��������ʤ���ϡ��ʤ�Ȥ����ڤ귿�ǹ��פʤ�ʹ�����Ƥ��褦���ʤ��ä������줬��������۲Ȥ佡���Ȥθ��դʤΤ���
�����Τʤ��ͤˡָ����ʤ������פȤ������Ȥ���äƤϹԤ��ʤ��ȤϤ褯ʹ�������Τ��Ȥǰ����ܤ�줿���Ȥ⤢�롣�����˶��ΰ����ͤ˶�礬�������ȸ��äƤϤ����ʤ����ȡ��Ǥ⡢�����ˤ��������������������˶������ڤ귿�θ��θ��դ��⡢�֤����ۤ�Ȥ�����פ�����ˤ���������������ʬ�������������פȸ���줿�������ܥ��ʤѤäƸ������Ф���������Ǥ��롣�֤�����������ʬ��������������������衣��ˤ����ʤ���衣��������ˤ����������������Ǥ��ޤ뤫���פȤʤ����Ǥ��������顢�������˶��ΰ����ͤ˶�礬�����ȸ��äƤϤ����ʤ��פȤ����Τ⡢���ڤ귿�ιͤ��ʤ�Ǥ����������Х��������������ͤˤ���ʤ��Ǥ��礦�����������ʤ��ȸ����Ƹ������Ф�ͤ⤤���Ǥ���
�ȡ��礤�ˡ����Ⱦ���ȡ٤���æ�������Ȥ����Ǥ����ޤ���
�ڶ��������¿�ۤ���̿�ݸ�����������˾�Ρ�ͭ�֡פ�����13�ͽ��ޤäơ����Τ����ä������������פ��Ԥ��뤿��˴�褷���ֲ���Х��ĥ����ס����Τʤ��ˡ��Ԥ��ʤ��ʤä��ͤ������ͤȤ��ƻ�����Τ餺�˥ĥ����˻��ä��Ƥ��ޤ��㤯�������ʽ����������ɤ��ʤ롩���Ȥ��������Ρ�������Ρ������ʤ��٤�վޡ����Ĥϡ�����������夵�����¨����˼��äƤ���ȻפäƤ����顢����ʱDz��ϤäƤ����������뤸����Ф餷������Ǥ����ʤʤ�ơ�������
����ˤ��Ƥ⡢��̤ˤ����Ϥȹ��פ��פ�ޤ��ʡ���̤�������Ϥȹ�ư�ϡ����Τȸ��������뤿��ι��פȷײ衣�¤�������������ι�ư�Ϥ�̤��������������Ϥ�����С��ܥ���긵�������������ʡ��Ȥ�����������˸����äƼ�������Х�����ǡ����뼫���ִ�Ԥ�ȯ��Ǥ롣����ȳ���ɬ��˲������롣��Τ��Ȥ���ۤɤˡ����������Ȥ����������ꡢ�����褦�Ȥ����Ȥ��˻��������äƤ��롣����ϡ��¤��ɤ��ơ��ޤǤ����ʤ��ߥ夫���ե��ξ�����ɤ���褦�ʴ���������äơ����Ƥ����ȸ�����Ǥ������ϤޤäƤޤ����͡��ɤ����ʤǤ���
�� �ӥǥ��վ��裲�ơ������Ⱦ���ȡ�
���θ塢�����Ѥ��������ˤαDz�ؤޤ��������βڡ������ä����ǡ���������ӥǥ���Ͽ�äƤ��������Ⱦ���ȡ٤�ֺ��ɡפ��뤳�Ȥˡʰ��Τ��Ŀ�̲�Ȥ������ˡ������ܤδվޤΤ����������٤Ϥ��α�����ª�������Ƥ��������Ƭ�����äƤ��롣�ܤ��ɤ�Ȥ���Ʊ�������������Ȥ����ͤ����Ԥ��ä��Τ����������ɤ�Ǥ��ʤ��������Ϥ��줬ʬ���뵤�����롣
¿������Ҥ��������ǡ����Ҽ����Ȥ��Ƥ��뤬�Τ����ˤǤϤʤ����ष���֤䤫�ˡ������ơ��ƼϤʤ���ĩȯŪ����Ҥ�����ӣ���롣�ۤ��15, 6ǯ���α����Ǥ���ˤ�ؤ�餺���ȤƤ�Ť���������ܿͤ�Ѥ�褦�ʵ��⤹�롣��ӣ���졢���ꤵ�졢����Ǥ⤽�������˴������դ��Ƥ������Ȥ���褦�˸�������Ҥ����������������ƥ��Ȥ����Τϡ����ܿͤˤȤäƤϰƳ��ޤ����������˻���ط�����ˤ������Ƥ���������������������ʬ����ˤ�֤���ʼ�ʬ�����ꤷ�Ƥ�餤�����פȤ��������ޥ��ҥ���˶ᤤ���ƥ������ޤ����㿩�äƤ��ʤ��Ȥϸ����ڤ�ʤ���
���Τʸ����ϳФ��Ƥ��ʤ����������������������ä��Τϡ�����μ�ʬ��ȯ������פȤ����褦�ʤ��Ȥ��ä��Ȼפ��ʤ����ơ��ºݤ���Ҥ���������Ψ�褷�ƥ��ȥ�åפƤߤ��롣����Ͼ�ħŪ�ʡˡ��֤ޤ��ޤ��ʥˤ�����äȥ����פȸ��äƤ����褦�ˤ�ʹ������������Ϸ�ɥܥ��Ȥ����ե��륿���̤��Ƽ�ʬ������ˤ��αDz褫�������ä���å������Ǥ���Τ����ɡ�
�����Τ������������Ѥ�������줿�����ǡ��ब�¿ͤˤʤäƤ����������ޤ��𡹤������ˡ�����������Ƥ��롣�±��Ȳ�²���ܿͤΥ��åץ��Ȥ�����̰��Τ��¿ͤ��¿ͤ餷��¤���Ƥ���������ʤ��礭����¡��Ȥ�줿�顢�ɤ�ʤ˸����ʿͤǤ��ȴ���ˤʤ�������Ȥ����褦�ʡ�Ŧ�Ф��줿��¡�Τʤ�Ȥ��礭���ä����ȡ����⤽���¿ͥɥ������Ĥ��Ϥʤ��ä��Τ��⤷��ʤ����������¿ͥɥ�����ˤʤäƤ���ʤ����Ϣ��礤���ۡˡ�
�¿ͤ��Ф��ơִ鿧�ɤ�����ʤ��פȤ��֤��䤤�丵���������͡פȸ����Ť��Ƥ��븫�οͤ����ͤ�ǤƤ��뤬���������䤽�θ����������ˤʤä��������ʤ���ϡ��ʤ�Ȥ����ڤ귿�ǹ��פʤ�ʹ�����Ƥ��褦���ʤ��ä������줬��������۲Ȥ佡���Ȥθ��դʤΤ���
�����Τʤ��ͤˡָ����ʤ������פȤ������Ȥ���äƤϹԤ��ʤ��ȤϤ褯ʹ�������Τ��Ȥǰ����ܤ�줿���Ȥ⤢�롣�����˶��ΰ����ͤ˶�礬�������ȸ��äƤϤ����ʤ����ȡ��Ǥ⡢�����ˤ��������������������˶������ڤ귿�θ��θ��դ��⡢�֤����ۤ�Ȥ�����פ�����ˤ���������������ʬ�������������פȸ���줿�������ܥ��ʤѤäƸ������Ф���������Ǥ��롣�֤�����������ʬ��������������������衣��ˤ����ʤ���衣��������ˤ����������������Ǥ��ޤ뤫���פȤʤ����Ǥ��������顢�������˶��ΰ����ͤ˶�礬�����ȸ��äƤϤ����ʤ��פȤ����Τ⡢���ڤ귿�ιͤ��ʤ�Ǥ����������Х��������������ͤˤ���ʤ��Ǥ��礦�����������ʤ��ȸ����Ƹ������Ф�ͤ⤤���Ǥ���
�ȡ��礤�ˡ����Ⱦ���ȡ٤���æ�������Ȥ����Ǥ����ޤ���
23:39:00 -
entee -
TrackBacks
2005-01-28
�֤�����פ�����Zefiro�ˤ��ᤤ�Ƥ�������ֶ�¤����
��ϻʬ����ϡ����ʤդ��ޡ˰����֤Ƥ��֤�����פ�¦����ʹ�����Ƥ���褦�ʤޤ��䤫���ǡ�ž����Ϥ�롣����ϡ������ͥåȤΣ����ռԤΤ���������������Τ��ռ�Ʊ�Τν����«�ͤ�������ܤΥХ��åȥۥ����ꤲ������ľ��ˡ���������ҤȤĤ����פ����Ф��Ƥ���褦�ʣ��ܤ�ͭ��Ū��©�ε��Ȥ��ƴ���������롣�����ơ�����ͭ̾�ʡ֥ե������פΥơ��ޡ����ν�ϻʬ���䷲���ǽ��12������ơ����ڴ郎�ȥ��åƥ�����������Ȥ�����������13�����ڴ�������ųڴ���������Ф����Ȥν������餫�������������ҥۡ���β����������������ä��ǽ��13����ǡ���ʬ����Ω����äƤ��벻�ڤ����������ˡ��פ鷺�Τ�ȿ�����ơ����ڤδ�Ӥ��Ф����Ѥ�äƤ��롣����ϡ����ޤ���ɤ����벻���θ��ΤȤ������������ưŪ����ڻ�ʤΤ���
�������������ꥢ�θųڥ���֥�������Ensemble Zefiro�Υ����Ȥ˱濫�äƹԤ����Ȥˡ�Zelenka�Υ���Х��Ф����Ȥ��ˤ�����ΤäƤ⤦���줳��10ǯ�ФäƤ���Τǡ����β��ڤ��Τä���10ǯ�η������ФäƤ��뤳�Ȥˤʤ롣�����ޤ������������դ˿���뵡����������Ȥ��������ˤ��Ƥ��ʤ��ä��������Ⱦ�����������ʤ�������å����Ƥ��ʤ���ʬ���������Τ褦�ʹ����˷äޤ줿�Τ��Ƥˤ�Ѥˤ�����ͧ�ͤΤ������Ǥ��롣
�������α��դ������ܤϥХ��å�����β��ڤǤϤʤ������ʥ⡼�ĥ���ȡ��ץ�����ࡣ�ᥤ��ϡ�13�ɤΤ���Υ���ʡ��ǡ�Serenade Nr. 10�ˡס����ʤ���֥����ѥ�ƥ������פ��Τ���ɳڥ���֥�ʤǤ��롣�ɳڥ���֥뤽�Τ�Τ����ޤꥳ���Ȥ�İ�����Ȥν���ʤ��ޥ��ʡ���ʬ��Ǥ��뤬�����줬�ųڴ�ˤ���Τǡ������⤽�줬13�ͽ��ޤ�ȸ����Τϡ���ۤɤΤ��ȤǤʤ��¤ꡢ�ʤ��ΤǤϤ���ޤ��������������ȥ�Υ��С�����13�ͤδɳڴ��ռԤ���Ф��Ʊ��դ���Ȥ������ȤϤ�����������������ʤ�Ȳ��������ڴ索���Υ��С��ˤ�����̱��ղ�Τ������Ǽ��夲���륫�����Ȥ����Τ�����äȤ��ꤽ���ʤ��ȤǤ��롣�����⸽�ߤǤϻ��¾强���Ƥ��ޤä������ɳڴ�Х��åȥۥ��ϥ����ͥåȤ��֤�������줬���ʥѡ��ȤǤ��뤷������λ���γڴ�ʤ��������������줿��ΤǤϤ��뤬�ˤǤα��դˤ��뤳�Ȥ����Ǥ��롣
Zelenka����ã����������ߤ�ˤ�����֣��ܤΥ����ܥ��ȥХ�����������㲻�Τ���Υ��ʥ��������ʡˡפǡ����Ȥ����ۤɤ��ο�����������ۤ����ƥ��˥å����Ĥ��Ƥ��줿Alfredo Bernardini��Paolo Grazzi��������Alberto Grazzi�ʤ����餯Paolo Grazzi�η��ˤ��������Τ��Ȥʤ��飱�֤ȣ��֥����ܥ��������ƥХ�����Σ��֤����Ƥ��롣���Σ��ͤ�����ƻĤ��10̾�ϡ����٤Ƽ�ʬ�ˤȤäơ��ۤܽ��Ƥ���ʹ���ͤФ���Ǥ����Ĵ�٤��顢����natural horn��ᤤ�Ƥ���Dileno Baldin�Ȥ����ͤϡ�Zefiro�ˤ��Vivaldi�ʽ��Ǥϡ��ȥ��ڥåȤ�ᤤ�Ƥ����餷�����Ȥ�Ƚ���ˡ�
���ڤ������ܤΥ����ܥ��ʳ��Ǥϡ���13�ɤΥ���ʡ��ǡפϣ��ܤΥ����ͥåȡ����ܤΥХ��åȥۥ���ܤΥХ������ܤΥʥ�����ۥ�����ƣ���Υ���ȥ�Х��Ȥ��������ˤʤ�ʥ���ȥ�Х������İ���Ƥߤ����ä��������Τ褦�ʸųڴ郎���ߤ���Τ��ʤ��Τ��������٤ϥ���ȥ�Х��ǡˡ����������ǻĤäƤ���⡼�ĥ���Ȥθ���Ȥ����Τϡ������餯�֥����ѥ�ƥ������װʳ��ˤϤʤ����顢�����롦�⡼�ĥ���ȡ��ץ������������Ȥ���С��ʤ��Ȥ˱��ռԤ��Ѥ��ʤ���Ȥ������Ȥˤʤ餶������ʤ���������������Zefiro��Ψ����Bernardini����⡼�ĥ���������λ���ˤ����餯���Τ褦�˱��դ��줿�Ǥ��������ڥ�Υϥ��ˡ��ʴɳڹ��ա˥С��������������ơ������ѥ�ƥ������Υե���С��ǡ��֥ե������η뺧�פ�ϥ��饤�Ȥη��DZ��դ����ΤǤ��롣��Ƭ�Ρ֥ե������פϤ��Τޤ��˽��ʤǵ�������ʬ�ζ�س�ȴ�ư�Ҥ��褦�ȶˤ��Ƥ���ΤǤ��롣
�����ѥ�ƥ������ϡ���ʬ��İ���Ƥ�����Τϥ����Υ��뤬�ش��Ƥ��륦������ե���Υ��С��ˤ���Τ�֥ե�ȥ٥顼���ش����פ�Τ�ޤ�Ƥ��٤ƥ����ڴ�ˤ���ΤǤ��ä������ųڴ�ˤ�륰���ѥ�ƥ������Ȥ����Τϡ�Ͽ���Τ�Τ�ޤ��İ�����ΤϽ��ƤǤ��ä��ΤǤϤʤ����Ȼפ����ޤ������Τ褦�ʴ�ͭ�Υѥե����ޥ�¾�Ǥ�ʤ�Zefiro�α��դ�İ����Ȥϡ�
�����ܤˤ���Bernardini�ϡ��츫�ؼ����Ȥ�������Ȥ�פ碌�����ƤƤ��롣���������ä�����դ�Ϥ��ȡ���ʬ���ڤ��ߡ�����˿ͤ�ڤ��ޤ��褦�Ȥ������ʤ��Τʤ����ڤ��Ф�����������ꡢ���������ȡֵҤ����˸����Ƥ���פȤ����⤢�ꡢ��̯�ʥХ���ФǷ��ߤǤʤ����٤˥����ƥ��ʡ��Ȥ��Ƥ����Ǥ���ä��ݿͤǤ��뤳�Ȥ�ʬ���롣���������⡢�ä��褦�ʲΤȵ�����Ʊ����İ�����Ƥ���벻�ڲȤǤ��롣
�ޡ��顼�Υ��ꥫ���奢�Ȥ����Τ���֥ޡ��顼�αƳ��פȤ����Τ����뤬���Ĥ�ߤޤ̥�����ؤθƤ����������ơ����餬�����פ碌��褦�����Ƥȥ��������奢�ǡָ��岻�ڡפ��ꤹ��¨�����դ�12�ͤ���֤����˼���ش���������12�ͤα��ղȤ����ζä��褦����Ψ�������������ѥե����ޡ�������ش��봬�����ᤵ�ʤ����Bernardini����¨�����롣����ǡ��ָ��岻�ڡפβ����뤫����Ū�����в����Ƥ��줿�Τ�������ʾ�Ρ���ɾ�Ȥ�����Τ���������������ϲ����Ϻ���̤��Ƹ���Ū���ڤΤ�����ʬ��Ф��ˤ�����äƤ��줿�Τ���
ZelenkaϿ���Ǥ��礤�˰ż����Ƥ���Bernardini���radical���ϡ�����α��ղ�ˤ�äơ����줬ñ�ʤ������������ˤ���¸�ߤ����ΤȤ��ƤǤϤʤ��ơ��ֲ��ڤ��̤��ƤΥҥ塼�⥢����ɾ�����פȤ�����Τμºߤ�ֶ�˸��뤳�Ȥ����褿�Τ���
�������������ꥢ�θųڥ���֥�������Ensemble Zefiro�Υ����Ȥ˱濫�äƹԤ����Ȥˡ�Zelenka�Υ���Х��Ф����Ȥ��ˤ�����ΤäƤ⤦���줳��10ǯ�ФäƤ���Τǡ����β��ڤ��Τä���10ǯ�η������ФäƤ��뤳�Ȥˤʤ롣�����ޤ������������դ˿���뵡����������Ȥ��������ˤ��Ƥ��ʤ��ä��������Ⱦ�����������ʤ�������å����Ƥ��ʤ���ʬ���������Τ褦�ʹ����˷äޤ줿�Τ��Ƥˤ�Ѥˤ�����ͧ�ͤΤ������Ǥ��롣
�������α��դ������ܤϥХ��å�����β��ڤǤϤʤ������ʥ⡼�ĥ���ȡ��ץ�����ࡣ�ᥤ��ϡ�13�ɤΤ���Υ���ʡ��ǡ�Serenade Nr. 10�ˡס����ʤ���֥����ѥ�ƥ������פ��Τ���ɳڥ���֥�ʤǤ��롣�ɳڥ���֥뤽�Τ�Τ����ޤꥳ���Ȥ�İ�����Ȥν���ʤ��ޥ��ʡ���ʬ��Ǥ��뤬�����줬�ųڴ�ˤ���Τǡ������⤽�줬13�ͽ��ޤ�ȸ����Τϡ���ۤɤΤ��ȤǤʤ��¤ꡢ�ʤ��ΤǤϤ���ޤ��������������ȥ�Υ��С�����13�ͤδɳڴ��ռԤ���Ф��Ʊ��դ���Ȥ������ȤϤ�����������������ʤ�Ȳ��������ڴ索���Υ��С��ˤ�����̱��ղ�Τ������Ǽ��夲���륫�����Ȥ����Τ�����äȤ��ꤽ���ʤ��ȤǤ��롣�����⸽�ߤǤϻ��¾强���Ƥ��ޤä������ɳڴ�Х��åȥۥ��ϥ����ͥåȤ��֤�������줬���ʥѡ��ȤǤ��뤷������λ���γڴ�ʤ��������������줿��ΤǤϤ��뤬�ˤǤα��դˤ��뤳�Ȥ����Ǥ��롣
Zelenka����ã����������ߤ�ˤ�����֣��ܤΥ����ܥ��ȥХ�����������㲻�Τ���Υ��ʥ��������ʡˡפǡ����Ȥ����ۤɤ��ο�����������ۤ����ƥ��˥å����Ĥ��Ƥ��줿Alfredo Bernardini��Paolo Grazzi��������Alberto Grazzi�ʤ����餯Paolo Grazzi�η��ˤ��������Τ��Ȥʤ��飱�֤ȣ��֥����ܥ��������ƥХ�����Σ��֤����Ƥ��롣���Σ��ͤ�����ƻĤ��10̾�ϡ����٤Ƽ�ʬ�ˤȤäơ��ۤܽ��Ƥ���ʹ���ͤФ���Ǥ����Ĵ�٤��顢����natural horn��ᤤ�Ƥ���Dileno Baldin�Ȥ����ͤϡ�Zefiro�ˤ��Vivaldi�ʽ��Ǥϡ��ȥ��ڥåȤ�ᤤ�Ƥ����餷�����Ȥ�Ƚ���ˡ�
���ڤ������ܤΥ����ܥ��ʳ��Ǥϡ���13�ɤΥ���ʡ��ǡפϣ��ܤΥ����ͥåȡ����ܤΥХ��åȥۥ���ܤΥХ������ܤΥʥ�����ۥ�����ƣ���Υ���ȥ�Х��Ȥ��������ˤʤ�ʥ���ȥ�Х������İ���Ƥߤ����ä��������Τ褦�ʸųڴ郎���ߤ���Τ��ʤ��Τ��������٤ϥ���ȥ�Х��ǡˡ����������ǻĤäƤ���⡼�ĥ���Ȥθ���Ȥ����Τϡ������餯�֥����ѥ�ƥ������װʳ��ˤϤʤ����顢�����롦�⡼�ĥ���ȡ��ץ������������Ȥ���С��ʤ��Ȥ˱��ռԤ��Ѥ��ʤ���Ȥ������Ȥˤʤ餶������ʤ���������������Zefiro��Ψ����Bernardini����⡼�ĥ���������λ���ˤ����餯���Τ褦�˱��դ��줿�Ǥ��������ڥ�Υϥ��ˡ��ʴɳڹ��ա˥С��������������ơ������ѥ�ƥ������Υե���С��ǡ��֥ե������η뺧�פ�ϥ��饤�Ȥη��DZ��դ����ΤǤ��롣��Ƭ�Ρ֥ե������פϤ��Τޤ��˽��ʤǵ�������ʬ�ζ�س�ȴ�ư�Ҥ��褦�ȶˤ��Ƥ���ΤǤ��롣
�����ѥ�ƥ������ϡ���ʬ��İ���Ƥ�����Τϥ����Υ��뤬�ش��Ƥ��륦������ե���Υ��С��ˤ���Τ�֥ե�ȥ٥顼���ش����פ�Τ�ޤ�Ƥ��٤ƥ����ڴ�ˤ���ΤǤ��ä������ųڴ�ˤ�륰���ѥ�ƥ������Ȥ����Τϡ�Ͽ���Τ�Τ�ޤ��İ�����ΤϽ��ƤǤ��ä��ΤǤϤʤ����Ȼפ����ޤ������Τ褦�ʴ�ͭ�Υѥե����ޥ�¾�Ǥ�ʤ�Zefiro�α��դ�İ����Ȥϡ�
�����ܤˤ���Bernardini�ϡ��츫�ؼ����Ȥ�������Ȥ�פ碌�����ƤƤ��롣���������ä�����դ�Ϥ��ȡ���ʬ���ڤ��ߡ�����˿ͤ�ڤ��ޤ��褦�Ȥ������ʤ��Τʤ����ڤ��Ф�����������ꡢ���������ȡֵҤ����˸����Ƥ���פȤ����⤢�ꡢ��̯�ʥХ���ФǷ��ߤǤʤ����٤˥����ƥ��ʡ��Ȥ��Ƥ����Ǥ���ä��ݿͤǤ��뤳�Ȥ�ʬ���롣���������⡢�ä��褦�ʲΤȵ�����Ʊ����İ�����Ƥ���벻�ڲȤǤ��롣
�ޡ��顼�Υ��ꥫ���奢�Ȥ����Τ���֥ޡ��顼�αƳ��פȤ����Τ����뤬���Ĥ�ߤޤ̥�����ؤθƤ����������ơ����餬�����פ碌��褦�����Ƥȥ��������奢�ǡָ��岻�ڡפ��ꤹ��¨�����դ�12�ͤ���֤����˼���ش���������12�ͤα��ղȤ����ζä��褦����Ψ�������������ѥե����ޡ�������ش��봬�����ᤵ�ʤ����Bernardini����¨�����롣����ǡ��ָ��岻�ڡפβ����뤫����Ū�����в����Ƥ��줿�Τ�������ʾ�Ρ���ɾ�Ȥ�����Τ���������������ϲ����Ϻ���̤��Ƹ���Ū���ڤΤ�����ʬ��Ф��ˤ�����äƤ��줿�Τ���
ZelenkaϿ���Ǥ��礤�˰ż����Ƥ���Bernardini���radical���ϡ�����α��ղ�ˤ�äơ����줬ñ�ʤ������������ˤ���¸�ߤ����ΤȤ��ƤǤϤʤ��ơ��ֲ��ڤ��̤��ƤΥҥ塼�⥢����ɾ�����פȤ�����Τμºߤ�ֶ�˸��뤳�Ȥ����褿�Τ���
23:39:00 -
entee -
TrackBacks
2005-01-09
�裸������Ρ������餤��
������̦�μ�Ť������ϯ�ɤȴ��¨�����濴�Ȥ����ѥե����ޥ��ꡣ��ǯ�ǽ�Υ饤���ˤդ��路���ڤ���Ÿ������żԤ����⤵��ϥӥ��ͥ����ԺߤǤ��ä��������ε�ž�ȡ������Ʋ�������ΰ�Ǥ�������ķʻҤ���Ρ֤�����פˤ�äơ���ɤ����ڤ롣����ˤϴ��ա�
�б�ԤϤ��Ĥ�Τ褦��¿�ͤˤ���¿�̡����������Ѥ�����Ϣ���Τ��ä����渨����˽��ÿͤ�������������ŵ�����������äƶ�Ĥ��Ƥ����ʤ����ƥ쥮��顼�б�Ԥ����������Ե����Ƥ���Ƥ����ˡ���åѤ���ƣ�䤵��ˤ�����ݤ����Ȥ��������Ф��Ƥ���롣�¤ˡ���⤷���͡��ʤΤǤ��롣���Ȥϡ��쥮��顼�б�Ԥξ���줵�ʻ������ķʻҤ����ߤ夵����������裳�����٤���о줷���ѿͲ�椵���¨���ж硢���ˡ�
���Τ�����ʬ���뤳�Ȥˤ������ʰʲ��ɾ�ά�˺ǽ�Υ��åȤǡ�����ܹ���ܥ� �� �� �� �Υȥꥪ�ǻϤ�롣�פ��Τۤ����Ȥ��������䤷���Τ�٤��Ȥ��������褯�ֹ礦�ף��ͤʤΤǤ��롣������Ȥ��٤��ʤΤ��ɤ����ϡ��ͤΥƥ����Ȥˤ���������������椵��ȼ�ʬ�Ϥ��ʤ������Ǥ����ΤǤ��롣���Υȥꥪ�˾��ġ��ʻ��Σ��ͤ�����ƨ�������о졣
�裲���ϱʻ��Υץ��åȤˤ���ϯ�ɥץ쥤�ס����餫�����Ѱդ��Ƥ�����ϯ���ѤΥƥ����Ȥ�ʻ��ܤ��ߤ�ܥ� �� �� �� �Σ��ͤ�Ʊ�����ɤϤ��Ȥ����츫�ʥʻ�ߡ��ƥ�����ϯ�ɤ�¨�����ȶ�������̣�臘�Ȥ�����äƥ���ץ�ʥ����ǥ��ʤΤǤ��뤬����������⤵���Ժߤ��ɤ����Ȥ˻�Ƥߤ롣���ͤΥ��������������ֶ���Ĵ���������װ���λ�ߡ��ʻ��Ϥ��줬�¤˹����ʤΤǤ��롣�վ�¦�ˤ��������ϡ��¤�Ψľ������Ƚ�������٤��ȿ������ʤ��餷�Ƥ���ơ���ľ�ʤ��ʤ��Ĥ餤�Ȥ����ǤϤ��ä������ʻ������¦�˾����뤳�ȤǤʤ�Ȥ����ᤴ�������θ�ϡ�������å������������Ǥ������Ȥä����ˡ����¨���������ˤʤ�����Ū���������ʻҤ����ϯ�ɤ��Ϥޤ�ȡ��ե�������ȥ���Х��á���Ƥߤ褦�Ȼפ��������¹ԡ�
�裳���ϡ������դ���Τ��餤������ʬ�ϡ�İ��¦�˲�롣�Ǹ�ϥ����˥��Υ��֥��ɳڴ��duduk���դ��ɤ��Ƥ��ޤä������ԥ��Τ��ڤ��ؤ��ƶʤ�餻�Ƥ��ޤä�������ˤϾ����Ϥ�������Τ��ͻҤ��ä���������Ū�ˤϤ��礦���ɤ��ä��ΤǤ���ʤʤɤȸ����С�˽�����ʡˡ�
�饤����ϡ����߳�ƻ�褤���������Ź���ˡ���椵���椵���ߤ夵�ʻ��������Ƽ�ʬ�Σ��ͤ��Ǥ��夲���Ǥ��夲�ν��ޤ�Ȥ��Ƥϣ��ͤϾ��ʤ����������ǤϤޤ������椵��Ȳ�椵���濴�ˤʤäơ��������ϡס֥˥塼�������ϡפʤɲ��ڤΥ������̵����ϤޤäƤ��ޤä������Ū�ˤϡ��֥��ƥ���פϳƿͤβ�������Ǥ��ꡢ���Ԥμ�Ѥ�ǡ�������������Ϥ��륫�����δ�����뤫���Υϥʥ��Ǥ����ʤ�������Ϥ���ǰ����Ϥʤ������������ᤷ�ƤߤƤ⡢���ڤΤ��뤬�ޤޤμ��֤ϡ����뤬�ޤޤΤ�ΤȤ���¸�ߤ��롣����ϡ�����ɤ�ª�������֤Ť��������������Ԥδ�˾��ȿ�Ǥ�����Τˤ����������֤��İ����뤳�ȤȤ�������ʤΤǤ��롣
�˥塼�������ȸƤФ�ơ����ͤ����ʤ��ȸ����Ȥ��ʻ�μ�ĥ�ˤ��������롢��ˤʤäơ֥˥塼�������פȸƤФ�벻�ڥ��ƥ���Ρ���äȤ�üŪ�˸������ܼ��פΰ�Ĥ��ȼ�ʬ�Ϲͤ��뤬������Ϥʤ��ʤ�ʬ���äƤ�館�ʤ����軰�Ԥ�̾����Ϳ���륫�ƥ�����顢�¤ϡ��������Ϻ�Ԥ�ƨ��褦�Ȥ����ΤʤΤǤ��롣����ϡ֥˥塼�������פ������äǤϤʤ����֥��㥺�פ���ƨ��롢�֥ҥ塼�����פ���ƨ��롢�֥��å��פ���ƨ��롢�Ȥ��������ǡ�̾���ο�����������줬ƨ��Ƥ��������ƥ�������롣�֤��β��ڤϥ˥塼�������ߥ塼���å����פȸƤФ�ƴ�ֲ��ڲȤ������Ϣ��Ƥ��Ƥ�餤�������Ǥ��롣
����ϡ��������פξ��ʲ���ȼ�äơ��ӥ��ͥ�����ص����դ���줿�Ȥ����Τ��������餯����������������������վԤ������ڤäƤ���˼�����ɬ�פʤɤʤ��ΤǤ��롣
����ˤ��Ƥ⡢�֥˥塼�������פؤ�ʬ��Ȥ����Τϡ��¤˰��դ������Ƥ���ʤȤ����Τ�������Ǥ���С�������Ū����ȷ�ӤĤ��Ƥ���ס�ŵ��Ūʬ����Ȼפ���
�б�ԤϤ��Ĥ�Τ褦��¿�ͤˤ���¿�̡����������Ѥ�����Ϣ���Τ��ä����渨����˽��ÿͤ�������������ŵ�����������äƶ�Ĥ��Ƥ����ʤ����ƥ쥮��顼�б�Ԥ����������Ե����Ƥ���Ƥ����ˡ���åѤ���ƣ�䤵��ˤ�����ݤ����Ȥ��������Ф��Ƥ���롣�¤ˡ���⤷���͡��ʤΤǤ��롣���Ȥϡ��쥮��顼�б�Ԥξ���줵�ʻ������ķʻҤ����ߤ夵����������裳�����٤���о줷���ѿͲ�椵���¨���ж硢���ˡ�
���Τ�����ʬ���뤳�Ȥˤ������ʰʲ��ɾ�ά�˺ǽ�Υ��åȤǡ�����ܹ���ܥ� �� �� �� �Υȥꥪ�ǻϤ�롣�פ��Τۤ����Ȥ��������䤷���Τ�٤��Ȥ��������褯�ֹ礦�ף��ͤʤΤǤ��롣������Ȥ��٤��ʤΤ��ɤ����ϡ��ͤΥƥ����Ȥˤ���������������椵��ȼ�ʬ�Ϥ��ʤ������Ǥ����ΤǤ��롣���Υȥꥪ�˾��ġ��ʻ��Σ��ͤ�����ƨ�������о졣
�裲���ϱʻ��Υץ��åȤˤ���ϯ�ɥץ쥤�ס����餫�����Ѱդ��Ƥ�����ϯ���ѤΥƥ����Ȥ�ʻ��ܤ��ߤ�ܥ� �� �� �� �Σ��ͤ�Ʊ�����ɤϤ��Ȥ����츫�ʥʻ�ߡ��ƥ�����ϯ�ɤ�¨�����ȶ�������̣�臘�Ȥ�����äƥ���ץ�ʥ����ǥ��ʤΤǤ��뤬����������⤵���Ժߤ��ɤ����Ȥ˻�Ƥߤ롣���ͤΥ��������������ֶ���Ĵ���������װ���λ�ߡ��ʻ��Ϥ��줬�¤˹����ʤΤǤ��롣�վ�¦�ˤ��������ϡ��¤�Ψľ������Ƚ�������٤��ȿ������ʤ��餷�Ƥ���ơ���ľ�ʤ��ʤ��Ĥ餤�Ȥ����ǤϤ��ä������ʻ������¦�˾����뤳�ȤǤʤ�Ȥ����ᤴ�������θ�ϡ�������å������������Ǥ������Ȥä����ˡ����¨���������ˤʤ�����Ū���������ʻҤ����ϯ�ɤ��Ϥޤ�ȡ��ե�������ȥ���Х��á���Ƥߤ褦�Ȼפ��������¹ԡ�
�裳���ϡ������դ���Τ��餤������ʬ�ϡ�İ��¦�˲�롣�Ǹ�ϥ����˥��Υ��֥��ɳڴ��duduk���դ��ɤ��Ƥ��ޤä������ԥ��Τ��ڤ��ؤ��ƶʤ�餻�Ƥ��ޤä�������ˤϾ����Ϥ�������Τ��ͻҤ��ä���������Ū�ˤϤ��礦���ɤ��ä��ΤǤ���ʤʤɤȸ����С�˽�����ʡˡ�
�饤����ϡ����߳�ƻ�褤���������Ź���ˡ���椵���椵���ߤ夵�ʻ��������Ƽ�ʬ�Σ��ͤ��Ǥ��夲���Ǥ��夲�ν��ޤ�Ȥ��Ƥϣ��ͤϾ��ʤ����������ǤϤޤ������椵��Ȳ�椵���濴�ˤʤäơ��������ϡס֥˥塼�������ϡפʤɲ��ڤΥ������̵����ϤޤäƤ��ޤä������Ū�ˤϡ��֥��ƥ���פϳƿͤβ�������Ǥ��ꡢ���Ԥμ�Ѥ�ǡ�������������Ϥ��륫�����δ�����뤫���Υϥʥ��Ǥ����ʤ�������Ϥ���ǰ����Ϥʤ������������ᤷ�ƤߤƤ⡢���ڤΤ��뤬�ޤޤμ��֤ϡ����뤬�ޤޤΤ�ΤȤ���¸�ߤ��롣����ϡ�����ɤ�ª�������֤Ť��������������Ԥδ�˾��ȿ�Ǥ�����Τˤ����������֤��İ����뤳�ȤȤ�������ʤΤǤ��롣
�˥塼�������ȸƤФ�ơ����ͤ����ʤ��ȸ����Ȥ��ʻ�μ�ĥ�ˤ��������롢��ˤʤäơ֥˥塼�������פȸƤФ�벻�ڥ��ƥ���Ρ���äȤ�üŪ�˸������ܼ��פΰ�Ĥ��ȼ�ʬ�Ϲͤ��뤬������Ϥʤ��ʤ�ʬ���äƤ�館�ʤ����軰�Ԥ�̾����Ϳ���륫�ƥ�����顢�¤ϡ��������Ϻ�Ԥ�ƨ��褦�Ȥ����ΤʤΤǤ��롣����ϡ֥˥塼�������פ������äǤϤʤ����֥��㥺�פ���ƨ��롢�֥ҥ塼�����פ���ƨ��롢�֥��å��פ���ƨ��롢�Ȥ��������ǡ�̾���ο�����������줬ƨ��Ƥ��������ƥ�������롣�֤��β��ڤϥ˥塼�������ߥ塼���å����פȸƤФ�ƴ�ֲ��ڲȤ������Ϣ��Ƥ��Ƥ�餤�������Ǥ��롣
����ϡ��������פξ��ʲ���ȼ�äơ��ӥ��ͥ�����ص����դ���줿�Ȥ����Τ��������餯����������������������վԤ������ڤäƤ���˼�����ɬ�פʤɤʤ��ΤǤ��롣
����ˤ��Ƥ⡢�֥˥塼�������פؤ�ʬ��Ȥ����Τϡ��¤˰��դ������Ƥ���ʤȤ����Τ�������Ǥ���С�������Ū����ȷ�ӤĤ��Ƥ���ס�ŵ��Ūʬ����Ȼפ���
23:23:00 -
entee -
TrackBacks
2004-11-10
Ǥ�������ζ���
�¤ϡ��������������ΤǤ�֤ˤ礦�פΤ��Ȥ�����Ƥ��Ƥ���褦�ʵ�������ΤǤ��뤬�����Υ��ڥ�ˡ�Ǥ���פȤ����Τ�����Τ˵����դ���������ǡ�����äȹ��Ƥ�����ʬ�Ρֿζ����ͥޥ����פȤ����Τ��ߥ��ڥ�ʤΤ�����������������������ǡ�˿���������Ĵ�٤���
�ڸ�����̡�
Ǥ����24100���
���6430���
���ξ�Ǥϡ�Ǥ���פ��ֿζ��פΣ��ܤ⤢�롣���ơ��ɤ��餬���������פΤ������Ȼפäơ�����λ�ŵ�ʹ�����*�ˤ�Ĵ�٤��顢ξ���Ȥ�¸�ߤ��롣��̣�ϡּ夭�������������������٤ळ�ȡ��ޤ������ο͡����Ȥ����ơפȤ��롣�ζ���֤��Ȥ����ơפȤ���Τϡ����������������ˤ��ü��ʤ��뤤���ˤλ��Ĥ٤����ˤ��ȷ��Ĥ��Ƥ��봶���������뤬���ּ夭�������������פȤ����Τϡ��ֿζ���Ǥ���פ�����Ȥ��Ƥʤ��ʤ�������
��* ������ҤȤ��ƿ��ꤷ�Ƥ���Ȥ������ȤǤϤʤ��ơ�����ˤϹ������ʤ��ä����顣��
��Ǥ�פΰ�̣�������Ǥ��롣�֤ޤ�����줿��ʬ�����פȸ��ä��Ȥ��������������������ֿΡפΰ�̣�ϡ��ȿ֤��줿�顥����
[Read More!]
�ڸ�����̡�
Ǥ����24100���
���6430���
���ξ�Ǥϡ�Ǥ���פ��ֿζ��פΣ��ܤ⤢�롣���ơ��ɤ��餬���������פΤ������Ȼפäơ�����λ�ŵ�ʹ�����*�ˤ�Ĵ�٤��顢ξ���Ȥ�¸�ߤ��롣��̣�ϡּ夭�������������������٤ळ�ȡ��ޤ������ο͡����Ȥ����ơפȤ��롣�ζ���֤��Ȥ����ơפȤ���Τϡ����������������ˤ��ü��ʤ��뤤���ˤλ��Ĥ٤����ˤ��ȷ��Ĥ��Ƥ��봶���������뤬���ּ夭�������������פȤ����Τϡ��ֿζ���Ǥ���פ�����Ȥ��Ƥʤ��ʤ�������
��* ������ҤȤ��ƿ��ꤷ�Ƥ���Ȥ������ȤǤϤʤ��ơ�����ˤϹ������ʤ��ä����顣��
��Ǥ�פΰ�̣�������Ǥ��롣�֤ޤ�����줿��ʬ�����פȸ��ä��Ȥ��������������������ֿΡפΰ�̣�ϡ��ȿ֤��줿�顥����
[Read More!]
08:00:00 -
entee -
TrackBacks




